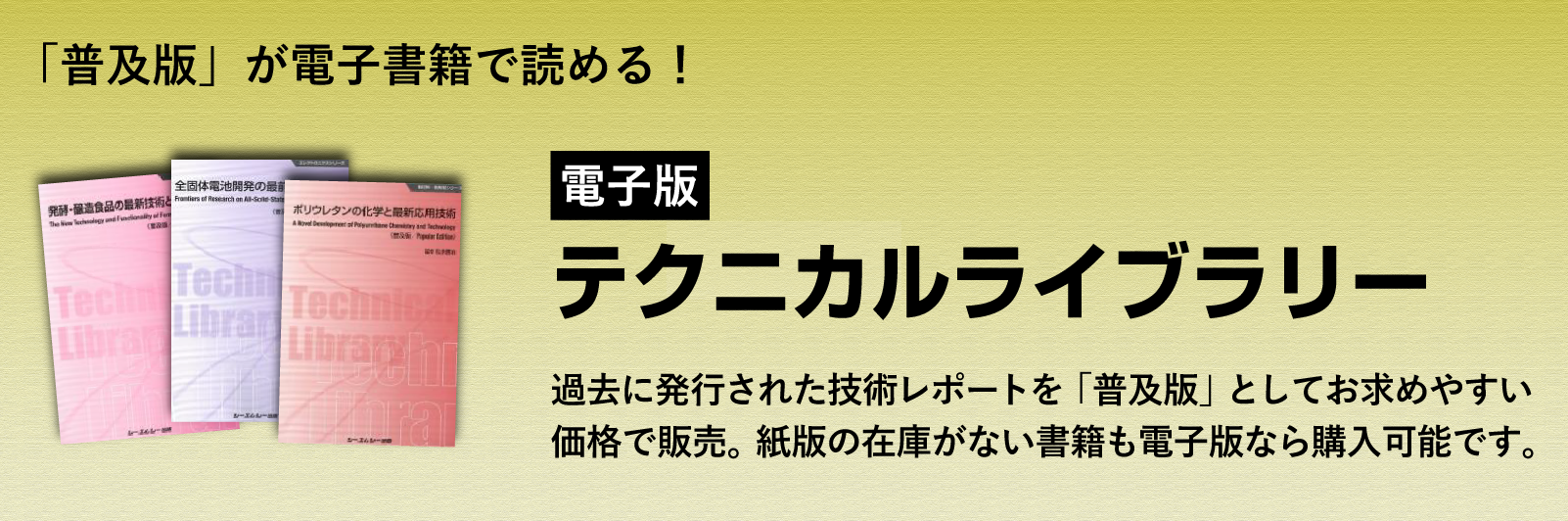書籍一覧
89 件
-

環状高分子の合成と機能発現《普及版》
¥6,270
2018年刊「環状高分子の合成と機能発現」の普及版。トポロジー幾何学に基づく環状高分子の理論解析から、分子設計、合成、構造・物性解析および環状構造固有の特性(トポロジー効果)による実用化探索まで、広範な研究成果を収載した1冊。
(監修:手塚育志)
<a href="https://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=115871"target=”_blank”>この本の紙版「環状高分子の合成と機能発現(普及版)」の販売ページはこちら(別サイトが開きます)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は、2019年当時のものを使用しております。
手塚育志 東京工業大学
出口哲生 お茶の水女子大学
上原恵理香 お茶の水女子大学
下川航也 埼玉大学
井田大地 京都大学
工藤宏人 関西大学
大内 誠 京都大学
鳴海 敦 山形大学
細井悠平 名古屋工業大学大学院
高須昭則 名古屋工業大学大学院
磯野拓也 北海道大学
佐藤敏文 北海道大学
落合文吾 山形大学
杉田 一 神奈川大学大学院
太田佳宏 神奈川大学
横澤 勉 神奈川大学
廣 雄基 産業技術総合研究所
平 敏彰 産業技術総合研究所
井村知弘 産業技術総合研究所
竹内大介 弘前大学
小坂田耕太郎 東京工業大学
久保智弘 University of Michigan
斎藤礼子 東京工業大学
足立 馨 京都工芸繊維大学
本多 智 東京大学
岡美奈実 東京大学
寺尾 憲 大阪大学
横山明弘 成蹊大学
中薗和子 東京工業大学
高田十志和 東京工業大学
野田結実樹 アドバンスト・ソフトマテリアルズ㈱
小林定之 東レ㈱
圓藤紀代司 元 大阪市立大学
角田貴洋 金沢大学
生越友樹 金沢大学
田村篤志 東京医科歯科大学
由井伸彦 東京医科歯科大学
下元浩晃 愛媛大学
井原栄治 愛媛大学
久保雅敬 三重大学
高野敦志 名古屋大学
羽渕聡史 King Abdullah University of Science and Technology
塩見友雄 長岡技術科学大学
竹下宏樹 滋賀県立大学
竹中克彦 長岡技術科学大学
山崎慎一 岡山大学大学院
平田修造 電気通信大学
バッハ マーティン 東京工業大学
春藤淳臣 九州大学
田中敬二 九州大学
-------------------------------------------------------------------------
<<目次>>
【第Ⅰ編 総論】
第1章 環状高分子の合成戦略とトポロジー効果
1 はじめに
2 環状高分子合成法の新展開
2.1 テレケリクス環化(RC法)
2.2 環拡大重合(RE法)
2.3 ESA-CF法
3 環状高分子のトポロジー効果
4 おわりに
【第Ⅱ編 理論】
第1章 環状高分子におけるトポロジー効果の理論
1 はじめに
2 結び目と絡み目:トポロジーの説明
3 環状高分子とランダムウォークあるいはランダムポリゴン
3.1 ガウス型ランダムウォークとその合成
3.2 環状鎖の回転半径と対相関関数
3.3 3次元のランダムウォークは容易に閉じない
3.4 排除体積を持つ環状鎖のランダムな配置の集団を生成する方法
4 トポロジー的絡み合い効果
4.1 トポロジー的絡み合い効果とその歴史的背景
4.2 結び目環状鎖の分配関数
4.3 結び目確率のシミュレーションと結果:排除体積とトポロジー効果の競合
4.4 トポロジー的膨張:トポロジー的エントロピー力の効果
5 結語
第2章 グラフ理論と結び目理論の環状高分子への応用
1 グラフ理論と環状高分子
2 結び目理論と環状高分子
第3章 環状みみず鎖モデルに基づく稀薄溶液物性の解析
1 環状Gauss鎖
2 環状みみず鎖―鎖の固さの影響
3 実験データ解析
4 いくつかのトピックス
【第Ⅲ編 設計・合成(環状高分子)】
第1章 環拡大重合法による分子量が制御された環状ポリマーの合成
1 はじめに
2 環拡大重合法による分子量の制御
3 環状チオエステル化合物とチイランとの環拡大重合
4 環状カルバミン酸チオエステル化合物とチイランとの環拡大重合
5 まとめ
第2章 環拡大カチオン重合による環状ポリマーの精密合成
1 緒言
2 環拡大カチオン重合の実現に向けて
3 SnBr4を用いたイソブチルビニルエーテルの環拡大カチオン重合
4 後希釈による環状ポリマー鎖の単分散化
5 さまざまなビニルエーテルの環拡大カチオン重合:環状トポロジーが感温性挙動とガラス転移温度に与える影響
6 まとめ
第3章 ビニルモノマーの環拡大重合
1 はじめに
2 環状開始剤によるビニルモノマーの環拡大重合
2.1 解離-結合(dissociation-combination)機構の活用
2.2 環状ジチオカルボニル化合物を用いた低温でのラジカル重合
2.3 環状アルコキシアミンによる制御ラジカル重合
2.3.1 開始剤合成
2.3.2 重合結果および特性評価
2.3.3 モデル反応
2.3.4 ブラシ化
3 環状連鎖移動剤を用いたビニルモノマーの重合
3.1 交換連鎖移動(degenerative chain transfer)機構の活用
3.2 環状RAFT剤存在下でのビニルモノマーの重合
3.3 環状RAFT剤によるビニルモノマーの環拡大重合
4 おわりに
第4章 希釈条件を必要としない閉環反応による環状ポリソルビン酸エステルの設計と合成
1 ソルビン酸エステルの立体規則性アニオン重合
2 N-ヘテロ環状カルベンによるビニルポリマーのアニオン重合と希釈条件を必要としない環化反応制御
3 使用できるビニルモノマーの拡張
第5章 有機分子触媒重合とクリック反応の組み合わせによる両親媒性環状ブロック共重合体の合成
1 はじめに
2 単環状BCPの合成
3 8の字型およびタッドポール型BCPの合成
4 三つ葉型および四つ葉型BCPの合成
5 かご型BCPの合成
6 まとめ
第6章 立体配座が規制されたモノマーの環化重合による大環状構造をもつポリマーの合成
1 緒言
2 α-ピネンから得たキラルビスアクリルアミドの環化重合と得られたポリマーのキラルテンプレートとしての可能性
3 環構造と水素結合を利用した19員環を形成する環化重合
4 19員環を形成する環化重合の応用
5 終わりに
第7章 分子内触媒移動を利用する環状高分子の合成
1 はじめに
2 環状ポリフェニレン
3 他の環状アリレーン
4 おわりに
第8章 環状トポロジーを有する界面活性剤の合成と応用
1 はじめに
2 環状POEアルキルエーテルの合成
3 環状POEアルキルエーテルの界面物性
3.1 表面張力低下能
3.2 自己集合挙動
3.3 ミセルの熱安定性
4 環状POEアルキルエーテルによる酵素活性阻害の抑制
5 おわりに
第9章 配位重合を用いた環状高分子の合成とミセル形成
1 環状高分子の合成
2 遷移金属錯体触媒による2-フェニルまたは2-アルキルメチレンシクロプロパンの重合
3 2-アルコキシメチレンシクロプロパンの開環重合による環状高分子合成
4 おわりに
第10章 遷移金属触媒を用いた環拡大重合法による環状高分子の合成
1 はじめに
2 Grubbsらによる環拡大重合法による環状ポリオレフィンの合成・評価・応用
3 Veigeらによる環拡大重合法による環状ポリアセチレン誘導体の合成・評価・応用
4 おわりに
第11章 テンプレート重合による環状高分子の合成
1 緒言
2 環状化合物を鋳型とする環状体合成
3 環状オリゴマーの特性
4 長鎖高分子を鋳型とする環状高分子合成
5 おわりに
第12章 静電相互作用による自己組織化(ESA-CF)による多環高分子の合成
1 はじめに
2 高分子トポロジー化学:多環状高分子トポロジーの精密設計
2.1 ESA-CFプロセス
2.2 スピロ形および連結形多環トポロジー
2.3 縮合形およびハイブリッド形多環トポロジー
2.4 高分子の精密折りたたみ:K3,3グラフ高分子の合成
3 おわりに
第13章 環状高分子が形作る分子集合体の機能
1 はじめに
2 環状両親媒性ブロック共重合体の自己組織化
3 可逆的かつ繰り返し可能なトポロジー変換
4 結論
第14章 環状高分子合成に向けた反応性オリゴマー/ポリマーの設計
1 はじめに
2 カチオン重合を用いたテレケリクスの設計
3 アニオン重合を用いたテレケリクスの設計
4 制御ラジカル重合を用いたテレケリクスの設計
5 その他の重合法を用いたテレケリクスの設計
6 おわりに
第15章 結合の切断・再生に基づく機能性環状高分子材料の開発
1 はじめに
2 網目状–星型–8の字型トポロジーの組換えに伴い粘弾性を制御できる高分子の開発
3 環状–直鎖状トポロジーの組換えによって流動性が変化する高分子の開発
4 おわりに
第16章 環状アミロースからの剛直環状高分子の合成と溶液中における構造・物性解析
1 はじめに(剛直な環状鎖)
2 線状アミロース誘導体の剛直性とらせん構造
3 環状アミロース誘導体の合成と溶液中における分子形態
4 環状アミロース誘導体濃厚溶液の液晶性
5 環状アミロース誘導体のキラル分離能
第17章 分子内水素結合を利用した大環状化合物の合成
1 はじめに
2 アミド
3 ホルムアミジンとウレア
4 ヒドラジド
5 イミン
6 まとめ
【第Ⅳ編 設計・合成(環状分子・超分子)】
第1章 ロタキサンの動的特性を用いた環状ポリマーの合成
1 はじめに
2 ロタキサンと高分子
3 [1]ロタキサンを用いた高分子の環化
4 自己組織化による環化:[c2]デイジーチェーンを用いた高分子の環化
5 さいごに
第2章 環動高分子材料 セルム製品シリーズ
1 はじめに
2 環動高分子材料の特徴
3 環動高分子材料セルム製品
4 エラストマー応用例
4.1 高分子誘電アクチュエータ・センサー
4.2 鏡面研磨メディア
5 おわりに
第3章 ポリロタキサンを導入したポリマー材料開発
1 はじめに
2 ポリロタキサン導入ポリアミド6の開発
3 ポリロタキサン導入ガラス強化系ポリアミド6の開発
4 ポリロタキサン導入炭素繊維強化プラスチックの開発
5 おわりに
第4章 ポリカテナン構造環状ジスルフィドポリマーの合成・特性化と形状記憶材料機能
1 はじめに
2 環状ジスルフィドの熱重合
3 生成ポリマーの構造決定
3.1 ポリマーのNMR,ESI-MSスペクトル解析
3.2 生成ポリマーの光分解挙動
3.3 原子間顕微鏡測定と動的光散乱測定
4 生成ポリマーの構造の性質
4.1 熱的性質
4.2 力学的性質
5 架橋体の合成と特性
6 形状記憶特性
7 おわりに
第5章 環状ホスト分子を基とした超分子集合体の創製
1 はじめに
2 柱状化合物の合成と特性
3 Pillar[n]areneによる超分子構造体
3.1 一次元チャンネル集合体
3.2 二次元シートの形成
3.3 三次元構造体の形成
4 おわりに
第6章 シクロデキストリン含有ポリロタキサンのバイオマテリアル応用
1 超分子を用いたバイオマテリアル設計
2 ポリロタキサンの自己会合を利用したバイオマテリアル
3 ポリロタキサンの分子可動性を利用したバイオマテリアル
4 分解性ポリロタキサンの医薬応用
5 おわりに
第7章 ビスジアゾカルボニル化合物を用いた環化重合体の合成
1 はじめに
2 ビナフチルリンカーモノマーの重合
3 シクロへキシレン,フェニレンリンカーを有するビスジアゾカルボニル化合物の環化重合
4 環化重合体のガラス転移温度
5 まとめ
第8章 環状高分子を利用する可動性架橋高分子の合成
1 はじめに
2 可動性架橋高分子
3 環状マクロモノマーを利用する可動性架橋高分子の合成
4 擬ポリロタキサンを経由する2段階の架橋反応
5 おわりに
【第Ⅴ編 解析】
第1章 環状高分子の精密キャラクタリゼーション
1 はじめに
2 環状高分子の一次構造の証明
3 環状高分子の含有率測定
3.1 新しいHPLCによる高分解能分析
3.2 LCCCによる環状高分子の分析
3.3 LCCCによるオタマジャクシ型高分子の分析
4 環状高分子の位相幾何学的(トポロジー)構造評価
5 終わりに
第2章 環状および多環状高分子の拡散挙動の単一分子分光解析
1 高分子粘弾性の分子レベルでの解析に向けて
2 絡み合い条件下での高分子拡散挙動の単一分子解析のための実験系の構築
3 単一分子拡散挙動の定量的解析のための手法の構築
4 Semi-dilute溶液中での環状高分子の拡散挙動
5 溶融体中での環状高分子の拡散挙動
6 溶融体中での多環状高分子の拡散挙動
7 最後に
第3章 環状高分子の結晶化挙動
1 はじめに
2 結晶ラメラにおける分子鎖の折り畳み構造
3 融解挙動
4 結晶化速度
4.1 核形成速度
4.2 結晶成長速度
5 おわりに
第4章 環状高分子の結晶化におけるトポロジー効果
1 はじめに
2 環状ポリエチレン(C-PE)と直鎖状ポリエチレン(L-PE)の合成
3 一次核生成速度Iと結晶成長速度Gの過冷却度ΔT依存性
4 C-PEとL-PEの一次核生成速度IのΔT依存性
5 C-PEとL-PEの結晶成長速度GのΔT依存性
6 おわりに
第5章 単一分子分光法による環状共役高分子のコンフォメーションおよび励起状態の解析
1 はじめに
2 共役系高分子のコンフォメーションの決定手法
3 環状と線状のフェニレンビニレン高分子のコンフォメーションの決定
4 環状と直鎖状のフェニレンビニレン高分子の光物性の違い
5 おわりに
第6章 環状自己組織化単分子膜の設計と表面特性
1 はじめに
2 環状SAMの設計・調製
3 SAMの調製とキャラクタリゼーション
4 SAMの表面特性
5 おわりに -

医薬品原薬の結晶化と物性評価:その最先端技術と評価の実際《普及版》
¥5,280
2019年刊「医薬品原薬の結晶化と物性評価:その最先端技術と評価の実際」の普及版。薬剤の安定性と溶解性の向上に向けた結晶化ならびに評価法をまとめた、原薬結晶の研究やプロセスモニタリングに携わる方々にお薦めの1冊。
(監修:川上亘作)
<a href="https://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=115870"target=”_blank”>この本の紙版「医薬品原薬の結晶化と物性評価:その最先端技術と評価の実際(普及版)」の販売ページはこちら(別サイトが開きます)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は、2019年当時のものを使用しております。
川上亘作 (国研)物質・材料研究機構
丸山美帆子 大阪大学
吉村政志 大阪大学
高野和文 京都府立大学
森 勇介 大阪大学;㈱創晶
滝山博志 東京農工大学
植草秀裕 東京工業大学
辛島正俊 武田薬品工業㈱
北西恭子 塩野義製薬㈱
及川倫徳 沢井製薬㈱
中西慶太 アステラス製薬㈱
高橋かより (国研)産業技術総合研究所
米持悦生 星薬科大学
井上元基 明治薬科大学
伊藤雅隆 東邦大学
大塚 誠 武蔵野大学
木嶋秀臣 小野薬品工業㈱
冨中悟史 (国研)物質・材料研究機構
高野隆介 中外製薬㈱
奥津哲夫 群馬大学
津本浩平 東京大学
長門石暁 東京大学
鳥巣哲生 大阪大学
内山 進 大阪大学
-------------------------------------------------------------------------
<<目次>>
【第1編 医薬品結晶の創成】
第1章 医薬品化合物の結晶化技術
1 はじめに
2 準安定形結晶の結晶化戦略
3 結晶化を促進させる技術
3.1 フェムト秒レーザー照射による結晶核発生誘起技術
3.2 超音波印加による結晶核発生誘起技術
3.3 ポリマー界面を用いた結晶化技術
3.4 超音波法とポリマー法の組み合わせによる核発生の効率化
4 結晶の安定性を向上させる技術
4.1 何が結晶の安定性を決めるのか
4.2 高品質結晶成長に適した条件とは
4.3 徐冷法と種結晶法
4.4 溶媒媒介相転移を利用した準安定形の結晶化
5 まとめ
第2章 共結晶の品質制御
1 はじめに
2 共結晶の晶析
2.1 相図と過飽和操作
2.2 共結晶析出と相図
3 Anti-Solvent添加晶析を併用した共結晶生成
4 Anti-Solvent添加晶析での共結晶の品質制御
5 まとめ
第3章 医薬品結晶の粉末結晶構造解析
1 はじめに
2 粉末X線回折データとは
3 粉末未知結晶構造解析の概要
3.1 測定
3.2 指数付け
3.3 反射強度抽出
3.4 初期構造モデルの決定
3.5 構造精密化
3.6 構造の吟味
4 粉末X線回折データから結晶構造が解析された化合物の例
4.1 脱水和転移現象の解明
4.2 脱水和転移と物性
5 理論計算による検証
6 おわりに
第4章 原薬の開発形態検討
1 はじめに
2 原薬形態の種類
3 各種スクリーニングの戦略
4 結晶多形スクリーニング
4.1 スラリー法
4.2 晶析法
4.3 安定形の評価方法
5 塩スクリーニング
6 共結晶スクリーニング
6.1 スラリー法
6.2 混合粉砕法
6.3 熱的手法
7 おわりに
【第2編 物性評価の実際と最前線】
第5章 創薬探索段階における物性パラメータ
1 はじめに
2 開発候補化合物の物性
3 物性パラメータが薬物動態に及ぼす影響
4 物性パラメータの定義,指標,及び評価方法
4.1 溶解度
4.2 Log D
4.3 pKa
5 計算値の利用
6 新薬の研究開発への応用
7 おわりに
第6章 新規溶解特性評価装置を使用した原薬物性評価
1 開発化合物の現状
2 開発過程におけるpKaのインパクト
3 開発過程における溶解度のインパクト
4 塩基性化合物のミクロな環境下におけるpH変動の実際
5 CheqSol法による薬物分類(ChaserおよびNon-Chaser)
6 Precipitation RateおよびRe-Dissolution Rate
7 おわりに
第7章 DDSの適用になくてはならない物性評価
1 はじめに
2 リポソームの適用を踏まえた低分子化合物の物性評価
3 PLGA粒子の適用を踏まえた低分子化合物の物性評価
4 DDS製剤の物性評価
4.1 DDS製剤の物性評価①―粒子径・粒度分布―
4.2 DDS製剤の物性評価②―形態・形状―
4.3 DDS製剤の物性評価③―表面電荷―
4.4 DDS製剤の物性評価④―熱力学特性―
4.5 DDS製剤の物性評価⑤―放出特性・封入率―
4.6 DDS製剤の物性評価⑥―pH,凝集,浸透圧,不純物―
5 最後に
第8章 溶解度測定の実際
1 はじめに
2 原薬の状態
3 平衡溶解度とKinetic solubility
4 平衡溶解度の測定手順
4.1 使用容器への吸着性の確認
4.2 撹拌方法
4.3 固体量と平衡化時間
4.4 固液分離
4.5 希釈
4.6 平衡化後の結晶形・pH確認
5 評価溶媒
6 平衡溶解度測定のオートメーション化
7 おわりに
第9章 粒子径測定の実際
1 はじめに
2 粒子径計測法
2.1 静的光散乱法
2.2 動的光散乱法
2.3 パルス磁場勾配核磁気共鳴法
3 粒子の物性評価の実際
3.1 回転半径等の特性値と粒子径の関係
3.2 回転半径等の特性値と粒子径の関係
3.3 粒子間長距離相互作用の評価
4 まとめ
【第3編 結晶の評価】
第10章 インシリコ技術による結晶多形および物性予測
1 はじめに
2 結晶物性評価に関わるインシリコ予測
2.1 結晶多形のインシリコ予測
2.2 粉末X線構造解析法による結晶構造の決定
2.3 医薬品開発における未知結晶多形の出現リスク評価
2.4 結晶形態のインシリコ予測
2.5 溶出挙動に及ぼす結晶形態の影響
3 おわりに
第11章 低波数ラマン分光法による結晶形評価
1 はじめに
2 低波数ラマン分光
3 低波数ラマンスペクトルを用いた結晶形評価
4 ケモメトリクス解析の活用によるラマンスペクトルの解釈
5 プローブによる晶析工程モニタリング
6 おわりに
第12章 吸湿性医薬品原薬の結晶化と製剤化の実際
1 はじめに
2 吸湿性医薬品原薬の物性改善
2.1 吸湿性医薬品原薬の多成分結晶化
2.2 水分子の吸着シミュレーション
2.2 水分子の吸着シミュレーション
3 吸湿性医薬品原薬の製剤設計の実際
第13章 製剤化工程における多形転移とその評価―Pharmaceutical Process Monitoringの背景と現状―
1 粉砕処理工程の医薬品結晶多形転移現象が製剤の生物学的利用能に与える影響
2 粉砕処理工程が化合物の異性化に与える影響
3 粉砕工程中の環境温度が結晶多形転移に与える影響
4 粉砕湿度が結晶多形転移に与える影響
5 医薬品造粒工程に発生する結晶多形転移が製剤特性に与える影響
6 医薬品製造中の結晶多形転移とProcess Analytical Technologyによる新規医薬品製造工程管理との関わり
7 結晶多形を含有する打錠用顆粒造粒製造過程における水和物転移のNIRモニタリング
8 顆粒造粒製造過程における共結晶生成のラマンモニタリング
9 結論
【第4編 非晶質の制御と評価】
第14章 医薬品原薬の結晶化傾向
1 はじめに
2 結晶化傾向の評価法
3 結晶化傾向のクラス分けと等温結晶化の関係
4 熱処理による非晶質状態の安定化
5 結晶化クラスと結晶化挙動の関係
6 おわりに
第15章 結晶化における二次核形成
1 はじめに
2 二次核形成機構の分類
2.1 イニシャル ブリーディング
2.2 コンタクト ニュークリエーション
2.3 フルイドシア
2.4 クロス ニュークリエーション
2.5 その他
3 関連する核形成ならびに多形転移現象
3.1 核形成:接触誘起不均一核形成(Contact-induced heterogeneous nucleation)
3.2 多形転移:エピタキシ媒介転移(epitaxy-mediated transformation)
4 おわりに
第16章 二体分布関数を用いた構造解析:医薬品への応用
1 はじめに
2 二体分布関数を用いた構造解析
3 二体分布関数の原理とデータ変換の概要
4 二体分布関数の測定
5 二体分布関数の導出
6 二体分布関数の解釈と解析
7 二体分布関数の医薬品への応用例「リトナビルの構造解析」
8 おわりに
第17章 非晶質の過飽和能を活かす製剤設計
1 非晶質製剤イントロダクション:過飽和は十分に活かされているのか?
2 日進月歩のASD処方・製剤設計
3 吸収性を反映した溶解性評価とは?
3.1 Biorelevant dissolution model
3.2 LLPSと吸収性
3.3 コロイドやナノアグリゲーションの分析と吸収性
3.4 投与剤としての吸収性評価
4 過飽和を活かした製剤設計とは?
4.1 賦形剤及び崩壊剤によるゲル化抑制
4.2 塩析効果によるゲル化抑制
4.3 Mesoporous silica
5 まとめ
【第5編 バイオ医薬の開発技術】
第18章 プラズモン共鳴を利用したタンパク質結晶化促進プレートの開発
1 タンパク質の結晶化
1.1 タンパク質の結晶化
1.2 タンパク質の光化学反応
1.3 光-分子強結合場を用いた反応場
2 局在プラズモン励起による結晶化実験
3 金蒸着した基盤による反応場の構築と結晶化実験
第19章 抗体医薬の基礎物性評価
1 抗体医薬にもとめられる物性とは
2 熱安定性評価
2.1 示差走査型カロリメーター(DSC)
2.2 示差走査型蛍光法(DSF)
3 相互作用評価
3.1 表面プラズモン共鳴法(SPR)
3.2 等温滴定型熱量計(ITC)
4 コンフォメーショナルな物性評価
4.1 円偏光二色性スペクトル法(CD)
4.2 小角X線散乱法(SAXS)
4.3 ラマン分光法(Raman)
5 まとめ
第20章 タンパク質凝集体の分析
1 はじめに
2 タンパク質凝集体分析における課題
3 タンパク質凝集体の分析手法
3.1 タンパク質凝集体の定量分析
3.2 タンパク質凝集体の定性分析
4 おわりに -

タンパク質のアモルファス凝集と溶解性《普及版》
¥5,940
2019年刊「タンパク質のアモルファス凝集と溶解性」の普及版。 タンパク質の凝集・溶解のメカニズム、測定・解析・予測・制御法、病態解明などや創薬など、安全かつ機能的なタンパク質の生産・利用に役立つ1冊。
(監修:黒田 裕、有坂文雄)
<a href="https://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=115839"target=”_blank”>この本の紙版「タンパク質のアモルファス凝集と溶解性(普及版)」の販売ページはこちら(別サイトが開きます)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は、2019年当時のものを使用しております。
黒田 裕 東京農工大学
有坂文雄 東京工業大学
白木賢太郎 筑波大学
岩下和輝 筑波大学
三村真大 筑波大学
宗 正智 大阪大学
後藤祐児 大阪大学
今村比呂志 立命館大学
渡邊秀樹 産業技術総合研究所
千賀由佳子 産業技術総合研究所
本田真也 産業技術総合研究所
太田里子 ㈱東レリサーチセンター
杉山正明 京都大学
城所俊一 長岡技術科学大学大学院
若山諒大 大阪大学
内山 進 大阪大学;自然科学研究機構
デミエン ホール 大阪大学
廣田奈美 堂インターナショナル
五島直樹 産業技術総合研究所
河村義史 バイオ産業情報化コンソーシアム
廣瀬修一 長瀬産業㈱
野口 保 明治薬科大学
丹羽達也 東京工業大学
田口英樹 東京工業大学
伊豆津健一 国立医薬品食品衛生研究所
津本浩平 東京大学
伊倉貞吉 東京医科歯科大学
池口雅道 創価大学
荒川 力 Alliance Protein Laboratories
江島大輔 シスメックス㈱
浅野竜太郎 東京農工大学
赤澤陽子 産業技術総合研究所
萩原義久 産業技術総合研究所
小澤大作 大阪大学
武内敏秀 大阪大学
永井義隆 大阪大学
安藤昭一朗 新潟大学脳研究所
石原智彦 新潟大学脳研究所
小野寺 理 新潟大学脳研究所
加藤昌人 University of Texas Southwestern Medical Center
米田早紀 大阪大学
鳥巣哲生 大阪大学
黒谷篤之 理化学研究所
柴田寛子 国立医薬品食品衛生研究所
石井明子 国立医薬品食品衛生研究所
-------------------------------------------------------------------------
<<目次>>
【第Ⅰ編 基礎】
第1章 タンパク質の溶解性およびアモルファス凝集の物理化学的解析
1 はじめに
2 タンパク質の溶解性の物理化学的研究
3 タンパク質の溶解性およびアモルファス凝集の物理化学的な解析
4 アモルファス凝集状態
5 平衡論的な考えに基づいたアモルファス凝集の議論
5.1 タンパク質凝集の可逆性
5.2 タンパク質溶解性の熱力学モデル
5.3 多数の因子(パラメータ)に影響されるタンパク質の溶解性(および凝集性)
6 おわりに
第2章 タンパク質の共凝集と液-液相分離
1 はじめに
2 凝集と共凝集
3 液-液相分離
4 コアセルベートと共凝集体
5 バイオ医薬品への応用
6 まとめ
第3章 アミロイド線維とアモルファス凝集
1 タンパク質のフォールディングと凝集
2 アミロイド線維とアモルファス凝集の構造
3 結晶化によく似たアミロイド線維形成と相図による理解
4 新たな視点“過飽和”からのアミロイド線維形成とアモルファス凝集
【第Ⅱ編 測定・理論および情報科学的解析・予測】
第1章 バイオ医薬品におけるタンパク質凝集体の評価
1 はじめに
2 タンパク質凝集体の分析法
2.1 サイズ排除クロマトグラフィー
2.2 超遠心分析法
2.3 動的光散乱法
2.4 静的光散乱法
2.5 流動場分離法
2.6 小角X線散乱法
2.7 ナノ粒子トラッキング法
2.8 フローイメージング法
2.9 光遮蔽法
2.10 目視
2.11 その他
3 抗体医薬品の凝集に関する新しい分析技術の開発と応用
3.1 非天然型構造特異的プローブを用いた検出技術
3.2 蛍光相関分光法と光散乱法による抗体医薬品の凝集化メカニズムの解明
4 おわりに
第2章 超遠心分析による会合体・凝集体の分析
1 はじめに
2 超遠心分析法の概要
3 AUC-SV法による測定例
4 第2ビリアル係数に基づく凝集性の予測
5 まとめ
第3章 光散乱による会合・凝集の検出
1 はじめに
2 静的光散乱と動的光散乱
3 サイズ排除クロマトグラフィー(SEC)とフィールドフローフラクショネーション(FFF)
4 凝集の起こりやすさの予測
5 まとめ
第4章 小角散乱法
1 はじめに
2 小角散乱の原理
2.1 溶液中の粒子の小角散乱
2.2 揺らぎを持った系の小角散乱
3 小麦タンパク質グリアジンの小角散乱
3.1 希薄状態でのグリアジンの溶液構造
3.2 溶液中のグリアジン構造の濃度依存性
4 最後に
第5章 タンパク質凝集・会合と熱測定
1 タンパク質の熱測定における凝集の問題
2 タンパク質の可逆的な会合体形成反応とタンパク質濃度依存性
3 タンパク質の高温での可逆的オリゴマー形成の例1:シトクロムcの場合
4 タンパク質の高温での可逆的オリゴマー形成の例2:デングウイルスの外殻タンパク質ドメイン3の場合
5 可逆的オリゴマー形成と凝集反応との関係について
第6章 イオン液体とタンパク質フォールディング―新しい溶媒への古い策略―
1 タンパク質フォールディングの基本的な説明
1.1 経験的スキーム1:中点分析
1.2 経験的スキーム2:m値法
2 古典的熱力学に基づいたタンパク質フォールディング特性のための機構的アプローチ
2.1 温度誘導性アンフォールディング
2.2 圧力誘導性アンフォールディング
2.3 変性剤誘導性アンフォールディング
第7章 タンパク質凝集の速度論を統合する理論的記述
1 バルク相における同種核形成によるアミロイド形成の単純な速度論モデル
2 バルク相における同種核形成によるアモルファス凝集の単純な速度論モデル
3 アミロイド形成と競合するアモルファス凝集
4 アモルファス凝集がアミロイド形成の中間体である場合
4.1 アミロイドの第2のルートとしてのアモルファス凝集:表面核形成
4.2 アミロイドの第2のルートとしてのアモルファス凝集:液相核形成
第8章 溶解性の網羅的解析と機械学習予測
1 溶解性のプロテオーム解析
2 タンパク質溶解性や凝集性のデータベース
3 機械学習予測
3.1 配列情報からの機能予測
3.2 予測手法の構築
3.3 予測手法の利用例
3.4 予測サービス
第9章 再構築型無細胞タンパク質合成系を用いたタンパク質凝集性の網羅解析
1 はじめに
2 再構築型無細胞タンパク質合成系を用いた凝集性評価
3 大腸菌全タンパク質に対する凝集性の網羅解析
4 大腸菌の凝集性タンパク質に対する分子シャペロンの効果
5 大腸菌内膜タンパク質と人工リポソーム
6 酵母細胞質タンパク質の凝集性の解析
7 天然変性領域と凝集性との関係
8 酵母細胞質タンパク質に対する分子シャペロンの凝集抑制効果
9 まとめ:大腸菌と酵母タンパク質のフォールディングの分子進化
【第Ⅲ編 制御】
第1章 タンパク質医薬品の凝集機構と凝集評価・抑制方法
1 はじめに
2 凝集と免疫原性
3 タンパク質の製剤中における凝集
4 測定法と管理指標の設定
5 臨床使用までの各段階におけるタンパク質の凝集
6 タンパク質の構造設計による凝集抑制
7 製剤処方の最適化による凝集抑制
8 凍結乾燥による凝集の抑制
9 まとめ
第2章 プロリン異性化とタンパク質凝集制御
1 プロリン異性化
2 プロリン異性化によるタウオパチーの制御
3 シクロフィリンDによるアミロイドβの凝集制御
4 プロリン異性化とタンパク質凝集制御
第3章 タンパク質のフォールディングと溶解性
1 フォールドしたタンパク質の溶解度
2 ジスルフィド結合を持つタンパク質の大腸菌での発現
3 封入体として得られたタンパク質のリフォールディング
4 フォールディングと会合の競合
第4章 短い溶解性向上ペプチドタグを用いたタンパク質の凝集の抑制
1 はじめに
2 溶解性向上ペプチドタグ(SEPタグ)
2.1 タンパク質融合による可溶化
2.2 SEPタグの開発
2.3 SEPタグ付加によるアミノ酸の溶解性・凝集性の指標
3 SEPタグを用いた溶解性制御の応用例
3.1 タンパク質の可溶化
3.2 SEPタグの実用化
3.3 SEPタグを用いた複数SS結合を形成する組換えタンパク質の発現と精製
4 おわりに
第5章 タンパク質の凝集抑制と凝集体除去
1 はじめに
2 タンパク質生産過程での会合の機構
2.1 コロイド会合
2.2 変性会合
2.3 変性の中間状態
3 高濃度タンパク質
3.1 クロマトグラフィーカラム中での濃縮
3.2 限外ろ過中の会合
4 発現中での会合
5 リフォールディングにおける会合
5.1 アクチビンA
5.2 リフォールディング過程での2量体形成
5.3 抗体
6 クロマトグラフィー精製中での会合
6.1 プロテインA
6.2 会合体除去クロマトグラフィー
7 会合体の影響
8 会合体の検出
8.1 抗体
8.2 疎水性タンパク質
第6章 巻き戻し法を用いた低分子抗体の調製
1 はじめに
2 一本鎖抗体(scFv)と巻き戻し法を用いた調製
3 巻き戻し法を用いたscFvの調製最適化
4 巻き戻し法を用いた低分子二重特異性抗体の調製
5 巻き戻し法を用いた低分子二重特異性抗体の最適化
6 巻き戻し法を用いたサイトカイン融合低分子抗体の調製
7 おわりに
第7章 抗体タンパク質の溶解性と変性状態からの可逆性
1 はじめに
2 抗体タンパク質の溶解性
2.1 抗体の種類とドメイン構成について
2.2 抗体タンパク質に求められる溶解性および安定性の評価法
2.3 IgG抗体由来ドメインの熱による影響
3 VHH抗体の溶解性と安定性
3.1 VHH抗体の構造安定性
3.2 VHH抗体の熱耐性の改善
3.3 ジスルフィド結合と安定性
4 まとめ
【第Ⅳ編 病態解明・産業応用】
第1章 ポリグルタミンタンパク質の凝集・伝播と細胞毒性
1 神経変性疾患とタンパク質凝集
2 ポリグルタミン病
3 ポリグルタミンタンパク質のアミロイド線維形成
4 ポリグルタミンタンパク質の細胞毒性
5 ポリグルタミンタンパク質のプリオン様伝播
5.1 ポリグルタミンタンパク質の異常構造の分子間伝播
5.2 異常タンパク質凝集体の細胞間伝播
6 おわりに
第2章 筋萎縮性側索硬化症における,タンパク質凝集および核内構造体の異常と疾病
1 はじめに
2 筋萎縮性側索硬化症と関連タンパク質
3 液相分離,LLPSとALS関連タンパク質
3.1 FUS
3.2 TDP-43
3.3 C9orf 72
4 ALSと核内構造体
5 まとめ
第3章 細胞内凝集とMembrane-less organelles
1 RNA顆粒:膜を持たない細胞内構造体
2 Low-complexity配列の相転移
3 LCドメインの液-液相分離
4 相分離とジェル化の原理
5 細胞内に存在するLCドメインポリマー
6 まとめ
第4章 創薬産業と溶解性・凝集性および関連制度
1 はじめに
2 バイオ医薬品開発における溶解性の検討
3 タンパク質の溶解性と凝集性について
4 さいごに
第5章 タンパク質の凝集・溶解性関連研究についての技術俯瞰と産業化に向けた知財戦略
1 はじめに
2 タンパク質の凝集・溶解性関連研究の技術俯瞰
3 特許情報から見たタンパク質の凝集・溶解性関連の研究状況・技術動向
4 発明(技術思想)の保護戦略について
5 特許取得の考慮事項
5.1 特許要件について
5.2 発明のカテゴリーについて
5.3 早期権利化の考慮について
6 発明の知財活用戦略
7 ライセンスによる知財活用
8 大学等からの技術移転・産業化
8.1 法整備について
8.2 近年の動向
9 まとめ
第6章 バイオ医薬品の品質・安全性確保における凝集体の評価と管理
1 バイオ医薬品の品質確保の概要
1.1 品質特性解析
1.2 品質管理戦略の構築
2 バイオ医薬品に含まれる凝集体および不溶性微粒子の評価方法に関する規制
2.1 薬局方
2.2 規制当局のガイドライン
3 課題とAMED-HS官民共同研究における取組
-

樹脂の溶融混練・押出機と複合材料の最新動向《普及版》
¥5,280
2018年刊「樹脂の溶融混練・押出機と複合材料の最新動向」の普及版。 樹脂の溶融混練メカニズムから押出機開発動向、スクリュ設計、樹脂混練シミュレーション、ナノ粒子・長繊維分散による複合材料製造までを網羅した1冊。
(監修:田上秀一)
<a href="https://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=115840"target=”_blank”>この本の紙版「樹脂の溶融混練・押出機と複合材料の最新動向(普及版)」の販売ページはこちら(別サイトが開きます)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は、2019年当時のものを使用しております。
田上秀一 福井大学
名嘉山祥也 九州大学
植松英之 福井大学
齊藤卓志 東京工業大学
田中達也 同志社大学
辰巳昌典 ㈱プラスチック工学研究所
橋爪慎治 ㈲エスティア
酒井忠基 静岡大学
久家立也 ㈱池貝
大田佳生 旭化成㈱
福澤洋平 ㈱日本製鋼所
竹田 宏 ㈱アールフロー
谷藤眞一郎 ㈱HASL
朝井雄太郎 アイ・ティー・エス・ジャパン㈱
山田紗矢香 ㈱神戸製鋼所
清水 博 ㈱HSPテクノロジーズ
木原伸一 広島大学
滝嶌繁樹 広島大学
合田宏史 ㈱プライムポリマー
森 良平 GSアライアンス㈱
仙波 健 (地独)京都市産業技術研究所
大峠慎二 トクラス㈱
伊藤弘和 (国研)産業技術総合研究所
福井武久 ㈱栗本鐵工所
-------------------------------------------------------------------------
<<目次>>
第1章 溶融混練メカニズム
1 溶融混練の基礎理論と現状
1.1 はじめに
1.2 溶融混練における2つの過程
1.3 連続式溶融混練
1.3.1 単軸スクリュ押出
1.3.2 二軸スクリュ押出
1.4 溶融混練部内の流れの数値計算
1.5 溶融混練過程を定量化するには
1.5.1 分配混合
1.5.2 分散混合
1.6 溶融混練過程評価の例
1.7 おわりに
2 溶融混練における樹脂の粘度・温度の影響
2.1 はじめに
2.2 粘度とは
2.2.1 流れの様式 せん断流れと伸長流れ
2.2.2 粘度の定義 せん断粘度と伸長粘度
2.3 高分子流体の粘度は何に依存するのか
2.3.1 ひずみ速度依存性
2.3.2 温度依存性
2.3.3 分子量依存性
2.4 樹脂の粘度や温度が混合混練に影響を及ぼす事例
2.4.1 高粘度流体が分散相である二成分系の溶融混練
2.4.2 高粘度流体が分散相である二成分系の溶融混練
2.4.3 ポリマー/ナノフィラー系複合材料の溶融混練に及ぼす樹脂の粘度の影響
2.4.4 ポリマー/ナノフィラー系複合材料の溶融混練に及ぼす樹脂の粘度の影響
2.5 おわりに
3 材料の溶融を考えるための伝熱基礎
3.1 はじめに
3.2 熱エネルギーのバランス
3.3 伝熱現象の基礎
3.4 樹脂材料の溶融について
3.5 熱物性値について(熱伝導率を例に)
3.6 熱エネルギー方程式の導出
第2章 押出機・混練技術動向
1 二軸押出機の変遷と最新の技術動向
1.1 混練技術・装置の変遷
1.2 二軸混練押出技術
1.2.1 混練用KDセグメント技術
1.2.2 高容量化と高トルク化技術
1.2.3 新たな混練用セグメント技術
1.3 おわりに
2 最近の押出機の開発動向と可視化解析押出技術
2.1 はじめに
2.2 最近の押出機の開発動向
2.3 可視化解析システム概要
2.4 可視化解析単軸押出装置
2.5 可視化解析二軸押出装置
2.6 終わりに
3 せん断分散における品質スケールアップと,品質スケールアップが不要な分散システム
3.1 はじめに
3.2 せん断分散における分散品質スケールアップ技術
3.3 伸長流動分散における分散品質
3.4 スラリー分散技術
3.5 LFP技術
3.6 各種ナノ分散システム
3.7 おわりに
4 二軸スクリュ押出機を用いたリアクティブプロセシング
4.1 二軸スクリュ押出機を用いたリアクティブプロセシングの優位点
4.2 リアクティブプロセシング実施例
4.3 ポリマーアロイのモルフォロジー形成に関連する要因
4.4 二軸スクリュ押出機内でのポリマーアロイのモルフォロジー形成
4.5 リアクティブプロセシングに用いるスクリュ形状の選定および操作条件の選定
4.5.1 スクリュエレメントの組み合わせ
4.5.2 各種材料の添加順序の選定
4.5.3 二軸スクリュ押出機を活用したリアクティブプロセシング操作と他の成形加工操作との複合化
4.6 まとめ
第3章 スクリュ設計
1 低温混練技術のためのスクリュデザインの最適化
1.1 はじめに
1.2 二軸押出機の構成
1.3 高速・低速回転時の樹脂温度比較
1.4 高トルク・高速回転・深溝化
1.4.1 高トルク
1.4.2 高速回転
1.4.3 深溝化
1.5 粘度とスクリュ形状の関係
2 同方向回転二軸押出機のスクリュ構成の最適化,混練条件の設定とスケールアップ
2.1 はじめに
2.2 同方向回転二軸押出機の装置概要
2.3 同方向回転二軸押出機の5つの混練要素について
2.3.1 スクリュの充満率
2.3.2 スクリュの圧力特性
2.3.3 温度計算
2.3.4 スクリュの混・練
2.3.5 押出機のシミュレーションの計算例
2.4 スケールアップの考え方
2.4.1 2~3乗則でスケールアップ時の課題
2.4.2 押出機の設計とスケールアップについて
2.4.3 分散混合と分配混合を使ったスケールアップ
2.4.4 まとめ
2.5 応用事例
2.5.1 スクリュ構成改良による溶融粘度比が大きな樹脂同士の分散性改良
2.5.2 混練ゾーンとベントポートの距離が短いためベントアップする場合の対策例
2.5.3 パウダー状樹脂のスクリュ構成による押出量の比較
2.6 おわりに
3 人工知能アルゴリズムを利用したスクリュデザインの自動最適化
3.1 はじめに
3.2 ディープラーニング(Deep Neural Network)
3.2.1 ディープラーニング(Deep Neural Network:DNN)とは
3.2.2 DNN教師あり学習
3.3 二軸スクリュデザインの自動最適化へのAI適用事例
3.3.1 二軸スクリュデザインの自動最適化へのアルゴリズム
3.3.2 実験と解析による教師データの作成
3.3.3 DNNによる学習ファイルの作成
3.3.4 AIによる推奨スクリュデザインの出力と検証実験
3.4 さいごに
第4章 シミュレーション・評価技術
1 二軸押出機の樹脂流動シミュレーション技術
1.1 はじめに
1.2 二軸スクリュ押出シミュレーション技術
1.3 FAN法シミュレーション
1.3.1 FAN法について
1.3.2 FAN法の基礎方程式
1.3.3 FAN法による二軸スクリュ混練シミュレーション
1.4 FEMによる3次元スクリュ流動解析
1.4.1 FEMについて
1.4.2 FEMの基礎方程式
1.4.3 FEMによる3次元スクリュ混練シミュレーション
1.5 粒子法シミュレーション
1.5.1 粒子法シミュレーションについて
1.5.2 MPS法の基礎方程式
1.5.3 二軸スクリュ押出機内における溶融樹脂の混練シミュレーション
1.6 さいごに
2 マクロとミクロをつなぐスクリュー押出機内流動解析
2.1 流動解析によるスクリュー押出機内流動状態の評価
2.2 粒子解析を利用したスクリュー特性評価とクリアランスに関する考察
2.3 クリアランス通過頻度の理論的予測
2.4 凝集粒子の粒径分布の予測
2.5 おわりに
3 コンピュータシミュレーションを利用した二軸スクリュ押出機内成形現象の可視化
3.1 はじめに
3.2 成形現象の定量化法
3.2.1 二軸スクリュ押出機モデリングツール
3.2.2 一般化Hele-Shaw流れの定式化
3.2.3 未充満状態の計算方法
3.3 二軸スクリュ押出機内成形現象の可視化例
3.3.1 未充満解析
3.3.2 繊維破断解析
3.4 おわりに
4 押出混練シミュレーション,樹脂挙動解析とスクリュ条件の求め方
4.1 セクションごとの役割と評価すべきパラメータ
4.2 フィード部,圧縮部,計量部,そしてミキシング部
4.2.1 フィード部で考慮すべき事
4.2.2 フィード部で評価すべき解析パラメータ
4.2.3 圧縮部で考慮すべき事
4.2.4 フィード部で評価すべき解析パラメータ
4.2.5 圧縮部にバリアフライトを設ける場合
4.2.6 バリア部で評価すべき解析パラメータ
4.2.7 計量部で考慮すべき事
4.2.8 計量部で評価すべき解析パラメータ
4.2.9 適切なせん断応力を得る為にできる事
4.2.10 ミキサーの要否と選択
4.3 まとめ
5 メッシュフリー法に基づく樹脂混練機内の非充満流動解析を活用した樹脂混練機セグメントの性能評価
5.1 はじめに
5.2 解析手法
5.2.1 支配方程式
5.2.2 離散化法(EFGM)
5.2.3 速度の近似関数
5.2.4 精度向上のための手法(計算点再配置)
5.3 提案した手法の精度の検証
5.3.1 同軸二重円筒クエット内完全充満流動
5.3.2 同軸二重円筒内の部分充満における流動
5.3.3 模擬混練実験との比較
5.4 混練評価への適用
5.4.1 混練実験と結果
5.4.2 流動解析手法と結果
5.4.3 流動解析を用いた混練性能評価
5.5 最後に
第5章 ナノ粒子分散によるナノコンポジット製造
1 高せん断成形加工技術を用いたナノコンポジット創製
1.1 はじめに
1.2 各種フィラーのナノ分散化の要因
1.3 熱可塑性エラストマー/CNT系ナノコンポジット
1.4 PVDF/PA6/CNT系ナノコンポジット
1.5 生分解性ポリマー/二酸化チタン系ナノコンポジット
1.6 PA11/層状ケイ酸塩系ナノコンポジット
1.7 熱可塑性高分子/炭素繊維/層状ケイ酸塩系ナノコンポジット
1.8 おわりに
2 高圧流体混練法によるCNTバンドルの解繊
2.1 はじめに
2.2 試料作製方法および試料評価方法
2.3 実験結果と考察
2.3.1 SCCO2およびN2雰囲気での混練によるCNTバンドル解繊効果
2.3.2 高圧流体混練法によるCNTバンドルの解繊メカニズム
2.4 まとめ
第6章 長繊維分散による複合材料製造
1 ガラス長繊維強化ポリプロピレン樹脂「モストロンTM-L」
1.1 はじめに
1.2 モストロンTM-Lとは
1.2.1 製造方法
1.2.2 特徴
1.3 材料設計に関する考え方
1.3.1 GFMBの材料設計
1.3.2 希釈樹脂(顔料の影響)
1.3.3 射出成形における機械物性(残存GF長と界面接着性)
1.4 GF配向を活かした設計支援
2 セルロースナノファイバーの応用と樹脂複合体マスターバッチ
2.1 セルロースとその研究背景
2.2 セルロースナノファイバーと各種樹脂との複合化
2.3 セルロースナノファイバー膜,紙
2.4 樹脂含浸法
2.5 全セルロース複合体
2.6 セルロースナノファイバーとゴムとの混合化
2.7 弊社においてのセルロースナノファイバービジネス
3 樹脂混練プロセスにおいて解繊されたセルロースナノファイバー/熱可塑性樹脂複合材料の特性
3.1 セルロースナノファイバーの特徴,性質と熱可塑性樹脂との複合化
3.2 CNF強化熱可塑性樹脂製造プロセス「京都プロセス」―セルロースの耐熱性とパルプ直接解繊―
3.3 京都プロセスにより製造されたCNF強化熱可塑性樹脂の特性
3.3.1 加工温度が低い汎用エンジニアリングプラスチックス
3.3.2 加工温度が高い汎用エンジニアリングプラスチックス
3.4 まとめ
4 バイオマスフィラーのプラスチックへの利用
4.1 はじめに
4.2 WPCの製造
4.2.1 WPCの原料
4.2.2 WPCのコンパウンド化
4.2.3 WPCの成形
4.3 WPCの性能
4.4 バイオマスフィラーを利用したプラスチックの展望
5 長繊維強化複合プラスチックの直接成形システム
5.1 はじめに
5.2 連続式二軸混練機について
5.3 直接成形システム・LFTDとは
5.4 CFの繊維長制御,高分散,長繊維化
5.5 成形事例の紹介
5.6 おわりに
-

リビングラジカル重合《普及版》
¥5,500
2018年刊「リビングラジカル重合」の普及版。構造が精密に制御された高分子を合成できる優れた重合手法であるリビングラジカル重合の、ゴム・シーリング、粘・接着剤など多岐にわたる応用分野を解説した1冊。
(監修:松本章一)
<a href="https://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=115803"target=”_blank”>この本の紙版「リビングラジカル重合(普及版)」の販売ページはこちら(別サイトが開きます)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は、2018年当時のものを使用しております。
松本章一 大阪府立大学大学院
澤本光男 中部大学;京都大学
大塚英幸 東京工業大学
大内 誠 京都大学
森 秀晴 山形大学
上垣外正己 名古屋大学
藤田健弘 京都大学
山子 茂 京都大学
中村泰之 (国研)物質・材料研究機構
佐藤浩太郎 名古屋大学
内山峰人 名古屋大学大学院
金岡鐘局 滋賀県立大学
伊田翔平 滋賀県立大学
後関頼太 東京工業大学
石曽根隆 東京工業大学
早川晃鏡 東京工業大学
小林元康 工学院大学
遊佐真一 兵庫県立大学
寺島崇矢 京都大学
南 秀人 神戸大学
杉原伸治 福井大学
岩 泰彦 関西大学
谷口竜王 千葉大学大学院
吉田絵里 豊橋技術科学大学
河野和浩 大塚化学㈱
中川佳樹 ㈱カネカ
有浦芙美 アルケマ㈱
嶋中博之 大日精化工業㈱
坂東文明 日本ゼオン㈱
佐藤絵理子 大阪市立大学大学院
辻井敬亘 京都大学
吉川千晶 (国研)物質・材料研究機構
榊原圭太 京都大学
北山雄己哉 神戸大学大学院
箕田雅彦 京都工芸繊維大学
須賀健雄 早稲田大学
有田稔彦 東北大学
-------------------------------------------------------------------------
<<目次>>
〔第Ⅰ編 基礎研究概説〕
第1章 リビングラジカル重合:総論
1 はじめに
1.1 ラジカル重合
1.2 連鎖重合
2 リビング重合とリビングラジカル重合
2.1 リビング重合の定義
2.2 リビング重合の発展とリビングラジカル重合
2.3 リビング重合とドーマント種
2.4 精密重合
2.5 リビング重合の特徴
2.6 リビング重合の実証
2.7 リビング重合と高分子精密合成
第2章 ニトロキシドを用いるリビングラジカル重合と動的共有結合ポリマー
1 はじめに
2 ニトロキシドラジカルを用いるリビングラジカル重合
2.1 ニトロキシドラジカル添加によるリビングラジカル重合
2.2 アルコキシアミン骨格を利用した精密高分子合成
3 ニトロキシドラジカルを用いる動的共有結合ポリマーの設計
3.1 動的共有結合化学とアルコキシアミン骨格
3.2 主鎖型動的共有結合ポリマーの設計
3.3 側鎖型および架橋型動的共有結合ポリマーの設計
4 おわりに
第3章 原子移動ラジカル重合によるシークエンス制御
1 緒言
2 交互共重合性モノマーを用いた配列制御
3 非共役モノマー種を用いた配列制御
4 かさ高さを用いた配列制御
5 環化重合を用いた配列制御
6 高効率的不活性化が可能なATRPを用いた配列制御
7 結言
第4章 RAFT重合による機能性高分子の分子設計・合成
1 はじめに
2 共役ジエン類のRAFT重合
3 ジビニルモノマー類のRAFT重合
4 反応性ハロゲン部位を有するビニルモノマー類のRAFT重合
5 おわりに
第5章 リビングラジカル重合系における立体構造制御
1 はじめに
2 拘束空間による立体構造制御
3 モノマー置換基による立体構造制御
4 溶媒や添加物による立体構造制御
5 おわりに
第6章 有機テルル化合物を用いるラジカル重合
1 はじめに
2 重合条件と反応機構
3 TERPによる高分子エンジニアリング
3.1 ホモポリマーの合成
3.2 共重合体の合成
3.3 重合末端の変換
3.4 官能基を持つ開始剤の合成と利用
4 多分岐高分子の制御合成
5 まとめ
第7章 制御重合を活用したラジカル重合反応の停止機構の解析
1 はじめに
1.1 研究の背景とコンセプト
1.2 これまでの研究報告
2 機構解明の手法
2.1 リビングラジカル重合法を利用した重合停止反応の解析方法
2.2 反応機構解析に用いられるリビングラジカル重合法とその反応方法
3 各モノマーについての重合停止反応機構の決定
3.1 MMA
3.2 スチレン
3.3 アクリレート
3.4 イソプレンの重合停止反応機構
4 停止反応機構に対する溶媒粘度の効果
5 まとめ
第8章 活性種の直接変換による新しい精密重合
1 はじめに
2 間接的な活性種の変換
3 直接的活性種の変換
4 炭素―ハロゲン結合を介した直接活性種変換
5 RAFT末端をドーマント種として介した直接的活性種変換と相互変換重合
6 まとめ
第9章 RAFT機構によるリビングカチオン重合
1 はじめに
2 カチオンRAFT重合の反応機構
3 カチオンRAFT重合における連鎖移動剤
4 カチオンRAFT重合におけるカチオン源
5 カチオンRAFT重合におけるモノマー
6 カチオンRAFT重合を用いた精密高分子合成
7 まとめ
第10章 リビングカチオン重合による機能性高分子の合成
1 はじめに
2 リビングカチオン重合の基礎
2.1 比較的弱いルイス酸を単独で用いる系
2.2 強いルイス酸と添加物を組み合わせた系
2.2.1 添加塩基(ルイス塩基)の系
2.2.2 添加塩の系
3 リビングカチオン重合の新しい展開
4 リビングカチオン重合を用いた種々の機能性高分子合成
4.1 植物由来モノマーから新しいバイオベース材料へ
4.2 刺激応答性材料
4.3 種々のポリマーによる表面・界面機能の制御
5 まとめ
第11章 リビングアニオン重合による水溶性・温度応答性高分子の合成
1 はじめに
2 水溶性・温度応答性ポリ(メタ)アクリルアミドの合成
2.1 N,N-ジアルキルアクリルアミド類のアニオン重合
2.2 保護基を有するN-イソプロピルアクリルアミドのアニオン重合
2.3 N,N-ジアルキルメタクリルアミドのアニオン重合
2.4 α-メチレン-N-メチルピロリドンのアニオン重合
3 水溶性・温度応答性ポリメタクリル酸エステルの合成
4 おわりに
〔第Ⅱ編 機能性高分子開発〕
第1章 リビングラジカル重合による高透明耐熱ポリマー材料の設計
1 はじめに
2 耐熱性アクリルポリマーの設計
3 ポリ置換メチレンの分子構造設計
3.1 マレイミド共重合体
3.2 ポリフマル酸エステル
4 ジチオ安息香酸エステルを用いるDiPFのRAFT重合
5 トリチオカーボネート誘導体を用いるDiPFのRAFT重合
6 おわりに
第2章 リビングラジカル重合によるPOSS含有ブロック共重合体の合成
1 はじめに
2 RAFT法によるPOSS含有ブロック共重合体の合成
2.1 POSS含有ブロック共重合体の分子設計
2.2 RAFT法によるホモポリマーの合成
2.3 RAFT法によるブロック共重合体の合成
2.4 PMAPOSS-b-PTFEMAのバルクにおける高次構造解析
2.5 PMAPOSS-b-PTFEMAの薄膜構造解析および誘導自己組織化(Directed Self-Assembly:DSA)
3 おわりに
第3章 異種材料接着を指向した表面開始制御ラジカル重合による表面改質
1 はじめに
2 表面開始制御ラジカル重合
3 高分子電解質ブラシによる接着
4 今後の課題と展望
第4章 リビングラジカル重合によるジャイアントベシクルの合成
1 はじめに
2 ポリイオンコンプレックスによるジャイアントベシクル形成
3 pH応答ジブロック共重合体によるジャイアントベシクル形成
4 おわりに
第5章 リビングラジカル重合による両親媒性ポリマーの合成と精密ナノ会合体の創出
1 はじめに
2 両親媒性ランダムコポリマー
2.1 精密合成
2.2 一分子折り畳みによるユニマーミセル
2.3 精密自己組織化による多分子会合ミセル
2.4 温度応答性ミセル
2.5 ナノ構造構築と機能
3 タンデム重合による両親媒性グラジエントコポリマー
4 末端選択的エステル交換と両親媒性局所機能化ブロックコポリマー
5 両親媒性環化ポリマー
6 両親媒性ミクロゲル星型ポリマー
7 おわりに
第6章 リビングラジカル重合を用いた機能性高分子微粒子の合成
1 はじめに
2 リビングラジカル重合による架橋粒子
3 リビングラジカル重合による中空(カプセル)粒子
4 リビングラジカル重合による内部モルフォロジーの制御
5 リビングラジカル重合による粒子表面性質制御
6 重合誘起自己組織化法(PISA)による微粒子の合成
7 おわりに
第7章 水酸基含有ビニルエーテル類の精密ラジカル重合と機能
1 はじめに
2 ビニルエーテル類の単独ラジカル重合が可能になるまで
3 水酸基含有ビニルエーテル類のフリーラジカル重合
4 水酸基含有ビニルエーテル類のRAFTラジカル重合
5 種々の水酸基含有ビニルエーテルを含むポリマーの合成・機能・応用
第8章 ポリマーバイオマテリアルの合成と医用材料への展開
1 はじめに
2 薬物担体の設計
3 バイオコンジュゲーション
4 生分解性ポリマー
5 表面改質(抗ファウリング,抗菌性)
6 おわりに
第9章 ラジカル的な炭素―炭素結合交換反応を用いる自己修復性ポリマー
1 はじめに
2 ジアリールビベンゾフラノン(DABBF)の特徴と反応性
3 DABBF骨格を有する自己修復性ポリマー
3.1 DABBF骨格を有する架橋高分子の合成と反応性
3.2 DABBF骨格を有する自己修復性高分子ゲルの設計
3.3 DABBF骨格を有する自己修復性バルク高分子の設計
4 おわりに
第10章 クリック反応およびリビングラジカル重合による機能性微粒子の調製
1 はじめに
2 クリック反応およびリビングラジカル重合による高分子微粒子の表面修飾と機能創出
2.1 アジ化ナトリウムを用いたα-ハロエステル基のアジド基への変換
2.2 ATRP開始基を有するカチオン性およびアニオン性高分子微粒子の合成
2.3 高分子微粒子表面のATRP開始基のアジド化
2.4 CuAACを利用した蛍光ラベル化によるATRP開始基の表面濃度およびグラフト密度の評価
3 高分子微粒子表面のグラフト鎖による機能発現
4 おわりに
第11章 光精密ラジカル重合を用いる高分子の設計と合成
1 はじめに
2 ニトロキシドを用いる光精密ラジカル重合法
3 光照射で進行するRAFT重合による光精密ラジカル重合法
4 光原子移動ラジカル重合による光精密ラジカル重合法
〔第Ⅲ編 応用展開〕
第1章 リビングラジカル重合法を用いた高機能ポリマー“TERPLUS”の開発
1 はじめに
2 有機テルル化合物を用いるリビングラジカル重合法(TERP法)
3 粘着剤開発への応用
4 TERP法を応用した粘着剤
5 顔料分散剤開発への応用
6 TERP法を応用した顔料分散剤
7 生産体制
8 まとめ
第2章 原子移動ラジカル重合を利用したテレケリックポリアクリレートの開発
1 序論
2 テレケリックポリアクリレートの開発の背景
3 工業化技術
4 特性と用途
5 おわりに
第3章 リビングラジカル重合の工業化と応用例
1 はじめに
2 アルケマのNMP機構:BlocBuilder? MA
3 アクリル系ブロックコポリマー:Nanostrength?
4 ブロックコポリマーによるエポキシ樹脂のじん性改質
5 ナノ構造PMMAキャスト板
6 NMPリビングポリマー:Flexibloc?
7 おわりに
第4章 有機触媒型制御重合を用いた新しい機能性ポリマー製造技術の開発
1 諸言
2 有機触媒型制御重合の反応機構と触媒
3 機能性ポリマーの開発と色材への実用化事例
3.1 顔料分散剤
3.2 水性顔料インクジェットインクへの応用
3.2.1 顔料分散剤の構成
3.2.2 顔料分散性と保存安定性
3.3 無機顔料の表面処理剤への応用
3.3.1 顔料表面処理剤の構成
3.3.2 顔料の表面処理と顔料分散性
4 最後に
第5章 リビングラジカル共重合による精密ニトリルゴムの合成
1 はじめに
2 リビングラジカル重合
3 開発の動機
4 遷移金属触媒を用いるリビングラジカル重合
5 ルテニウム触媒による重合
6 鉄触媒による重合
7 まとめ
第6章 リビングラジカル重合を活用した易解体性粘着材料の設計
1 はじめに
2 反応性高分子を用いる易解体性粘着材料の設計
3 主鎖分解性ポリマーを利用する易解体性粘着材料の設計
4 架橋とガス生成を相乗的に利用する易解体性粘着材料の設計
4.1 反応性アクリル系ブロック共重合体の高分子量化
4.2 半減期が異なる二種の開始剤を用いるTERPの開発
5 おわりに
第7章 リビングラジカル重合によるポリマーブラシ形成とトライボロジー制御
1 はじめに
2 リビングラジカル重合によるポリマーブラシの精密合成
3 ポリマーブラシの構造と物性
4 トライボロジー制御
第8章 リビングラジカル重合による材料表面の生体適合性向上
1 はじめに
2 CPBのバイオイナート特性
2.1 CPBのサイズ排除効果とタンパクとの相互作用
2.2 タンパク吸着
2.3 細胞接着
2.4 血小板粘着
3 濃厚ポリマーブラシのバイオアクティブ特性
4 CPBを用いた生体適合性材料
4.1 構造制御ボトルブラシのハイドロゲルコーティング
4.2 表面改質セルロースナノファイバーを用いた足場材料
4.3 CPB被覆ナノ微粒子を用いた医療材料
5 さいごに
第9章 リビングラジカル重合を用いた医療用分子認識材料の創製
1 はじめに
2 リビングラジカル重合と生体分子複合化による分子認識材料創製
2.1 遺伝子デリバリー
2.2 DNA検出
2.3 高分子ワクチン
3 リビングラジカル重合による高分子リガンドの創製
3.1 バイオマーカータンパク質に対する高分子リガンド
3.2 レクチンに対する高分子リガンド
3.3 高分子リガンドカプセル
4 リビングラジカル重合による疾病診断のための分子インプリントポリマーの創製
5 おわりに
第10章 精密重合法とナノインプリント法の融合による階層的表面構造ポリマー薄膜の創製
1 はじめに
2 ナノインプリント法と精密グラフト重合を用いるポリマーピラー薄膜の作製
3 polyCMSを素材ポリマーとするグラフト修飾ピラー薄膜の作製と表面特性
4 光架橋性ポリマーを素材とするグラフト修飾ピラー薄膜の作製と表面特性
5 高規則性貫通型AAOを鋳型として作製したグラフト修飾ピラー薄膜への展開
第11章 リビングラジカル重合を用いたUV硬化と傾斜ナノ構造の形成
1 はじめに
2 光リビングラジカル重合の研究動向
3 光リビングラジカル重合のUV硬化への適用と重合誘起型相分離
4 精密UV硬化による相分離同時形成:位置付けと将来展望
第12章 リビングラジカル重合法を援用したフィラーの機能化(無機フィラーからセルロースナノ結晶まで)
1 概略
2 高分子によるナノ微粒子表面の機能化
3 固定化=グラフト重合からの脱却
4 粒子共存制御ラジカル重合法の開発
5 タイヤトレッドゴムの補強材としての活用
6 フィラー充填による3次元伝導内部構造を持つ電解質膜への応用
7 セルロースナノクリスタル粉末の製造とフィラーとしての応用展開
8 まとめ
-

有機フッ素化合物の最新動向《普及版》
¥5,280
2018年刊「有機フッ素化合物の最新動向」の普及版。電解液、発光材料、機能性色素、フッ素樹脂など様々な機能性材料として応用される有機フッ素化合物を解説した1冊。
(監修:今野 勉)
<a href="https://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=115804"target=”_blank”>この本の紙版「有機フッ素化合物の最新動向(普及版)」の販売ページはこちら(別サイトが開きます)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は、2018年当時のものを使用しております。
今野 勉 京都工芸繊維大学
柴富一孝 豊橋技術科学大学
網井秀樹 群馬大学
國信洋一郎 九州大学
新名清輝 名古屋工業大学
柴田哲男 名古屋工業大学
住井裕司 名古屋工業大学
藤田健志 筑波大学
渕辺耕平 筑波大学
市川淳士 筑波大学
山崎 孝 東京農工大学
丹羽 節 (国研)理化学研究所
矢島知子 お茶の水女子大学
井上宗宣 (公財)相模中央化学研究所
山口博司 名古屋大学
水上 進 東北大学
平井憲次 (公財)相模中央化学研究所
小林 修 (公財)相模中央化学研究所
森 達哉 住友化学㈱
氏原一哉 住友化学㈱
庄野美徳 住友化学㈱
南部典稔 東京工芸大学
山田重之 京都工芸繊維大学
久保田俊夫 茨城大学
折田明浩 岡山理科大学
船曳一正 岐阜大学
大槻記靖 日本ゼオン㈱
伊藤隆彦 ㈱フロロテクノロジー
井本克彦 ダイキン工業㈱
入江正樹 ダイキン工業㈱
長谷川直樹 ㈱豊田中央研究所
宮崎久遠 旭化成㈱
西 栄一 旭硝子㈱
-------------------------------------------------------------------------
<<目次>>
第1章 フッ素化合物の合成
1 最近のフッ素化剤動向
1.1 はじめに
1.2 求核的フッ素化剤の動向
1.2.1 Fluolead
1.2.2 XtalFluor
1.2.3 PhenoFluor
1.2.4 PhenoFluorMix
1.2.5 PyFluor
1.3 N-F結合型求電子的フッ素化剤の最近の応用例
1.3.1 遷移金属触媒を用いたC-F結合形成反応
1.3.2 キラルアニオン相間移動触媒
1.4 おわりに
2 最近のフルオロアルキル化剤の動向
2.1 はじめに
2.2 求核的トリフルオロメチル化反応の進展
2.3 求電子的トリフルオロメチル化反応,酸化的トリフルオロメチル化反応の進展
2.4 ラジカル的トリフルオロメチル化反応の進展
2.5 おわりに
3 位置選択的なトリフルオロメチル化反応の開発
3.1 はじめに
3.2 C(sp2)-H結合の位置選択的なトリフルオロメチル化
3.2.1 5員環ヘテロ芳香族化合物の位置選択的なトリフルオロメチル化
3.2.2 6員環ヘテロ芳香族化合物の位置選択的なトリフルオロメチル化
3.2.3 芳香族化合物の位置選択的なトリフルオロメチル化
3.2.4 オレフィン性C-H結合の位置選択的なトリフルオロメチル化
3.3 C(sp3)-H結合の位置選択的なトリフルオロメチル化
3.3.1 カルボニルα位のトリフルオロメチル化
3.3.2 ベンジル位のトリフルオロメチル化
3.4 今後の展望
4 ペンタフルオロスルファニル化合物の最新動向
4.1 はじめに
4.2 SF5基置換芳香族炭化水素の合成
4.3 SF5基置換複素環式化合物の合成
4.3.1 芳香族炭化水素上にSF5基が結合した複素環式化合物の合成
4.3.2 SF5基が複素環上に直接結合した複素環式化合物(5員環)の合成
4.3.3 SF5基が複素環上に直接結合した複素環式化合物(6員環)の合成
4.4 SF5芳香環部位およびSF5複素環式化合物部位を直接導入する試薬の開発
4.5 おわりに
5 トリフルオロメタンスルホニル基含有化合物の最新動向
5.1 はじめに
5.2 芳香族トリフロン(Ar-SO2CF3),複素環トリフロン(HetAr-SO2CF3)の合成
5.2.1 フリーデル・クラフツ反応を用いる手法
5.2.2 Thia-Fries転位を用いる合成法
5.2.3 超原子価ヨードニウム塩を用いたアリールトリフロンの合成
5.2.4 芳香族ジアゾ化合物とCF3SO2Naを用いた手法
5.2.5 CF3SO2NaとPd触媒下でのカップリング反応を用いた手法
5.2.6 ベンザインに対するトリフリル化反応
5.2.7 N-芳香族プロピオールアミドとスルフィン酸の光環化反応
5.2.8 トリフリルジアリール-λ3-ヨードニウムイリド塩試薬を用いた芳香族トリフロン,ピリジルトリフロンの合成
5.3 おわりに
6 テトラフルオロエチレン基を有する有機分子の合成開発
6.1 はじめに
6.2 テトラフルオロエチレン基含有化合物の合成法
6.2.1 直接法
6.2.2 間接法(ビルディング・ブロック法)
7 フッ素脱離を利用する炭素-フッ素結合活性化反応の現状
7.1 序
7.2 遷移金属によるフッ素脱離
7.3 β-フッ素脱離によるC-F結合活性化
7.3.1 酸化的環化
7.3.2 酸化的付加
7.3.3 求電子的カルボ(アミノ)メタル化
7.3.4 挿入
7.3.5 ラジカル付加
7.4 α-フッ素脱離によるC-F結合活性化
7.5 総括
8 フッ素原子あるいは含フッ素アルキル基を有する不斉炭素の構築法
8.1 はじめに
8.2 触媒的アルドール反応
8.3 キラルなスルフィンアミドを用いた反応
8.4 直接的なトリフルオロメチル化ならびにフッ素化反応
8.5 環化を伴うトリフルオロメチル化ならびにフッ素化反応
8.6 アルキン類と含フッ素カルボニル化合物との反応
8.7 含フッ素アルキン類とα,β-不飽和カルボニル化合物との反応
8.8 トリフルオロメチル基を有した化合物のプロトン移動反応
8.9 おわりに
9 TFE,HFP,CTFEなどの安価な市販のフッ素原料を用いた合成
9.1 はじめに:ペルフルオロアルケン類を起点とする精密有機合成
9.2 脱フッ素を経る置換反応
9.2.1 10族遷移金属触媒を用いた交差カップリング反応
9.2.2 銅触媒を用いた交差カップリング反応
9.2.3 N-ヘテロサイクリックカルベン(NHC)類の付加
9.3 炭素-炭素二重結合への付加反応
9.3.1 銅を用いた付加反応
9.3.2 金属フッ化物の付加を起点とする変換
9.3.3 ニッケル(0)錯体への環化付加を経る変換
9.4 ペルフルオロアルケン類の交差オレフィンメタセシス反応への利用
9.5 TFEの実験室レベルでの新規発生法
9.6 最後に
10 可視光レドックス触媒を用いた有機フッ素化合物の合成
10.1 はじめに
10.2 ルテニウム,イリジウム錯体を用いた可視光ペルフルオロアルキル化
10.3 有機色素を用いた可視光ペルフルオロアルキル化
10.4 錯形成などを利用した可視光ペルフルオロアルキル化
10.5 おわりに
第2章 医農薬分野への応用
1 フッ素系医薬の動向
1.1 はじめに
1.2 フッ素系医薬
1.2.1 消化器官用薬
1.2.2 糖尿病治療薬
1.2.3 循環器官用薬
1.2.4 血液用薬
1.2.5 鎮痛・抗炎症薬
1.2.6 内分泌系用薬
1.2.7 抗菌薬
1.2.8 抗真菌薬
1.2.9 抗ウィルス薬
1.2.10 抗悪性腫瘍薬
1.2.11 中枢神経系用薬
1.2.12 泌尿器官用薬
1.2.13 感覚器官用薬
1.2.14 呼吸器官用薬
1.2.15 遺伝性疾患治療薬
1.2.16 放射線診断用薬
2 PET用診断薬の合成ならびにその応用
2.1 PET検査について
2.2 サイクロトロンと標識合成装置
2.3 PET核種について
2.4 PET核種18Fについて
2.4.1 18O(p,n)18F反応について
2.4.2 20Ne(d,α)18F反応について
2.4.3 その他の18F製造法について
2.5 当院における18F-PET用診断薬について
2.6 その他の臨床研究18F-PET診断薬
2.7 新規18F-PET診断薬の開発に向けて
3 MRIなどへの機能性含フッ素プローブ応用
3.1 はじめに
3.2 分子イメージングプローブの開発(その1):OFF/ON型低分子19F MRIプローブ
3.3 19F MRIプローブの高感度化
3.4 分子イメージングプローブの開発(その2):OFF/ON型ナノ粒子19F MRIプローブ
3.5 まとめ
4 フッ素系農薬の開発動向
4.1 はじめに
4.2 フッ素系除草剤
4.2.1 アセト乳酸合成酵素(ALS)阻害剤
4.2.2 プロトポルフィリノーゲン酸化酵素(PPO)阻害剤
4.2.3 カロテノイド生合成阻害剤
4.2.4 細胞分裂阻害剤
4.2.5 その他のフッ素系阻害剤
4.3 フッ素系殺虫剤
4.3.1 GABA作動性塩化物イオン(塩素イオン)チャネルブロッカー
4.3.2 ナトリウムチャネルモジュレーター
4.3.3 ニコチン性アセチルコリン受容体(nAChR)競合的モジュレーター
4.3.4 プロトン勾配を撹乱する酸化的リン酸化脱共役剤
4.3.5 キチン生合成阻害剤
4.3.6 ミトコンドリア電子伝達系複合体及び複合体阻害剤
4.3.7 リアノジン受容体モジュレーター
4.3.8 その他の作用機構に属するフッ素系殺虫剤
4.3.9 作用機構が不明あるいは不明確なフッ素系殺虫剤
4.4 フッ素系殺菌剤
4.4.1 ミトコンドリア呼吸鎖電子伝達系複合体阻害剤
4.4.2 ステロール生合成のC14位のデメチラーゼ阻害剤(DMI剤)
4.4.3 その他の作用機構に属するフッ素系殺菌剤
4.4.4 作用機構未分類のフッ素系殺菌剤
4.5 最後に
5 含フッ素家庭防疫用殺虫剤の探索研究
5.1 はじめに
5.2 アミドフルメト
5.3 ジメフルトリン
5.4 メトフルトリン
5.5 プロフルトリン
5.6 モンフルオロトリン
5.7 α-ピロン化合物
5.8 おわりに
第3章 低分子機能性材料
1 フッ素化ジエーテル化合物の物性および電気化学特性
1.1 はじめに
1.2 物理的,化学的および電気化学的性質
1.3 リチウム二次電池への応用
2 フッ素系発光材料
2.1 はじめに
2.2 フッ素系蛍光材料
2.2.1 希薄溶液で利用できる含フッ素蛍光分子
2.2.2 固体状態で発光可能な含フッ素蛍光分子
2.2.3 液晶状態で発光可能な含フッ素蛍光分子
2.3 フッ素系りん光材料
2.3.1 含フッ素配位子をもつイリジウム錯体
2.3.2 含フッ素りん光発光性金錯体
2.3.3 ハロゲン結合型りん光発光共結晶
2.4 おわりに
3 有機電界効果トランジスターを指向した含フッ素有機半導体材料の設計と評価
3.1 はじめに
3.2 BPEPEの合成とキャリア輸送能評価
3.3 FPEの合成とキャリア輸送能評価
3.4 おわりに
4 フッ素置換基を活用した機能性色素の設計とその特性
4.1 はじめに
4.2 モノメチンシアニン色素へのフッ素置換基の導入効果
4.3 フッ素置換基を有するモノ,トリ,およびペンタメチンシアニン色素
4.4 ヘプタメチンシアニン色素へのフッ素置換基導入の効果
4.5 おわりに
5 地球環境型フッ素系溶剤“ゼオローラH”
5.1 はじめに
5.2 洗浄剤の動向
5.3 フッ素系洗浄剤の種類と基本物性比較
5.4 ゼオローラHとは
5.4.1 毒性データ
5.4.2 ゼオローラHシリーズの基本物性
5.4.3 ゼオローラHTAによる洗浄システム
5.4.4 ゼオローラHTAの溶解性・洗浄性
5.4.5 ランニングコスト低減
5.5 おわりに
第4章 高分子機能性材料
1 常温型フッ素系コーティング剤による電子部品・実装基板の防湿性・防水性付与
1.1 はじめに
1.2 概要
1.3 皮膜特性面での優位点
1.4 使用上のメリット
1.4.1 皮膜不燃性
1.4.2 コーティング液非引火性
1.4.3 高信頼性
1.5 使用例
1.5.1 防湿・イオンマイグレーション防止・リーク防止
1.5.2 リチウムイオン電池電解液対策
1.5.3 LEDの劣化防止(硫化防止性)
1.6 今後の方向性と環境への配慮
2 塗料用水性フッ素樹脂の耐候性と水性架橋技術
2.1 はじめに
2.2 有機溶剤と環境問題
2.3 フッ素樹脂の水性化
2.4 水性塗料用フッ素樹脂
2.4.1 エマルションタイプ
2.4.2 水性架橋システム
2.5 終わりに
3 自動車向け高機能フッ素ゴム
3.1 序章
3.2 フッ素ゴムの種類と特徴
3.2.1 フッ素ゴムの特徴とASTM分類
3.3 自動車の地球環境問題への取り組み
3.4 自動車向けフッ素ゴムに求められる機能と開発動向
3.4.1 排気系
3.4.2 燃料系
3.4.3 動力系
3.4.4 冷却系
3.5 おわりに
4 フッ素電解質材料の固体高分子形燃料電池触媒層への応用
4.1 はじめに
4.2 固体高分子形燃料電池の触媒層
4.3 触媒層アイオノマー
4.3.1 触媒層アイオノマーのプロトン伝導性
4.3.2 触媒層アイオノマーのガス透過性
4.3.3 触媒層アイオノマーの白金触媒表面への吸着による触媒被毒
4.4 まとめ
5 固体高分子型燃料電池用フッ素系電解質膜の高機能化
5.1 はじめに
5.2 固体高分子型燃料電池(PEFC)
5.3 電解質膜の特徴と機能発現因子
5.4 高性能,高耐久電解質膜の開発
5.5 最後に
6 接着性フッ素樹脂及びその応用
6.1 緒言
6.2 フッ素樹脂の特性,市場及び用途
6.3 接着性フッ素系高分子材料の紹介及び複合化
6.3.1 接着性フッ素樹脂とは
6.3.2 接着性フッ素樹脂を用いた複合化
6.4 自動車におけるフッ素樹脂系高分子材料の用途
6.5 燃料系の防止材料,長期耐久部材としてのフッ素樹脂
6.5.1 燃料チューブの動向
6.5.2 フッ素樹脂の燃料バリア機構
6.5.3 成形性に優れた接着性ETFEの開発と燃料ホースシステム
6.6 接着性フッ素樹脂の新たな展開
6.7 フッ素技術によるポリアミド樹脂の改質について
-

スマートセルインダストリー《普及版》
¥3,850
2018年刊「スマートセルインダストリー」の普及版。ゲノム情報等の大規模データベース構築、遺伝子配列シミュレーション、長鎖DNA合成技術やAI基盤技術など、スマートセルを創出するためのプラットフォーム技術を徹底解説した1冊。
(監修:久原 哲)
<a href="https://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=115764"target=”_blank”>この本の紙版「スマートセルインダストリー ―微生物細胞を用いた物質生産の展望― (普及版)」の販売ページはこちら(別サイトが開きます)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は、2018年当時のものを使用しております。
久原 哲 九州大学
蓮沼誠久 神戸大学
田村具博 産業技術総合研究所
近藤昭彦 神戸大学
森 良仁 日本テクノサービス㈱
柘植謙爾 神戸大学
高橋俊介 神戸大学
板谷光泰 慶應義塾大学
谷内江望 東京大学;慶應義塾大学
石黒 宗 慶應義塾大学;東京大学
石井 純 神戸大学
西 晶子 神戸大学
北野美保 神戸大学
中村朋美 神戸大学
庄司信一郎 神戸大学
秀瀬涼太 神戸大学
木村友紀 千葉大学
関 貴洋 千葉大学
大谷悠介 千葉大学
栗原健人 千葉大学
梅野太輔 千葉大学
八幡 穣 筑波大学
野村暢彦 筑波大学
三谷恭雄 産業技術総合研究所
野田尚宏 産業技術総合研究所
菅野 学 産業技術総合研究所
松田史生 大阪大学
光山統泰 産業技術総合研究所
荒木通啓 京都大学;神戸大学
白井智量 理化学研究所
厨 祐喜 神戸大学
川﨑浩子 製品評価技術基盤機構
細山 哲 製品評価技術基盤機構
寺尾拓馬 製品評価技術基盤機構
亀田倫史 産業技術総合研究所
池部仁善 産業技術総合研究所
油谷幸代 産業技術総合研究所
齋藤 裕 産業技術総合研究所
田島直幸 産業技術総合研究所
西宮佳志 産業技術総合研究所
玉野孝一 産業技術総合研究所
北川 航 産業技術総合研究所
安武義晃 産業技術総合研究所
守屋央朗 岡山大学
寺井悟朗 東京大学
伊藤潔人 ㈱日立製作所
武田志津 ㈱日立製作所
広川安孝 九州大学
花井泰三 九州大学
酒瀬川信一 旭化成ファーマ㈱
小西健司 旭化成ファーマ㈱
村田里美 旭化成ファーマ㈱
吉田圭太朗 産業技術総合研究所
小笠原 渉 長岡技術科学大学
志田洋介 長岡技術科学大学
鈴木義之 長岡技術科学大学
掛下大視 花王㈱
五十嵐一暁 花王㈱
小林良則 (一財)バイオインダストリー協会
田代康介 九州大学
矢追克郎 産業技術総合研究所
吉田エリカ 味の素㈱
大貫朗子 味の素㈱
臼田佳弘 味の素㈱
小森 彩 神戸天然物化学㈱
小島 基 神戸天然物化学㈱
鈴木宗典 神戸天然物化学㈱
仲谷 豪 長瀬産業㈱
山本省吾 長瀬産業㈱
石井伸佳 長瀬産業㈱
曽田匡洋 長瀬産業㈱
阪本 剛 三菱ケミカル㈱
山田明生 三菱ケミカル㈱
豊田晃一 地球環境産業技術研究機構
久保田健 地球環境産業技術研究機構
小暮高久 地球環境産業技術研究機構
乾 将行 地球環境産業技術研究機構
片山直也 江崎グリコ㈱
大段光司 江崎グリコ㈱
塚原正俊 ㈱バイオジェット
熊谷俊高 ㈱ファームラボ
藤森一浩 産業技術総合研究所
久保亜希子 江崎グリコ㈱
佐原健彦 産業技術総合研究所
竹村美保 石川県立大学
三沢典彦 石川県立大学
高久洋暁 新潟薬科大学
荒木秀雄 不二製油グループ本社㈱
中川 明 石川県立大学
南 博道 石川県立大学
宮田 健 鹿児島大学
新川 武 琉球大学
玉城志博 琉球大学
梅津光央 東北大学
新井亮一 信州大学
七谷 圭 東北大学
中山真由美 東北大学
新谷尚弘 東北大学
阿部敬悦 東北大学
-------------------------------------------------------------------------
<<目次>>
総論
1 はじめに
2 先端バイオ技術の国際動向
3 我が国独自のスマートセルインダストリーの構築へ
4 微生物開発に資する情報解析技術
5 バイオ×デジタルによる「スマートセル創出プラットフォーム」の開発
6 将来展開
【第1編 ハイスループット合成・分析・評価技術】
第1章 ハイスループット長鎖DNA合成技術
1 ハイスループットDNA化学合成技術の開発
1.1 はじめに
1.2 長鎖DNA合成に特化したDNA合成機の試作
1.3 ハイスループットDNA合成機の試作
1.4 おわりに
2 OGAB法による長鎖DNA合成技術
2.1 はじめに
2.2 枯草菌を用いた遺伝子集積法のOGAB法
2.3 自動化を意識した遺伝子集積法の第二世代OGAB法
2.4 おわりに
3 枯草菌ゲノムベクターを利用する長鎖DNAの(超)長鎖化技術
3.1 ゲノム合成とは
3.2 ゲノム合成に必須な枯草菌ゲノムベクターシステム
3.3 第3世代ドミノ法,接合伝達システム開発
3.4 第2世代のドミノ法が示した,合成対象ゲノムのGC含量制限
3.5 まとめ
4 全ゲノム合成時代における長鎖DNA合成の考え方
4.1 全ゲノム合成時代のための生物学小史
4.2 DNAアセンブリ技術群
4.3 次世代のDNAアセンブリ
4.4 共通の課題
第2章 ハイスループット微生物構築・評価技術
1 微生物を用いた物質生産とハイスループット微生物構築技術
1.1 はじめに
1.2 微生物によるバイオ化学品の発酵生産
1.3 微生物構築の自動化システム―AmyrisやZymergenを例に―
1.4 自動化システムを取り巻く状況
1.5 おわりに
2 バイオセンサー利用したハイスループット評価技術
2.1 はじめに
2.2 見える代謝物を見る戦略の限界
2.3 代謝物センサーを用いる細胞工学
2.4 見えない代謝物を見る
2.5 展望
3 非破壊イメージングによるハイスループット評価技術
3.1 はじめに
3.2 細胞形態や空間配置の非破壊・低侵襲3次元評価技術
3.3 細胞の種類や代謝状態の非破壊評価技術
3.4 おわりに
第3章 オミクス解析技術
1 トランスクリプトーム解析技術
1.1 RNA-seqのサンプル調製の概要
1.2 RNA-Seqデータの品質管理
1.3 スマートセルの遺伝子発現情報の取得の際に求められる技術展望
2 スマートセル設計に資するメタボローム解析
2.1 はじめに
2.2 メタボローム解析の概要
2.3 動的メタボロミクスの開発と微生物育種への応用
2.4 スマートセル設計に資するメタボローム解析
3 高精度定量ターゲットプロテオーム解析技術
3.1 はじめに
3.2 スマートセル評価におけるタンパク質定量技術の必要性
3.3 ターゲットプロテオミクス法の有用性
3.4 ターゲットプロテオミクスの実際1:サンプル前処理とデータ取得
3.5 ターゲットプロテオミクスの実際2:MRMアッセイメソッドの構築
3.6 MRMアッセイメソッド構築の高速化に向けて
3.7 ターゲットプロテオミクスを用いた出芽酵母1遺伝子破壊株の解析
3.8 人工タンパク質を用いた定量の高精度化
第4章 測定データのクオリティコントロール,標準化データベースの構築
1 はじめに
2 本研究課題の役割
3 本データベースの独自性
4 測定データのクオリティコントロール
5 標準化データベースの構築
6 スマートセルデータベースの将来像
7 最後に
【第2編 情報解析技術】
第1章 代謝系を設計する情報解析技術
1 新規代謝経路の設計
1.1 はじめに
1.2 代謝経路設計ツール(1):M-path
1.3 代謝経路設計ツール(2):BioProV
1.4 おわりに
2 代謝モデル構築と代謝経路設計
2.1 はじめに
2.2 代謝モデル構築
2.3 代謝経路設計:HyMeP
2.4 今後の課題
3 微生物資源の有効活用
3.1 スマートセル構築のための生物資源の活用概略
3.2 人工代謝経路設計ツールの機能向上への生物資源の活用
3.3 微生物資源の入手方法
4 代謝設計に向けた酵素選択
4.1 はじめに
4.2 代謝設計ツール:M-pathの利用
4.3 クラスタリング法の利用
4.4 機械学習法の利用
4.5 おわりに
5 酵素の機能改変
第2章 遺伝子発現制御ネットワークモデルの構築
1 はじめに
2 遺伝子発現制御と物質生産理由
3 遺伝子選択手法の開発
4 ネットワーク構造推定
5 実証課題への適用に向けて
第3章 遺伝子配列設計技術
1 情報解析に基づく遺伝子配列改変による発現量調節
1.1 放線菌生産データに基づく,遺伝子配列設計法の開発
1.2 DNA-ヒストン結合能を変化させる配列改変
2 コドン(超)最適化という設計戦略
2.1 はじめに―コドン(超)最適化という設計戦略
2.2 コドンの最適化の基礎
2.3 コドン最適化の実際
2.4 発現量を最大化するためのコドン超最適化
2.5 おわりに―コドン置換による更なる配列設計
3 大量データに基づく遺伝子配列設計
3.1 はじめに
3.2 コドンとタンパク質発現の関係
3.3 翻訳開始との関係
3.4 翻訳伸長との関係
3.5 タンパク質フォールディングとの関係
3.6 翻訳終結との関係
3.7 mRNA分解との関係
3.8 分泌との関係
3.9 Codon Adaptation Index
3.10 我々のアプローチ
3.11 OGAB法によるキメラCDSライブラリの構築
3.12 おわりに
第4章 統合オミクス解析技術
1 はじめに
2 生体細胞における複層的制御システム
3 生物階層と情報解析技術
4 統合モデルの構築
5 実証課題への適用に向けて
第5章 知識整理技術
1 バイオ生産に資するAI基盤技術
1.1 はじめに
1.2 AI技術の現状
1.3 バイオ分野におけるAI技術適用の課題
1.4 スマートセル開発支援知識ベース
1.5 おわりに
2 合成代謝経路を導入したシアノバクテリアによる有用物質生産
2.1 はじめに
2.2 合成代謝経路を導入したシアノバクテリアによるイソプロパノール生産
2.3 合成代謝経路を導入したシアノバクテリアによる1,3-PDOの生産
2.4 おわりに
【第3編 産業応用へのアプローチ】
第1章 診断薬用酵素コレステロールエステラーゼ(CEN)生産への応用
第2章 セルラーゼ生産糸状菌の複数酵素同時生産制御に向けた技術開発
1 バイオリファイナリーとセルロース系バイオマス分解糸状菌Trichoderma reesei
1.1 セルロース系バイオマスを原料としたバイオリファイナリー
1.2 セルロース系バイオマスの分解
1.3 既知の調節因子
2 Trichoderma reesei糖質加水分解酵素生産制御
2.1 糖質加水分解酵素の生産比率制御の意義
2.2 糖質加水分解酵素生産比率制御とDBTLサイクル
第3章 カルボンの生産性向上による代謝解析・酵素設計技術の有効性検証
1 酵素設計技術を用いたP450の改変とリモネンからカルボンへの変換
2 リモネン発酵生産菌の構築
第4章 Streptomyces属放線菌を用いた物質生産技術:N-STePP(R)
1 はじめに
2 N-STePP(R)
3 応用例1:天然紫外線吸収アミノ酸「シノリン」の生産
4 応用例2:多機能アミノ酸「エルゴチオネイン」の生産
5 おわりに
第5章 スマートセルシステムによる有用イソプレノイド生産微生物の構築の取組み
1 はじめに
2 イソプレノイド生合成経路に関わる研究の概要
2.1 メバロン酸経路
2.2 非メバロン酸経路
3 イソプレノイド生産微生物構築におけるスマートセルシステムの活用
3.1 有用イソプレノイド生産微生物の構築
3.2 今後の展望
第6章 網羅的解析を利用した高生産コリネ型細菌の育種戦略
1 トランスクリプトーム解析を用いた乳酸生産濃度向上戦略
2 メタボローム解析を用いたアラニン生産濃度向上戦略
3 メタボローム解析を用いたシキミ酸生産濃度向上戦略
4 計算機およびトランスポゾンライブラリーを用いたタンパク質分泌生産量の向上戦略
第7章 紅麹色素生産の新展開
1 はじめに
2 紅麹菌と産業利用の変遷
3 紅麹菌の分類学的な位置づけと二次代謝経路
4 紅麹色素に関する従来の研究と遺伝子組換え技術
5 紅麹菌GB-01株の全ゲノム塩基配列の取得
6 スマートセル実現にむけた新規数理モデル開発と遺伝子改変
7 さいごに
第8章 植物由来カロテノイドの微生物生産
1 はじめに
2 植物由来カロテノイドの市場性と機能性
3 大腸菌による植物由来カロテノイドの生産研究
3.1 大腸菌で生産可能な植物由来カロテノイド
3.2 大腸菌を用いたカロテノイド生産の生産性向上の試み
4 酵母による植物由来カロテノイドの生産研究
4.1 カロテノイド生産酵母における生産性向上の試み
4.2 カロテノイド非生産酵母での代謝経路の導入によるカロテノイド生産
4.3 出芽酵母を宿主として用いた新たな取り組み
5 おわりに
第9章 油脂酵母による油脂発酵生産性改善へ向けた技術開発
1 油脂産業の現状と油脂酵母
2 油脂蓄積変異株の取得とその油脂蓄積性
3 油脂酵母のTAG合成・分解
4 油脂蓄積変異株のTAG合成・分解経路関連遺伝子の発現挙動
5 油脂酵母L.starkeyiの遺伝子組換え技術
6 今後の開発
第10章 情報解析技術を活用したアルカロイド発酵生産プラットフォームの最適化
第11章 計算化学によるコンポーネントワクチン開発のための分子デザイン
1 はじめに
2 ワクチンの種類と特徴
3 ワクチン抗原における分子デザインについて
4 分子の安定性:耐熱性付与
5 計算化学とライブラリー法を融合したコンポーネントワクチン開発
6 まとめ
第12章 微生物の膜輸送体探索と産業利用―輸送工学の幕開け―
1 微生物の膜輸送体研究の現状
2 膜輸送体の産業利用
3 結言
-

機能性ポリウレタンの進化と展望《普及版》
¥5,610
2018年刊「機能性ポリウレタンの進化と展望」の普及版。「ポリウレタン」の合成、構造、物性の基礎から、自動車、建築、寝具用フォーム、3Dプリンター用樹脂、耐震粘着ゲル、自己修復性塗料などの応用分野まで徹底解説した1冊。
(監修:古川睦久、和田浩志)
<a href="http://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=115765"target=”_blank”>この本の紙版「機能性ポリウレタンの進化と展望(普及版)」の販売ページはこちら(別サイトが開きます)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は、2018年当時のものを使用しております。
古川睦久 ながさきポリウレタン技術研究所;長崎大学
和田浩志 AGC㈱
染川賢一 鹿児島大学
落合文吾 山形大学
遠藤 剛 近畿大学
村上裕人 長崎大学
宇山 浩 大阪大学
三俣 哲 新潟大学
梅原康宏 (公財)鉄道総合技術研究所
城野孝喜 東ソー㈱
鈴木千登志 AGC㈱
岩崎和男 岩崎技術士事務所
瀬底祐介 東ソー㈱
髙橋亮平 東ソー㈱
藤原裕志 東ソー㈱
徳本勝美 東ソー㈱
稲垣裕之 東レ・ダウコーニング㈱
植木健博 大八化学工業㈱
八児真一 第一化成㈱
外山 寿 Cannon S.p.A
佐藤正史 ㈱イノアックコーポレーション
佐渡信一郎 住化コベストロウレタン㈱
桐原 修 松尾産業㈱
六田充輝 ダイセル・エボニック㈱
大川栄二 ウレタンフォーム工業会
小玉誠志 プロセブン㈱
佐々木孝之 AGC㈱
林 伸治 ディーアイシーコベストロポリマー㈱
前田修二 日清紡テキスタイル㈱
勝野晴孝 日清紡テキスタイル㈱
萩原恒夫 横浜国立大学
シーエムシー出版
-------------------------------------------------------------------------
<<目次>>
【ポリウレタンの化学編】
第1章 ポリウレタンの合成
1 はじめに
2 イソシアネートと活性水素化合物の反応
2.1 イソシアネートの合成
2.2 イソシアネートの反応機構
2.3 イソシアネートを用いたポリウレタンの合成法
2.4 合成に用いるポリオール,イソシアネート,鎖延長剤
3 イソシアネートを用いないウレタン合成
3.1 ビスクロロ炭酸エステル並びにビスクロロギ酸エステルを用いる合成
3.2 環状カーボナートを用いる方法
4 おわりに
第2章 イソシアネートのウレタン化反応機構
1 はじめに
2 イソシアネートX-N=C=OとアルコールR-OHの構造と性質,その作用について
2.1 MOPAC2016 PM7等での評価
2.2 フェニルイソシアネートとアルコールとのウレタン化反応へのフェニル置換基の効果
3 イソシアネートX-N=C=OとアルコールR-OHとのウレタン化反応の反応機構
3.1 イソシネートとアルコールとの反応の速度論的解析と理論計算による多分子機構の検証
3.2 イソシアネートX-NCOとアルコールR-OH等とのウレタン化反応のPM6シミュレーション
4 イソシアネートのウレタン化反応への触媒の作用機構について
4.1 イソシアネートのウレタン化反応への第3級アミンの触媒作用
4.2 イソシアネートのウレタン化反応への有機強酸等による触媒作用
5 生成物のカルバミン酸の不安定・脱炭酸性およびカルバミン酸エステルの安定さについて
5.1 フェニルカルバミン酸の水との反応
5.2 フェニルカルバミン酸メチルと水との挙動
6 まとめ
第3章 ポリウレタンの物性への化学構造と凝集構造の影響
1 はじめに
2 ポリウレタンの構成要素鎖
3 化学構造因子の物性への影響
3.1 ポリウレタンの製造法の影響
3.2 ポリマーグリコールの分子量分布の影響
3.3 ハードセグメントの分子量分布
3.4 鎖延長剤の混合比の影響
4 硬化温度の影響
5 ポリウレタンの物性と凝集構造の可視化
5.1 ミクロ凝集構造とゴム弾性
5.2 ポリウレタンのミクロ凝集構造の可視化
6 将来展望
第4章 新しいポリウレタン
1 ポリヒドロキシウレタンの合成と応用
1.1 背景
1.2 環状カーボナートの合成
1.3 ポリヒドロキシウレタンの合成と反応
1.4 ポリヒドロキシウレタンの応用
1.5 まとめ
2 トポロジカルな構造をもつポリウレタン
2.1 はじめに
2.2 ロタキサン構造をもつポリウレタン
2.3 主鎖に環状化合物を導入したネットワークポリウレタン
2.4 ポリロタキサンで架橋したポリウレタン
2.5 まとめ
3 環境対応ポリウレタン バイオベースポリオールを基材とするPU
3.1 はじめに
3.2 植物油脂を用いる高分子材料
3.3 植物油脂を用いるバイオポリウレタン
3.4 分岐状ポリ乳酸ポリオール
3.5 ダイマー酸をベースとするポリウレタン
3.6 おわりに
4 磁場応答性ソフトマテリアル
4.1 はじめに
4.2 磁性エラストマーの可変粘弾性
4.3 磁性エラストマーの応用
4.4 おわりに
【素材と加工編】
第5章 イソシアネート
1 はじめに
2 イソシアネートモノマー
2.1 イソシアネートの合成方法
2.2 代表的なイソシアネートモノマーの種類と反応性
2.3 特殊イソシアネート化合物を含む各種イソシアネートモノマー
2.4 変性ポリイソシアネート
第6章 ポリオール
1 はじめに
2 ポリエーテルポリオール
2.1 PPG
2.2 変性PPG
2.3 ポリオキシテトラメチレングリコール
3 ポリエステルポリオール
3.1 重縮合系ポリエステルポリオール
3.2 ポリカプロラクトンポリオール
4 ポリカーボネートジオール
5 ポリオレフィン系ポリオール
5.1 ポリブタジエンポリオール
6 各種ポリオールの性状とそのポリウレタンの特徴
7 非化石炭素資源由来ポリオール
7.1 植物油系ポリオール
8 おわりに
第7章 第三成分(鎖延長剤・硬化剤・架橋剤)
1 第三成分の概要
1.1 第三成分とは
1.2 第三成分の内容(中身)
1.3 第三成分の種類
1.4 第三成分の重要性
1.5 第三成分の使用状況
2 ジオール系第三成分
2.1 ジオール系第三成分の種類
2.2 ジオール系第三成分の製造方法
2.3 ジオール系第三成分の特徴
2.4 ジオール系第三成分の用途分野
3 ジアミン系第三成分
3.1 ジアミン系第三成分の種類
3.2 ジアミン系第三成分の製法
3.3 ジアミン系第三成分の特徴
3.4 ジアミン系第三成分の用途分野
4 その他の第三成分など
4.1 多価アルコール系の第三成分
4.2 その他の第三成分
5 総括(まとめ)
第8章 触媒
1 はじめに
2 ポリウレタンフォーム用触媒の活性機構
2.1 無触媒系における反応機構
2.2 触媒存在下における反応機構
3 ポリウレタンフォーム用触媒の種類
3.1 樹脂化反応活性と泡化反応活性
3.2 温度依存性
3.3 架橋反応活性
4 開発動向
4.1 軟質フォーム用反応遅延型触媒(TOYOCAT-CX20)
4.2 軟質フォーム用エミッション低減触媒(RZETA)
4.3 硬質フォーム用HFO発泡剤対応触媒(TOYOCAT-SX60)
5 おわりに
第9章 界面活性剤
1 はじめに
2 ポリウレタン発泡系におけるシリコーン整泡剤の位置づけ
3 シリコーン整泡剤の構造
4 シリコーン整泡剤の機能と役割
4.1 原料の均一混合・分散(乳化作用)
4.2 気泡核の生成(巻き込みガスの分散)
4.3 気泡の安定化(合一の防止)
4.4 セルの安定化(膜の安定化)
4.5 まとめ
5 シリコーン整泡剤の選択
5.1 軟質スラブおよびホットモールドフォーム用整泡剤
5.2 高弾性モールドフォーム
5.3 硬質フォーム
5.4 その他のフォーム
5.5 整泡剤の選択基準
6 今後の動向
第10章 難燃剤と難燃化技術
1 はじめに
2 ウレタンフォームの燃焼と難燃化機構
2.1 吸熱反応による難燃化
2.2 炭化促進による難燃化
2.3 希釈効果
2.4 ラジカルトラップによる難燃化
3 難燃剤の種類と特徴
3.1 ハロゲン系難燃剤
3.2 リン系難燃剤
3.3 水酸化金属系難燃剤
4 ウレタンフォームの難燃規格と評価方法
4.1 自動車
4.2 家具
4.3 電子材料
4.4 建材
4.5 その他
5 難燃剤の選択
6 おわりに
第11章 添加剤
1 はじめに
2 高分子の劣化
3 高分子の安定化
4 ポリウレタン用添加剤
4.1 スパンデックスの特許例
4.2 スパンデックス用添加剤の特徴
5 高分子の変色問題
5.1 変色原因
5.2 変色メカニズム
5.3 何故片ヒンダードフェノール系AOが変色しにくいか?
6 ポリウレタンに用いられている添加剤の例
7 まとめ
第12章 成形加工プロセス~ポリウレタン コンポジット成形について~
1 はじめに
2 RRIM(Reinforced Reaction Injection Molding)
3 成形装置
3.1 フィラープレミックス装置
3.2 エアローデイング
3.3 RRIM注入機
3.4 金型
3.5 成形プレス
4 ポリウレタンRTM(Resin transfer Molding)
5 ウレタンRTM成形装置
5.1 ガラス繊維プレカットおよびプリフォーム
5.2 高圧RTM注入機
5.3 成形金型
5.4 成形プレス
【ポリウレタンの応用製品編】
第13章 ポリウレタンフォームの最新技術動向
1 はじめに
2 軟質スラブウレタンフォーム
2.1 自動車用途
2.2 衣類用途
2.3 寝具,家具用途
2.4 フィルター用途
3 軟質モールドウレタンフォーム
4 硬質ウレタンフォーム・硬質イソシアヌレートフォーム
5 気体混入法
6 まとめ
第14章 自動車用内装材料
1 はじめに
2 ポリウレタンの特徴
3 シート・ヘッドレスト
4 インストルメントパネル
5 内装天井
6 ステアリングホイール
7 ロードフロア
8 衝撃吸収材
9 ドアトリムパネル
10 おわりに
第15章 ポリウレタンを使った環境対応型塗料・自己修復塗料に至る道
~機能性付与の観点から~
1 はじめに
2 PUR塗料の歴史とその機能性付与
3 環境対応型塗料とPUR系塗料
4 機能性塗料とPUR材料・塗料
5 自己治癒・自己修復
6 PUR塗料と自己修復性
6.1 自動車用塗料・上塗り塗料
6.2 プラスチック用塗料・ソフトフィール塗料
7 PUR系自己修復塗料の採用事例
8 今後の技術課題とその開発の方向性
8.1 水性UVポリウレタンアクリレート
8.2 水性ブロックイソシアネート(水性BL)
8.3 ハイブリッド化
9 おわりに
第16章 異種材料とポリウレタンの接着
1 はじめに
2 TPUとPEBAのインサート成形による接着・複合化の従来技術とその問題点
2.1 TPUをインサートしPEBAをオーバーモールドする際の問題点
2.2 PEBAをインサートしTPUをオーバーモールドする際の問題点
3 界面反応を利用したTPUとPEBAの直接接着(ダイアミド? K2シリーズ)
3.1 Type III型PEBAにおける,TPUをインサートしPEBAをオーバーモールドするプロセス
3.2 Type III型PEBAにおける,PEBAをインサートしTPUをオーバーモールドするプロセス
4 界面反応によるTPU-PEBA複合化による効果
4.1 PEBAインサートによる金型および工程の簡略化
4.2 TPUと金属の接合における接着層としての硬質ナイロン
4.3 MuellによるTPUの発泡とType III型PEBAシートの複合化
5 まとめ
第17章 断熱材(硬質ウレタンフォーム)
1 はじめに
2 硬質ウレタンフォーム断熱材とは
2.1 硬質ウレタンフォームの特長
2.2 硬質ウレタンフォーム製品の種類
3 硬質ウレタンフォームの用途
4 製品仕様と断熱性能
5 発泡剤の変遷
6 吹付け硬質ウレタンフォームの行政・業界動向
6.1 フロン排出抑制法
6.2 JIS A 9526の改正
6.3 優良断熱材認証制度
7 準建材トップランナー制度(案)について
8 省エネ基準適合義務化について
9 まとめ
第18章 耐震粘着マット
1 はじめに
2 ポリウレタン粘着ゲルの設計
3 ポリウレタン耐震粘着マットの特性
4 基材の異なる耐震ゲルの比較
5 耐震粘着ゲルの性能向上化
6 おわりに
第19章 体圧分散フォーム
1 はじめに
2 体圧分散フォーム
3 マットレスとしてのウレタンフォームの特性
3.1 体圧分散性能
3.2 圧縮時の通気性
3.3 温度依存性
3.4 寝返りのしやすさ
3.5 底づきの定量化
4 人体から見た性能評価
4.1 体圧分散性
4.2 体圧分散性の測定(1)
4.3 体圧分散性の測定(2)
4.4 寝返りのしやすさ
4.5 官能評価
5 まとめ
第20章 熱可塑性ポリウレタンエラストマー
1 はじめに
2 TPUの基本特性
2.1 製法と構造
2.2 TPUの原料と特性
2.3 ウレタン基濃度
3 成形方法とTPUの用途
4 TPUの高機能化
4.1 低硬度TPU
4.2 高耐熱性TPU
4.3 高透湿性TPU
4.4 耐光変色性TPU
4.5 ノンハロゲン難燃性TPU
4.6 非石油由来TPU
5 今後の展開
第21章 ポリウレタン系弾性繊維
1 はじめに
2 基礎技術
2.1 材料
2.2 製造方法
2.3 物性
2.4 用途
3 最近の技術動向
4 各社のスパンデックス
4.1 ライクラ?
4.2 ロイカ?
4.3 モビロン?
5 今後の展開
第22章 ポリウレタンと3Dプリンティング
1 はじめに
2 3Dプリンティング
3 熱可塑性ポリウレタン樹脂と熱硬化性ポリウレタン樹脂の3Dプリンティングへの利用
3.1 熱可塑性ポリウレタン(TPU)の粉末床溶融結合法(PBF)による3Dプリンティング
3.2 熱硬化性ポリウレタンの3Dプリンティングへの展開
4 TPUを用いた材料押し出し法による3Dプリンティング
5 まとめ
【ポリウレタンの市場編】
第23章 日本市場
1 概要
2 原料
2.1 ポリイソシアネート
2.2 ポリオール
3 ポリウレタン樹脂の製法および用途
4 ポリウレタンの需給
第24章 海外市場
1 概要
1.1 ウレタンフォーム
1.2 非ウレタンフォーム
1.3 中国市場
-

触媒劣化《普及版》
¥4,950
2018年刊「触媒劣化」の普及版。「触媒」の各合成プロセス、用途における劣化解析・対策・長寿命化および、特許・文献情報から劣化対策事例を掲載した1冊。
(監修:室井髙城、増田隆夫)
<a href="http://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=115766"target=”_blank”>この本の紙版「触媒劣化 ―原因、対策と長寿命触媒開発―(普及版)」の販売ページはこちら(別サイトが開きます)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は、2018年当時のものを使用しております。
室井髙城 アイシーラボ
中村吉昭 日揮ユニバーサル㈱
冨重圭一 東北大学
関根 泰 早稲田大学
堀 正雄 ユミコア日本触媒㈱
久保田岳志 島根大学
関 浩幸 JXTGエネルギー㈱
荒川誠治 日揮触媒化成㈱
長井康貴 ㈱豊田中央研究所
中坂佑太 北海道大学
増田隆夫 北海道大学
岡部晃博 三井化学㈱
藤川貴志 アルベマール日本㈱
畠山 望 東北大学
三浦隆治 東北大学
鈴木 愛 東北大学
宮本 明 東北大学
角 茂 千代田化工建設㈱
里川重夫 成蹊大学
霜田直宏 成蹊大学
菊地隆司 東京大学
江口浩一 京都大学
坂 祐司 コスモ石油㈱
渡部光徳 日揮触媒化成㈱
佐野庸治 広島大学
鈴木 賢 旭化成㈱
常木英昭 ㈱日本触媒
山本祥史 宇部興産㈱
井伊宏文 宇部興産㈱
佐藤智司 千葉大学
赤間 弘 日産自動車㈱
薩摩 篤 名古屋大学
松田臣平 ㈲マツダリサーチコーポレーション
戸根直樹 日揮ユニバーサル㈱
梨子田敏也 日揮ユニバーサル㈱
難波哲哉 (国研)産業技術総合研究所
永長久寛 九州大学
濱田秀昭 (国研)産業技術総合研究所
志知 明 ㈱豊田中央研究所
井上朋也 (国研)産業技術総合研究所
多湖輝興 東京工業大学
中嶋直仁 クラリアント触媒㈱
松下康一 JXTGエネルギー㈱
今川健一 千代田化工建設㈱
清水研一 北海道大学
今 喜裕 (国研)産業技術総合研究所
中村陽一 (国研)産業技術総合研究所
川原 潤 三井化学㈱
二宮 航 三菱ケミカル㈱
木村 学 広栄化学工業㈱
米本哲郎 住友化学㈱
-------------------------------------------------------------------------
<<目次>>
【第1編 基礎】
第1章 工業プロセスにおける触媒劣化と対策
1 触媒劣化
1.1 はじめに
1.2 劣化現象
1.3 触媒毒と選択性付与剤
1.4 工業触媒の寿命
1.5 触媒劣化
1.6 触媒毒
1.7 シンターリング
1.8 触媒自体の変化
1.9 磨耗,粉化
1.10 劣化対策
1.11 おわりに
2 前処理
2.1 はじめに
2.2 微量S除去
2.3 一酸化炭素の除去
2.4 酸素除去
2.5 ハロゲンの除去
2.6 アセチレン,オレフィンの選択水素化除去
2.7 脱メタル触媒
2.8 ダミー触媒
2.9 使用済み触媒による前処理
2.10 おわりに
3 触媒調製法による劣化対策
3.1 はじめに
3.2 耐硫黄触媒
3.3 耐熱触媒(シンターリング防止触媒)
3.4 溶出防止触媒
3.5 カーボン析出防止触媒
3.6 担体の強度向上
3.7 脱硫触媒における重金属対策
3.8 ゼオライト触媒
4 反応器の最適設計による劣化対策
4.1 はじめに
4.2 反応器
4.3 反応流
4.4 発熱反応
4.5 カードベット反応器
4.6 連続再生装置
4.7 おわりに
5 反応装置の運転法による劣化対策-接触改質プロセスの進化を例に
5.1 初めに
5.2 接触改質プロセスの役割
5.3 接触改質プロセス発展の経緯
5.4 触媒の機能(反応メカニズム)
5.5 接触改質プロセスの進化
5.6 既設接触改質装置における運転可能期間と再生能力の改善
6 再生処理法
6.1 はじめに
6.2 洗浄再生
6.3 湿式還元再生
6.4 水素ストリッピング
6.5 カーボンバーン(デコーキング)
6.6 連続再生
6.7 金属の再分散
6.8 おわりに
第2章 触媒劣化現象
1 水蒸気改質におけるNi系触媒の活性劣化
2 シフト反応における貴金属系触媒のシンタリング
2.1 シフト反応における貴金属触媒の位置づけ
2.2 金を担持した触媒の劣化挙動
2.3 白金を担持した触媒の劣化挙動
2.4 考えられる劣化抑制対策
3 自動車排ガス浄化触媒の劣化と対策
3.1 自動車排ガス浄化触媒の概要
3.2 自動車触媒の劣化モード
3.3 各種劣化の実態と対策
4 水素化脱硫触媒とその劣化
4.1 緒言
4.2 Co-Mo系脱硫触媒とその活性構造
4.3 脱硫触媒の活性構造形成過程と高活性化
4.4 水素化精製触媒の劣化とその要因
4.5 おわりに
5 FCC触媒のコーク生成,金属堆積による劣化と対策
5.1 はじめに
5.2 FCC触媒の劣化要因
5.3 FCC触媒の劣化対策
5.4 まとめ
第3章 劣化触媒の解析
1 固体触媒のキャラクタリゼーション
1.1 はじめに
1.2 物性測定装置
1.3 粒度分布
1.4 機械的強度
1.5 表面積と細孔分布
1.6 金属表面積の測定
1.7 蛍光X線分析(XRF)
1.8 Electron Probe Microanalyzer(EPMA)
1.9 TG(示差熱天秤)
1.10 アンモニアTPD(昇温脱離,Temperature-Programmed Desorption)
1.11 AES(オージェ電子分光分析,Auger Electron Spectroscopy)
1.12 XPS(X-ray Photoelectron Spectroscopy)
1.13 X線解析(XRD:X-Ray Diffraction)
1.14 電子顕微鏡
1.15 Cl,S,Pの化学分析
1.16 おわりに
2 自動車排気浄化用触媒における貴金属粒子と担体との相互作用,粒成長現象の解析
2.1 はじめに
2.2 セリア担体上でのPt粒成長抑制機構
2.3 Pt-各種担体との相互作用とPt粒成長
2.4 セリア担体上でのPt粒子の還元挙動
2.5 おわりに
3 炭素析出によるゼオライト触媒の劣化と再生
3.1 はじめに
3.2 炭化水素の拡散係数
3.3 ZSM-5に析出したコークの燃焼速度解析
3.4 おわりに
4 ゼオライト成形体触媒のコーク析出による劣化と対策
4.1 はじめに
5 軽油超深度脱硫触媒の劣化と寿命推定
5.1 はじめに
5.2 軽油脱硫触媒の劣化メカニズム
5.3 触媒上の堆積コークの特徴
5.4 触媒の長寿命化
5.5 触媒寿命推定
5.6 おわりに
6 シンタリングによる触媒劣化のシミュレーション
7 迅速寿命試験
7.1 はじめに
7.2 触媒の劣化現象の理解
7.3 実際の反応試験
7.4 触媒試験
7.5 触媒寿命の推定法
7.6 おわりに
第4章 触媒の長寿命化
1 合成ガス製造プロセスにおける触媒劣化要因と対策について
1.1 合成ガス製造プロセス
1.2 CO2リフォーミング(CT-CO2AR?)技術
1.3 接触部分酸化(D-CPOX)技術
1.4 まとめ
2 水蒸気改質触媒の耐久性
2.1 水蒸気改質触媒の劣化機構
2.2 大型装置用触媒の劣化と対策
2.3 小型改質器用触媒の劣化と対策
2.4 貴金属触媒の劣化と対策
3 スピネル複合触媒によるジメチルエーテル水蒸気改質反応
3.1 ジメチルエーテル水蒸気改質反応と触媒
3.2 アルミナ複合Cu系スピネル触媒
3.3 触媒劣化と再生
3.4 触媒寿命の予測
3.5 触媒耐久性の向上
3.6 まとめ
4 流動接触分解装置における劣化要因およびその対応策
4.1 FCC装置の概要
4.2 FCC触媒の概要
4.3 FCC触媒の劣化要因
4.4 当社での取り組み
4.5 総括
5 直脱/RFCCのインテグレーション
5.1 諸言
5.2 直脱およびRFCCの概要
5.3 触媒劣化に対する原料油性状因子
5.4 直脱触媒の劣化対策
5.5 RFCC触媒の劣化対策
5.6 直脱-RFCCのインテグレーション
5.7 結言
6 高圧・超臨界流体反応場による炭素析出抑制
6.1 はじめに
6.2 重質油の軽質化反応
6.3 2-メチルナフタレンのメチル化反応
6.4 おわりに
7 高水熱安定性ゼオライト触媒の開発
7.1 はじめに
7.2 脱アルミニウム挙動
7.3 アルカリ土類金属修飾MFIゼオライト触媒の開発
7.4 ゼオライト水熱転換によるリン修飾CHAゼオライト触媒の開発
7.5 おわりに
8 メタクリル酸メチル製造用金-酸化ニッケルコアシェル型ナノ粒子触媒の開発
8.1 はじめに
8.2 金-酸化ニッケルナノ粒子触媒の開発
8.3 長期触媒寿命を保証する工業触媒の開発
8.4 本技術の実用化
8.5 おわりに
9 エチレンイミン製造用触媒の開発と長寿命化
9.1 緒言
9.2 触媒・反応プロセスの概要
9.3 触媒劣化と対策
10 亜硝酸メチルを用いた気相カルボニル化触媒の開発
10.1 緒言
10.2 MNによる気相カルボニル化
10.3 気相カルボニル化触媒の開発
10.4 まとめ
11 固体酸触媒プロセスにおける触媒活性劣化の抑制
12 自動車触媒の耐熱性向上による触媒の長寿命化
12.1 はじめに
12.2 高温暴露による触媒劣化;シンタリング現象
12.3 担持貴金属触媒の耐熱性向上技術
13 自動車排ガス浄化用Ag触媒の高活性化とシンタリング抑制
13.1 はじめに
13.2 NO還元活性の還元剤依存性と水素添加効果
13.3 NO還元活性の反応雰囲気および担体依存性
13.4 Ag種のシンタリング抑制の例-Ag/Al2O3
13.5 Ag種のシンタリング抑制の例-Ag/CeO2
13.6 Ag種のシンタリング抑制の例-Ag/SnO2
14 アンモニア脱硝触媒の開発と長寿命化
14.1 はじめに
14.2 窒素酸化物(NOX)除去プロセス
14.3 SCR用の脱硝触媒の開発
14.4 酸性硫安の析出による酸化チタン系触媒の活性低下
14.5 まとめ
15 環境浄化触媒の劣化要因と対策
15.1 はじめに
15.2 触媒燃焼法の特長
15.3 環境浄化触媒の種類
15.4 劣化要因と対策
15.5 おわりに
【第2編 劣化対策事例】
第5章 環境触媒
第6章 石油・エネルギー
第7章 石油化学・合成化学
-

再生医療・創薬のための3次元細胞培養技術《普及版》
¥3,410
2018年刊「再生医療・創薬のための3次元細胞培養技術」の普及版。立体的組織・臓器を調製するための3次元細胞培養技術から、周辺材料、装置・システム構築、その応用展開までを網羅した1冊。
(監修:紀ノ岡正博)
<a href="http://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=115749"target=”_blank”>この本の紙版「再生医療・創薬のための3次元細胞培養技術(普及版)」の販売ページはこちら(別サイトが開きます)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は、2018年当時のものを使用しております。
紀ノ岡正博 大阪大学
清水達也 東京女子医科大学
菊地鉄太郎 東京女子医科大学
古川克子 東京大学
赤木隆美 大阪大学
明石 満 大阪大学
角昭一郎 京都大学
根岸みどり 武蔵野大学
森本雄矢 東京大学
竹内昌治 東京大学
佐藤記一 群馬大学
酒井康行 東京大学
厖媛 清華大学
ステファニー・ウタミ・ストコ (株)日立製作所
新野俊樹 東京大学
今泉幸文 クアーズテック(株)
金木達朗 日産化学工業(株)
堀川雅人 日産化学工業株
櫻井敏彦 鳥取大学
山本雅哉 東北大学
植村壽公 大阪大学;(株)ジェイテックコーポレーション
秋枝静香 (株)サイフューズ
谷口英樹 横浜市立大学
阿久津英憲 (国研)国立成育医療研究センター研究所
川崎友之 (国研)国立成育医療研究センター研究所
土屋勝則 大日本印刷(株)
吉村知紗 横浜国立大学
景山達斗 (地独)神奈川県立産業技術総合研究所(KISTEC);横浜国立大学
福田淳二 横浜国立大学;(地独)神奈川県立産業技術総合研究所(KISTEC)
塩田 良 (株)パーキンエルマージャパン
松崎典弥 大阪大学
高木大輔 (株)リコー
瀬尾 学 (株)リコー
宮川 繁 大阪大学
澤 芳樹 大阪大学
中野洋文 東京工業大学
-------------------------------------------------------------------------
<<目次>>
【第I編 3次元細胞培養技術】
第1章 総論:立体的な組織をつくることとその活用
1 はじめに
2 立体培養の要とその支援技術
3 創薬スクリーニングへの展開技術
4 おわりに
第2章 細胞シート工学を基盤とした立体臓器製造技術
1 はじめに
2 細胞シート
3 温度応答性培養皿
4 細胞シートの積層化
5 細胞シートマニピュレーションデバイスと自動積層化装置
6 積層化細胞シートの成熟化
7 より複雑な3次元組織の作製
8 積層限界と血管網の導入
9 おわりに
第3章 スキャフォールドフリーモデルの3次元構築法
1 はじめに
2 再生軟骨のニーズ
3 再生軟骨の解決すべき課題
4 スキャフォールドフリーモデルの構築
5 おわりに
第4章 スフェロイド培養における3次元細胞積層化
1 はじめに
2 三次元細胞積層化技術
3 細胞スフェロイド化技術
4 肝スフェロイドモデル
5 膵スフェロイドモデル
6 おわりに
第5章 膵島など細胞集塊の作製技術
1 はじめに
2 細胞集塊の必要性について
3 細胞集塊の一般的な問題点
4 細胞集塊の作製法
5 新しい細胞集塊作製用器材
6 おわりに
第6章 細胞ファイバ技術を応用した3次元組織構築
1 はじめに
2 細胞ファイバの構築法と機能評価
2.1 コアシェル型細胞ファイバの作製法
2.2 コアシェル型細胞ファイバの機能評価
2.3 マイクロスタンプを用いた細胞ファイバの構築
3 細胞ファイバの移植組織としての利用と創薬モデルへの応用
3.1 移植組織としての神経ファイバ
3.2 移植組織としてのラット膵島細胞ファイバ
3.3 創薬モデルへの応用
4 おわりに
第7章 マイクロ流体デバイスを用いた細胞培養とマイクロ臓器モデル
1 はじめに
1.1 マイクロ流体デバイス
1.2 細胞実験のためのマイクロ流体デバイス
2 マイクロ流体デバイスを用いた細胞培養
3 薬物動態の解析のためのマイクロ臓器モデルの開発
4 消化,吸収,代謝を考慮に入れたバイオアッセイチップ
4.1 胃・十二指腸モデル
4.2 腸管吸収モデル
4.3 肝臓モデル
4.4 消化吸収代謝の複合モデル
5 腎排泄マイクロモデル
6 おわりに
第8章 階層的流路ネットワークを配備した組織再構築用担体
1 はじめに
2 トップダウンとボトムアップの両アプローチの融合―マクロ流路ネットワークと組織モジュール充填法の利用―
2.1 対象スケールに応じたコンセプトの融合
2.2 担体デザインと製作
3 新担体を用いた細胞凝集体の充填灌流培養
4 新たな組織モジュール充填法用のマイクロ担体の作成―物質交換性と力学特性の両立―
5 おわりに
【第II編 周辺材料】
第1章 3次元細胞培養担体 CERAHIVE(R)
1 はじめに
2 生体内近似環境について
3 均一で大量の細胞塊形成について
4 細胞塊の回収方法について
5 CERAHIVE(R)の種類
6 最後に
第2章 接着細胞用浮遊培養基材・FCeM(R)Cellhesion(R)を用いた新しい3次元培養
1 3次元培養について
2 FCeM(R)シリーズの開発
3 FCeM(R) Cellhesionと足場依存性
4 FCeM(R) Cellhesionを用いた簡便な3D培養法
5 FCeM(R) Cellhesionを用いたヒト由来細胞の培養
6 おわりに
第3章 プロテオグリカン-アテロコラーゲン複合化による3次元培養基材の作製と細胞機能評価
1 はじめに
2 細胞外マトリックスの抽出
3 PG-AC複合化による3次元培養基材の作製
4 PG-AC複合化3次元培養基材を用いた細胞機能評価
4.1 高密度化した水和ゲルの細胞機能評価
4.2 高密度化したキセロゲルの細胞機能評価
5 まとめ
第4章 高機能ゲルを用いた3次元足場材料
1 はじめに
2 再生医療・創薬のための3次元足場材料
3 ハイドロゲルとは
4 ハイドロゲルの機能化
4.1 ハイドロゲルの加工
4.2 球状のハイドロゲル
4.3 リソグラフィーを用いた微細加工
4.4 3Dプリンターを利用した加工
4.5 力学的性質の制御
5 生理活性物質を用いたハイドロゲルの機能化
5.1 タンパク質との相互作用と細胞接着性
5.2 生理活性物質の配向固定化
5.3 生理活性物質の徐放化
6 高機能ゲルを用いた3次元足場材料
6.1 細胞集合体形成のためのハイドロゲル微粒子
6.2 創薬研究のプラットフォームとしてのOrgans-on-a Chip
6.3 擬似3次元培養としてのサンドイッチ培養
6.4 オルガノイド
7 おわりに
【第III編 装置・システム構築】
第1章 再生医療・創薬を目指した自動3次元培養装置を用いたシステム化
1 はじめに
2 再生医療に向けた開発
2.1 CELL FLOAT(R)
2.2 回転制御システム
2.3 培養液交換機構
2.4 臨床用大型軟骨組織を構築するための再生医療向け3次元細胞培養システムの開発
3 創薬に向けた開発
3.1 CELL FLOAT(R)による多数組織の構築技術
3.2 手培養によるスクリーニングプロセス
3.3 ピックアッププロセス
3.4 粉砕プロセス
3.5 自動スクリーニング装置と手培養との比較
4 結語
第2章 バイオ3Dプリンタ「レジェノバ」を用いた三次元組織構築
1 はじめに
2 三次元組織の構築
3 バイオ3Dプリンタ
4 「KENZAN方式」バイオ3Dプリンタ
5 バイオ3Dプリンタを用いた臨床開発事例
5.1 細胞製人工血管の開発
5.2 細胞製神経導管(Bio 3D Conduit)の開発
6 今後の展開
7 おわりに
【第IV編 応用展開】
第1章 iPS細胞を用いたヒト肝臓オルガノイドの創出技術
1 はじめに
2 器官発生プロセスの再現によるヒト立体臓器の創出
3 ヒト臓器創出技術の創薬プロセスへの応用
4 おわりに
第2章 ES/iPS細胞を用いたミニ小腸の作製
1 はじめに
2 ミニ小腸作製の細胞ソース:多能性幹細胞特性について
3 幹細胞から多細胞組織構造体を作製する
4 小腸の組織構造と機能
5 腸管オルガノイドの創生と特性
6 ミニ小腸の創生
7 高機能化オルガノイドのデバイス装置融合の可能性
8 おわりに
第3章 毛髪再生医療のための毛包原基の大量調製技術
1 はじめに
2 脱毛症治療のための毛髪再生医療
3 細胞選別現象を用いた自発的な毛包原基の形成
4 毛包原基の大量調製のための毛髪再生チップ
5 成体細胞を用いた毛髪再生
6 今後の展望
第4章 3次元培養細胞イメージングによる毒性試験の展望
1 はじめに
2 3次元培養細胞モデルの有用性
3 3次元培養細胞におけるイメージングの役割とその手法
3.1 共焦点方式
3.2 2光子方式
3.3 光シート方式
3.4 光干渉断層撮影(Optical Coherence Tomography:OCT)
4 3次元画像解析ソフトウェア
5 3次元スタック画像を使った解析の実際
5.1 2次元での解析
5.2 2.5次元の解析
5.3 3次元の解析
6 まとめ
第5章 三次元生体組織モデルの構築および薬剤効果測定・毒性評価への応用
1 三次元生体組織モデルの重要性
2 組織構築の2つのアプローチ
2.1 細胞積層法
2.2 細胞集積法
3 心筋細胞へ適用可能な細胞コート法(濾過LbL法)の開発
4 同期拍動する三次元ヒトiPSC-CM組織体の構築
5 毛細血管様ネットワークを有する三次元ヒトiPSC-CM組織体の構築と毒性評価への応用
6 おわりに
第6章 難治性癌・癌幹細胞の3次元スフェアー培養による薬剤探索
1 はじめに
2 ヒト癌遺伝子と癌細胞の足場非依存性増殖
3 癌幹細胞(Cancer Stem Cell)のスフェロイド培養
4 癌幹細胞の3次元培養法
5 癌幹細胞のスフェロイド増殖:高速解析法
6 「PrimeSurface」96Uで増殖するスフェロイドの形態
6.1 ヒト大腸癌細胞株HCT116
6.2 ヒト膵臓癌細胞MiaPaCa2
6.3 マウス由来の癌化細胞
7 NRSF:mSin3相互作用を標的にした化合物ライブラリー
8 髄芽腫DAOYのスフェアー増殖を抑制する化合物の探索
9 まとめ
-

生物の優れた機能から着想を得た新しいものづくり―バイオミメティクスからの発展―《普及版》
¥4,510
2018年刊「生物の優れた機能から着想を得た新しいものづくり」の普及版。進化の過程で生物が手に入れた優れた性質をものづくりへ応用する研究開発を、機械工学における分野に基づいて構成した1冊。
(監修:萩原良道)
<a href="http://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=115750"target=”_blank”>この本の紙版「生物の優れた機能から着想を得た新しいものづくり―バイオミメティクスからの発展―(普及版)」の販売ページはこちら(別サイトが開きます)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は、2018年当時のものを使用しております。
萩原良道 京都工芸繊維大学
浦田千尋 (国研)産業技術総合研究所
Peter W. Wilson University of Tasmania;
University of South Florida
藤本信貴 住友精化(株)
桑原純平 筑波大学
神原貴樹 筑波大学
小方 聡 首都大学東京
大保忠司 (株)荏原製作所
能見基彦 (株)荏原製作所
山中拓己 (株)コベルコ科研
福井智宏 京都工芸繊維大学
森西晃嗣 京都工芸繊維大学
伊藤慎一郎 工学院大学
米澤 翔 京都工芸繊維大学
新谷充弘 山本光学(株)
山盛直樹 日本ペイントマリン(株)
松田雅之 日本ペイントマリン(株)
稲田孝明 (国研)産業技術総合研究所
小塩和弥 京都工芸繊維大学
田和貴純 第一工業製薬(株)
石川将次 京都工芸繊維大学
長谷川洋介 東京大学
中山雅敬 Max Planck Institute for Heart and Lung Research
麓 耕二 青山学院大学
松本光央 京都工芸繊維大学
射場大輔 京都工芸繊維大学
本宮潤一 鳥取大学
柄谷 肇 京都工芸繊維大学
安藤規泰 東京大学
木之下博 兵庫県立大学
山下かおり 大日本印刷(株)
中村太郎 中央大学
山田泰之 中央大学
東 善之 京都工芸繊維大学
釜道紀浩 東京電機大学
高木賢太郎 名古屋大学
-------------------------------------------------------------------------
<<目次>>
序論
1 バイオミメティクス
2 Bio-inspired engineering
3 生物のかくれた機能・反応
4 シンポジウム
5 着想を得た生物
【第1編 材料】
第1章 生物の“分泌”から着想を得た環境適用可能な難付着性材料
1 はじめに
2 難付着性の評価方法
3 最近の撥液処理
3.1 潤滑された難付着表面(SLIPS)
3.2 SLIPSの課題
4 生物体表の粘液分泌から着想を得た難付着表面
4.1 葉脈状空洞の利用
4.2 ヤドクガエルの分泌腺からの着想
4.3 ナメクジ体表の粘液分泌からの着想
4.4 ミミズ体表の模倣
5 まとめ
第2章 Bio-inspired Slippery and Ice-repellent coatings-fast Growing Fields in Materials Science
1 ABSTRACT
2 Introduction
3 Background
4 SLIPS
4.1 Nucleation and ALTA
4.2 Adhesion of Ice
5 Ice Binding Proteins
6 Conclusion
第3章 鮮やかな光沢フィルムの開発と展開
1 はじめに
2 金属光沢をもつ有機材料
2.1 π共役系チオフェン-ピロール系有機化合物
2.2 アゾベンゼン基を有する有機化合物
2.3 チオフェン系オリゴマー
3 金属光沢をもつ含色素ポリアニリン類縁体
3.1 含色素ポリアニリン類縁体の合成
3.2 光学特性
3.2.1 色度
3.2.2 光沢度
3.2.3 反射光
3.2.4 金属調光沢の発現機構
3.2.5 電磁波透過性
3.2.6 その他の色素ポリマー
4 おわりに
【第2編 流体】
第1章 寒天ゲルを利用した流れの抵抗低減
1 はじめに
2 装置および方法
2.1 供試寒天ゲル壁
2.2 矩形流路実験装置
2.3 流路高さ測定
2.4 染み込み深さ測定
2.5 抗力測定
3 実験結果および考察
3.1 圧力損失測定結果
3.2 染み込み深さ測定結果
3.3 抗力測定結果
3.4 低減メカニズムの考察
4 おわりに
第2章 小型飛翔機械の開発に向けたトンボの空力制御研究
1 はじめに
2 トンボの空力計算モデル構築
2.1 数値流体力学(CFD)
2.2 空力計算モデルのモデル形状
2.3 空力計算モデルのメッシュ
2.4 使用する計算スキーム
3 飛行条件と評価結果
3.1 飛行条件
3.2 ピッチング運動が空気流動に与える影響
3.3 前後翅位相差が空力に与える影響
4 まとめ
第3章 昆虫規範型ロボットのはばたき位相差が飛翔特性に及ぼす影響
1 初めに
2 供試対象トンボ規範型ロボット(MAV)
3 実験
3.1 自律飛行実験
3.2 風洞試験
3.3 可視化実験
4 実験結果と考察
4.1 飛行実験と流体力試験結果
4.2 可視化実験結果
5 終わりに
第4章 イルカの表皮から着想を得た波状面による乱流摩擦抵抗低減
1 はじめに
2 圧力抵抗
3 摩擦抵抗
3.1 イルカの皮膚
3.2 皮膚の剥がれ
3.3 柔軟壁
3.4 二次元波状面
3.5 有限幅の固体波状面
3.6 硬度の異なる波状面
3.7 微細溝を有する波状面
4 おわりに
第5章 開水路底面に配置された角錐台の波状表面による圧力抗力および摩擦抗力の低減効果の検証
1 はじめに
2 イルカの抵抗低減
2.1 圧力抗力の減少
2.2 摩擦抗力の減少
3 立体物への応用
4 実験方法
4.1 実験装置
4.2 角錐台
5 計測手法
5.1 全抗力計測手法
5.2 速度計測手法
5.3 差圧計測手法
6 結果および考察
6.1 全抗力
6.2 摩擦抗力
6.3 圧力抗力
6.4 循環流の影響
7 おわりに
第6章 海洋生物にヒントを得た超低燃費型船底防汚塗料の開発
1 付着生物との闘い
2 最近の船底防汚塗料
2.1 はじめに
2.2 拡散型防汚塗料
2.3 自己研磨型防汚塗料
2.4 崩壊型防汚塗料
3 高速遊泳能力を持つ海洋生物の知恵に学ぶ
3.1 サメ
3.2 ペンギン
3.3 イルカ
3.4 マグロ
4 低摩擦船底防汚塗料
4.1 社会的背景
4.2 バイオミメティックから塗料へ
4.3 船舶の抵抗成分
4.4 低摩擦船底塗料(LFC)
4.4.1 低摩擦船底塗料の効果の検証
4.4.2 低摩擦船底塗料の摩擦抵抗低減効果
4.5 超低摩擦船底塗料(A-LFC)
4.5.1 超低摩擦船底塗料の効果の検証
4.6 ヒドロゲルによる燃費低減効果の推定メカニズム
5 おわりに
【第3編 熱】
第1章 不凍タンパク質の機能を活用した氷の核生成抑制技術
1 不凍タンパク質(AFP)の機能
2 氷の核生成抑制
3 過冷却器凍結閉塞防止への応用技術
4 おわりに
第2章 冬カレイ由来の不凍タンパク質の代替物質であるポリペプチドを用いた着氷を抑制する機能表面
1 はじめに
2 機能表面の創製
3 着氷防止
4 防氷性に関する測定・評価
5 除氷性に関する測定・評価
6 おわりに
第3章 セルロースナノファイバーの氷結晶成長抑制能について
1 はじめに
2 ナノセルロースについて
2.1 CNFの調製方法
2.2 TEMPO酸化によるCNFの調製
3 実験
3.1 一方向凍結試験による氷成長界面形状,界面温度低下度および成長速度の測定
3.2 試料
4 結果・考察
4.1 各セルロース系試料液における氷成長界面形状の観察
4.2 界面温度低下度の評価
4.3 界面成長速度の評価
5 結論
6 TOCNFの氷結晶成長抑制能の応用
第4章 冬カレイから着想を得た微細流路内氷スラリー流の氷成長・融解の制御
1 研究背景
2 研究目的
3 研究方法
3.1 観察装置
3.2 氷スラリー生成装置
4 氷粒子融解へのHPLC6の影響
4.1 速度計測
4.1.1 計測手法
4.1.2 氷スラリー流の速度計測結果
4.1.3 氷粒子塊の移動速度へのHPLC6の影響
4.2 濃度計測
4.2.1 計測手法
4.2.2 計測結果
5 氷粒子融解へのポリペプチドの影響
5.1 静止水溶液中の氷粒子の観察
5.2 静止水溶液中の氷粒子計測
5.3 水溶液流中の氷粒子計測
6 おわりに
第5章 毛細血管リモデリングと流路ネットワーク最適化
1 生体血管網における分岐パターン
2 工学と流路ネットワーク最適化
3 毛細血管網の形成プロセス
4 最適制御理論に基づく流路ネットワーク最適化
5 まとめ
第6章 生物の組織形状に由来する微小空間用熱交換器に関する基礎的研究
1 はじめに
2 魚の鰓(エラ)形状に由来する狭隘空間用高効率熱交換器に関する基礎的研究
3 赤血球の血管内ずり流動に由来する高効率熱・物質熱輸送システムに関する基礎的研究
3.1 吸水性ポリマーについて
3.2 アルギン酸カルシウムビーズについて
4 まとめと今後の展望
第7章 イルカの表皮のしわとはがれからヒントを得たすべり波状面の乱流摩擦抵抗と熱伝達に関する数値シミュレーション
1 はじめに
2 イルカの皮膚
2.1 皮膚のしわ
2.2 皮膚の剥がれ
3 計算方法
3.1 計算領域
3.2 支配方程式の解法
3.3 計算条件
3.4 境界条件
4 計算結果と考察
4.1 せん断応力
4.2 乱流熱流束と平均ヌセルト数
5 おわりに
【第4編 計測制御】
第1章 生物の歩行に学ぶアクティブ振動制御
1 研究背景
2 アクティブ動吸振器による高層構造物の制振
2.1 構造物用制振装置としてのパッシブ動吸振器
2.2 アクティブ動吸振器とその課題
3 神経振動子を利用するアクティブ動吸振器用の制御系
3.1 神経振動子
3.2 神経振動子と位置制御器を利用したアクティブ動吸振器制御システム
4 神経振動子を組み込んだ制振システムの制御アルゴリズム
4.1 制御系の概要
4.2 制御アルゴリズムの定式化
4.2.1 制御対象
4.2.2 神経振動子
4.2.3 神経振動子に含まれる構造物の応答情報
4.2.4 補助質量の目標変位生成法
4.2.5 補助質量の位置制御器
5 位置制御器のゲイン設計法
5.1 構造物と補助質量の相対運動と消散エネルギの関係
5.2 PDゲイン設計法
6 数値シミュレーション
6.1 提案したシステムの制振効果
6.2 補助質量のストローク制約
7 おわりに
第2章 バイオセンサー構築のための発光細菌発光機能の他細胞系における部分的再構成
1 はじめに
2 生物発光関連化学
3 細菌生物発光機能
4 Y1-Yellowによるミトコンドリアの可視化
5 生物発光による環境毒性のセンシング
6 Cd2+-H2O2共添加による発光応答
第3章 昆虫-機械ハイブリッドロボットが拓く昆虫模倣匂い源探索ロボットの未来
1 はじめに
2 生物の匂い源探索行動
2.1 匂いの分布と受容
2.2 濃度勾配を利用した探索
2.3 濃度勾配を利用しない探索
2.4 複数感覚の統合
3 昆虫模倣ロボット:理想と現実
3.1 神経科学とロボット
3.2 生物行動のバイオミメティクス
3.3 どこまで生物を理解する必要があるのか
4 昆虫-機械ハイブリッドロボット
4.1 昆虫操縦型ロボットのしくみ
4.2 昆虫操縦型ロボットの匂い源探索能力
4.3 未来の匂い源探索ロボットで実験する
5 まとめと展望
第4章 トカゲの巧みな摩擦戦略-ヤモリの手の高グリップ力とサンドフィッシュの鱗の低摩擦・低摩耗-
1 はじめに
2 ヤモリの手の高いグリップ力
3 サンドフィッシュの鱗の低摩擦・低摩耗
4 まとめ
【第5編 設計・加工】
第1章 ナノインプリントテクノロジーとバイオミメティクス
1 印刷技術の応用(ナノインプリントテクノロジー)とバイオミメティクス
2 ナノインプリントテクノロジーによる生物表面を模倣した微細凹凸フィルム
3 生物表面の微細凹凸構造の持つ多機能性
3.1 超撥水性と超親水性
3.2 超低反射性
3.3 抗菌性・防カビ性
4 終わりに
【第6編 ロボティクス】
第1章 ソフトアクチュエーションによる生物型ロボティクス・メカトロニクス
1 はじめに
2 生物型ロボットとソフトアクチュエータ
3 ソフトアクチュエーションとしての人工筋肉
3.1 空気圧人工筋肉
3.2 軸方向繊維強化型人工筋肉
4 ミミズの蠕動運動による移動手法を利用した管内検査ロボット
4.1 ミミズの蠕動運動について
4.2 空気圧人工筋肉による蠕動運動の実現
4.3 ミミズロボットの応用事例
4.3.1 大腸内視鏡推進補助装置
4.3.2 工業用内視鏡ロボット
5 大腸の蠕動運動を規範とした固液2相・高粘度流体の混合搬送機
5.1 様々な物体を運ぶ・混ぜる腸管の優れた機能を応用
5.2 蠕動運動型混合搬送機
5.3 蠕動運動型混合搬送機の応用
5.3.1 優しくかつ高速に粉体を運ぶ
5.3.2 柔らかく安全に連続的に混ぜて運ぶ―固体推進薬製造への応用―
6 おわりに
第2章 Clap and Flingを利用した羽ばたき翼型飛行ロボットの開発について
1 緒論
2 羽ばたき翼における高揚力メカニズム
3 羽ばたき機構
4 翼のつくりと推力
5 羽の実験的最適化
5.1 羽ばたきロボット
5.2 計測装置
5.3 実験方法
5.4 実験結果
5.4.1 4パターンのアスペクト比による比較
5.4.2 3パターンの剛性による比較
5.4.3 アスペクト比,剛性,ギア比を含めた比較
5.4.4 空気合力による比較
5.5 実験結果
6 自立・自律飛行実験
6.1 羽ばたきロボットの概要
6.2 ピッチング抑制制御
6.3 実験方法
6.4 実験結果
7 結言
第3章 高分子素材のソフトアクチュエータと生物模倣ロボットへの応用
1 高分子アクチュエータ
2 電場応答性高分子材料
2.1 誘電エラストマアクチュエータ
2.2 導電性高分子アクチュエータ
2.3 イオン導電性高分子アクチュエータ
3 EAPの利用法
3.1 駆動方法
3.2 センサ利用
4 生物模倣ロボットへの応用
4.1 水中推進ロボット
4.2 歩行ロボットや他の生物模倣ロボット
4.3 ヘビ型推進ロボットの例
5 おわりに
-

血流改善成分の開発と応用《普及版》
¥3,850
2018年刊「血流改善成分の開発と応用」の普及版。動脈硬化や認知症の予防、美容効果、冷え性改善、眼精疲労・肩こり解消、疲労回復、育毛、男性機能向上など、幅広い効果が期待される「血流改善成分」について詳述した1冊。
(監修:大澤俊彦)
<a href="https://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=115751"target=”_blank”>この本の紙版「血流改善成分の開発と応用(普及版)」の販売ページはこちら(別サイトが開きます)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は、2018年当時のものを使用しております。
大澤俊彦 愛知学院大学
永井 雅 (株)ヘルスケアシステムズ
内藤通孝 椙山女学園大学
正本和人 電気通信大学
北市伸義 北海道医療大学病院
山田秀和 近畿大学
内藤裕二 京都府立医科大学/同附属病院
上原謙二 (株)アドメデック
姜勇求 MCヘルスケア(株)
中島 毅 MCヘルスケア(株)
板良敷朝将 サラヤ(株)
石川大仁 (株)ヘルスケアシステムズ
夏目みどり (株)明治
數村公子 浜松ホトニクス(株)
倉重(岩崎)恵子 (株)明治フードマテリア
山下陽子 神戸大学大学院
芦田 均 神戸大学大学院
小椋康裕 アスタリール(株)
高萩英邦 アスタリール(株)
高柳勝彦 (株)ダイセル
向井克之 (株)ダイセル
折越英介 三栄源エフ・エフ・アイ(株)
上田英輝 (株)東洋新薬
川村弘樹 (株)東洋新薬
野辺加織 (株)東洋新薬
宅見央子 江崎グリコ(株)
中村裕道 タマ生化学(株)
堀江俊治 城西国際大学
橋本和樹 城西国際大学
來村昌紀 城西国際大学
田嶋公人 城西国際大学
奥西 勲 金印(株)
西堀すき江 東海学園大学
山口勇将 日本大学
熊谷日登美 日本大学
阿部皓一 三菱ケミカルフーズ(株)
青木由典 三菱ケミカルフーズ(株)
田村 元 三菱ケミカルフーズ(株)
都築 毅 東北大学大学院
森田匡彦 協和発酵バイオ(株)
坂下真耶 (株)ファーマフーズ
宮﨑秀俊 アサヒグループホールディングス(株)
大木浩司 アサヒグループホールディングス(株)
長岡 功 順天堂大学
-------------------------------------------------------------------------
<<目次>>
【第I編 総論】
第1章 血流障害の原因
1 はじめに
2 血液凝固の原因
3 血管障害と酸化ストレス
4 酸化ストレス・炎症
5 酸化ストレスと血管・血流障害
5.1 酸化ストレスと血圧
5.2 酸化ストレスと血栓
5.3 酸化ストレスと動脈硬化
6 酸化ストレスに特異的なバイオマーカーの開発
第2章 血流障害と心血管疾患
1 血管の構造
2 血管の機能
3 動脈硬化の定義
4 粥状硬化の病理
5 粥状硬化の成因論
6 血行力学と粥状硬化の関わり
7 内皮機能と粥状硬化の関わり
8 静脈の血流障害
第3章 血流障害と脳機能
1 はじめに
2 脳の機能分化と脳血流の分配制御
3 脳血流の揺らぎとデフォルトモードネットワーク
4 脳血流と神経血管カップリング
5 加齢に伴う脳血流の低下と認知症
6 今後の展望:生涯健康な脳を維持するために
第4章 血流障害と眼精疲労
1 はじめに
2 LED電球や液晶画面の使用が増えるとなぜ眼精疲労が惹起されるのか?
3 眼精疲労への介入―アスタキサンチン(サケ/イクラ)
3.1 縄文時代の画期性
3.2 ヒトでの臨床効果
3.3 アスタキサンチン摂取の実際
4 眼調節機能と眼精疲労への介入―アントシアニン(ブルーベリー/ビルベリー)
4.1 「ブルーベリーは眼に良い」の根拠
4.2 VDT負荷試験への介入
5 眼調節機能と眼精疲労への介入―緑茶
6 おわりに
第5章 血流障害と肌トラブル
1 はじめに
2 血流障害と体表面の温度
3 皮膚のレベル
3.1 ダーマトポローシス(皮膚粗鬆症)
3.2 血管の問題
3.3 血液成分の問題
3.4 血管を支配する神経の問題
3.5 かさつき(乾燥)
3.6 しみ
3.7 くすみ
4 容貌のレベル
4.1 しわ
4.2 たるみ
4.3 髪質・脱毛
4.4 爪の変化
5 体型のレベル(筋膜までとする)
5.1 皮下脂肪
5.2 セルライト
6 さいごに
第6章 血流障害と消化器疾患
1 はじめに
2 虚血再灌流性胃粘膜傷害
3 NSAIDsによる消化管粘膜傷害
4 炎症性腸疾患
5 肝疾患
6 おわりに
【第II編 血流評価法】
第1章 レーザドップラー法
1 はじめに
2 測定原理
3 測定例
第2章 MCFAN(Micro channel array flow analyzer)
1 開発背景
2 特徴(システム)
3 MCFAN検査とは
4 MCFAN検査の測定方法
5 MCFAN検査の意義
6 MCFAN検査の医学的意味
7 臨床と応用
第3章 血管内皮機能測定法FMD(Flow-Mediated Dilatation)
1 はじめに
2 血管内皮機能(FMD)を測定する意義
3 血管内皮機能(FMD)測定
4 おわりに
第4章 酸化ストレス・炎症マーカー測定
1 はじめに
2 抗体チップ測定法の開発
3 生活習慣病改善効果に関する臨床試験
3.1 背景
3.2 試験デザイン
3.3 結果
4 おわりに
第5章 光センシングによる抗酸化・抗炎症評価法の開発
1 好中球の自然免疫反応を利用した「抗酸化・抗炎症・自然免疫賦活同時評価細胞試験」と作用機序解析法
2 神経細胞保護活性評価法
3 血管機能保護活性評価法
4 微量血液による生体内抗酸化機能評価法
【第III編 血流改善素材・成分】
第1章 水抽出型(膜濃縮)カシスポリフェノール(AC10)
1 カシスとは
2 水抽出型(膜濃縮)カシスポリフェノール(AC10)とは
3 水抽出型(膜濃縮)カシスポリフェノール(AC10)の特長
4 水抽出型(膜濃縮)カシスポリフェノール(AC10)による末梢血流サポート機能
4.1 安静時の末梢血流サポート機能
4.2 タイピング負荷時の末梢血流サポート機能(疲労様症状;肩の違和感,こり緩和)
4.3 冷水負荷時の末梢血流サポート機能(末梢体温維持,冷え緩和)
4.4 顔面の末梢血流サポート機能(疲労様症状;目のクマ緩和)
4.5 脳の末梢血流サポート機能
4.6 末梢血流サポート機能(末梢血管拡張機能)の作用機序
5 水抽出型(膜濃縮)カシスポリフェノール(AC10)の安全性
第2章 黒大豆ポリフェノール
1 はじめに
2 黒大豆ポリフェノール
3 ヒト介入試験デザイン
4 血管機能改善効果
5 酸化ストレス抑制効果
6 血中ならびに尿中ポリフェノール含量の変化
7 まとめ
第3章 アスタキサンチン
第4章 β-クリプトキサンチン
1 動脈硬化リスク低減
2 NO依存性血管拡張作用
3 血管内皮障害保護作用
4 血流改善作用
5 冷え性改善
第5章 ケルセチン
1 はじめに
2 ケルセチンの特性
3 ケルセチンの血流改善作用
4 ケルセチンのその他の機能性
4.1 抗高血圧作用および抗コレステロール作用
4.2 脳機能改善作用
5 おわりに
第6章 多様な機能性を有する素材「フラバンジェノール(R)」
1 はじめに
2 フラバンジェノール(R)の特徴
3 フラバンジェノール(R)の血流改善作用
4 血流改善作用の作用機序
4.1 血管拡張作用
4.2 赤血球変形能向上作用
5 フラバンジェノール(R)の多様な機能性
5.1 メタボ予防(LDLコレステロール値低下)
5.2 むくみ(浮腫)改善
5.3 シミ改善
5.4 育毛促進
6 フラバンジェノール(R)の安全性
7 おわりに
第7章 ヘスペリジンおよびヘスペリジン誘導体
1 ヘスペリジンとは
2 ヘスペリジン誘導体の開発
3 ヘスペリジンの吸収と代謝
4 糖転移ヘスペリジン・分散ヘスペレチンの血中動態
5 身体局部を冷却した冷え性改善試験
6 全身を緩慢に冷却した冷え性改善試験
7 肌状態の改善作用
8 自律神経に及ぼす影響
9 まとめ
第8章 イチョウ葉エキスの血流改善について
1 はじめに
2 GBEの成分組成
3 GBEの作用機序
3.1 血小板凝集抑制および血管拡張作用
3.2 赤血球の変形能向上作用
3.3 抗酸化作用
4 間欠性跛行(末梢血管疾患)の改善
5 脳機能の改善
5.1 認知症の改善
5.2 健常者の記憶力増進
6 眼血流の改善
7 おわりに
第9章 カプサイシノイド
1 はじめに
2 カプサイシノイド
3 温度感受性受容体
4 辛味と高温に反応するカプサイシン受容体TRPV1
5 カプサイシンの生理作用
6 胃におけるTRPV1の分布
7 カプサイシン感受性知覚神経から遊離される神経伝達物質
8 カプサイシンの胃粘膜血流増大作用メカニズム
9 ショウガ成分ジンゲロール
10 結び:カプサイシノイドは胃腸でも味わう
第10章 ワサビ(スルフィニル)
1 はじめに
2 わさびの血流改善効果
2.1 抗血小板凝集抑制作用
2.2 TRPA1刺激作用
2.3 抗酸化作用
2.4 ヒトでの血流改善効果
3 血流改善が寄与する作用
3.1 育毛効果
3.2 認知症改善効果
3.3 美肌効果
4 その他の機能性成分
5 おわりに
第11章 含硫フレーバー(ニンニク,シイタケ)
1 フレーバーの作用
2 ニンニクフレーバーの血小板凝集抑制作用
3 ニンニクフレーバー前駆体の血小板凝集抑制作用
4 シイタケフレーバーの血小板凝集抑制作用
5 まとめ
第12章 ビタミンE
1 ビタミンEとは
2 ビタミンEの血行改善作用
2.1 血行改善のメカニズム
2.2 血行改善作用におけるビタミンE同族体の比較
2.3 ヒトにおけるビタミンEの血流改善作用
3 まとめ
第13章 n-3系脂肪酸(DHA,EPA)
1 n-3系脂肪酸(DHA,EPA)とは
2 DHA・EPAと血管機能の背景
3 DHA・EPAと血管機能に対する効果
4 DHA・EPAと血圧に対する効果
5 脳血管系でのDHA・EPAの機能
6 DHA・EPAによる直接作用とその代謝産物による間接作用
7 DHA・EPAによる血管性認知症予防
第14章 シトルリン
1 シトルリンの代謝
2 シトルリンとNOサイクル
3 シトルリンと血管内皮機能
4 シトルリンと運動生理機能
5 おわりに
第15章 卵白ペプチドの血流改善作用について
1 卵白ペプチドの開発
2 卵白ペプチドの機能性探索
2.1 運動疲労軽減効果
2.2 眼精疲労軽減効果
3 卵白ペプチドの血管拡張メカニズム
4 他の食品素材との組み合わせによる相乗効果作用
5 まとめ
第16章 「ラクトトリペプチド」の血流を向上させる作用と健康の維持・増進への活用
1 血流と血流依存性血管拡張の生理学的な意義
2 「ラクトトリペプチド」のFMDを向上させる作用
3 「ラクトトリペプチド」の前腕血流量を向上させる作用
4 「ラクトトリペプチド」の血流を向上させるメカニズム
第17章 グルコサミン
1 はじめに
2 血小板凝集抑制作用
3 血管内皮細胞の活性化抑制
4 グルコサミンの抗動脈硬化作用
5 おわりに
-

感覚重視型技術の最前線―心地良さと意外性を生み出す技術―《普及版》
¥3,630
2018年刊「感覚重視型技術の最前線」の普及版!「触感」「心地良さ」を追求し、感覚の評価や計測に基づいたものづくり・ことづくりを紹介した1冊。
(監修:秋山庸子)
<a href="http://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=115649"target=”_blank”>この本の紙版「感覚重視型技術の最前線 ―心地良さと意外性を生み出す技術―(普及版)」の販売ページはこちら(別サイトが開きます)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は、2018年当時のものを使用しております。
秋山庸子 大阪大学
岩村吉晃 東邦大学
坂本真樹 電気通信大学
渡邊淳司 日本電信電話(株)
早川智彦 東京大学
望山 洋 筑波大学
藤本英雄 名古屋工業大学
岩木 直 (国研)産業技術総合研究所
原田暢善 フリッカーヘルスマネジメント(株)
山口明彦 東北大学
近井 学 (国研)産業技術総合研究所
井野秀一 (国研)産業技術総合研究所
石丸園子 東洋紡(株)
金井博幸 信州大学
早瀬 基 花王(株)
松江由香子 クラシエホームプロダクツ(株)
西村崇宏 国立特別支援教育総合研究所
土井幸輝 国立特別支援教育総合研究所
藤本浩志 早稲田大学
長谷川晶一 東京工業大学
三武裕玄 東京工業大学
井上真理 神戸大学
仲村匡司 京都大学
木村裕和 信州大学
岡本美南 TOTO(株)
白井みどり 大阪市立大学
瓜﨑美幸 淀川キリスト教病院
山本貴則 (地独)大阪産業技術研究所
山田憲嗣 大阪大学
武田真季 大阪大学
大野ゆう子 大阪大学
-------------------------------------------------------------------------
<<目次>>
【第I編 感覚のメカニズム】
第1章 感覚の分類と触覚
1 はじめに
2 触覚、特殊感覚、一般感覚、体性感覚
2.1 アリストテレスの五感と触覚
2.2 Weberの触覚と一般感覚
2.3 感覚点の研究に始まる皮膚受容器同定の試み
2.4 体性感覚
3 体性感覚の生理学
3.1 触圧覚の受容器
3.2 温度受容器と痛覚受容器
3.3 皮膚の無毛部と有毛部
3.4 深部感覚
3.5 深部受容器
3.6 自己受容感覚、固有感覚
3.7 運動感覚
3.8 単一神経活動電位記録による皮膚受容器の同定
3.9 体性感覚を伝える末梢神経の種類と伝導速度
3.10 Microneurogramにより同定されたヒトの触覚受容器
3.11 原始感覚と識別感覚:Headの2元説
3.12 識別感覚の中枢
4 無髄(C)線維の生理学:快楽的(hedonic)触覚
4.1 無髄(C)線維の活動電位記録
4.2 ヒトの触覚にかかわる無髄線維活動の記録と同定
4.3 ヒトの触覚にかかわる無髄線維興奮の最適刺激
4.4 有毛部の低閾値無髄線維の役割:有髄線維を失った患者での観察
4.5 触覚を伝える低閾値無髄線維は島皮質に投射し、体性感覚野には投射しない
4.6 GLでは島皮質が厚くなり、体性感覚野が薄くなっている
4.7 快楽的触覚を処理する脳部位は島
5 おわりに
第2章 五感と快不快
1 感覚を表すオノマトペ
2 オノマトペの音に反映される手触りの快不快
3 食べたり飲んだりした時の感覚もオノマトペの音に反映される
4 オノマトペの音に反映される手触りと味の快不快の共通性
5 オノマトペの音から感覚的印象を推定するシステム
【第II編 感覚をはかる・感覚ではかる~計測技術】
第3章 感覚のオノマトペと官能評価
1 感覚イメージとその表象
2 オノマトペによる触り心地の可視化
3 触覚オノマトペの分布図の作成
4 オノマトペ分布図と想起される素材・質感
5 オノマトペ分布図の音韻論による分析
6 オノマトペの分布図を利用した触相図の作成
7 触相図の利用法
第4章 快・不快をはかる~触覚の官能評価と物理量の関係~
1 快・不快とは
2 触覚の快・不快の決定因子の検討
3 触覚を表す言葉と触対象の系統化
3.1 触覚を表す言葉の快・不快への分類
3.2 触対象の系統化
4 快・不快と物理量の関係づけ
4.1 触対象による快・不快の官能評価の特徴
4.2 快・不快と物理量の関係
5 快・不快の物理モデル構築と妥当性評価に向けて
第5章 触覚ではかる
1 はじめに:微小面歪の検出
2 触覚コンタクトレンズ
3 Morphological Computationという視点
3.1 Morphological Computationとは
3.2 Morphological Computationとしての触知覚
3.3 ゴム製人工皮膚層メカトロサンド
3.4 典型例としてのひずみゲージサンド
4 ひずみゲージサンドによる微小面歪検出
4.1 ひずみゲージサンドの基本特性
4.2 機械学習の利用
5 おわりに
第6章 視覚ではかる―ちらつき知覚の変化に基づく簡易疲労計測技術―
1 はじめに
2 ちらつき知覚のコントラストによる変化を用いた疲労検査
3 強制選択・上下法によるちらつき知覚閾値の決定方法
4 ネットワークを用いた日常疲労計測のためのプロトタイプシステム
5 まとめ
【第III編 感覚をつくる・つかう~提示・代行技術~】
第7章 ロボットハンドへの触覚導入
1 はじめに
2 ロボットハンドで使われている触覚センサ
2.1 光学式触覚センサ
2.2 触覚のモダリティ
3 触覚センサを搭載したロボットハンドの応用事例
3.1 触覚センサを使った対象物・環境認識
3.2 触覚センサを使った物体操作
4 触覚は本当に必要か?
4.1 触覚と行動学習
5 オープンソース触覚センサプロジェクト
第8章 感覚代行
1 はじめに
2 感覚代行研究の歴史
3 視覚に障害がある人たちへの福祉技術(視覚の代行技術)
4 聴覚に障害がある人たちへの福祉技術(聴覚の代行技術)
5 楽しみを分かちあう福祉技術
6 おわりに
【第IV編 感覚を重視したものづくり・ことづくり~生活環境設計からロボットまで~】
第9章 繊維製品における心地良さの計測技術
1 はじめに
2 心地良いと感じられる商品の開発手法
3 熱・水分特性に関する心地良さの数値化
4 肌触りに関する心地良さの数値化
5 圧力特性に関する心地良さの数値化
6 生理計測による心地良さの数値化
7 おわりに
第10章 健康と快適を目指した衣服における感性設計・評価
1 はじめに
2 熱中症リスク管理に貢献するスマート衣料の開発
2.1 産学連携による包括的な課題解決策の提案
2.2 実効性を担保する設計・評価サイクルの実践
3 肥満症予防を目指した運動効果促進ウェアの開発
4 高機能ウェア開発における「着心地」という障壁
第11章 感性を考慮したスキンケア化粧品設計
1 はじめに
2 感性価値の評価
3 感性価値を化粧品へ付加するために必要な処方ポイント
3.1 五感へアプローチする方法
3.1.1 視覚へのアプローチ
3.1.2 嗅覚へのアプローチ
3.1.3 触覚へのアプローチ
3.2 意識へアプローチする方法
4 おわりに
第12章 ヘアケア製品における感性設計―シャンプーのなめらかな洗いごこちを生み出す技術―
1 シャンプーの基本機能
2 シャンプーの組成
3 心地良さを感じる機能
4 なめらかな指どおりとは
5 なめらかな指どおりを生み出す技術
6 コアセルベート
7 反力積分値による毛髪すべり性測定
8 シャンプーの感性機能設計
9 今後の展望
第13章 ユーザの特性に合わせた操作しやすいタッチパネル情報端末のGUI設計
1 はじめに
2 ユーザの特性評価と設計への応用
2.1 ユーザの身体寸法を考慮したGUI設計
2.2 画面表面での指先の滑りやすさを考慮したGUI設計
2.3 操作方法や手指の姿勢を考慮したGUI設計
3 タッチパネル情報端末のアクセシビリティ
4 おわりに
第14章 柔らかいロボットの開発
1 はじめに
2 人を傷つけず、自らが壊れないロボット
2.1 力や圧力を拡大する機構
2.2 慣性力
2.3 コンプライアンス性の高い関節、ロボット
2.4 全体が柔軟な機構
3 ぬいぐるみによる屈曲機構
3.1 素材等の選定
3.1.1 綿
3.1.2 糸
3.1.3 布
3.1.4 外皮とクッション
3.1.5 糸を巻き取るアクチュエータ
3.2 糸の組み合わせと配糸
3.3 長軸回りの回転関節
3.4 繰り返し精度と提示可能な力の範囲
4 ぬいぐるみロボットの制御
4.1 計測データに基づく運動学・逆運動学計算
4.2 力制御
4.2.1 力計測
4.2.2 制御計算の分散処理
5 ぬいぐるみロボットの動作生成
5.1 キーフレームの再生
5.2 外界センサ入力に応じた動作生成
6 ぬいぐるみロボットの機能と性能
6.1 運動性能と力制御の効果
6.2 耐久性
7 今後の展望
第15章 自動車における感性設計
1 はじめに
2 布の触感
2.1 人の皮膚特性と布の特性
2.2 触感の主観評価
2.3 布の触感の客観的評価に用いられる物理特性
2.4 客観評価式
3 自動車シート用材料の触感
3.1 試料と主観評価
3.2 主観評価
3.3 物理特性の測定
3.4 主観評価結果
3.5 物理特性と主観評価の関係
3.6 既存式(秋冬用紳士スーツ地)の客観評価式への応用
3.7 シート用材料の客観評価式の誘導
3.8 評価式を用いた客観評価と主観評価との関係
3.8.1 秋冬用紳士スーツ地の既存式による客観評価
3.8.2 誘導された自動車シート用皮革の式による客観評価
4 おわりに
第16章 木材の見えの数値化と印象評価との関係
1 はじめに
2 画像解析による材面の特徴抽出
3 木質床材の外観特性の抽出と表現
3.1 木質床材の収集
3.2 材鑑画像の取得
3.3 画像解析
3.4 画像特徴量の設定
4 材面の印象評価
5 おわりに
第17章 住環境の快適条件―温熱環境と音環境―
1 住環境の快適条件
2 住環境の温熱的快適性
3 居住空間における快適な音環境
第18章 住環境における感性設計(浴室用シャワーヘッド)
1 背景、目的
2 シャワー吐水の浴び心地に影響する心理的要因の分析
2.1 評価形容語の抽出
2.2 浴び心地に対する心理構造の分析
3 シャワー吐水のすすぎやすさに対する心理構造分析
3.1 実験① すすぎやすさとすすぎ時間の関係検証
3.2 実験② すすぎやすさの心理構造分析
3.3 すすぎ時のシャワー水流観察
3.4 すすぎやすさを高める心理的、物理的要因の考察
4 おわりに
第19章 認知症高齢者の「心地良さ」と環境づくり
1 はじめに
2 認知症高齢者の特徴
2.1 認知症とは
2.2 認知症の症状
2.2.1 中核症状
2.2.2 BPSD
2.3 加齢に伴う変化
3 認知症高齢者の環境づくりに関する研究
3.1 認知症高齢者の環境づくりの意義・目的
3.2 認知症高齢者への環境支援のための指針(PEAP 日本版3)
3.3 環境づくりに関する介入研究の紹介
3.3.1 事例1
3.3.2 事例2
4 おわりに
第20章 褥瘡予防寝具に求められる性能―シープスキン寝具の検討例―
1 はじめに
2 倫理的配慮
3 高齢被験者による実証実験と官能評価
4 高齢被験者から得られた仙骨部接触圧および組織血流量と官能評価の関係
5 高齢被験者の身体的特徴と仙骨部接触圧および組織血流量との関係
6 おわりに
第21章 看工融合領域におけるロボットによる心地良さへの試み
1 はじめに
2 看工融合領域
3 看工融合領域とロボット
3.1 洗髪ロボット
3.2 心地よさを評価するポイントについて(洗浄効果に着目)
4 おわりに
-

臓器チップの技術と開発動向《普及版》
¥4,840
2018年刊「臓器チップの技術と開発動向」の普及版!創薬、疾患発症機序解明、食品栄養・機能性研究、化学物質毒性試験など、さまざまな応用が期待される「臓器チップ」の開発技術を詳述した1冊。
(監修:酒井康行、金森敏幸)
<a href="http://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=115666"target=”_blank”>この本の紙版「臓器チップの技術と開発動向(普及版)」の販売ページはこちら(別サイトが開きます)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は、2018年当時のものを使用しております。
酒井康行 東京大学
金森敏幸 (国研)産業技術総合研究所
小島肇夫 国立医薬品食品衛生研究所
安西尚彦 千葉大学
田端健司 アステラス製薬(株)
木村啓志 東海大学
藤井輝夫 東京大学
田中 陽 (国研)理化学研究所
今任景一 早稲田大学
武田直也 早稲田大学
石田誠一 国立医薬品食品衛生研究所
伊藤弓弦 (国研)産業技術総合研究所
松崎典弥 大阪大学
福田淳二 横浜国立大学
森 宣仁 東京大学
竹内昌治 東京大学
梨本裕司 京都大学
横川隆司 京都大学
民谷栄一 大阪大学
二井信行 芝浦工業大学
楠原洋之 東京大学
前田和哉 東京大学
佐藤 薫 国立医薬品食品衛生研究所
髙山祐三 (国研)産業技術総合研究所
木田泰之 (国研)産業技術総合研究所
小森喜久夫 東京大学
岩尾岳洋 名古屋市立大学
松永民秀 名古屋市立大学
田川陽一 東京工業大学
玉井美保 東京工業大学
藤山陽一 (株)島津製作所
須藤 亮 慶應義塾大学
西澤松彦 東北大学
長峯邦明 東北大学
鳥澤勇介 京都大学
伊藤 竣 東北大学
Li-Jiun Chen 東北大学
梶 弘和 東北大学
加納ふみ 東京工業大学
野口誉之 東京大学
村田昌之 東京大学授
薄葉 亮 東京大学
松永行子 東京大学
佐々木直樹 東洋大学
中澤浩二 北九州市立大学
篠原満利恵 東京大学
杉浦慎治 (国研)産業技術総合研究所
佐藤記一 群馬大学
亀井謙一郎 京都大学
-------------------------------------------------------------------------
<<目次>>
【第I編 総論】
第1章 臓器チップの国内外の研究開発動向と展望
1 はじめに
2 Human-on-a-chip
3 MPSへのシフト
4 今後の方向性
第2章 動物実験代替法としての臓器チップへの期待
1 序論
2 動物実験代替法に関する国際動向
3 公定化された試験法の有用性と限界
4 全身毒性試験の代替開発への取り組み
4.1 欧州の動向
4.2 米国の動向
4.3 OECDの動向
4.4 日本の動向
4.5 Microphysiologicalsystemでの現状と課題
5 終わりに
第3章 Physiological modelとしての臓器チップへの期待
1 はじめに
2 生物学と生理学
3 多臓器円環の概念
4 多臓器円環の課題と臓器チップの有用性
5 臓器チップによる「自律臓器学」の確立へ
6 まとめ
第4章 製薬企業から見た臓器チップへの期待
1 医薬品研究開発における不確実性
2 Microphysiological systemと臓器チップ
3 薬物動態試験としての臓器チップ
3.1 小腸
3.2 肝臓
3.3 腎臓
3.4 血液脳関門
4 製薬企業で用いる細胞培養システム
5 生理学的速度論とmicrophysiological systems
6 将来への期待
7 モダリティの多様化とMPSへの期待
8 産官学での取り組みの期待
【第II編 要素技術】
第1章 臓器チップ開発のための微細加工技術
1 はじめに
2 ポリジメチルシロキサン(PDMS)の特徴
3 製作プロセス
4 臓器チップのための機能集積化技術
5 細胞培養のための表面処理技術
6 おわりに
第2章 超薄板ガラスのマイクロ流体チップ
1 緒言
2 超薄板ガラスハンドリング・加工技術開発
3 ガラスバルブ
4 ガラスポンプ
5 ガラスセンサー
6 ガラスフィルター
7 超薄板ガラスチップ
8 結言
第3章 基材の表面形状および性状が細胞に与える影響
1 はじめに
2 細胞の基材への接着
3 基材表面の性質が細胞に与える影響
3.1 化学的性質
3.2 機械的性質
3.3 形状
4 おわりに
第4章 Microphysiological systems用細胞とその標準化
1 はじめに
2 開発の歴史から見るMPSの変遷
3 MPS用細胞に求められる性能基準
4 細胞の規格化
5 測定法の規格化
6 おわりに
第5章 高分子化学に基づく3次元組織構築
1 生体組織モデルの重要性
2 化学的細胞操作
3 組織構築の2つのアプローチ
4 細胞積層法
5 細胞集積法
6 肝組織チップによる薬物毒性評価
7 おわりに
第6章 電気化学的手法による3次元組織の構築
1 はじめに
2 電気化学的な細胞脱離を利用した血管構造の作製
3 静水圧を利用したシーソー型送液システムの開発
4 おわりに
第7章 血管内包型3次元組織の構築
1 はじめに
2 血管内包型3次元組織の構築方法
2.1 ワイヤ抜去法
2.2 コラーゲン・ソフトリソグラフィ法
2.3 犠牲構造除去法
2.4 血管新生法
2.5 各方式の比較
3 血管内包型皮膚チップ
3.1 皮膚チップについて
3.2 血管内包型皮膚チップの開発
3.3 皮膚モデルの評価
3.4 経皮吸収試験への応用
4 おわりに
第8章 微小流体デバイス内における生体組織と血管網の融合
1 はじめに
2 血管内皮細胞を用いた血管網形成技術
3 オンチップにおけるhLFによるHUVECの血管新生
4 自己組織化によるスフェロイド内部への管腔構造の形成
5 おわりに
第9章 On-chip細胞デバイス
1 はじめに-オンチップテクノロジーから細胞デバイスへ-
2 細胞チップを用いたアレルゲンの測定
3 ペプチドライブラリーアレイチップを用いた神経成長因子のスクリーニング
4 局在表面プラズモン共鳴ナノデバイスを用いた細胞シグナルモニタリング
5 シングル細胞解析デジタルデバイス
6 マイクロ流体デバイスを用いたシングル細胞機能解析
7 ラマンイメージング解析を用いた細胞分化プロセスの非侵襲解析
第10章 細胞培養マイクロ流体デバイスの凍結保存
1 はじめに
2 細胞の凍結保存とマイクロ流体
2.1 細胞の凍結保存に求められる条件
2.2 細胞凍結保存のためのマイクロ流体チップ
3 可搬性のある細胞凍結保存用マイクロ流体チップの開発
3.1 細胞凍結用マイクロ流体チップに求められる条件
3.2 デバイスの構造
3.3 マイクロ流れの生成
3.4 細胞の凍結保存
4 おわりに
第11章 Body-on-a-chipを用いた薬物動態解析と個体レベルへの外挿の重要性
1 はじめに
2 BOCにおけるコンパートメント中の薬物濃度に関する考察
3 BOCにおいて想定される薬物動態に関する考察
4 BOCから得られたデータに基づくヒト個体レベルの薬物動態への外挿の
ストラテジー
5 体内動態における非線形性の取り扱い
6 PKモデルとPDモデルとの統合による薬効予測
7 終わりに
【第III編 臓器チップ】
第1章 創薬のためのin vitro血液脳関門モデルの開発─現状と展望
1 新薬開発と血液脳関門(blood brain barrier:BBB)
2 BBBの構造と機能
3 非細胞系モデル
4 細胞系モデルの登場
5 齧歯類細胞モデル
6 ウシ(bovine),ブタ(porcine)細胞モデル
7 株化細胞モデル
8 ヒト細胞モデル
9 In vitro BBBモデルへの工学的アプローチ
10 BBB on a chipへ
11 終わりに
第2章 心毒性評価の臓器チップ開発に資するヒト自律神経系の生体外再構築
1 はじめに
2 ヒト多能性幹細胞からの自律神経系誘導法開発
3 自律神経を接続した培養ヒト心筋組織の作製
4 おわりに
第3章 In vitro培養肺胞モデルとチップ化検討
1 はじめに
2 肺胞の構造
3 ヒト細胞株を用いた肺胞上皮モデル
4 ラット初代細胞を用いた肺胞上皮モデル
5 今後の課題
6 おわりに
第4章 経口投与薬物の吸収・代謝過程を模倣した小腸-肝臓連結デバイスの開発
1 はじめに
2 既存の腸管チップ
3 小腸とデバイスに利用可能な細胞
4 ヒトiPS細胞から小腸上皮細胞への分化誘導
5 小腸-肝臓2臓器連結デバイス開発
5.1 デバイスに対する開発コンセプト
5.2 現在開発中のデバイス
6 おわりに
第5章 腎機能を再現するKidney-on-a-chip
1 はじめに
2 腎臓の機能と構造
3 Glomerulus-on-a-chip:糸球体モデルデバイス
4 Tubule-on-a-chip:尿細管モデルデバイス
5 腎機能を集積化した多臓器モデルデバイス
6 おわりに
第6章 流体デバイスを用いたES/iPS細胞由来肝臓モデル
1 序論
2 これまでのマイクロ流体デバイスを用いた細胞培養
3 肝臓の構造
4 肝組織培養モデルと流体デバイス
5 最後に
第7章 マイクロ流体システムによる血管形成モデルと肝細胞3次元培養モデルの融合
1 血管形成の培養モデル
2 肝細胞3次元培養モデル
3 血管形成モデルと肝細胞3次元培養モデルの融合
第8章 筋肉細胞チップ
1 はじめに
2 収縮能を有する骨格筋細胞の培養と評価
3 骨格筋細胞の3次元培養
4 骨格筋と異種細胞の共培養
5 おわりに
第9章 骨髄機能の再現に向けたOrgan-on-a-chip
1 はじめに
2 骨髄を模倣したin vitro培養システム
3 生体内での骨髄の作製
4 生体外での骨髄機能の維持
5 薬剤評価への応用
6 おわりに
第10章 網膜疾患を模倣するOrgan-on-a-chip
1 はじめに
2 網膜の恒常性
3 inner BRBを模倣するOrgan-on-a-chip
4 outer BRBを模倣するOrgan-on-a-chip
5 動物から採取した網膜組織を搭載するOrgan-on-a-chip
6 おわりに
第11章 セミインタクト細胞リシール技術を用いた糖尿病モデル細胞アレイとその解析法
1 はじめに
2 セミインタクト細胞リシール技術について
3 リシール細胞技術を用いた「糖尿病態モデル肝細胞」作製
4 イメージング技術を用いた糖尿病態細胞のフェノタイピング
5 糖尿病モデル細胞アレイとFIQAS顕微鏡・画像解析システムを用いた糖尿病改善薬の可視化スクリーニング
6 将来展開
第12章 3次元微小血管チップによる血管新生と血管透過性の評価手法の構築
1 はじめに
2 従来の血管新生および透過性アッセイ手法
3 ボトムアップ組織工学に基づく血管チップの作製
4 血管チップを用いた新生血管の経時変化の追跡
5 血管チップを用いた血管透過性の評価
6 おわりに
第13章 無細胞マイクロ腫瘍血管モデルの開発とナノ薬剤評価への応用
1 はじめに
2 ナノ薬剤を用いる薬物送達(ナノDDS)
3 ナノDDSの評価系
4 無細胞マイクロ腫瘍血管モデル
5 多孔膜垂直配置型デバイスの開発
6 おわりに
第14章 スフェロイドアレイ化デバイス
1 はじめに
2 スフェロイドの特徴
3 スフェロイド形成の原理と汎用的技術
4 スフェロイドアレイ化デバイス
5 肝細胞スフェロイドのアレイ化培養
6 おわりに
第15章 酸素透過プレートと肝モデル応用
1 はじめに
2 酸素透過性プレートの開発
3 酸素透過プレートを用いた階層的重層化培養
4 凝集体培養
5 肝チップの開発動向と肝モデルへの応用
6 おわりに
第16章 臓器由来細胞を集積化したBody-on-a-chip
1 はじめに
2 バルクスケールの複数臓器由来細胞共培養装置
3 マイクロスケールの複数臓器由来細胞共培養デバイス:Body-on-a-chip
4 実用化に向けたBody-on-a-chip
5 おわりに
第17章 マルチスループットMicrophysiological systems
1 背景
2 圧力駆動型の循環培養デバイス
3 マルチスループットMultiorgans-on-a-chip
4 プラットフォームとしてのマルチスループットMicropysiological systems
5 マルチスループットMultiorgans-on-a-chipを用いた抗癌剤プロドラッグの評価
6 今後の展望
第18章 薬物動態解析のためのマイクロ人体モデル
1 はじめに
2 消化,吸収,代謝を考慮に入れたバイオアッセイチップ
2.1 胃・十二指腸モデル
2.2 腸管吸収モデル
2.3 肝臓モデル
2.4 消化吸収代謝の複合モデル
3 腎排泄マイクロモデル
4 おわりに
第19章 抗がん剤の副作用を再現するBody-on-a-chipの開発
1 背景
2 実験方法
2.1 生体外抗がん剤副作用モデル
2.2 iHCCのデザイン
2.3iHCC製造プロセス
2.4 デバイス制御
2.5 細胞培養
2.6 iHCCにおける細胞培養
2.7 iHCCにおける抗がん剤細胞試験
2.8 96ウェルプレートでの抗がん剤細胞試験
2.9 死細胞染色
2.10 顕微鏡観察と画像解析
3 結果と考察
3.1 iHCCにおける細胞培養
3.2 iHCCにおける薬物検査
4 結論
-

食品機能性成分の吸収・代謝・作用機序《普及版》
¥5,280
2018年刊「食品機能性成分の吸収・代謝・作用機序」の普及版。食品中の生体調節機能成分について「体内動態」や「機能発現機序」を詳述し、確かな機能性と安全性を備えた機能性食品の開発に役立つ1冊。(監修:宮澤陽夫)
<a href="http://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=115667"target=”_blank”>この本の紙版「食品機能性成分の吸収・代謝・作用機序(普及版)」の販売ページはこちら(別サイトが開きます)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は、2018年当時のものを使用しております。
宮澤陽夫 東北大学
薩 秀夫 前橋工科大学
山本晃久 前橋工科大学
鈴木大斗 前橋工科大学
宮澤大樹 東京医科歯科大学
田村 基 (国研)農業・食品産業技術総合研究機構
田原 優 University of California Los Angeles
柴田重信 早稲田大学
井上奈穂 山形大学
久保田真敏 新潟薬科大学
門脇基二 新潟工科大学
安尾しのぶ 九州大学
古瀬充宏 九州大学
吉澤史昭 宇都宮大学
小林淳平 神戸大学
大島敏久 大阪工業大学
原 博 北海道大学
松井利郎 九州大学
君羅好史 城西大学
真野 博 城西大学
前渕元宏 不二製油グループ本社(株)
神田 淳 (株)明治
中山恭佑 (株)明治
東 誠一郎 (株)明治
佐藤三佳子 日本ハム(株)
片倉善範 九州大学
三浦 豊 東京農工大学
西村直道 静岡大学
園山 慶 北海道大学
山口喜勇 松谷化学工業(株)
何森 健 香川大学
渡部睦人 東京農工大学
野村義宏 東京農工大学
福島道広 帯広畜産大学
北川真知子 松谷化学工業(株)
池田郁男 東北大学
西川正純 宮城大学
菅原達也 京都大学
佐藤匡央 九州大学
森田有紀子 九州大学
澤田一恵 築野食品工業(株)
松木 翠 築野食品工業(株)
橋本博之 築野食品工業(株)
仲川清隆 東北大学大学院
川上祐生 岡山県立大学
池本一人 三菱ガス化学(株)
松郷誠一 金沢大学
生田直子 神戸大学
津田孝範 中部大学
小竹英一 (国研)農業・食品産業技術総合研究機構
立花宏文 九州大学
石見佳子 (国研)医薬基盤・健康・栄養研究所
宅見央子 江崎グリコ(株)
永塚貴弘 東北大学
-------------------------------------------------------------------------
<<目次>>
【第I編 吸収・代謝・作用効率に影響を与える因子】
第1章 腸管上皮トランスポーター
1 腸管上皮細胞
2 腸管上皮における食品成分の主要な吸収経路
2.1 トランスポーターを介した吸収経路
2.2 トランスサイトーシスを介したエネルギー依存的細胞内輸送経路
2.3 細胞間隙を介した透過経路
2.4 細胞内単純拡散経路
3 腸管上皮トランスポーター
4 腸管上皮トランスポーターの食品成分による制御・調節
5 終わりに
第2章 食品ナノ粒子化
1 はじめに
2 食品由来のナノ粒子
3 無機ナノ粒子の生体への暴露
4 食品ナノ粒子の用途
5 食品ナノ粒子の体内動態
6 食品ナノ粒子の安全性評価
6.1 細胞毒性
6.2 炎症
6.3 酸化ストレス
7 おわりに
第3章 腸内細菌
1 はじめに
2 食物繊維,オリゴ糖
3 ポリフェノール
3.1 イソフラボン
3.2 ケルセチン
3.3 エラグ酸
3.4 カテキン
3.5 クロロゲン酸
3.6 リグナン
第4章 体内時計,時間栄養学
1 はじめに
2 哺乳類の体内時計
3 時間栄養学,時間薬理学
4 糖吸収の日内変動
5 タンパク質吸収の日内変動
6 脂質吸収の日内変動
7 細胞間隙を介する吸収の日内変動
8 肝臓における異物代謝の日内変動
9 時差ボケ等による体内時計の不調
10 カフェインによる体内時計制御
11 ポリフェノールによる体内時計制御
第5章 食品成分の相乗・相加・相殺作用
1 食品成分の相乗作用
2 食品成分の相加作用
3 食品成分の相殺作用
【第II編 機能性成分の吸収・代謝・作用機序】
第1章 アミノ酸
1 概観:アミノ酸の吸収
1.1 中性アミノ酸輸送
1.2 塩基性アミノ酸輸送
1.3 酸性アミノ酸輸送
1.4 Pro,Hyp,Gly輸送
1.5 β-アミノ酸およびTau
1.6 ジ・トリペプチド
2 ストレス・睡眠関連アミノ酸
2.1 はじめに
2.2 ストレス・睡眠調節作用を有するアミノ酸とその関連物質
2.3 概日時計の調節作用を有するアミノ酸
3 分枝鎖アミノ酸(BCAA)
3.1 分枝鎖アミノ酸の腸管での吸収
3.2 分枝鎖アミノ酸の肝性脳症改善作用
3.3 分枝鎖アミノ酸の代謝
3.4 ロイシンのタンパク質代謝調節機能
3.5 ロイシンによるmTORC1の活性制御
3.6 イソロイシンの糖代謝調節機能
3.7 おわりに
4 D-アミノ酸
第2章 タンパク質・ペプチド
1 概観:タンパク質・ペプチドの消化・吸収・代謝・体内動態(生理作用)
1.1 タンパク質の消化
1.2 タンパク質消化産物の吸収
1.3 ペプチドの吸収と生理作用
2 低分子・オリゴペプチド
2.1 はじめに
2.2 ペプチド機能
2.3 in vitroでのペプチド透過挙動
2.4 in vivoでのペプチド吸収挙動
2.5 おわりに
3 コラーゲンペプチドの吸収,代謝とその作用機序
3.1 はじめに
3.2 コラーゲンペプチドについて
3.3 コラーゲンペプチドの吸収
3.4 コラーゲンペプチドの血中動態と組織移行
3.5 コラーゲンペプチド摂取による効果と作用メカニズム
3.6 まとめ
4 大豆ペプチド
4.1 はじめに
4.2 大豆ペプチドの易吸収性
4.3 肉体疲労に対する大豆ペプチド摂取の効果
4.4 大豆ペプチド摂取によるロコモティブシンドローム予防効果(抗炎症作用)
4.5 認知機能改善に関与する大豆由来ペプチド
4.6 おわりに
5 乳タンパク質であるホエイタンパク質やカゼインおよびそれに由来したペプチド
5.1 乳タンパク質とは
5.2 ホエイタンパク質とそのペプチド
5.3 カゼインとそのペプチド
6 イミダゾールジペプチド
6.1 はじめに
6.2 イミダゾールジペプチドの消化・吸収について
6.3 脳機能改善効果について
6.4 イミダゾールジペプチドによる脳機能改善のメカニズム
6.5 イミダゾールジペプチドの安全性
6.6 おわりに
第3章 糖類
1 概観:糖質の消化・吸収・代謝・体内動態
1.1 食品中の糖質について
1.2 糖質の消化,吸収,代謝,体内動態について
1.3 糖質の消化過程と疾病との関連
2 食物繊維をはじめとするルミナコイドの大腸発酵を介した新たな展望
2.1 はじめに
2.2 大腸H2による酸化ストレス軽減
2.3 高H2生成細菌叢の導入による大腸高H2生成環境の構築
2.4 大腸内発酵によるH2の供給持続性
2.5 おわりに
3 オリゴ糖(フラクトオリゴ糖,マンノオリゴ糖(マンノビオース),ガラクトオリゴ糖)
3.1 はじめに
3.2 オリゴ糖の製造
3.3 オリゴ糖の食品としての機能
3.4 フラクトオリゴ糖
3.5 マンノオリゴ糖(マンノビオース)
3.6 ガラクトオリゴ糖
4 希少糖
4.1 はじめに
4.2 D-プシコース
4.3 体内動態(吸収・代謝・発酵)
4.4 生理機能および作用機序
4.5 希少糖含有シロップ
4.6 おわりに
5 グルコサミン,コンドロイチン硫酸,ヒアルロン酸
5.1 はじめに
5.2 グルコサミン
5.3 コンドロイチン硫酸
5.4 ヒアルロン酸
5.5 おわりに
6 β-グルカン,イヌリン,レジスタントスターチ
6.1 はじめに
6.2 食物繊維
6.3 おわりに
7 難消化性デキストリン
7.1 難消化性デキストリンとは
7.2 難消化性デキストリンの吸収および代謝(体内動態)
7.3 難消化性デキストリンの生理機能および作用機序
7.4 おわりに
第4章 脂肪酸・油脂類
1 概観:脂肪酸・油脂類の消化・吸収・代謝・体内動態
1.1 はじめに
1.2 トリアシルグリセロールの消化・吸収・代謝・体内動態
1.3 脂肪酸の消化・吸収・代謝・体内動態
1.4 リン脂質の消化・吸収・代謝・体内動態
1.5 ステロールの消化・吸収・代謝・体内動態
1.6 おわりに
2 n-3系脂肪酸(α-リノレン酸,EPA,DHA),n-6系脂肪酸(リノール酸,アラキドン酸)
2.1 はじめに
2.2 脂肪酸の吸収機構
2.3 リノール酸,α-リノレン酸の代謝と機能
2.4 アラキドン酸の代謝と機能
2.5 EPA・DHAの代謝と機能
2.6 n-3系,n-6系脂肪酸と保健機能食品
2.7 おわりに
3 グリセロリン脂質,グリセロ糖脂質,スフィンゴ脂質
3.1 グリセロリン脂質
3.2 グリセロ糖脂質
3.3 スフィンゴ脂質
4 油脂成分(植物ステロール・ステロールエステル)
4.1 植物ステロールとコレステロール-構造について-
4.2 植物ステロールの吸収
4.3 植物ステロールの食事コレステロールの吸収阻害
4.4 副作用
4.5 おわりに
5 γ-オリザノール
5.1 γ-オリザノールとは
5.2 γ-オリザノールの消化・吸収・代謝
5.3 HPLC-MS/MSによるγ-オリザノールの消化・吸収・代謝の評価
第5章 ビタミン様物質
1 コエンザイムQ10
1.1 はじめに
1.2 コエンザイムQ10の化学構造
1.3 コエンザイムQ10の生合成経路
1.4 コエンザイムQ10の吸収・代謝
2 PQQ
2.1 PQQとは(物質,分布,摂取,安全性)
2.2 吸収,代謝
2.3 機能
2.4 作用機序
2.5 まとめ
3 α-リポ酸
3.1 リポ酸とは
3.2 α-リポ酸の吸収性
3.3 α-リポ酸の抗糖尿作用,エネルギー産生作用,抗がん作用
3.4 おわりに
第6章 植物二次代謝成分
1 アントシアニン
1.1 はじめに
1.2 給源と摂取量,代謝・吸収
1.3 肥満・糖尿病予防・抑制作用の視点からのアントシアニンの機能と作用機序
1.4 アントシアニンの健康機能:代謝・吸収の知見も踏まえた課題,今後の展望
2 カロテノイド
2.1 カロテノイドとは
2.2 食品中のカロテノイド含有量
2.3 カロテノイドの消化/可溶化
2.4 カロテノイドの吸収選択性
2.5 カロテノイドの代謝(骨格の開裂)と機能性
2.6 カロテノイドの代謝(末端環の変換)と機能性
3 緑茶カテキン
3.1 はじめに
3.2 緑茶カテキン
3.3 緑茶カテキンの吸収と代謝
3.4 緑茶カテキンの生体調節作用とそのしくみ
3.5 緑茶カテキン代謝物の生体調節作用
3.6 食品因子による緑茶カテキンの活性調節
4 イソフラボンの吸収,代謝,作用機序
4.1 イソフラボン概要
4.2 食品中の大豆イソフラボン組成とその含量
4.3 イソフラボン配糖体とアグリコンの腸管における吸収
4.4 生体内における大豆イソフラボンの代謝
4.5 イソフラボンおよび代謝産物の機能性
5 ヘスペリジンおよびヘスペリジン誘導体
5.1 ヘスペリジンとは
5.2 ヘスペリジン誘導体の開発
5.3 ヘスペリジンの吸収と代謝
5.4 分散ヘスペレチンの血中動態
5.5 血中代謝物の構造
5.6 血流改善の作用機序
5.7 身体局部を冷却した冷え性改善試験
5.8 全身を緩慢に冷却した冷え性改善試験
5.9 まとめ
6 クロロゲン酸
6.1 はじめに
6.2 クロロゲン酸の吸収・代謝
6.3 クロロゲン酸の生理作用
6.4 おわりに
-

酵母菌・麹菌・乳酸菌の産業応用展開《普及版》
¥4,400
2018年刊「酵母菌・麹菌・乳酸菌の産業応用展開」の普及版!酵母菌・麹菌・乳酸菌について、機能性食品、化合物・タンパク質・ペプチドなどの有用物質生産、エネルギー生産、創薬、医療ほか多様な応用事例を解説した1冊。
(監修:五味勝也、阿部敬悦)
<a href="http://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=115631"target=”_blank”>この本の紙版「酵母菌・麹菌・乳酸菌の産業応用展開(普及版)」の販売ページはこちら(別サイトが開きます)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は、2018年当時のものを使用しております。
五味勝也 東北大学
阿部敬悦 東北大学
松鹿昭則 (国研)産業技術総合研究所
秦 洋二 月桂冠(株)
赤田倫治 山口大学
中村美紀子 山口大学
星田尚司 山口大学
松山 崇 (株)豊田中央研究所
戒能智宏 島根大学
川向 誠 島根大学
船戸耕一 広島大学
雜賀あずさ (国研)産業技術総合研究所
森田友岳 (国研)産業技術総合研究所
冨本和也 (独)酒類総合研究所
安部博子 (国研)産業技術総合研究所
久保佳蓮 東京大学
大矢禎一 東京大学
八代田陽子 (国研)理化学研究所
吉田 稔 (国研)理化学研究所
若林 興 日本盛(株)
井上豊久 日本盛(株)
磯谷敦子 (独)酒類総合研究所
藤井 力 (独)酒類総合研究所
田中瑞己 静岡県立大学
一瀬桜子 東北大学
五味勝也 東北大学
坊垣隆之 大関(株)
坪井宏和 大関(株)
幸田明生 大関(株)
黒田 学 天野エンザイム(株)
石垣佑記 天野エンザイム(株)
天野 仁 天野エンザイム(株)
丸山潤一 東京大学
堤 浩子 月桂冠(株)
福田克治 月桂冠(株)
尾関健二 金沢工業大学
加藤範久 広島大学
楊永寿 広島大学
Thanutchaporn Kumrungsee 広島大学
南 篤志 北海道大学
劉成偉 北海道大学
尾﨑太郎 北海道大学
及川英秋 北海道大学
吉見 啓 東北大学
宮澤 拳 東北大学
張斯来 東北大学(現 神戸大学)
田中拓未 東北大学
中島春紫 明治大学
塚原正俊 (株)バイオジェット
山田 修 (独)酒類総合研究所
仲原丈晴 キッコーマン(株)
内田理一郎 キッコーマン(株)
小川 順 京都大学
岸野重信 京都大学
米島靖記 日東薬品工業(株)
岡野憲司 大阪大学
田中 勉 神戸大学
本田孝祐 大阪大学
近藤昭彦 神戸大学
池田史織 九州大学
善藤威史 九州大学
園元謙二 九州大学
山崎(屋敷)思乃 関西大学
谷口茉莉亜 関西大学
片倉啓雄 関西大学
吉本 真 森永乳業(株)
武藤正達 森永乳業(株)
小田巻俊孝 森永乳業(株)
清水(肖)金忠 森永乳業(株)
伊澤直樹 (株)ヤクルト本社中央研究所
藤谷幹浩 旭川医科大学
伊藤尚文 熊本大学
太田訓正 熊本大学
山本直之 東京工業大学
-------------------------------------------------------------------------
<<目次>>
【第I編 酵母菌】
第1章 木質系バイオマスからの有用物質生産に向けた酵母の育種開発
1 はじめに
2 バイオマスの特徴と発酵生産における酵母の必要特性
3 酵母のキシロース発酵性
3.1 キシロース発酵性酵母の開発
3.2 キシロース発酵性酵母のオミックス解析
3.3 呼吸欠損株によるキシロース発酵
4 酵母の高温耐性
4.1 高温発酵の重要性
4.2 酵母の耐熱性機構の解析と耐熱性酵母の活用
4.3 耐熱性を示すキシロース発酵性酵母株の開発
5 おわりに
第2章 スーパー酵母・スーパー麹菌によるバイオリファイナリー技術
1 清酒醸造とバイオエタノール
2 清酒酵母と細胞表層工学
3 清酒酵母に麹菌の機能を付与させる
4 バイオマスからのエタノール発酵
5 安定な遺伝子発現するための新技術-HELOH法
6 スーパー麹菌によるバイオマスの直接分解
7 醸造技術をバイオ燃料生産へ
第3章 耐熱性酵母Kluyveromyces marxianusを用いた物質生産と育種技術
1 はじめに
2 耐熱性酵母Kluyveromyces marxianusの歴史
3 Kluyveromyces marxianusの耐熱性と糖資化性
4 Kluyveromyces marxianusのエタノール発酵
5 Kluyveromyces marxianusの遺伝学を確立するために
6 1倍体性酵母(haploid-prone yeast)と2倍体性酵母(diploid-prone yeast)
7 1倍体性ホモタリック酵母Kluyveromyces marxianusの交配育種
8 1倍体性酵母Kluyveromyces marxianusの栄養要求性変異株の取得
9 Kluyveromyces marxianusにおけるウラシル要求性変異株の取得
10 Kluyveromyces marxianusの遺伝子操作と非相同末端結合
11 Kluyveromyces marxianusをモデル酵母とする基礎研究
第4章 酵母による高活性ターミネーターを利用したタンパク質高生産
1 はじめに
2 ターミネーター活性の網羅的な評価と最高活性DIT1ターミネーターの発見
3 DIT1ターミネーターの作用原理の解明と目的タンパク質の高生産への応用
4 発現カセット・ライブラリを利用したコンビナトリアル・スクリーニング
5 おわりに
第5章 酵母によるコエンザイムQ10の生産
1 コエンザイムQ(CoQ)とは
2 酵母におけるCoQ研究?CoQ合成とイソプレノイド側鎖合成?
3 CoQ合成経路の上流の経路?メバロン酸経路?
4 CoQの高生産
5 酵母を用いたCoQ生産性の向上
6 CoQ10高生産に向けたアプローチ
第6章 酵母によるヒト型セラミドの高効率生産技術
1 はじめに
2 スフィンゴ脂質について
3 皮膚や毛髪におけるセラミドの役割について
4 組換え酵母によるセラミドNSの生産
5 代謝改変によるセラミドNS生産の向上
6 代謝の区画化によるセラミドNS生産の向上
7 おわりに
第7章 担子菌酵母によるバイオ化学品の生産
1 はじめに
2 担子菌酵母による物質生産
3 有機酸の生産
4 脂質の生産
5 糖脂質(バイオ界面活性剤)の生産
6 おわりに
第8章 バイオ医薬品生産に向けた出芽酵母の糖鎖構造改変
1 バイオ医薬品とその動向
2 バイオ医薬品と糖タンパク質糖鎖
3 バイオ医薬品生産プラットフォームとしての出芽酵母
4 出芽酵母のN-結合型糖鎖構造改変
5 出芽酵母のO-結合型糖鎖構造改変
6 出芽酵母によるバイオ医薬品生産の現状と今後の展望
第9章 新しい創薬ツールとしての出芽酵母
1 はじめに
2 化学遺伝学プロファイリング
3 形態プロファイリング
4 遺伝子発現プロファイリング
5 細胞壁をターゲットとした新しい抗真菌剤
6 おわりに
第10章 酵母ケミカルゲノミクスを用いた化合物作用機序解明のための大規模高速解析法
1 はじめに
2 合成致死性にもとづいたケミカルゲノミクス
3 ハプロ不全にもとづいたケミカルゲノミクス
4 遺伝子過剰発現による化合物の耐性化を利用したケミカルゲノミクス
5 おわりに
第11章 老香を発生させにくい清酒酵母の育種
1 はじめに
2 スクリーニング方法の検討
3 MTA非資化性変異株のスクリーニング
4 DMTS-P1 簡易生成試験
5 DMTS-P1 低生産株の原因遺伝子の調査
6 DMTS-P1 低生産株による小仕込試験
7 ホモ変異型2倍体の取得
8 ホモ変異型2倍体による小仕込試験
9 安定性試験
10 まとめ
【第II編 麹菌】
第1章 麹菌のカーボンカタボライト抑制関連因子の制御による酵素高生産
1 はじめに
2 CCR制御に関わる因子
3 糸状菌におけるCCRの制御機構
4 麹菌のCCR関連因子(CreA,CreB)の破壊によるアミラーゼの高生産
5 麹菌のcreAおよびcreB破壊によるバイオマス分解酵素の高生産
6 CreDの機能解析と変異導入による酵素高生産
7 まとめと今後の展望
第2章 麹菌によるタンパク質大量生産システムの開発
1 はじめに
2 麹菌タンパク質高発現システムの構築と改良
2.1 シス・エレメントRegionⅢの機能を利用したプロモーターの構築
2.2 5’UTRの改変による翻訳の効率化
2.3 高効率なターミネーターを用いた発現システムの改良
3 高発現システムを用いたタンパク質生産の実績
4 おわりに
第3章 麹菌酵素の生産と応用
1 麹菌酵素製剤の歴史
2 麹菌酵素製剤の製造
3 麹菌酵素の応用
3.1 ヘルスケア分野
3.1.1 日本国内での消化酵素製剤への利用
3.1.2 米国でのダイエタリーサプリメント利用
3.2 食品加工分野
3.2.1 糖質加工分野
3.2.2 タンパク質加工分野
3.2.3 その他分野
第4章 麹菌の有性世代の探索・不和合性の発見と交配育種への利用
1 はじめに
2 麹菌には2つの接合型MAT1-1型とMAT1-2型が存在する
3 麹菌の接合型遺伝子の機能解析
4 麹菌の細胞融合能の再発見
5 麹菌における不和合性の発見
6 麹菌における有性生殖の発見の試み
7 おわりに
第5章 麹菌Aspergillus oryzaeが産生する環状ペプチド,フェリクリシン,デフェリフェリクリシン
1 フェリクリシン(Fcy)
1.1 貧血改善効果
1.2 Fcyの溶解特性
2 デフェリフェリクリシン(Dfcy)
2.1 抗酸化活性
2.2 メラニン抑制効果
2.3 炎症抑制効果
第6章 α-エチル-D-グルコシドの発酵生産法の開発と新規機能性を利用した各種商品への応用
1 はじめに
2 焼酎醸造でのα-EG生産
3 酒粕再発酵でのα-EG生産
3.1 高生産発酵法
3.2 蒸留残渣の用途開発
4 日本酒醸造でのα-EG生産
4.1 酒母仕込の純米酒
4.2 純米吟醸酒
5 ヒトパッチ試験によるα-EGの評価
5.1 有効濃度と時間
5.2 浴用酒としての用途開発
6 ヒト成人線維芽細胞によるα-EGの評価
6.1 有効濃度
6.2 クロロゲン酸との比較
7 まとめと今後の展開
第7章 麹菌由来酸性プロテアーゼによる腸内善玉菌増加作用
1 はじめに
2 麹菌発酵ごぼうの機能性
3 麹菌由来プロテアーゼ剤の機能性
4 米麹菌由来酸性プロテアーゼの善玉菌増加作用の発見
5 おわりに
第8章 麹菌を宿主としたカビの二次代謝産物の生産
1 はじめに
2 麹菌異種発現系を用いた天然物の異種生産
2.1 生合成マシナリーの再構築による天然物の異種生産
2.2 麹菌異種発現系の特徴
2.2.1 標的遺伝子に含まれるイントロンの除去が不要
2.2.2 補助酵素の共発現が不要
2.2.3 毒性物質に対する自己耐性能
2.2.4 課題
3 麹菌異種発現系の応用例
4 まとめ
第9章 麹菌の細胞壁α-1,3グルカン欠損株による高密度培養と物質高生産への利用
1 糸状菌の細胞壁構築シグナル伝達機構解析
2 糸状菌における細胞壁多糖AGの生物学的機能
3 AG欠損株の高密度培養への応用
4 麹菌における第二の菌糸接着因子の発見
第10章 麹菌由来界面活性タンパク質(ハイドロフォービン)の特性とその応用技術
1 ハイドロフォービンの生態
2 ハイドロフォービンの構造と重合性
3 ハイドロフォービンの物理的性質
4 ハイドロフォービンと酵素タンパク質の相互作用
5 ハイドロフォービンの産業応用
第11章 黒麹菌のゲノム解析とその産業応用
1 黒麹菌のゲノム解析の意義
2 黒麹菌の歴史
3 黒麹菌のゲノム解析による再分類
4 黒?菌A. luchuensis NBRC 4314株の全ゲノム解析
5 全ゲノム情報によるA. luchuensisの種内系統解析
6 A. luchuensisのルーツは沖縄県
7 黒麹菌のゲノム解析によるさらなる産業振興
第12章 麹菌酵素活性の制御による機能性ペプチド高含有醤油の開発
1 はじめに
2 醤油中のペプチドを増加させる試み
3 諸味中のペプチダーゼ活性の抑制方法
4 大豆発酵調味液からのACE阻害ペプチドの単離同定と定量
5 血圧が高めのヒトを対象とした連続摂取試験
6 特定保健用食品(トクホ)としての実用化と機能性表示食品への展開
【第III編 乳酸菌】
第1章 乳酸菌の脂肪酸変換機能とその産業利用
1 はじめに
2 乳酸菌に見出された不飽和脂肪酸飽和化代謝
3 乳酸菌の脂肪酸変換活性を活用した脂肪酸誘導体の生産
3.1 共役脂肪酸生産
3.1.1 リノール酸の異性化による共役リノール酸(CLA)生産
3.1.2 リシノール酸の脱水による共役リノール酸(CLA)生産
3.1.3 乳酸菌による種々の共役脂肪酸の生産
3.2 水酸化脂肪酸,オキソ脂肪酸などの不飽和脂肪酸飽和化代謝産物の生産
4 水酸化脂肪酸にみる乳酸菌脂質変換物の実用化開発
4.1 HYAの生物ならびに食品における存在
4.2 HYAの生理機能
4.3 HYAの実用化検討
5 おわりに
第2章 乳酸菌の遺伝子操作技術の進展
1 はじめに
2 プラスミドの発見とその利用
3 従来の遺伝子破壊/置換技術
4 最新の遺伝子破壊/置換技術
4.1 λ Red相同組換え法の応用
4.2 CRISPR-Cas9システムを用いたゲノム編集
第3章 乳酸菌由来抗菌性ペプチド、バクテリオシンの機能と応用
1 はじめに
2 乳酸菌バクテリオシンの多様性
3 乳酸菌バクテリオシンの生合成と作用機構
4 ナイシンの利用
4.1 食品保存への応用
4.2 非食品用途への応用
4.2.1 手指用殺菌洗浄剤
4.2.2 乳房炎予防剤・治療剤
4.2.3 口腔ケア剤
5 新しい乳酸菌バクテリオシンの利用と展望
6 おわりに
第4章 乳酸菌と酵母との相互作用,および乳酸菌の炭水化物への接着現象の解析とプロバイオティクスへの応用
1 はじめに
2 発酵食品における乳酸菌と酵母の関与
3 乳酸菌と酵母の共生系を利用した物質生産
4 乳酸菌と酵母の接着の機構
5 乳酸菌と酵母の接着による応答
6 乳酸菌と酵母との接着の意義
7 乳酸菌の炭水化物への接着とプロバイオティクスとしての応用
8 おわりに
第5章 ビフィズス菌・乳酸菌のプロバイオティクス機能と製品開発
1 プロバイオティクスとは
2 プロバイオティクスの生理作用
2.1 プロバイオティクスの抗アレルギー作用
2.2 プロバイオティクスの抗肥満作用
2.3 プロバイオティクスによる抗がん作用
2.4 プロバイオティクスによる脳機能改善
3 プロバイオティクスとしてのビフィズス菌・乳酸菌の製品開発
3.1 ヨーグルト製品開発
3.2 菌末製造開発
3.3 ビフィズス菌の生菌数測定法
4 おわりに
第6章 乳酸菌・ビフィズス菌発酵を利用した基礎化粧品素材の開発
1 はじめに
2 皮膚と乳酸菌発酵液
3 乳酸菌・ビフィズス菌発酵を利用した化粧品素材
3.1 脱脂粉乳の乳酸菌発酵液
3.2 乳酸桿菌/アロエベラ発酵液
3.3 大豆ビフィズス菌発酵液
3.4 ヒアルロン酸
4 効果測定
5 安全性
6 おわりに
第7章 乳酸菌由来活性物質を用いた新規治療薬の開発
1 乳酸菌由来の腸管保護活性物質
1.1 菌培養上清からの腸管保護活性物質の同定
1.2 乳酸菌由来長鎖ポリリン酸の作用機序
1.2.1 腸管バリア機能の増強作用
1.2.2 腸炎モデルへの治療効果
2 乳酸菌由来の抗腫瘍活性物質
2.1 菌培養上清からの抗腫瘍活性物質の同定
2.2 腫瘍モデルに対する治療効果
第8章 乳酸菌による細胞のリプログラミング
1 はじめに
2 多能性幹細胞について
3 細菌感染による細胞変性
4 乳酸菌による細胞形質の転換
5 細菌による細胞リプログラミングの応用可能性
第9章 アレルギー改善乳酸菌の開発
1 はじめに
2 アレルギーリスクの抑制への課題
3 アレルギーリスク低減乳酸菌の選択
4 ヒトに対する有効性の確認
5 作用メカニズム
6 おわりに
-

中分子創薬に資するペプチド・核酸・糖鎖の合成技術《普及版》
¥5,280
2018年刊「中分子創薬に資するペプチド・核酸・糖鎖の合成技術」の普及版!中分子医薬開発において重要な「ペプチド」「核酸」「糖鎖」のそれぞれについて、合成法・高機能化技術を解説した1冊。
(監修:千葉一裕)
<a href="http://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=115632"target=”_blank”>この本の紙版「中分子創薬に資するペプチド・核酸・糖鎖の合成技術(普及版)」の販売ページはこちら(別サイトが開きます)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は、2018年当時のものを使用しております。
千葉一裕 東京農工大学
荒戸照世 北海道大学病院
吉矢 拓 (株)ペプチド研究所
木曽良明 長浜バイオ大学
北條裕信 大阪大学
川上 徹 大阪大学
小早川拓也 東京医科歯科大学
玉村啓和 東京医科歯科大学
布施新一郎 東京工業大学
北條恵子 神戸学院大学
木野邦器 早稲田大学
相沢智康 北海道大学
木村寛之 東京大学
加藤敬行 東京大学
菅 裕明 東京大学
岡田洋平 東京農工大学
JITSUBO(株)
高橋大輔 味の素(株)
関根光雄 (株)環境レジリエンス;東京工業大学
佐々木茂貴 九州大学
額賀陽平 東京理科大学
和田 猛 東京理科大学
萩原健太 群馬大学
尾崎広明 群馬大学
桒原正靖 群馬大学
藤本健造 北陸先端科学技術大学院大学
中村重孝 北陸先端科学技術大学院大学
木村康明 名古屋大学
阿部 洋 名古屋大学
若松秀章 東北医科薬科大学
名取良浩 東北医科薬科大学
斎藤有香子 東北医科薬科大学
吉村祐一 東北医科薬科大学
山吉麻子 京都大学
新貝恭広 近畿大学大学院
藤井政幸 近畿大学
清尾康志 東京工業大学
大窪章寛 東京工業大学
石田秀治 岐阜大学
佐野加苗 群馬大学
松尾一郎 群馬大学
佐藤智典 慶應義塾大学
上田善弘 京都大学
川端猛夫 京都大学
田中浩士 東京工業大学
稲津敏行 東海大学
長島 生 (国研)産業技術総合研究所
清水弘樹 (国研)産業技術総合研究所
野上敏材 鳥取大学
伊藤敏幸 鳥取大学
田中知成 京都工芸繊維大学
加藤紀彦 京都大学
山本憲二 石川県立大学
千葉靖典 (国研)産業技術総合研究所
-------------------------------------------------------------------------
<<目次>>
【第I編 総論】
第1章 中分子医薬品の開発・規制動向
1 核酸医薬品の規制の動向と現状
1.1 はじめに
1.2 国内外における核酸医薬品の規制に係わる動き
1.3 核酸医薬品の品質管理の考え方
1.4 核酸医薬品の非臨床安全性評価の考え方
1.5 まとめ
2 ペプチド医薬品の規制の動向と現状
2.1 はじめに
2.2 ペプチド医薬品の品質管理の考え方
2.3 ペプチド医薬品の非臨床安全性評価の考え方
2.4 まとめ
【第II編 ペプチド】
第1章 ペプチド合成法の開発動向と展望
第2章 ペプチドチオエステルの合成とタンパク質合成への利用
1 ペプチドチオエステルとタンパク質合成
2 t-Butoxycarbonyl(Boc)法によるペプチドチオエステルの合成
3 9-fluorenylmethoxycarbonyl(Fmoc)法によるペプチドチオエステルの調製
3.1 N-アルキルシステイン(NAC)をN-Sアシル転位素子として用いるチオエステル調製法
3.2 NAC構造の最適化によるチオエステル化効率の向上
3.3 システイニルプロリルエステル(CPE)をチオエステル前駆体として用いる方法
4 ペプチドチオエステルのタンパク質合成への応用
4.1 ワンポット合成法によるTIM-3 Igドメインの合成
4.2 ワンポット法によるヒトsuperoxide dismutaseの合成
5 おわりに
第3章 ペプチドミメティック(ジペプチドイソスター)の合成と応用
1 はじめに―ペプチドミメティック―
2 これまでのペプチドミメティック
2.1 遷移状態模倣型ミメティック
2.2 基底状態模倣型ミメティック
3 クロロアルケン型ジペプチドイソスター(CADI)
3.1 CADIの分子設計
3.2 クロロアルケン骨格の構築法
3.3 CADIの立体選択的合成法とペプチド合成への適用化
3.4 CADIの応用展開―RGDペプチドへの適用を例に―
4 まとめと展望
第4章 マイクロフロー法によるペプチド合成
第5章 マイクロ波を用いる水中ペプチド固相合成法
1 はじめに
2 水分散型保護アミノ酸ナノ粒子を用いる水中ペプチド固相合成
3 マイクロ波水中迅速ペプチド固相合成法の開発
3.1 マイクロ波照射による水中固相合成迅速化
3.2 マイクロ波水中固相合成による合成困難配列ペプチドの合成
4 マイクロ波照射下水中反応におけるラセミ化の検証
4.1 マイクロ波照射下Cys残基のラセミ化とCys含有ペプチドの水中合成
4.2 マイクロ波照射下His残基のラセミ化とHis含有ペプチドの水中合成
5 おわりに
第6章 ペプチド合成酵素を利用した触媒的アミド合成
1 はじめに
2 アミノ酸リガーゼ(ATP-grasp-ligase)によるペプチド合成
2.1 アミノ酸リガーゼの探索とジペプチド合成
2.2 オリゴペプチド合成
2.3 ポリアミノ酸合成
3 アデニル化酵素(acyl-AMP-ligase)によるアミド結合形成
3.1 アデニル化ドメインによるペプチド合成
3.2 脂肪酸アミド合成
3.3 芳香族カルボン酸アミド合成
4 アシルCoA合成酵素によるアミド結合形成
5 おわりに
第7章 ペプチドの遺伝子組換え微生物を用いた高効率生産技術
1 はじめに
2 大腸菌を宿主とした組換えペプチドの生産
2.1 可溶型でのペプチドの生産
2.2 不溶型でのペプチドの生産
3 酵母を宿主とした組換えペプチドの生産
4 組換えペプチドのNMR解析への応用
5 おわりに
第8章 遺伝暗号リプログラミングを用いた特殊ペプチド翻訳合成と高速探索技術
1 はじめに
2 FITシステム
3 特殊環状ペプチドスクリーニング技術「RaPIDシステム」
4 RaPIDシステムによる特殊ペプチド探索の事例
4.1 KDM4阻害ペプチドの探索
4.2 iPGM阻害ペプチドの探索
4.3 METに対する人工アゴニストペプチドの探索
4.4 多剤輸送体MATE阻害ペプチドによる結晶構造解析
5 FITシステム,RaPIDシステムの今後の展望
第9章 高効率ペプチド製造技術Molecular HivingTM
第10章 AJIPHASE(R);ペプチドやオリゴ核酸の効率的大量合成法
1 はじめに
2 AJIPHASE(R)法によるペプチド合成
3 超効率的ペプチド合成法 第三世代AJIPHASE(R)
4 AJIPHASE(R)によるオリゴ核酸合成
5 AJIPHASE(R)によるオリゴ核酸の大量製造
6 おわりに
【第III編 核酸】
第1章 核酸合成法の開発動向と展望
1 はじめに
2 核酸合成関連の副反応
2.1 固相合成におけるキャップ化反応の副反応
2.2 UnyLinker合成時の副反応
2.3 ホスファイト中間体の硫化反応
3 大量合成を指向した研究
4 核酸合成の保護基の開発動向
4.1 リン酸基の保護基
4.2 5'-水酸基の保護基
5 RNA合成における最近の動向
5.1 TBDMS基の2'-水酸基への導入法の改良
5.2 O,O-およびO,S-アセタールを介した保護基の開発
5.3 2'-O-修飾RNAの合成
6 おわりに
第2章 インテリジェント人工核酸―クロスリンク核酸・官能基転移核酸の合成―
1 はじめに
2 クロスリンク核酸
3 クロスリンク剤(T-ビニル)の合成
4 RNA標的クロスリンク反応
5 RNAの部位および塩基選択的化学修飾
6 官能基転移核酸の創成
7 今後の展望
第3章 リン原子修飾核酸医薬の立体制御
1 はじめに
2 オキサザホスホリジン法によるホスホロチオエートDNAの立体選択的合成
3 オキサザホスホリジン法によるホスホロチオエートRNAの立体選択的合成
4 オキサザホスホリジン法によるボラノホスフェートDNAの立体選択的合成
5 オキサザホスホリジン法によるボラノホスフェートRNAの立体選択的合成
6 今後の展望
第4章 ゼノ核酸アプタマーの開発
1 はじめに
2 ライブラリの構築
3 RNAアプタマー
3.1 RNAアプタマー
3.2 修飾RNAアプタマー
4 DNAアプタマー
4.1 DNAアプタマー
4.2 修飾DNAアプタマー
5 核酸アプタマーの応用
5.1 バイオセンサ
5.2 医薬品
6 総括
第5章 光架橋性人工核酸の合成と応用
1 はじめに
2 光クロスリンク法
3 光ライゲーション法
4 まとめ
第6章 機能性核酸合成を指向した化学的核酸連結反応
1 求電子性ホスホロチオエステル基を用いた連結反応の開発
2 細胞内での化学的連結反応によるsiRNA分子の構築
第7章 新規グリコシル化反応の開発―Pummerer型チオグリコシル化反応の開発と展開―
1 はじめに
2 Pummerer型チオグリコシル化反応の開発と2’-置換4’-チオヌクレオシドの合成
3 4’-チオリボヌクレオシドの合成
4 チオピラノースを用いたPummerer型チオグリコシル化反応
5 超原子価ヨウ素を用いたグリコシル化反応の開発と展開
6 おわりに
第8章 siRNA,miRNA-mimicおよびanti-miR核酸の設計指針
1 siRNAの設計法
1.1 siRNAの作用機序
1.2 siRNAの配列選択法
1.3 siRNAの化学修飾法
2 miRNA-mimicの設計法
2.1 miRNAの作用機序
2.2 miRNA-mimicの配列選択法
2.3 miRNA-mimicの化学修飾法
3 anti-miR核酸の設計法
3.1 anti-miR核酸の作用機序
3.2 anti-miR核酸の配列選択法
3.3 anti-miR核酸の化学修飾法
第9章 核酸コンジュゲートの合成
1 液相合成法
1.1 クリック反応
1.2 二価性リンカーを用いるフラグメント縮合法
1.3 ネイティブライゲーション法
1.4 オキシム,ヒドラゾン形成反応
2 固相合成法
2.1 ホスホアミダイト法
2.2 タンデム合成法
2.3 フラグメントカップリング法
第10章 塩基部無保護ホスホロアミダイト法による核酸合成
1 塩基部無保護核酸合成法の有用性
2 塩基部無保護ホスホロアミダイト法の概略
3 STEP 1:5’-O-選択的カップリング
3.1 塩基部無保護ホスホロアミダイト試薬(2)の合成
3.2 アルコール型活性化剤による5’-O-選択的カップリング反応
4 STEP 2:P-N結合切断反応
5 STEP 5:脱CE反応とSTEP 6:切り出し反応
6 塩基部無保護ホスホロアミダイト法による核酸合成例
7 終わりに
【第IV編 糖鎖】
第1章 総論:糖鎖合成法の開発動向と展望
第2章 酵素化学法による糖鎖合成
1 糖鎖の合成
2 糖転移酵素を利用した酵素-化学法による糖鎖合成
3 糖加水分解酵素によるオリゴ糖合成
4 糖加水分解酵素を積極的に利用した酵素-化学法による高マンノース型糖鎖の合成
4.1 分岐構造を有する高マンノース型糖鎖8糖の合成
4.2 糖加水分解酵素の限定分解反応によるトップダウン型高マンノース型糖鎖ライブラリ構築
4.3 改変型エンドα-マンノシダーゼを用いた高マンノース型糖鎖の合成
第3章 糖鎖プライマー法によるバイオコンビナトリアル合成
1 はじめに
2 糖鎖プライマー法とは
3 糖鎖プライマーによる細胞での糖鎖伸長
4 グライコミクスへの活用
5 糖鎖ライブラリーとしての活用
6 おわりに
第4章 触媒的位置選択的アシル化
1 はじめに
2 汎用型触媒による無保護グルコピラノシドのアシル化
3 グルコピラノシドの位置選択的アシル化の先駆的研究
4 グルコピラノシドの4位高選択的アシル化
5 触媒量の低減化
6 アシル化配糖体の位置選択的全合成
7 ポリオール系天然物の位置選択的誘導化
8 さいごに
第5章 α(2,8)シアリル化反応の発展と高分子型Siglec-7リガンドの開発
1 はじめに
2 α(2,8)シアリル化の課題と克服
3 糖鎖高分子型のSiglec-7リガンド
4 まとめ
第6章 フルオラス合成
1 はじめに
2 フルオラス化学とは
3 アシル型フルオラス保護基を用いたフルオラス糖鎖合成
4 アシル型フルオラス担体の開発と糖鎖合成への応用
5 ベンジル型フルオラス担体の開発と糖鎖合成への応用
6 おわりに
第7章 マイクロ波を利用した糖鎖・糖ペプチド精密合成
1 マイクロ波の化学反応への利用
2 糖鎖合成
3 糖ペプチド合成
4 結語
第8章 液相電解自動合成法によるオリゴ糖合成
1 はじめに
2 オリゴ糖自動合成法の原理
3 液相電解自動合成法によるオリゴ糖合成
4 生物活性オリゴ糖合成への展開
5 まとめ
第9章 無保護糖アノマー位の直接活性化を基盤とする糖鎖高分子の保護基フリー合成
1 はじめに
2 無保護糖アノマー位の直接活性化
3 糖鎖高分子の保護基フリー合成
3.1 グリコシルアジドを経由する糖鎖高分子の合成
3.2 チオグリコシドを経由する糖鎖高分子の合成
4 糖鎖高分子の機能評価
4.1 金表面への固定化とレクチンとの結合評価
4.2 インフルエンザウイルスとの結合評価
5 おわりに
第10章 Endo-M酵素による糖鎖付加と均一化
1 はじめに
2 エンドグリコシダーゼの糖転移反応
3 Endo-Mの糖転移活性とグリコシンターゼ化
4 グリコシンターゼを利用したシアロ糖ペプチドの合成
5 グリコシンターゼによる糖タンパク質糖鎖の均一化
6 その他の改変エンドグリコシダーゼによる糖転移反応
7 コアフコース含有糖鎖に作用するEndo-Mの作出
8 おわりに
第11章 酵母細胞および酵素法を組み合わせた糖タンパク質合成
1 はじめに
2 酵母を利用したヒト型糖タンパク質生産
3 トランスグリコシレーションによる糖タンパク質糖鎖の均一化
4 糖転移酵素による糖鎖修飾
5 まとめ
-

二酸化炭素・水素分離膜の開発と応用《普及版》
¥4,840
2018年刊「二酸化炭素・水素分離膜の開発と応用」の普及版!低炭素化社会、水素社会実現に向けて必須のキーテクノロジーである二酸化炭素・水素の分離膜、分離プロセス、膜反応器について体系的にまとめた1冊。
(監修:中尾真一、喜多英敏)
<a href="http://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=115633"target=”_blank”>この本の紙版「二酸化炭素・水素分離膜の開発と応用(普及版)」の販売ページはこちら(別サイトが開きます)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は、2018年当時のものを使用しております。
中尾真一 工学院大学
喜多英敏 山口大学
田中一宏 山口大学
川上浩良 首都大学東京
田中俊輔 関西大学
長澤寛規 広島大学
金指正言 広島大学
都留稔了 広島大学
甲斐照彦 地球環境産業技術研究機構
神尾英治 神戸大学
松山秀人 神戸大学
上宮成之 岐阜大学
原 重樹 産業技術総合研究所
熊切 泉 山口大学
谷原 望 宇部興産(株)
須川浩充 ダイセル・エボニック(株)
森里 敦 Cameron, A Schlumberger Company
岡田 治 (株)ルネッサンス・エナジー・リサーチ
武脇隆彦 三菱ケミカル(株)
矢野和宏 日立造船(株)
余語克則 地球環境産業技術研究機構;奈良先端科学技術大学院大学
藤村 靖 日揮(株)
甲斐慎二 田中貴金属工業(株)
吉宗美紀 産業技術総合研究所
原谷賢治 産業技術総合研究所
山本浩和 NOK(株)
川瀬広樹 日本特殊陶業(株)
高木保宏 日本特殊陶業(株)
伊藤正也 日本特殊陶業(株)
井上隆治 日本特殊陶業(株)
西田亮一 地球環境産業技術研究機構
伊藤直次 宇都宮大学
古澤 毅 宇都宮大学
-------------------------------------------------------------------------
<<目次>>
【第I編 二酸化炭素・水素分離膜の開発と応用】
第1章 二酸化炭素・水素分離膜総論
1 はじめに
2 膜による気体分離
3 高分子膜
4 無機膜
5 おわりに
第2章 二酸化炭素分離膜
1 高分子膜
1.1 セルロース膜
1.2 ポリスルホン膜
1.3 ポリイミド膜
1.4 Thermally Rearranged(TR)Polymer膜
1.5 Polymer of Intrinsic Microporosity(PIM)膜
1.6 Mixed-Matrix Membrane(MMM)
2 無機膜
2.1 ゼオライト
2.1.1 はじめに
2.1.2 ゼオライト膜の製膜
2.1.3 CO2分離性能
2.1.4 おわりに
2.2 多孔性金属錯体(MOF)の分離膜への展開
2.2.1 はじめに
2.2.2 MOFの特性
2.2.3 MOFの製膜
2.2.4 おわりに
2.3 炭素膜
2.3.1 はじめに
2.3.2 炭素膜の製膜
2.3.3 CO2分離性能
2.3.4 おわりに
2.4 シリカ系多孔膜によるCO2分離
2.4.1 はじめに
2.4.2 アモルファスシリカ膜
2.4.3 ゾル-ゲル法によるシリカ系多孔膜の細孔径制御とCO2分離性能
2.4.4 親和性付与によるCO2分離性能の向上:アミノシリカ膜
2.4.5 大気圧プラズマCVDシリカ膜
2.4.6 おわりに
2.5 その他の無機膜
2.5.1 はじめに
2.5.2 多孔質ガラス膜
2.5.3 Dual-Phase膜
3 促進輸送膜
3.1 はじめに
3.2 促進輸送膜の研究開発動向
3.3 おわりに
4 イオン液体膜
4.1 イオン液体膜のCO2選択透過性能
4.2 イオン液体の設計
4.3 イオン液体膜の構造設計
第3章 水素分離膜
1 高分子膜
1.1 ポリイミド膜
1.2 その他の高分子膜
1.2.1 はじめに
1.2.2 高分子の1次構造と気体の透過選択性との関係
1.2.3 水素分離膜
1.2.4 おわりに
2 無機膜
2.1 シリカ膜
2.1.1 ゾル-ゲル法によるシリカ系膜の水素透過特性
2.1.2 CVD膜
2.2 金属
2.2.1 パラジウム膜
2.2.2 非パラジウム系金属膜
2.3 炭素膜
2.3.1 はじめに
2.3.2 炭素膜の構造
2.3.3 水素分離
2.3.4 おわりに
2.4 ゼオライト膜
2.4.1 はじめに
2.4.2 ゼオライト細孔構造と,ゼオライト膜による水素選択性の発現
2.4.3 水素分離用のゼオライト膜合成への異なるアプローチ
2.4.4 ゼオライト膜の水素透過性
2.4.5 膜構造の影響
2.4.6 共存する分子の吸着阻害
2.4.7 おわりに
【第II編 二酸化炭素・水素分離膜の実用プロセス】
第1章 二酸化炭素分離膜の実用プロセス
1 ポリイミド膜を用いるプロセス
1.1 BPDA系ポリイミド中空糸膜による二酸化炭素分離
1.1.1 はじめに
1.1.2 ポリイミド中空糸膜および膜モジュール
1.1.3 二酸化炭素分離
1.1.4 おわりに
1.2 エボニック製ガス分離膜「SEPURAN(R)」を用いた効率的なバイオガス精製技術および他の展開事例について
1.2.1 バイオガスの分離
1.2.2 稀有ガスの分離
2 酢酸セルロース膜を用いるプロセス―CO2原油強制回収施設における膜分離法によるCO2分離技術
2.1 はじめに
2.2 高分子膜による天然ガスCO2分離の歴史
2.3 天然ガス精製プラントにおけるCO2膜分離プロセス
2.3.1 前処理(Pre-Treatment)
2.3.2 SACROC EOR CO2膜分離プラント
2.3.3 Denbury CO2膜分離プラント
2.3.4 浮体式生産貯蔵積出設備(Floating Production, Storage and Offloading:FPSO)におけるCO2膜分離
3 CO2選択透過膜(促進輸送膜)の各種CO2脱分離・回収プロセスへの応用
3.1 水素製造プロセスへの応用
3.1.1 CO2選択透過膜(促進輸送膜)の原理と水素製造プロセスへの適用効果
3.1.2 CO2選択透過膜の開発
3.2 おわりに
4 CO2分離・回収(Pre-combustion)のための分子ゲート膜モジュールの開発
4.1 はじめに
4.2 分子ゲート膜
4.3 次世代型膜モジュール技術研究組合による分子ゲート膜モジュールの開発
4.4 おわりに
5 ゼオライト膜を用いるプロセス
5.1 ゼオライト膜による二酸化炭素分離
5.1.1 高シリカCHA型ゼオライト膜の特徴と浸透気化特性
5.1.2 高シリカCHA型ゼオライト膜のCO2分離特性
5.2 オールセラミック型膜エレメントによるゼオライト分離膜のガス分離応用
5.2.1 緒言
5.2.2 オールセラミック型膜エレメント
5.2.3 ガス分離プロセスに向けた適用
5.2.4 結言
5.3 CO2分離回収コストの大幅低減を実現可能な革新的ピュアシリカゼオライト膜の開発
5.3.1 はじめに
5.3.2 CO2分離材料としてのピュアシリカゼオライト
5.3.3 ピュアシリカCHA型ゼオライト膜の開発とCO2分離性能
5.3.4 実用化のイメージ・インパクト
5.4 DDR型ゼオライト膜を用いた天然ガス精製プロセス
5.4.1 DDR型ゼオライト膜の構造と特徴
5.4.2 大面積分離膜エレメントの製造とプロセス化
5.4.3 DDR型ゼオライト膜の天然ガス精製プロセスへの適用
5.4.4 DDR型ゼオライト膜の天然ガス精製プロセスへの適用検討例
5.4.5 DDR型ゼオライト膜分離プロセスの開発状況
第2章 水素分離膜の実用プロセス
1 水素分離プロセスにおけるパラジウム基水素分離膜
1.1 はじめに
1.2 パラジウム基水素分離膜を用いた水素高純度化技術
1.3 水素分離膜に使用されるパラジウム基合金
1.4 実用プロセスへの応用
1.5 まとめ
2 ゼオライト膜を用いるプロセス
2.1 はじめに
2.2 水素精製システムへのゼオライト膜の適用
2.3 ピュアシリカゼオライト膜による水素精製
2.4 まとめと今後の展望
3 水素精製用カーボン膜モジュールとその応用プロセス
3.1 はじめに
3.2 有機ハイドライド型水素ステーション構想
3.3 中空糸カーボン膜の開発
3.4 カーボン膜モジュールの製造検討概要
3.5 モジュール性能評価
3.6 プロセス設計検討
3.7 おわりに
【第III編 二酸化炭素・水素分離膜を用いる膜反応器】
第1章 膜反応器総論
1 はじめに
2 膜反応器の機能による分類
3 膜反応器で用いられる分離膜
4 膜反応器の分類
5 膜反応器システムの構築
6 膜反応器の産業応用
7 おわりに
第2章 二酸化炭素透過膜を用いる膜反応器
1 はじめに
2 炭化水素を原料とした水素製造への膜反応器の適用
3 水素選択透過膜,または,二酸化炭素選択透過膜を適用したプロセスの違い
4 水性ガスシフト反応への二酸化炭素分離技術の適用
5 高温二酸化炭素分離技術の適用
6 おわりに
第3章 水素透過膜を用いる膜反応器
1 メタン水蒸気改質膜反応器
1.1 多孔質膜
1.1.1 はじめに
1.1.2 シリカ膜の耐水蒸気性および水素選択性の向上
1.1.3 触媒膜の開発と膜反応器への応用
1.1.4 まとめ
1.2 触媒一体化モジュール
1.2.1 はじめに
1.2.2 開発背景
1.2.3 MOCの構造・動作原理
1.2.4 MOCの耐久性
1.2.5 MOCの耐久性を支える3つの対策
1.2.6 さらなる耐久性の向上のために
1.2.7 おわりに
2 MCH脱水素膜反応器
2.1 はじめに
2.2 水素社会構築とエネルギーキャリアとしてのメチルシクロヘキサン(MCH)
2.3 MCH脱水素用膜反応器の開発
2.3.1 水素分離膜の長尺化
2.3.2 脱水素プロセスの低コスト化
2.3.3 その他課題への対応
2.4 おわりに
3 アンモニア分解-脱水素膜反応器
3.1 水素貯蔵輸送材料としてのアンモニア
3.2 アンモニア分解による水素製造の課題
3.3 低温分解に活性な触媒の探索
3.3.1 アンモニア分解触媒の現状
3.3.2 低温活性触媒の調製
3.4 低温下で耐久性のあるパラジウム複合膜の開発
3.4.1 Pd/Pt/Al2O3複合膜
3.4.2 Pd/Ti/Al2O3複合膜試験
3.5 膜反応器によるアンモニア分解の促進
3.5.1 CVD法による管状パラジウム膜の作製
3.5.2 メンブレンリアクターによるアンモニア分解
4 シリカ膜を用いる硫化水素の熱分解膜反応器
4.1 水素化脱硫と硫化水素の熱分解反応
4.2 シリカ膜の製膜と膜反応器
4.3 膜反応器の性能
-

AI導入によるバイオテクノロジーの発展《普及版》
¥3,960
2018年刊「AI導入によるバイオテクノロジーの発展」の普及版。AIのバイオテクノロジーへの応用について、機械学習や深層学習の解説から医療・創薬・ヘルスケア・ものづくりへの展開まで、様々な切り口からまとめた1冊。
(監修:植田充美)
<a href="http://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=115626"target=”_blank”>この本の紙版「AI導入によるバイオテクノロジーの発展(普及版)」の販売ページはこちら(別サイトが開きます)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は、2018年当時のものを使用しております。
植田充美 京都大学
北野宏明 特定非営利活動法人システム・バイオロジー研究機構
馬見塚拓 京都大学
花井泰三 九州大学
山本泰智 大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構
藤田広志 岐阜大学
桜田一洋 (国研)理化学研究所
城戸 隆 ㈱Preferred Networks
三浦夏子 京都大学
田中 博 東京医科歯科大学;東北大学
徳久淳師 (国研)理化学研究所
種石 慶 (国研)理化学研究所
奥野恭史 京都大学
富井健太郎 (国研)産業技術総合研究所
関嶋政和 東京工業大学
澤 芳樹 大阪大学
徳増有治 大阪大学
三宅 淳 大阪大学
田川聖一 大阪大学
新岡宏彦 大阪大学
山本修也 大阪大学
大東寛典 大阪大学
浅谷学嗣 大阪大学
孫光鎬 電気通信大学
加藤竜司 名古屋大学
松田史生 大阪大学
油屋駿介 京都大学
青木裕一 東北大学
細川正人 早稲田大学
竹山春子 早稲田大学
五條堀孝 アブドラ国王科学技術大学
山本佳宏 (地独)京都市産業技術研究所
青木 航 京都大学
本田直樹 京都大学
高野敏行 京都工芸繊維大学
飯間 等 京都工芸繊維大学
寶珍輝尚 京都工芸繊維大学
-------------------------------------------------------------------------
<<目次>>
第1章 AIと生命科学
1 人工知能駆動生命科学の始まりからノーベル・チューリング・チャレンジまで
1.1 生命科学と人間の認知限界
1.2 ノーベル・チューリング・チャレンジ
1.3 科学的発見のエンジンを作る
1.4 プラットフォームの構築
1.5 科学的発見のもたらす革命:人類の能力の拡張と能力のコモディティー化
2 機械学習・データマイニングの生命科学への応用
2.1 はじめに
2.2 行列の学習
2.2.1 教師なし学習(クラスタリング)
2.2.2 教師あり学習(分類・回帰)
2.2.3 特徴量選択
2.3 バスケットデータ,文字列,時系列データの学習
2.3.1 頻出パタンマイニング
2.3.2 確率モデル
2.4 グラフ/ネットワーク/相同性の学習
2.4.1 ノードクラスタリング
2.4.2 半教師あり学習
2.4.3 複数グラフからの頻出サブグラフマイニング
2.5 データ統合型機械学習
2.6 能動学習:実験計画
2.7 おわりに
3 システム生物学と合成生物学へのAIの利用と展開
3.1 はじめに
3.2 トランスクリプトームデータに対するクラスタリング解析
3.3 Fuzzy k-meansクラスタリングによるトランスクリプトームデータのクラスタリング解析
3.4 トランスクリプトームの時系列データに対する微分方程式を用いた前処理法
3.5 トランスクリプトームデータに対する判別分析
3.6 サポートベクターマシンによるトランスクリプトームデータの判別分析
4 生命科学におけるLinked Open Data(LOD)を用いた知識共有
4.1 生物学と知識共有
4.2 関連知識の取得とオントロジーによる解決策
4.3 効果的な知識共有を実現するための技術基盤
4.4 Linked Open Data(LOD)の構築
4.5 データベースのRDF化
第2章 医療への展開
1 AIのコンピュータ支援診断(CAD)への展開
1.1 はじめに
1.2 これまでのCAD
1.2.1 黎明期(1960年代~1970年代)
1.2.2 成長期(1980年代~1990年代)
1.2.3 実用期(1998年:CAD元年~2010年代前半)
1.3 第3次AIブーム時代のCAD
1.4 次世代型CADの開発に向けて
1.5 おわりに
2 情報革命とバイオメディカル革命の融合~IoTとAIを利用した予測と予防の医療~
2.1 はじめに
2.2 バイオメディカル分野の課題
2.3 X-Tec
2.4 生命医科学のパラダイム転換
2.5 ライフコースモデル
2.6 動力学モデルによる生命医科学の推論
2.6.1 状態の概念の導入
2.6.2 次元の圧縮
2.6.3 状態変数の粒度
2.6.4 経時変化の離散化
2.6.5 データ同化
2.6.6 自由度と自由度の縮約
2.7 日本発のヘルステックの実現
3 遺伝子解析とAI技術を用いたパーソナルゲノム情報環境
3.1 はじめに
3.2 パーソナルゲノムを用いた疾患リスク予測
3.2.1 疾患リスク予測の信頼性と数理モデル
3.2.2 「失われた遺伝率」(Missing Heritability)の問題
3.2.3 パーソナルゲノム情報の社会心理学的評価
3.3 MyFinder構想
3.3.1 MyFinderのデザインフィロソフィー
3.4 パーソナルゲノムによる自己発見
3.5 機械学習技術への期待と課題
3.5.1 Deep Learning
3.5.2 解釈可能性
3.5.3 機械学習工学(Machine Learning Engineering)
3.6 おわりに
4 非侵襲的代謝診断の臨床応用(実用化)に向けたビッグデータ活用への期待
4.1 はじめに
4.2 がん治療における非侵襲的代謝診断の位置づけ
4.3 超偏極13CMRIによる代謝イメージング
4.3.1 概要
4.3.2 In vivoモデルによる診断および治療効果検証
4.3.3 臨床への展開と実例
4.3.4 In vitro三次元細胞培養系による検証
4.3.5 多様な代謝経路可視化の取り組み
4.3.6 代謝応答モデル化・シミュレーションの試み
4.4 今後の展望と期待
第3章 医薬への展開
1 AIを用いたビッグデータからの創薬
1.1 はじめに―創薬を巡る状況と計算論的アプローチへの期待
1.2 ビッグデータやAIを活用した計算創薬/DRの「基本枠組み」
1.2.1 「生体分子プロファイル型計算創薬・DR」における疾患と薬剤の相互作用の捉え方
1.2.2 生体分子ネットワーク準拠の計算創薬/DRの「3層ネットワークモデル」
1.2.3 生体分子プロファイル型創薬・DRの方法の分類
1.3 ビッグデータからAIを用いて創薬を行う
1.3.1 AIバーチャルスクリーニング法
1.3.2 タンパク質相互作用ネットワークでの標的分子AI探索法
1.4 おわりに
2 創薬におけるビッグデータの可能性
2.1 はじめに
2.2 生体高分子の構造を計測する手法
2.3 バーチャルスクリーニング
2.4 リアルワールドデータとシミュレーションワールドデータの融合
2.5 おわりに
3 医療創薬へのAI応用の可能性
3.1 医療創薬へのAI応用の現状と可能性
3.2 標的タンパク質の同定及びリード化合物探索と最適化
3.3 早期ADMET
3.4 既存薬再開発などに向けたアプローチ
3.5 包括的取り組み
3.6 AI活用の鍵:データの量,質,利用可能性
3.7 結語
4 スマート創薬による,スーパーコンピュータ,AIと生化学実験の連携が拓く創薬
4.1 はじめに
4.2 AI(機械学習)
4.2.1 創薬分野におけるAI利用の背景
4.2.2 IT創薬コンテストの実施によるIT創薬の普及とSBDD及びLBDDで活用可能なデータセットの整備
4.3 スーパーコンピュータ
4.3.1 スーパーコンピュータの背景
4.3.2 スーパーコンピュータを用いた創薬
4.4 まとめ
第4章 大阪大学医学部・病院における人工知能応用の取り組み
1 「大阪大学 大学院医学系研究科・医学部附属病院 産学連携・クロスイノベーションイニシアティブ」「AIメディカルヘルスケアプラットフォーム」設立の背景
1.1 緒言:基盤となる産学連携・クロスイノベーションイニシアティブ
1.2 AIメディカルヘルスケアプラットフォームの目的
2 AIメディカルの重要性と方向―大阪大学医学部におけるAIメディカル研究の取り組みを中心に―
2.1 はじめに
2.2 人工知能応用型医療技術開発内容について
2.3 産業応用の視点
2.3.1 医学と人工知能の組み合わせは必須の産業プラットフォームとなる
2.3.2 人工知能の経済への影響
2.3.3 日本の国際競争力のシフト:ものつくりから新領域へ
2.4 メディカル・人工知能領域の教育体制
2.5 まとめ
3 人工知能Deep Learningの医学応用
3.1 緒言:技術概観
3.1.1 画像解析・病理診断
3.1.2 診断・カルテ解析
3.1.3 在宅医療
3.1.4 創薬
3.1.5 ウイルス・病原菌解析
3.1.6 実用・医療経済との関連
3.2 オートエンコーダーによるウイルス遺伝子解析
3.3 必要なコンピューターとプログラム
3.4 ディープラーニングと科学と複雑系
3.5 医療と社会的な視点からの議論
4 人工知能の医療画像解析への応用
4.1 はじめに
4.2 畳み込みニューラルネットワークによる細胞画像判別
4.2.1 細胞画像の準備
4.2.2 CNNの構造
4.2.3 細胞分化の識別
4.2.4 細胞画像識別について今後の展望
4.3 おわりに
第5章 ヘルスケアへの展開
1 機械学習クラスタ解析を応用した感染症スクリーニングシステムの研究開発
1.1 はじめに
1.2 機械学習の概要と感染症スクリーニングへの応用
1.3 感染症スクリーニングシステムの紹介と自己組織化マップを用いた感染症判別
1.3.1 バイタルサイン計測に基づく感染症スクリーニングシステムの開発
1.3.2 自己組織化マップとk‒means法を併用した感染症の判別
1.4 季節性インフルエンザ患者を対象とした感染症スクリーニングの検出精度評価
1.5 おわりに
2 細胞培養におけるAI関連技術の応用―画像解析による細胞品質管理
2.1 はじめに
2.2 細胞培養の発展と現状
2.3 細胞培養における新しいフロンティア
2.4 細胞培養の実用化における課題
2.5 細胞培養におけるAI関連技術の応用事例
2.5.1 間葉系幹細胞の分化予測
2.5.2 iPS細胞の培養状況モニタリング評価
2.6 画像を用いた細胞品質管理に期待されるAI関連技術
2.6.1 イメージング計測技術に求められるAI関連技術
2.6.2 画像認識に求められるAI関連技術
2.6.3 データ解析技術に求められるAI関連技術
2.7 まとめ
第6章 ものづくりへの展開
1 微生物によるモノづくりのためのトランスオミクスデータ解読をめぐって
1.1 はじめに
1.2 学習(learn)段階の役割
1.3 データ処理の課題 ピークピッキング
1.4 データの可視化
1.5 データ解読の実際
1.6 エンリッチメント解析
1.7 因果関係のグラフ表示
1.8 まとめ
2 環境問題解決への微生物利用最適化に向けた展開
2.1 はじめに
2.2 微生物Clostridium cellulovoransの特徴
2.3 環境問題解決を目指したC. cellulovoransの定量プロテオーム解析
2.4 今後の展開
3 人工知能技術の代謝工学および農業への応用
3.1 はじめに
3.2 深層学習を用いたタンパク質細胞内局在の予測
3.3 深層学習を用いた遺伝子間相互作用の予測
3.4 植物の表現型解析における機械学習の活用
3.5 おわりに
4 微生物のゲノム情報のビッグデータ化とAI
4.1 はじめに
4.2 国内外のメタゲノム解析の研究動向―海洋メタゲノム解析を例として
4.3 メタゲノミクス・シングルセルゲノミクスの課題
4.4 シングルセルゲノミクスの課題を打破する液滴反応技術とバイオインフォマティクス技術の統合
4.5 メタゲノム・シングルセルゲノムデータ解析へのAI導入による未来展望
4.6 おわりに
5 先端バイオ計測技術の醸造現場への導入と機械学習によるイノベーションへの期待
5.1 はじめに
5.2 清酒生産における品質管理の現状
5.3 課題解決のためには…清酒製造のための工程管理指標の探索
5.4 現場で使えるポジショニングシステムを目指して
5.5 醸造分野におけるIT技術の導入
第7章 今後の期待する展開
1 脳機能の解明を目指した個体レベルのdata‒driven scienceの実装
1.1 はじめに
1.2 機能的セロミクスの戦略
1.3 機能的セロミクスの実証
1.4 神経ネットワークの動作原理の理解に向けて
2 定量データに基づく生体情報処理の同定
2.1 背景
2.2 細胞移動における細胞内情報処理の同定
2.3 成長円錐走化性の細胞内情報処理
2.4 精子幹細胞ダイナミクスの同定
3 生物種を横断した情報の整備
3.1 生物横断研究の流れ
3.2 統一化に向かうモデル生物データベースの現状
3.3 オーソログによる生物横断検索
3.4 生物横断を柱として進む希少疾患研究
3.5 表現型で横断できるか:フェノログの試み
3.6 生物横断を容易にするための情報整備:データベース化を容易にする論文形式の導入
3.7 サイバーから実研究を加速するためのインフラ整備
3.8 最後に
4 粒子群最適化法によるニューラルネットワークの柔軟な学習
4.1 はじめに
4.2 ニューラルネットワークにおける最適化問題
4.3 従来の最適化法とその問題点
4.4 粒子群最適化法
4.5 柔軟な学習の実行例
4.6 おわりに
5 個人と社会のためのAIとIoT基盤
5.1 はじめに
5.2 個人と社会のための枠組み
5.2.1 枠組み
5.2.2 解決すべき課題
5.3 応用例
5.4 関連研究
5.5 おわりに
6 バイオテクノロジーにおいて期待されるAIの姿
6.1 はじめに
6.2 データサイエンスの現況と問題点
6.3 次世代に向けた生命現象解析
6.4 今後の展開
-

自動車用制振・遮音・吸音材料の最新動向《普及版》
¥3,960
2018年刊「自動車用制振・遮音・吸音材料の最新動向」の普及版。騒音発生メカニズムから材料開発、材料の最適配置、性能評価・シミュレーションまで、自動車騒音対策の全てが分かる1冊。
(監修:山本崇史)
<a href="http://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=115628"target=”_blank”>この本の紙版「自動車用制振・遮音・吸音材料の最新動向(普及版)」の販売ページはこちら(別サイトが開きます)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は、2018年当時のものを使用しております。
山本崇史 工学院大学
吉田準史 大阪工業大学
飯田明由 豊橋技術科学大学
井上尚久 東京大学
新井田康朗 クラレクラフレックス(株)
加藤大輔 豊和繊維工業(株)
森 正 ニチアス(株)
次橋一樹 (株)神戸製鋼所
板野直文 日本特殊塗料(株)
竹内文人 三井化学(株)
丸山新一 京都大学
山内勝也 九州大学
西村正治 鳥取大学;Nラボ
竹澤晃弘 広島大学
黒沢良夫 帝京大学
山口誉夫 群馬大学
見坐地一人 日本大学
山口道征 エム・ワイ・アクーステク
木村正輝 ブリュエル・ケアー・ジャパン
廣澤邦一 OPTIS Japan(株)
木野直樹 静岡県工業技術研究所
-------------------------------------------------------------------------
<<目次>>
第1章 自動車で発生する音とその対策
1 TPAによる車室内騒音分析
1.1 自動車騒音の音源と対策
1.2 車室内騒音の寄与分離手法について
1.3 実稼働TPA法
1.4 固体伝搬音と空気伝搬音およびその分離
1.5 模型自動車を用いた寄与分離の実施
1.6 まとめ
2 車体周りの流れに起因する車内騒音の予測技術
2.1 緒言
2.2 空力騒音
2.3 車内騒音解析(直接解析)
2.4 波数・周波数解析
2.5 まとめ
第2章 自動車用制振・遮音・吸音材料の開発
1 音響振動連成数値解析による積層型音響材料の部材性能予測
1.1 はじめに
1.2 材料の分類とモデル化
1.2.1 固定材料
1.2.2 空気層
1.2.3 多孔質材料
1.2.4 材料間の連続条件
1.3 吸音率・透過損失予測のための問題設定
1.3.1 伝達マトリクス法との比較
1.3.2 問題設定
1.3.3 解析上の留意点
1.4 音響透過損失の解析例
1.4.1 解析条件
1.4.2 理論解析値の傾向
1.4.3 数値解析値の傾向
2 自動車吸音材の特徴と性能、応用例、今後の展開
2.1 はじめに
2.2 不織布とは
2.3 不織布の吸音特性
2.4 不織布系吸音材の具体例
2.4.1 内装
2.4.2 エンジン周辺
2.4.3 その他
2.5 不織布系自動車吸音材の課題と今後について
3 ノイズキャンセリング機能を有する防音材料の開発
3.1 はじめに
3.2 開発品の概要
3.2.1 開発品の防音構造
3.2.2 開発品の根源となった技術
3.3 実験的検討
3.3.1 平板試料の音響透過損失
3.3.2 フィルムと遮音材の振動速度
3.3.3 車両音響評価
3.4 開発品の消音メカニズム
3.4.1 2×2行列の伝達マトリックス法
3.4.2 開発品の周波数応答関数
3.4.3 フィルムと遮音材の理想的な振動形態
3.5 おわりに
4 自動車用遮音・防音材料の開発
4.1 はじめに
4.2 Biot理論に基づく音響予測
4.3 積層構造の設計 自動車向け超軽量防音カバー「エアトーン®」
4.4 「エアトーン®」の特長
4.5 「エアトーン®」の適用事例
4.6 まとめ
5 微細多孔板を用いた近接遮音技術
5.1 緒言
5.2 多孔板を用いた固体音低減効果の実験的検証
5.3 数値解析による固体音低減特性の検証
5.3.1 多孔板サイズの影響
5.3.2 多孔板仕様の影響
5.3.3 多孔板複層化の効果
5.4 結言
6 自動車用制振塗料の技術動向
6.1 はじめに
6.2 汎用制振塗料について
6.2.1 制振の位置付け
6.2.2 制振機構
6.2.3 汎用制振塗料の設計
6.2.4 汎用制振塗料の制振特性
6.3 自動車用制振塗料について
6.3.1 自動車用制振材の変遷
6.3.2 自動車用制振塗料の詳細
6.3.3 自動車市場における制振材の性能評価方法と音響解析の重要性
6.3.4 塗装工程について
6.4 おわりに
7 振動制御用エラストマー材料の開発動向
7.1 はじめに
7.2 エラストマーの概説
7.2.1 熱硬化性エラストマー
7.2.2 熱可塑性エラストマー
7.3 エラストマーによる振動制御
7.3.1 防振と制振
7.3.2 エラストマーの動的粘弾性挙動
7.4 制振材料の基礎的な考え方
7.4.1 非拘束型と拘束型
7.4.2 2層構造:非拘束型制振材料
7.4.3 3層構造:拘束型制振材料
7.5 熱可塑性ポリオレフィンABSORTOMER®(アブソートマー®)の展開
7.5.1 ABSORTOMER®の特徴
7.5.2 ABSORTOMER®の動的粘弾性特性
7.5.3 ABSORTOMER®とEPDMの複合化
7.5.4 ABSORTOMER®とTPVの複合化
7.6 おわりに
8 均質化法による多孔質吸音材料の微視構造設計
8.1 はじめに
8.2 均質化法による動的特性の予測手法
8.2.1 ミクロスケールの支配方程式
8.2.2 多孔質材に拡張した均質化法
8.3 Biotパラメータの同定
8.3.1 空孔率
8.3.2 密度
8.3.3 流れ抵抗
8.3.4 迷路度と特性長
8.3.5 ヤング率とポアソン比
8.4 Delany-Bazleyモデル
8.5 解析モデル
8.6 解析結果
8.6.1 ユニットセルサイズによる影響
8.6.2 Delany-Bazleyモデルとの比較
8.7 まとめ
第3章 自動車における騒音制御
1 自動車で発生する音の性質と吸遮音材の要求特性
1.1 自動車で発生する音とその性質
1.2 騒音の抑制方法と対策手順
2 自動車におけるサウンドデザインと音質評価技術
2.1 はじめに
2.2 自動車のサウンドデザイン~音の価値の積極的な活用~
2.2.1 サウンドデザインとは何か?
2.2.2 単純な抑制からデザインへ
2.3 音の心理的側面
2.3.1 音の遮蔽(マスキング)
2.3.2 聴覚器の周波数選択性
2.3.3 聴覚フィルタと臨界帯域
2.3.4 音の大きさ(ラウドネス)
2.3.5 音の3属性
2.4 音質評価技術
2.4.1 音色と音質
2.4.2 音質評価のための注意点
2.4.3 測定の尺度水準
2.4.4 主観評価手法
2.5 次世代自動車のサウンドデザイン課題
2.5.1 車両接近通報音のデザイン
2.5.2 走行音の積極的なデザイン
2.5.3 車室内音環境のデザイン
3 薄膜を利用した騒音対策手法
3.1 はじめに
3.2 音響透過壁
3.2.1 音響透過壁の基本コンセプト
3.2.2 ダクトへの音響透過壁の適用
3.2.3 カーエアコンダクトへの応用
3.3 薄膜軽量遮音構造
3.3.1 MSIの基本構造
3.3.2 遮音量計測実験
3.3.3 遮音量のシミュレーション
3.3.4 MSIの遮音メカニズム
4 トポロジー最適化による減衰材料の最適配置
4.1 はじめに
4.2 トポロジー最適化
4.3 固有振動数解析に基づく最適化
4.4 周波数応答解析での最適化
4.5 まとめ
5 極細繊維材の吸音率予測手法の開発
5.1 はじめに
5.2 ナノ繊維単体の計算手法
5.3 ナノ繊維を含む積層吸音材の計算結果
5.4 まとめ
第4章 遮音・吸音材料の評価と自動車への応用
1 モード歪みエネルギー法による制振防音性能の予測
1.1 自動車用制振・防音構造のモード歪みエネルギー法による解析
1.2 自動車用制振構造への応用例
2 ハイブリッド統計的エネルギー解析手法を用いた防音仕様の検討
2.1 はじめに
2.2 統計的エネルギー解析手法(SEA法)
2.2.1 基本的な考え方
2.3 ハイブリッドSEA法
2.3.1 解析SEAモデル作成に必要な情報収集
2.3.2 解析SEAモデル作成
2.3.3 入力サブシステムの定義
2.3.4 伝達経路ネットワーク図作成
2.3.5 構造・音響加振実験
2.3.6 ハイブリッド化
2.4 防音材仕様検討
2.4.1 Design Modification(DM)モデル化手法
3 多孔質材料の吸・遮音メカニズムと評価手法
3.1 はじめに
3.2 多孔質材料のいろいろ、吸音要素
3.3 吸音性を表す量
3.3.1 材料に関わる音波の音圧挙動の定式化
3.4 おわりに
4 11.5 kHzまで測定可能な高周波域吸音率/透過損失測定用音響管の開発
4.1 はじめに
4.2 音響管による吸遮音性能評価方法
4.2.1 吸音率測定方法
4.2.2 垂直入射透過損失測定
4.3 音響管による高周波域測定の対応
4.3.1 上限周波数
4.3.2 下限周波数
4.3.3 平面波伝搬条件を満たす音響管寸法
4.3.4 高周波域まで測定できる音響管
4.3.5 高周波域対応音響管の課題
4.4 測定事例
4.5 まとめ
5 Biotパラメータの実測と予測
5.1 はじめに
5.2 多孔質材料の数理モデル
5.3 パラメータの定義
5.3.1 多孔度
5.3.2 単位厚さ当たりの流れ抵抗
5.3.3 迷路度
5.3.4 粘性特性長
5.3.5 熱的特性長
5.3.6 弾性率
5.3.7 内部損失係数
5.4 パラメータの測定方法
5.4.1 多孔度
5.4.2 単位厚さ当たりの流れ抵抗
5.4.3 迷路度
5.4.4 特性長
5.4.5 弾性率
5.5 パラメータの予測法
5.5.1 JCAモデルにおけるパラメータの数値流体力学的予測
5.5.2 変形による繊維系多孔質材料のパラメータの変化のための予測式
5.6 おわりに
6 Biotモデルにおける非音響パラメータの同定法
6.1 はじめに
6.2 セルウィンドウに細孔の開いた薄膜を有するポリウレタンフォームの垂直入射吸音率の測定
6.3 筆者が行った測定に基づく非音響パラメータの同定法
6.4 海外研究者による非音響パラメータの同定法
6.5 まとめ
-

バイオフィルム制御に向けた構造と形成過程―特徴・問題点・事例・有効利用から読み解くアプローチ―《普及版》
¥3,520
2017年刊「バイオフィルム制御に向けた構造と形成過程―特徴・問題点・事例・有効利用から読み解くアプローチ―」の普及版。周辺環境により異なる特徴をもつバイオフィルムへの個別対策として、その構造や形成過程、各種細菌の生理活性を理解するために欠かせない1冊!
(監修:松村吉信)
<a href="http://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=115615"target=”_blank”>この本の紙版「バイオフィルム制御に向けた構造と形成過程(普及版)」の販売ページはこちら(別サイトが開きます)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は、2017年当時のものを使用しております。
松村吉信 関西大学
田代陽介 静岡大学
天野富美夫 大阪薬科大学
米澤英雄 杏林大学
久保田浩美 花王㈱
池田 宰 宇都宮大学
千原康太郎 早稲田大学
常田 聡 早稲田大学
古畑勝則 麻布大学
本田和美 越谷大袋クリニック
大薗英一 日本医科大学
泉福英信 国立感染症研究所
福智 司 三重大学
矢野剛久 花王㈱
川野浩明 東京工業大学
末永祐磨 東京工業大学
馬場美岬 東京工業大学
細田順平 東京工業大学
沖野晃俊 東京工業大学
兼松秀行 鈴鹿工業高等専門学校
河原井武人 日本大学
野村暢彦 筑波大学
-------------------------------------------------------------------------
<<目次>>
第1章 バイオフィルムの構造と形成機構
1 一般的なバイオフィルム構造とその形成過程、バイオフィルム評価
1.1 はじめに
1.2 一般的なバイオフィルム構造
1.3 バイオフィルムが形成される環境
1.4 バイオフィルムを構成する微生物細胞
1.5 バイオフィルムの環境ストレス耐性・抗菌剤耐性
1.6 バイオフィルム形成過程
1.7 バイオフィルム対策
1.8 バイオフィルム評価
1.9 まとめ
2 緑膿菌が形成するバイオフィルムの構造と特徴
2.1 はじめに
2.2 緑膿菌のバイオフィルム形成過程
2.2.1 付着
2.2.2 マイクロコロニー形成
2.2.3 成熟
2.2.4 脱離
2.3 バイオフィルムの構成成分
2.3.1 細胞外多糖
2.3.2 細胞外DNA
2.3.3 細胞外タンパク質
2.3.4 膜小胞
2.4 Quorum sensingよるバイオフィルム制御
2.5 c-di-GMPによるバイオフィルム制御
2.6 環境ストレスに応答したバイオフィルム形成
2.7 おわりに
3 サルモネラが形成するバイオフィルムの構造
3.1 はじめに
3.2 サルモネラのバイオフィルム
3.2.1 サルモネラのバイオフィルムの形成機構と構造
3.2.2 サルモネラのバイオフィルムに関する問題
3.3 サルモネラのストレス応答とバイオフィルム形成
4 Helicobacter pyloriが形成するバイオフィルムの構造
4.1 はじめに
4.2 ピロリ菌の細菌学的特徴とその病原性
4.3 ピロリ菌感染
4.4 ピロリ菌のバイオフィルム形成
4.5 ピロリ菌バイオフィルムの構造
4.6 最後に
5 乳酸菌バイオフィルムの構造と特徴
5.1 はじめに
5.2 乳酸菌汚染対策とバイオフィルム
5.3 野菜上の微生物の存在状態
5.4 乳酸菌バイオフィルムの形成
5.5 乳酸菌バイオフィルムの構造
5.6 乳酸菌バイオフィルムのストレス耐性
5.7 タマネギから分離した乳酸菌のバイオフィルムにおけるストレス耐性
5.8 終わりに
6 バイオフィルム形成とQuorum Sensing機構
6.1 はじめに
6.2 Quorum Sensing機構
6.3 細菌によるバイオフィルム形成へのQuorum Sensing機構の関与
6.4 Quorum Sensing機構制御技術
6.5 Quorum Sensing制御によるバイオフィルム形成抑制技術
6.6 おわりに
7 バイオフィルム内のストレス環境とPersister形成
7.1 はじめに
7.2 Persister形成と栄養枯渇
7.3 Persister形成とプロトン駆動力
7.4 Persister形成とATP枯渇
7.5 Persister形成とその他のストレス
7.5.1 ジオーキシックシフト
7.5.2 薬剤排出ポンプ
7.5.3 酸化ストレス
7.5.4 クオラムセンシング
7.6 おわりに
第2章 バイオフィルム形成が及ぼす問題点と制御・防止対策
1 バイオフィルムの発生例と分離菌について
1.1 バイオフィルムの発生
1.2 バイオフィルムの微生物的解析
1.2.1 バイオフィルムの発生事例
1.2.2 バイオフィルムの採取と観察
1.2.3 バイオフィルムの発生状況と外観
1.2.4 バイオフィルムの顕微鏡観察
1.2.5 バイオフィルムの従属栄養細菌数
1.2.6 バイオフィルムの構成菌種
1.2.7 バイオフィルムと構成細菌から抽出した色素の類似性
1.2.8 まとめ
1.3 バイオフィルムに関する新たな視点
1.4 バイオフィルムに関する今後の課題
2 血液透析の医療現場におけるバイオフィルム形成の問題点と解決への糸口
2.1 はじめに
2.2 配管内バイオフィルムの証明
2.2.1 パルスフィールド法によるGenotypeの同一性
2.2.2 作業者の手による水系汚染
2.2.3 分離菌構成の合目的性
2.3 血液透析医療の現場の問題点
2.3.1 黎明期からOn-line血液透析ろ過(HDF)まで治療法の変遷
2.3.2 日本の透析液清浄度の測定事情
2.3.3 透析液製造系への清浄化対策の限界
2.4 問題点を解決するための打開策
2.4.1 現実対応手段
2.4.2 抜本的な解決手段:機器構造・施設配管の問題
3 口腔バイオフィルムの特殊性と制御法の現状
3.1 はじめに
3.2 口腔におけるバイオフィルム形成の特殊性
3.2.1 歯表面における口腔常在バイオフィルム形成菌の付着、凝集
3.2.2 死菌による口腔バイオフィルム形成
3.2.3 歯石形成
3.2.4 舌上のバイオフィルム
3.2.5 口腔粘膜のバイオフィルム
3.2.6 日和見菌による口腔バイオフィルム形成
3.2.7 口腔バイオフィルム形成と口臭
3.2.8 口腔バイオフィルム形成と全身疾患
3.3 口腔バイオフィルム形成の制御方法
3.3.1 物理的な口腔清掃方法
3.3.2 代用甘味料を用いたバイオフィルム未形成
3.3.3 洗口剤によるバイオフィルム形成抑制
3.3.4 歯磨きペーストによるバイオフィルム形成抑制
3.3.5 クオラムセンシング阻害によるバイオフィルム形成抑制
3.4 おわりに
4 バイオフィルム制御と洗浄技術
4.1 バイオフィルムの形成と洗浄による制御
4.2 水を用いた清拭洗浄
4.3 アルカリ剤の洗浄効果
4.4 次亜塩素酸の洗浄効果
4.4.1 硬質表面汚れに対するOCl-の洗浄力
4.4.2 樹脂収着汚れに対するHOClの洗浄力
4.5 界面活性剤の併用効果
4.6 塩素系アルカリフォーム洗浄の効果
4.7 気体状HOClによる付着微生物の殺菌
5 生活環境におけるバイオフィルムの制御
5.1 生活環境におけるバイオフィルム
5.2 生活環境におけるバイオフィルムの制御戦略上の特徴
5.3 制御技術構築に向けた戦略
5.4 浴室ピンク汚れ制御に関する研究例
5.5 おわりに
6 プラズマによるバイオフィルム洗浄・殺菌
6.1 プラズマと殺菌
6.2 大気圧プラズマの生成・利用方法
6.2.1 コロナ・アーク放電
6.2.2 誘電体バリヤ放電
6.2.3 グライディングアーク放電
6.2.4 リモート型プラズマ処理
6.2.5 液中殺菌用プラズマ照射法
6.3 各ガス種のプラズマにより液中に導入される活性種
6.4 大気圧低温プラズマによる殺菌効果
6.4.1 各種浮遊菌に対する大気圧低温プラズマの殺菌効果
6.4.2 プラズマバブリングによる付着したバイオフィルム構成菌の不活化
6.4.3 超音波併用プラズマバブリングによる付着したバイオフィルム構成菌の不活化
6.5 おわりに
7 無機物表面のバイオフィルムの評価と対策
7.1 はじめに
7.2 無機物表面に形成されるバイオフィルムとその特徴
7.3 バイオフィルムが引き起こす工業的な問題
7.3.1 腐食・スケール問題
7.3.2 医療衛生問題
7.4 バイオフィルムの評価法
7.4.1 光学顕微鏡
7.4.2 分光学的手法
7.4.3 染色法
7.5 バイオフィルムの対策の現状
7.5.1 機械的方法
7.5.2 薬剤による除去
7.5.3 材料側からのアプローチその他
7.6 終わりに
第3章 バイオフィルムの有効利用
1 バイオフィルムを用いた有用物質生産
1.1 はじめに
1.2 発酵食品
1.3 バイオフィルムリアクター
1.4 発電微生物
2 バイオフィルムの有効利用に向けたバイオフィルム解析とその展望
2.1 はじめに
2.2 簡易的バイオフィルム定量のための解析手法
2.3 バイオフィルム構造の解析手法
2.4 複合微生物系バイオフィルムの解析技術
2.5 バイオフィルム研究技術の将来展望
-

内外美容成分―食べる化粧品の素材研究―《普及版》
¥4,510
2017年刊「内外美容成分―食べる化粧品の素材研究―」の普及版。内外美容の特許事情やその素材の研究動向および、機能性表示食品市場の主要メーカー・素材について解説した1冊!
(監修:島田邦男)
<a href="http://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=115616"target=”_blank”>この本の紙版「内外美容成分(普及版)」の販売ページはこちら(別サイトが開きます)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は、2017年当時のものを使用しております。
島田邦男 琉球ボーテ(株)
日比野英彦 日本脂質栄養学会
香西雄介 神奈川歯科大学
印南 永 神奈川歯科大学
矢野嘉宏 知財問題研究家
渡辺章夫 中部大学
米澤貴之 中部大学
照屋俊明 琉球大学
禹 済泰 中部大学;(株)沖縄リサーチセンター
坪井 誠 一丸ファルコス(株);岐阜薬科大学
田川 岳 丸善製薬(株)
向井克之 (株)ダイセル
下田博司 オリザ油化(株)
築城寿長 ダイワボウノイ(株);信州大学
宮本 達 (株)アイフォーレ
大門奈央 キユーピー(株)
吉田英人 キユーピー(株)
森藤雅史 (株)明治
竹田翔伍 オリザ油化(株)
山下修矢 農業・食品産業技術総合研究機構
立花宏文 九州大学
上岡龍一 崇城大学;表参道吉田病院
上岡秀嗣 健康予防医学研究所
-------------------------------------------------------------------------
<<目次>>
【第I編 総論】
第1章 我が国における内外美容の規制の現状
1 はじめに
2 食品領域と内外美容
2.1 変遷
2.2 科学的根拠と表示
2.3 一般食品
2.4 保健機能食品
2.5 機能性表示食品
2.6 栄養機能食品
2.7 健康補助食品
3 おわりに
第2章 最近の脂質に関するトピックスと内外美容への応用
1 皮膚の構造と脂質
2 セラミドの役割
3 アシルセラミド
3.1 アシルセラミドの機能
3.2 表皮の構造とアシルセラミド
3.3 アシルセラミドの生合成
3.4 表皮におけるセラミドと皮膚バリア機能
3.5 スフィンゴ脂質の経口摂取が皮膚に与える影響
4 皮膚におけるホスホリパーゼの役割
4.1 脂質メディエーター
4.2 分泌性ホスホリパーゼA2
4.3 皮膚に特異的に発現しているホスホリパーゼ
5 おわりに
第3章 骨構造解析とその技術を応用した肌構造評価法
1 はじめに
2 骨構造と骨密度
3 骨構造解析
4 皮溝の構造解析
第4章 内外美容の最新特許事情
1 はじめに
2 内外美容の特許事情全体をどのように調べるか?
3 内外美容に関する主要技術の特許事情調査
3.1 コラーゲンに関する特許出願動向
3.2 ヒアルロン酸に関する特許出願動向
3.3 セラミドに関する特許出願動向
3.4 グルコサミンに関する特許出願動向
3.5 レスベラトロールに関する特許出願動向
4 おわりに
【第II編 内外美容素材の研究動向】
第5章 ノビレチン(シークヮーサー抽出物)の化粧品・健康食品原料への有用性
1 はじめに
2 シークヮーサーとノビレチンについて
3 ノビレチンの抗肥満効果
4 ノビレチンの抗シワ効果
5 ノビレチンの抗掻痒効果
6 ノビレチンの美白効果
7 さいごに
第6章 サケ鼻軟骨プロテオグリカンとアーティチョーク葉抽出物シナロピクリンの肌老化改善
1 はじめに
2 肌構造
3 プロテオグリカン
3.1 サケ鼻軟骨プロテオグリカン
3.2 サケ鼻軟骨プロテオグリカンの抗加齢・美容効果
3.3 ヒト皮膚細胞への作用
3.4 美容効果外用
3.5 経口摂取による美容効果
3.6 プロテオグリカンの働き
3.7 プロテオグリカンのまとめ
4 アーティチョーク葉抽出物
4.1 アーティチョーク
4.2 アーティチョーク葉に含まれるシナロピクリン
4.3 肌におけるNF-κB
4.4 アーティチョーク葉
4.5 美容効果外用
4.6 経口摂取による美容効果
4.7 アーティチョークのまとめ
5 終わりに
第7章 パイナップル由来グルコシルセラミドの内外美容
1 はじめに
2 パイナップル由来グルコシルセラミドについて
3 臨床試験による美肌効果
3.1 長期経口摂取試験
3.2 化粧用エキスの併用効果
4 メカニズムの機能性研究
4.1 表皮をターゲットにした機能性評価
4.2 真皮をターゲットにした機能性検討
5 パイナップル由来グルコシルセラミドの安全性
5.1 長期摂取試験
5.2 過剰摂取試験
6 おわりに
第8章 うんしゅうみかん由来β-クリプトキサンチンの美容効果について
1 はじめに
2 β-クリプトキサンチンによるコラーゲン産生促進作用
3 β-クリプトキサンチンによるヒアルロン酸,アクアポリン産生促進作用
4 β-クリプトキサンチンによる美白作用
5 β-クリプトキサンチン経口摂取によるシミ消去作用
6 おわりに
第9章 紫茶エキスの抗肥満およびスキンケア効果
1 はじめに
2 紫茶エキスの抗肥満作用
3 紫茶エキスのスキンケア効果
4 おわりに
第10章 機能性フタロシアニンと皮膚への作用
1 機能性フタロシアニン
1.1 はじめに
1.2 機能性フタロシアニン
1.3 機能性フタロシアニンの触媒機能
1.4 繊維への応用
1.5 消臭・抗菌繊維「デオメタフィ」
1.6 抗アレルゲン繊維「アレルキャッチャー」
1.7 黄砂・PM2.5への対応
1.8 痒み鎮静繊維「アレルキャッチャーAD」
1.9 おわりに
2 美容酵素メディエンザイムの作用メカニズム
2.1 はじめに
2.2 化粧品の安全性に関わる問題
2.3 メディエンザイムについて
2.4 メディエンザイムの皮膚透過性
2.5 メディエンザイムの有用性
2.6 内外美容の有用性
2.7 表面美容効果と内側からの美容効果
2.8 まとめ
第11章 脂質の内外美容素材としての機能
1 はじめに
2 化粧品用リン脂質
3 環状ホスファチジン酸
4 毛穴目立ち
5 N-3系脂肪酸
6 おわりに
第12章 高付加価値を持つヒアルロン酸の内外美容
1 はじめに
2 ヒアルロン酸の性質
3 ヒアルロン酸の塗布による皮膚改善効果
3.1 低分子ヒアルロン酸
3.2 超保湿型ヒアルロン酸
4 ヒアルロン酸の経口摂取
4.1 ヒトに対する経口摂取ヒアルロン酸の皮膚改善効果
4.2 紫外線照射皮膚障害マウスに対する経口投与ヒアルロン酸の光老化予防効果
4.3 経口投与のヒアルロン酸の吸収について
5 おわりに
第13章 乳由来スフィンゴミエリンの皮膚バリア機能改善効果
1 はじめに
2 乳由来のスフィンゴミエリンとその構造
3 乳由来スフィンゴミエリンの皮膚バリア機能改善効果
3.1 ドライスキンモデルによる評価
3.2 紫外線照射モデルによる評価
3.3 荒れ肌モデルによる評価
3.4 ヒトによる評価
4 おわりに
第14章 イチゴ種子エキスの角層セラミドおよび表皮バリアー機能分子に及ぼす作用
1 はじめに
2 イチゴ種子エキス
3 表皮機能に関与する分子
3.1 セラミド
3.2 フィラグリン
3.3 インボルクリン
4 実験方法
5 結果および考察
5.1 角層セラミドに及ぼす影響
5.2 角層セラミド合成に関与する遺伝子発現への影響
5.3 フィラグリンおよびインボルクリン発現への影響
6 おわりに
第15章 フラボノイドの抗アレルギー作用
1 はじめに
2 フラボノイドとは
3 Ⅰ型アレルギーの発症機序
4 フラボノイドの抗アレルギー作用
4.1 フラボノール
4.2 フラボン
4.3 イソフラボン
4.4 メチル化カテキン
5 おわりに
第16章 焼酎もろみエキスの美白効果に関する研究
1 はじめに
2 単式蒸留しょうちゅう
2.1 一次仕込み
2.2 二次仕込み
2.3 蒸留
3 焼酎粕の化粧品への応用
4 おわりに
【第III編 機能性表示食品市場と内外美容】
第17章 機能性表示食品制度における注目企業と商品
1 大手食品,飲料メーカー
1.1 キリンホールディングス
1.2 アサヒグループホールディングス
1.3 ミツカン
1.4 日本水産
1.5 カゴメ
1.6 サントリーホールディングス
1.7 大塚食品/三井物産
1.8 江崎グリコ
1.9 森永グループ(森永製菓/森永乳業)
1.10 ヤクルト本社
1.11 日本ハム
1.12 味の素
1.13 伊藤園
1.14 雪印メグミルク
2 医薬品,香粧品メーカー
2.1 ライオン
2.2 花王
2.3 ファンケル
2.4 ロート製薬
2.5 森下仁丹
2.6 武田薬品工業
2.7 小林製薬
2.8 資生堂
3 健康食品,通信販売メーカー
3.1 キューサイ
3.2 八幡物産
3.3 日健総本社
3.4 日本予防医薬
3.5 ファイン
4 機能性食品の原料メーカー
4.1 ユーグレナ
4.2 DSMグループ
4.3 ホクガン
4.4 池田糖化工業
4.5 富士化学工業
4.6 ニチレイバイオサイエンス
4.7 太陽化学
4.8 築野食品工業
4.9 ブロマ研究所
5 生産者団体,異業種メーカーその他
5.1 アークレイ
5.2 JAみっかび/農研機構果実研究所
5.3 新潟市農業活性化研究センター
5.4 井原水産
第18章 主要機能性素材の市場動向
1 美容/アンチエイジング素材
1.1 コラーゲン
1.2 プラセンタエキス
1.3 セサミン
1.4 セラミド
1.5 大豆イソフラボン/エクオール
1.6 マカ抽出物
2 骨/関節サポート素材,抗ロコモ素材
2.1 ヒアルロン酸
2.2 グルコサミン/アセチルグルコサミン
2.3 コンドロイチン(コンドロイチン硫酸塩)
2.4 クレアチン
3 アイケア素材
3.1 ルテイン/ゼアキサンチン
3.2 アスタキサンチン
3.3 ビルベリー
3.4 カシス
4 健脳サポート素材
4.1 イチョウ葉エキス
4.2 DHA
4.3 ナットウキナーゼ
5 ダイエット素材
5.1 L-カルニチン
5.2 カプサイシン(トウガラシ抽出物)/カプシエイト
5.3 黒ショウガ(黒ウコン)
5.4 キトサン
5.5 明日葉
6 免疫サポート素材
6.1 アガリクス(ヒメマツタケ)
6.2 植物性乳酸菌
6.3 プロポリス
7 その他の機能性素材
7.1 ウコン(ターメリック)抽出物/クルクミン
7.2 核酸(DNA-Na)
7.3 乳酸菌
-

最新フォトレジスト材料開発とプロセス最適化技術《普及版》
¥5,280
2017年刊「最新フォトレジスト材料開発とプロセス最適化技術」の普及版。フォトレジスト材料および露光技術の特長を最大限に発揮させるためのレジストプロセス技術の最適化を徹底解説した1冊。
(監修:河合晃)
<a href="http://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=115606"target=”_blank”>この本の紙版「最新フォトレジスト材料開発とプロセス最適化技術(普及版)」の販売ページはこちら(別サイトが開きます)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は、2017年当時のものを使用しております。
河合 晃 長岡技術科学大学
佐藤和史 東京応化工業㈱
工藤宏人 関西大学
有光晃二 東京理科大学
古谷昌大 東京理科大学
髙原 茂 千葉大学
青合利明 千葉大学
岡村晴之 大阪府立大学
青木健一 東京理科大学
山口 徹 日本電信電話㈱
藤森 亨 富士フイルム㈱
白井正充 大阪府立大学
堀邊英夫 大阪市立大学
柳 基典 野村マイクロ・サイエンス㈱
太田裕充 野村マイクロ・サイエンス㈱
関口 淳 リソテックジャパン㈱
小島恭子 ㈱日立製作所
新井 進 信州大学
清水雅裕 信州大学
渡邊健夫 兵庫県立大学
佐々木 実 豊田工業大学
宮崎順二 エーエスエムエル・ジャパン㈱
-------------------------------------------------------------------------
<<目次>>
【第I編 総論】
第1章 リソグラフィープロセス概論
1 はじめに
2 リソグラフィープロセス
3 3層レジストプロセス
4 DFR積層レジストプロセス
5 マルチパターニング技術
6 表面難溶化層プロセス
7 ナノインプリント技術
8 PEB(Post exposure bake)技術
9 CEL(Contrast enhanced lithography)法
10 反射防止膜(BARC)
11 イメージリバーサル技術
12 液浸露光技術
13 超臨界乾燥プロセス
14 シランカップリング処理
15 位相シフトプロセス
第2章 フォトレジスト材料の技術革新の歴史
1 はじめに
2 技術の変遷
3 ゴム系ネガ型レジスト
4 ノボラック-NQDポジ型レジスト
5 化学増幅レジスト―i線ネガ型レジストからKrFネガ型レジスト―
6 KrF化学増幅ポジ型レジスト
7 ArF化学増幅ポジ型レジスト
8 ArF液浸露光用化学増幅レジスト
9 EUVレジスト
10 その他のリソグラフィ用材料
10.1 EB
10.2 DSA
10.3 ナノインプリント
11 まとめ
【第II編 フォトレジスト材料の開発】
第1章 新規レジスト材料の開発
1 はじめに
2 極端紫外線露光装置を用いた次世代レジスト材料
3 分子レジスト材料
4 分子レジスト材料の例
4.1 カリックスアレーンを基盤とした分子レジスト材料
4.2 フェノール樹脂タイプ
4.3 特殊骨格タイプ
4.4 光酸発生剤(PAG)含有タイプ
4.5 金属含有ナノパーティクルを用いた高感度化レジスト材料の開発
4.6 主鎖分解型ハイパーブランチポリアセタール
5 おわりに
第2章 酸・塩基増殖反応を利用した超高感度フォトレジスト材料
1 はじめに
2 酸増殖レジスト
2.1 酸増殖ポリマーの設計と分解挙動
2.2 感光特性評価
2.3 EUVレジストとしての評価
3 塩基増殖レジスト
3.1 ネガ型レジストへの塩基増殖剤の添加効果
3.2 塩基増殖ポリマーの設計
4 おわりに
第3章 光増感による高感度開始系の開発
1 はじめに
2 増感反応
3 励起一重項電子移動反応
4 光誘起電子移動反応を用いた高感度酸発生系
5 光電子移動反応を用いた高感度光重合系
6 連結型分子による分子内増感
7 光増感高感度開始系の産業分野での応用
第4章 光酸発生剤とその応用
1 はじめに
2 光酸発生剤の開発
3 光酸発生剤の応用研究
4 おわりに
第5章 デンドリマーを利用したラジカル重合型UV硬化材料
1 はじめに
2 デンドリティック高分子を利用したUV硬化材料の研究背景
3 デンドリマー型UV硬化材料の大量合成
3.1 “ダブルクリック”反応によるデンドリマー骨格母体の合成~多段階交互付加(AMA)法
3.2 デンドリマーの末端修飾によるポリエンデンドリマーの合成
4 デンドリマーを用いたUV硬化材料の特性評価
4.1 エン・チオール光重合
4.2 ポリアリルデンドリマー系UV硬化材料の特性評価
4.3 ポリノルボルネンデンドリマー系UV硬化材料の特性評価
4.4 多成分混合系UV硬化材料
5 おわりに
第6章 自己組織化(DSA)技術の最前線
1 はじめに
2 ブロック共重合体の誘導自己組織化技術
2.1 ブロック共重合体リソグラフィ
2.2 グラフォエピタキシ技術
2.3 化学的エピタキシ技術
3 DSA材料
3.1 高χブロック共重合体材料
3.2 中性化層材料
4 終わりに
第7章 EUVレジスト技術の現状と今後の展望
1 はじめに
2 フォトレジスト材料の変遷
3 EUVレジスト材料
3.1 化学増幅型ポジレジスト
3.2 化学増幅型ネガレジスト(EUV-NTI(ネガティブトーンイメージング))
3.3 新規EUVレジスト(非化学増幅型メタルレジスト)
4 おわりに
【第III編 フォトレジスト特性の最適化と周辺技術】
第1章 最適化のための技術概論
1 はじめに
2 感度曲線とコントラスト
3 スピンコート特性
4 表面エネルギーによる付着剥離性の解析
4.1 分散・極性成分
4.2 接触角法による分散・極性成分の測定方法
4.3 拡張係数Sによるレジスト液の広がり評価
4.4 拡張係数Sによる液中での付着評価
第2章 UVレジストの硬化特性と離型力
1 はじめに
2 UVナノインプリントプロセス
3 UV硬化特性および硬化樹脂の特性評価方法
4 硬化樹脂の構造と機械的特性
5 離型力に及ぼす硬化樹脂の貯蔵弾性率の影響
6 おわりに
第3章 多層レジストプロセス
1 多層レジストプロセスの動向
1.1 はじめに
1.2 多層レジストプロセスの必要性
1.3 3層レジストプロセス
1.4 Si含有2層レジストプロセス
1.5 DFR積層レジストプロセス
2 ハーフトーンマスク用の多層レジスト技術(LCD)
2.1 はじめに
2.2 実験
2.2.1 下層レジストと上層レジストの決定
2.2.2 下層レジストの感度に対するプリベーク温度依存性
2.2.3 上層レジストの感度のプリベーク温度依存性
2.2.4 プリベーク温度決定後のレジスト2層塗布
2.2.5 中間層の検討
2.3 結果と考察
2.3.1 各レジストの感度曲線
2.3.2 下層レジスト,上層レジストの感度曲線
2.3.3 プリベーク温度決定後の2層レジスト
2.3.4 中間層の検討
2.3.5 3層レジストの評価
2.4 おわりに
第4章 フォトレジストの除去特性(ドライ除去)
1 還元分解を用いたレジスト除去
1.1 はじめに
1.2 原子状水素発生装置
1.3 レジストの熱収縮,レジスト除去速度の水素ガス圧依存性,基板への影響についての実験条件
1.4 追加ベーク温度,時間に対するレジストの熱収縮率評価結果
1.5 水素ガス圧力を変化させたときのレジスト除去速度
1.6 到達基板温度とレジスト除去速度との関係
1.7 原子状水素照射によるPoly-Si,SiO2,SiN膜のパターン形状への影響
1.8 おわりに
2 酸化分解を用いたレジスト除去
2.1 はじめに
2.2 実験
2.2.1 湿潤オゾンによるイオン注入レジスト除去
2.2.2 イオン注入レジストの硬さ評価
2.3 結果と考察
2.3.1 湿潤オゾンによるイオン注入レジスト除去
2.3.2 イオン注入レジストの硬さ
2.3.3 イオン注入レジストの硬化のメカニズム
2.4 結論
第5章 フォトレジストの除去特性(湿式除去)
1 はじめに
2 現状の技術
3 湿式によるレジスト除去方法の分類
3.1 溶解・膨潤による方法
3.2 酸化・分解による方法
4 湿式によるレジスト除去特性事例
4.1 概要
4.2 物性と特徴
4.3 機構
4.4 レジスト除去のシミュレーション
4.5 レジスト除去速度比較
4.6 金属配線のダメージ比較
4.7 膜表面残留物比較
5 おわりに
第6章 フォトレジストプロセスに起因した欠陥
1 はじめに
2 レジスト膜の表面硬化層
3 濡れ欠陥(ピンホール)
4 ポッピング
5 環境応力亀裂(クレイズ)
6 乾燥むら
【第IV編 材料解析・評価】
第1章 レジストシミュレーション
1 はじめに
2 VLESの概要
3 VLES法のための評価ツール
4 露光ツール(UVESおよびArFESシステム)
5 現像解析ツール(RDA)
5.1 測定原理
5.2 現像速度を利用した感光性樹脂の現像特性の評価
6 リソグラフィーシミュレーションを利用したプロセスの最適化-1
6.1 シングルシミュレーション
6.1.1 CD Swing Curve
6.1.2 Focus-Exposure Matrix
7 リソグラフィーシミュレーションを利用したプロセスの最適化-2
7.1 ウェハ積層膜の最適化
7.2 光学結像系の影響の評価
7.3 OPCの最適化
7.4 プロセス誤差の影響予測とLERの検討
8 まとめ
第2章 EUVレジストの評価技術
1 EUVリソグラフィとEUVレジスト材料
1.1 EUVリソグラフィの背景
1.2 EUVレジスト材料と技術課題
2 EUVレジストの評価技術
2.1 量産向けEUV露光装置
2.2 EUVレジストの評価項目
2.3 EUV光透過率評価
2.4 EUVレジストからのアウトガス評価
2.5 EUVレジストの感度・解像度に係わる評価
2.6 新プロセスを採用したEUVレジストの評価
第3章 フォトポリマーの特性評価
1 はじめに
2 ベース樹脂の設計―部分修飾によるレジスト特性の制御と最適化―
2.1 ベース樹脂の設計指針
2.2 tBOC-PVPのtBOC化率とレジストの溶解速度および感度との相関
2.3 tBOC-PVPのtBOC化率とレジスト解像度との相関
3 溶解抑制剤の設計(その1)―未露光部の溶解抑制によるレジスト高解像度化―
3.1 溶解抑制剤の設計指針
3.2 プロセス条件の最適化
3.3 フェノール系溶解抑制剤の融点と未露光部の溶解速度との関係
3.4 溶解抑制剤の化学構造と未露光部の溶解速度との関係
3.5 カルボン酸系溶解抑制剤の分子量とレジストの溶解速度との関係
4 溶解抑制剤の設計(その2)―露光部の溶解促進によるレジスト高解像度化―
4.1 溶解促進剤の設計指針
4.2 溶解促進剤のpKaと膜の溶解速度との関係
4.3 溶解抑制剤の化学構造とレジスト特性との関係
5 酸発生剤の設計―レジスト高感度化―
5.1 酸発生剤の設計指針
5.2 レジスト感度の酸発生剤濃度依存性
5.3 酸発生剤の種類とレジスト感度との相関
6 高感度・高解像度レジストの開発
7 おわりに
第4章 ナノスケール寸法計測(プローブ顕微鏡)
1 はじめに
2 AFMを用いた寸法測定の誤差要因
3 高分子集合体の凝集性と寸法制御
4 LER(line edge roughness)
第5章 付着凝集性解析(DPAT法)による特性評価
1 はじめに
2 DPAT法
3 レジストパターン付着性の熱処理温度依存性
4 レジストパターン付着性のサイズ依存性
5 パターン形状と剥離性
6 溶液中のパターン付着性
7 レジストパターンのヤング率測定
【第V編 応用展開】
第1章 フォトレジストを用いた電気めっき法による微細金属構造の創製
1 諸言
2 各種微細金属構造の創製
2.1 積層めっきと選択的溶解による微細金属構造の創製
2.2 電気めっき法による鉛フリーはんだバンプの形成
2.3 電気めっき法による金属/カーボンナノチューブ複合体パターンの形成
2.4 内部空間を有する金属立体構造の創製
3 おわりに
第2章 ナノメートル級の半導体用微細加工技術と今後の展開
1 半導体微細加工技術について
2 極端紫外線リソグラフィ技術
3 EUVリソグラフィの現状と今後の展開
3.1 EUV光源開発
3.2 EUV用露光装置
3.3 EUVレジスト
4 まとめと今後の展望
第3章 3次元フォトリソグラフィ
1 背景
2 スプレー成膜
3 スプレー成膜に関係する気流特性
4 露光技術
5 応用デバイス
6 まとめ
【第VI編 レジスト処理装置】
第1章 塗布・現像装置の技術革新
1 はじめに
2 スピン塗布プロセスの実際
2.1 スピンプログラム
2.2.1 塗布プロセスの影響
{1}高速回転時間の影響
{2}塗布時の湿度の影響
3 HMDS処理
3.1 HMDSの原理
3.1.1 HMDS処理効果の確認
4 プリベーク
5 現像技術の概要
5.1 ディップ現像
5.2 スプレー現像
5.3 パドル現像
5.4 ソフトインパクトパドル現像
第2章 密着強化処理(シランカップリング処理)の最適化技術
1 はじめに
2 HMDSによる表面疎水化処理
3 HMDS処理プロセスの最適化
4 HMDS処理装置
5 HMDS処理によるレジスト密着性と付着性制御
6 おわりに
第3章 露光装置の進展の歴史と技術革新
1 露光装置の歴史
2 ステッパー
3 超解像技術による微細化
4 スキャナー方式の登場と液浸露光による超高NA化
5 最新の液浸露光装置
6 EUVリソグラフィーの開発と最新状況
-

医療・診断をささえるペプチド科学―再生医療・DDS・診断への応用―《普及版》
¥5,280
2017年刊「医療・診断をささえるペプチド科学」の普及版。ペプチドの合成法や設計指針、さらに細胞培養・分化、生体適合性付与、再生治療、薬物送達、イメージング、診断デバイスへの応用を解説した1冊。
(監修:平野義明)
<a href="http://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=115607"target=”_blank”>この本の紙版「医療・診断をささえるペプチド科学(普及版)」の販売ページはこちら(別サイトが開きます)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は、2017年当時のものを使用しております。
平野義明 関西大学
新留琢郎 熊本大学
大髙 章 徳島大学
重永 章 徳島大学
北村正典 金沢大学
国嶋崇隆 金沢大学
中路 正 富山大学
山本憲一郎 長瀬産業㈱
西内祐二 ㈱糖鎖工学研究所
深井文雄 東京理科大学
保住建太郎 東京薬科大学
熊井 準 東京薬科大学
野水基義 東京薬科大学
堤 浩 東京工業大学
三原久和 東京工業大学
二木史朗 京都大学
秋柴美沙穂 京都大学
河野健一 京都大学
富澤一仁 熊本大学
ベイリー小林菜穂子 東亞合成㈱;慶應義塾大学
吉田徹彦 東亞合成㈱;慶應義塾大学
松本卓也 岡山大学
鳴瀧彩絵 名古屋大学
大槻主税 名古屋大学
蟹江 慧 名古屋大学
成田裕司 名古屋大学医学部附属病院
加藤竜司 名古屋大学
多田誠一 (国研)理化学研究所
宮武秀行 (国研)理化学研究所
伊藤嘉浩 (国研)理化学研究所
馬原 淳 (国研)国立循環器病研究センター研究所
山岡哲二 (国研)国立循環器病研究センター研究所
柿木佐知朗 関西大学
伊田寛之 新田ゼラチン㈱
塚本啓司 新田ゼラチン㈱
平岡陽介 新田ゼラチン㈱
酒井克也 金沢大学
菅 裕明 東京大学
松本邦夫 金沢大学
岡田清孝 近畿大学
濵田吉之輔 大阪大学
松本征仁 埼玉医科大学
武田真莉子 神戸学院大学
土居信英 慶應義塾大学
和田俊一 大阪薬科大学
浦田秀仁 大阪薬科大学
濱野展人 ブリティッシュコロンビア大学
小俣大樹 帝京大学
髙橋葉子 東京薬科大学
根岸洋一 東京薬科大学
中瀬生彦 大阪府立大学
服部能英 大阪府立大学
切畑光統 大阪府立大学
齋藤 憲 新潟大学
近藤英作 新潟大学
近藤科江 東京工業大学
口丸高弘 東京工業大学
門之園哲哉 東京工業大学
長谷川功紀 京都薬科大学
臼井健二 甲南大学
南野祐槻 甲南大学
宮﨑 洋 ㈱ダイセル
横田晋一朗 甲南大学
山下邦彦 ㈱ダイセル
濵田芳男 甲南大学
軒原清史 ㈱ハイペップ研究所
-------------------------------------------------------------------------
<<目次>>
【第I編 ペプチド合成】
第1章 ペプチドの固相合成
1 はじめに
2 固相担体の選択
3 手動合成における合成容器と基本操作
4 Fmoc-アミノ酸
5 最初のアミノ酸(カルボキシ末端のアミノ酸)の樹脂への導入
6 ペプチド伸長サイクル
7 Fmoc基の定量
8 脱樹脂,脱保護
9 ペプチドの精製
10 おわりに
第2章 ペプチドの液相合成
1 はじめに
2 古典的な液相法
3 液相法の最近の進歩─フラグメント縮合─
4 液相法の最近の進歩─長鎖脂肪族構造を有するアンカーの利用─
5 おわりに
第3章 アミド結合形成のための縮合剤
1 はじめに
2 カルボジイミド系縮合剤
2.1 N,N’-Dicyclohexylcarbodiimide(DCC)
2.2 N-Ethyl-N’-[3-(dimethylamino)propyl]carbodiimide hydrochloride(EDC)またはwater soluble carbodiimide(WSCI)
3 添加剤
3.1 1-Hydroxybenzotriazole(HOBt)および1-hydroxy-7-azabenzotriazole(HOAt)
3.2 Oxyma
4 ホスホニウム系縮合剤
4.1 BOPおよびPyBOP,PyAOP
5 ウロニウム/グアニジウム系縮合剤
5.1 HBTUおよびHATU
6 COMU
7 向山試薬
8 4-(4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium chloride(DMT-MM)
9 近年開発された脱水縮合法や脱水縮合剤
第4章 遺伝子組換え法によるタンパク質・ポリペプチドの合成とその応用
1 はじめに
2 一般的な遺伝子組換え法によるタンパク質・ポリペプチドの合成
3 多機能キメラタンパク質の合成と細胞の精密制御材料への応用
4 タンパク質の細胞への作用時機を制御できるタンパク質放出材料の開発
5 まとめ
第5章 ペプチド合成用保護アミノ酸
1 はじめに
2 アミノ酸の保護体とその合成
3 アミノ酸側鎖の官能基の保護体
4 α,α-2置換アミノ酸の合成
5 α,α-2置換アミノ酸の保護体とその合成
6 α,α-2置換アミノ酸含有ジペプチド保護体
第6章 ペプチド医薬の化学合成─ペプチド合成における副反応の概要と抑制策─
1 はじめに
2 ペプチド医薬の化学合成
2.1 ペプチド合成の原理
2.2 コンバージェント法による長鎖ペプチドの合成
3 高純度ペプチドセグメントの調製
3.1 欠損/短鎖ペプチドの混入
3.2 ペプチド鎖伸長時に伴うアミノ酸のラセミ化
3.3 アスパルチミド(Asi)形成
4 おわりに
【第II編 ペプチド設計】
第1章 細胞接着モチーフ(フィブロネクチン)
1 はじめに
2 分子構造
3 血漿性,細胞性,および胎児性フィブロネクチン
4 フィブロネクチンマトリックスアセンブリー
5 細胞接着基質としてのフィブロネクチン
5.1 細胞接着モチーフ
5.2 反細胞接着モチーフ
第2章 細胞接着モチーフ(ラミニン)
1 概要
2 ラミニン由来細胞接着ペプチドの網羅的スクリーニング
3 細胞接着ペプチドの受容体
4 細胞接着活性ペプチドのがん転移促進・阻害におよぼす影響
5 ラミニン由来活性ペプチドを用いた細胞接着メカニズムの解析
6 様々な生理活性を示すラミニン由来活性ペプチド
7 まとめ
第3章 ペプチド立体構造の設計と機能
1 はじめに
2 α-ヘリックスペプチドの設計,構造安定化および機能
3 β-シートペプチドの設計,構造安定化および機能
4 ループペプチドの設計と機能
5 おわりに
第4章 生体内安定性─N結合型糖鎖修飾を用いた医薬品創製─
1 はじめに
2 化学修飾による薬物動態の改善
3 ペプチド/タンパク質の糖鎖修飾
3.1 発現法による糖鎖修飾
3.2 化学合成による糖鎖修飾
3.3 N結合型糖鎖修飾によるペプチド医薬の創製
4 おわりに
第5章 細胞膜透過性
1 はじめに
2 膜透過ペプチドを用いる方法
3 エンドソームの不安定化を誘導する方法
4 ステープルドペプチドを用いるアプローチ
5 まとめ
【第III編 細胞作製・分化】
第1章 CPPペプチドを用いたiPS細胞作製・分化誘導技術
1 はじめに
2 タンパク質導入法
3 タンパク質導入法によるiPS細胞の作製
4 タンパク質導入法によるインスリン産生細胞への分化誘導
5 おわりに
第2章 機能性ペプチドによるゲノム安定性の高いiPS細胞の判別・選別法
1 ゲノム不安定性,がん,免疫
2 iPS細胞とがん細胞
3 iPS細胞とカルレティキュリン
4 ゲノム安定性の高いiPS細胞の判別法
5 機能性ペプチドによるゲノム安定性の高いiPS細胞の判別法
6 ゲノム安定性の高いiPS細胞の判別・選別法
7 おわりに
第3章 ラミニン由来活性ペプチドと再生医療
1 はじめに
2 ラミニン由来活性ペプチド
3 ラミニン由来活性ペプチドを用いたペプチド-多糖マトリックス
4 ラミニン活性ペプチドを用いたペプチド-ポリイオンコンプレックスマトリックス(PCM)
5 ペプチド-多糖マトリックス上での生物活性に及ぼすスペーサー効果
6 おわりに
第4章 体外での生体組織成長を促進するペプチド材料
1 オルガノイド研究の新展開
2 唾液腺組織発生と分岐形態形成(Branching morphogenesis)
3 組織成長における周囲化学的環境の整備
4 RGD配列を導入したアルジネート上での顎下腺組織培養
5 オルガノイド成長制御の今後の展開
第5章 ペプチドを利用した3次元組織の構築
1 はじめに
2 細胞接着性ペプチドを利用した細胞の3次元組織化
3 マイクロ流路を用いた3次元組織体の構築
4 ペプチドを用いた新規な3次元組織体の構築
5 まとめ
【第IV編 生体適合性表面の設計】
第1章 人工ポリペプチドを用いた生体模倣材料の開発
1 はじめに
2 軟組織再生のためのポリペプチド
2.1 エラスチン類似ポリペプチド
2.2 ナノファイバー形成能を持つエラスチン類似ポリペプチド
2.3 GPG誘導体による機能性ナノファイバーの創製
3 硬組織再生のためのポリペプチド
4 おわりに
第2章 移植留置型の医療機器表面に再生能を付与する細胞選択的ペプチドマテリアル
1 背景~体内埋め込み型医療機器材料の現状~
2 医療機器材料としてのペプチド
2.1 細胞接着ペプチド被覆型医療材料
2.2 細胞を用いたペプチドアレイ探索
2.3 細胞選択的ペプチド
3 細胞選択的ペプチドの探索と医療機器材料開発に向けて
3.1 クラスタリング手法を用いたEC選択的・SMC選択的ペプチドの探索
3.2 BMPタンパク質由来の細胞選択的骨化促進ペプチドの探索
3.3 ペプチド-合成高分子の組み合わせ効果による細胞選択性
4 まとめ
第3章 接着性成長因子ポリペプチドの設計と合成
1 はじめに
2 ムール貝由来接着性ペプチドを利用した成長因子タンパク質の表面固定化
3 進化分子工学を利用した成長因子タンパク質の表面固定化
4 おわりに
第4章 機能性ペプチド修飾による脱細胞小口径血管の開存化
1 はじめに
2 脱細胞化組織
3 細胞外マトリックスの機能を担うさまざまなペプチド分子
4 リガンドペプチドを固定化した小口径脱細胞血管
5 おわりに
第5章 リガンドペプチド固定化技術による循環器系埋入デバイスの細胞機能化
1 はじめに
2 循環器系埋入デバイス構成材料
3 リガンドペプチドの固定化による循環器系デバイス基材の細胞機能化
4 チロシンをアンカーとしたリガンドペプチド固定化技術とその応用
5 おわりに
【第V編 再生治療】
第1章 再生医療に向けてのゼラチン,コラーゲンペプチド
1 はじめに
2 ゼラチンについて
2.1 生体親和性および生体吸収性
2.2 細胞接着性
2.3 加工性および分解性
3 医療用途向け素材beMatrix
3.1 beMatrixゼラチン
3.2 安全性対応
3.3 高度精製品
3.3.1 エンドトキシン
3.3.2 ウイルス
3.3.3 局方対応
3.3.4 滅菌方法
3.3.5 原料の管理
3.3.6 その他
3.4 beMatrixコラーゲンペプチド
4 さいごに
第2章 環状ペプチド性人工HGFの創製と再生医療への可能性
1 はじめに
2 HGF-MET系の生理機能と構造
3 RaPID技術
4 特殊環状ペプチド性人工HGF
5 HGFの臨床開発と特殊環状ペプチド性人工HGFの可能性
第3章 線溶系活性化作用を持つ新規ペプチドと再生医療応用
1 はじめに
2 血液線溶と組織線溶
3 SPのプラスミノーゲン活性化促進作用
4 皮膚創傷治癒と組織線溶系
5 SPの皮膚創傷治癒促進作用
6 おわりに
第4章 オステオポンチン由来ペプチドによる血管新生と生体材料への可能性
第5章 ペプチドを利用した糖尿病・骨代謝疾患の機能再建と再生
1 超高齢化社会の骨代謝疾患と糖尿病の関係性とペプチド製剤による機能再建
2 CRFペプチドファミリーのインスリン分泌促進
3 CRFペプチドファミリーを介する血糖調節とアポトーシス抑制
4 1型糖尿病の再生医療の可能性-膵β細胞の分化・成熟
5 ペプチドホルモンによる膵β細胞の成熟促進
6 細胞間コミュニケーションによる品質管理と恒常性維持
7 ペプチドを利用したDDSと疾患の機能再建と再生
7.1 骨指向性型ペプチドDDS
7.2 ポリカチオン型P[Ap(DET)]ナノミセル粒子
7.3 セルフアセンブル(自己組織化)型ペプチドDDS
8 今後の展望
【第VI編 DDS】
第1章 バイオ医薬の経粘膜デリバリーにおける細胞膜透過ペプチド(CPPs)の有用性
1 はじめに
2 CPPsの発見と利用性
3 CPPsの種類とその特徴
4 CPPsの細胞膜透過メカニズム
5 CPPsの機能を利用した前臨床研究
5.1 CPPs-薬物架橋型による研究
5.2 CPPs非架橋型薬物送達研究
5.3 CPPs非架橋型薬物送達法における吸収促進メカニズム
6 臨床開発の状況
7 おわりに
第2章 タンパク質の細胞質送達を促進するヒト由来膜融合ペプチド
1 はじめに
2 細胞融合に関与するタンパク質の部分ペプチドの利用
3 ヒト由来の膜透過促進ペプチドの探索
4 ヒト由来の膜透過促進ペプチドS19の作用機序
5 おわりに
第3章 核酸医薬のデリバリーを指向したAib含有ペプチドの創製
1 はじめに
2 細胞膜透過性ペプチド中のAib残基の重要性
2.1 Peptaibol由来Aib含有ペプチドの細胞膜透過性
2.2 細胞膜透過性両親媒性ヘリックスペプチド中のAib残基の重要性
3 Aib含有細胞膜透過性ペプチドの核酸医薬のデリバリーツールとしての可能性
3.1 Peptaibol由来Aib含有ペプチドによるアンチセンス核酸の細胞内デリバリー
3.2 MAP(Aib)によるsiRNAの細胞内デリバリー
4 まとめ
第4章 ペプチド修飾リポソームによるDDS
1 はじめに
2 がんを標的としたペプチド修飾リポソーム
2.1 AG73ペプチドを利用した遺伝子デリバリー
2.2 AG73ペプチドを利用したドラッグデリバリー
2.3 AG73バブルリポソームを利用した超音波造影剤と遺伝子デリバリー
3 脳を標的としたペプチド修飾リポソーム
4 おわりに
第5章 機能性ペプチド修飾型エクソソームを基盤にした細胞内導入技術
1 はじめに
2 エクソソーム
3 エクソソームの細胞内移行におけるマクロピノサイトーシス経路の重要性
4 人工コイルドコイルペプチドを用いたエクソソームの受容体ターゲット
5 アルギニンペプチドのエクソソーム膜修飾によるマクロピノサイトーシス誘導促進と効率的な細胞内移行
6 おわりに
第6章 創薬研究におけるホウ素含有アミノ酸およびペプチド
1 はじめに
2 プロテアソーム阻害剤
3 ホウ素中性子捕捉療法(BNCT)に用いるホウ素化合物
3.1 ホウ素アミノ酸
3.2 ホウ素ペプチド
4 結語
【第VII編 診断・イメージング】
第1章 胆道がんホーミングペプチドによる新規腫瘍イメージング技術の開発
1 はじめに
2 がん細胞選択的透過ペプチドの単離
3 胆管がん選択的透過ペプチドの開発
4 胆管がん細胞透過ペプチドBCPP-2のin vitro評価と改良点
5 担がんモデルマウスによるBCPP-2Rペプチドのin vivo評価
6 BCPP-2Rペプチドの細胞透過メカニズム
7 おわりに
第2章 機能ペプチドを利用した生体光イメージング
1 はじめに
2 生体光イメージングの鍵となる「生体の窓」
3 第1の生体の窓を利用した発光イメージング
4 酸素依存的分解機能ペプチド
5 細胞膜透過性ペプチド
6 ペプチドプローブを使った光イメージング
7 BRETを用いた生体光イメージングプローブ
8 おわりに
第3章 放射性標識ペプチドを用いた分子病理診断・内用放射線治療薬剤の開発
1 諸言
2 イメージングと内用放射線療法
3 ペプチドを放射性薬剤化する利点
4 放射性元素の利用とペプチドへの標識
5 臨床応用されている放射性標識ペプチドの開発プロセス
6 放射性ペプチド薬剤を用いた内用放射線療法
7 今後の展望;Theranosticsへの課題
第4章 ペプチド固定化マイクロビーズを用いたバイオ計測デバイスの開発
1 はじめに
2 ペプチド固定化担体にマイクロビーズを用いる利点
3 アミロイドペプチド固定化マイクロビーズの開発
4 皮膚感作性試験用ペプチド固定化マイクロビーズの開発
5 おわりに
第5章 ペプチドマイクロアレイPepTenChipシステムによる検査診断
1 はじめに
2 マイクロアレイによるバイオ検出の基盤技術と新規な生体計測法
3 バイオチップのための新規基板材料と表面化学
4 アレイ化法の検討とマイクロアレイのための蛍光検出器の設計製作
5 これまでのPepTenChipの基礎的研究における応用例
6 結語
-

プラズマ産業応用技術―表面処理から環境,医療,バイオ,農業用途まで―《普及版》
¥5,390
2017年刊「プラズマ産業応用技術」の普及版。表面処理・環境・医療・バイオ・農業用途まで様々な複合領域で産業応用が拡がっているプラズマ技術の進展をまとめた1冊!
(監修:大久保雅章)
<a href="http://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=9437"target=”_blank”>この本の紙版「プラズマ産業応用技術(普及版)」の販売ページはこちら(別サイトが開きます)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は、2017年当時のものを使用しております。
大久保雅章 大阪府立大学
西山秀哉 東北大学
浦島邦子 科学技術・学術政策研究所
高松利寛 神戸大学
沖野晃俊 東京工業大学
渡辺隆行 九州大学
清水一男 静岡大学
浪平隆男 熊本大学
水越克彰 東北大学
玉井鉄宗 龍谷大学
清野智史 大阪大学
堀部博志 (株)栗田製作所
西村芳実 (株)栗田製作所
難波愼一 広島大学
田村 豊 春日電機(株)
宮原秀一 東京工業大学
大久保雄司 大阪大学
山村和也 大阪大学
川口雅弘 (地独) 東京都立産業技術研究センター
油谷 康 日本バルカー工業(株)
高島和則 豊橋技術科学大学
水野 彰 豊橋技術科学大学
川上一美 富士電機(株)
宮下皓高 東京都市大学
江原由泰 東京都市大学
金 賢夏 (国研)産業技術総合研究所
寺本慶之 (国研)産業技術総合研究所
尾形 敦 (国研)産業技術総合研究所
早川幸男 岐阜大学
神原信志 岐阜大学
竹内 希 (国研)産業技術総合研究所
安岡康一 東京工業大学
村田隆昭 (株)東芝
山本 柱 日本山村硝子(株)
黒木智之 大阪府立大学
佐藤岳彦 東北大学
中谷達行 岡山理科大学
平田孝道 東京都市大学
高木浩一 岩手大学
金澤誠司 大分大学
金子俊郎 東北大学
佐々木渉太 東北大学
神崎 展 東北大学
栗田弘史 豊橋技術科学大学
松浦寛人 大阪府立大学
-------------------------------------------------------------------------
<<目次>>
第1章 プラズマ生成技術と応用機器
1 機能性プラズマ流体の流動と応用
1.1 はじめに
1.2 プラズマ流体の機能性とプラズマ流動システム
1.3 熱および熱非平衡プラズマ流体の応用例
1.3.1 プラズマジェットの安定化・定値制御
1.3.2 プラズマ溶射の磁場制御
1.3.3 ハイブリッドプラズマ流動システム
1.3.4 細管内プラズマポンプシステム
1.4 非熱プラズマ流体の応用例
1.4.1 燃焼促進用DBDプラズマジェット
1.4.2 微粒子およびミストDBDプラズマアクチュエータチューブ
1.4.3 気泡プラズマジェットシステム
2 プラズマの産業応用に関する技術動向
2.1 プラズマ技術とは
2.2 プラズマ技術を利用した産業の歴史
2.3 プラズマを利用した産業
2.3.1 電気集塵機(Electrostatic Precipitator:EP)
2.3.2 家庭用空気清浄機
2.3.3 ごみ処理
2.3.4 表面処理(半導体製造,塗装など)
2.3.5 水処理
2.3.6 医療
2.3.7 農業
2.3.8 その他
2.4 今後の動向
3 低温プラズマの種類・発生方法と医療分野への応用
3.1 はじめに
3.2 大気圧低温プラズマの発生方法
3.2.1 バリヤ放電プラズマ
3.2.2 高周波電極放電プラズマ
3.2.3 グライディングアーク
3.2.4 LFプラズマジェット
3.2.5 電極放電プラズマジェット
3.2.6 ダイレクト型プラズマ処理
3.2.7 リモート型プラズマ処理
3.3 大気圧低温プラズマの応用とメカニズム
3.3.1 大気圧低温プラズマ中で生成される活性種
3.3.2 低温プラズマによる微生物の不活化
3.3.3 低温プラズマによる止血
3.4 おわりに
4 熱プラズマの種類,発生方法と応用
4.1 熱プラズマの特徴
4.2 熱プラズマの発生方法
4.2.1 直流アーク
4.2.2 高周波プラズマ
4.2.3 多相交流アーク
4.3 溶射
4.4 熱プラズマによるインフライト溶融
4.5 熱プラズマによるナノ粒子合成
4.5.1 金属間化合物ナノ粒子の合成と応用
4.5.2 セラミックスナノ粒子の合成と応用
4.6 熱プラズマによる廃棄物処理
4.7 熱プラズマプロセッシングの課題
5 マイクロプラズマの発生方法と応用
5.1 マイクロプラズマとは
5.2 マイクロプラズマの発生
5.3 マイクロプラズマ駆動回路について
5.4 マイクロプラズマの応用例
5.5 マイクロプラズマによる室内空気浄化
5.6 マイクロプラズマによる表面改質
5.7 マイクロプラズマによる能動的流体制御
5.8 マイクロプラズマによる能動的微粒子制御
5.9 まとめに代えて
6 パルスパワーを用いた非熱平衡プラズマ形成とその応用
6.1 はじめに
6.2 典型的なパルス放電様相の経時変化
6.3 汎用パルス放電による非熱平衡プラズマの形成
6.4 汎用パルス放電形成非熱平衡プラズマによるプラズマプロセス
6.5 ナノ秒パルス放電による非熱平衡プラズマの形成とそのプラズマプロセス
6.6 パルスパワーを用いた非熱平衡プラズマ形成とその応用の今後
7 流水中における放電プラズマ発生システムの開発と応用
7.1 水中での放電によるプラズマの生成
7.2 水中プラズマによる金属ナノ粒子の生成
7.3 プラズマによる有機化合物の分解と活性酸素種の発生
7.4 フロー式プラズマの開発
7.5 海水など電気伝導度の高い水のプラズマ処理
7.6 キャビテーションとプラズマの融合による材料プロセッシング
7.7 おわりに
8 分光計測によるプラズマ診断
8.1 可視域におけるプラズマ分光
8.2 受動分光による温度・密度計測
8.2.1 ドップラー拡がりによる原子・イオン温度計測
8.2.2 ボルツマンプロット法による電子温度計測
8.2.3 連続スペクトル放射を用いた電子温度計測
8.2.4 シュタルク拡がりによる電子密度計測
8.3 発光線強度比法による電子温度・密度計測
8.4 輻射輸送
8.5 分子分光による振動・回転温度計測
第2章 表面処理への応用
1 コロナ処理による表面改質技術
1.1 はじめに
1.2 コロナ処理装置の構成
1.2.1 コロナ処理装置の構成
1.2.2 導入事例
1.2.3 放電部の構成
1.3 表面の改質効果
1.3.1 接触角・ぬれ張力
1.3.2 化学的改質
1.3.3 物理的改質
1.4 経時変化
1.5 金属箔への処理
1.6 不織布への処理
1.7 おわりに
2 大気圧プラズマ表面処理装置の開発
2.1 はじめに
2.2 新しい大気圧プラズマ装置
2.2.1 マルチガスダメージフリープラズマジェット
2.2.2 平面処理用リニア型ダメージフリープラズマ
2.2.3 大気圧マルチガスコロナ
2.2.4 大気圧マルチガスマイクロプラズマ
2.2.5 マルチガス高純度熱プラズマ
2.2.6 温度制御プラズマ
2.3 大気圧プラズマを用いた表面処理
2.3.1 表面の親水化処理
2.3.2 銅酸化膜の還元処理
2.3.3 半導体レジストの剥離
2.4 低温プラズマを用いた表面付着物分析
2.5 おわりに
3 熱アシストプラズマ処理によるフッ素樹脂の表面改質
3.1 はじめに
3.2 フッ素樹脂
3.3 プラズマ処理中の圧力の影響
3.4 プラズマ処理中の試料表面温度の影響
3.5 おわりに
4 プラズマ表面処理の動向と医療用ゴム接着技術への応用
4.1 はじめに
4.2 プラズマ表面処理プロセスの動向
4.2.1 誘導結合型RFプラズマによる表面処理
4.2.2 DLCプラズマ表面処理
4.2.3 プラズマによる触媒表面処理
4.2.4 その他のプラズマによる表面処理の動向
4.3 プラズマ処理とプラズマグラフト重合処理
4.3.1 プラズマ処理の電極系の例
4.3.2 プラズマ表面処理とプラズマグラフト重合処理の効果
4.3.3 大気圧プラズマグラフト重合と接着性向上の原理
4.3.4 大気圧プラズマグラフト重合装置の概要
4.3.5 フッ素樹脂フィルムのブチルゴムに対する接着性向上と応用例
4.3.6 フッ素樹脂フィルムのブチルゴムに対する接着性向上の加硫(架橋)および接着の方法
4.3.7 フッ素樹脂フィルム-ブチルゴム複合体の剥離試験と試験結果
4.4 おわりに
5 プラズマイオン注入法による表面改質技術
5.1 緒言
5.2 高周波-高電圧パルス重畳型PBII&D法とは
5.2.1 概要
5.2.2 重畳型PBII&D法の独自のパラメータ
5.2.3 注入・成膜の同時処理
5.2.4 注入深さ
5.2.5 利点と欠点
5.3 複雑形状・微細形状への注入成膜
5.4 結言
6 プラズマ重合によるPTFEの表面処理
6.1 はじめに
6.2 フィルムの表面処理
6.3 多孔体の表面処理
6.3.1 PTFE多孔膜について
6.3.2 ePTFEの表面処理
6.3.3 PTFEナノファイバーの表面処理
6.4 おわりに
第3章 環境浄化への応用
1 自動車からの排気ガスの処理
1.1 はじめに
1.2 電気集塵によるディーゼルPMの除去
1.2.1 集塵電極表面の微細加工による再飛散抑制
1.2.2 電気集塵とDPFの併用によるディーゼルPMの除去
1.2.3 電気集塵とDPFの併用によるディーゼルPMの除去
1.3 放電プラズマによるディーゼルNOx浄化
1.3.1 プラズマによる尿素からのアンモニア直接合成
1.4 おわりに
2 船舶用ディーゼルエンジン排ガスの浄化
2.1 はじめに
2.2 背景
2.3 ESPの特徴
2.4 ESPの実用分野
2.5 船舶分野への応用
2.5.1 船舶用と道路トンネル用の違い(課題,問題点)
2.5.2 道路トンネル用ESPの改良
2.5.3 ホール型ESP(新考案)
2.6 実機レベルの試験
2.6.1 実船搭載の補機関を使った陸上試験
2.6.2 実船搭載の主機関を使った陸上試験
2.7 実用化に向けて
2.8 更なる高機能化
3 排ガスナノ粒子の電気集じん装置による捕集
3.1 はじめに
3.2 排ガス粒子の物性
3.3 排ガス粒子の排出源
3.4 電気集じん装置
3.5 再飛散現象
3.6 次世代電気集じん装置
4 プラズマ触媒複合プロセスによる有害ガス分解
4.1 はじめに
4.2 プラズマ触媒プロセスの概要と特徴
4.2.1 プラズマ触媒プロセスの概要
4.2.2 プラズマ触媒反応器の種類
4.3 有害ガスの分解事例
4.3.1 窒素酸化物(NOx)除去
4.3.2 脱臭とVOC分解
4.3.3 低温プラズマを用いた触媒調製と再生
4.3.4 相互作用のメカニズム
4.4 おわりに
5 大気圧プラズマを用いた水素製造
5.1 はじめに
5.2 実験装置および実験方法
5.2.1 流通式プラズマ反応器
5.2.2 バッチ式プラズマ反応器
5.2.3 プラズマ発生電源
5.3 プラズマメンブレンリアクターによる水素生成特性
5.3.1 H2分離特性(差圧の影響)
5.3.2 H2分離特性(水素濃度の影響)
5.3.3 NH3分解特性(バッチ式反応器)
5.3.4 PMRの高純度H2生成特性
5.3.5 PMRの水素透過メカニズム
5.4 おわりに
6 気泡プラズマを用いた水処理
6.1 はじめに
6.2 水中気泡内プラズマによる酢酸分解
6.3 水中気泡内プラズマによるPFOS分解
6.4 まとめ
7 気液混相放電によるOHラジカル生成水処理システム
7.1 はじめに
7.2 反応過程
7.3 モデル化
7.4 実験装置
7.5 実験結果および考察
7.6 結論
8 オゾンの生成技術とオゾン注入法による排ガス処理
8.1 はじめに
8.2 オゾンの生成技術
8.2.1 オゾンの性質
8.2.2 オゾン生成技術
8.2.3 オゾン発生装置
8.2.4 オゾンの応用分野
8.3 オゾン注入法による排ガス処理
8.3.1 プラズマ・ケミカル複合処理技術
8.3.2 ボイラ排ガス処理の例
8.3.3 ガラス溶解炉排ガス処理の例
8.4 おわりに
9 温室効果ガス(N2O,PFCs)の分解処理
9.1 大気圧低温プラズマを利用したN2O分解処理
9.2 低気圧誘導結合型プラズマを利用したPFCsの分解処理
第4章 医療・バイオ・農業への応用
1 プラズマ殺菌
1.1 はじめに
1.2 微生物の種類と形態ならびに病原性の発現
1.2.1 ウイルス
1.2.2 細菌
1.2.3 真菌
1.2.4 原虫
1.2.5 プリオン
1.3 紫外線およびオゾンによる微生物の不活化とその原理
1.4 プラズマによる微生物の不活化と原理
1.5 おわりに
2 低温プラズマを用いた生体適合性表面の設計と医療デバイス応用
2.1 はじめに
2.2 冠動脈ステント用のDLCの設計と適用
2.3 生体模倣DLCの設計と生体適合性評価
2.3.1 低温プラズマ処理によるDLC膜表面のゼータ電位制御
2.3.2 バイオミメティックスDLCの生体適合性評価
2.4 細管内面用の低温プラズマCVD法の開発と人工血管への適用
2.4.1 交流高電圧バースト低温プラズマCVD法の開発
2.4.2 細管内面DLCコーティングの物性評価
2.4.3 DLC人工血管の動物実験
2.5 おわりに
3 プラズマ照射/吸入による疾患の治療
3.1 はじめに
3.2 大気圧プラズマの医療応用
3.2.1 プラズマ照射/吸入による疾患治療
3.2.2 一酸化窒素と生体活性
3.2.3 プラズマ吸入による心筋梗塞の緩和治療
3.2.4 低酸素性脳症モデルラットへのプラズマ吸入による脳組織の保護及び再生
3.3 おわりに
4 高電圧・プラズマ技術の農業・水産分野への応用
4.1 はじめに
4.2 農水食分野への高電圧プラズマ利用の歴史
4.3 プラズマ照射による発芽制御
4.4 水中プラズマを用いた植物の生育促進
4.5 担子菌の子実体形成―キノコ生産性向上
4.6 高電圧を用いた鮮度保持
4.7 おわりに
5 植物への大気圧プラズマジェット照射の効果
5.1 植物処理用プラズマ源
5.2 シロイヌナズナへのプラズマ照射
5.3 カイワレ大根へのプラズマ照射
5.4 植物へのプラズマ照射の作用メカニズム
6 細胞膜輸送に対するプラズマ刺激の効果
6.1 はじめに
6.2 プラズマ照射による薬剤分子導入
6.3 細胞膜輸送を促進する最適なプラズマ刺激量
6.4 プラズマ促進細胞膜輸送における促進因子の同定
6.5 プラズマ間接照射が誘導する細胞膜輸送の詳細な作用機序
6.6 おわりに
7 プラズマ照射に対する生体応答
7.1 はじめに
7.2 プラズマ照射に対する生体応答における多階層性
7.3 溶液中に生成される活性種とその計測
7.4 生体分子損傷
7.5 ウイルスの不活化
7.6 枯草菌芽胞の不活化
7.7 出芽酵母へのプラズマ照射と細胞応答
7.8 おわりに
8 大気圧プラズマによるバイオディーゼル燃料無毒化
8.1 はじめに
8.2 フォルボールエステル
8.3 プラズマ源
8.4 PMAのプラズマ分解
8.5 プラズマ源の改良と放電ガスの影響
8.6 プラズマ誘起紫外線の効果
-

レドックスフロー電池の開発動向《普及版》
¥4,290
2017年刊「レドックスフロー電池の開発動向」の普及版。再生可能エネルギーの積極的な導入に伴い、電力貯蔵用二次電池として重要となるレドックスフロー電池の研究動向をまとめた1冊!
(監修:野﨑健,佐藤縁)
<a href="http://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=9438"target=”_blank”>この本の紙版「レドックスフロー電池の開発動向(普及版)」の販売ページはこちら(別サイトが開きます)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は、2017年当時のものを使用しております。
野﨑健 元 (国研)産業技術総合研究所
佐藤縁 (国研)産業技術総合研究所
津島将司 大阪大学
増田洋輔 古河電池(株)
佐藤完二 LEシステム(株)
董雍容 住友電気工業(株)
片山靖 慶應義塾大学
大原伸昌 (株)ギャラキシー
中井重之 (株)ギャラキシー
塙健三 昭和電工(株)
市川雅敏 昭和電工(株)
井関恵三 昭和電工(株)
織地学 昭和電工(株)
丸山純 (地独)大阪産業技術研究所
吉原佐知雄 宇都宮大学
小林真申 東洋紡(株)
飯野匡 昭和電工(株)
重松敏夫 住友電気工業(株)
内山俊一 埼玉工業大学
鈴木崇弘 大阪大学
城間純 (国研)産業技術総合研究所
金子祐司 (国研)産業技術総合研究所
笘居高明 東北大学
本間格 東北大学
小柳津研一 早稲田大学
-------------------------------------------------------------------------
<<目次>>
【第Ⅰ編 基礎】
第1章 レドックスフロー電池とは
1 はじめに
2 RFBの原理
3 RFBの原理的特長と難点
4 RFBの構成要素
4.1 電解液
4.2 電極材料
4.3 隔膜
4.4 その他のRFB構成材料
5 RFBの用途とコスト
6 RFBの用語について
7 おわりに
第2章 レドックスフロー電池の国内外研究動向
1 はじめに
2 セル(流路構造)
3 電極
4 隔膜
5 電解液およびレドックス反応系
6 実証事業など
7 まとめ
【第Ⅱ編 要素技術】
第3章 レドックスフロー電池およびレドックスキャパシタへの電池用セパレータ適用
1 はじめに
2 電池材料のコスト
3 汎用電池用セパレータ適用可能性の検討
3.1 原理
3.2 セパレータの種類とコスト
3.3 小型セルによる充放電試験
4 考察
5 応用例
5.1 レドックスフロー電池
5.2 レドックスキャパシタ
6 総括
第4章 電解液
1 バナジウム電解液
1.1 はじめに
1.2 レドックスフロー電池の電解液開発経緯
1.3 バナジウム電解液の特徴と性質
1.3.1 バナジウム電解液の酸化還元反応
1.3.2 電極との電子交換反応速度
1.4 火力発電所燃焼煤からの電解液原料バナジウム回収
1.4.1 原料バナジウムの市況価格の推移
1.4.2 オリマルジョン燃焼煤
1.4.3 スートマンプロセスによるメタバナジン酸アンモニウムの回収
1.4.4 石油コークス(PC)焚き火力発電所の燃焼煤
1.4.5 LEシステムの下方流燃焼炉によるバナジウムの回収
1.5 バナジウム電解液製造法
1.5.1 鹿島北共同発電の電解液製造法
1.5.2 LEシステムの電解液製造
1.6 バナジウム電解液のエネルギー密度向上に向けた新しい動き
2 チタン・マンガン系電解液
2.1 はじめに
2.2 チタン・マンガン系電解液の開発
2.2.1 電解液の要求事項
2.2.2 チタン・マンガン系電池の動作原理、課題
2.2.3 チタン・マンガン系電解液の基本特性
2.3 電池性能向上
2.3.1 抵抗成分
2.3.2 電極の表面処理
2.3.3 電流-電圧特性と出力特性
2.3.4 小型電池の試験結果
2.4 おわりに
3 イオン液体
4 高濃度バナジウム電解液
4.1 まえがき
4.2 VRFB電解液 高濃度化の試み
4.3 新規な電解液としての高濃度電解液
4.4 おわりに
第5章 電極材料
1 VGCF®TM電極を使った高出力RFB
1.1 はじめに
1.2 VGCF®の特性紹介
1.3 VGCF®シート
1.4 VGCF®シートをつかったRedox Flow Battey
1.5 おわりに
2 ポーラスカーボン電極表面におけるレドックス反応
2.1 はじめに
2.2 酸素含有官能基を付与した炭素表面におけるジオキソバナジウムイオン還元反応機構
2.3 Fe-N4サイト含有炭素薄膜の被覆によるジオキソバナジウムイオン還元反応の促進
2.4 3次元網目状構造を有する酸化黒鉛還元体におけるバナジウムイオン酸化還元反応
2.5 おわりに
3 ボロンドープダイヤモンド電極および活性炭繊維電極
3.1 ボロンドープダイヤモンド電極
3.1.1 概説
3.1.2 BDD電極の製膜と作製
3.1.3 基板の前処理
3.1.4 マイクロ波プラズマCVD法
3.1.5 製膜したBDDの観察
3.1.6 BDD電極の作製
3.1.7 電解液の作製
3.1.8 セルの作製
3.1.9 酸素終端処理と水素終端処理
3.1.10 バナジウム溶液中におけるBDD電極の電気化学特性
3.1.11 コバルト溶液中におけるBDD電極の電気化学特性
3.1.12 まとめと考察
3.2 活性炭繊維電極―フローセルにおける性能評価
3.2.1 活性炭繊維
3.2.2 概説
3.2.3 電解液の作製
3.2.4 セルの作製
3.2.5 定電流充放電試験
3.2.6 結果と考察
3.2.7 まとめと考察
3.3 総括
4 炭素電極
4.1 炭素電極の要求特性
4.2 炭素電極の導電性と電極活性
4.3 炭素電極の通液性と組織構造
4.4 炭素電極の耐久性
4.5 双極板一体化電極
4.6 薄型電極
第6章 双極板
1 はじめに
2 双極板の種類
2.1 不浸透性カーボン
2.2 膨張黒鉛系
2.3 プラスチックカーボン
3 要求特性
3.1 電気特性
3.2 耐久性
3.3 不純物
3.4 機械的特性
3.5 成形加工特性
4 最近の技術動向
5 おわりに
第7章 システム設計
1 大規模レドックスフロー(RF)電池
1.1 大規模蓄電池に要求される特性
1.2 レドックスフロー電池の基本システム構成
1.2.1 システム構成要素
1.2.2 システム設計
1.2.3 電気システムとしての構成
1.3 大規模レドックスフロー電池の設計例
1.3.1 需要家設置の例
1.3.2 電力系統での実証試験例
1.4 課題と今後の展開
2 多目的レドックスフロー電池
2.1 まえがき
2.2 緒言
2.3 多目的レドックスフロー電池
2.3.1 埼玉工業大学レドックスフロー電池
2.3.2 多目的レドックスフロー電池 ―レドックスキャパシタとしての利用―
2.4 レドックスフロー電池技術の新展開
2.5 結言
3 第2世代レドックスフロー電池
3.1 はじめに
3.2 第2世代レドックスフロー電池の電極流路構造
3.3 まとめ
3.4 謝辞
4 レドックスフロー電池の応用としての間接型燃料電池
4.1 「間接型燃料電池」の概念
4.2 固体高分子型燃料電池の原理と課題
4.3 固体高分子型燃料電池の課題解決の一手段としての間接型燃料電池
4.4 間接型燃料電池の開発課題
4.5 アノード(燃料極)側の間接化の研究動向
4.6 カソード(酸素極)側の間接化の研究動向
4.7 間接型燃料電池システム全体に関連する研究動向
第8章 評価手法
1 レドックスフロー電池のSOCの計測方法
1.1 電流積算法によるSOCの計測
1.2 OCVからSOCの計測
1.3 分光法によるSOCの計測
1.4 クーロメトリーによるSOCの計測
2 レドックスフロー電池の電解液の連続測定
2.1 はじめに
2.2 RFBの基本設計に必要な電解液の物性値
2.2.1 セルスタックのシャント電流損失とポンプ動力損失
2.2.2 セル性能に及ぼす電解液の特性
2.3 RFBの運転制御とモニタリング
2.4 RFBの電極材料の評価手法と電解液
2.5 おわりに
【第Ⅲ編 新規レドックスフロー電池の開発】
第9章 有機レドックスフロー電池
1 はじめに
2 有機レドックス種として用いられる分子類
2.1 キノン類
2.2 TEMPO、MVなどの利用
2.3 フェロセンなどの有機金属錯体の利用
2.4 その他
2.5 生体関連分子から
3 電極材料と隔膜
4 問題点・課題・今後の展開
第10章スラリー型レドックスフロー電池/キャパシタ
1 はじめに
2 セミソリッドフロー電池
3 電気化学フローキャパシタ
3.1 カーボン材料の高濃度化
3.2 レドックス反応容量利用
4 有機レドックスフローキャパシタ
5 結言
第11章 レドックスポリマー微粒子を活物質として用いたレドックスフロー電池
1 はじめに
2 有機レドックスフロー電池の構成
3 高密度レドックスポリマーの電荷貯蔵特性
3.1 レドックス活性基
3.2 主鎖構造
3.3 高密度レドックスポリマー層のレドックス応答
4 レドックス活性微粒子を用いたフロー電池
4.1 ポリマー微粒子のレドックス過程
4.2 レドックスフロー活物質として働く微粒子
5 おわりに
-

フレキシブル熱電変換材料の開発と応用《普及版》
¥4,290
2017年刊「フレキシブル熱電変換材料の開発と応用」の普及版。有機系材料のメカニズムからモジュール開発までの作製プロセス、材料探索には欠かせない材料特性評価、ヘルスケア・住環境などワイヤレスセンサーネットワークへの応用展開までを網羅した1冊。
(監修:中村雅一)
<a href="http://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=9431"target=”_blank”>この本の紙版「フレキシブル熱電変換材料の開発と応用(普及版)」の販売ページはこちら(別サイトが開きます)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は、2017年当時のものを使用しております。
中村雅一 奈良先端科学技術大学院大学
戸嶋直樹 山口東京理科大学名誉教授
石田敬雄 (国研)産業技術総合研究所
町田洋 東京工業大学
井澤公一 東京工業大学
小島広孝 奈良先端科学技術大学院大学
林大介 首都大学東京
客野遥 神奈川大学
中井祐介 首都大学東京
真庭豊 首都大学東京
野々口斐之 奈良先端科学技術大学院大学;(国研)科学技術振興機構
河合壯 奈良先端科学技術大学院大学
堀家匠平 神戸大学
石田謙司 神戸大学
宮崎康次 九州工業大学
末森浩司 (国研)産業技術総合研究所
小矢野幹夫 北陸先端科学技術大学院大学
荒木圭一 (株)KRI
伊藤光洋 古河電気工業(株)
桐原和大 (国研)産業技術総合研究所
中本剛 愛媛大学
仲林裕司 北陸先端科学技術大学院大学
向田雅一 (国研)産業技術総合研究所
塚本修 NETZSCH Japan(株)
池内賢朗 アドバンス理工(株)
橋本寿正 (株)アイフェイズ
馬場貴弘 (株)ピコサーム
関本祐紀 奈良先端科学技術大学院大学
竹内敬治 (株)NTTデータ経営研究所
青合利明 千葉大学
中島祐樹 九州大学
藤ヶ谷剛彦 九州大学
桂誠一郎 慶應義塾大学
-------------------------------------------------------------------------
<<目次>>
【第I編 総論】
第1章 有機系熱電変換材料研究の歴史と現状、そして展望
1 はじめに
2 有機熱電変換材料の特徴
2. 1 物理学的視点
2. 2 化学的視点
2. 3 生物学的視点
2. 4 工学的視点
3 導電性高分子を用いる有機熱電材料の研究
4 導電性ポリアニリンの熱電性能の改善
5 高電導度の導電性高分子の熱電変換材料
6 有機系ハイブリッド熱電材料の研究
7 CNTを含む三元系ハイブリッド有機熱電材料
8 まとめと将来展望
第2章 フレキシブル熱電変換技術に関わる基本原理と材料開発指針
1 はじめに
2 熱電変換素子の基本構造とエネルギー変換効率
3 ゼーベック係数を表す一般式およびゼーベック係数と導電率の相反性
4 ゼーベック係数の様々な近似式
5 フレキシブル熱電変換素子特有の条件
【第II編 性能向上を目指した材料開発】
第1章 フレキシブル熱電変換素子に向けた有機熱電材料の広範囲探索
1 はじめに
2 有機熱電材料の広範囲探索結果
3 有望な材料系についての考察
第2章 高い熱電変換性能を示す導電性高分子:PEDOT系材料について
1 序
2 PEDOT系の合成,薄膜化技術
3 PEDOT系熱電材料の性能
4 おわりに
第3章 有機強相関材料における巨大ゼーベック効果
第4章 有機半導体材料における巨大ゼーベック効果
1 はじめに
2 巨大ゼーベック効果の発見
3 巨大ゼーベック効果の一般性
4 巨大ゼーベック効果の有用性
5 分子配向と巨大ゼーベック効果
6 基準振動解析
7 格子熱伝導率
8 おわりに
第5章 カーボンナノチューブのゼーベック効果
1 はじめに
2 ゼーベック効果と熱電変換素子
3 単層カーボンナノチューブ(SWCNT)
4 SWCNTのゼーベック係数(計算)
4. 1 半導体型(s-)と金属型SWCNT(m-SWCNT)のゼーベック係数
4. 2 直径依存性(1本のSWCNT)
4. 3 SWCNT-SWCNT接合の効果
4. 4 m-SWCNTとs-SWCNTの混合
4. 5 並列混合モデルの直径依存性
5 フィルムの熱電物性(測定)
6 最後に
第6章 カーボンナノチューブ熱電材料の超分子ドーピングによる高性能化
1 はじめに
2 ドーピングの重要性
3 ホスフィン誘導体を用いたn型カーボンナノチューブ
4 クラウンエーテル錯体を用いたn型カーボンナノチューブ
5 まとめ
第7章 有機強誘電体との界面形成に基づくカーボンナノチューブ熱電材料の極性制御
1 はじめに
2 カーボンナノチューブ熱電材料の極性制御手法
3 電界効果型ドーピングにおける有機強誘電体の利用
4 SWCNT/P(VDF/TrFE)積層素子の作製と熱電変換特性
5 π型モジュールの構築
6 おわりに
第8章 タンパク質単分子接合を用いたカーボンナノチューブ熱電材料の高性能化
1 はじめ
2 目指す接合構造とその作成法
3 タンパク質単分子接合による熱電特性の向上効果
4 おわりに
第9章 印刷できる有機-無機ハイブリッド熱電材料
1 はじめに
2 印刷の取り組み
3 ナノ粒子を用いた熱電薄膜
4 PEDOT:PSS-Bi2Te3コンポジット熱電
5 有機-無機材料界面の熱抵抗
6 まとめ
【第III編 モジュール開発】
第1章 フレキシブルなフィルム基板上に印刷可能な熱電変換素子
1 はじめに
2 ユニレグ型フレキシブル熱電変換素子
3 まとめ
第2章 インクジェットを活用したBi-Te系フレキシブル熱電モジュールの開発
1 はじめに
2 Bi-Te系熱電インクの開発とインクジェット熱電モジュール
3 Bi-Te系熱電インクを用いたナノバルクの作製と高性能化
4 おわりに
第3章 π型構造を有するフレキシブル熱電変換素子
1 はじめに
2 フレキシブル熱電変換素子とは
3 ナノ粒子の合成
4 インク化
5 薄膜の作製~カレンダ処理
6 π型フレキシブル熱電変換素子の作製
7 ファブリックモジュール
8 まとめと今後の展望
第4章 カーボンナノチューブ紡績糸を用いた布状熱電変換素子
1 はじめに
2 布状熱電変換素子の構造
3 ウェットスピニング法によるCNT紡糸法概要
4 CNT分散法の検討
5 バインダーポリマー量の検討
6 CNT紡績糸のn型ドーピング
7 CNT紡績糸への縞状ドーピングによる布状熱電変換素子の試作と評価
8 おわりに
第5章 導電性高分子を用いた繊維複合化熱電モジュール
1 はじめに
2 繊維複合化PEDOT:PSS素子の作製と構造
3 繊維複合化PEDOT:PSS素子の物性
4 繊維複合化PEDOT:PSS素子の熱電出力の試算と最適化
5 素子と電極の実効的な接触抵抗の低減
6 繊維複合化素子で作製したモジュールによる熱電発電
7 おわりに
【第IV編 材料特性評価】
第1章 マイクロプローブ法を用いた熱電変換材料のゼーベック係数測定法の開発
1 はじめに
2 ゼーベック係数測定法
2. 1 NagyとTothの方法
2. 2 定常法と微分法
3 マイクロプローブ法によるゼーベック係数測定装置
4 マイクロプローブ法を用いたゼーベック係数の分布測定
4. 1 亜鉛-アンチモン系熱電変換材料
4. 2 ビスマス-テルル系熱電変換材料
5 今後の展望と課題
第2章 異方性を考慮した有機系熱電材料の特性評価法
1 はじめに
2 有機熱電材料の評価
2. 1 有機熱電材料について
2. 2 PEDOT/PSSについて
2. 2. 1 構造異方性とその評価手法
2. 2. 2 異方性を考慮した特性評価結果
2. 3 キャリア評価手法について
2. 4 異方性を考慮した熱電モジュールデザイン
3 おわりに
第3章 SBA458 Nemesis(R)によるゼーベック係数測定とフラッシュアナライザーLFA467 HyperFlash(R)による熱拡散率・熱伝導率評価
1 はじめに
2 ゼーベック係数測定装置について
2.1 NETZSCH社製ゼーベック係数・電気伝導率測定システムSBA458 Nemesis(R)について
2. 2 SBA458 Nemesis(R)でのゼーベック係数(S)の測定原理
2. 3 SBA458 Nemesis(R)での電気伝導率(σ)の測定
2. 4 SBA458 Nemesis(R)による熱電変換材料の測定事例
3 フラッシュ法による有機薄膜の熱拡散率・熱伝導率測定
3. 1 フラッシュ法による薄膜試料の熱拡散率・熱伝導率測定
3. 2 面内方向における熱拡散率・熱伝導率の評価
4 おわりに
第4章 熱電計測に関わる総括とフレキシブル材料への応用
1 はじめに
2 試料厚さと測定法
2. 1 ゼーベック係数と電気抵抗率
2. 2 熱伝導率
3 薄板試料の測定法
3. 1 面内方向のゼーベック係数と電気抵抗率
3. 2 光交流法を用いた熱拡散率評価
4 おわりに
第5章 温度波熱分析法による熱伝導率・熱拡散率の迅速測定
1 はじめに
2 熱物性と温度波法
2. 1 熱物性
2. 2 熱拡散方程式
2. 3 熱拡散長・熱的に厚い条件と薄い条件
3 実際の装置
3. 1 測定システム
3. 2 温度波の位相変化から熱拡散率を求める方法
3. 3 温度依存性
3. 4 振幅の減衰から熱伝導率を測定する方法
3. 5 交流型熱電能を求める方法
4 まとめ
第6章 パルス光加熱サーモリフレクタンス法による熱物性値の測定
1 はじめに
2 光パルス加熱法
3 レーザーフラッシュ法
4 パルス光加熱サーモリフレクタンス法
5 ピコ秒サーモリフレクタンス法
6 ナノ秒サーモリフレクタンス法
7 応答関数法
8 界面熱抵抗の測定
9 まとめ
第7章 3ω法による糸状試料の熱伝導率評価
1 はじめに
2 3ω法の概要
3 3ω法の測定原理
4 3ω法による熱伝導率測定例
5 おわりに
【第V編 応用展開】
第1章 エネルギーハーベスティングの現状とフレキシブル熱電変換技術に期待されること
1 はじめに
2 エネルギーハーベスティング技術の概要
2. 1 様々なエネルギーハーベスティング技術
2. 2 光エネルギー利用技術
2. 3 力学的エネルギー利用技術
2. 4 熱エネルギー利用技術
2. 5 電波エネルギー利用技術
2. 6 その他のエネルギー利用技術
2. 7 関連技術
3 エネルギーハーベスティング技術の市場動向
3. 1 昔からあるエネルギーハーベスティング製品
3. 2 スタンドアロン製品からIoT応用へ
3. 3 IoT分野への熱電発電デバイスの活用
4 フレキシブル熱電変換技術に期待されること
4. 1 熱電変換技術全般への期待
4. 2 フレキシブル熱電変換技術への期待
第2章 フレキシブル熱電変換技術の応用展開と技術課題
1 はじめに
2 有機系熱電変換材料
2. 1 導電性ポリマー系熱電材料
2. 2 有機無機ハイブリッド系熱電材料
2. 3 CNTコンポジット系熱電材料
3 フレキシブル熱電変換モジュールの構造
3. 1 π型モジュール
3. 2 Uni-Leg型モジュール
3. 3 Planar型モジュール
3. 4 In-Plane型モジュール
4 フレキシブル熱電モジュールの応用展開
4. 1 センサネットワークにおける中低温排熱利用の微小自立電源
4. 2 エネルギーハーベスタを目指した富士フイルムの有機熱電変換モジュール
4. 3 健康社会実現に向けた体温利用のヘルスモニター電源
5 今後に向けたフレキシブル熱電モジュールの技術課題
5. 1 有機系熱電材料の課題
5. 2 フレキシブルモジュールの課題
第3章 「未利用熱エネルギー革新的活用技術」プロジェクトにおける有機系熱電変換技術への期待
1 序
2 プロジェクト内における有機系熱電材料の目指す応用出口,研究内容について
3 有機系熱電材料の性能について
4 有機系材料のための計測技術開発
5 おわりに
第4章 大気下安定n型カーボンナノチューブ熱電材料の探索
1 緒言
2 単層CNTシートのn型化
3 n型単層CNTシートの大気安定化
4 最後に
第5章 温熱感覚を呈示するフレキシブルな熱電変換デバイス「サーモフィルム」
1 はじめに
2 「サーモフィルム」
3 「サーモフィルム」によるヒューマンインタフェースの応用イメージ
4 フレキシブル熱電変換材料が拓くイノベーション
-

生薬・薬用植物研究の最新動向《普及版》
¥3,850
2017年刊「生薬・薬用植物研究の最新動向」の普及版。国産化と安定供給が課題となっている生薬・薬用植物について、その有用成分の探索から臨床応用への展望までを収録した1冊。
(監修:高松智)
<a href="http://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=9432"target=”_blank”>この本の紙版「生薬・薬用植物研究の最新動向(普及版)」の販売ページはこちら(別サイトが開きます)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は、2017年当時のものを使用しております。
高松智 昭和大学
渡辺均 千葉大学
新藤聡 千葉大学
池上文雄 千葉大学
秋葉秀一郎 福島県立医科大学
佐橋佳郎 福島県立医科大学
三潴忠道 福島県立医科大学
安藤広和 金沢大学
佐々木陽平 金沢大学
御影雅幸 東京農業大学
永津明人 金城学院大学
森川敏生 近畿大学
大野高政 松浦薬業㈱
今井昇治 松浦薬業㈱
和田篤敬 小林製薬㈱
荒井哲也 小林製薬㈱
落合和 星薬科大学
嶋田努 金沢大学附属病院
条美智子 富山大学
柴原直利 富山大学
小池佑果 昭和大学
北島満里子 千葉大学
三巻祥浩 東京薬科大学
黒田明平 東京薬科大学
松尾侑希子 東京薬科大学
小野政輝 東海大学
倉永健史 北海道大学
山崎真巳 千葉大学
伊藤卓也 富山大学
白畑辰弥 北里大学
小西成樹 北里大学
小林義典 北里大学
飯島洋 日本大学
五十嵐信智 星薬科大学
今理紗子 星薬科大学
杉山清 星薬科大学
多田明弘 ポーラ化成工業㈱
榎本有希子 ㈱ファンケル
山下弘高 岐阜薬科大学
田中宏幸 岐阜薬科大学
稲垣直樹 岐阜薬科大学
伊藤直樹 北里大学
永田豊 諏訪中央病院
-------------------------------------------------------------------------
<<目次>>
【第1編 栽培技術・品質管理】
第1章 薬用植物の新たな苗生産技術
1 はじめに
2 薬用植物栽培における問題点
3 トウキにおける系統選抜と苗生産技術
3. 1 トウキ栽培の現状と問題点
3. 2 採種法の確立
3. 3 トウキ栽培におけるセル成型苗生産の導入
第2章 漢方生薬「黄連」の加工調製方法の変化に伴うアルカロイド含量への影響
1 はじめに
2 中国における黄連の加工調製方法
3 方法
3. 1 実験材料
3. 2 生薬の分別
3. 3 加熱によるアルカロイドへの影響
3. 4 試料の調製
3. 5 UPLCの測定条件
4 結果
4. 1 色調による分別
4. 2 分別した検体の定量
4. 3 加熱によるアルカロイドへの影響
5 考察
第3章 漢方生薬「麻黄」の国産化研究
1 はじめに
2 栽培圃場について
3 繁殖方法について
3. 1 種子繁殖
3. 2 挿し木法
3. 3 株分け法
4 栽培マオウの経年変化について
4. 1 実験材料及び方法
4. 2 結果
4. 3 考察
5 追肥効果について
5. 1 実験材料及び方法
5. 2 結果
5. 3 考察
6 まとめ
第4章 定量NMR(1H-qNMR)法による生薬成分の分析〜生薬キョウニン, トウニン, ウバイに含まれるamygdalin の定量を例に〜
1 はじめに
2 トウニン, キョウニン, ウバイとamygdalin
3 1H-qNMR法の条件検討 〜溶媒の検討〜
4 1H-qNMRの測定手順
4. 1 仲介物質HMD溶液の濃度決定
4. 2 Amygdalin標準品の純度決定と定量可能範囲の確認
4. 3 生薬中のamygdalin含有率の確認
5 測定の結果
6 HPLC測定値との比較
7 おわりに
【第2編 薬理】
第5章 カンカニクジュヨウ(Cistanche tubulosa)の耐糖能改善作用成分
1 はじめに
2 カンカニクジュヨウの含有成分
3 Echinacosideおよびacteosideの抗糖尿病作用
4 カンカニクジュヨウ含有フェニルエタノイド配糖体のα-グルコシダーゼおよびアルドース還元酵素阻害活性
5 おわりに
第6章 パフィアエキスパウダーの経口美肌素材としての有用性
1 はじめに
1. 1 皮膚の構造
1. 2 皮膚老化とコラーゲン
2 パフィアの加齢による皮膚老化に対する有用性
3 パフィアの紫外線による皮膚老化に対する有用性
4 パフィアエキスパウダーの皮膚線維芽細胞活性化作用
5 モニターアンケート調査
6 パフィアエキスパウダーの安全性
7 おわりに
第7章 大柴胡湯の抗肥満作用の検討
1 はじめに
2 漢方処方「大柴胡湯」
3 大柴胡湯の肥満に対する臨床効果
4 大柴胡湯の抗肥満効果に対する構成生薬の関与
5 大柴胡湯の抗肥満効果の作用機序
6 おわりに
第8章 黒ショウガ酢酸エチル可溶部の褐色脂肪細胞に対する効果
1 はじめに
2 間葉系幹細胞から各脂肪細胞への細胞系譜
3 白色脂肪細胞と褐色脂肪細胞の分布と特徴
4 褐色脂肪細胞のエネルギー代謝
5 自然発症2型糖尿病モデルマウスに対するKPの酢酸エチル画分の効果
6 褐色脂肪細胞に対するKPEの効果
7 初代褐色脂肪細胞に対するKPEポリメトキシフラボノイドの分化誘導効果
8 まとめ
第9章 五苓散の糖尿病モデルラットにおける水代謝調節作用の検討
1 はじめに
2 浮腫と糖尿病
3 水分代謝調節と水チャネル
4 水分代謝と漢方薬
5 実験概要
6 実験結果
7 まとめ
8 おわりに
【第3編 創薬シード】
第10章 古典から考える天然資源の利用と新たな創薬シーズの探索
1 はじめに
2 古典より生み出された新薬〜artemisinin〜
3 天然物活用法としての漢方
4 漢方特有の病状「瘀(お)血(けつ)」に作用する活性成分を求めて
第11章 薬用資源植物からの生物活性アルカロイドの探索
1 はじめに
2 Kopsia属植物含有アルカロイド
3 Voacanga africana含有アルカロイド
4 おわりに
第12章 薬用植物の生物活性成分の検討
1 はじめに
2 ビャクダン心材の成分と腫瘍細胞毒性
2. 1 ビャクダンについて
2. 2 ビャクダンの心材の成分と化学構造
2. 3 化合物1-24の腫瘍細胞毒性と構造活性相関
2. 4 アポトーシス誘導活性
2. 5 PPAR-γリガンドとの併用による腫瘍細胞毒性増強作用
3 レモンガヤの葉から単離されたトリテルペンの膵リパーゼ阻害活性と血中トリグリセリド低下作用
3. 1 レモンガヤについて
3. 2 レモンガヤの葉の主成分とその化学構造
3. 3 シンボポゴノールの膵リパーゼ阻害活性と血中TG低下作用
4 フキタンポポの葉より単離・同定されたアルドース還元酵素阻害物質
4. 1 植物抽出エキスのアルドース還元酵素阻害活性のスクリーニング
4. 2 フキタンポポの葉のAR阻害活性の探索とその化学構造
4. 3 化合物26-36のAR阻害活性
5 ビロードモウズイカの葉より単離・同定されたキサンチンオキシダーゼ阻害物質
5. 1 植物抽出エキスのキサンチンオキシダーゼ酵素阻害物質のスクリーニング
5. 2 ビロードモウズイカの葉のXO阻害活性の探索とその化学構造
5. 3 化合物37と38のXO阻害活性
6 結語
第13章 樹脂配糖体の化学構造に関する研究
1 はじめに
2 ヤラピンの構造研究
2. 1 樹脂配糖体画分の構成有機酸の研究
2. 2 樹脂配糖体画分の構成オキシ脂肪酸および構成単糖の研究
2. 3 樹脂配糖体画分の構成配糖酸の研究
2. 4 真性樹脂配糖体の研究
3 コンボルブリンの構造研究
3. 1 PharbitinのIndium(Ⅲ)Chloride処理生成物の研究
3. 2 Negative-ion FAB-MSによるPharbitinの構成樹脂配糖体の考察
4 おわりに
第14章 化学合成を駆使した稀少天然物化学研究
第15章 薬用成分の生合成制御に関するゲノム機能学的研究
1 はじめに
2 薬用植物を対象としたゲノム科学の世界的な動向
3 薬用植物のトランスクリプトーム解析
4 トランスクリプトームとメタボロームの統合解析
5 ゲノム情報に基づくトランスクリプトーム解析
6 合成生物学による植物由来アルカロイド生産への応用
7 ゲノム編集による代謝エンジニアリングの可能性
8 まとめ
第16章 ミャンマー伝統医学の最新動向と薬用植物の科学的根拠の解明
1 はじめに
2 ミャンマー伝統医学の伝承
2. 1 ミャンマー伝統医学の現状
2. 2 ミャンマー伝統薬と薬用植物園
2. 3 ミャンマー伝統薬と配置薬
3 ミャンマー産薬用植物由来の活性物質の探索
3. 1 Jatropha multifidaの抗インフルエンザ活性
3. 2 ミャンマー産薬用植物由来の抗ウイルス活性物質
3. 3 ミャンマー産薬用植物由来の抗リーシュマニア活性物質
4 おわりに
第17章 フローリアクターを利用したサポニンの合成研究
1 序
2 結果
2. 1 C-28位配糖化
2. 2 連続的フロー式C-28位配糖化-バッチ式脱保護法の検討
2. 3 フロー式C-3位配糖化の検討
2. 4 フロー式C-3位配糖化の検討
3 おわりに
【第4編 臨床応用】
第18章 柴胡加竜骨牡蛎湯の血管内皮前駆細胞保護作用
1 序論
2 柴胡加竜骨牡蛎湯のEPC保護作用評価実験
2. 1 概要
2. 2 実験方法
2. 3 酸化ストレス抑制測定
2. 4 炎症性サイトカイン量
3 結論
第19章 腸管のアクアポリンに対する生薬大黄の作用
1 はじめに
2 大黄およびセンナの瀉下作用
3 生体内での水輸送タンパク質;アクアポリン
4 腸管におけるAQPの役割;大腸での水輸送機構
5 大黄およびセンノシドAの瀉下作用における大腸AQP3の役割
5. 1 大黄およびセンノシドAの瀉下作用と大腸AQP3との関係
5. 2 センノシドA投与による大腸AQP3の発現低下メカニズム
6 おわりに
第20章 有用植物の化粧品への応用と現状
1 はじめに
2 方法
2. 1 アサガオカラクサ抽出物の調製
2. 2 アサガオカラクサ抽出物のエストロゲン受容体タンパク発現作用
2. 3 アサガオカラクサ抽出物の成長ホルモン受容体タンパク発現作用
2. 4 アサガオカラクサ抽出物のエストロゲン受容体増加によるコラーゲン産生作用
2. 5 アサガオカラクサ抽出物の成長ホルモン受容体増加によるコラーゲン産生作用
2. 6 UVA照射によるエストロゲン受容体のmRNA発現量
3 結果
3. 1 アサガオカラクサ抽出物のエストロゲン受容体タンパク発現作用
3. 2 アサガオカラクサ抽出物の成長ホルモン受容体タンパク発現作用
3. 3 アサガオカラクサ抽出物のエストロゲン受容体増加によるコラーゲン産生作用
3. 4 アサガオカラクサ抽出物の成長ホルモン受容体増加によるコラーゲン産生作用
3. 5 UVA照射によるエストロゲン受容体のmRNA発現量
4 化粧品への応用
5 おわりに
第21章 生薬・有用植物由来成分の新規美白機能研究“Macrophage migration inhibitoryfactor(MIF)分泌”への検討・応用
1 はじめに
2 メラノサイトにおけるメラニン合成に着目した抑制成分
3 紫外線によるメラノサイトの活性化パラクラインネットワーク機構
4 MIFによるケラチノサイトを介したシミ形成促進メカニズム
5 MIF分泌抑制剤と美白効果
6 Centaurea cyanus抽出物のMIF分泌抑制機能と美白効果
7 おわりに
第22章 食物アレルギーに対する和漢薬の有用性の検討
1 食物アレルギー
1. 1 アレルギーの現状
1. 2 食物アレルギーの現状
1. 3 食物アレルギーが誘導される機序
1. 4 消化管免疫
1. 5 アレルギーと腸内細菌
1. 6 食物アレルギーの治療
2 アレルギーと漢方薬
2. 1 慢性アレルギー疾患と漢方薬
2. 2 食物アレルギー治療における漢方薬など
2. 3 食物アレルギー治療における漢方薬の課題
2. 4 食物アレルギー治療における漢方薬の可能性
第23章 社会的ストレス誘発うつ様行動並びに脳内炎症に対する香蘇散の効果
1 はじめに
2 社会的ストレス誘発うつ様行動に対する香蘇散の効果
3 社会的ストレス誘発脳内炎症に対する香蘇散の効果
4 まとめ
第24章 〈トピック〉腸間膜静脈硬化症と漢方方剤の関連性
1 要旨
2 はじめに
3 疾患概念形成と呼称
4 漢方薬との関連性
4. 1 症例報告・症例集積報告
4. 2 山梔子服用者
4. 3 漢方専門外来における検討
5 山梔子含有医療用漢方製剤
5. 1 山梔子含有一般医薬品
5. 2 山梔子使用の注意点
6 本疾患を早期発見するための注意点
6. 1 リスク
6. 2 病態
6. 3 症状
6. 4 診断・画像診断の注意点
6. 5 腹部単純X線・腹部単純CT・注腸X線
6. 6 腹部超音波検査
6. 7 大腸内視鏡
6. 8 鑑別診断・組織学的検査
6. 9 腸間膜静脈硬化症の治療
6. 10 腸間膜静脈硬化症の管理
7 まとめ
-

生体ガス計測と高感度ガスセンシング《普及版》
¥4,290
2017年刊「生体ガス計測と高感度ガスセンシング」の普及版。呼気ならびに皮膚ガスによる疾病・代謝診断および、生体ガス計測のための高感度ガスセンシング技術について解説した1冊!
(監修:三林浩二)
<a href="http://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=9417"target=”_blank”>この本の紙版「生体ガス計測と高感度ガスセンシング(普及版)」の販売ページはこちら(別サイトが開きます)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は、2017年当時のものを使用しております。
三林浩二 東京医科歯科大学
奥村直也 中部大学
下内章人 中部大学
近藤孝晴 中部大学
財津崇 東京医科歯科大学
川口陽子 東京医科歯科大学
宮下正夫 日本医科大学千葉北総病院
山田真吏奈 日本医科大学千葉北総病院
佐藤悠二 ㈱セント.シュガージャパン
木村那智 ソレイユ千種クリニック
魚住隆行 ㈱HIROTSUバイオサイエンス
広津崇亮 九州大学
梶山美明 順天堂大学
三浦芳樹 順天堂大学
藤村務 東北医科薬科大学
樋田豊明 愛知県がんセンター中央病院
高野浩一 大塚製薬㈱
品田佳世子 東京医科歯科大学
藤澤隆夫 三重病院
荒川貴博 東京医科歯科大学
當麻浩司 東京医科歯科大学
大桑哲男 名古屋工業大学
光野秀文 東京大学
櫻井健志 東京大学
神崎亮平 東京大学
都甲潔 九州大学
野崎裕二 東京工業大学
中本高道 東京工業大学
今村岳 物質・材料研究機構
柴弘太 物質・材料研究機構
吉川元起 物質・材料研究機構
林健司 九州大学
菅原徹 大阪大学
菅沼克昭 大阪大学
鈴木健吾 新コスモス電機㈱
山田祐樹 ㈱NTTドコモ
檜山聡 ㈱NTTドコモ
李丞祐 北九州市立大学
花井陽介 パナソニック㈱
沖明男 パナソニック㈱
下野健 パナソニック㈱
岡弘章 パナソニック㈱
壷井修 ㈱富士通研究所
西澤美幸 ㈱タニタ
佐野あゆみ ㈱タニタ
佐藤等 ㈱タニタ
池田四郎 ㈱ガステック
石井均 ㈲アルコシステム
-------------------------------------------------------------------------
<<目次>>
【第I編 呼気ならびに皮膚ガスによる疾病・代謝診断】
第1章 生体ガスによる疾病診断及びスクリーニングと今後の可能性
1 疾病・代謝由来ガスの酵素触媒機能に基づく高感度計測
1.1 はじめに
1.2 薬物代謝酵素を用いた生化学式ガスセンサ(バイオスニファ)
1.2.1 魚臭症候群(遺伝疾患)の発症関連酵素を用いたトリメチルアミン用バイオスニファ
1.2.2 口臭成分メチルメルカプタン用の光ファイバー型バイオスニファ
1.3 脂質代謝・糖尿病のためのバイオスニファ
1.3.1 酵素の逆反応を用いたアセトンガス用バイオスニファ
1.3.2 イソプロパノール用バイオスニファ
1.4 アルコール代謝の呼気計測による評価
1.4.1 エタノールガス用バイオスニファ
1.4.2 アセトアルデヒドガス用バイオスニファ
1.4.3 飲酒後の呼気中エタノール&アセトアルデヒド計測
1.5 酵素触媒機能を用いた多様な生化学式ガスセンサ
1.5.1 加齢臭ノネナールのバイオセンシング
1.5.2 酵素阻害のメカニズムを利用したニコチンセンサ
1.5.3 酵素によるガス計測の特徴を生かした「デジタル無臭透かし」
1.6 おわりに
2 呼気分析の臨床的背景,呼気診断法の現状と課題
2.1 はじめに
2.2 呼気診断の歴史
2.3 呼気成分の由来
2.4 腸内発酵に伴う呼気水素
2.5 アセトンと脂質代謝
2.6 呼気アセトンと心不全
2.7 呼気採取法と保管法
2.8 随時呼気採取による呼気低分子化合物の検討
2.9 おわりに
3 口気・呼気診断による口臭治療
3.1 はじめに
3.2 口臭の主な原因物質とその生成機序
3.3 口臭測定法
3.3.1 口臭測定条件
3.3.2 口気と呼気の官能検査
3.3.3 測定機器による口臭検査
3.4 口臭症の国際分類
3.4.1 真性口臭症
3.4.2 仮性口臭症
3.4.3 口臭恐怖症
3.5 診断と治療のガイドライン
3.5.1 真性口臭症の診断と治療
3.5.2 仮性口臭症の診断と治療
3.5.3 口臭恐怖症の診断と治療
3.6 おわりに
4 がん探知犬
4.1 はじめに
4.2 がん探知犬に関する報告
4.3 研究方法と成果
4.4 がんが発するにおい物質
4.5 がん探知犬研究の将来
5 糖尿病アラート犬
5.1 糖尿病アラート犬とは
5.2 糖尿病アラーと犬の育成方法
5.3 糖尿病アラート犬の現状と問題点
5.4 糖尿病アラート犬の低血糖探知能力に関する検証
5.5 低血糖探知の科学的裏付け
5.6 CGMとの比較
5.7 CGMの時代における糖尿病アラート犬の意義
5.8 日本における糖尿病アラート犬の育成
5.9 揮発性有機化合物の低血糖モニタリングへの応用
6 線虫嗅覚を利用したがん検査
6.1 はじめに
6.2 がん検査の現状
6.3 がんには特有の匂いがある
6.4 嗅覚の優れた線虫
6.5 線虫はがんの匂いを識別する
6.6 線虫嗅覚を利用したがん検査N-NOSE
6.7 N-NOSE の精度
6.8 生物診断N-NOSE の特徴
6.9 今後の展望
第2章 呼気・皮膚ガスによる疾病・代謝診断
1 食道がん患者の呼気に含まれる特定物質
1.1 はじめに
1.2 研究の目的
1.3 研究の方法
1.3.1 呼気の収集と吸着
1.3.2 ガスクロマトグラフィー・マススペクトロメトリー(GC/MS)
1.4 結果
1.5 考察
2 呼気肺がん検査
2.1 はじめに
2.2 呼気検査について
2.2.1 健常者の呼気
2.2.2 肺がん患者と健常者での呼気の違い
2.2.3 肺がんの呼気分析
2.2.4 呼気成分解析システムによる肺がん検出の試み
2.2.5 呼気からの遺伝子異常推定の試み
2.2.6 呼気凝縮液を用いた肺がんの遺伝子異常の検出
2.3 おわりに
3 ピロリ菌の測定:尿素呼気試験法
3.1 はじめに
3.2 H. pyloriの特徴
3.3 診断と治療
3.4 13C 尿素呼気試験法
3.5 測定原理
3.6 POCone の動作原理
3.7 測定原理
3.8 POCone(R)の現状
4 呼気中アセトンガスの計測意義
4.1 はじめに
4.2 呼気中にアセトンガスが生じるしくみ
4.3 病気ではなく,生活上の原因
4.3.1 過度なダイエット,糖質制限,飢餓状態
4.3.2 激しい運動
4.4 病気および代謝異常による原因
4.4.1 糖尿病
4.4.2 糖尿病性ケトアシドーシス
4.4.3 高脂肪質食症,肝機能障害・肝硬変,高ケトン血症をきたす疾患・症状など
4.4.4 子供の周期性嘔吐症・自家中毒・アセトン血性嘔吐症
4.5 呼気中アセトンガスの計測意義と測定について
5 呼気診断による喘息管理
5.1 はじめに
5.2 喘息の病態と呼気診断
5.3 一酸化窒素:NO
5.3.1 NO産生のメカニズム
5.3.2 呼気NOの測定方法
5.3.3 喘息の診断における呼気NO測定
5.3.4 喘息治療管理における呼気NO測定
5.4 硫化水素:H2S
5.5 一酸化炭素:CO
5.6 おわりに
6 呼気アセトン用バイオスニファ(ガスセンサ)による脂質代謝評価
6.1 はじめに
6.2 アセトンガス用の光ファイバ型バイオスニファ
6.2.1 光ファイバ型バイオスニファの作製
6.2.2 アセトンガス用バイオスニファの特性評価
6.3 運動負荷における呼気中アセトン濃度の計測
6.3.1 バイオスニファを用いた運動負荷における呼気中アセトン濃度の計測方法
6.3.2 運動負荷に伴う呼気中アセトン濃度の経時変化
6.4 まとめと今後の展望
7 皮膚一酸化窒素の計測
7.1 はじめに
7.2 一酸化窒素(NO)の生理的機能
7.2.1 血管拡張のメカニズム
7.3 NO 測定方法
7.3.1 皮膚ガスの特徴
7.4 ヒトの皮膚ガス採取方法
7.5 ラットの皮膚ガス採取方法
7.6 糖尿病・肥満と皮膚ガスNO 濃度
7.7 運動・低酸素環境と皮膚ガスNO 濃度
7.8 おわりに
【第II編 生体ガス計測のための高感度ガスセンシング技術】
第1章 計測技術の開発
1 昆虫の嗅覚受容体を活用した高感度匂いセンシング技術
1.1 はじめに
1.2 昆虫の嗅覚受容体の特徴
1.3 「匂いセンサ細胞」によるセンシング技術
1.3.1 性フェロモン受容体を用いた「匂いセンサ細胞」の原理検証
1.3.2 一般臭検出素子の開発
1.3.3 細胞パターニングによる匂い識別技術
1.4 「匂いセンサ昆虫」によるセンシング技術
1.5 おわりに
2 抗原抗体反応やAI を用いたガスセンシング
2.1 はじめに
2.2 超高感度匂いセンサ
2.3 AI を用いた匂いセンサ
2.4 展望
3 呼気・皮膚ガスのための可視化計測システム(探嗅カメラ)
3.1 はじめに
3.2 酵素を利用した生体ガスの高感度センシング
3.3 生体ガス中エタノール用の可視化計測システム「探嗅カメラ」
3.3.1 エタノールガス用探嗅カメラ
3.3.2 呼気・皮膚ガス中エタノールの可視化計測とアルコール代謝能の評価応用
3.4 おわりに
4 機械学習を用いた匂い印象の予測
4.1 はじめに
4.2 匂いの印象予測の原理
4.3 計算機実験の準備
4.4 深層ニューラルネットワークによる匂い印象予測
4.5 オートエンコーダによる次元圧縮
4.6 予測モデルの訓練
4.7 次元圧縮手法の比較
4.8 ニューラルネットワークの印象予測精度
4.9 研究の今後の展望
5 超小型・高感度センサ素子MSS を用いた嗅覚センサシステムの総合的研究開発
5.1 はじめに
5.2 膜型表面応力センサ(MSS)
5.3 MSS を用いた呼気診断
5.4 感応膜の開発
5.5 ニオイの評価法
5.6 おわりに
6 匂いの可視化システム
6.1 はじめに
6.2 匂いの可視化センシング
6.2.1 匂いの質の可視化:匂いコードセンサと匂いクラスタマップ
6.2.2 生体由来の匂いと匂い型に基づく人の識別
6.3 匂いの可視化とイメージセンシング
6.3.1 匂いイメージセンサ
6.3.2 匂い可視化例
6.4 匂いセンサのハイパー化
6.5 おわりに
7 ヘルスケアを目的とした揮発性有機化合物(VOC)を検出するナノ構造のガスセンサ素子
7.1 はじめに
7.2 酸化モリブデンとナノ構造の基板成長
7.3 ガスセンサ素子の作製とセンサ特性
7.4 まとめ
8 口臭測定器 ブレストロンII-高感度VSC センサによる呼気中VSC 検出機構と活用事例-
8.1 はじめに
8.2 口臭測定器に要求される性能
8.3 ブレストロンIIの検出メカニズム
8.4 高感度VSC センサの構造と検出原理
8.5 高感度VSC センサの感度特性
8.6 ブレストロンIIを用いた性能評価(測定条件の影響)
8.7 ガスクロによる計測結果との相関
8.8 使用上の注意点
8.9 ブレストロンの活用事例
9 生体ガス計測におけるドコモの取り組み
9.1 はじめに
9.2 呼気計測装置の開発とセルフ健康検査への応用
9.3 皮膚ガス計測装置の開発と健康管理への応用
9.4 おわりに
10 呼気中アンモニアの即時検知を目指した水晶振動子ガスセンサシステムの開発
10.1 はじめに
10.2 水晶発振子の原理および検知膜の製膜過程の追跡
10.3 湿度およびアンモニアに対する応答特性の評価
10.4 呼気中のアンモニアガス検知
10.5 おわりに
第2章 メーカーによる研究開発の動向
1 肺がん診断装置の開発
1.1 はじめに
1.2 肺がんバイオマーカーとその測定技術
1.2.1 肺がんバイオマーカー
1.2.2 揮発性肺がんバイオマーカー
1.2.3 揮発性肺がんマーカーの測定技術
1.3 呼気肺がん診断システムの開発
1.3.1 呼気濃縮技術の開発
1.3.2 呼気診断センサチップの開発
1.3.3 呼気診断センサチップ測定装置の開発
1.4 おわりに
2 アンモニア成分の測定技術と携帯型呼気センサーの開発
2.1 はじめに
2.2 呼気分析に高まる期待
2.3 新しいアンモニア検知材料CuBr
2.4 高感度・高選択なセンサーデバイス
2.5 手軽で迅速な呼気センサーシステム
2.6 呼気中アンモニア濃度のサンプリング測定
2.7 ガス選択性と呼気分析の新たな応用
2.8 おわりに
3 脂肪燃焼評価装置
3.1 はじめに
3.2 直接熱量測定による消費エネルギー評価
3.3 これまで研究されてきた「脂肪燃焼評価法」
3.4 呼気アセトン濃度分析による脂肪燃焼評価法
3.5 脂肪燃焼評価における今後の展望
3.6 おわりに
4 見えない疲労の見える化 ~パッシブインジケータ法を用いた皮膚ガス測定~
4.1 働き方と疲労
4.2 パッシブインジケータの開発
4.2.1 パッシブインジケータ
4.2.2 皮膚ガスとは
4.2.3 皮膚アンモニア
4.2.4 皮膚アンモニアの測定法
4.3 パッシブインジケータの仕組み
4.3.1 構造
4.3.2 比色認識の原理
4.3.3 使い方
4.4 アプリケーション例
4.4.1 製造業における現場作業者とデスクワーカー(日内変動)
4.4.2 介護施設における介護職従業員(週内変動)
4.4.3 公立中学校における教員(週内変動)
4.5 今後の展望
5 生体ガス分析用質量分析装置
5.1 はじめに
5.2 生体ガス分析用質量分析装置
5.2.1 装置の概要と原理
5.2.2 生体ガス濃度分析における質量分析計の利点
5.3 ガス気量(換気量)の計測
5.4 生体ガス分析におけるガス濃度の意味と留意点
5.5 生体ガス気量(換気量)の表示法
5.6 酸素消費量や二酸化炭素排出量などのガス出納量の算出法
5.7 ガス分析と気量計測とのラグタイム補正
5.8 ガスサンプリングの手法
5.8.1 マルチサンプリング
5.8.2 膜透過サンプリング
5.9 生体ガス分析の応用例
5.9.1 人の呼気ガス分析
5.9.2 微生物・細胞培養排ガス分析
5.9.3 動物の呼気ガス分析
5.9.4 13CO2/12CO2 安定同位体ガス分析
-

高分子微粒子ハンドブック《普及版》
¥5,280
2017年刊「高分子微粒子ハンドブック」の普及版。高分子微粒子の作製、構造制御・機能化、測定・分析など多岐にわたる研究を詳述し、各項目末には実験条件や素材、器具、測定技術をまとめた「実験項」も掲載した1冊!
(監修:藤本啓二)
<a href="http://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=9418"target=”_blank”>この本の紙版「高分子微粒子ハンドブック(普及版)」の販売ページはこちら(別サイトが開きます)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は、2011年当時のものを使用しております。
藤本啓二 慶應義塾大学
鈴木清 福井大学
福井有香 慶應義塾大学
榎本航之 山形大学
菊地守也 山形大学
川口正剛 山形大学
安田昌弘 大阪府立大学
清水秀信 神奈川工科大学
谷口竜王 千葉大学大学院
杉原伸治 福井大学
酒井健一 東京理科大学
酒井秀樹 東京理科大学
高見拓 理化学研究所
村上義彦 東京農工大学
小関英一 (株)島津製作所
塚田雄亮 ホソカワミクロン(株)
辻本広行 ホソカワミクロン(株)
福井寛 福井技術士事務所
神谷秀博 東京農工大学大学院
田中克史 京都工芸繊維大学
中野政身 東北大学
渡部花奈子 東北大学大学院
長尾大輔 東北大学大学院
藤井秀司 大阪工業大学
中村吉伸 大阪工業大学
藪浩 東北大学
菊池明彦 東京理科大学
小石眞純 東京理科大学
不動寺浩 (国研)物質・材料研究機構
三ツ石方也 東北大学
高宇 東北大学
朱慧娥 東北大学
山本俊介 東北大学
宮下徳治 東北大学
竹岡敬和 名古屋大学
桑折道済 千葉大学
木俣光正 山形大学
松尾亮太郎 スペクトリス(株)
則末智久 京都工芸繊維大学
池田純子 日本ルフト(株)
村田薫 日本エフイー・アイ(株)
高橋幸生 大阪大学
-------------------------------------------------------------------------
<<目次>>
【第1編 高分子微粒子とは】
1 はじめに
2 高分子微粒子の特徴
3 微粒子を測定する
4 微粒子をデザインする
4. 1 微粒子で集める
4. 2 微粒子で見る・検出する
4. 3 微粒子で分ける
4. 4 微粒子が立ちなおらせる
4. 5 微粒子で作る
4. 6 微粒子で運ぶ
4. 7 微粒子で形作る
5 高分子微粒子をつくる
5. 1 単量体(モノマー)からつくる
5. 2 ポリマーからつくる
6 高分子微粒子を集める
7 まとめて次へ
【第2編 高分子微粒子の作製】
第1章 合成的手法
1 乳化重合
1. 1 はじめに
1. 2 乳化重合と類似の不均一系でのラジカル重合と,それらの利点
1. 3 様々な不均一系ラジカル重合
1. 4 乳化重合の操作の一例
1. 5 典型的な乳化重合での系の状態の変化
1. 6 粒子直径への仕込み条件の影響の典型的なパターン
1. 7 ソープフリー乳化重合
1. 8 シード乳化重合
1. 9 マイクロエマルション重合
1. 10 乳化重合などの微粒子分散系ラジカル重合の重合速度
実験項:スチレンの乳化重合
2 ミニエマルション重合
2. 1 はじめに
2. 2 炭酸カルシウムハイブリッドナノ粒子の作製
2. 3 蛍光性ハイブリッドナノ粒子の作製
2. 4 まとめ
実験項:炭酸カルシウムハイブリッドナノ粒子の作製
3 分散重合
3. 1 はじめに
3. 2 不均一系重合における分散重合法の特徴と合成指針
3. 3 線状およびブロック共重合体を分散剤として用いた微粒子合成
3. 4 マクロモノマーを用いた微粒子合成
3. 5 分散重合による微粒子核形成機構と微粒子径制御
3. 6 おわりに
実験項:非極性媒体分散重合法によるpoly(MMA-co-AN)微粒子の合成
4 懸濁重合
4. 1 はじめに
4. 2 懸濁重合の重合動力学
4. 3 懸濁重合における粒径制御
4. 4 単分散な高分子微粒子の調整
4. 5 ガラス球充填層と管型反応器を組み合わせた新しい連続懸濁重合
4. 6 ガラス球充填層によって作製されるモノマー液滴径の支配因子
4. 7 管型反応器を用いたエマルションの連続重合
実験項:連続液滴作製および連続管型反応器による高分子微粒子の連続合成
5 沈殿重合
5. 1 はじめに
5. 2 沈殿共重合によるポリアクリルアミド粒子の作製
5. 3 NCPAM とアクリルアミドの沈殿共重合
5. 4 N-イソプロピルアクリルアミドの水中沈殿重合
5. 5 おわりに
実験項:酸不溶性カルボン酸モノマーを含むヒドロゲル粒子の作製
6 高分子微粒子表面からのATRP によるグラフト鎖の導入
6. 1 はじめに
6. 2 リビングラジカル重合による高分子微粒子の表面修飾
6. 3 おわりに
実験項:高分子微粒子表面からのATRPによるグラフト鎖の導入
7 RAFT 分散重合
7. 1 はじめに
7. 2 分散重合
7. 3 RAFT 分散重合とブロックコポリマーの自己組織化
7. 4 RAFT 水系分散重合と種々の自己組織体
7. 5 おわりに
実験項:RAFT水系分散重合によるPMPC-PHPMAブロックコポリマー組織の合成
第2章 コロイド化学的手法
1 機能性界面制御剤(AIM)による乳化
1. 1 はじめに
1. 2 AIM 乳化系の特徴
1. 3 シリコーン系両親媒性高分子による乳化
1. 4 ホスホリルコリン類似基を有するジェミニ型両親媒性物質による乳化
1. 5 おわりに
2 一段階乳化による多孔質高分子微粒子の形成
2. 1 はじめに
2. 2 自己乳化現象を利用した「一段階乳化による」多孔質高分子微粒子の形成
2. 3 最後に
実験項:高分子微粒子の作製と物性評価
3 転相温度乳化法により得られるO/W 型ナノエマルションモノマー油滴の
重合による高分子微粒子の合成
3. 1 はじめに
3. 2 転相温度乳化によるO/W 型ナノエマルションの調製
3. 3 O/W 型ナノエマルションモノマー油滴の重合による高分子微粒子の合成
3. 4 おわりに
実験項:PITにより得られるO/W型ナノエマルションモノマー油滴の重合による高分子微粒子の合成
4 ポリマー鎖の会合によって微粒子を作る
4. 1 分子間力によるポリマー鎖の会合
4. 2 疎水性相互作用による微粒子化
4. 3 静電相互作用による微粒子化
4. 4まとめ
実験項:ジスルフィド結合による内部架橋型微粒子の作製
5 ポリ乳酸系両親媒性ポリマーミセル
5. 1 はじめに
5. 2 ラクトソームの粒径制御
5. 3 ラクトソームへの薬剤内包および標識剤の担持によるTheranostics
5. 4 おわりに
実験項:ICG 標識ポリ乳酸内包ラクトソームの作製
低濃度ICG 標識ポリL 乳酸内包ラクトソーム(2 nmol/mg)
第3章 生分解性高分子PLGA 微粒子の調製と医薬・化粧品応用
1 はじめに
2 PLGA ナノ粒子の特徴
3 PLGA ナノ粒子の調製
4 PLGA ナノ粒子の医薬・化粧品への応用
5 おわりに
実験項:水中エマルション溶媒拡散法によるPLGAナノ粒子の調製手順例
【第3編 高分子微粒子の構造制御・機能化】
第4章 分散技術・安定化
1 粒子分散および表面処理の基本
1. 1 粒子の分散
1. 2 表面処理
実験項:酸化チタンへのポリメチルシロキサンの被覆
2 界面設計によるナノ粒子の分散制御
2. 1 はじめに
2. 2 ナノ粒子の分散機構と阻害要因
2. 3 界面構造設計によるナノ粒子分散法の事例
2. 4 ナノ粒子の分散機構の解析法,コロイドプローブAFM 法
2. 5 終わりに
実験項:オレイル基を修飾したFe3O4ナノ粒子合成法
3 ナノ粒子分散系におけるレオロジー
─微細間隙における電場・無電場での流動と流体の微細構造
3. 1 はじめに
3. 2 無電場での流動と流体の微細構造
3. 3 直流電場での流動と流体の微細構造
3. 4 まとめ
実験項:微粒子分散系のレオロジー測定
第5章 形状制御
1 コアシェル微粒子の作製と機能化
1. 1 コアシェル微粒子の特徴と作製方法
1. 2 コアシェル微粒子の機能化と応用
1. 3 微小な反応容器(アトリアクター)としてのコアシェル微粒子
1. 4 微粒子ナノインプリントによるナノ表面層の創製
実験項:シード重合によるコアシェル微粒子の開発
2 Yolk/Shell 構造粒子
2. 1 はじめに
2. 2 Yolk/Shell 構造粒子の合成法
2. 3 可動性コア粒子内包型Yolk/Shell 構造粒子
2. 4 おわりに
実験項:ポリマー層の焼成除去を利用した可動性コア内包型Yolk/Shell 構造粒子の合成
3 高機能化リキッドマーブル
3. 1 はじめに
3. 2 リキッドマーブル
3. 3 機能性リキッドマーブルの合成
3. 4 おわりに
実験項:光応答性リキッドマーブルの作製
第6章 相分離
1 自己組織化析出法による微粒子の創製と機能化
1. 1 自己組織化析出法
1. 2 ポリマーブレンド微粒子
1. 3 ブロック共重合体微粒子
1. 4 反応を利用したナノ構造の形成
1. 5 ナノ構造を持つ微粒子の機能化
1. 6 まとめ
実験項:自己組織化析出法による微粒子の創製と機能化
第7章 異形化~ロッド状微粒子の作製~
1 はじめに
2 ロッド状微粒子
2. 1 無機材料,金属材料からなるロッド状微粒子
2. 2 高分子からなる異形微粒子
2. 3 刺激に応答して形状が変化する微粒子の調製
3 おわりに
実験項:球状微粒子からロッド状微粒子への形状変換方法
第8章 組織化・集積化
1 ハイブリダイゼーションによる微粒子の複合・組織化
1. 1 はじめに
1. 2 微粒子複合・組織化実験
2 コロイド結晶薄膜の形成とその機能発現
2. 1 はじめに
2. 2 コロイド結晶薄膜の成膜
2. 3 構造色が応力で可逆変化する新材料
2. 4 構造材料の歪みの可視化とインフラ検査への応用
2. 5 おわりに
実験項:単分散コロイド粒子懸濁液の合成と調製
3 フッ素系両親媒性高分子を利用した微粒子薄膜の作製と機能
3. 1 はじめに
3. 2 フッ素系両親媒性高分子微粒子薄膜の作製
3. 3 フッ素系両親媒性高分子微粒子薄膜の機能
3. 4 まとめ
実験項:フッ素系両親媒性高分子を利用した微粒子薄膜の作製
4 コロイド系における構造発色
4. 1 はじめに
4. 2 コロイド結晶の構築
実験項:インバースオパールと刺激応答性高分子ゲル微粒子を複合した構造発色性材料
第9章 複合化
1 ポリドーパミンシェルを有する微粒子の作製と機能
1. 1 はじめに
1. 2 PDA の特徴
1. 3 PDA シェルを有する微粒子の作製
1. 4 透明PDA 薄膜による表面改質
1. 5 PDA 複合粒子を用いた構造色材料
1. 6 おわりに
実験項:PSt 粒子をコアとしPDA シェルを有する微粒子の作製
2 ミネラル架橋による微粒子の作製
2. 1 はじめに
2. 2 生体高分子の集積化とミネラル架橋
2. 3 ミネラル架橋部位を利用した物質の担持と放出
2. 4 まとめ
実験項:CaP 架橋型DNA ゲル微粒子(DNA-CaP2)の作製
【第4編 高分子微粒子の測定・分析】
第10章 微粒子およびその表面を測定する分析法
1 はじめに
2 サンプリング法
3 機器分析装置による粒子表面分析
4 微粒子の流動性
5 おわりに
実験項:SEM およびTEM 観察試料の作成
第11章 微粒子のサイズ・ゼータ電位測定
1 はじめに
2 粒子径測定
2. 1 動的光散乱法(DLS:Dynamic Light Scattering)
2. 2 光子相関法(PCS:Photon Correlation Spectroscopy)
2. 3 3つの粒子径分布(散乱強度,体積,個数)
3 粒子径測定の判断基準と測定時の注意点
3. 1 自己相関関数を確認する
3. 2 典型的な自己相関関数の例
3. 3 DLS 測定での注意点
4 ゼータ電位測定
4. 1 微粒子に働く力
4. 2 ゼータ電位と電気的二重層
4. 3 電気泳動
4. 4 電気浸透流の影響
4. 5 ゼータ電位を変化させる要因
4. 6 ゼータ電位測定時の注意点
5 測定事例
5. 1 DLS測定事例〈熱応答性ポリマー〉
5. 2 ゼータ電位評価事例〈無機イオンの吸着〉
6 最後に
第12章 微粒子形状・運動性測定(超音波)
1 はじめに
2 動的超音波散乱法
3 超音波スペクトロスコピー法
4 おわりに
実験項:超音波スペクトロスコピー法のセットアップと解析の流れ
第13章 微粒子の分散凝集状態評価および界面特性評価(NMR)
1 はじめに
2 測定原理
2. 1 緩和時間測定による分散凝集状態の評価及び比表面積の比較
2. 2 緩和時間測定による界面特性評価
3 評価事例
3. 1 カーボンナノチューブの比表面積相対比較~MWCNT の最適な分散条件
3. 2 界面が異なる粒子の添加剤2 種の吸着状態~分散剤のスクリーニング
3. 3 分散剤の最適量評価
3. 4 2種以上分散剤の吸脱着挙動評価
4 おわりに
第14章 微粒子の切片・断面観察
1 はじめに
2 FIB とは
3 FIB による断面加工の特長
4 FIB のための試料準備
5 高分子材料断面に役立つFIB の機能
5. 1 高分解能イメージング機能
5. 2 微細加工機能
6 FIB の化学反応処理
7 FIB による断面加工プロセス
8 Cryo-FIB 加工
第15章 ナノ粒子の粒度分布と内部組織の複合分析
1 はじめに
2 CXDI の原理
3 X線自由電子レーザー施設SACLA
4 SACLAにおける金属ナノ粒子のCXDI 実験
5 金属ナノ粒子のナノ組織と粒径の複合分析
6 おわりに
-

抗菌ペプチドの機能解明と技術利用《普及版》
¥3,960
2017年刊「抗菌ペプチドの機能解明と技術利用」の普及版。抗菌・抗真菌、抗がん活性など幅広い生物活性をもつ「抗菌ペプチド」の医薬・食品への利活用に向けた作用機構、評価、臨床、応用事例をまとめた一冊。
(監修:長岡功)
<a href="http://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=9383"target=”_blank”>この本の紙版「抗菌ペプチドの機能解明と技術利用(普及版)」の販売ページはこちら(別サイトが開きます)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は、2017年当時のものを使用しております。
長岡功 順天堂大学
川村出 横浜国立大学
岩室祥一 東邦大学
若林裕之 森永乳業(株)
橋本茂樹 東京理科大学
田口精一 東京農業大学;北海道大学
山崎浩司 北海道大学 ※「崎」は、たつさきが正式表記
吉村幸則 広島大学
相沢智康 北海道大学
谷口正之 新潟大学
落合秋人 新潟大学
加治屋勝子 鹿児島大学
南雄二 鹿児島大学
中神啓徳 大阪大学
田村弘志 LPSコンサルティング事務所;順天堂大学
JohannesReich University of Regensburg
鈴木香 順天堂大学
伊藤英晃 秋田大学
ニヨンサバフランソワ 順天堂大学
善藤威史 九州大学
角田愛美 阪本歯科医院
永利浩平 (株)優しい研究所
園元謙二 九州大学
北河憲雄 福岡歯科大学
小磯博昭 三栄源エフ・エフ・アイ(株)
米北太郎 日本ハム(株)
岩崎崇 鳥取大学
石橋純 (国研)農業・食品産業技術総合研究機構
-------------------------------------------------------------------------
<<目次>>
【第 I 編 合成・機能解明】
第1章 抗菌ペプチドの構造-機能相関の研究
1 はじめに
2 抗菌ペプチドの構造の特徴と抗菌活性モデル
3 固体NMR分光法
4 ペプチド合成
5 ヘリックス型の抗菌ペプチドの構造
5.1 アラメチシン
5.2 メリチン
5.3 ラクトフェランピン
5.4 グラミシジンA
6 両生類に存在する抗菌ペプチド
6.1 マガイニン2とPGLa
6.2 ボンビニンH2とH4
7 終わりに
第2章 両生類の抗菌ペプチドとその多機能性
1 はじめに
2 両生類の生息環境と皮膚構造
3 両生類抗菌ペプチドの多様なファミリー、多様なサブタイプ
4 両生類抗菌ペプチドの網羅的解析
5 抗菌ペプチドの探索源としての両生類の有用性
6 両生類抗菌ペプチドの多機能性
6.1 抗ウイルス活性
6.2 細菌毒素結合活性
6.3 レクチン様作用
6.4 イムノモデュレーター作用
6.5 マスト細胞脱顆粒作用
6.6 抗酸化作用
7 終わりに
第3章 ラクトフェリンの抗菌・抗ウイルス作用機構
1 ラクトフェリンとは
2 ラクトフェリンの抗菌作用機構
2.1 ラクトフェリンのin vitro抗菌作用
2.2 ラクトフェリシンのin vitro抗菌作用
2.3 ラクトフェリンのin vitro抗バイオフィルム作用
2.4 ラクトフェリンのin vivoでの細菌・真菌感染防御作用
3 ラクトフェリンの抗ウイルス作用機構
4 おわりに
第4章 ラショナルなデザインによる抗菌ペプチドの特性改変
1 はじめに
2 アミノ酸の置換
2.1 疎水性アミノ酸による置換
2.2 塩基性アミノ酸による置換
2.3 疎水性アミノ酸と塩基性アミノ酸による置換
2.4 Dアミノ酸による置換
3 アミノ酸の欠失
4 オリゴペプチドの付加
5 キメラペプチドの形成
6 脂肪酸の付加
6.1 ラウリル酸の付加
6.2 他の脂肪酸の付加
7 非タンパク質性アミノ酸による置換
7.1 アルキルアミノ酸による置換
7.2 嵩高い芳香族アミノ酸による置換
8 おわりに
第5章 昆虫由来抗菌ペプチドの進化工学的高活性化
1 はじめに
2 アピデシン作用機序研究の変遷
3 アピデシンの高活性化
3.1 進化工学システムの基盤整備
3.2 進化工学研究に基づく合理的高活性化へ
4 タナチン作用機序研究の変遷
5 タナチンの高活性化
6 おわりに
第6章 乳酸菌由来の抗菌ペプチド(バクテリオシン)による食中毒菌と腐敗細菌の発育抑制
1 乳酸菌による食品保蔵
2 食品保蔵における非加熱殺菌技術の必要性
3 乳酸菌の産生する抗菌ペプチド(バクテリオシン)
4 食品微生物制御へのバクテリオシン産生乳酸菌の利用
5 バクテリオシン産生乳酸菌による食中毒菌の制御
5.1 プロテクティブカルチャーによる制御
5.2 バクテリオシンを含有する発酵粉末または培養上清による制御
5.3 精製または粗精製バクテリオシンによる制御
5.4 乳酸菌産生バクテリオシンのその他の利用方法
6 バクテリオシンによる腐敗菌の制御
7 抗菌ペプチド耐性菌の出現
8 おわりに
第7章 鳥類生殖器の抗菌ペプチドと感染防御システム
1 はじめに
2 鳥類のToll様受容体
3 鳥類のディフェンシンとカテリシジン
4 ニワトリ卵巣におけるTLRとAvBDの発現特性
5 ニワトリ卵管におけるTLRとAvBDの発現特性
6 卵管の抗菌ペプチド分泌
7 オス生殖器と精子におけるAvBDsの特性
8 おわりに
第8章 抗菌ペプチドの遺伝子組換え微生物を用いた高効率生産技術
1 はじめに
2 大腸菌を宿主とした可溶性での抗菌ペプチドの生産
3 大腸菌を宿主とした不溶性での抗菌ペプチドの生産
4 酵母を宿主とした抗菌ペプチドの生産
5 組換え抗菌ペプチドのNMR解析への応用
6 おわりに
【第 II 編 機能評価・臨床試験】
第1章 病原微生物を標的とした抗菌ペプチドの生体防御に関する多機能性評価
1 はじめに
2 コメα-amylase由来ペプチド(Amyl-1-18)のアミノ酸置換体の設計
3 Amyl-1-18とそのアミノ酸置換体の抗菌活性
4 Amyl-1-18とそのアミノ酸置換体の抗菌作用の機構
4.1 細胞膜損傷作用
4.2 タンパク質合成阻害作用
5 Amyl-1-18とそのアミノ酸置換体の抗炎症活性
6 Amyl-1-18とそのアミノ酸置換体の抗炎症作用の機構
7 Amyl-1-18とそのアミノ酸置換体の創傷治癒作用
8 まとめと今後の課題
第2章 天然物由来抗菌ペプチドの同定および機能性評価
1 抗菌ペプチドの位置づけ
2 特徴
3 植物由来抗菌ペプチドの分子内ジスルフィド結合の重要性
4 今後の展開
第3章 新規抗菌性ペプチドによる難治性皮膚潰瘍治療薬の臨床試験
1 はじめに
2 新規機能性ペプチドAG30/5C
3 皮膚潰瘍を標的とした探索的な臨床研究計画
3.1 評価項目
3.2 選択基準
3.3 除外基準
3.4 試験方法
3.5 併用治療
3.6 解析手法
4 皮膚潰瘍を標的とした探索的な臨床研究結果
4.1 有効性評価
4.1.1 潰瘍面積(cm2)
4.1.2 潰瘍面積の縮小率(%)
4.1.3 菌量
4.2 有効性の結論
4.3 安全性評価
4.3.1 有害事象
4.3.2 臨床検査値の評価
4.4 安全性の結論
5 臨床試験に対する全般的考察
第4章 エンドトキシン測定法と抗菌ペプチド
1 はじめに
2 リムルステストおよびLAL試薬の開発経緯
3 リムルステストの諸方法と最近の進歩
4 リムルス反応に対する干渉因子
5 測定干渉への対処方法
6 エンドトキシンとタンパク質との相互作用
7 生体防御ペプチド中のエンドトキシン測定の意義
8 HDPの抗エンドトキシン活性
9 今後の課題および展望
【第 III 編 技術利用】
第1章 Cathelicidin抗菌ペプチドの作用メカニズムと敗血症治療への応用
1 はじめに
2 cathelicidinの構造と抗菌メカニズム
3 エンドトキシンに対する中和効果
4 敗血症モデル動物に対するcathelicidinペプチドの効果
5 LL-37による宿主細胞活性化のメカニズム
6 新たに明らかになったLL-37のLPS除去作用
7 敗血症治療への応用の可能性と問題点
第2章 納豆抽出抗菌ペプチドの抗がん剤への応用
1 緒言
2 材料及び方法
2.1 材料
2.2 納豆抽出成分
2.3 培養がん細胞
2.4 タンパク質定量及び培養細胞生存率
2.5 Butyl column chromatography
2.6 HPLC、アミノ酸配列
3 結果
3.1 納豆抽出成分のがん細胞に及ぼす影響
3.2 煮豆抽出成分、及び納豆菌のHeLa細胞に及ぼす影響
3.3 納豆抽出成分の他のがん細胞に及ぼす影響
3.4 がん細胞増殖阻止因子の同定
4 考察
第3章 抗菌ペプチドと皮膚疾患
1 はじめに
2 ヒトの皮膚疾患におけるAMPの役割
2.1 乾癬
2.2 アトピー性皮膚炎
2.3 酒さ
2.4 尋常性?創
2.5 全身性エリテマトーデス
2.6 創傷治癒
3 結論と今後の展望
第4章 乳酸菌抗菌ペプチドの口腔ケア剤への応用
1 はじめに
2 乳酸菌が生産する抗菌ペプチド、バクテリオシン
2.1 一般的な性質と分類
2.2 ナイシンの特徴
3 ナイシンの利用
3.1 食品への利用
3.2 非食品用途への利用
4 ナイシンの口腔ケアへの利用
4.1 口腔用天然抗菌剤、ネオナイシン(R)の開発
4.2 ネオナイシン(R)の口腔細菌への効果
4.3 口腔ケア製品、オーラルピース(R)の開発
5 新しい乳酸菌抗菌ペプチドの利用
6 今後の展望
第5章 ヒト上皮組織に対する抗菌ペプチドの作用
1 上皮組織とは
2 ケラチノサイトを取り巻く抗菌ペプチドの種類
3 分化と抗菌ペプチド
3.1 ケラチノサイトに由来する抗菌ペプチド
3.2 分化によるケラチノサイトの抗菌ペプチドの分泌促進
3.3 ケラチノサイト由来抗菌ペプチドによるケラチノサイトの分化
4 抗菌ペプチドと細胞遊走
5 癌細胞と抗菌ペプチド
5.1 抗菌ペプチドによるケラチノサイトの細胞死
5.2 ケラチノサイト由来癌細胞による抗菌ペプチドの分泌
6 最後に
第6章 抗菌ペプチド(リゾチーム、ナイシン、ε-ポリリジン・プロタミン)の食品添加物としての利用
1 はじめに
2 リゾチーム
2.1 リゾチームの抗菌効果
2.2 リゾチームの安定性
2.3 リゾチームの効果的な使い方
3 ナイシン
3.1 ナイシンの抗菌効果
3.2 ナイシンの安定性について
3.3 ナイシンの効果的な使用方法
4 ε-ポリリジン、プロタミン
4.1 ε-ポリリジン、プロタミンの抗菌効果
4.2 ε-ポリリジン、プロタミンの安定性
4.3 ε-ポリリジン、プロタミンの効果的な使い方
5 おわりに
第7章 抗菌ペプチドのプローブとしての利用
1 はじめに
2 プローブに適した抗菌ペプチドのスクリーニング
3 抗菌ペプチドの遺伝子組換え生産
4 ラテラルフロー法への応用
5 まとめ
第8章 昆虫由来の抗菌ペプチドの応用
1 昆虫の生体防御機構
2 昆虫の抗菌ペプチド
3 昆虫抗菌ペプチドの応用:抗生物質
4 昆虫抗菌ペプチドの応用:抗がん剤
5 昆虫抗菌ペプチドの応用:ミサイル療法
6 総括
-

有機エレクトロニクス封止・バリア技術の開発《普及版》
¥4,290
2017年刊「有機エレクトロニクス封止・バリア技術の開発」の普及版。製品展開に欠かせない水蒸気バリア測定についても詳述した、有機エレクトロニクス開発に必須の封止・バリア技術をまとめた一冊。
(監修:蛯名武雄)
<a href="http://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=9384"target=”_blank”>この本の紙版「有機エレクトロニクス封止・バリア技術の開発(普及版)」の販売ページはこちら(別サイトが開きます)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は、2017年当時のものを使用しております。
蛯名武雄 (国研)産業技術総合研究所
占部哲夫 ソニー(株)
清水貴央 NHK放送技術研究所
吉田学 (国研)産業技術総合研究所
沖本忠雄 (株)神戸製鋼所
松村英樹 北陸先端科学技術大学院大学
座間秀昭 (株)アルバック
樫尾幹広 リンテック(株)
大橋健寛 リンテック(株)
西嶋健太 リンテック(株)
塩田聡 大日本印刷(株)
米沢禎久 双葉電子工業(株)
稗田茂 双葉電子工業(株)
中野雅司 ランテクニカルサービス(株)
Sue C. Lewis Corning Incorporated
若林明伸 (株)MORESCO
田中秀康 旭化成(株)
小森常範 東レエンジニアリング(株)
友松弘行 リケンテクノス(株)
野口幸紀 (株)イチネンケミカルズ
平田雄一 信州大学
高萩寿 (株)住化分析センター
井口恵進 (株)テクノ・アイ
馬路哲 住ベリサーチ(株)
今村貴浩 (株)MORESCO
吉田肇 (国研)産業技術総合研究所
鈴木晃 次世代化学材料評価技術研究組合
-------------------------------------------------------------------------
<<目次>>
【第1編 フレキシブル有機エレクトロニクスとバリア技術】
第1章 フレキシブル有機ELディスプレイの開発とバリア技術
1 有機ELディスプレイ進化の経緯
2 フレキシブル有機ELディスプレイの生産方法
3 有機ELディスプレイ素子の劣化
4 有機ELの封止(バリア)技術
第2章 大気安定な逆構造有機ELデバイス
1 はじめに
2 大気安定な逆構構造有機ELデバイスの開発
2.1 フィルム基板に求められる性能
2.2 大気安定な有機ELの開発目的
2.3 大気安定な逆構造有機デバイスの特徴
2.4 発光特性と大気安定性評価
3 逆構造有機ELを用いたディスプレイ試作
4 おわりに
第3章 プリンテッドエレクトロニクスと封止技術
1 はじめに
2 有機半導体に対する外気の影響
3 有機半導体デバイスに対する封止効果
4 有機半導体用封止膜
5 まとめ
【第2編 バリア・封止材料】
第4章 プラズマCVD装置とガスバリア膜
1 はじめに
2 フレキシブルバリア膜形成の課題
3 ロールツーロールプラズマCVD装置
3.1 装置の特長
3.2 プロセスの特長
4 樹脂フィルム向けハイバリア膜成膜
4.1 皮膜の特長
4.2 バリア性に対する基板の平滑性の影響
4.3 バリア性に対するダストの影響
4.4 SiNx膜の形成
5 バリア膜形成用CVD装置
5.1 研究開発用CVDスパッタ両用ロールコータW35シリーズ
5.2 生産用SiOxハイバリア膜ロールコータW60シリーズ
6 まとめ
第5章 Cat-CVD法による有機EL用ガスバリヤ膜作製
1 はじめに
2 Cat-CVD法と作製される膜の特長
3 Cat-CVD膜の有機EL用ガスバリヤ膜としての応用例
4 安全な原料を用いたSiNx系膜作製,および,有機膜作製とその積層ガスバリヤ膜応用
5 まとめ
第6章 ALD法による水蒸気バリア膜
1 はじめに
2 単層膜の特性
3 積層膜の開発と評価
4 量産技術への取り組み
5 おわりに
第7章 粘土膜クレーストと耐熱水蒸気バリア膜の開発
1 粘土を主成分とする耐熱フィルム
2 耐熱ガスバリアフィルムの設計指針-ナノコンポジット化と多積層化
3 粘土を主成分とする耐熱フィルムへの柔軟性付与・透明性向上・ガスバリア性付与
4 粘土を主成分とするフィルムの開発事例
4.1 粘土を主成分とするフィルム
4.2 水熱処理による粘土のアスペクト比の増大とガスバリア性の向上
4.3 耐熱性高分子をバインダーとした粘土フィルム
4.4 耐熱有機カチオン粘土フィルム
4.5 粘土フィルムのその他の特性
5 粘土と改質リグニンからなるハイブリッド膜
6 水蒸気バリア膜
7 耐熱性とガスバリア性の両立に向けて
第8章 フレキシブル有機ELディスプレイ用透明封止シート
1 はじめに
2 封止方法
3 ガスバリアフィルム
3.1 低水蒸気透過性(ハイガスバリア性)
3.2 光学特性
3.3 耐久性
3.4 屈曲性
4 封止剤
4.1 水蒸気透過性
4.2 粘着剤の封止性能
5 封止シートを用いた封止性能評価
6 おわりに
第9章 透明蒸着バリアフィルムの開発
1 ガスバリアフィルムに要求される機能
2 蒸着手法
2.1 CVD方式
2.2 PVD方式
3 ガスバリア性能評価
3.1 IB-PET-PUB
3.2 IB-PET-PXB
3.3 超バリアフィルム
4 まとめ
第10章 有機EL向け乾燥剤
1 はじめに
2 OLEDパネル構造について
3 乾燥剤の捕水メカニズム
4 乾燥剤OleDryのラインナップ
5 充填用乾燥剤(OleDry-F)の特長
5.1 充填剤による有機層のダメージについて
5.2 OleDry-Fの光学特性について
5.3 OleDry-Fの捕水性能について
5.4 充填乾燥剤プロセスフロー
6 パネル構造に対する水分の拡散経路の違い
7 充填用無機乾燥剤の開発
第11章 常温接合によるフレキシブル有機EL封止
1 表面活性化常温接合
2 薄膜を中間層とした常温接合技術
3 Feナノ密着層を用いた常温接合技術
4 有機EL封止工程への常温接合技術の応用
5 フレキシブル有機EL製造工程への常温接合技術の応用
第12章 超薄板フレキシブルガラス
1 はじめに
2 フレキシブルガラスの物理特性
3 機械的信頼性
4 連続加工-R2Rプロセス
5 電子デバイスへのフレキシブルガラスの応用
6 まとめ
第13章 フレキシブル有機EL用封止材
1 フレキシブル有機ELの封止方式について
2 ダム&フィル封止について
3 液状材料を用いた全面封止について
4 PSAフィルムを用いた封止について
5 薄膜封止(TFE:Thin Film Encapsulation)について
6 まとめ
第14章 新しい粘土分散技術を用いたガスバリア膜
1 はじめに
2 目標とするガスバリア膜の設計指針
3 技術的課題
4 技術その1:液晶性粘土の利用
5 技術その2:分散を保持したイオン交換
6 技術その3:有機溶媒置換とアミン添加
7 実際に作成されたガスバリア膜の構造と物性
8 総括および謝辞
第15章 R2Rバリア膜成膜装置の開発
1 はじめに
2 内挿型ICP電極を用いたプラズマCVD法によるバリア膜の形成
3 R2Rバリア膜成膜装置(RTCシリーズ)
3.1 R2R量産対応装置(RTC-V1400)
3.2 研究開発向け小型装置RTC-SV300
4 まとめ
第16章 カバーガラス代替新規プラスチックフィルム
1 はじめに
2 REPTYRDC100の基本特性
3 REPTYRDC100の製品グレードと特徴
4 進化するREPTYRDC100の機能
5 車載用途への展開について
5.1 車内内装部材としての応用
5.2 ウィンドウへの適用
6 おわりに
第17章 ステンレスの電気絶縁/表面平たん化技術
1 はじめに
2 粘土鉱物とは
3 粘土コーティング剤
4 粘土皮膜の利点
【第3編 バリア・封止材料評価技術】
第18章 フィルムのバリア性測定
1 はじめに
2 膜のバリア性能の指標
3 透過装置の測定原理
4 測定結果へのリークの影響
5 測定手順とリークの取り扱いについて
第19章 API-MSを用いた水蒸気バリア測定
1 はじめに
2 API-MS検出器の特徴および原理
3 API-MS法によるフレキシブルバリアフィルム基板のWVTR測定
4 API-MS法などの高感度装置を活用した接着部評価法
5 おわりに
第20章 差圧法DELTAPERMによる水蒸気透過率測定
1 差圧法の歴史的位置づけとDELTAPERM(デルタパーム)
2 ハイバリアフィルム用標準機としてのDELTAPERM
3 DELTAPERMの測定原理
4 差圧法の主な特徴
5 差圧法の顕著な改良
6 高機能向けハイバリアフィルムの生産現場の業界標準器としての推進
第21章 カルシウム法による水蒸気バリア測定
1 カルシウム法の概要
2 光学測定法
3 電気測定法
4 面積測定法
5 カルシウム法の課題と最近の取り組み
6 その他の測定法
7 まとめ
第22章 質量分析器を用いた水蒸気バリア測定
1 はじめに
2 ガス・水蒸気透過率測定装置
3 高速・高感度のガス・水蒸気透過率測定装置(スーパーディテクト)の測定原理
4 まとめ
第23章 水蒸気バリア性測定におけるトレーサビリティの確保
1 トレーサビリティとは
2 不確かさとは
3 国家標準と国際標準
4 水蒸気バリア性測定のトレーサビリティとは
4.1 キャリアガスの流量と水蒸気濃度とから水蒸気透過度を求める方法
4.2 ガスクロマトグラフ法
4.3 差圧法
4.4 質量分析法
5 水蒸気バリア性測定に関連する国家標準
5.1 標準ガス
5.2 湿度標準
5.3 圧力真空標準と標準コンダクタンスエレメント (SCE)
6 標準ガスバリアフィルムの開発状況
7 まとめ
第24章 有機EL素子における水蒸気バリア性評価手法の信頼性検討
1 はじめに
2 バリア性能の評価指標と測定装置
3 有機EL素子用封止材の水蒸気バリア性能評価
3.1 バリアフィルムの水蒸気バリア性評価
3.2 接着材の水蒸気バリア性評価技術
4 おわりに
-

ポリイミドの機能向上技術と応用展開《普及版》
¥3,960
2017年刊「ポリイミドの機能向上技術と応用展開」の普及版。ポリイミドの物性・構造を深く理解し、機能化に向けた分子設計、応用展開事例等を把握できる1冊。
(監修:松本利彦)
<a href="http://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=9376"target=”_blank”>この本の紙版「ポリイミドの機能向上技術と応用展開(普及版)」の販売ページはこちら(別サイトが開きます)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は、2017年当時のものを使用しております。
松本利彦 東京工芸大学
後藤幸平 後藤技術事務所
森川敦司 茨城大学
長谷川匡俊 東邦大学
早川晃鏡 東京工業大学
寺境光俊 秋田大学
山田保治 神奈川大学
古川信之 佐世保工業高等専門学校
市瀬英明 長崎県工業技術センター
竹市力 豊橋技術科学大学名誉教授
岩佐怜穂 明治大学
風間伸吾 明治大学
永井一清 明治大学
津田祐輔 久留米工業高等専門学校
石田雄一 (国研)宇宙航空研究開発機構
前田郷司 東洋紡(株)
富川真佐夫 東レ(株)
村上睦明 (株)カネカ;大阪大学招聘教授
難波江裕太 東京工業大学
金子達雄 北陸先端科学技術大学院大学
劉貴生 国立台湾大学
-------------------------------------------------------------------------
<<目次>>
【第1編 ポリイミドの合成・分子設計】
第1章 ポリイミドの機能化設計のための構造・特性と機能発現の制御
1 ポリイミドの構造と分類
2 ポリイミドの開発の歴史とエンプラ系での耐熱性の位置づけ
3 ポリイミド構造と特性の関係
3.1 ポリイミド固有の構造因子
3.1.1 一次構造因子(化学構造)
3.1.2 高次構造因子(電荷移動錯体形成による分子内・分子間相互作用)
4 おわりに
第2章 ポリイミドの合成
1 はじめに
2 二段階合成法
2.1 ポリアミド酸を経由する方法
2.2 ポリアミド酸誘導体を経由する方法
3 一段階合成法
3.1 高温溶液合成法
3.2 イオン液体中での合成
3.3 ジイソシアネートを用いる合成
3.4 テトラカルボン酸ジチオ無水物を用いる合成
3.5 溶媒を用いない合成
4 ポリイソイミドを経由する三段階合成法
5 反応溶液からの相分離を利用して成型体を作製する方法
【第2編 ポリイミドの機能向上技術動向―設計・処理・複合/アロイ化・評価―】
第1章 無色透明ポリイミドの分子設計と高性能化技術
第2章 溶液加工性を有する低熱膨張性透明ポリイミド
1 透明耐熱樹脂の必要性
2 ポリイミドフィルムの着色の抑制と低熱膨張化のための方策
2.1 透明性に及ぼす因子
2.2 ポリイミドの化学構造と透明性の関係
2.3 ポリイミドフィルムの透明性に及ぼす化学構造以外の因子
2.4 ポリイミドの化学構造と低熱膨張特性の関係、およびモノマーの選択
2.5 線熱膨張係数を測定する際の留意点
3 低熱膨張係数と高透明性を同時に実現するポリイミド系の探索
3.1 脂環式ジアミンを用いる系
3.1.1 ポリイミド前駆体を重合する際の問題点
3.1.2 trans-1,4-CHDAより得られるPIフィルムの低熱膨張性
3.2 脂環式テトラカルボン酸二無水物と芳香族ジアミンからなる系
3.2.1 脂環式テトラカルボン酸二無水物の重合反応性とその他の問題
3.2.2 フィルム物性
3.3 溶液キャスト製膜により低熱膨張性で可撓性のある透明耐熱フィルムを与える系
3.3.1 溶媒溶解性の改善に付随する好都合な特性
3.3.2 CBDAを用いる系
3.3.3 脂環式モノマーに頼らずに要求特性に近づく試み
4 おわりに
第3章 自己組織化を利用する多孔化ポリイミド膜の創成
1 はじめに
2 高周期性ポーラスポリイミド膜の創製
2.1 分子間相互作用を利用する高周期性ポリイミド前駆体(ポリアミド酸コンポジット)のナノ構造制御
2.2 ポリアミド酸コンポジット膜(BCP/PAA膜)の調製とポーラスポリイミド化
2.3 高温加熱処理によるBCP/PAA膜の炭素化
2.4 BCP/PAA膜の高温熱処理膜の三角相図
2.5 BCP/PAAコンポジット薄膜におけるナノ構造制御
3 おわりに
第4章 多分岐ポリイミドの合成と機能化
1 多分岐ポリマー(ハイパーブランチポリマー)とは
2 AB2型モノマーの自己重縮合によるハイパーブランチポリイミドの合成
3 A2型,B3型モノマーの重縮合によるハイパーブランチポリイミドの合成
4 まとめ
第5章 多分岐ポリイミド-シリカハイブリッドの合成と特性
1 はじめに
2 PI系複合材料の合成
2.1 PI-SiO2 HBDの合成
2.2 HBPI-SiO2 HBDの合成
3 HBPI-SiO2 HBDの特性
4 HBPI-SiO2 HBDの応用
4.1 多孔性ポリイミド
4.2 気体分離膜
5 おわりに
第6章 熱可塑性ポリイミド/ポリヒドロキシエーテル系ポリマーアロイ
1 はじめに
2 ポリ(ヒドロキシエーテル)(PHE)の基礎
3 熱可塑性ポリイミドの基礎
4 ポリマーアロイの基礎
5 熱可塑性ポリイミド/ポリヒドロキシエーテル系ポリマーアロイ
5.1 主鎖にアミド構造を有するPHE(アミド構造含有PHE)
5.2 有機溶剤に可溶な熱可塑性ポリイミド
5.3 PHE/PI系ポリマーアロイフィルムの調製方法
5.4 PHEおよびPHE/PI系ポリマーアロイの熱機械的特性
5.5 PHEおよびPHE/PI系ポリマーアロイの化学的耐熱性
5.6 PHE/PI系ポリマーアロイの相溶性
5.7 PHEおよびPHE/PI系ポリマーアロイの表面構造
5.8 PHEおよびPHE/PI系ポリマーアロイの防湿性
6 おわりに
第7章 ポリイミドハイブリッド膜のガス透過性とガス分離性
1 はじめに
2 ポリイミドハイブリッド膜開発の方向性
3 イオン液体ハイブリッド膜
3.1 液膜~ガス吸収液含有まで
3.2 イオン液体
4 ABAトリブロックコポリマー型ハイブリッド膜
4.1 ABAトリブロックコポリマー
4.2 PMMA
4.3 アダマンタン
4.4 POSS
5 おわりに
第8章 紫外線照射表面濡れ性制御ポリイミド
1 はじめに
2 紫外線照射濡れ性制御ポリイミドの合成と物性評価
3 長鎖アルキル基を有する紫外線照射濡れ性制御ポリイミド
4 天然物骨格に基づく紫外線照射濡れ性制御ポリイミド
5 不飽和長鎖アルキル基を有する紫外線照射濡れ性制御ポリイミド
6 光反応性の官能基を有する紫外線照射濡れ性制御ポリイミド
7 各種の表面分析
8 おわりに
第9章 ポリイミド/炭素繊維複合材料の作製と強度評価
1 はじめに
2 CFRPマトリックス用ポリイミドの分子設計
2.1 成形材料に求められる条件
2.2 反応性末端剤
3 プリプレグ用熱硬化性ポリイミド樹脂
3.1 プリプレグ/オートクレーブ成形の概要
3.2 PMR-15
3.3 PETI-5
3.4 TriA-PI
3.5 TriA-SI
3.6 TriA-X
3.7 PETI-340M
4 レジントランスファーモールディング(RTM)用熱硬化性ポリイミド樹脂
4.1 RTM成形の概要
4.2 PETI-330
5 熱可塑性ポリイミド樹脂
6 まとめ
【第3編 ポリイミドの応用展開】
第1章 耐熱・低線膨張ポリイミドフィルムとその応用
1 はじめに
2 ポリイミド
3 XENOMAX(R)の特性
3.1 CTE:線膨張係数
3.2 粘弾性特性
3.3 機械特性,熱収縮率,電気特性
3.4 耐薬品性
3.5 ガス透過性
3.6 難燃性
4 XENOMAX(R)の応用技術
4.1 半導体パッケージ用サブストレート
4.1.1 ビルドアップ層
4.1.2 コア層
4.2 三次元実装パッケージ
4.3 無機薄膜形成用フレキシブル基板
4.3.1 誘電体薄膜,厚膜
4.3.2 半導体薄膜
5 まとめ
第2章 感光性ポリイミドの展開と将来動向
1 はじめに
2 電子材料への展開
3 リチウムイオン電池への展開
4 ディスプレイ分野への展開
5 イメージセンサーへの展開
6 おわりに
第3章 ポリイミドからのグラファイト作製と応用
1 緒言
2 ポリイミド(PI)からグラファイトへ
2.1 PIの熱分解反応
2.2 炭素前駆体の形成
2.3 グラファイト化反応
3 PIより得られるグラファイトの物性
3.1 理想的グラファイトの物性
3.2 グラファイト膜(Graphinity)の物性
3.3 グラファイトブロック(GB)の物性
3.4 超薄膜グラファイトの物性
4 グラファイトの応用
4.1 放熱シートとしての応用
4.2 グラファイトブロック(GB)の応用
4.3 グラファイト超薄膜の加速器応用
5 結論
第4章 ポリイミドガス分離膜の設計開発
1 はじめに
2 高分子膜のガス透過モデル
3 膜材料としてのポリイミド
4 ポリイミドの分離性能
5 ポリイミド膜の分離性能向上
5.1 拡散係数(D)の増大
5.2 架橋構造の導入による拡散係数(D)の制御
5.3 炭化による拡散係数の制御
5.4 溶解係数(S)の向上
5.5 ブロックコポリマーによる拡散係数(D)と溶解係数(S)の制御の可能性
5.6 他素材とのハイブリッドとその他の方法
6 ポリイミド膜の展望
6.1 酸素富化空気の製造:O2/N2分離
6.2 CO2回収技術
7 おわりに
第5章 芳香族ポリイミドの炭素化による燃料電池用カソード触媒
1 はじめに
2 研究背景
3 カーボン系カソード触媒の機能・要求特性
4 ポリイミド微粒子から作製したカーボン系カソード触媒の性能
5 ポリイミド微粒子の作製法、および炭素化法
6 メソポーラス化の取り組み
7 おわりに
第6章 バイオポリイミドの開発と有機無機複合化による透明メモリーデバイスの作製
1 芳香族生体分子
2 バイオ芳香族ジアミン
3 芳香族バイオポリイミドの合成
4 有機無機複合化
5 おわりに
-

泡の生成メカニズムと応用展開《普及版》
¥3,850
2017年刊「泡の生成メカニズムと応用展開」の普及版。洗浄料・化粧品・食品・医薬品などさまざまな分野で利用されている泡について、その評価法、応用展開までをまとめた1冊!
(監修:野々村美宗)
<a href="http://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=9379"target=”_blank”>この本の紙版「泡の生成メカニズムと応用展開(普及版)」の販売ページはこちら(別サイトが開きます)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は、2017年当時のものを使用しております。
野々村美宗 山形大学
坂井隆也 花王(株)
村上 良 甲南大学
幕田寿典 山形大学
伊藤豊文 川研ファインケミカル(株)
小山匡子 太陽化学(株)
森垣篤典 ライオン(株)
吉村倫一 奈良女子大学
脇田和晃 日油(株)
兼井典子 曽田香料(株)
遠藤知佳 ライオン(株)
吉川貴士 三洋貿易(株)
柿澤恭史 ライオン(株)
角本次郎 日進化学(株)
鈴木 亮 帝京大学
小俣大樹 帝京大学
小田雄介 帝京大学
丸山一雄 帝京大学
土屋好司 東京理科大学
-------------------------------------------------------------------------
<<目次>>
第Ⅰ編 泡に関する最新研究動向
第1章 泡の生成・消滅プロセス
第2章 起泡力と泡安定性
1 はじめに
2 起泡力と泡安定性
3 起泡力
3. 1 泡沫体積の時間変化という考え方
3. 2 少ない力で立つ泡という考え方(動的表面張力と起泡力)
3. 3 動的表面張力の考え方と取扱い
4 泡安定性
4. 1 排液に影響を与える因子
5 起泡力と泡安定性の測定
5. 1 Ross-Miles 試験
5. 2 起泡力の測定
6 おわりに
第3章 微粒子で安定化された泡およびドライリキッド
1 はじめに
2 微粒子の流体界面吸着
3 微粒子の濡れ性と微粒子で安定化された分散系のタイプの関係
4 空気-水分散系の安定化と転相現象
5 空気-水分散系の安定化に対する界面活性剤の添加や水相のpH および塩濃度変化の効果
5. 1 親水的な微粒子の界面活性剤吸着に伴う疎水化
5. 2 疎水的な微粒子の界面活性剤吸着に伴う親水化
5. 3 水相のpH および塩濃度変化
6 カタストロフィック転相
7 空気-液体分散系の安定化:ドライオイルや油の泡
8 L/A 分散系の応用例
8. 1 ドライリキッドを用いたエマルションの作製
8. 2 マルチプルドライリキッド
9 おわりに
第4章 泡による洗浄機能の革新
1 はじめに
2 泡と皮膚へのマイルド性
3 泡と皮脂の洗浄力
4 おわりに
第5章 マイクロバブル
1 はじめに
2 超音波を利用したマイクロバブルの生成メカニズム
2. 1 マイクロバブル生成現象
2. 2 界面の時間的挙動と気泡生成メカニズム
3 超音波ホーンを利用したマイクロバブル発生
4 超音波マイクロバブルを利用して作る中空マイクロカプセル
4. 1 シアノアクリレート中空マイクロカプセル製法の概要
4. 2 中空マイクロカプセル調製結果
5 おわりに
第Ⅱ編 起泡性製剤の原料
第6章 アミノ酸系界面活性剤
1 はじめに
2 主要なアシルアミノ酸塩
2. 1 アシルグルタミン酸塩
2. 2 アシルグリシン塩
2. 3 アシルサルコシン塩
2. 4 アシルメチル-β-アラニン塩
2. 5 アシルアスパラギン酸塩
2. 6 アシルシルクアミノ酸塩
2. 7 新規アニオン性界面活性剤
3 パーソナルケアへの応用
3. 1 泡立ちと泡質
3. 2 配合時の粘度
3. 3 コアセルベートの形成
4 その他の用途
第7章 アルキルリン酸塩
1 はじめに
2 アルキルリン酸塩の界面化学的性質
3 アルキルリン酸塩による液晶形成とエマルションの安定化
4 アルキルリン酸塩の洗浄・起泡力
5 おわりに
第8章 ポリグリセリン系界面活性剤
1 はじめに
2 ポリグリセリンの構造
3 ポリグリセリン脂肪酸エステル(PGFE)の特徴
3. 1 PGFE の曇点
3. 2 臨界ミセル濃度(CMC)
3. 3 PGFE-水2 成分の相図
3. 4 PGFE の起泡性
4 起泡性ラウリン酸デカグリセリンの特長
5 テトラグリセリンラウリルエーテルの特長
6 まとめ
第9章 アルファスルホ脂肪酸エステルナトリウム
1 はじめに
2 α-SFE の基本物性と界面活性能
2. 1 α-SFE の製法
3 α-SFE の家庭用粉末洗剤への応用
第10章 ジェミニ型界面活性剤
1 はじめに
2 ジェミニ型界面活性剤
3 四級アンモニウム塩ジェミニ型カチオン界面活性剤
4 カルボン酸塩ジェミニ型アニオン界面活性剤
5 ベタイン系ジェミニ型両性界面活性剤
6 異種親水基を含むヘテロジェミニ型界面活性剤
7 異種疎水鎖を含むハイブリッドジェミニ型界面活性剤
8 糖含有ジェミニ型非イオン界面活性剤
9 おわりに
第11章 長鎖PEG を有する非イオン性活性剤の泡質改善
1 はじめに
2 ラウリン酸PEG-80 ソルビタン(PSL)の泡質改善効果
3 ポリオキシエチレンアルキルエーテル(PAE)を用いた泡物性評価
3. 1 使用したPAE とそれらの物性
3. 2 泡弾性のひずみ依存性測定
3. 3 泡の粘弾性測定
3. 4 IR による泡膜測定
4 泡質改善メカニズム関する考察
5 おわりに
第12 章 界面活性剤水溶液の起泡性に及ぼす香料の影響
1 はじめに
2 香料
2. 1 香料とは
2. 2 界面活性剤水溶液への香料の可溶化
3 SDS水溶液の起泡性に及ぼす香料化合物の影響
3. 1 SDS水溶液の泡立ちに及ぼす香料化合物の影響
3. 2 SDS水溶液の泡の安定性に及ぼす香料化合物の影響
4 SDS水溶液の起泡性に及ぼす調合香料の影響
5 シャンプーの起泡性に及ぼす香料の影響
6 おわりに
第13章 消泡剤
1 はじめに
2 泡の消えるプロセスとそのコントロール
3 物理的な消泡技術
4 化学的な消泡技術
5 新しい消泡剤とそのメカニズム
6 おわりに
第Ⅲ編 泡の評価法
第14章 動的表面張力
1 はじめに
2 起泡に関わる物理的因子
3 動的表面張力の測定方法
3. 1 振動ジェット法(振動液柱法)
3. 2 最大泡圧法(バブルプレッシャー法)
4 表面吸着速度の解析理論
5 界面活性剤水溶液の起泡性の評価
第15章 泡安定性の測定
1 はじめに
2 泡安定性の注意点
3 測定法
3. 1 泡体積の目視測定
3. 2 ロス=マイルス試験法
3. 3 泡の大きさの評価
3. 4 泡からの液の排出の評価
4 泡安定性の自動評価
5 おわりに
第16章 表面粘弾性の測定
1 はじめに
2 Gibbs 弾性とMarangoni 効果
3 表面粘弾性の測定方法
4 おわりに
第17章 レオロジー
1 はじめに
2 レオロジーの基本
2. 1 レオロジーとは
2. 2 弾性・粘性,粘弾性
3 定常流測定
3. 1 実際の測定
3. 2 泡の測定例
4 動的粘弾性測定
4. 1 実際の測定
4. 2 泡の測定例
5 時間とともに消える泡の動的粘弾性測定
5. 1 泡の寿命の数値化
5. 2 泡の寿命測定と感触
6 時間とともに消える泡の定常流測定
6. 1 泡の特徴時間の測定
6. 2 泡の特徴時間と感触
7 まとめ
第18章 シャンプー・ボディソープ等身体洗浄剤の使用感に関わる泡の評価法
1 はじめに
2 身体洗浄剤の種類と泡の特徴
2. 1 ボディソープ
2. 2 ヘアシャンプー
3 身体洗浄剤の使用感に関わる泡の評価法
3. 1 官能評価
3. 2 起泡力の評価
3. 3 泡沫安定性の評価
3. 4 泡沫のレオロジー
4 おわりに
第Ⅳ編 化粧品、医薬品等における応用展開
第19章 エアゾール製品の泡と化粧品への応用
1 エアゾール製品とは
2 エアゾール製品に使用する噴射剤
3 エアゾール製品の泡
4 クラッキングフォーム
5 炭酸ガスを用いた泡状エアゾール製品の開発
6 炭酸ガスの作用
7 炭酸ガスを泡の中に閉じ込める技術
8 炭酸ガスによる肌質改善効果
9 おわりに
第20章 マイクロバブル・ナノバブルの医療への応用
1 はじめに
2 超音波イメージング
3 超音波造影剤(マイクロバブル)
4 標的指向型超音波造影剤の開発
5 ナノバブルの開発
6 微小気泡を利用した超音波抗がん剤デリバリー
7 脳への薬物デリバリー
8 おわりに
第21章 マイクロバブル
1 はじめに
2 超音波診断
3 超音波診断用造影剤
4 抗体標識微小気泡を用いた超音波分子イメージング
4. 1 超音波診断用造影バブルの微小化
4. 2 抗体標識微小気泡の肝癌細胞への集積性
5 おわりに
第22章 起泡性化粧品の処方設計
1 処方設計の考え方
2 起泡剤
2. 1 アニオン界面活性剤
2. 2 両性界面活性剤
2. 3 ノニオン界面活性剤
3 増泡剤
-

車載用リチウムイオン電池の高安全・評価技術《普及版》
¥4,950
2017年刊「車載用リチウムイオン電池の高安全・評価技術」の普及版。車載用リチウムイオン電池の安全性に関する概論から、電池開発、各種材料、パッケージ技術、劣化評価解析、市場分析についても解説した1冊!
(監修:吉野彰・佐藤登)
<a href="http://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=9378"target=”_blank”>この本の紙版「車載用リチウムイオン電池の高安全・評価技術(普及版)」の販売ページはこちら(別サイトが開きます)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は、2017年当時のものを使用しております。
吉野彰 旭化成(株)
佐藤登 名古屋大学;エスペック(株)
鳶島真一 群馬大学
高見則雄 (株)東芝
江守昭彦 日立化成(株)
小林弘典 (国研)産業技術総合研究所
常山信樹 住友金属鉱山(株)
武内正隆 昭和電工(株)
堀尾博英 森田化学工業(株)
西川聡 帝人(株)
山田一博 東レバッテリーセパレータフィルム(株)
河野公一 東レバッテリーセパレータフィルム(株)
薮内庸介 日本ゼオン(株)
脇坂康尋 日本ゼオン(株)
山下孝典 大日本印刷(株)
右京良雄 京都大学
末広省吾 (株)住化分析センター
新村光一 (株)本田技術研究所
野口実 (株)本田技術研究所
中村光雄 (株)SUBARU
梶原隆志 エスペック(株)
奥山 新 エスペック(株)
楠見之博 (株)コベルコ科研
辰巳砂昌弘 大阪府立大学
林晃敏 大阪府立大学
井手仁彦 三井金属鉱業(株)
所千晴 早稲田大学
大和田秀二 早稲田大学
薄井正治郎 JX金属(株)
稲垣佐知也 (株)矢野経済研究所
-------------------------------------------------------------------------
<<目次>>
【第I編 総論】
第1章 リチウムイオン電池の安全性に関する一考察
1 はじめに
2 車載用リチウムイオン電池の市場動向
3 安全性に関する技術進歩
3.1 無機物層表面被覆
3.2 Thermal Runaway抑制技術の進歩
3.3 固体電解質電池の登場
4 安全性向上に関する今後の展開方向
第2章 車載用リチウムイオン電池の安全性概論
1 自動車業界間に課せられる環境規制と各社のビジネスモデル
2 欧州勢を中心としたEV動向と各社戦略
3 群雄割拠となるEVワールド
4 電池業界の動向と戦略
4.1 自動車業界と一体化した日本の電池業界
4.2 日韓電池業界の今後の課題
5 車載用電池の信頼性・安全性確保に関するビジネスモデル
5.1 各種電池の事故・リコールの歴史
5.2 受託試験ビジネスと認証事業による開発効率向上
6 日本の部材各社のビジネスモデル
7 次世代革新電池研究から電池事業ビジネスモデルまで
【第II編 リチウムイオン電池の高安全化技術】
第3章 安全性の現状、課題と向上策
1 はじめに
2 リチウムイオン電池の市場トラブル例
2.1 事故原因の解析と対策品の安全性
2.2 電池の複数社調達(供給)
2.3 液漏れの課題
3 リチウムイオン電池の安全性評価の基本的な考え方
4 リチウムイオン電池の安全性試験
4.1 重要試験項目
4.2 内部短絡試験
5 完全放電状態の電池の熱暴走
6 まとめと今後の展開
第4章 安全、高出入力、長寿命性能に優れたチタン酸リチウム負極系二次電池
1 諸言
2 電池性能と安全性の課題
3 基本性能と安全性
3.1 LTO粒子のLi吸蔵・放出反応の速度論
3.2 LTO負極系二次電池の特長
3.3 安全技術
3.4 高出力型LTO/LMO系セル
3.5 高エネルギー型LTO/NCM系セル
4 今後の展望
第5章 電池制御システムによる高安全化技術
1 まえがき
2 電池制御アーキテクチャ
2.1 電池制御回路
2.2 電池制御専用IC
2.3 均等化回路
3 電池制御ソフト
3.1 ソフト構成
3.2 電池制御パラメータの定義
3.2.1 SOC
3.2.2 SOH
3.2.3 許容電流(電力)
4 高安全、高信頼システム
4.1 漏電検出
4.2 フェールセーフ
5 むすび
【第III編 電池材料から見た安全性への取り組み】
第6章 電気自動車用リチウムイオン電池
1 はじめに
2 車載用LIBのセル設計
3 車載用LIBの材料構成
4 高性能化へ向けた材料開発の進展
5 安全性の視点からの考察
6 おわりに
第7章 正極活物質用非鉄金属原料確保の必要性
1 BEV伸長には非鉄金属原料確保が必須
2 ニッケルは大丈夫か?
3 BEV向け正極活物質用ニッケルをさらに確保するために
3.1 ニッケル資源の新規開発
3.2 電気ニッケルの使用
3.3 リサイクル推進
4 コバルトは危機的状態
5 コバルト対策は?
5.1 新規ニッケル鉱山開発からのバイプロダクトに期待
5.2 コバルト使用量の削減
5.2.1 NCAの優位性
5.2.2 LFPはコバルトを使用しないという点が魅力
5.2.3 PHV、HEVとの共存
6 マンガンは心配いらない
7 ここ数年間、リチウムは供給タイト
7.1 Big4の動向
7.2 新興勢力
8 おわりに
第8章 負極材料
1 はじめに:昭和電工の黒鉛系Liイオン二次電池(LIB)関連材料紹介
2 炭素系LIB負極材料の開発状況
2.1 LIB負極材料の種類と代表特性
2.2 LIB要求項目
2.3 各種炭素系LIB負極材料の特性
3 人造黒鉛負極材のサイクル寿命、保存特性、入出力特性の改善
3.1 人造黒鉛SCMG(R)-ARの特徴
3.2 人造黒鉛SCMG(R)(AGr)、表面コート天然黒鉛(NGr)の耐久試験後の解析
3.3 人造黒鉛SCMG(R)の急速充放電性(入出力特性)改良
3.4 人造黒鉛SCMG(R)のさらなる高容量化:Si黒鉛複合負極材の開発
4 VGCF(R)のLIB負極用導電助剤としての状況
第9章 電解質系
1 はじめに
2 中国における電気自動車と電解質の市場動向
3 電解質の種類
3.1 LiPF6
3.2 LiBF4
3.3 LiTFSI
3.4 LiFSI
3.5 LiPO2F2
4 電解質に対する顧客の要求
5 中国における原材料調達
6 車載用の電池と電解質
7 電解質の安全性について
8 中国における電池及び電解質事業の実態
9 北米及び欧州における電池及び電池材料
10 電気自動車市場の真実
11 まとめ
第10章 セパレータ
1 はじめに
2 ポリオレフィン微多孔膜とシャットダウン機能
3 耐熱加工ポリオレフィン微多孔膜
4 不織布セパレータ
5 接着層加工ポリオレフィン微多孔膜
6 おわりに
第11章 高エネルギー密度・高入出力化に向けたセパレータ材料の安全性への取り組み
1 リチウムイオン二次電池とその動向
1.1 リチウムイオン二次電池の登場
1.2 LIBのセル種とその用途拡大
1.3 LIBの高エネルギー密度化と高入出力化
2 LIBセパレータの役割
2.1 第1の役割「極板間の電子的絶縁性」
2.2 第2の役割「極板間のイオン伝導性」
2.3 第3の役割「LIB長期寿命への寄与」
2.4 第4の役割「高LIB安全化への寄与」
3 LIBセパレータの製造プロセス
4 LIBセパレータの製品設計
4.1 高エネルギー密度化・高入出力密度化に向けた製品設計
4.2 高安全化に向けた製品設計
5 LIBセパレータの技術動向
5.1 高強度化/薄膜化、圧縮性制御(機械的性質関連)
5.2 シャットダウン(閉孔)の低温化
5.3 熱破膜(メルトダウン)の高温化
5.4 高電圧化対応
5.4.1 セパレータ表面の酸化現象
5.4.2 セパレータの酸化抑制
5.5 細孔構造制御
5.6 その他技術動向
6 次世代に向けて
6.1 デンドライト成長検出技術
6.2 評価技術の高度化
7 最後に
第12章 機能性バインダー
1 はじめに
2 リチウムイオン二次電池用機能性バインダー
3 負極用バインダー
3.1 車載用負極バインダーに求められる特性
3.2 長期繰り返し使用における電極の膨らみへの対応
3.3 シリコン系活物質への対応
4 セパレータ関連材料
4.1 LIB内への耐熱層の導入
4.2 セパレータの耐熱収縮性向上
4.3 セラミック層の配置場所による比較
5 おわりに
第13章 パッケージングの技術と電池の安全性
1 DNPバッテリーパウチの歴史
2 バッテリーパウチの安全性
3 製品へ要求される性能
3.1 成形性
3.2 耐電解液性
3.3 水蒸気バリア性
3.4 気密性
3.5 絶縁性
3.6 耐熱性/耐寒性
4 ラミネートフィルム生産工程と品質
5 電池評価技術
6 バッテリーパウチの課題
【第IV編 リチウムイオン電池の解析事例】
第14章 リチウムイオン電池の高温耐久性と安定性
1 はじめに
2 電池特性評価
3 サイクル試験による特性変化および解析
3.1 サイクル試験による特性変化と電気化学的解析
3.2 電極評価・解析
4 Mg置換による(LiNi0.8Co0.15Al0.05O2)の安定化
5 まとめ
第15章 リチウムイオン電池の高性能化に向けた分析評価技術
1 はじめに
2 電極構造の数値化
2.1 概要
2.2 電極内の空隙構造
2.3 導電助剤分散・導電性ネットワーク
2.4 バインダの偏在・剥離強度
3 三次元空隙ネットワーク解析によるリチウムイオン電池電極の評価法
3.1 概要
3.2 実験方法
3.3 結果と考察
4 充放電中の電極活物質の構造変化を知るためのその場分析
4.1 概要
4.2 低温下におけるリチウムイオン電池のin situ分析
4.2.1 概要
4.2.2 実験方法
4.2.3 結果と考察
4.3 電極断面のRamanイメージング
4.3.1 概要
4.3.2 実験方法
4.3.3 結果と考察
5 複合的分析手法によるLIB劣化原因の解析
5.1 概要
5.2 実験方法
5.3 結果と考察
6 まとめ
【第V編 安全性評価技術】
第16章 自動車メーカーから見る安全性評価技術
1 はじめに
2 車両に搭載される電池の特徴
3 車両に搭載される電池の安全性
4 各国の安全性評価基準
4.1 SAE J2464
4.1.1 一般試験指針
4.1.2 有害物監視
4.1.3 機械的試験
4.1.4 熱的非定常試験
4.1.5 電気的非定常試験
4.2 GB/T 31485-2015
4.2.1 GB/T 31485-2015セル安全試験
4.2.2 GB/T 31485?2015電池モジュール安全試験
4.2.3 UN R100 Part2
4.3 UN38.3
5 車両搭載電池の安全性における今後の展望
第17章 次世代自動車におけるリチウムイオン二次電池の使い方と評価
1 はじめに
2 電動車両と蓄電デバイス
3 電動車両向け蓄電システムの出力/容量比
4 車種ごとに異なる使い方とマネージメント
4.1 BEV(電気自動車)
4.1.1 充放電パターン
4.1.2 REESSのエネルギマネージメント(BEV)
4.2 HEV(ハイブリッド自動車)
4.2.1 充放電パターン
4.2.2 REESSのエネルギマネージメント(HEV)
4.3 PHEV(プラグインハイブリッド自動車)
4.3.1 充放電パターン
4.3.2 REESSのエネルギマネージメント(PHEV)
5 電池劣化の車両への影響
6 自動車用蓄電デバイスの評価
6.1 REESSの試験標準
6.1.1 ISO12405-1
6.1.2 ISO12405-2
6.1.3 ISO12405-3
6.2 REESSの安全性基準
6.3 その他の評価試験
7 終わりに
第18章 安全性評価の認証
1 はじめに
2 安全性評価の重要性
3 国連協定規則
4 UN ECE R100.02 PartIIについて
5 UN ECE R100.02 PartIIの安全性試験
5.1 Vibration(振動)[附則8A]
5.2 Thermal shock and cycling(熱衝撃およびサイクル試験)[附則8B]
5.3 Mechanical shock(メカニカルショック)[附則8C]
5.4 Mechanical integrity(メカニカルインテグリティー)[附則8D]
5.5 Fire resistance(耐火性)[附則8E]
5.6 External short circuit protection(外部短絡保護)[附則8F]
5.7 Overcharge protection(過充電保護)[附則8G]
5.8 Over-discharge protection(過放電保護)[附則8H]
5.9 Over-temperature protection(過昇温保護)[附則8I]
6 認可取得までのプロセス
7 おわりに
第19章 安全性評価の受託
1 はじめに
2 外部短絡試験における温度依存性の検証
2.1 自動車用二次電池の安全性試験における新たな技術課題
2.2 環境温度を考慮した安全性試験の現状
2.3 環境温度を制御した外部短絡試験の事例
2.4 試験結果と考察
2.5 その他
3 圧壊試験における圧壊方法の検証
3.1 試験条件・治具の違いの検証事例
3.2 試験結果と考察
4 失活処理のノウハウ
4.1 試験後の失活処理が必要なケース
4.2 失活方法事例
4.2.1 エネルギー放出系
4.2.2 破壊系
4.3 失活方法の選択例
5 おわりに
第20章 安全性評価の受託試験機能
1 はじめに
2 受託試験機関の目的、必要性
3 受託試験機関の状況
4 受託試験の概要
5 安全性評価試験の実施例
5.1 安全性評価試験設備
5.2 安全性試験時の発生ガス分析
5.2.1 発生ガスの回収および分析手法
5.2.2 過充電試験時のリアルタイム発生ガス分析
5.3 リチウムイオン電池の安全性試験シミュレーション
6 おわりに
【第VI編 次世代電池技術】
第21章 全固体電池
1 はじめに
2 無機固体電解質の特性
3 全固体電池の作動特性
4 おわりに
第22章 車載用次世代電池としての全固体電池の展望
1 はじめに
2 ポストリチウムイオン電池
3 全固体電池
4 三井金属における硫化物系全固体電池材料の開発
5 硫化物系固体電解質
6 硫化物系全固体電池の電池特性
7 硫化物系全固体電池の展望
8 層状正極を用いた全固体電池の高充電圧電池特性
9 高電位正極LNMOを用いた全固体電池の高充電圧電池特性
10 全固体電池の特長を活かしたシリコン負極の電池特性
11 おわりに
【第VII編 リサイクル】
第23章 リチウムイオン電池のリサイクル技術
1 はじめに
2 加熱プロセスにおけるCo等の形態変化
3 物理選別によるCo成分の濃縮
4 おわりに
【第VIII編 市場展望】
第24章 リチウムイオン電池及び部材市場の現状と将来展望
1 概要
2 車載用LiB市場動向
3 主要四部材動向
4 正極材動向
5 負極材
6 電解液
7 セパレーター
8 LiB用主要四部材国別動向
9 今後の展望
-

ヘルスケア・ウェアラブルデバイスの開発《普及版》
¥4,070
2017年刊「ヘルスケア・ウェアラブルデバイスの開発」の普及版。ウェアラブルデバイスに求められる装着違和感の低減、動きへの追従性などの課題解決へ向けた材料、実装技術を紹介した1冊。
(監修:菅沼克昭)
<a href="http://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=9363"target=”_blank”>この本の紙版「ヘルスケア・ウェアラブルデバイスの開発(普及版)」の販売ページはこちら(別サイトが開きます)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は、2017年当時のものを使用しております。
菅沼克昭 大阪大学
高河原和彦 日本電信電話(株)
小笠原隆行 日本電信電話(株)
樋口雄一 日本電信電話(株)
家裕隆 大阪大学
安蘇芳雄 大阪大学
竹田泰典 山形大学
時任静士 山形大学
関口貴子 (国研)産業技術総合研究所
荒木徹平 大阪大学
吉本秀輔 大阪大学
植村隆文 大阪大学
関谷毅 大阪大学
入江達彦 東洋紡(株)
石丸園子 東洋紡(株)
吉田学 (国研)産業技術総合研究所
井上雅博 群馬大学
鳥光慶一 東北大学
川喜多仁 (国研)物質・材料研究機構
竹内敬治 (株)NTTデータ経営研究所
保坂寛 東京大学
菅原徹 大阪大学
荒木圭一 (株)KRI
辻村清也 筑波大学
四反田功 東京理科大学
植原聡 日立化成(株)
柴田智章 日立化成(株)
池田綾 日立化成(株)
矢田部剛 日立化成(株)
天童一良 日立化成(株)
峯岸知典 日立化成(株)
越地福朗 東京工芸大学
能木雅也 大阪大学
和泉慎太郎 神戸大学
竹井邦晴 大阪府立大学
鈴木克典 ヤマハ(株)
木村睦 信州大学
岡部祐輔 セメダイン(株)
大高秀夫 バンドー化学(株)
-------------------------------------------------------------------------
<<目次>>
第1章 IoTとウェアラブルの世界
1 IoTのためのウェアラブル・フレキシブル・エレクトロニクス
1.1 IoTとウェアラブル・デバイス
1.2 ウェアラブルで必要とされる要素技術
1.3 ウェアラブル・デバイスとプリンテッド・エレクトロニクス
2 導電性機能素材hitoe(R)を用いたウェアラブル技術と応用展望
2.1 はじめに
2.2 導電性機能素材“hitoe(R)”と,ウェア型生体情報計測デバイス
2.2.1 導電性機能素材“hitoe(R)”
2.2.2 ウェア型生体情報計測デバイスの構成技術
2.3 スマートフォンによる生体情報の推定
2.3.1 心電波形による呼吸活動の推定
2.3.2 心拍数による運動許容量の推定
2.3.3 加速度による様態情報の推定
2.4 生体情報に基づくサービス応用への展開
2.5 まとめ
第2章 フレキシブルトランジスタ
1 塗布法への適用に向けたn型有機トランジスタ材料の開発
1.1 はじめに
1.2 OFETの素子構造と駆動原理
1.3 n型OFET材料に向けた電子受容性ユニットの設計
1.4 カルボニル架橋電子受容性ユニットを導入したn型OFET材料の開発
1.5 ジシアノメチレン基導入シクロペンテン縮環チオフェンに基づくn型OFET材料開発
1.6 N-アルキルフタルジチオイミドを末端ユニットに導入したn型OFET材料の開発
1.7 おわりに
2 超薄型フィルム上に作製した全印刷型有機集積回路
2.1 はじめに
2.2 全印刷有機薄膜トランジスタの作製プロセス
2.2.1 トランジスタ構造が抱える課題
2.2.2 印刷電極が抱える課題
2.3 超薄型フィルム基板上の全印刷型有機集積回路
2.3.1 超薄型フィルム基板上への全印刷型有機トランジスタの作製
2.3.2 超薄型フィルム基板上のデバイス特性
2.4 今後の展望
3 導電性単層CNTゴム複合材料による柔軟・伸張性トランジスタ
3.1 概要
3.2 単層CNTゴムトランジスタの構造
3.3 CNTゴムトランジスタの製造プロセス
3.4 単層CNT,ゴム,ゲルのトランジスタの柔軟性
3.5 おわりに
第3章 ストレッチャブル配線
1 ウェアラブルデバイスのための印刷可能なストレッチャブル配線
1.1 はじめに
1.2 ストレッチャブル配線
1.3 銀ナノワイヤを用いたストレッチャブル透明導電膜
1.4 レーザーを用いた非接触印刷によるストレッチャブル配線の形成
1.5 超ストレッチャブル配線
1.6 まとめ
2 ストレッチャブル導電性ペーストの開発と応用展望
2.1 はじめに
2.2 ストレッチャブル導電性ペースト
2.2.1 概要
2.2.2 伸長時の抵抗変化
2.2.3 繰り返し伸縮時の抵抗変化
2.2.4 スクリーン印刷性
2.2.5 ストレッチャブル導電性ペーストまとめ
2.3 ストレッチャブル配線を用いた応用例
2.3.1 フィルム状機能素材“COCOMI(R)”
2.3.2 心電図計測
2.3.3 心電図計測ウェアの活用
2.3.4 生体情報計測ウェアの開発の課題
2.4 おわりに
3 高伸縮導電配線
3.1 はじめに
3.2 高耐久・高伸縮配線の実現
3.3 高伸縮性短繊維配向型電極
3.4 高伸縮性マトリクス状センサーシート
3.5 まとめ
4 伸縮性配線の疲労メカニズムと実装技術
4.1 はじめに
4.2 主な伸縮配線材料の種類
4.2.1 金属および関連材料
4.2.2 導電性高分子
4.2.3 エラストマーをバインダとした導電ペースト
4.2.4 伸縮性配線材料の比較
4.3 繰返し変形に伴う疲労現象
4.3.1 金属疲労
4.3.2 エラストマー(ゴム)の疲労
4.4 伸縮性導電ペースト印刷配線の繰返し引張試験
4.5 今後のストレッチャブルデバイスの発展を見据えた実装技術上の課題
4.6 おわりに
5 フレキシブルシルク電極
5.1 はじめに
5.2 フレキシブルシルク電極
5.3 応用例
5.3.1 フレキシブルシルク電極(絹糸)
5.4 おわりに
6 樹脂との密着性と柔軟性に優れた導電材料の開発とフレキシブルインターコネクトへの応用
6.1 はじめに
6.2 高導電性ポリマー/金属複合材料とその構造
6.3 光溶液化学を用いた導電性ポリマー/金属複合材料の高速合成
6.4 液滴塗布プロセスと光化学反応プロセスの融合による導電性ポリマー/金属複合材料の微細パターンの形成
6.5 導電性ポリマー/金属複合材料とプラスチック基材との密着性
6.6 導電性ポリマー/金属複合材料の柔軟性
6.7 おわりに
第4章 電池・電源
1 ウェアラブルデバイス向けエネルギーハーベスティング技術
1.1 はじめに
1.2 ウェアラブルデバイスの電源オプション
1.2.1 電源配線
1.2.2 電池
1.2.3 無線電力伝送
1.2.4 エネルギーハーベスティング
1.3 ウェアラブル向けエネルギーハーベスティング技術の開発動向
1.3.1 太陽電池
1.3.2 電波
1.3.3 力学的エネルギー
1.3.4 熱エネルギー(温度差)
1.3.5 その他の発電方式
1.4 今後の課題
2 ジャイロ型振動発電機
2.1 はじめに
2.2 ジャイロ効果
2.3 モータ回転型発電機
2.4 ダイナビー型発電機
2.5 おわりに
3 ウェアラブルデバイスに向けたフレキシブル・マイクロ熱電素子の開発
3.1 はじめに
3.2 熱電発電(変換)技術
3.3 フレキシブル熱電モジュール(素子)の設計指針(デザインと用途)
3.4 フレキシブル熱電モジュールの作製方法と変換特性
3.5 フレキシブル熱電モジュールの信頼性
3.6 ウェアラブル・ポータブル用フレキシブル・マイクロ熱電モジュール
4 塗布型フレキシブル熱電変換素子の作製技術とウェアラブルデバイスへの適用
4.1 はじめに
4.2 フレキシブル熱電変換素子とは
4.3 ナノ粒子の合成
4.4 インク化
4.5 薄膜の作製~カレンダ処理
4.6 π型フレキシブル熱電変換素子の作製
4.7 ファブリックモジュール
4.8 まとめと今後の展望
5 ウェアラブル電源としてのバイオ電池
5.1 化学物質(バイオ燃料)からの環境発電
5.2 バイオ電池の作動原理,技術
5.3 性能向上に向けた課題と開発動向
5.3.1 炭素のメソ孔制御
5.3.2 炭素のマクロ孔制御
5.4 高性能ウェアラブルバイオ電池の開発:印刷型電池
5.5 未来のアプリケーション
5.6 まとめ
第5章 その他材料・技術
1 ウェアラブルデバイスのための透明封止材
1.1 はじめに
1.2 当社の透明封止材のコンセプト
1.3 透明封止材の評価方法と基準
1.4 透明封止材の評価結果
1.4.1 機械特性
1.4.2 光学特性
1.4.3 透湿性
1.4.4 埋め込み特性
1.4.5 曲げ試験
1.4.6 伸び試験
1.4.7 防水試験
1.4.8 信頼性試験
1.5 おわりに
2 人体通信技術のウェアラブルデバイスへの活用
2.1 はじめに
2.2 ワイヤレスボディエリアネットワーク
2.3 人体通信を利用したマルチメディア映像・音声信号の伝送
2.4 人体通信技術の自動車システムへの適用
2.5 まとめ
3 セルロースナノファイバーを用いた折り畳み可能な透明導電膜とペーパー太陽電池
3.1 背景と目的
3.2 結果および考察
3.3 結論
4 ウェアラブル呼気センサのための半導体ナノ材料
4.1 はじめに
4.2 酸化モリブデンとナノ構造の基板成長
4.3 ガスセンサ素子の作製とセンサ特性
4.4 まとめ
第6章 センサデバイス開発
1 ウェアラブル生体センサ
1.1 はじめに
1.2 ウェアラブル生体センサの課題
1.3 ウェアラブル生体センサの低消費電力化技術
1.3.1 センサとアナログ回路
1.3.2 メモリとロジック回路
1.3.3 無線通信
1.4 ウェアラブル生体センサシステムの開発事例
1.4.1 心拍抽出アルゴリズムの開発
1.4.2 不揮発マイコンの開発
1.4.3 SoCの開発
1.5 まとめ
2 ウェアラブルなフレキシブル健康管理パッチ実現に向けて
2.1 はじめに
2.2 加速度センサ
2.3 温度センサ
2.4 紫外線センサ
2.5 心電センサ
2.6 センサ集積健康管理パッチ
2.7 結言
3 紡績性MWCNTを用いた衣類型ウェアラブルモーションセンサ
3.1 はじめに
3.2 薄型ストレッチャブル動ひずみセンサの概要
3.3 製造プロセス,構造,動作原理
3.4 センサの特性
3.4.1 静的特性,動的特性
3.4.2 繰り返し耐久性
3.5 センサの動作原理
3.6 伸縮配線技術
3.7 応用提案と応用事例
3.7.1 モーションセンシング
3.7.2 衣類型ウェアラブルモーションセンサ
3.7.3 動作認識
3.7.4 呼吸計測
3.7.5 ロコモーショントレーニング向けサポーター
3.7.6 データグローブとその活用
3.8 おわりに
4 有機導電性繊維を用いたテキスタイルデバイス
4.1 はじめに
4.2 テキスタイルデバイス
4.3 異方的機能を持つ配列ナノファイバー集合体
4.4 導電性高分子の繊維化とデバイス化
4.5 まとめ
5 低温硬化形導電性接着剤「セメダインのSX-ECA」の開発とデバイス応用
5.1 はじめに
5.2 エレクトロニクスの現状
5.3 設計コンセプト
5.4 低温硬化・フレキシブル導電性接着剤の特長
5.5 SX-ECAの応用例
5.5.1 柔軟EMIシールド
5.5.2 印刷による配線形成
5.5.3 銀ナノワイヤハイブリッドによる高性能化
5.5.4 柔軟接続構造設計
5.5.5 高意匠性衣類
5.6 おわりに
6 伸縮性ひずみセンサ「C-STRETCH(R)」の開発
6.1 はじめに
6.2 C-STRETCH(R)の計測原理と基礎特性
6.3 C-STRETCH(R)の特長
6.4 応用の利用例
6.5 おわりに
-

フローマイクロ合成の実用化への展望《普及版》
¥3,520
2017年刊「フローマイクロ合成の実用化への展望」の普及版。フローマイクロ合成の実用化に向けて、化学・製薬・香料・合成樹脂メーカーによる実例解説および、ポンプ・装置・電機・食品・鉄鋼メーカーによるデバイス開発技術を収載した1冊。
(監修:吉田潤一)
<a href="http://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=9282"target=”_blank”>この本の紙版「フローマイクロ合成の実用化への展望(普及版)」の販売ページはこちら(別サイトが開きます)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は、2017年当時のものを使用しております。
吉田潤一 京都大学
富樫盛典 (株)日立製作所
三宅亮 東京大学
荒井秀紀 (株)タクミナ
伊藤寿英 (株)タクミナ
島崎寿也 (株)タクミナ
橘内卓児 富士テクノ工業(株)
前澤真 (株)ワイエムシィ
野村伸志 (株)中村超硬
嶋田茂人 (株)ナード研究所
野一色公二 (株)神戸製鋼所
中原祐一 味の素(株)
豊田倶透 (株)カネカ
小沢征巳 日産化学工業(株)
安川隼也 三菱レイヨン(株)
二宮航 三菱レイヨン(株)
星野学 三菱レイヨン(株)
中﨑義晃 (株)ナノ・キューブ・ジャパン
山本哲也 高砂香料工業(株)
田口麻衣 ダイキン工業(株)
中谷英樹 ダイキン工業(株)
臼谷弘次 武田薬品工業(株)
松山一雄 花王(株)
浅野由花子 (株)日立製作所
佐藤忠久 (株)ナノイノベーション研究所
高山正己 塩野義製薬(株)
金熙珍 京都大学
永木愛一郎 京都大学
-------------------------------------------------------------------------
<<目次>>
【第I編 デバイス開発】
第1章 3Dプリンターによるデバイス作製
1 フローマイクロデバイス
2 フローマイクロデバイスの材質と特徴
3 デバイス加工のデジタル化の歴史
4 3Dプリンターによるデバイス加工の方法
5 3Dプリンターによるフローマイクロデバイスの作製事例
第2章 フローマイクロ合成研究者が知っておくべき各種ポンプの違いと特長
1 はじめに
2 ポンプの種類について
2.1 非容積式ポンプ
2.1.1 遠心ポンプ
2.1.2 軸流ポンプおよび斜流ポンプ
2.2 容積式ポンプ
2.2.1 容積式ポンプ:往復式ポンプ
2.2.2 容積式ポンプ:回転式ポンプ
3 フローマイクロ合成研究者が用いるポンプ
3.1 スムーズフローポンプ
3.2 スムーズフローポンプの特徴について
3.3 生産機適正について
3.4 フローマイクロ合成の研究で用いられるポンプ
3.4.1 シリンジポンプ
3.4.2 プランジャポンプ
3.4.3 ダイヤフラムポンプ
3.4.4 小流量の実験における注意点
4 最後に
第3章 高定量性の3連式無脈動定量プランジャーポンプ
1 マイクロプロセスに必要な液体供給の要素
2 マイクロプロセスに必要な液体供給機器
2.1 精密ギヤーポンプ
2.2 一軸偏心ねじポンプ(モーノポンプ)
2.3 高速液体クロマトグラフィー(high performance liquid chromatography,略称:HPLC)用ポンプ
2.4 シリンジポンプ
2.5 2連式無脈動定量プランジャーポンプ(産業用)
2.6 ダイヤフラムポンプ
3 3連式無脈動定量プランジャーポンプ
3.1 往復動ポンプ
3.2 従来の往復動ポンプ
3.3 2連式無脈動定量プランジャーポンプ
3.4 3連式プランジャーポンプ
3.5 当社製3連式無脈動定量プランジャーポンプ
3.6 当社製3連式無脈動定量プランジャーポンプの性能
4 3連式無脈動定量プランジャーポンプのマイクロプロセスにおける適応性
4.1 性能
4.2 外気遮断性
4.3 耐蝕性
4.4 耐スラリー液性
4.5 操作性及び制御の拡張
4.6 ブチルリチウムの連続運転
第4章 医薬品を中心とした少量・中規模マイクロリアクタシステム
1 はじめに
2 YMC製マイクロミキサの特徴
3 YMC製マイクロリアクタについて
3.1 KeyChem-Basic,L/LPの特徴
3.2 KeyChem-H,水素吸蔵合金キャニスター,5%Pd/SCの特徴
3.3 KeyChem-Lumino2の特徴,光源の紹介
4 KeyChem-Integralの特徴,紹介
5 おわりに
第5章 連続フロー式マイクロリアクターシステム
1 はじめに
2 連続フロー式マイクロリアクターシステム
2.1 X-1αの基本システム構成・機能
2.2 代表的反応における実証データ
3 各種デバイスによる拡張性
3.1 ミキサー
3.2 気体流量制御装置
3.3 光反応用ユニット
4 おわりに
第6章 撹拌子を有する多段連続式撹拌槽型反応器
1 はじめに
2 流通型反応器
3 Coflore ACR(Agitated Cell Reactor)
4 Coflore ATR(Agitated Tube Reactor)
5 鈴木-宮浦クロスカップリング反応
6 スラリーの連続フロープロセス
7 接触水素化脱塩素反応
8 高圧条件での接触水素化反応
9 カーボンナノチューブの効率的な化学修飾
10 生体触媒による酸化反応
11 連続晶析
12 おわりに
第7章 積層型多流路反応器(SMCR(R))
1 はじめに
2 バルク生産用マイクロリアクターの基本概念
3 バルク生産用熱交換器から大容量MCRへ
4 大容量MCR 積層型多流路反応器(SMCR(R))について
5 SMCR(R)の適用事例
5.1 抽出用途への適用検討
5.2 実験内容および結果
5.3 SMCR(R)による商業化事例
6 分解型SMCR(R)での適用用途拡大
7 おわりに
第8章 フローマイクロリアクターを用いた連続合成プロセスの構築
1 はじめに
1.1 化学合成におけるフローマイクロリアクターの特長
1.2 フローマイクロリアクターの課題
1.2.1 化学合成と化学工学の融合による反応場の構築
1.2.2 パラメータの多さによる開発スピードの遅延
1.2.3 安定な連続化プロセスの構築
1.3 京都大学マイクロ化学生産研究コンソーシアムにおける取り組み
2 フローマイクロリアクターによる高分子合成
3 フローマイクロリアクターによるアニオン重合システムの構築
3.1 連続反応システムの構築とシステムの検証
3.2 モノマー/開始剤の比率がポリマー分子量に及ぼす影響の評価
3.3 アニオン重合によるポリスチレン連続運転システムの検証
4 おわりに
【第II編 企業の実例】
第1章 マイクロリアクターを用いたイソブチレンのリビングカチオン重合
1 はじめに
2 リビング重合とマイクロリアクター
3 イソブチレン系樹脂と現行プロセスの課題
4 マイクロリアクターを用いた連続重合検討
4.1 反応機構解析
4.2 速度論解析・反応速度シミュレーション
4.3 ラボ実証実験
4.4 高活性触媒
4.5 連続化がもたらすエネルギーメリット
5 おわりに
第2章 フローリアクターでの香月シャープレス不斉エポキシ化
1 はじめに
2 香月シャープレス不斉エポキシ化(KSAE)反応
3 スケールアップ課題
4 フロー検討用装置
5 シンナミルアルコールの不斉エポキシ化
5.1 フロー系への置き換え
5.2 バッチ反応との比較
6 メタリルアルコールの不斉エポキシ化
7 クエンチ連続化
8 スケールアップ
8.1 除熱限界
9 w/o MSフロー法の基質適用性
10 結論
11 おわりに
第3章 マイクロ化学プロセスを利用する新規アクリルモノマー製造技術の開発
1 はじめに
2 ピルビン酸エステルの合成へのマイクロリアクターの利用
2.1 ラボスケールのマイクロリアクターでの操作方法
2.2 ベンチスケールのマイクロリアクターでの操作方法
2.3 結果
2.4 ピルビン酸エステルの合成まとめ
3 α-アシロキシアクリレートの合成
3.1 ラボスケールのバッチ反応での検討
3.2 ラボスケールのマイクロリアクターでの検討
3.3 ベンチスケールマイクロリアクターでの検討
3.4 α-アシロキシアクリレート合成まとめ
4 α-アシロキシアクリレートの製造プロセスの提案
4.1 検討方法
5 終わりに
第4章 マイクロリアクターを用いたシングルナノ粒子の製造
1 はじめに
2 ITO代替導電性材料
3 ドーパントの検討
3.1 ドーピング化学種の検討
3.2 計算結果と考察
3.3 ドーピング量の検討
3.4 ドーピングSnO2のバンド構造
4 マイクロ化学プロセスを用いた合成
4.1 ドーピング用マイクロリアクターの設計
4.2 マイクロ化学プラントの試作(マイクロ化学プロセス,周辺装置試作)
4.3 合成条件の検討
4.4 透明性
5 まとめ
第5章 不斉水素化反応へのマイクロリアクターの適応
1 はじめに
2 マイクロリアクターの特徴
3 高速不斉水素化触媒RUCY(R)を用いた不斉水素化反応へのマイクロリアクターの適応
3.1 小スケール検討
3.2 速度論解析による流路長最適化
3.3 流路径の反応に対する影響
3.4 気液導入部の最適化
3.5 触媒溶液の安定性改善
3.6 温度コントロール
3.7 React IRによる流動状態の評価
4 まとめ
第6章 マイクロリアクターを用いた含フッ素ファインケミカル製品の合成
1 はじめに
2 フッ素化合物とフッ素ファインケミカル製品
3 フッ素化合物の合成方法
4 フッ素系ケミカル製品のマイクロリアクターを用いた事例
4.1 マイクロリアクターを用いた直接フッ素化反応
4.2 マイクロリアクターを用いたビルディングブロック法
4.3 マイクロリアクターを用いたエポキシ化反応
4.4 マイクロリアクターを用いたハロゲン-リチウム交換反応
4.5 マイクロリアクターの生産設備としての利用可能性
5 おわりに
第7章 フローケミストリー技術を用いたスケールアップ
1 はじめに
2 医薬品製造におけるフローケミストリーの適用
3 不安定活性種の発生と応用
4 フローケミストリーを用いた有機リチウム反応のボロン酸合成への適用
5 フローケミストリーを用いたプロセス開発
6 フローケミストリーを用いたスケールアップ検討
7 ボロン酸Xの製造
8 最後に
第8章 高速混合を利用した高効率微細乳化
1 はじめに
2 空間のマイクロ化の効果
2.1 層流におけるミリ秒混合の必要条件
2.2 乱流におけるミリ秒混合の必要条件
2.3 液液混合における空間のマイクロ化の効果
3 マイクロミキサー開発事例
4 高効率微細乳化プロセスの提案
4.1 微細乳化の課題と着目点
4.2 実験と結果
5 おわりに
第9章 フローマイクロリアクターシステムによる製造プロセス
1 はじめに
2 マイクロリアクターの導入プロセス
3 マイクロリアクターの適用事例
3.1 水分離用マイクロリアクター
3.2 抽出用マイクロリアクター
3.3 濃縮用マイクロリアクター
4 マイクロリアクターシステムの開発事例
4.1 ラボ・少量生産用マイクロリアクターシステム(MPS-α200)
4.2 反応・乳化用マイクロリアクタープラント
4.2.1 中量産用マイクロリアクタープラント
4.2.2 量産用マイクロリアクタープラント
5 おわりに
第10章 大量物質生産を目指したマイクロリアクターシステム
1 はじめに
2 マイクロ化学プラント
2.1 マイクロ化学プラントのサイズについて
2.2 マイクロ化学プラントのフレキシブル性
2.3 マイクロ化学プラントによる工業化検討対象について
3 工業化する上での重要な留意点
3.1 生産性を考慮したマイクロ化学プラント設計
3.2 工業化を検討する反応の反応速度について
4 工業化において重要な技術
4.1 送液制御技術
4.1.1 無脈動もしくは低脈動送液技術
4.1.2 送液流量の均等分配技術
4.2 マイクロ流路閉塞防止技術
4.2.1 マイクロ流路構造による閉塞防止(「イコーリングアップ」技術)
4.2.2 マイクロ流路径拡大による閉塞抑制(「疑似イコーリングアップ」技術)
4.2.3 自動化技術による閉塞防止
4.2.4 反応媒体流の急激な圧力変化による閉塞防止
5 工業化検討の現状と将来展望
【第III編 産業界の動向】
第1章 フローマイクロリアクターの製薬業界の動向
1 はじめに
2 製薬業界での使いどころと利点
3 医薬品研究での実例
4 医薬品業界におけるフロー・マイクロ合成技術の展望
第2章 フローマイクロリアクターの化学業界の動向
1 はじめに
2 実用化の例1:DSM社でのアクリルアミドの生産
3 実用化の例2:Xi’an Huian Chemical社でのトリニトログリセリンの生産
4 実用化の例3:Sigma-Aldrich社でのレチノールの生産
5 実用化の例4:Clariant社でのフェニルボロン酸の生産
6 おわりに
-

実用化に向けたソフトアクチュエータの開発と応用・制御技術《普及版》
¥3,960
2017年刊「実用化に向けたソフトアクチュエータの開発と応用・制御技術」の普及版。ソフトアクチュエータの基礎・開発・応用研究について、それぞれの専門家の解説をまとめた1冊。
(編集:シーエムシー出版)
<a href="http://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=9301"target=”_blank”>この本の紙版「実用化に向けたソフトアクチュエータの開発と応用・制御技術(普及版)」の販売ページはこちら(別サイトが開きます)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は、2017年当時のものを使用しております。
千葉正毅 千葉科学研究所
杉野卓司 (国研)産業技術総合研究所
岩曽一恭 大阪大学
高島義徳 大阪大学
原田明 大阪大学
三俣哲 新潟大学
梅原康宏 (公財)鉄道総合技術研究所
白須圭一 東北大学
山本剛 東北大学
橋田俊之 東北大学
高木賢太郎 名古屋大学
荒川武士 名古屋大学
釜道紀浩 東京電機大学
舛屋賢 九州大学
田原健二 九州大学
安積欣志 (国研)産業技術総合研究所
今井郷充 日本大学
嵯峨宣彦 関西学院大学
上杉薫 大阪大学
森島圭祐 大阪大学
都井裕 東京大学
中村太郎 中央大学
戸森央貴 山形大学
田實佳郎 関西大学
和氣美紀夫 (有)Wits
脇元修一 岡山大学
谷口浩成 大阪工業大学
李毅 信州大学
橋本稔 信州大学
山内健 新潟大学
-------------------------------------------------------------------------
<<目次>>
【総論編】
第1章 ソフトアクチュエータの開発状況
1 概要
2 研究開発の状況
2.1 高分子材料を利用するアクチュエータ
2.2 形状記憶材料を利用するアクチュエータ
2.3 空気圧を利用するアクチュエータ
2.4 静電力を利用するアクチュエータ
3 企業動向
【基礎研究編 ソフトアクチュエータの材料・動力別分類】
第1章 誘電エラストマーアクチュエータ
1 はじめに
2 誘電エラストマーの原理
2.1 DEアクチュエータの素材,性能および開発動向
2.2 DE素材の性能
2.2.1 ヒステリシスおよびクリープ
2.2.2 漏れ電流と抵抗値
3 DEアクチューターの開発状況
4 DEセンサー
5 DE発電
5.1 DEの発電理論
5.2 DE発電の数式モデル
6 おわりに
第2章 ナノカーボン高分子アクチュエータ
1 はじめに
2 ナノカーボン高分子アクチュエータの構成
3 ナノカーボン高分子アクチュエータの特性評価法
4 ナノカーボン高分子アクチュエータの変形メカニズム
5 ナノカーボン高分子アクチュエータの応答特性の改善
5.1 添加物による電極の改良
5.2 耐久性の改善
6 ナノカーボン高分子アクチュエータの実用化に向けた取組み
7 おわりに
第3章 超分子アクチュエータ
1 はじめに
2 分子マシン
3 超分子マシンエレメント
4 分子シャトル
5 分子ローター
6 カテナン
7 刺し違い2量体(Daisy Chain)
8 超分子マシン
9 分子マシンから巨視的なアクチュエータの設計
9.1 クラウンエーテルを含むDaisy Chainポリマー
9.2 分子モーターの回転により収縮するポリマー
9.3 超分子錯体の形成,解離を駆動力とするアクチュエータ
9.4 分子マシンのスライドを駆動力とするアクチュエータ
10 まとめ
第4章 磁場で駆動するソフトアクチュエータ
1 はじめに
2 磁性ソフトアクチュエータ
3 磁性ゲルの可変粘弾性
4 磁性エラストマーの可変粘弾性
5 鉄道車両への応用
6 おわりに
第5章 CNT/エポキシ複合材料を用いた熱バイモルフ
1 はじめに
2 配向CNT/エポキシ複合材料の作製と線膨張係数の評価
3 アクチュエータのたわみ量と発生力
4 熱バイモルフのたわみ量と発生力の評価
5 おわりに
第6章 釣糸人工筋アクチュエータ
1 はじめに
2 コイル形状の釣糸人工筋アクチュエータ(TCPA)の物理原理
2.1 温度変化に基づく応答の原理
2.2 釣糸人工筋アクチュエータの形状と作製方法
3 TCPAの作製とジュール加熱による電場駆動
3.1 コイル形状の釣糸人工筋アクチュエータの作製
3.2 ニクロム線によるジュール加熱
4 電圧駆動される釣糸人工筋アクチュエータのモデル化
4.1 モデル化
4.2 実験データを用いたシステム同定
5 おわりに
第7章 形状記憶ポリマーアクチュエータ
1 形状記憶ポリマーの概要
1.1 形状記憶ポリマーの特徴
1.2 形状記憶のメカニズム
1.3 形状記憶ポリマーの種類と応用例
2 形状記憶ポリマーのアクチュエータへの応用
2.1 設計のための検討項目
2.2 形状記憶ポリマーのみによる2方向動作
2.2.1 方向動作のメカニズム
2.2.2 ポリウレタン系形状記憶ポリマーの温度特性
2.2.3 アクチュエータの構造
2.2.3 アクチュエータの特性
第8章 低圧駆動型空気圧人工筋アクチュエータ
1 はじめに
2 軸方向強化型空気圧人工筋アクチュエータ
2.1 実験概要
2.2 基礎特性
2.3 空気圧人工筋アクチュエータの生物学的特性
2.3.1 等張性収縮特性
2.3.2 等尺性収縮特性
3 空気圧バルーンを用いた腱駆動アクチュエータ
3.1 基本構造と駆動原理
3.2 基礎特性
3.3 腱駆動アクチュエータの生物学的特性
3.3.1 等張性収縮特性
3.3.2 等尺性収縮特性
4 まとめ
第9章 マイクロナノマシンとソフトマテリアルが拓く生命機械融合ソフト&ウェットロボティクス
1 はじめに
2 筋細胞を用いたバイオアクチュエータ
3 耐環境性に優れたバイオアクチュエータ
4 筋細胞の3 次元組織構築によるバイオアクチュエータとその応用
4.1 心筋ゲルアクチュエータ
4.2 培養神経ネットワークによる筋組織の運動制御
5 筋細胞バイオアクチュエータの光制御
6 力学刺激を用いたバイオアクチュエータの高性能化
7 バイオアクチュエータの力学的特性評価
8 今後の展開
【開発研究編 実用化に向けたモデリング・理論】
第1章 高分子アクチュエータ/センサの計算モデリング
1 形状記憶ポリマーの概要
2 導電性高分子アクチュエータ
3 導電性高分子アクチュエータの電気化学・多孔質弾性応答の計算モデリング
3.1 多孔質弾性体の剛性方程式
3.2 圧力に対するポアソン方程式
3.3 体積ひずみの発展方程式
3.4 イオン輸送方程式
3.5 計算手順
4 固体電解質ポリピロールアクチュエータの電気化学・多孔質弾性応答解析
5 導電性高分子センサ
6 導電性高分子を用いた力学センサの数値シミュレーション
7 まとめ
第2章 特性変動を考慮した高分子アクチュエータの制御
1 はじめに
2 IPMCアクチュエータの制御
3 セルフチューニング制御
3.1 制御則
3.2 逐次最小二乗法に基づくパラメータ更新
3.3 適用結果
4 セルラーアクチュエータ制御
4.1 制御則
4.2 適用結果
第3章 高出力型空気圧人工筋肉と機能性流体デバイスを用いた可変粘弾性関節による瞬発力発生機構とその応用
1 はじめに
2 可変粘弾性マニピュレータ
2.1 空気圧人工筋肉
2.2.1 空気圧人工筋肉の特徴
2.2.2 空気圧人工筋肉の種類
2.2 MRブレーキ
2.3 人工筋肉とMRブレーキを用いた可変粘弾性機構
2.3.1 可変粘弾性関節機構の意味
2.3.2 空気圧人工筋肉とMRブレーキを用いた可変粘弾性関節機構
3 応用例
3.1 投てきロボット
3.2 ジャンプロボット
4 おわりに
【応用研究編 ソフトアクチュエータの応用事例紹介】
第1章 圧電性高分子から圧電ファブリックへ
1 はじめに
2 圧電性
3 圧電ファブリック
3.1 圧電ファブリックとは
3.2 圧電ファブリックからの圧電信号とデバイス
3.3 圧電ファブリックの特徴
4 おわりに
第2章 誘電エラストマ人工筋肉の応用
1 はじめに
2 アクチュエータへの応用例
2.1 産業ロボットの開発
2.2 DEモータの製作
2.3 医療用への展開
2.4 医療センサへの応用事例
2.5 透明アクチュータの開発
3 発電デバイスへの応用
3.1 波を利用した発電システム
3.2 海流・水流による発電
3.3 新しいアイデアを用いた風力発電へのチャレンジ
3.4 床発電システム
4 おわりに
第3章 空気圧ソフトアクチュエータの医療応用
1 空気圧ソフトアクチュエータの医療応用について
2 2方向湾曲型空気圧アクチュエータの開発とイレウスチューブへの応用
2.1 背景
2.2 2方向湾曲アクチュエータ
2.3 イレウスチューブへの適用
2.4 まとめ
3 空気圧バックアクチュエータを用いた足関節拘縮予防装置の開発
3.1 背景
3.2 足関節の関節可動域運動
3.3 空気圧バックアクチュエータ
3.4 関節可動域運動試験
3.5 まとめ
第4章 PVCゲル人工筋肉のウェアラブルロボットへの応用
1 はじめに
2 積層型PVCゲル人工筋肉
2.1 PVCゲルと駆動原理
2.2 PVCゲル人工筋肉の構造
2.3 駆動特性
3 歩行アシストウェアへの応用
3.1 引張り型モジュール構造
3.2 アシストウェアの構造
3.3 歩行アシスト
3.4 設計と試作
4 アシスト効果の検証実験
4.1 実験方法
4.2 実験結果
5 おわりに
第5章 生物の問題解決法を活用したソフトアクチュエータの開発
1 はじめに
2 生物を模倣した材料の設計-TRIZというアイデア創出法-
3 多孔質構造を有するソフトアクチュエータの開発
4 おわりに
-

医療用バイオマテリアルの研究開発《普及版》
¥4,290
2017年刊「医療用バイオマテリアルの研究開発」の普及版。生体適合性高分子材料の開発の歴史から、臨床応用を目指した研究やその実用例までを紹介した1冊。
(監修:青柳隆夫)
<a href="http://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=9302"target=”_blank”>この本の紙版「医療用バイオマテリアルの研究開発(普及版)」の販売ページはこちら(別サイトが開きます)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は、2017年当時のものを使用しております。
青柳隆夫 日本大学
中岡竜介 国立医薬品食品衛生研究所
迫田秀行 国立医薬品食品衛生研究所
植松美幸 国立医薬品食品衛生研究所
宮島敦子 国立医薬品食品衛生研究所
野村祐介 国立医薬品食品衛生研究所
蓜島由二 国立医薬品食品衛生研究所
伊佐間和郎 帝京平成大学
岩崎清隆 早稲田大学
梅津光生 早稲田大学
田中賢 九州大学;山形大学
蟹江慧 名古屋大学
成田裕司 名古屋大学医学部付属病院
加藤竜司 名古屋大学
石原一彦 東京大学
馬場俊輔 大阪歯科大学
橋本典也 大阪歯科大学
笠原真二郎 日本特殊陶業(株)
築谷朋典 国立循環器病研究センター研究所
伊藤恵利 (株)メニコン;名古屋工業大学
荒雅浩 (株)ジェイ・エム・エス
大矢裕一 関西大学
水田亮 筑波大学;物質・材料研究機構
田口哲志 物質・材料研究機構;筑波大学
鈴木治 東北大学
穴田貴久 東北大学
小山義之 結核予防会 新山手病院
伊藤智子 結核予防会 新山手病院
江里口正純 結核予防会 新山手病院
松村和明 北陸先端科学技術大学院大学
玄丞烋 京都工芸繊維大学
伊藤壽一 滋賀県立成人病センター研究所
岩井聡一 大阪大学
石原雅之 防衛医科大学校
新山瑛理 物質・材料研究機構;筑波大学
宇都甲一郎 物質・材料研究機構
荏原充宏 物質・材料研究機構;筑波大学;東京理科大学
小林尚俊 物質・材料研究機構
玉田 靖 信州大学
武岡真司 早稲田大学
木村俊作 京都大学
辻本洋行 同志社大学
高木敏貴 同志社大学
萩原明於 同志社大学
岡村陽介 東海大学
中澤靖元 東京農工大学
牧田昌士 ORTHOREBIRTH(株)
西川靖俊 ORTHOREBIRTH(株)
春日敏宏 名古屋工業大学
-------------------------------------------------------------------------
<<目次>>
【第1編 生体適合性高分子材料の基礎】
第1章 生体適合性高分子材料の種類と特徴
1 はじめに
2 生体適合高分子材料の開発の歴史
3 水の構造に着目したバイオインターフェース
4 ポリマーの精密重合と表面の構築
5 炎症反応に着目した血液適合性材料開発
6 最後に
第2章 生体適合性材料の評価方法とその標準化
1 はじめに
2 医用材料の種類
2.1 金属材料
2.2 セラミックス材料
2.3 ポリマー(高分子)材料
3 医用材料の生体適合性
3.1 生体安全性について
3.2 生体適合性について
4 国際標準化
5 おわりに
第3章 生体内劣化評価法の開発
1 はじめに
2 人工関節における超高分子量ポリエチレンのガンマ線照射に伴う劣化
3 超高分子量ポリエチレンの生体脂質による劣化
4 生体吸収性材料
5 まとめ
第4章 血液適合性評価法の開発
1 はじめに
2 ホリゾンタル試験法
2.1 溶血性試験
2.1.1 現行公定法
2.1.2 簡易溶血性試験法
2.1.3 陽性対照材料
2.2 血栓性試験
2.2.1 血液側からの評価法
2.2.2 材料側からの評価法
3 分子動力学的シミュレーションを利用した材料評価
4 Engineering-based Medicineに基づく血液適合性試験
4.1 左心補助人工心臓用脱血管のin vitro血栓性試験法
4.2 持続的血液濾過器のin vitro血栓性試験法
5 おわりに
【第2編 医療機器部材用材料の開発】
第1章 Poly(ω-methoxyalkyl acrylate)類の抗血栓能
1 はじめに
2 医療機器の表面で起こる現象
3 タンパク質の吸着現象-吸着と構造変化
4 材料に含水した水の状態の解析
5 材料表面に存在する中間水の役割
6 抗血栓性高分子の設計
7 おわりに
第2章 インフォマティクスを活用した細胞選択的ペプチド被覆型医療機器材料の設計
1 背景~体内埋め込み型医療機器材料の現状~
2 医療機器材料としてのペプチド
2.1 細胞接着ペプチド被覆型医療材料
2.2 細胞を用いたペプチドアレイ探索
2.3 細胞選択的ペプチド
3 細胞選択的ペプチドの探索と医療機器材料開発に向けて
3.1 クラスタリング手法を用いたEC選択的・SMC選択的ペプチドの探索
3.2 BMPタンパク質由来の細胞選択的骨化促進ペプチドの探索
3.3 ペプチド-合成高分子の組み合わせ効果による細胞選択性
4 まとめ
第3章 スーパーエンジニアリングプラスチック表面への生体親和性修飾
1 エンジニアリングプラスチックとしてのポリアリルエーテルケトン
2 PEEKの化学構造に着目した自己開始光グラフト重合法
3 自己開始光グラフト重合法によるPEEK表面へのポリマー層の構築
3.1 自己開始光グラフト重合
3.2 各種のグラフトポリマー層を有するPEEKの表面特性
4 ポリマーグラフト層を持つPEEK表面の生体親和性
4.1 医療デバイスを作るバイオマテリアルの生体親和性の必要性
4.2 リン脂質ポリマーをグラフトしたPEEK表面の生体親和性
4.2.1 血漿からのタンパク質吸着
4.2.2 血小板多血漿からの血小板粘着
4.2.3 細菌付着性の評価
5 おわりに
第4章 ポリエーテルエーテルケトン多孔体の骨造成能
1 はじめに
2 ポリエーテルエーテルケトンとは
3 PEEKへの骨結合性の付与
4 表面発泡PEEKの開発
5 PEEK製 歯槽骨再建材のコンセプト
6 PEEK多孔体の作製
7 ウサギ大腿骨骨欠損モデルを用いた表面発泡 PEEK多孔体の骨造成
8 おわりに
第5章 心不全治療と人工心臓
1 はじめに
2 補助人工心臓の目的
3 補助人工心臓システムの構造とマテリアル
4 空気圧駆動式補助人工心臓システム(ニプロVAS)
5 体内植込み型補助人工心臓(EVAHEART)
6 体内植込み型補助人工心臓の課題
7 まとめ
第6章 脂質付着抑制能をもつ両親媒性高分子材料の開発
1 はじめに
2 シリコーンハイドロゲル素材の主成分
2.1 シリコーン成分
2.1.1 変性ポリシロキサン
2.1.2 シリコーンモノマー
2.2 親水性成分
3 シリコーンハイドロゲル素材の特徴
3.1 酸素透過性
3.2 水溶性物質透過性
3.3 タンパク質付着
4 シリコーンハイドロゲル素材の課題
4.1 脂質付着
4.2 透明性
4.3 透明性と脂質付着抑制の系譜
4.3.1 DMAAの活用とその課題
4.3.2 相分離サイズスケールの原因追跡とNMMPの活用
5 おわりに
第7章 Legacoat技術による人工心肺回路の血液適合性向上
1 はじめに
2 血液適合性コーティング「Legacoat」
2.1 MPCポリマーについて
2.2 コーティング技術に求められる要求事項
3 「Legacoat」の効果
4 まとめ
【第3編 ゲル材料の開発と応用】
第1章 温度応答性インジェクタブルポリマー
1 はじめに
2 生分解性インジェクタブルポリマー:その用途
3 生分解性インジェクタブルポリマーの課題
4 分子形態制御:強度向上と温度応答性制御
5 薬物放出制御
6 粉末化と即時溶解による利便性向上
7 共有結合ゲル
8 おわりに
第2章 疎水化タラゼラチンシーラント
1 はじめに
2 生体組織接着性を向上させる高分子ゲルの設計
3 疎水化タラゼラチンを用いた外科用シーラント
3.1 タラゼラチンへの生体組織接着性の付与
3.2 疎水化タラゼラチンを用いた外科用シーラントの機能評価
3.3 疎水化タラゼラチンシーラントと細胞・生体組織との相互作用評価
4 結論
第3章 リン酸八カルシウム/ゼラチン複合体
1 序論
2 OCPの骨伝導の特徴
2.1 OCPの細胞応答性
2.2 OCPの生体反応性
2.2.1 タンパク質吸着
2.2.2 骨形成と生体内吸収性
3 OCP骨補填材
3.1 Gelについて
3.2 Gel単体の生体応答性
3.3 OCP/Gel複合体
3.3.1 OCP/Gelの生体材料学的設計論
3.3.2 生体応答
3.3.3 骨再生を促進するメカニズム
4 まとめ
第4章 生体接着性水和ゲルを形成する可溶性止血材・癒着防止材
1 生体接着性材料
1.1 生体接着性材料の医療機器への応用
2 生体組織接着性ポリマー
2.1 シアノアクリレート系接着剤
2.2 フィブリン糊
2.3 ポリアクリル酸(PAA)
3 PAA/PVP水素結合ゲル
3.1 PAA/PVP水素結合錯体
3.2 膨潤性PAA/PVP複合体
3.2.1 固体/液体界面での複合体形成
3.2.2 膨潤性PAA/PVP複合体の組織接着性
3.2.3 膨潤性PAA/PVP複合体の生体内での解離・再溶解
4 膨潤性PAA/PVP複合体の止血材への応用
4.1 止血効果
4.2 臨床研究と商品化
4.2.1 外傷,穿刺後の止血
4.2.2 口腔内・抜歯後の止血
4.2.3 商品化
5 膨潤性PAA/PVP複合体の癒着防止材への応用
6 生体接着性材料の今後
第5章 生分解性多糖類ハイドロゲルの医療応用
1 はじめに
2 分解性多糖類を用いた医療用接着剤
3 アルデヒド導入多糖類のゲル化とその分解メカニズム
4 アルデヒド導入セルロースの生体内分解性
5 おわりに
第6章 ゼラチンハイドロゲルを利用した難聴治療
1 はじめに
2 耳の構造と聞こえのしくみ
3 難聴の種類
4 現在の最先端技術を応用した新しい感音難聴治療
5 内耳への薬物局所投与方法
6 ゼラチンハイドロゲルを利用した薬物内耳局所投与
7 ゼラチンハイドロゲルIGF-1による臨床試験
7.1 第I-II相臨床試験
7.2 第II相臨床試験(ステロイド鼓室内投与とのランダム化比較試験:多施設臨床試験)
第7章 ハイドロキシアパタイトアガロースゲルを用いた骨再生医療
1 はじめに
2 ハイドロキシアパタイトアガロースゲル
3 臨床研究の概要
4 結果
5 結論
第8章 内視鏡手術用の粘膜下注入剤
1 はじめに
2 光硬化性キトサンゲル
3 光硬化性キトサンゲルを使用した内視鏡的消化器粘膜下層剥離術
4 おわりに
【第4編 シート・繊維材料の開発と応用】
第1章 ナノファイバーシートによるがん治療
1 はじめに
2 皮膚癌用ナノファイバーメッシュ
3 肺癌用ナノファイバーメッシュ
4 悪性中皮腫用ナノファイバーメッシュ
5 肝癌用ナノファイバーメッシュ
6 結言
第2章 絹フィブロインナノ繊維構造体の角膜再生足場材としての応用
1 緒言
2 医療用材料としてのシルク
3 シルクタンパク質の加工
3.1 多様な形状への加工
3.2 化学修飾
3.3 遺伝子組換えカイコ技術
4 シルクナノファイバー不織布の作製
5 角膜再生材料としての評価
6 おわりに
第3章 生体適合性高分子ナノシートの物性と医療応用
1 諸言
2 ナノシートの作製
2.1 交互積層法(LbL)
2.2 キャスト法
3 ナノシートの密着性
4 ナノシートの分子透過性
5 ナノシートの分解特性
6 多孔質ナノシートとマイクロディスク型ナノシートの構築
7 ナノシートの医療応用
7.1 創傷被覆材(ナノ絆創膏)として
7.2 薬物徐放材として
8 ナノ医療のプラットフォームとしての将来展望
第4章 ポリプロピレン不織布へのペプチドナノシート表面修飾
1 体外循環デバイス
2 バイオマテリアル表面と免疫応答
3 繊維表面のラフネス
4 水中でのself-standingな自己組織化単分子膜
5 PP不織布繊維表面のペプチドナノシートによる被覆
第5章 PGA不織布の繊維径などの構造の検討
1 はじめに
2 PGA不織布の構造など
2.1 臨床使用可能なPGA不織布の概要
2.2 生体内分解性と臨床的特性
2.2.1 シートタイプPGA不織布
2.2.2 チューブタイプPGA不織布
2.2.3 新規開発タイプPGA不織布
2.3 不織布の構造と生体の反応性
2.3.1 シートタイプPGA不織布
2.3.2 チューブタイプPGA不織布
2.3.3 新規開発PGA不織布
3 近年の臨床使用の方向性を示すPGA不織布の研究
3.1 シートタイプPGA不織布
3.1.1 膵損傷と膵液漏出の予防効果
3.1.2 内視鏡的粘膜下層剥離術における潰瘍の処置
3.1.3 肝臓切除手術における切離断面の被覆
3.2 チューブタイプPGA不織布
3.2.1 膵切離時の補強
3.2.2 消化管断端の補強
3.2.3 血管の縫合切離時の補強
4 おわりに
第6章 裁断化超薄膜の調製と水性表面改質材としての医用展開~熱傷創の改質・抗血栓性界面の提供~
1 はじめに
2 センチメートルサイズの高分子超薄膜
3 サブミリメートルサイズの裁断化超薄膜
3.1 裁断化超薄膜の調製法と物性
3.2 裁断化超薄膜の水性表面改質材としての応用: 熱傷創の表面改質
3.3 裁断化超薄膜の水性表面改質材としての応用: 抗血栓性界面の提供
4 おわりに
第7章 シルクフィブロイン複合材料の心臓修復パッチ材料への応用
1 はじめに
2 心臓修復パッチ
3 生体吸収性心臓修復パッチの開発
4 おわりに
第8章 綿形状人工骨充填材
1 はじめに
2 綿形状人工骨充填材
2.1 成分
2.2 繊維化
2.3 使用方法
3 おわりに
-

食品機能性成分の安定化技術《普及版》
¥3,850
2016年刊「食品機能性成分の安定化技術」の普及版。食品機能性成分別の物性・効能、不安定性要因、安定化技術、さらには製品適用事例等をまとめた1冊。
(監修:寺尾啓二)
<a href="http://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=9277"target=”_blank”>この本の紙版「食品機能性成分の安定化技術(普及版)」の販売ページはこちら(別サイトが開きます)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は、2016年当時のものを使用しております。
寺尾啓二 ㈱シクロケム;神戸大学;神戸女子大学
上岡勇輝 日油㈱
飯塚正男 理研ビタミン㈱
石田善行 ㈱シクロケムバイオ
上梶友記子 ㈱シクロケムバイオ
生田直子 神戸大学大学院
松郷誠一 金沢大学大学院
岡本陽菜子 ㈱シクロケムバイオ
王堂哲 ロンザジャパン㈱
西澤英寿 新田ゼラチン㈱
長谷篤史 新田ゼラチン㈱
井上直樹 新田ゼラチン㈱
越智浩 森永乳業㈱
佐藤浩之 三栄源エフ・エフ・アイ㈱
小磯博昭 三栄源エフ・エフ・アイ㈱
相澤光輝 焼津水産化学工業㈱
浅利晃 ㈱ヒアルロン酸研究所
黒住誠司 甲陽ケミカル㈱
加賀出穂 甲陽ケミカル㈱
島田研作 松谷化学工業㈱
古根隆広 ㈱シクロケムバイオ
椿和文 ㈱ADEKA
中田大介 ㈱シクロケム
佐藤慶太 ㈱シクロケムバイオ
笠井通雄 日清オイリオグループ㈱
戸田登志也 フジッコ㈱
市川剛士 サンブライト㈱
眞岡孝至 (一財)生産開発科学研究所
小暮健太朗 徳島大学
上野千裕 ㈱シクロケムバイオ
渡邉由子 三菱化学フーズ㈱
田川大輔 森下仁丹㈱
-------------------------------------------------------------------------
<<目次>>
【第Ⅰ編 汎用技術】
第1章 油脂コーティング・可溶化技術による機能性成分の生体利用率向上
1 はじめに
2 当社のコーティング技術
2.1 油脂コーティング技術
2.2 マルチコーティング技術
2.3 球形コーティング
2.4 ビフィズス菌への耐酸性付与
2.5 水溶性ビタミンの生体利用率の向上
3 可溶化技術
3.1 可溶化技術概要
3.2 脂溶性ビタミン可溶化液
3.3 脂溶性機能脂質成分可溶化液
4 おわりに
第2章 リケビーズ
1 はじめに
2 マイクロカプセルとは
3 安定化のデータ・事例
3.1 使用例1(機能性成分の酸化安定性の向上,ハンドリング改善)
3.2 使用例2(香料;メントール)
3.3 使用例3(2成分接触による配合変化防止)
4 製品適用事例
5 リケビーズその他のシェル剤
6 まとめ
第3章 シクロデキストリン
1 はじめに
2 シクロデキストリンの性質
2.1 包接機能
2.2 シクロデキストリンの水溶性
2.3 シクロデキストリンの消化性
2.4 シクロデキストリンの安全性
2.5 包接化方法
3 CD包接による機能性食品素材の安定化
4 おわりに
【第Ⅱ編 成分別技術】
第1章 コエンザイムQ10
1 はじめに
2 コエンザイムQ10の問題点
3 コエンザイムQ10の安定性改善
3.1 シクロデキストリン
3.2 熱・光に対する安定性
3.3 他製剤との配合
3.4 サプリメントの開発
4 おわりに
第2章 R-α-リポ酸
1 R-α-リポ酸とは
2 R-α-リポ酸の安定化
3 シクロデキストリンを用いたR-α-リポ酸の安定化技術
3.1 R-α-リポ酸-CD包接複合化法
3.2 R-α-リポ酸-CD包接複合体のSEM解析
3.3 R-α-リポ酸-CD包接複合体のXRD解析
3.4 R-α-リポ酸-CD包接複合体の熱安定性試験
3.5 R-α-リポ酸-CD包接複合体の酸安定性試験
3.6 R-α-リポ酸-γCD包接複合体の吸収性と溶解性試験
3.7 R-α-リポ酸-γCD包接複合体のヘルシーエイジング効果,抗糖尿作用
4 おわりに
第3章 δ-トコトリエノール
1 はじめに
2 γCD包接によるα-TPおよびγ-T3の安定性の改善
2.1 T3-γCD包接複合体の作製
2.2 T3-γCD包接複合体の熱安定性の検討
3 γCD包接によるT3の生体利用能の向上
3.1 γCD包接化によるT3の吸収性への影響
3.2 γCD包接化によるT3の生理活性への影響
3.3 T3-γCD包接複合体の効果
4 おわりに
第4章 L-カルニチン
1 はじめに
2 L-カルニチンの基本物性
3 利用上の安定性
4 熱安定性
5 光に対する安定性
6 安定化技術
7 加工実績
8 安全性
9 使用上の留意点
10 機能性と利用分野
10.1 脂肪燃焼の促進
10.2 体重・血中中性脂肪の減少効果
10.3 アセチルカルニチンを生成しエネルギー代謝を円滑化
10.4 アセチルカルニチンの神経作用
10.5 スポーツ栄養素としての活用
10.6 がん患者の場合
11 おわりに
第5章 コラーゲンペプチドの製造方法とその安定化技術の特徴
1 はじめに
1.1 コラーゲンとは
1.2 コラーゲン,ゼラチン,コラーゲンペプチド,アミノ酸の違い
2 コラーゲンペプチドの製法と品質への影響
2.1 ゼラチンの抽出技術
2.2 コラーゲンペプチドの製法
3 コラーゲンペプチドのアプリケーションへの利用
3.1 コラーゲンペプチドの性質や特徴
3.2 コラーゲンペプチドの反応性
3.3 コラーゲンペプチドの介護食への利用
4 コラーゲンペプチドの機能性
4.1 生理活性ペプチド
4.2 肌への効果
第6章 乳ペプチドを用いた食品物性安定化と適用事例
1 はじめに
2 粘度
3 食感向上
3.1 麺の食感向上
3.2 魚ねり製品の食感向上
3.3 チーズの食感向上
4 起泡性
4.1 起泡性ペプチド
4.2 焼成食品への応用
4.3 発泡飲料への応用
4.4 ホイップクリームへの応用
5 おわりに
第7章 抗菌ペプチド(リゾチーム,ナイシン)
1 はじめに
2 リゾチーム
3 リゾチームの抗菌効果
4 リゾチームの安定性
5 リゾチームの効果的な使い方
6 食品添加物としてのナイシン
7 ナイシンの抗菌効果
8 ナイシンの安定性について
9 ナイシンの効果的な使用方法
10 おわりに
第8章 グルコサミンの物性と応用
1 はじめに
2 NAGとグルコサミン
3 製造方法
4 食品への利用に関わる物性
4.1 味質と甘味度
4.2 溶解度
4.3 吸湿性と水分活性
4.4 pH安定性
4.5 着色性
5 サプリメントへの応用例
6 安全性
7 おわりに
第9章 ヒアルロン酸
1 はじめに
2 ヒアルロン酸の生物学・生化学
3 ヒアルロン酸の生理活性は分子量によって異なる
4 極大のヒアルロン酸による抗腫瘍作用
5 極小のヒアルロン酸(HA4)による組織恒常性維持
6 おわりに
第10章 キトサン
1 はじめに
2 キトサンの酸に対する溶解性
2.1 キトサンの溶解方法
2.2 溶解可能な酸の種類
2.3 キトサンの粘度と分子量の関係
2.4 キトサンの酸解離定数(pKa)とpHによるキトサンの性質
3 キトサンの抗菌性
3.1 キトサンの分子量と各種菌への抗菌性
3.2 キトサンの各種菌への抗カビ性
3.3 日持ち向上剤としての食品への応用例
4 キトサンの物性
4.1 吸湿性(粉末)
4.2 苛酷試験による粘度,および着色変化(粉末)
4.3 保存安定性(粉末,ポリエチレン袋入り)
4.4 加熱試験による粘度,および着色変化(溶液)
4.5 保存試験(溶液)
4.6 食品加工を想定した安定性
4.7 加工食品の使用例
5 まとめ(キトサンの食品中の安定化)
第11章 難消化性デキストリンの応用
1 はじめに
2 製造方法,分析方法および安全性
3 物理化学的性質
4 構造
5 特長
5.1 マスキング効果
5.2 安定化効果
5.3 その他の特長―生理機能
6 今後の展望
第12章 α-シクロデキストリン
1 はじめに
2 化学的安定性
3 健康に対する機能性
3.1 食後の血中中性脂肪値に対する上昇抑制効果
3.2 脂肪酸の選択的排泄効果
3.3 食後の血糖値の上昇抑制効果
3.4 LDL-コレステロール低減効果
3.5 抗アレルギー効果
4 安定化ならびにその他の応用
4.1 色素の褐変化防止
4.2 タンパクの安定化
4.3 相乗的な抗菌効果の向上
4.4 水溶性の向上
4.5 味のマスキング効果
4.6 その他の応用
5 おわりに
第13章 大麦由来βグルカン
1 はじめに
2 大麦βグルカンの食経験と健康強調表示について
3 大麦βグルカン分子について
4 抽出された大麦βグルカンの特徴
5 大麦βグルカンの機能性
5.1 内臓脂肪の蓄積と耐糖能に及ぼす影響
5.2 大麦βグルカンの抗酸化作用
5.3 低分子化大麦βグルカンの免疫活性評価
5.4 大麦βグルカンの血圧降下作用
6 おわりに
第14章 シクロデキストリンによる不飽和脂肪酸の安定化技術
1 はじめに
2 脂肪酸について
3 CDによる脂肪酸の安定化
3.1 試験方法
3.2 包接体調製方法
3.3 ω-3不飽和脂肪酸(PUFA)-CD包接体
3.4 ω-6系不飽和脂肪酸(PUFA)-CD包接体粉末
3.5 中鎖飽和脂肪酸-CD包接体
4 おわりに
第15章 クリルオイル
1 はじめに
2 オキアミ
3 クリルオイル
4 クリルオイルの酸化安定性向上
第16章 α-リノレン酸
1 はじめに
2 α-リノレン酸を含有する食用油
3 α-リノレン酸の安定性
3.1 保存時および開封後の安定性
3.2 酸化安定化技術
3.3 調理時の安定性
4 α-リノレン酸の栄養機能トピックス
5 おわりに
第17章 大豆イソフラボン
1 はじめに
2 大豆イソフラボンとは
3 大豆食品に含まれるイソフラボン
3.1 イソフラボン量
3.2 イソフラボン組成
4 大豆加工中のイソフラボンの変化
5 発酵によるイソフラボンの構造変換
6 シクロデキストリン(CD)による大豆イソフラボンの包接
7 おわりに
第18章 カロテノイド(リコピン,ルテイン,カロテン)
1 カロテノイドとは
2 主要なカロテノイドについて
2.1 ベータカロテン
2.2 リコピン
2.3 ルテイン
3 カロテノイド製剤の安定性と安定化技術
3.1 酸化防止剤による安定化
3.2 コーティング等による安定化
4 おわりに
第19章 アスタキサンチン
1 はじめに アスタキサンチンの構造と自然界における分布
2 アスタキサンチンの生理機能
2.1 抗酸化作用
2.2 その他の生理作用
3 アスタキサンチンの分解要因
3.1 熱,光による異性化
3.2 アルカリ溶液中での反応
3.3 酸素(活性酸素)やフリーラジカルとの反応
4 アスタキサンチンの安定化技術
4.1 抽出時に熱や酸素への暴露による分解を防ぐための技術
4.2 製品中のアスタキサンチンの安定化技術
4.3 光,紫外線遮断の容器の開発
5 まとめ
第20章 イソチオシアネート類とテルペノイド
1 はじめに
2 イソチオシアネート類
2.1 ワサビの辛味成分AITCの安定化
2.2 大根の辛味成分MTBIの安定化
3 テルペノイド
3.1 l-メントール
3.2 ヒノキチオール
3.3 ゲラニオール
3.4 リモネン
第21章 プロバイオティクスの先駆け-有胞子性乳酸菌ラクリスTM-
1 はじめに
2 有胞子性乳酸菌の形成
3 有胞子性乳酸菌の特長
4 有胞子性乳酸菌の腸管内での増殖と影響
5 有胞子性乳酸菌の食品への利用
6 有胞子性乳酸菌の安全性と位置づけ
7 おわりに
第22章 森下仁丹シームレスカプセル技術とビフィズス菌カプセルへの応用
1 はじめに
2 森下仁丹シームレスカプセル技術について
2.1 森下仁丹シームレスカプセルの製造方法
2.2 森下仁丹シームレスカプセルの機能と特性
2.3 生きた乾燥ビフィズス菌末のカプセル化
2.4 バイオカプセルの開発
3 ビフィズス菌カプセルへの応用
3.1 ビフィズス菌カプセル
3.2 ビフィズス菌カプセル接種効果
-

異種材料接合技術《普及版》
¥3,740
2016年刊「異種材料接合技術」の普及版。自動車、宇宙・航空など各産業分野で採用されている軽量化技術の突破口である「マルチマテリアル」のための異種材料接合技術について解説した1冊。
(監修:中田一博)
<a href="http://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=9278"target=”_blank”>この本の紙版「異種材料接合技術(普及版)」の販売ページはこちら(別サイトが開きます)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は、2016年当時のものを使用しております。
中田一博 大阪大学名誉教授;大阪大学
井上雅博 群馬大学
立野昌義 工学院大学
早川伸哉 名古屋工業大学
佐藤千明 東京工業大学
塩山務 バンドー化学㈱
高橋正雄 大成プラス㈱
林知紀 メック㈱
三瓶和久 ㈱タマリ工業
花井正博 多田電機㈱
吉川利幸 多田電機㈱
水戸岡豊 岡山県工業技術センター
日野実 広島工業大学
前田知宏 輝創㈱
望月章弘 ポリプラスチックス㈱
永塚公彬 大阪大学
佐伯修平 ㈱電元社製作所
北本和 ㈱電元社製作所
岩本善昭 ㈱電元社製作所
榎本正敏 ㈱WISE企画
瀬知啓久 鹿児島県工業技術センター
堀内伸 (国研)産業技術総合研究所
鈴木靖昭 鈴木接着技術研究所
-------------------------------------------------------------------------
<<目次>>
〔第1編 異種材料の接合メカニズム・表面処理〕
第1章 接着・接合技術のための化学結合論
1 はじめに
2 化学結合とは何か
2.1 化学結合の概念
2.2 分子中の電荷分布に起因する化学結合の性質
2.3 金属結合のモデル化
3 2つの分子間に発生する化学的相互作用
3.1 van der Waals力
3.2 水素結合の形成
4 化学的相互作用を解析するための古典モデル
4.1 水素結合の古典的なモデル化
4.2 溶解度パラメータ
4.3 古典モデルの適用限界
5 分子軌道論に基づく界面結合形成の解析
5.1 酸・塩基仮説の考え方
5.2 分子軌道論に基づく界面相互作用の解析
5.3 電子の化学ポテンシャル
5.4 電子の化学ポテンシャルの微分による反応性指標の導入
5.5 フロンティア分子軌道論と酸・塩基仮説の比較
5.6 現実の系で界面電子移動が発現する条件
6 おわりに
第2章 異種材料接合界面の力学
1 はじめに
2 異種材料接合界面端近傍における力学的問題点
2.1 異材界面端近傍の応力
2.2 Dundursの複合パラメータ
2.3 特異応力場
3 セラミックス/金属接合体の引張り強度と破壊様式
3.1 接合体引張り強度および破壊様式に及ぼす接合処理温度の影響
3.2 接合体引張り強度に及ぼす接合界面端形状の影響
4 おわりに
第3章 金属と樹脂のレーザ接合における表面処理と接合強度
1 はじめに
2 レーザ接合の原理
2.1 熱可塑性樹脂のレーザ溶着
2.2 金属と樹脂のレーザ接合
2.3 接合面の到達温度
3 アルミニウムとアクリルの接合
3.1 金属接合面の前処理
3.1.1 サンドブラスト処理
3.1.2 陽極酸化処理
3.2 レーザ光吸収率
3.3 接合強度
3.4 接合面の観察
3.4.1 アルミニウムの接合面(接合前)
3.4.2 アクリルの接合面(接合後)
3.4.3 サンドブラストと陽極酸化の処理効果の比較
3.5 金属微細孔への樹脂の流入深さ
3.5.1 樹脂の流入深さと接合強度の関係
3.5.2 接合面内の温度分布と樹脂の流入深さの関係
4 チタンとアクリルの接合
5 おわりに
〔第2編 異種材料接合における技術開発〕
第1章 接着法
1 次世代自動車へのCFRPの適用と接着技術の課題
1.1 はじめに
1.2 現状における接着接合の車体構造への適用
1.2.1 スチール製車体の接着接合
1.2.2 アルミ製車体の接着接合
1.2.3 プラスチック材料の車体への適用と接着接合
1.2.4 複合材料の車体への適用と接着接合
1.3 今後の車体軽量化への取り組みと接着接合技術
1.3.1 マルチマテリアル化
1.3.2 組み立て工程への適合性
1.3.3 接着剤の硬化速度の問題
1.3.4 インプロセス塗装,アウトプロセス塗装への対応
1.3.5 接着技術にも求められる環境対応
1.4 おわりに
2 ゴムと金属の直接接着技術
2.1 はじめに
2.2 ゴム固有の問題
2.3 直接加硫接着技術
2.3.1 ブラスとゴムの直接加硫接着
2.3.2 亜鉛とゴムの直接加硫接着
2.4 今後の技術開発について
第2章 射出成形(インサート成形)による接合
1 異材質接合品への耐湿熱性能の付与
1.1 はじめに
1.2 NMT
1.3 新NMT
1.4 射出接合可能な樹脂
1.5 恒温恒湿試験
1.6 腐食による接合部の破壊
1.7 NMTへの耐湿熱性能の付与
1.8 アルミ以外の金属での湿熱性能
1.9 まとめ
2 粗化エッチングによる樹脂・金属接合
2.1 はじめに
2.2 アマルファ処理について
2.3 各種金属での粗化形状
2.4 インサート射出成形による接合強度測定サンプルの作成
2.5 インサート射出成形による接合強度測定結果
2.6 考察
第3章 高エネルギービーム接合
1 レーザ技術を用いたCFRP・金属の接合技術と今後の課題
1.1 はじめに
1.2 自動車の軽量化と材料の変遷
1.3 自動車構成材料のマルチマテリアル化と異材接合
1.4 樹脂材料のレーザ溶着技術
1.5 樹脂と金属のレーザ溶着技術
1.5.1 化学的な結合による方法
1.5.2 機械的な結合による方法
1.6 CFRPと金属材料の接合
1.6.1 CFRPの自動車部材への適用と課題
1.6.2 熱可塑性CFRTPの接合技術
1.7 今後の課題と展望
2 電子ビーム溶接による銅とアルミニウムなどの異種金属接合
2.1 はじめに
2.2 電子ビーム溶接法について
2.2.1 原理
2.2.2 特長
2.2.3 他工法との比較
2.2.4 適用用途
2.3 異種金属材料の溶接事例
2.3.1 銅-銅合金の接合事例
2.3.2 銅-アルミの接合事例
2.3.3 銅-ステンレスの接合事例
2.3.4 アルミ合金の溶接事例
2.4 電子ビーム溶接機について
2.5 現状の課題と今後の展望について
3 エラストマーからなるインサート材を用いた異種材料のレーザ接合技術
3.1 はじめに
3.2 インサート材を用いたレーザ接合
3.2.1 開発プロセスの特徴
3.2.2 プラスチックとの接合
3.2.3 金属との接合
3.2.4 他の異種材料接合プロセスとの違い
3.3 現在の取り組み
3.3.1 スマートフォンへの採用
3.3.2 様々な分野への拡がり
3.4 今後の展開
3.4.1 熱可塑性CFRPの接合
3.4.2 新たな接合の可能性
3.5 おわりに
4 インサート材を用いた異種材料のレーザ接合のための金属表面処理
4.1 はじめに
4.2 接着に適した金属表面の改質
4.2.1 熱可塑性エラストマーをインサートしたアルミニウム-プラスチックレーザ接合
4.2.2 接着性に優れたアルミニウム合金への陽極酸化処理
4.3 おわりに
5 ポジティブアンカー効果による金属とプラスチックの直接接合
5.1 はじめに
5.2 金属-プラスチック直接接合技術の概要
5.3 ポジティブアンカー効果による金属とプラスチックの接合
5.4 PMS処理
5.4.1 PMS処理概要
5.4.2 PMS処理方法
5.4.3 PMS処理条件
5.5 金属とプラスチックの接合
5.6 おわりに
6 樹脂表面へのレーザ処理による異種材料接合技術
6.1 緒言
6.2 AKI-LockRの概要
6.3 AKI-LockRの諸特性
6.3.1 接合強度
6.3.2 従来の接合技術とAKI-LockRの接合強度比較
6.3.3 耐久性
6.3.4 かしめ,収縮による圧着効果
6.3.5 まとめ
6.4 結言
第4章 摩擦撹拌接合
1 摩擦攪拌接合による異種材料接合の展望
1.1 状態図から見た金属材料同士の異材接合の可能性評価
1.2 異材接合が可能となる接合界面構造
1.3 摩擦攪拌接合(FSW)法
1.4 FSWによる異材接合継手形成例
1.4.1 鉄/アルミニウム 異材接合
1.4.2 鉄/銅 異材接合
1.4.3 鉄/チタン 異材接合
1.4.4 アルミニウム/チタン 異材接合
1.4.5 アルミニウム/銅 異材接合
1.4.6 アルミニウム/マグネシウム 異材接合
1.4.7 マグネシウム/チタン 異材接合
1.4.8 鋳物・ダイカスト材と展伸材との異材接合
1.4.9 複合材料(粒子分散型アルミニウム基合金)と展伸材との異材接合
1.5 摩擦攪拌点接合FSSWによる異材接合
2 摩擦重ね接合法による金属と樹脂・CFRPの接合
2.1 はじめに
2.2 摩擦重ね接合
2.3 金属/樹脂の接合
2.3.1 Al合金/ポリアミド6の接合特性に及ぼすAl合金中のMg添加量の影響
2.3.2 鉄鋼材料/樹脂の接合に及ぼす樹脂中の極性官能基の影響
2.4 金属/CFRTPの接合
2.5 金属への表面処理が接合特性に及ぼす影響
2.6 ロボットFLJによる金属/CFRTPの接合
2.7 まとめ
第5章 その他の接合方法
1 シリーズ抵抗スポット溶接による金属とCFRPの接合
1.1 はじめに
1.2 シリーズ抵抗スポット溶接を用いた金属/樹脂・CFRPの接合
1.3 実験方法
1.4 実験結果および考察
1.5 まとめ
2 アルミニウムとチタンのアーク溶接
2.1 はじめに
2.2 異種金属材料接合の基本的な考え方
2.3 A6N01と純TiのTIG溶接
2.3.1 供試材および溶接条件
2.3.2 溶接結果
2.4 おわりに
3 レーザろう付による金属とセラミックス・ダイヤモンドの接合
3.1 はじめに
3.1.1 レーザろう付(レーザブレージング)とは
3.1.2 セラミックスと金属の異材接合
3.1.3 セラミックスと金属の異材接合へのレーザブレージングの応用
3.2 接合方法と装置の特徴
3.2.1 接合方法
3.2.2 装置の特徴
3.3 代表的な接合事例
3.3.1 SiC,サイアロンならびに単結晶ダイヤモンドと超硬合金への適用事例
3.3.2 界面反応層の生成状況とせん断強度
3.4 まとめ
〔第3編 評価〕
第1章 異種材料接合の国際標準化
1 背景
2 樹脂-金属接合界面特性評価方法の開発
2.1 引張り接合特性(突合わせ試験片)
2.2 せん断接合特性
2.3 剥離強度特性
2.4 樹脂-金属接合界面の封止特性評価
2.5 冷熱衝撃試験,高温高湿試験
2.6 疲労試験
3 国際標準化活動
第2章 異種材料接合部の耐久性評価と寿命予測法
1 アレニウスの式に基づいた温度による劣化および耐久性評価法
1.1 化学反応速度式と反応次数
1.2 濃度と反応速度および残存率との関係
1.3 材料の寿命の決定法
1.4 反応速度定数と温度との関係
1.5 アレニウス式を用いた寿命推定法
2 アイリングモデルによる機械的応力,湿度などのストレス負荷条件下の耐久性加速試験および寿命推定法
2.1 アイリングの式を用いた寿命推定法
2.2 アイリング式を用いた湿度に対する耐久性評価法
2.2.1 Lycoudesモデルによる寿命予測方法例
2.2.2 Lycoudesモデルによる寿命予測の具体例
2.3 Sustained Load Test
2.3.1 接着剤A(一液性120℃/1h硬化エポキシ系)の場合
2.3.2 接着剤F(二液性60℃/3h硬化エポキシ系)の場合
2.3.3 フィルム型接着剤(177℃ 加熱硬化 ノボラック・エポキシ系)の場合
3 ジューコフ(Zhurkov)の式を用いた応力下の継手の寿命推定法
3.1 ジューコフの式
3.2 ジューコフの式による接着継手のSustained Load Test結果の解析
-

高熱伝導樹脂の設計・開発《普及版》
¥3,520
2016年刊「高熱伝導樹脂の設計・開発」の普及版。高分子の熱伝導現象、熱伝導率の測定方法、高分子そのものの高熱伝導化、応用分野での放熱設計等について解説した1冊。
(監修:伊藤雄三)
<a href="http://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=9279"target=”_blank”>この本の紙版「高熱伝導樹脂の設計・開発(普及版)」の販売ページはこちら(別サイトが開きます)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は、2016年当時のものを使用しております。
伊藤雄三 工学院大学
上利泰幸 (地独)大阪市立工業研究所
池内賢朗 アドバンス理工㈱
鴇崎晋也 三菱電機㈱
原田美由紀 関西大学
長谷川匡俊 東邦大学
上谷幸治郎 立教大学
大山秀子 立教大学
田中慎吾 ㈱日立製作所
北條房郎 ㈱日立製作所
竹澤由高 日立化成㈱
武藤兼紀 古河電子㈱
橋詰良樹 東洋アルミニウム㈱
中村将志 神島化学工業㈱
坂本健尚 神島化学工業㈱
冨永雄一 産業技術総合研究所
堀田裕司 産業技術総合研究所
内田哲也 岡山大学
正鋳夕哉 ユニチカ㈱
横井敦史 豊橋技術科学大学
小田進也 豊橋技術科学大学
武藤浩行 豊橋技術科学大学
林蓮貞 ㈱KRI
林裕之 ㈱KRI
阿多誠介 産業技術総合研究所
福森健三 ㈱豊田中央研究所
近藤徹 阿波製紙㈱
藤田哲也 ㈱ジィーサス
門田健次 デンカ㈱
安田丈夫 東芝ライテック㈱
蒲倉貴耶 東芝ライテック㈱
-------------------------------------------------------------------------
<<目次>>
【第Ⅰ編 熱伝導理論と熱分析法】
第1章 高分子材料の熱伝導現象の基礎
1 緒言
2 熱伝導の基礎
2. 1 熱伝導率の定義(Fourierの法則)
2. 1. 1 1次元
2. 1. 2 3次元
2. 2 熱伝導率と物質定数との関係(Debyeの式)
2. 3 電子による熱伝導とフォノンによる熱伝導
2. 3. 1 電子による熱伝導
2. 3. 2 ヴィーデマン―フランツの法則(Wiedemann-Franz law)
2. 3. 3 様々な物質の熱伝導率
2. 4 熱伝導率を決める因子,定圧体積比熱,フォノンの速度,平均自由行程
2. 5 平均自由行程を決める因子,静的散乱と動的散乱
2. 5. 1 フォノンの静的散乱
2. 5. 2 フォノンの動的散乱
2. 6 Boltzmann の輸送方程式によるフォノンフォノン散乱を考慮した熱伝導率の定量的解析
3 高分子の熱伝導
3. 1 高分子の熱伝導の特徴
3. 2 高分子の高次構造と熱伝導率
3. 2. 1 結晶性と熱伝導率
3. 2. 2 分子配向と熱伝導率
4 高熱伝導高分子
4. 1 高分子の高熱伝導化のメカニズム
4. 1. 1 絶縁性と高熱伝導の両立
4. 1. 2 高分子の熱伝導率の理論限界―ポリエチレン結晶の熱伝導率の理論解析―
第2章 高分子材料の高熱伝導化技術と最近のトレンド
1 高放熱性高分子材料への期待
2 高分子自身の高熱伝導化
3 高分子材料の複合化による熱伝導率の向上
3. 1 複合材料の熱伝導率に与える影響因子とそれを踏まえた高熱伝導化方法
3. 2 従来から行われている改善方法
3. 2. 1 ファイバー状および板状の充填材の使用
3. 2. 2 充填材の粒度分布の工夫
3. 2. 3 充填材の連続体形成量の増大
3. 3 最近開発された改善方法
3. 3. 1 充填材の連続体形成量をさらに増大するために充填材を連続相に
3. 3. 2 充填材の接触面を増大し,完全な連続相に
3. 3. 3 ダブルパーコレーションの利用
3. 3. 4 多種の粒子の利用
3. 3. 5 複合液晶性高分子材料の熱伝導率
3. 3. 6 カーボン系フィラーの利用
4 応用分野と将来性
第3章 熱伝導率・熱拡散率測定装置の使用法と応用事例
1 はじめに
2 バルク材料の測定方法
2. 1 各測定方法の説明
2. 2 測定事例
3 基板上の薄膜材料の測定方法
4 おわりに
第4章 高分子材料の熱伝導率の分子シミュレーション技術
1 はじめに
2 各種材料の熱伝導性
3 結晶のデバイ理論
4 熱伝導率の分子シミュレーション技術
5 解析事例
6 おわりに
【第Ⅱ編 高分子の高熱伝導化】
第1章 エポキシ樹脂の異方配向制御による高熱伝導化
1 はじめに
2 メソゲン骨格エポキシ樹脂の特徴と局所配列構造を持つエポキシ樹脂の熱伝導性
3 巨視的な異方配列構造を持つエポキシ樹脂の熱伝導性
4 低融点型液晶性エポキシ樹脂の熱伝導性
5 配列構造形成を利用した高熱伝導コンポジットの調製
第2章 ベンゾオキサゾール基含有サーモトロピック液晶性ポリマー
1 電気絶縁性・高熱伝導性樹脂材料の必要性
2 ポリベンゾオキサゾール(PBO)繊維の熱伝導性と放熱フィルムへの適用の可能性
3 ベンゾオキサゾール(BO)基を含む高分子系
3. 1 長鎖アルキレン基含有PBO
3. 2 BO基をペンダントしたポリメタクリレート(側鎖型PBO)
3. 3 BO基含有ジアミンとビスエポキシドの熱硬化物
4 液晶性エポキシ樹脂に残された問題と課題
第3章 断熱材から伝熱材へ ?ナノセルロースの挑戦?
1 はじめに
2 ナノセルロースと紙
3 セルロースの伝熱特性
4 ナノセルロースの調製
5 NCシートと繊維構造
6 NCシートの熱伝導特性
7 NCシートを骨格とする透明熱伝導フィルム
8 おわりに
【第Ⅲ編 フィラーの高熱伝導化】
第1章 高熱伝導性と高耐水性を両立するAlNフィラー皮膜の設計
1 はじめに
2 AlN表面へのα-Al2O3皮膜層の形成
3 AlN表面へのα-Al2O3/有機ハイブリッド皮膜層の形成
4 ハイブリッド皮膜AlNフィラーの熱伝導率の予測
5 おわりに
第2章 高熱伝導AlNフィラーFAN-fシリーズ
1 はじめに
2 古河電子フィラーについて
2. 1 FAN-fシリーズ
2. 2 製法概略
2. 3 各グレード概略
2. 3. 1 FAN-f80-A1(以下f80)
2. 3. 2 FAN-f30-A1(以下f30)
2. 3. 3 FAN-f50-A1(以下f50)
2. 3. 4 FAN-f05-A1(以下f05)
3 AlN の課題
3. 1 耐水性
3. 2 古河電子での水和対策
3. 3 表面処理
4 古河電子でのフィラー用途開発取組み
5 おわりに
第3章 Al/AlN フィラー(TOYAL TecFillerR)
1 TOYAL TecFiller?について
2 アルミニウムフィラー
2. 1 金属の熱伝導
2. 2 アルミニウム熱伝導フィラー
2. 3 TOYAL TecFiller TFHシリーズ
3 窒化アルミニウムフィラー
3. 1 窒化アルミニウムの熱伝導
3. 2 窒化アルミニウムの製造方法
3. 3 窒化アルミニウム熱伝導フィラー
3. 4 TOYAL TecFiller TFZ シリーズ
第4章 熱伝導フィラー用マグネシウム化合物
1 はじめに
2 熱伝導フィラー用酸化マグネシウム
2. 1 酸化マグネシウムの一般特性
2. 2 耐水性・耐酸性の改善
2. 3 応用特性例
3 熱伝導フィラー用無水炭酸マグネシウムについて
3. 1 炭酸マグネシウムの一般特性
3. 2 合成マグネサイト
3. 3 応用特性例
4 最後に
第5章 高熱伝導性コンポジット用h-BN剥離フィラー
1 はじめに
2 低充填量でのコンポジットの高熱伝導化を可能とするフィラーの形状
3 機械的プロセスを利用した高アスペクト比のh-BN剥離フィラーの開発
4 剥離h-BNフィラーがおよぼすコンポジットの熱伝導率,機械特性および成形性への影響
5 おわりに
第6章 単層カーボンナノチューブの凝集構造制御と複合体への応用
1 はじめに
2 SWNTナノフィラー
3 SWNTナノフィラーを用いたPVAとの複合体フィルムの作製とその構造評価
4 複合体フィルムの物性評価
4. 1 力学物性
4. 2 熱物性
5 延伸フィルムの物性評価
5. 1 力学物性
5. 2 熱物性
6 延伸複合体フィルム中のSWNTナノフィラーの配向
7 まとめ
【第Ⅳ編 コンポジット材料の高熱伝導化】
第1章 高放熱ナイロン6樹脂
1 はじめに
2 高熱伝導率フィラー
3 高放熱ナイロン6樹脂の概要
3. 1 高放熱ナイロン6樹脂の特性
3. 2 高放熱ナイロン6樹脂の成形加工性
3. 3 耐衝撃グレードの開発
4 高放熱ナイロン6樹脂の放熱性
4. 1 ヒートシンクでの放熱性評価
4. 2 金属との一体成形
5 採用事例
6 おわりに
第2章 高熱伝導高分子複合材料設計のための微構造制御
1 はじめに
2 複合粒子作製と微構造設計
2. 1 複合粒子作製
2. 2 微構造設計
2. 3 静電吸着複合法の利点
3 複合材料の設計指針
3. 1 h-BN-PMMA複合粒子設計
3. 2 h-BN-PMMA複合材料の作製
3. 3 パーコレーション構造および配向構造
4 おわりに
第3章 セルロースナノファイバー/h-BN複合絶縁性放熱材
1 はじめに
2 CNFの製造およびその特性について
3 表面エステル化修飾CNFの一段階調製法について
4 アセチル化修飾CNFをマトリックスとした複合化放熱材
4. 1 複合化放熱材のマトリックスとするCNFのメリット
4. 2 Acetyl-CNFをマトリックスとした複合化放熱材の作製と評価
5 おわりに
第4章 単層カーボンナノチューブの複合化によるゴムの熱伝導性向上
1 緒言
2 CNTを用いた柔らく熱伝導性の高い材料開発
2. 1 CNTの熱伝導率
2. 2 CNT/CFハイブリッド材料
2. 3 熱伝導材料としてのCNTの分散処理
3 まとめ
第5章 CNT分散構造制御による絶縁樹脂の高熱伝導化技術
1 はじめに
2 樹脂の高熱伝導化技術
2. 1 従来手法-無機系熱伝導性フィラーの配合-
2. 2 新規手法-マトリックス樹脂の高熱伝導化-
2. 2. 1 樹脂の分子構造制御技術-液晶性分子骨格の導入-
2. 2. 2 高熱伝導性と高絶縁性を両立する新規CNT分散構造モデルと材料創製
2. 2. 3 CNT分散構造制御PPS系複合体の熱伝導性と絶縁性
2. 2. 4 新規手法の応用
3 おわりに
第6章 CARMIX熱拡散シート
1 はじめに
2 「CARMIX熱拡散シート」各グレードの特徴
2. 1 グレードと基本物性
2. 2 各グレードの特長
2. 3 構造
2. 4 表面加工
2. 5 性能比較
2. 5. 1 ヒーターを用いた放熱テスト
2. 5. 2 ヒートシンクとして比較
3 まとめと今後の展開
【第Ⅴ編 応用別放熱設計】
第1章 パワーエレクトロニクス機器の放熱設計と樹脂材料
1 パワーエレクトロニクス機器とその動向
1. 1 パワーエレクトロニクスの課題
2 製品の熱設計の考え方と放熱部材としての樹脂
2. 1 製品の熱設計の考え方
2. 2 熱設計の原理
2. 2. 1 消費電力(発熱量)の把握
2. 2. 2 目標熱抵抗の算出
2. 2. 3 エレクトロニクス製品の熱回路
2. 3 樹脂材料に求められる絶縁性と熱伝導の両立性
3 パワーエレクトロニクス装置の熱設計例とその課題
3. 1 太陽光発電システムとその熱設計例
3. 2 パワーコンディショナーの構成
3. 3 熱設計の例
3. 4 実装構造上の課題
3. 5 製品設計に必要な高熱伝導性材料の性能と樹脂の可能性
第2章 次世代自動車のパワーモジュールにおける放熱設計と求められる樹脂材料
1 はじめに
2 HEV/PHEVに用いられるインバータ
3 インバータの放熱設計
4 求められる樹脂材料
5 おわりに
第3章 LED照明の放熱設計と求められる樹脂材料
1 白色LED照明と放熱技術
2 LED照明に用いられる樹脂材料
-

潜熱蓄熱・化学蓄熱・潜熱輸送の最前線《普及版》
¥4,180
2016年刊「潜熱蓄熱・化学蓄熱・潜熱輸送の最前線」の普及版。CO2削減のキーテクノロジーとして、潜熱蓄熱・化学蓄熱・潜熱輸送の理論、材料・技術開発、応用事例を解説した1冊。
(監修:鈴木洋)
<a href="http://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=9225"target=”_blank”>この本の紙版「潜熱蓄熱・化学蓄熱・潜熱輸送の最前線(普及版)」の販売ページはこちら(別サイトが開きます)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は、2016年当時のものを使用しております。
鈴木洋 神戸大学
加藤之貴 東京工業大学
島田亙 富山大学
田中明美 東京大学
富重道雄 東京大学
能村貴宏 北海道大学
大河誠司 東京工業大学
春木直人 岡山大学
大宮司啓文 東京大学
竹林英樹 神戸大学
窪田光宏 名古屋大学
藤岡惠子 ㈱ファンクショナル・フルイッド
劉醇一 千葉大学
小倉裕直 千葉大学
小林敬幸 名古屋大学
大久保英敏 玉川大学
萩原良道 京都工芸繊維大学
稲田孝明 産業技術総合研究所
熊野寛之 青山学院大学
麓耕二 弘前大学
富樫憲一 青山学院大学
堀部明彦 岡山大学
日出間るり 神戸大学
川南剛 神戸大学
熊野智之 神戸市立工業高等専門学校
-------------------------------------------------------------------------
<<目次>>
【第I編 基礎理論】
第1章 概論
1 未利用熱
2 潜熱蓄熱
3 化学蓄熱
4 潜熱輸送
第2章 潜熱蓄熱の基礎
1 潜熱と顕熱
2 潜熱蓄熱材料
3 過冷却
4 伝熱特性
5 相分離
6 まとめ
第3章 化学蓄熱の基礎論
1 化学蓄熱の必要性
2 化学蓄熱の原理と構成
3 回分型
3.1 反応系の条件と選択
3.2 化学蓄熱材料の開発事例
4 循環型
5 まとめ
第4章 潜熱輸送の基礎
1 潜熱輸送とは
2 潜熱輸送材料
3 結晶成長と凝集
4 流動特性
5 伝熱特性
【第II編 潜熱蓄熱】
第1章 包接型水和物
1 はじめに
2 相図(状態図)
3 比熱・潜熱
4 結晶構造
5 核生成・結晶成長
6 ガス種分離などへの応用
第2章 生体脂質の相変化
1 はじめに
2 皮膚組織の生体脂質
3 皮膚組織の構造
4 生体脂質の構造変化の測定方法
4.1 示差走査熱量測定(Differential Scanning Calorimetry:DSC)
4.2 比熱容量測定
5 細胞間脂質の相変化
5.1 細胞間脂質の融解
5.2 体温近傍での細胞間脂質、皮下脂肪の相変化
6 おわりに
第3章 高温熱源回収に向けた金属/合金系潜熱蓄熱材料の開発
1 はじめに
2 金属/合金PCMの概説
2.1 金属/合金PCMの種類
2.2 金属/合金PCMの特徴と利点
2.3 合金PCMにおける問題点
3 金属/合金系PCMの材料開発事例(Al-Si合金を例として)
3.1 Al-Si合金系PCMに適したセラミックス材料の探索
3.2 Al-Si合金系PCMのカプセル化
3.2.1 カプセル化の意義
3.2.2 マクロカプセル化の事例
3.2.3 マイクロカプセル化の事例
4 おわりに
第4章 過冷却解消
1 過冷却とは
1.1 均質核生成と不均質核生成
1.2 電解水の例
1.3 酢酸ナトリウム3水和物の例
2 解消確率の話
2.1 定義
2.2 凝固確率の算出方法
2.3 凝固開始予測方法
3 能動制御の話
3.1 電場
3.2 固体の衝突、摩擦
3.3 衝撃
3.4 超音波
3.5 膜付きカプセル
第5章 金属繊維材を用いた蓄放熱促進技術
1 はじめに
2 潜熱蓄熱材料の熱伝導率促進
3 金属繊維材
4 金属繊維材混合が潜熱蓄熱材料の熱物性値に与える影響
4.1 熱伝導率
4.2 その他の熱物性
5 金属繊維材混合による潜熱蓄熱材料の蓄放熱促進
5.1 放熱(凝固)特性
5.2 蓄熱(融解)特性
6 まとめ
第6章 微細領域の相変化
1 諸言
2 エリスリトールとメソポーラスシリカ
3 ナノ細孔内部におけるエリスリトールの相変化過程
4 ナノ細孔内部におけるエリスリトールの相変化と熱履歴
5 結言
第7章 建築材における蓄熱技術
1 はじめに
2 住宅における潜熱蓄熱利用技術の紹介
2.1 潜熱蓄熱空調システム
2.2 戸建住宅の太陽熱潜熱蓄熱給湯暖房システム
2.3 集合住宅の太陽熱潜熱蓄熱暖房システム
3 まとめ
【第III編 化学蓄熱】
第1章 無機水和物系反応材料
1 はじめに
2 低温化学蓄熱用反応系の探索
3 LiOH/LiOH・H2O系の化学蓄熱・ヒートポンプ特性
4 LiOH/LiOH・H2O系化学蓄熱の実現に向けた課題と課題解決に向けた取り組み
5 LiOHとMPCの複合化によるLiOHの水和速度の向上
5.1 LiOH・MPC複合材料の調製および水和特性評価
5.2 LiOH・MPC複合材料の水和速度の向上効果
6 おわりに
第2章 塩化カルシウム系反応材
1 はじめに
2 反応系と熱力学特性、作動サイクル
3 多孔性粒子層の構造と熱物性値の変化
4 体積と空隙率
5 熱容量
6 熱伝導度
6.1 有効熱伝導度と気相条件
6.2 反応気体の付加・脱離による有効熱伝導度の変化
7 塩化カルシウム/水系の反応特性
8 作動特性
9 おわりに
第3章 水酸化マグネシウム系材料
1 緒言
2 化学蓄熱の作動原理
3 化学蓄熱材の化学修飾
4 蓄熱密度の比較と今後の開発課題
第4章 カルシウム系ケミカルヒートポンプによる熱リサイクルシステム開発
1 はじめに
2 化学蓄熱技術
3 ケミカルヒートポンプ技術
3.1 熱機関とヒートポンプ
3.2 ケミカルヒートポンプの操作例
4 各種ケミカルヒートポンプシステムの開発状況
4.1 ケミカルヒートポンプ用反応材料
4.2 100℃レベル熱源駆動‐冷・温熱生成:硫酸カルシウム系ケミカルヒートポンプシステム
4.2.1 冷凍車両用エンジン廃熱蓄熱型冷熱生成ケミカルヒートポンプシステム
4.2.2 地域エネルギーリサイクル有効利用ケミカルヒートポンプコンテナシステム
4.2.3 小型電子デバイスの自己排熱駆動冷却システム
4.3 400℃レベル熱源駆動‐冷・温熱生成:酸化カルシウム系ケミカルヒートポンプシステム
4.3.1 工場排熱リサイクル型ケミカルヒートポンプドライヤーシステム
4.3.2 自動車廃熱再生利用ケミカルヒートポンプシステム
5 おわりに
第5章 化学蓄熱の伝熱促進
1 はじめに
2 化学蓄熱材料の高熱伝導度化
3 高熱伝導度化材料を用いた化学蓄熱充填層試験
4 まとめ
第6章 ハロゲン化アルカリ金属系蓄熱剤を用いる長期蓄放熱サイクル
1 はじめに
2 臭化カルシウム(CaBr2)水和反応を用いる化学蓄
3 塩化カルシウム(CaCl2)水和反応を用いる化学蓄熱
4 おわりに
【第IV編 潜熱輸送】
第1章 流動性のある潜熱蓄冷材
1 はじめに
2 相平衡状態図(融点図)
3 固液共存相における結晶成長
4 流動性のある潜熱蓄冷材
5 おわりに
第2章 I型不凍タンパク質とそれを基にした不凍ポリペプチドの利用
1 はじめに
2 溶質の添加
3 不凍タンパク質
4 型不凍タンパク質
5 一方向凝固
6 氷スラリー流
7 不凍ポリペプチド
8 短時間予熱効果
9 おわりに
第3章 不凍タンパク質の代替物質
1 不凍タンパク質の氷スラリーへの応用技術
2 不凍タンパク質の代替物質
2.1 ポリビニルアルコール
2.2 ブロック共重合体
2.3 その他の高分子
2.4 ポリペプチド、タンパク質
2.5 糖類
2.6 酢酸ジルコニウム
2.7 界面活性剤
3 おわりに
第4章 TBAB水和物スラリー
1 TBAB水和物
2 TBAB水和物の特徴
3 TBAB水和物スラリーの生成特性
4 TBAB水和物スラリーの流動特性と熱伝達特性
5 まとめ
第5章 無機水和物スラリー
1 はじめに
2 無機水和物スラリー
3 リン酸水素2ナトリウム12水和物スラリー
4 アンモニウムミョウバンスラリー
5 流動と伝熱
6 抵抗低減技術
7 まとめ
第6章 エマルション蓄熱の現状と可能性
1 はじめに
2 エマルションの種類
3 ナノエマルションの生成方法と安定性
3.1 生成方法
3.2 安定性
4 ナノエマルションの諸特性
4.1 ナノエマルションの平均粒径
4.2 密度
4.3 粘度
4.4 熱伝導率
4.5 ナノエマルションの相変化特性
第7章 D相乳化法により生成された相変化エマルションの諸特性
1 はじめに
2 D相乳化法による相変化エマルションの生成方法
3 相変化エマルションの粒径分布
4 長期分散安定性および繰り返し使用に対する耐久性試験
4.1 目視による長期分散安定性の評価
4.2 DSC曲線
4.3 供試エマルションの粘性係数
5 まとめ
第8章 マイクロカプセルスラリーの流動・熱伝達特性
1 マイクロカプセルスラリー概説
2 マイクロカプセルスラリーの熱物性
3 マイクロカプセルスラリーの圧力損失
4 直管内流動時の熱伝達挙動
5 搬送動力と熱交換量の関係
6 曲管内流動時の熱伝達挙動
7 まとめ
第9章 潜熱輸送スラリーの凝集沈降抑制技術
1 はじめに
2 低温系スラリーの流動特性、および、凝集抑制技術
3 高温系スラリーの流動特性、および、凝集抑制技術に関する現状
4 アンモニウムミョウバン水和物スラリー、および、物性
5 アンモニウムミョウバン水和物スラリー中での粒子の沈降防止技術
6 アンモニウムミョウバン水和物の結晶成長
7 まとめ
第10章 固体冷媒による冷凍・ヒートポンプ技術
1 固体冷媒による熱量効果
2 固体冷媒によるエントロピー制御のメカニズム
3 固体冷媒のエントロピー変化
3.1 磁気熱量効果
3.2 電気熱量効果
3.3 弾性熱量効果
3.4 断熱温度変化の見積もり
4 固体冷媒材料の種類
5 固体冷媒冷凍・ヒートポンプの能力と成績係数
6 まとめ
第11章 輻射冷暖房への応用
1 序論
2 人体の輻射による放熱量
3 生活に関わる輻射輸送
4 輻射冷暖房システムの概要
5 放射パネルの高性能化
5.1 放射パネル表面の材質
5.2 放射パネルにおける潜熱輸送スラリーの利用
6 躯体蓄熱の発展に向けた潜熱輸送技術の応用
7 まとめ
-

機能性色素の新規合成・実用化動向《普及版》
¥3,850
2016年刊「機能性色素の新規合成・実用化動向」の普及版。各応用分野における性能向上、新しい応用分野を切り拓くための機能性色素各種の新規合成技術を詳しく解説した1冊。
(監修:松居正樹)
<a href="http://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=9226"target=”_blank”>この本の紙版「機能性色素の新規合成・実用化動向(普及版)」の販売ページはこちら(別サイトが開きます)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は、2016年当時のものを使用しております。
松居正樹 岐阜大学
松本真哉 横浜国立大学
前田壮志 大阪府立大学
小野利和 九州大学
久枝良雄 九州大学
村中厚哉 (国研)理化学研究所;埼玉大学
内山真伸 東京大学;(国研)理化学研究所
窪田裕大 岐阜大学
船曳一正 岐阜大学
樋下田貴大 日本化薬㈱
望月典明 日本化薬㈱
八木繁幸 大阪府立大学
櫻井芳昭 (地独)大阪府立産業技術総合研究所
平本昌宏 (共)自然科学研究機構
坂本恵一 日本大学
高尾優子 (地独)大阪市立工業研究所
久保由治 首都大学東京
大山陽介 広島大学
榎俊昭 広島大学
-------------------------------------------------------------------------
<<目次>>
【総論】
第1章 機能性色素の現況
1 感熱・感圧色素
2 熱転写色素
3 カラーフィルタ用色素
4 二色性色素
5 記録用色素
6 インクジェット色素
7 有機光電導体(OPC)の電荷発生材料
8 トナー
9 太陽電池用色素
10 医療用色素
11 波長変換色素
12 センサー色素
13 その他
第2章 機能性色素の構造・物性の評価と設計
1 はじめに
2 色素分子の電子状態
3 固体状態の色素の電子状態の検討
4 機能性色素の分子設計について
【新規合成技術編】
第1章 新規スクアレン色素の開発
1 はじめに
2 縮合反応によるスクアレン色素の合成
3 触媒的クロスカップリングによるスクアレン色素の合成
4 スクアレン発色団への官能基の導入と応用展開
5 おわりに
第2章 分子の自己組織化を用いた新規の機能性色素開発
1 はじめに
2 分子の自己組織化を利用した共結晶デザイン
3 分子の自己組織化を利用した多成分結晶の調製
3.1 多成分結晶の設計と構造
3.2 多成分結晶の光機能特性
3.3 有機化合物センサーへの応用
4 おわりに
第3章 フタロシアニン系近赤外色素の合成技術
1 はじめに
2 アズレン縮合型フタロシアニン誘導体(アズレノシアニン)
3 芳香族性ヘミポルフィラジン
4 拡張型フタロシアニン
5 おわりに
第4章 ホウ素錯体色素の開発
1 はじめに
2 有機ホウ素錯体と蛍光特性
3 有機ホウ素錯体の表記法
4 N^N型ホウ素錯体
4.1 対称型BODIPY色素の合成法
4.2 非対称型BODIPY色素の合成法
4.3 BODIPY色素のメソ位(8位)への置換基導入法
4.4 BODIPY色素のβ位(2位および6位)への置換基導入法
4.5 BODIPY色素のα位(3位および5位)への置換基導入法
4.6 BODIPY色素のβ’位(1位および7位)への置換基導入法
4.7 BODIPY色素のホウ素原子上(4位)への置換基導入法
4.8 BODIPY色素の吸収および蛍光特性
4.9 BODIPY色素のメソ位の置換基の吸収・蛍光特性への影響
4.10 BODIPY色素のα位,β位,β’位の置換基の吸収・蛍光特性への影響
4.11 BODIPY色素のホウ素原子上の置換基の吸収・蛍光特性への影響
4.12 縮環型BODIPY
4.13 アザBODIPY
4.14 BODIPY色素における固体蛍光発現のための指針
4.15 ピリドメテンホウ素錯体
5 O^O型ホウ素錯体
6 N^O型ホウ素錯体
6.1 チアゾール単核ホウ素錯体
6.2 ピラジン単核ホウ素錯体
6.3 ピリミジン単核ホウ素錯体
6.4 ピリミジン二核ホウ素錯体
6.5 キノイド型二核ホウ素錯体
7 おわりに
第5章 シアニン色素の新展開
1 はじめに
2 高耐熱性ヘプタメチンシアニン色素の開発
2.1 ヨウ化物イオンを有するヘプタメチンシアニン色素(GF-8)の合成
2.2 各種アニオンを有するヘプタメチンシアニン色素の合成
2.3 各種アニオンを有するヘプタメチンシアニン色素(GF-8,9,10,11,15,16,17)のジクロロメタン(CH2Cl2)溶液中での紫外可視吸収および蛍光スペクトル
2.4 各種アニオンを有するヘプタメチンシアニン色素(GF-8,9,10,11,15,16,17)のTG-DTA測定
3 高耐光性ヘプタメチンシアニン色素の開発
3.1 メソ位に各種アミド基を有するヘプタメチンシアニン色素の合成
3.2 メソ位に各種アミド基を有するヘプタメチンシアニン色素のアニオン交換
3.3 メソ位に各種アミド基を有するヘプタメチンシアニン色素(GF-20,30)のCH2Cl2溶液中での紫外可視吸収および蛍光スペクトル
3.4 メソ位に各種アミド基を有するヘプタメチンシアニン色素(GF-20,30)のTG-DTA測定
3.5 分子軌道計算によるヘプタメチンシアニン色素のカチオン部分の構造
3.6 色素(GF-8,15,17,20,30)のジクロロメタン溶液中での耐光性試験
4 おわりに
【実用化動向編】
第1章 エレクトロニクス分野
1 ディスプレイ用二色性色素の開発
1.1 液晶ディスプレイ市場と偏光板の要求の変化
1.2 染料系偏光板の特徴
1.3 新規高性能染料系偏光板の開発
1.3.1 新規染料偏光板の光学特性
1.3.2 新規染料偏光板の耐久性
1.4 色相制御可能な偏光板の開発
1.4.1 偏光板の色相の問題
1.4.2 各波長における二色性の制御
1.4.3 各波長の二色性を制御した偏光板の光学特性
1.5 終わりに
2 有機EL用発光材料の開発
2.1 はじめに
2.2 発光材料の分類
2.3 蛍光材料
2.4 りん光材料
2.5 TADF材料
2.6 おわりに
3 マイクロレンズアレイの開発
3.1 はじめに
3.2 マイクロレンズアレイの作製方法
3.3 電着法によるカラーマイクロレンズアレイの作製
3.3.1 ITOガラス基板上への単色マイクロレンズアレイの作製
3.3.2 シリコン基板上への三色マイクロレンズアレイの作製
3.4 まとめ
第2章 エネルギー変換分野
1 ppmドーピングによる有機半導体のpn制御と有機太陽電池応用
1.1 はじめに
1.2 ppmドーピング技術
1.3 pn制御
1.4 ケルビンバンドマッピング―キャリア濃度とイオン化率―
1.5 共蒸着膜のpn制御
1.6 ドーピングイオン化率増感
1.7 最単純n+pホモ接合におけるppmドーピング効果
1.8 まとめ
2 フタロシアニン誘導体の太陽電池素子への応用
2.1 はじめに
2.2 フタロシアニン
2.3 有機化合物系太陽電池
2.3.1 有機薄膜太陽電池
2.3.2 色素増感太陽電池
2.4 まとめ
3 有機太陽電池材料を目指した新規ポルフィリノイド系有機半導体の開発
3.1 はじめに
3.2 ポルフィリノイド系色素
3.3 有機太陽電池におけるポルフィリン色素
3.4 有機薄膜太陽電池
3.4.1 p-nバルクヘテロ接合型OPV用有機半導体
3.4.2 p-i-nバルクヘテロ接合型OPV用有機半導体
3.4.3 p-nヘテロ接合型OPV用有機半導体
3.5 おわりに
第3章 医療分野
1 分子認識用色素;蛍光センサーの開発動向と利用
1.1 はじめに
1.2 設計指針
1.3 Dexter型エネルギー移動
1.4 光誘起電子移動(PET)
1.5 蛍光共鳴エネルギー移動(FRET)
1.6 励起状態分子内プロトン移動(ESIPT)
1.7 凝集誘起発光(AIE)
1.8 近赤外光の利用
1.9 結語
2 光線力学的療法用色素の開発
2.1 はじめに
2.2 一重項酸素1O2発生の評価法
2.3 ポルフィリン系光増感色素
2.4 フタロシアニン系光増感色素
2.5 BODIPY系光増感色素
2.6 キサンテン系およびフェノチアジニウム系光増感色素
2.7 ピリリウム系,アジニウム系およびスクアリン系光増感色素
2.8 複素多環系光増感色素
2.9 遷移金属(Ru,Pt,Ir)錯体系光増感色素
2.10 おわりに
-

IoTを指向するバイオセンシング・デバイス技術《普及版》
¥3,190
2016年刊「IoTを指向するバイオセンシング・デバイス技術」の普及版。バイオ・化学センシング、ウェアラブルデバイス、そして情報通信・サイバー関連まで、IoTを指向したセンシング技術についてまとめた1冊。
(監修:民谷栄一、関谷毅、八木康史)
<a href="http://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=9227"target=”_blank”>この本の紙版「IoTを指向するバイオセンシング・デバイス技術(普及版)」の販売ページはこちら(別サイトが開きます)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は、2016年当時のものを使用しております。
民谷栄一 大阪大学
當麻浩司 東京医科歯科大学
荒川貴博 東京医科歯科大学
三林浩二 東京医科歯科大学
永井秀典 (国研)産業技術総合研究所
永谷尚紀 岡山理科大学
山中啓一郎 大阪大学
村橋瑞穂 大阪大学
齋藤真人 大阪大学
牛島ひろみ (有)バイオデバイステクノロジー
遠藤達郎 大阪府立大学
脇田慎一 (国研)産業技術総合研究所
坂田利弥 東京大学
村上裕二 豊橋技術科学大学
山崎浩樹 ㈱テクノメディカ
横田知之 東京大学
南豪 東京大学
南木創 東京大学
時任静士 山形大学
徳田崇 奈良先端科学技術大学院大学
竹原宏明 奈良先端科学技術大学院大学(現)東京大学
野田俊彦 奈良先端科学技術大学院大学
笹川清隆 奈良先端科学技術大学院大学
太田淳 奈良先端科学技術大学院大学
荒木徹平 大阪大学
菅沼克昭 大阪大学
関谷毅 大阪大学
北村雅季 神戸大学
中村雅一 奈良先端科学技術大学院大学
槇原靖 大阪大学
村松大吾 大阪大学
八木康史 大阪大学
沼尾正行 大阪大学
吉本秀輔 大阪大学
内山彰 大阪大学
-------------------------------------------------------------------------
<<目次>>
第1章 IoTのためのバイオ・化学センシング
1 揮発性化学情報(生体ガス・匂い成分)のためのバイオスニファ&探嗅カメラ
1.1 はじめに
1.2 酵素を利用したガス・匂い成分の高感度センシング
1.3 脂質代謝評価のための生化学式ガスセンサ「バイオスニファ」
1.3.1 酵素を用いたアセトンガス用バイオスニファ
1.3.2 呼気中アセトン計測による脂質代謝評価
1.4 呼気中エタノール用の可視化計測システム「探嗅カメラ」
1.4.1 エタノールガス用探嗅カメラ
1.4.2 呼気エタノールガスの可視化計測とアルコール代謝能の評価応用
1.5 おわりに
2 遺伝子センシング
2.1 はじめに
2.2 超高速PCR技術
2.3 IoTによる遠隔医療を志向した遺伝子センシングシステム
2.4 おわりに
3 食品機能センシング
3.1 はじめに
3.2 食品の機能性表示
3.3 食品機能センシング
3.3.1 抗酸化力測定
3.3.2 ORACによる抗酸化力測定
3.3.3 電気化学発光(ECL)による抗酸化力測定
3.4 食品機能のIoT利用
3.5 まとめ
4 微生物・ウイルスセンシング
4.1 はじめに
4.2 モバイル電気化学バイオセンサー
4.2.1 モバイル遺伝子センシング
4.3 モバイル型生菌数センサー
4.4 携帯電話カメラ機能を用いたモバイルバイオセンサーの開発
5 スポーツバイオセンシング
5.1 はじめに
5.2 無線通信機能を備えた携行型電気化学センサの開発
5.3 電気化学計測条件の検討
5.4 実試料の計測
5.5 まとめ
6 テロ対策化学生物剤センシング
6.1 はじめに
6.2 化学剤・生物剤センシング
6.3 捕集から検知までを可能にする自動検知装置の開発
6.4 おわりに
7 重金属汚染センシング
7.1 はじめに
7.2 6種類の重金属の同時測定
7.3 実サンプルを用いた測定
7.4 おわりに
8 ポリマー製フォトニック結晶を用いたポータブルバイオセンシング
8.1 はじめに
8.2 ナノ光学デバイスのバイオセンシングデバイスへの応用
8.2.1 ナノフォトニクス
8.2.2 ナノフォトニクスを用いたバイオセンシングデバイス開発の利点
8.3 ポリマーを基材としたバイオセンシングデバイスの開発
8.3.1 ナノインプリントリソグラフィーを基盤技術とした「プリンタブルフォトニクス」
8.3.2 フォトニック結晶
8.4 IoT応用を指向したフォトニック結晶バイオセンシングデバイス
8.4.1 ポリマー製フォトニック結晶を用いた酵素反応の検出
8.4.2 CMOSカメラを用いた酵素反応の検出
8.5 おわりに
9 ストレスセンシング
9.1 はじめに
9.2 ストレス学説とストレスマーカー計測の課題
9.3 ストレスセンシング用バイオ・化学センシングデバイス技術
9.4 ストレスセンシング用マイクロ流体デバイス技術
9.4.1 唾液NO代謝物分離アッセイ用マイクロ流体デバイスの開発
9.4.2 唾液NO代謝物分離アッセイの実唾液による実証研究
9.5 ストレスセンシング用マイクロバイオセンサー技術
9.5.1 ストレスセンシング用マイクロバイオセンサーの開発
9.6 ウエアラブルバイオセンサー技術
9.6.1 ストレスセンシング用ウエアラブルバイオセンサー
9.6.2 有機トランジスター型FETバイオセンサーの研究
9.6.3 有機トランジスター型FETストレスマーカーセンサーの基礎研究
9.7 終わりに
10 IoT/体外診断デバイスに向けた半導体バイオセンサの可能性
10.1 はじめに
10.2 半導体バイオセンサの原理
10.3 半導体/バイオインターフェイス構造の理解・設計・応用
10.4 診断医療における半導体バイオセンサの可能性
10.4.1 採血フリーグルコーストランジスタ
10.4.2 酵素活性イオンセンシングに向けた一方向固定酵素ゲートトランジスタの創製
10.4.3 アレルギー診断に向けた半導体原理に基づくバイオセンシング技術
10.4.4 Molecular charge contact法による生体分子計測
10.4.5 分子動力学シミュレーションによる半導体/バイオインターフェイス構造の解明
10.4.6 マルチバイオパラメータの同時計測技術
10.5 むすび
11 指輪型精神性発汗計測デバイス
11.1 はじめに
11.2 ストレス社会とストレスチェック制度
11.3 ストレスとは
11.4 ストレス計測
11.5 指輪型デバイス
11.6 指輪型発汗計
12 POCT型体外診断用機器の実用化
12.1 臨床検査用POCT機器
12.2 IoT機能搭載の臨床検査機器
12.3 ヘルスケア領域における検査機器のIoT機能
12.4 最後に
第2章 フレキシブルデバイス
1 フレキシブル温度センサ
1.1 はじめに
1.2 従来の温度センサ
1.3 ポリマーPTC
1.4 体温付近で反応するポリマーPTC
1.5 印刷可能なフレキシブルポリマーPTC
1.6 まとめ
2 有機FET型化学センサ
2.1 はじめに
2.2 有機トランジスタ型化学センサの構造と動作原理
2.3 オンサイト検出を指向した環境計測用センサデバイス
2.4 抗体および酵素を用いないアレルゲン検出法
2.5 有機FET型センサによる身体情報の可視化
2.6 おわりに
3 CMOS技術によるインプランタブル生体センサ
3.1 はじめに
3.2 CMOSチップ搭載インプランタブルセンサに求められる特徴
3.3 インプランタブルCMOSイメージセンサによるグルコースセンシング
3.4 CMOS搭載型フレキシブルバイオデバイスの実現
3.5 まとめと将来展望
4 柔軟なウェアラブルデバイスに向けた銀ナノワイヤ配線の開発
4.1 はじめに
4.2 ウェアラブルデバイス用材料に求められる機械的性質
4.3 ストレッチャブル配線の開発動向
4.4 銀ナノワイヤを用いたストレッチャブル配線技術
4.5 まとめ
5 電極表面処理技術と物性評価
5.1 はじめに
5.2 金属表面の性質
5.3 単分子膜形成
5.4 仕事関数
5.5 表面エネルギー
6 フレキシブルエナジーハーベスター
6.1 エナジーハーベスティングとは
6.2 環境エネルギーの種類と対応するエナジーハーベスターの特徴
6.3 光利用エナジーハーベスター
6.4 電波利用エナジーハーベスター
6.5 振動・圧力利用エナジーハーベスター
6.6 熱利用エナジーハーベスター
第3章 情報通信・サイバー関連
1 歩行映像解析によるバイオメトリック個人認証
1.1 はじめに
1.2 歩容認証の流れと特徴表現
1.2.1 歩容認証の流れ
1.2.2 モデルに基づく特徴表現
1.2.3 見えに基づく特徴表現
1.3 観測方向変化に頑健な手法
1.3.1 生成的アプローチ
1.3.2 識別的アプローチ
1.4 おわりに
2 センサデータに基づく情報システムの構築
2.1 センサデータに基づく音楽コンテンツ生成
2.2 共感空間:人の感情と行動を考慮するアンビエントシステム
2.3 音楽聴取者の生体信号データからのモチーフの発見とそれによる感情の特定
2.3.1 手法
2.3.2 結果
2.3.3 まとめ
3 ストレッチャブル電極を用いた生体計測システム
3.1 はじめに
3.2 ストレッチャブル電極を備えたワイヤレス脳波計測システム
3.2.1 ワイヤレス脳波計測センサシステム
3.2.2 ストレッチャブル電極シート
3.2.3 接触インピーダンス計測回路
3.3 実測結果
3.4 フロンタール脳波を用いたアルツハイマー診断
3.4.1 被験者
3.4.2 脳波計測
3.4.3 実測結果
3.5 まとめ
4 ウェアラブルセンサによるスポーツ支援
4.1 ウェアラブルセンサとスポーツ
4.2 ウェアラブルセンサを用いた深部体温推定
4.2.1 深部体温計測の現状
4.2.2 生体温熱モデル
4.2.3 Gaggeの2ノードモデルによる深部体温推定
4.2.4 モデルパラメータのキャリブレーション
4.3 今後の展望
-

機能性粘着製品の開発と応用《普及版》
¥4,290
2016年刊「機能性粘着製品の開発と応用」の普及版。機能性粘着製品の材料開発および各分野におけるその動向、さらに様々な機能性を有した粘着剤と粘着製品について網羅収載した1冊。
(監修:地畑健吉)
<a href="http://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=9178"target=”_blank”>この本の紙版「機能性粘着製品の開発と応用(普及版)」の販売ページはこちら(別サイトが開きます)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は、2016年当時のものを使用しております。
地畑健吉 接着コンサルタント
馬場俊一郎 東洋紡(株)
橋本貞治 日本ゼオン(株)
河野和浩 大塚化学(株)
纐纈明美 東亞合成(株)
中村昭宏 東レ・ダウコーニング(株)
櫻井良寛 荒川化学工業(株)
河野雅和 ハリマ化成(株)
林益史 藤森工業(株)
宮内康次 (株)UBE科学分析センター
小田純久 サイデン化学(株)
戸高勝則 (株)寺岡製作所
市川功 リンテック(株)
杉崎俊夫 リンテック(株)
小林真盛 リンテック(株)
安藤雅彦 日東電工(株)
阪下貞二 (株)ニトムズ
川原康慈 ニチバン(株)
三ツ谷直也 日本合成化学工業(株)
加納義久 古河電気工業(株)
渡邉淳朗 セメダイン(株)
星健太郎 大日本印刷(株)
上田晃生 テサテープ(株)
上北聡之 テサテープ(株)
濱野尚 共同技研化学(株)
青木孝浩 ビッグテクノス(株)
-------------------------------------------------------------------------
<<目次>>
【総論編】
第1章 機能性粘着剤の開発動向
1 はじめに
2 粘着剤の機能と特性
3 機能性粘着剤の機能と開発動向
3.1 接着に関わる機能
3.1.1 光学フィルム適性
3.1.2 曲面接着性
3.1.3 再剥離性
3.1.4 解体性
3.1.5 段差追従性
3.1.6 放射線硬化性
3.1.7 皮膚貼付性
3.2 耐性に関わる機能
3.2.1 透明性
3.2.2 難燃性
3.2.3 帯電防止性
3.2.4 熱伝導性
3.2.5 低金属腐食性
3.2.6 近赤外線吸収性
4 おわりに
【材料編】
第2章 ポリエステル合成紙
1 ラベル用ポリエステル系合成紙の開発経緯
1.1 東洋紡の工業用フィルム
1.2 粘着ラベル市場
2 ラベル用ポリエステル系合成紙「カミシャイン(R)」
2.1 微細空洞の設計
2.2 空洞含有量と積層構造の設計
2.3 本製品の柔軟性
2.4 本製品のクッション性
2.5 本製品の印刷適性
2.6 耐熱性と耐薬品性
2.7 環境適性
2.8 一般物性
3 想定する用途と今後の開発
第3章 ゴム系粘着剤
1 ゴム系粘着剤の構成成分
1.1 ゴム・エラストマー
1.2 粘着付与樹脂
1.3 老化防止剤
1.4 軟化剤・可塑剤
2 ゴム系粘着剤の配合設計(レオロジーモデル)
3 ゴム系粘着剤の技術動向と開発品
3.1 ホットメルト系SISの耐熱性向上
3.2 ラベル向けダイカット性に優れる粘着剤
3.3 ホットメルトタイプの絶縁テープ向け粘着剤
第4章 リビングラジカル重合を用いたアクリル系粘着剤
1 はじめに
2 リビングラジカル重合とは
3 有機テルル化合物を用いるリビングラジカル重合法(TERP法)
4 粘着剤開発への応用
5 TERP法を応用した粘着剤/TERPLUS Nシリーズ
6 生産体制
7 まとめ
第5章 アクリル系粘着剤
1 はじめに
2 溶剤型アクリル系粘着剤
2.1 ベースポリマーの設計
2.1.1 モノマー組成
2.1.2 分子量および分子量分布
2.2 架橋方法
2.3 粘着付与剤の種類と配合
3 エマルション型アクリル系粘着剤
3.1 ベースポリマーの設計
3.1.1 モノマー組成
3.1.2 分子量
3.1.3 重合用界面活性剤
3.2 架橋方法
3.3 その他の添加剤
4 無溶剤型粘着剤
4.1 ホットメルト型
4.1.1 設計
4.2 液状硬化型
4.2.1 UV架橋型の設計
4.2.2 UV重合型の設計
5 最近のアクリル系粘着剤
5.1 光学用途向けパネル接着用粘着剤
5.2 光硬化型粘接着フィルム
6 アクリル系粘着剤の将来展望
第6章 シリコーン系粘着剤
1 はじめに
2 シリコーン系粘着剤の基本的な性質と特徴
3 過酸化物硬化型シリコーン粘着剤
4 付加硬化型シリコーン粘着剤
5 シリコーン粘着剤の関連製品
5.1 シリコーン粘着剤用剥離剤
5.2 カラーペースト
5.3 プライマー
6 おわりに
第7章 超淡色粘着付与樹脂
1 はじめに
2 色調
3 粘着付与樹脂
4 超淡色粘着付与樹脂
4.1 水素化石油樹脂
4.2 超淡色ロジン誘導体
5 最近の開発動向
5.1 高耐候性・低重合阻害性ロジン誘導体「PE-590」
5.2 超淡色液状ロジンエステル「パインクリスタルMEシリーズ」
6 おわりに
第8章 環境対応型ロジン系粘着付与剤樹脂エマルション
1 緒言
2 技術的動向
2.1 エマルション型タッキファイヤーの製造方法
2.2 接着剤用粘着付与剤樹脂エマルション
2.3 粘着剤用エマルションタッキファイヤー
3 物性試験
4 消泡剤
5 機械的安定性
6 VOC放散速度
7 海外での展開
8 まとめ
9 おわりに
第9章 剥離フィルム
1 はじめに
2 剥離フィルムの種類
3 剥離に関連する因子
3.1 接着し難さ(くっつき難さ)
3.1.1 粘着剤や粘着性物質の濡れ難さ(低表面張力)
3.1.2 粘着剤や粘着性物質との親和性が乏しいこと(非親和性)
3.2 剥がしやすさ
4 剥離剤の種類
5 シリコーン系剥離剤
5.1 硬化タイプ
5.2 剥離剤の形態
5.3 剥離性の制御
6 剥離フィルムの製造と評価
6.1 剥離フィルムの製造方法
6.2 剥離フィルムの評価方法
7 製品例
7.1 光学粘着テープ用剥離フィルム
7.2 シリコーン粘着剤用剥離フィルム
7.3 経皮吸収薬用剥離フィルム
7.4 偏光板用剥離フィルム
7.5 積層セラミックコンデンサ用剥離フィルム
8 今後の展開
8.1 高品質
8.2 高品位
8.3 環境対応
第10章 粘・接着材料の最新分析
1 はじめに
2 粘・接着物質の構造解析
2.1 MA-g-POのグラフト構造高感度分析
2.1.1 粘・接着性発現化合物:MA-g-PO
2.1.2 MAグラフト構造解析:従来法と新規解析法
2.1.3 超臨界メタノールによるグラフトMAのメチル化-1H-NMR分析
2.2 表面修飾無機フィラーの修飾構造解析
2.2.1 粘・接着物質複合材料:表面修飾無機フィラー
2.2.2 ポリマー修飾無機フィラーとその構造解析
2.2.3 超臨界メタノール処理-1H-NMR分析
3 粘・接着界面の評価
3.1 界面特性依存材料:CFRP
3.2 界面粘・接着性評価:マイクロドロップレット法
3.3 界面状態の検証:サイジング剤と界面強度
3.4 粘・接着メカニズム:メカニズム関連因子とせん断強度
4 おわりに
【粘着製品編】
第11章 機能性粘着剤の開発
1 はじめに
2 粘着剤の設計
2.1 組成・形態
2.2 粘着付与樹脂
2.3 分子量・架橋
3 粘着剤の機能性付与
3.1 粘着シート、テープへの機能性付与
3.2 光学的性能
3.2.1 透過率・黄変
3.2.2 屈折率
3.2.3 複屈折、複屈折温度依存性
3.3 電気的性能
3.3.1 表面抵抗
3.3.2 帯電性
3.3.3 誘電率
3.4 力学的性能
3.4.1 応力緩和、流動性
3.4.2 再剥離
3.5 熱的性能
3.6 各種基材への対応
3.6.1 紙基材
3.6.2 感熱紙基材
3.6.3 塩ビ基材
3.6.4 各種フィルム基材
3.6.5 不織布、発泡体基材
4 粘着剤の環境性能
4.1 製造時の環境負荷
4.2 粘着付与樹脂の乳化
5 粘着剤のコストダウン
6 おわりに
第12章 エレクトロニクス関連粘着製品
1 概要
2 具体的事例
3 無支持体両面テープの設計アプローチ
4 設計情報
4.1 アクリルモノマー
4.2 架橋剤
4.3 試験条件
5 設計アプローチ
5.1 粘着剤設計
5.1.1 ベースポリマー設計
5.1.2 架橋系選択
5.1.3 その他
5.2 セパレーター設計
5.2.1 基材選択
5.2.2 セパレーター表面粗さ
5.2.3 離型剤選択
5.3 加工条件の配慮
5.4 製品全体の代表的性能と関連の応用製品
6 まとめ
第13章 半導体部品組立用粘接着テープ
1 はじめに
2 バックグラインドテープ(BG テープ)
3 ダイシングテープ
3.1 ダイシングテープの組成・設計
3.2 ダイシング方法
4 ダイボンディングテープ
4.1 ダイボンディングテープの技術背景
4.2 ダイボンディングテープの課題と設計
5 素子裏面保護用テープ
6 結論
第14章 機能性粘着剤とテープ、ラベル
1 はじめに
2 帯電防止性の付与
3 導電性の付与
4 難燃性の付与
5 環境対応性(リサイクル適性)の付与
6 その他用途や製品設計への展開
7 おわりに
第15章 家庭用粘着製品
1 はじめに
2 家庭用粘着製品とは
3 代表的な家庭用粘着製品
3.1 粘着クリーナー
3.1.1 粘着カーペットクリーナー
3.1.2 フローリング用クリーナー
3.1.3 マルチタイプ粘着クリーナー コロコロ(R)フロアクリン
3.1.4 ペット用粘着クリーナー
3.1.5 タッチパネル用粘着クリーナー タッチパネルコロコロ
3.2 家庭用両面テープ
3.2.1 はがせる両面テープ ミズトレック(R)
3.2.2 はがせる両面テープ強力接着用
3.2.3 はがせる両面テープ強力固定用
3.2.4 はがせるフック
3.3 窓ガラス断熱シート
3.4 優肌絆(R)
3.5 ウォールインテリア decolfa(R)
4 おわりに
第16章 医療用粘着製品
1 絆創膏
2 ドレッシングテープ
3 ハイドロコロイドテープ
4 傷あとケアテープ
5 経皮吸収製剤
【話題製品編】
第17章 光学部材用粘着剤の開発と動向
1 はじめに
2 光学部材用粘着剤
2.1 液晶ディスプレイ(LCD)
2.1.1 耐久性
2.1.2 リワーク性
2.1.3 光漏れ(ムラ)抑制
2.1.4 帯電防止性
2.1.5 保存安定性
2.2 今後の動向
2.2.1 偏光板の構成の変化
2.2.2 LCD構成
3 タッチパネル
3.1 タッチパネル用粘着剤
3.1.1 耐久性
3.1.2 金属非腐食
3.1.3 耐湿熱白化性
3.1.4 段差追従性
3.1.5 誘電率
3.1.6 耐ブリスター性
4 おわりに
第18章 医療用シリコーン系粘着製品
1 はじめに
2 シリコーン粘着剤の基本的な性質と特徴
2.1 強粘着タイプの医療用シリコーン粘着剤
2.2 弱粘着タイプのシリコーンソフトスキン粘着剤(Soft Skin Adhesive: SSA)
3 おわりに
第19章 UV硬化型粘着剤の接着制御メカニズムと評価法および応用展開
1 はじめに
2 UV硬化型粘着剤における粘着特性の低下機構
3 UV硬化型粘着テープにおける評価・解析法
4 UV硬化型粘着剤における応用展開
5 おわりに
第20章 無溶剤弾性粘着剤
1 はじめに
2 液体の粘着剤 セメダインBBX
2.1 セメダインBBXの長所・短所
2.2 セメダインBBXの構成
2.3 セメダインBBXの一般性状
2.4 セメダインBBXの粘着性データ
2.4.1 タック
2.4.2 粘着力
2.4.3 凝集力
3 セメダインBBXの接着性と耐久性能
3.1 再はく離性(糊残り性)
3.2 耐水性、熱老化性
3.3 ポリエチレン、ポリプロピレンへの粘着性
4 用途例
5 おわりに
第21章 異種材接合に用いる接着フィルム
1 はじめに
2 開発経緯
3 粘接着フィルムの特徴
3.1 粘接着性
3.2 粘接着フィルムの基本構成
3.3 熱硬化タイプ(柔軟グレード)
3.4 熱硬化タイプ(高流動グレード)
3.5 光遅延硬化タイプ
4 今後の展望
第22章 再剥離可能な粘着テープ
1 はじめに
2 剥離時の粘着強さに変化がないテープ
3 剥離時の粘着強さの低下技術
第23章 分子勾配膜テープと反応系 ―粘着技術の特徴と用途開発―
1 はじめに
2 分子勾配膜膜テープ(両面粘接着テープ)
2.1 詳細
3 分子勾配膜両面テープの多層成膜と応力吸収
4 分子勾配膜の実力
4.1 SUSとオレフイン系(PP)での比較
4.2 耐熱性について
4.2.1 評価
5 瞬間接着型:分子勾配膜反応型テープ
6 まとめ
第24章 熱対策粘着テープ-熱伝導性、熱放射性、遮熱性、断熱性をもつ粘着テープ-
1 はじめに
2 熱伝導性テープ
3 熱放射テープ
4 遮熱テープ
5 断熱テープ
6 まとめ
-

藻類由来バイオ燃料と有用物質《普及版》
¥3,960
2016年刊「藻類由来バイオ燃料と有用物質」の普及版。バイオマス資源として有望な微細藻類の産業利用についての研究開発動向および、多岐に亘る藻類由来有用物質について詳述した1冊。
(編集:シーエムシー出版編集部)
<a href="http://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=9229"target=”_blank”>この本の紙版「藻類由来バイオ燃料と有用物質(普及版)」の販売ページはこちら(別サイトが開きます)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は、2016年当時のものを使用しております。
加藤美砂子 お茶の水女子大学
今村壮輔 東京工業大学;(国研)科学技術振興機構
田中寛 東京工業大学;(国研)科学技術振興機構
宮下英明 京都大学
井村綾子 京都大学
荒谷彰吾 京都大学
沈元 京都大学
石井健一郎 京都大学
神川龍馬 京都大学
萩原浩 花王㈱
岩井雅子 東京工業大学
太田啓之 東京工業大学
竹下毅 東京大学
河野重行 東京大学
松本光史 電源開発㈱
野島大佑 東京農工大学
田中剛 東京農工大学
増田篤稔 玉川大学
金裕史 仙台市 まちづくり政策局
木谷径治 マイクロ波化学㈱
石塚章斤 マイクロ波化学㈱
岡田茂 東京大学
神田英輝 名古屋大学
福永哲也 出光興産㈱
冨重圭一 東北大学
中川善直 東北大学
田村正純 東北大学
星野孝仁 ㈱ちとせ研究所
岩田修 ㈱ユーグレナ
西尾幸郎 四国大学
平野篤 東京電力ホールディングス㈱
小山内崇 明治大学
芝上基成 (国研) 産業技術総合研究所
竹中裕行 マイクロアルジェコーポレーション㈱
清水稔仁 オリザ油化㈱
単少傑 オリザ油化㈱
下田博司 オリザ油化㈱
佐藤剛毅 パナックアドバンス㈱
大木利哉 パナックアドバンス㈱
林雅弘 宮崎大学
-------------------------------------------------------------------------
<<目次>>
【第1編 藻類の研究開発】
第1章 微細藻類の脂質代謝メカニズム
1 はじめに
2 トリアシルグリセロールの代謝
2.1 脂肪酸の生合成
2.2 TAGの生合成
3 トリテルペノイドの代謝
3.1 トレボキシア藻Botryococcus brauniiに含まれる脂質
3.2 ボトリオコッセンの生合成
第2章 藻類オイル生合成のチェックポイントキナーゼTOR
1 はじめに
2 単細胞紅藻Cyanidioschyzon merolaeにおける窒素代謝制御
3 栄養源を感知するTORキナーゼ
4 TOR不活性化による油滴・トリアシルグリセロールの蓄積
5 TAG生合成制御におけるTORの作用点
6 微細藻類のTAG蓄積におけるTOR機能の保存性
7 TAG生合成のON/OFFを決定するチェックポイントキナーゼTOR
8 油脂生合成において枢要な機能を発揮するTOR発見の意義
第3章 寒天培地上での生育速度を指標とした油脂蓄積微細藻類の探索
1 はじめに
2 微細藻類バイオマス生産におけるコスト削減の課題
3 表面塗布培養
4 寒天平板上での生育速度を指標とした微細藻類株の選抜
5 選抜された藻類の同定と多様性
6 選抜された藻類の油脂蓄積
7 選抜株の生育およびバイオマス生産性の評価
8 おわりに
第4章 藻類を利用した持続可能な油脂原料の開発
1 はじめに
2 ラウリン酸生産藻類の探索
3 培地・培養条件の改良によるラウリン酸の生産性向上
4 藻類由来の中鎖脂肪酸特異的Acyl‐ACP thioesterase(TE)の発見
5 藻類由来の中鎖脂肪酸特異的β‐Ketoacyl ACP synthase(KAS)の発見
6 最後に
第5章 リン欠乏応答性プロモーターを利用したナンノクロロプシス油脂合成の改変
1 植物における油脂代謝改変研究
2 藻類における油脂代謝研究
3 クラミドモナスを用いた油脂蓄積
4 ナンノクロロプシスを用いた油脂蓄積の応用
5 今後の展望
第6章 微細藻類のデンプン・オイル蓄積と重イオンビーム照射による増産株作出
1 はじめに
2 クロレラ 6種8株の強光条件下の培養
3 クロレラのデンプン・オイル蓄積
4 強光で加速されるデンプン・オイル蓄積
5 デンプンとオイルのトレードオフ
6 重イオンビーム照射とハイスループットスクリーニング
7 重イオンビーム照射後に単離したクロレラ株の表現型
8 栄養塩飢餓による選抜株のデンプンとオイルの蓄積誘導
9 重イオンビーム育種と微細藻類のオイル生産性
10 おわりに
【第2編 藻類の培養・分離・抽出・精製】
第7章 海洋微細藻類によるグリーンオイル生産における屋外大量培養技術開発
1 はじめに
2 CO2削減効果を有するグリーンオイル生産に必要な培養技術
2.1 既存の培養方法
2.2 低エネルギー型培養装置
2.3 グリーンオイル生産に必要な微細藻類の能力
3 グリーンオイル年間生産に向けた屋外培養技術
3.1 年間生産のハードル
3.2 ソラリス株およびルナリス株
3.3 ソラリス株,ルナリス株による年間を通じた屋外培養
3.4 培養規模の大型化と天然海水利用
4 社会実証に向けてのまとめ
第8章 微細藻類の大量培養システムの開発
1 はじめに
2 微細藻類培養装置開発に関する基礎的知見
2.1 培養槽における環境制御項目
2.2 光環境
2.3 溶存ガス環境
3 設計における環境因子の定量方法
3.1 培養槽外郭周辺の光環境設計計算
3.2 培養槽内の光環境計測と培養器形状
3.2.1 光透過測定装置と結果
3.2.2 解析
3.2.3 考察
3.3 培養内におけるガス挙動
3.3.1 培養槽内における溶存酸素濃度動態について
3.3.2 培養槽を用いた溶存酸素動態の検討事例
4 実用プラントにおける餌料用微細藻類培養システム開発
4.1 培養槽条件と設計と性能
4.2 実用プラントシステム
5 屋外培養についての留意点
第9章 生活排水を用いた藻類バイオマス培養への取り組み
1 はじめに
1.1 東日本大震災の経験と教訓から
1.2 プロジェクトの経緯
1.3 プロジェクトの体制
2 本プロジェクトが目指すシステムとその特徴
2.1 研究対象としている2つの藻類
2.2 目指すオイル生産システム
3 プロジェクトの状況
3.1 研究開発の進捗状況
3.2 LCAの実施
4 最後に
第10章 マイクロ波を用いた藻類からの油分抽出技術の開発
1 はじめに
2 マイクロ波による藻類からの油分抽出の利点
3 マイクロ波抽出の特徴
4 藻類溶液へのマイクロ波照射の効果
5 サセプターの開発
6 マイクロ波抽出条件の開発
7 マイクロ波と超音波複合系の開発
8 マイクロ波抽出装置の大型化
9 おわりに
第11章 微細藻類からの効率的な炭化水素抽出
1 はじめに
2 B. brauniiにおける炭化水素蓄積の特殊性
3 様々な溶媒による抽出
4 加熱処理による炭化水素の回収
5 藻体の改質による炭化水素回収性の向上
第12章 低沸点溶媒による高含水微細藻類からの油脂抽出技術
1 微細藻類からバイオ燃料への変換の問題点
2 液化ジメチルエーテルによる油脂抽出手法
3 液化ジメチルエーテルによる油脂抽出の例
4 結言
第13章 藻類由来オイルの燃料用途への転換技術の開発
1 はじめに
2 バイオマス燃料関連の政策・規制
3 水素化バイオ燃料
3.1 水素化バイオ燃料とは
3.2 水素化バイオ燃料の製造方法
4 微細藻類からの水素化バイオ燃料の製造
4.1 微細藻類の特徴
4.2 微細藻燃料のプレイヤー
4.3 微細藻油からの水素化バイオ燃料の製造工程
4.3.1 油の分子構造と水素化工程の違い
4.3.2 脂肪酸トリグリセリドの水素化処理
4.3.3 炭化水素系原料の水素化処理
4.4 出光興産における水素化バイオ燃料の取組み
4.4.1 脂肪酸トリグリセリド系藻類油の燃料化
4.4.2 炭化水素系藻類油の燃料化
5 まとめ
6 今後の展望
第14章 金属触媒を用いた藻類オイルの軽質化
1 はじめに
2 触媒の活性金属スクリーニング
3 Ru/CeO2触媒を用いたスクワランの水素化分解反応試験結果と従来触媒系との比較
4 Ru/CeO2触媒上の水素化分解反応を用いたスクワランの軽質化
5 Ru/CeO2触媒の構造的特徴
6 まとめ
【第3編 藻類産生物質の応用】
第15章 藻類バイオ燃料の商業生産実現に向けた日本での研究開発における課題
1 主旨
2 背景
2.1 藻類バイオ燃料生産研究開発に見られる日米間の大きな差
3 米国での藻類バイオ燃料研究開発の推移
3.1 藻類バイオ燃料商業生産に関する目標の設定
3.2 現状の把握,目標に至る「叩き台」としての道筋の提示
3.3 TEA,LCA,RAによる現状の評価,課題の整理
3.4 研究開発環境の整備およびモデルケースの実証試験
3.5 ロードマップの改訂および更なる研究開発
4 総括
第16章 ユーグレナオイルの利用について
1 ユーグレナについて
2 ユーグレナの貯蔵多糖と油脂について
3 ユーグレナの育種による油脂高含有株の取得
4 油脂を含む細胞内コンポーネントのイメージング
5 ユーグレナ燃料の実用化に向けた取り組み
6 総括と展望
第17章 イカダモのバイオ燃料への応用
1 はじめに
2 バイオディーゼル原料としてのイカダモDesmodesmus pleiomorphus SUHL0708株
3 SUHL0708藻体からのソックスレー法による油分抽出
4 メタノール亜臨界抽出(Buchi高速高圧抽出装置 E-916での抽出実験)
5 マイクロウエーブ抽出とGC/MSによる油分定性
5.1 マイクロウエーブ抽出法
5.2 GS/MSによる脂肪酸組成分析
6 メタノール超臨界抽出
7 まとめ
第18章 ラン藻由来原料によるバイオプラスチック生産
1 はじめに
2 単細胞性ラン藻シネコシスティス
3 ラン藻の代謝
4 ラン藻が生み出すバイオプラスチック原料
5 新しいラン藻の創出方法とPHB生産
6 ラン藻の嫌気発酵とコハク酸生産
7 まとめ
第19章 ミドリムシ由来多糖を主原料とする有機材料の開発
1 ミドリムシ
2 パラミロン
3 パラミロンドーナツ
4 熱可塑性樹脂(ミドリムシプラスチック)
5 透明フィルム
6 ナノファイバー
7 まとめ
第20章 藻類由来バイオマスプラスチックの実用化への課題と考察
1 はじめに
2 藻類バイオマスプラスチックの研究・開発
2.1 シネコシスチス(Synecocystis sp.)
2.2 ユーグレナ(Euglena sp.)
2.3 ファエオシスチス(Phaeocystis sp.)
2.4 ポルフィリディウム(Porphyridium sp.)
2.5 ファエオダクチラム(Phaeodactylum sp.)
3 藻類バイオマスプラスチック実用化への課題と考察
3.1 藻類バイオマスプラスチックに要求される品質特性
3.2 バイオマスプラスチック製造法の確立が先か微細藻類大量培養法の確立が先か
3.3 バイオマスプラスチックに関わる認定マーク
3.4 微細藻類の大量培養技術の確立
3.5 微細藻類の培養生産コスト
3.6 遺伝子導入微細藻類の大量培養
4 微細藻類利用の多角化とカスケード利用
5 おわりに
第21章 ヘマトコッカス藻から得られるアスタキサンチンの食品への展開
1 はじめに
2 アスタキサンチン
3 アスタキサンチンの安定性
4 アスタキサンチンの安全性
5 アスタキサンチンの機能性
6 おわりに
第22章 微細藻類の細胞外多糖類(EPS)の実用化を目指して
1 はじめに
2 微細藻類のホワイトバイオテクノロジー産業への活用へ向けた最近の動き
3 微細藻類に由来するEPSの生物学的・化学的特徴
4 将来的な実用化に際しての課題
第23章 DHA含有クロレラの特性と機能性
1 はじめに
2 DHA含有クロレラの調製と脂質特性
2.1 クロレラ細胞による脂肪酸の取り込みと蓄積
2.2 DHA含有クロレラの脂質特性
3 DHAクロレラのワムシ餌料としての利用
4 DHA含有クロレラの血中コレステロール上昇抑制作用
5 おわりに
-

再生医療・細胞治療のための細胞加工物評価技術《普及版》
¥3,960
2016年刊「再生医療・細胞治療のための細胞加工物評価技術」の普及版。再生医療・細胞治療における、ウイルス・細菌や不純物混入、同一・均一性、免疫反応などの評価手法から安全指針、品質管理を網羅した1冊。
(監修:佐藤陽治)
<a href="http://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=9230"target=”_blank”>この本の紙版「再生医療・細胞治療のための細胞加工物評価技術(普及版)」の販売ページはこちら(別サイトが開きます)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は、2016年当時のものを使用しております。
佐藤陽治 国立医薬品食品衛生研究所
内田恵理子 国立医薬品食品衛生研究所
古田美玲 国立医薬品食品衛生研究所
山口照英 金沢工業大学
蓜島由二 国立医薬品食品衛生研究所
清水則夫 東京医科歯科大学
外丸靖浩 東京医科歯科大学
渡邊健 東京医科歯科大学
森尾友宏 東京医科歯科大学
宮川繁 大阪大学
安田智 国立医薬品食品衛生研究所
小原有弘 (国研)医薬基盤・健康・栄養研究所
羽室淳爾 京都府立医科大学
井家益和 ㈱ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング
斉藤大助 九州大学
須山幹太 九州大学
小原收 (公財)かずさDNA研究所
加藤竜司 名古屋大学
蟹江慧 名古屋大学
水谷学 大阪大学
紀ノ岡正博 大阪大学
高橋匠 東海大学
豊田恵利子 東海大学
佐藤正人 東海大学
大島勇人 新潟大学
本田雅規 愛知学院大学
齋藤充弘 大阪大学
澤芳樹 大阪大学
馬場耕一 大阪大学
西田幸二 大阪大学
舘野浩章 (国研)産業技術総合研究所
佐俣文平 京都大学
土井大輔 京都大学
髙橋淳 京都大学
廣瀬志弘 (国研)産業技術総合研究所
竹内朋代 筑波大学
嶽北和宏 (独)医薬品医療機器総合機構
尾山和信 (独)医薬品医療機器総合機構
大迫洋平 京都大学
金子新 京都大学
-------------------------------------------------------------------------
<<目次>>
【第1編 細胞加工物の評価技術】
第1章 再生医療・細胞治療製品のマイコプラズマ検査
1 はじめに
2 培養細胞を汚染するマイコプラズマの性質
3 日局17のマイコプラズマ否定試験の概要
4 培養法
4.1 原理と特徴
4.2 操作法と注意点
5 DNA染色法
5.1 原理と特徴
5.2 操作法と注意点
6 核酸増幅法(Nucleic Acid Amplificatio Test:NAT)
6.1 原理と特徴
6.2 操作法と注意点
6.3 NATのバリデーション
7 再生医療製品にマイコプラズマ否定試験を適用する場合の考え方
7.1 試験結果が被験者への投与後にしか得られない場合
7.2 検体量が少ない場合
7.3 接着細胞の場合
7.4 培養上清を検体とする場合
7.5 最終製品にNATを適用することが困難な場合
8 おわりに
第2章 エンドトキシン規格値と検査法
1 はじめに
2 in vitro LPS規格値の設定:培養細胞に対するLPSの影響
2.1 細胞増殖に及ぼす影響
2.2 分化能に及ぼす影響
3 in vivo LPS規格値の設定:LPSの生体影響
4 エンドトキシン試験
4.1 測定法
4.2 スキャホールド等の医用材料・実験器具等の測定
4.3 培地,血清,培養上清および細胞等の測定
4.4 HCPT
5 おわりに
第3章 ウイルス検査
1 はじめに
2 検査対象ウイルス
3 ドナー検査
3.1 血清学的検査
3.2 核酸増幅検査
3.3 ウインドウピリオドを勘案した検査
4 生物由来原料の検査
5 細胞加工物のウイルス検査
6 ウイルスの迅速検査系の開発
6.1 網羅的ウイルス検査
6.2 ウイルスの迅速定量法
7 データ収集
8 おわりに
第4章 重症心不全治療に用いられる移植細胞に関する免疫学的考察
1 はじめに
2 自己細胞による細胞治療の利点と欠点
3 アロ体性幹細胞の心不全に対する有効性,免疫原性
3.1 他家骨髄間葉系幹細胞
3.2 他家筋芽細胞
4 iPS細胞由来心筋細胞の免疫原生
4.1 移植急性期における宿主移植片反応
4.2 移植慢性期における宿主移植片反応
4.3 他家iPS細胞由来移植片の生着と寿命
4.4 iPS細胞の免疫原性に関する基盤研究
5 免疫学的メカニズムを用いた細胞治療の有効性向上
第5章 造腫瘍性評価
1 はじめに
2 ヒト細胞加工製品の造腫瘍性試験における考え方
3 ヒト細胞加工製品における造腫瘍性関連試験
3.1 in vivo 造腫瘍性試験
3.2 フローサイトメトリー
3.3 定量的逆転写PCR(qRT-PCR)
3.4 ドロップレットデジタルPCR(ddPCR)
3.5 GlycoStem法
3.6 Essential-8/LN521培養増幅法
3.7 (デジタル)軟寒天コロニー形成試験
3.8 細胞増殖特性解析
4 おわりに
第6章 生細胞数・生細胞率検査と細胞同一性検査
1 はじめに
2 生細胞数・生細胞率検査
2.1 細胞計数の方法
2.2 生死の判定
2.3 自動計数機器
2.4 細胞計数のタイミング
2.5 計数結果の記録
3 細胞同一性検査
3.1 STR-PCR法によるヒト細胞認証試験
3.2 その他の方法
第7章 培養細胞の均質性検査
1 はじめに
2 培養ヒト角膜内皮細胞の移入による角膜組織の再建
3 細胞の品質規格の重要性
4 臨床の安全性と有効性の再現性を支える品質
4.1 培養ヒト角膜内皮細胞の形態・細胞特性は不均質である
5 移植に適した目的細胞の選定と効能試験
6 培養ロット・条件による不均質な細胞亜集団組成の変動
7 移植目的細胞の確認試験法
7.1 細胞密度,FACS,産生産物
7.2 目的細胞の純度試験法(FACSによる目的細胞の純度検定)
8 移植に用いる目的細胞の同質性の検証試験
8.1 目的細胞の同質性確認試験法(細胞の機能性指標を用いる試験法)
9 目的細胞・非目的細胞の生体機能確認試験法
10 おわりに
第8章 非細胞成分由来不純物検査
1 はじめに
2 非細胞成分と製造工程由来不純物
2.1 非細胞成分の安全性評価
2.2 製造工程由来不純物の安全性評価
3 非細胞成分由来不純物
3.1 原料および材料の品質
3.2 製造工程由来不純物
4 実例
4.1 培地と添加物
4.2 ウシ血清
4.3 抗生物質
4.4 細胞剥離液
4.5 スキャフォールド
4.6 製品保存液
5 おわりに
第9章 次世代シーケンシングによる細胞のゲノム安定性評価
1 はじめに
2 巨視的レベルのゲノム構造変化の次世代シーケンシングによる検出
3 微視的レベルのゲノム構造変化の次世代シーケンシングによる検出
4 エピゲノム変異の検出法
5 RNAプロファイリングによるゲノム構造変化の検出
6 現在の課題と今後の展望
第10章 画像を用いた細胞加工物および培養工程の評価
1 序論:細胞評価としての細胞観察
2 細胞画像を用いた細胞評価(細胞形態情報解析)
2.1 細胞評価に細胞画像を用いるためには
2.2 細胞画像から得られる情報とは
2.3 細胞画像を用いた細胞評価適応例
2.4 細胞画像を用いた細胞評価の生物学的考察
3 細胞形態情報解析の展開
4 細胞形態情報解析を支える細胞加工工程情報
5 最後に
第11章 製造のモニタリング評価
1 はじめに
2 再生医療等における製品形態の多様性と製造モニタリングの考え方
3 再生医療等製品の製造で生じる現状の課題
4 製造モニタリングについて
4.1 環境モニタリング
4.2 工程モニタリング
5 加速度センサーを用いた動作キャリブレータの可能性
6 おわりに
【第2編 治療部位・疾患別の評価技術】
第12章 関節軟骨再生の細胞加工物(製品)評価技術
1 はじめに
2 膝関節軟骨再生の原材料と最終製品の分類
3 ヒト体細胞由来製品の評価項目
4 自己軟骨細胞シートにおける評価技術
5 同種軟骨細胞シートにおける評価技術
6 ヒト人工多能性幹(iPS)細胞由来製品の評価項目
7 おわりに
第13章 歯
1 はじめに
2 歯髄の発生と構造
2.1 歯髄の発生
2.2 歯髄の構造
3 歯髄の特徴と分化能
4 永久歯,乳歯および過剰歯の歯髄幹細胞
5 歯髄幹細胞の評価技術
5.1 歯髄幹細胞の未分化性を評価する技術
5.2 in vitroにおける硬組織形成細胞への分化能を評価する技術
5.3 in vivo実験を用いた硬組織形成能の機能評価技術
5.4 表面抗原解析による歯髄幹細胞の機能評価技術
6 iPS細胞の樹立
7 おわりに
第14章 心臓・血管系
1 はじめに
2 移植細胞シートの機能評価
3 非臨床試験での評価
3.1 有効性を示唆するために必要な実験
3.2 非侵襲的評価方法(心エコー,CT,MRI)
3.3 侵襲的評価(組織学的評価,遺伝子・タンパク質発現解析)
3.4 移植細胞の残存評価
3.5 動物実験モデル
4 臨床試験での評価
4.1 筋芽細胞シート移植における細胞機能評価
4.2 「ハートシート」における臨床評価
5 おわりに
第15章 培養細胞シートを用いた角膜再生治療への取り組み
1 はじめに
2 角膜上皮疾患と再生治療の背景
3 自己培養口腔粘膜上皮細胞シート移植による角膜再生治療
4 ヒトiPS細胞由来培養上皮細胞シートを用いた角膜再生治療の開発
5 自家培養角膜上皮細胞シートを用いた企業主導治験
6 角膜内皮の再生治療
7 おわりに
第16章 糖鎖を標的としたヒト間葉系幹細胞の品質管理技術の開発
1 背景
2 糖鎖は「細胞の顔」?
3 細胞表層糖鎖を迅速高感度に解析する技術:レクチンアレイ
4 ヒト多能性幹細胞の糖鎖
5 ヒト間葉系幹細胞の糖鎖
6 α2-6シアリルN型糖鎖の機能
7 まとめ
第17章 神経
1 はじめに
2 神経細胞の評価技術
2.1 qPCR法
2.2 免疫細胞化学
2.3 フローサイトメトリー
2.4 神経突起の評価
2.5 電気生理学的手法による評価
3 ドパミン神経細胞の評価技術
3.1 核型分析
3.2 SNP分析
3.3 CNV分析
3.4 高速液体クロマトグラフィー(HPLC)
3.5 パーキンソン病ラットモデル
4 おわりに
【第3編 評価技術についての動向】
第18章 国際標準化の状況
1 はじめに
2 再生医療等製品に関する試験法・評価法の国際標準化の状況
3 細胞加工装置に関する国際標準化の状況
4 再生医療用途の足場材料に関する国際標準化の状況
5 再生医療分野の国際標準化の展望
6 おわりに
第19章 研究用組織試料の収集と分譲
1 はじめに
2 組織試料の収集にあたって
2.1 インフォームド・コンセント
2.2 組織試料採取の準備
3 凍結組織試料の収集・保管
3.1 組織の採取
3.2 組織の処理・組織片試料(dry sample)の調整
3.3 包埋組織試料(OCT sample)の調整
4 凍結組織試料の搬送
5 感染性試料の扱い,試料の廃棄
6 ホルマリン固定パラフィン包埋試料の作製・保管
7 試料の分譲
7.1 倫理審査
7.2 共同研究契約,試料分譲同意書
7.3 分譲手数料
8 おわりに
第20章 ヒト細胞加工製品の品質及び非臨床安全性の確保に関する各種指針を踏まえた私見
1 はじめに
2 ヒト細胞加工製品の品質確保
2.1 一般的な品質確保の考え方について
2.2 ヒト細胞加工製品の特徴
2.3 ヒト細胞加工製品の品質確保を適正かつ合理的に行うための留意事項
2.4 品質確保のまとめ
3 ヒト細胞加工製品の非臨床開発時点における品質からみたin vivo試験や評価の考え方
3.1 一般的留意事項
3.2 造腫瘍性評価について
4 おわりに
第21章 再生医療等製品の製造管理及び品質管理
1 はじめに
2 再生医療を取り巻く新たな規制の枠組み
3 再生医療等製品の特徴と品質設計における課題
4 再生医療等製品の品質における基本の考え方
5 技術移管に向けた製品品質の理解と知識管理の重要性
6 再生医療等製品の製造管理及び品質管理における要点と課題
7 品質リスクマネジメントの考え方
8 ベリフィケーションによる品質保証のアプローチ
9 治験製品の製造管理及び品質管理の要点
10 再生医療等製品のCMC 開発研究での留意点
11 おわりに
第22章 臨床用原材料細胞のセルバンク
1 はじめに
2 再生医療用HLA-ホモiPS細胞ストックプロジェクト
3 「臨床用原材料細胞のセルバンク」としてのiPS細胞ストック
4 FiTにおける臨床用iPS細胞の製造・品質管理
4.1 ドナー適格性の判定
4.2 製造に使用する原料等・工程資材
4.3 製造方法
4.4 品質管理方法
5 おわりに
-

ポリマーナノコンポジットの開発と分析技術《普及版》
¥3,960
2016年刊「ポリマーナノコンポジットの開発と分析技術」の普及版。各種別のコンポジット技術や応用展開に加え、コンポジット構造の状態、物性を測る分析技術についても解説した1冊!
(監修:岡本正巳)
<a href="http://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=9169"target=”_blank”>この本の紙版「ポリマーナノコンポジットの開発と分析技術(普及版)」の販売ページはこちら(別サイトが開きます)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は、2016年当時のものを使用しております。
上田一恵 ユニチカ(株)
岡本正巳 豊田工業大学
棚橋満 名古屋大学
堀内伸 (国研)産業技術総合研究所
髙嶋洋平 甲南大学
鶴岡孝章 甲南大学
冨田知志 奈良先端科学技術大学院大学
赤松謙祐 甲南大学
芝田正之 大日精化工業(株)
小池常夫 島貿易(株)
藤井透 同志社大学
大窪和也 同志社大学
仙波健 (地独)京都市産業技術研究所
陣内浩司 東北大学
西辻祥太郎 山形大学
浅野敦志 防衛大学校
中嶋健 東京工業大学
尾崎幸洋 関西学院大学
佐藤春実 神戸大学
長尾大輔 東北大学
日髙貴志夫 山形大学
吉本尚起 (株)日立製作所
西澤仁 西澤技術研究所
西谷要介 工学院大学
川口正剛 山形大学
-------------------------------------------------------------------------
<<目次>>
【第I編 ナノコンポジット材料の開発】
第1章 クレイナノコンポジット
1 ポリアミド系クレイナノコンポジット
1.1 はじめに
1.2 ナイロン6クレイナノコンポジットの作製方法
1.3 ナイロン6クレイナノコンポジットの物性、特長
1.3.1 軽量で高剛性、高耐熱性
1.3.2 吸水特性、バリア性能
1.3.3 色調
1.3.4 成形性
1.3.5 リサイクル性
1.3.6 物性のまとめ
1.4 NANOCON(R)の応用例
1.4.1 軽量高強度用途
1.4.2 良外観用途
1.5 今後の展開
2 クレイナノコンポジット材料の現状と将来展望
2.1 はじめに
2.2 PCN材料の構造制御と現状の技術課題
2.2.1 高分子鎖の層間挿入
2.2.2 層状有機修飾フィラーの層剥離を目的とした研究例
2.2.3 完全な層剥離型PCN
2.2.4 メソ構造(ネットワーク)形成
2.2.5 ポリ乳酸をベースにしたPCNにおける結晶化過程のダイナミクス
2.2.6 微細発泡体と2次加工
2.2.7 クレイ化学の基本原理を基軸とした新規な研究
2.2.8 クレイを使った再生医療・組織工学の研究
2.3 まとめと展望
第2章 無機材料ナノコンポジット
1 ポリプロピレン/親水性シリカ系ナノコンポジットの簡易調製法と機械的特性
1.1 はじめに
1.2 無機ナノフィラーの表面疎水化処理フリーの有機/無機系ナノコンポジットの簡易調製法
1.2.1 従来のブレンド法
1.2.2 ナノフィラーの表面疎水化処理フリーの新規ブレンド法の開発戦略と概要
1.3 新規手法によるポリプロピレン/シリカ系ナノコンポジットの調製
1.3.1 予備作製した易解砕性シリカナノ粒子弱集合体の特性
1.3.2 溶融混練により達成されるポリプロピレン中でのシリカナノ粒子集合体の解砕・分散性
1.4 親水性表面を有するコロイダルシリカが分散したポリプロピレン/シリカ系ナノコンポジットの機械的特性
1.4.1 対象コンポジット
1.4.2 本系ナノコンポジットのiPP結晶化度
1.4.3 静的引張り特性
2 高分子/金属ナノコンポジットの構造制御と機能
2.1 はじめに
2.2 昇華性金属錯体を用いたポリマー/金属ナノコンポジットの作製
2.3 高分子フィルム内部への金属ナノ粒子の集積化・パターニング
2.4 金属ナノ粒子の集積化による発現機能
2.5 おわりに
3 金属ナノ粒子分散ナノコンポジット材料
3.1 はじめに
3.2 従来プロセスでの金属ナノ粒子/ポリマーナノコンポジットの作製
3.3 ポリイミドをマトリックスとするナノコンポジットの作製
3.3.1 マトリックスしてのポリイミド
3.3.2 ポリイミド樹脂の表面改質を利用する金属イオンの導入
3.3.3 水素還元処理による金属ナノ粒子の合成
3.4 ナノ粒子サイズと粒子間距離の制御
3.5 In Situ合成法の応用
3.6 おわりに
第3章 カーボンナノチューブナノコンポジット
1 CNT複合導電性プラスチックナノコンポジット材料
1.1 開発の背景
1.2 分散処理技術
1.2.1 分散剤処方
1.2.2 加工法
1.3 分散の評価と分散の効果
1.3.1 分散評価法
1.3.2 分散の効果:CNTの分散に伴い樹脂物性が向上する例を示す。
1.4 CNTナノコンポジットの応用事例
1.4.1 導電性
1.4.2 成形性
1.5 今後の展開
2 CNT充填エポキシ樹脂繊維強化複合材料
2.1 CNT充填エポキシ樹脂繊維強化複合材料について
2.2 局在化CNT充填エポキシ樹脂繊維強化複合材料
2.2.1 繊維織物等へのCNTグラフトによる局在化
2.2.2 層間補強によるCNT/繊維ハイブリッド化手法
2.2.3 電着法によるCNT/繊維ハイブリッド化手法
2.2.4 エレクトロスピニング法によるCNT/繊維ハイブリッド化手法
2.3 あとがき
第4章 セルロースナノファイバーナノコンポジット
1 CNFコンポジットの開発
1.1 CNFとは
1.2 CNFの活用
1.3 エポキシ母材のCNF(物理的)変性によるCFRPの疲労寿命の向上
1.4 エポキシ母材のCNF変性により、なぜCFRPの疲労寿命が向上するのか?
1.5 CNFの適量添加により、エポキシ樹脂とカーボン繊維界面の接着強度が増す
1.6 CNFの活用
2 CNF/熱可塑性樹脂
2.1 はじめに
2.2 CNFと熱可塑性樹脂混合における課題
2.3 セルロースの化学変性
2.4 セルロースと熱可塑性プラスチックの複合化手法
2.5 変性CNFの耐熱性樹脂への適用
2.6 CNF強化樹脂材料のリサイクル特性の評価
2.7 まとめ
【第II編 ナノコンポジット材料の分析】
第5章 電子線トモグラフィによるナノコンポジット三次元観察と解析
1 はじめに
2 電子線トモグラフィ(TEMT)の概要と分解能
2.1 ナノフィラー含有ゴム材料の三次元観察および解析
2.1.1 元素識別型電子線トモグラフィによるナノフィラーの識別
2.1.2 三次元画像の精度と定量性
2.1.3 ナノフィラー含有ゴム材料の構造解析例
第6章 超小角X線散乱法によるナノコンポジット解析
1 はじめに
2 USAXS法
2.1 Bonse-Hartカメラ
2.2 放射光を用いた長距離パスカメラ
3 USAXS法による階層構造の解析
3.1 Bonse-Hartカメラを用いたUSAXS測定
3.2 長距離カメラを用いたUSAXS測定
4 さいごに
第7章 固体高分解能NMR法による高分子複合材料の構造解析
1 はじめに
2 PMAA/PVAcブレンドとPK/PAアロイの相溶性解析
3 N6/mmt複合材料(ナノコンポジット)のモルフォロジー解析
4 PVIBE/ε-PL/sapoナノコンポジットの結晶相の融点とラメラ厚
5 最後に
第8章 ポリマー系ナノコンポジットのAFMによる弾性率マッピング
1 はじめに
2 AFMナノメカニカル計測
3 実例1 カーボンブラック充填ゴム
4 実例2 カーボンナノチューブ充填ゴム
5 まとめ
第9章 チップ増強ラマン散乱法
1 はじめに
2 TERSの特徴
3 TERS装置とチップの特性
3.1 TERS装置の光学配置とその特性
3.2 チップの作製法
3.3 測定装置
4 TERSによるポリマーナノコンプジットの研究
4.1 TERSによるポリマーナノコンプジットの研究例1
4.2 TERSによるポリマーナノコンプジットの研究例2
5 終わりに
【第III編 応用】
第10章 高屈折率透明ナノコンポジット薄膜
1 はじめに
2 ゾル-ゲル法による結晶性BTナノ粒子の合成
3 ポリマーとの複合化のためのBTナノ粒子表面修飾
3.1 ポリメタクリル酸メチルとBTナノ粒子のナノコンポジット薄膜
3.2 ポリイミドとBTナノ粒子のナノコンポジット薄膜
4 まとめ
第11章 電磁波吸収材料のナノコンポジット技術
1 はじめに
2 ナノコンポジット粒子の開発
3 電磁波吸収ナノコンポジット
4 体積抵抗率測定法
5 電磁波吸収測定法
5.1 空洞共振法
5.2 マイクロストリップライン法
5.3 同軸管法
5.4 自由空間法
6 おわりに
第12章 ナノコンポジットを用いた難燃材料
1 はじめに
2 ナノコンポジット難燃材料とその特徴
3 難燃材料に使用されるナノフィラーの種類と特徴
4 ナノコンポジットの製造法
5 ナノコンポジット難燃材料の難燃機構とその特性
5.1 ナノコンポジット難燃材料の難燃機構と難燃性
6 難燃性ナノコンポジットの最近の研究動向
7 従来難燃系とナノフィラーの併用難燃系の研究動向
第13章 ナノコンポジットを用いたトライボマテリアル
1 はじめに
2 ナノコンポジットを用いたトライボマテリアル
2.1 カーボンナノファイバー充填系
2.2 ナノ炭酸カルシウム充填系
3 多成分系複合材料
3.1 多成分系複合材料のトライボロジー的性質
3.2 多成分系複合材料のトライボロジー的性質に及ぼす混練手順の影響
4 おわりに
第14章 有機・無機ハイブリッドナノ微粒子の創成
1 はじめに
2 微粒子集積法を用いた透明ポリメタクリル酸ブチル-ZrO2ハイブリッドラテックス膜の合成
3 ミニエマルション法によるZrO2内包高分子微粒子の合成
4 おわりに
5 謝辞
-

マイクロニードルの製造と応用展開《普及版》
¥3,080
2016年刊「マイクロニードルの製造と応用展開」の普及版。マイクロニードルについて、材料選定から各種製造方法と性能評価を解説し、さらに医療・医薬品や美容・化粧品への応用事例も多数紹介した1冊!
(監修:中川晋作)
<a href="http://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=9171"target=”_blank”>この本の紙版「マイクロニードルの製造と応用展開(普及版)」の販売ページはこちら(別サイトが開きます)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は、2016年当時のものを使用しております。
中川晋作 大阪大学
押坂勇志 城西大学
藤堂浩明 城西大学
杉林堅次 城西大学
権英淑 コスメディ製薬(株)
神山文男 コスメディ製薬(株)
小幡誉子 星薬科大学
福田光男 (株)ライトニックス(Lightnix, Inc.)
青柳誠司 関西大学
式田光宏 広島市立大学
加藤暢宏 近畿大学
高橋英俊 東京大学
許允禎 慶煕大学校
伊藤浩志 山形大学
三重野計滋 (株)ワークス
廣部祥子 大阪大学
岡田直貴 大阪大学
小山田孝嘉 富士フイルム(株)
勝見英正 京都薬科大学
山本昌 京都薬科大学
深水秀一 浜松医科大学
水上高秀 浜松医科大学
伊東忍 (株)アイ・ティー・オー;慶應義塾大学
森文子 クリニックモリ;慶應義塾大学
内田貴子 (株)アイ・ティー・オー
金澤秀子 慶應義塾大学
野原哲矢 (株)東洋発酵
-------------------------------------------------------------------------
<<目次>>
第1章 マイクロニードルの基礎
1 マイクロニードルの製造法と応用
1.1 はじめに
1.2 マイクロニードル製造方法
1.2.1 材料
1.2.2 製造方法
1.2.3 マイクロニードルの形状と投与方法
1.3 マイクロニードルで穿刺した試験方法
1.3.1 皮膚透過試験
1.3.2 穿刺深さの評価法
1.3.3 皮膚透過試験評価法
1.4 マイクロニードルとエレクトロポレーションの併用
1.5 おわりに
2 医療用デバイスとしてのマイクロニードルの開発
2.1 はじめに
2.2 医療用デバイスとしてのマイクロニードルの要求性能
2.3 医療用デバイスとしてのマイクロニードルの種類および構成材料
2.4 医療用デバイスとしてのマイクロニードルの機械的強度
2.5 医療用デバイスとしてのマイクロニードルの投与器具(アプリケータ)
2.6 医療用デバイスとしてのマイクロニードルの皮膚挿入性および薬物送達性
2.6.1 ヒアルロン酸溶解型マイクロニードル
2.6.2 PGA生分解性非溶解型マイクロニードル
2.7 医療用デバイスとしてのマイクロニードルの皮膚安全性
2.8 まとめ
3 マイクロニードルの設計および材料選定のポイント
3.1 はじめに
3.2 マイクロニードルの種類,形状および材料
3.2.1 固体マイクロニードル
3.2.2 コーティング型マイクロニードル
3.2.3 溶解型マイクロニードル
3.2.4 中空型マイクロニードル
3.2.5 マイクロニードルパッチ
3.3 マイクロニードルの選択と適用
3.4 将来の展望
4 痛みを感じない蚊の針を模倣したマイクロニードルの設計―ごみを残さない新しい医療機器の実現―
4.1 はじめに(背景)
4.2 これまでの刺さることの基本構造:従来の概念での針構造
4.3 バイオミメティックスからの考察
4.4 マイクロニードルの現状
4.5 マイクロニードルに必要な設計
4.6 これからのマイクロニードルにとっての重要性
4.7 今後の展開
4.8 まとめ
第2章 マイクロニードル製造技術と穿刺評価
1 蚊を模倣したマイクロニードルの開発
1.1 はじめに
1.2 蚊の針の構造と穿刺動作
1.3 有限要素法による穿刺動作のシミュレーション
1.3.1 解析モデルと解析手法
1.3.2 シミュレーション結果
1.4 超高精度光造形によるマイクロニードルの作製
1.4.1 蚊の上唇と2本の小顎を模倣した3本一組の針の作製(蚊の忠実な模倣)
1.4.2 半割状の針を2本組み合わせた針の作製(成形可能)
1.4.3 半割状マイクロニードルの作製および評価結果
1.5 まとめ
2 エッチング及びモールド加工技術を用いたマイクロニードルの開発
2.1 はじめに
2.2 MEMS加工技術によるマイクロニードル開発の経緯
2.2.1 Si製マイクロニードル加工プロセス
2.2.2 低コスト化Si製マイクロニードル加工プロセス
2.2.3 生分解性マイクロニードル加工プロセス
2.3 エッチング加工技術によるSi製マイクロニードルの開発
2.3.1 Si製マイクロニードルの作製方法
2.3.2 エッチング加工で作製したSi製マイクロニードル
2.4 モールド加工技術による生分解性マイクロニードルの開発
2.4.1 生分解性マイクロニードルの作製方法
2.4.2 モールド加工で作製した生分解性マイクロニードル
2.5 まとめ
3 リソグラフィを利用したマイクロニードルの開発
3.1 はじめに
3.2 厚膜フォトリソグラフィ
3.3 フォトレジストパターニングによるマイクロニードル型の形成
3.4 裏面照射型移動マスク露光法
3.5 移動マスク露光装置の構成
3.6 レジストの露光特性
3.7 フォトレジスト形状シミュレーション
3.8 作製したフォトレジスト製マイクロニードル
3.9 コンドロイチン硫酸Cナトリウム製マイクロニードルの作製
3.10 まとめ
4 回転傾斜露光によるマイクロニードルアレイの作製
4.1 回転傾斜露光方法
4.2 回転傾斜露光方法を用いた成形マスクの作製
4.2.1 逆円錐構造
4.2.2 円錐構造
4.2.3 成形マスタを用いたモールド加工
4.3 露光量の違いを利用した円錐構造の作製
4.3.1 各パラメータの定義
4.3.2 屈折による影響
4.4 紫外線露光量の割合
4.4.1 紫外線露光領域の定義
4.4.2 紫外線が照射される区間の割合
4.5 紫外線の減衰
4.6 回転傾斜露光時の露光量
4.7 円錐構造の作製
4.8 まとめ
5 射出成形および熱インプリントによるマイクロニードルアレイの作製と構造形成
5.1 はじめに
5.2 マイクロ・ナノスケールの微細表面転写成形の課題と動向
5.3 射出成形によるマイクロニードルアレイの成形
5.4 ホットエンボスもしくはRtRナノインプリントによるニードル成形の研究
6 精密微細機械加工技術を用いたマイクロニードルアレイの開発
6.1 諸言
6.2 自己溶解型マイクロニードルとは
6.3 マスター金型
6.3.1 マスター金型と材質
6.3.2 加工工具の選定と機械への装着
6.3.3 加工条件
6.3.4 加工機械
6.3.5 加工環境
6.4 鋳型の製作
6.4.1 鋳型
6.5 成形加工方法
6.5.1 研究用流し込み金型での試作開発
6.5.2 量産型
6.6 測定方法
6.6.1 非接触レーザー測定
6.7 結言
7 物理的アプローチによるマイクロニードル穿刺評価
7.1 はじめに
7.2 荷重変位曲線に基づいた力学的穿刺評価方法
7.2.1 荷重変位曲線から穿刺特性を計測評価する方法
7.2.2 複数回実施の荷重変位曲線から穿刺の有無を判別する方法
7.3 光学的穿刺評価方法
7.4 まとめ
第3章 医療・医薬品への展開
1 自己溶解型マイクロニードルを用いた経皮ワクチン製剤の開発
1.1 はじめに
1.2 ワクチンの標的部位としての皮膚
1.3 皮内注射ワクチンの有用性
1.4 マイクロニードルを用いた経皮ワクチン製剤
1.4.1 ソリッドマイクロニードル
1.4.2 中空マイクロニードル
1.4.3 コーティングマイクロニードル
1.4.4 生分解性および溶解型マイクロニードル
1.5 溶解型マイクロニードルを用いた経皮ワクチン製剤の開発
1.6 おわりに
2 マイクロニードルアレイ医薬品開発
2.1 はじめに
2.2 マイクロニードルアレイ医薬品開発
2.2.1 不活化全粒子インフルエンザワクチンを内包したMNAによる免疫誘導
2.2.2 ヒト成長ホルモンを内包したマイクロニードルアレイ製剤
2.3 おわりに
3 ヒアルロン酸を素材とする溶解型マイクロニードルを利用した糖尿病治療薬の経皮デリバリー
3.1 はじめに
3.2 ヒアルロン酸を利用した溶解型マイクロニードルの開発
3.3 ヒアルロン酸マイクロニードルを用いた糖尿病治療薬インスリンの経皮デリバリー
3.4 ヒアルロン酸を素材とする先端部封入型マイクロニードルの開発
3.5 先端部封入型マイクロニードルを利用した糖尿病治療薬エキセナチドの経皮デリバリー
3.6 おわりに
4 マイクロニードルを用いた皮膚疾患治療法の開発
4.1 はじめに
4.2 脂漏性角化症に対する外科的療法
4.3 レチノイドを用いた薬物療法の開発動向
4.4 ATRA装填マイクロニードル製剤を用いた薬物療法の開発
4.5 ATRA装填マイクロニードル製剤の安定性および安全性
4.6 ATRA装填マイクロニードル製剤の臨床研究
4.7 おわりに
第4章 美容・化粧品への展開
1 マイクロニードルのアンチエイジング化粧品への応用
1.1 はじめに
1.2 化粧品マイクロニードルの特徴
1.3 マイクロニードルの基本性能
1.3.1 マイクロニードルの溶解性および薬剤送達性
1.3.2 マイクロニードルによる薬剤皮膚浸透性
1.3.3 マイクロニードルの皮膚安全性
1.4 マイクロニードルのしわケアへの応用
1.5 マイクロニードルの美白への応用
1.6 マイクロニードルの育毛への応用
1.7 おわりに
2 マイクロニードルの形成外科,美容皮膚科治療への応用
2.1 はじめに
2.2 マイクロニードル(MN)の歴史
2.3 我々の開発した3本針MN
2.4 3本針MNの臨床応用
2.4.1 ボトックスビスタ?による皺取り
2.4.2 局所麻酔
2.4.3 その他
2.5 現状と今後の展望
3 マイクロニードルの美容医療における臨床応用
3.1 はじめに
3.2 b-FGFの皮膚への各種導入方法の検討
3.3 b-FGFの定量
3.4 ELISA法によるb-FGFの皮膚内濃度の定量
3.5 GFPによる疑似ペプチドの皮膚内分布の可視化
3.6 細胞染色における膠原繊維の分布
3.7 b-FGFの製剤内部の力価変化
3.8 ELISA法による皮膚内b-FGF濃度
3.9 皮膚内の膠原繊維密度
3.10 共焦点レーザー顕微鏡観察による皮膚内のGFP分布
3.11 臨床試験の結果
3.12 マイクロニードルによるドラッグデリバリーシステム
3.13 b-FGFの製剤中の安定化技術
3.14 おわりに
4 米糠大豆発酵物配合マイクロニードルの有用性
4.1 はじめに
4.2 米糠大豆発酵物とレチノール成分の機能
4.2.1 真皮線維芽細胞増殖促進
4.2.2 コラーゲン合成量
4.2.3 「モイスチャーパッチ」連用試験(ヒト試験)
4.3 まとめ
-

中空微粒子の合成と応用《普及版》
¥3,300
2016年刊「中空微粒子の合成と応用」の普及版。有機・無機・エマルション・バブルテンプレートなど各種合成法を網羅し、フィルム・塗料・建材分野から最新応用技術までを詳述した1冊!
(監修:藤 正督)
<a href="http://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=9172"target=”_blank”>この本の紙版「中空微粒子の合成と応用(普及版)」の販売ページはこちら(別サイトが開きます)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は、2016年当時のものを使用しております。
藤正督 名古屋工業大学
福井有香 慶應義塾大学
藤本啓二 慶應義塾大学
片桐清文 広島大学
松田厚範 豊橋技術科学大学
遊佐真一 兵庫県立大学
石井治之 東北大学
谷口竜王 千葉大学大学院
仲村龍介 大阪府立大学
高井千加 名古屋工業大学
大谷政孝 高知工科大学
小廣和哉 高知工科大学
荻崇 広島大学
岡田友彦 信州大学学術研究院
土屋好司 東京理科大学
酒井秀樹 東京理科大学
幕田寿典 山形大学
冨岡達也 名古屋工業大学
遠山岳史 日本大学
飯村健次 兵庫県立大学
長嶺信輔 京都大学
突廻恵介 JSR(株)
村口良 日揮触媒化成(株)
中村皇紀 関西ペイント販売(株)
-------------------------------------------------------------------------
<<目次>>
第1章 有機粒子テンプレート
1 リポソームを鋳型とした中空微粒子の合成
1. 1 はじめに
1. 2 テンプレートとしてのリポソーム
1. 3 リポソーム表面への交互積層化による中空微粒子(リポナノカプセル)の作製
1. 4 リポナノカプセルの機能:物質の封入・放出制御
1. 5 リポナノカプセルの機能:細胞との相互作用
1. 6 リポナノカプセルの機能:組織化による膜構造体(バイオスキャフォールド)の作製
1. 7 ミネラルコーティングによる有機無機ハイブリッドリポナノカプセルの作製
1. 8 まとめ
2 交互積層法による中空粒子の合成
2. 1 はじめに
2. 2 交互積層法による高分子電解質中空粒子の合成
2. 3 高分子電解質多層膜表面における酸化物層形成による無機中空粒子の合成
2. 4 水溶性チタン錯体の交互積層によるチタン酸化物系中空粒子の合成
2. 5 おわりに
3 pH応答性ポリマーミセルを鋳型にした中空粒子の合成
3. 1 はじめに
3. 2 PS-PAA-PEOの合成
3. 3 PS-PAA-PEOミセルの作製
3. 4 カルシウムイオン(Ca2+)と高分子ミセルのコンプレックス形成
3. 5 中空CaWO4ナノ粒子の作製
3. 6 ZnO中空ナノ粒子の作製
3. 7 まとめ
4 ベシクルテンプレートを利用した中空粒子の合成
4. 1 はじめに
4. 2 中空シリカ粒子の構造・形状を決定するベシクル構造・形状
4. 3 ベシクルテンプレート法で用いられるベシクルの種類
4. 4 おわりに
5 表面修飾された高分子微粒子をテンプレートに用いた中空粒子の調製
5. 1 はじめに
5. 2 テンプレートとなるコア-シェル粒子の合成
5. 2. 1 ソープフリー乳化重合によるコア粒子の合成
5. 2. 2 コア粒子表面からのATRP によるコア-シェル粒子の合成
5. 3 コア-シェル粒子をテンプレートとする有機/無機複合粒子および中空粒子の調製
5. 3. 1 サブミクロンサイズの中空粒子の作製
5. 3. 2 ミクロンサイズの中空粒子の作製
5. 3. 3 ナノサイズの中空粒子の作製
5. 4 おわりに
第2章 無機粒子テンプレート
1 金属ナノ粒子の酸化による中空粒子合成
1. 1 はじめに
1. 2 金属ナノ粒子の酸化による酸化物ナノ中空粒子の形成
1. 3 金属ナノワイヤーの酸化による酸化物ナノチューブの形成
1. 4 中空構造の形成メカニズム
1. 5 中空構造の熱的安定性
1. 6 おわりに
2 溶解性無機粒子をテンプレートとした中空粒子合成
2. 1 はじめに
2. 2 ゾルゲル法の基礎
2. 3 無機/ ケイ酸塩中空粒子の作製及び一般的なアプローチ
2. 3. 1 ハードテンプレート法から溶解性無機粒子をテンプレートへ
2. 3. 2 溶解性無機粒子テンプレートの展開
2. 4 おわりに
第3章 エマルションテンプレート
1 中空多孔質構造を有するナノ粒子集合体の一段階合成
1. 1 はじめに
1. 2 中実および中空MARIMO TiO2集合体のワンポット単工程合成
1. 3 中空MARIMO TiO2集合体空孔内への貴金属合金ナノ粒子の充填
1. 4 中空MARIMO複合酸化物ナノ粒子集合体ワンポット合成と物性制御
1. 4. 1 合成
1. 4. 2 中空Al2O3-TiO2複合集合体の高温耐性
1. 4. 3 中空ZnO-TiO2複合集合体のバンドギャップエネルギー制御
1. 5 まとめ
2 噴霧法および液相法によるテンプレート粒子を用いた中空微粒子の合成
2. 1 はじめに
2. 2 テンプレート粒子を利用する中空微粒子の合成方法
2. 2. 1 概要
2. 2. 2 液相法による中空微粒子の合成法
2. 2. 3 噴霧法による中空微粒子の合成法
3 油中水滴分散型エマルションを利用した中空粒子合成
3. 1 はじめに
3. 2 油中水滴分散型(W/O)エマルションを用いた中空粒子の合成
3. 2. 1 有機高分子
3. 2. 2 シリカ類
3. 2. 3 その他の無機化合物
3. 3 内包
3. 3. 1 磁性微粒子の内包
3. 3. 2 触媒活性粒子の内包
3. 4 まとめと展望
第4章 バブルテンプレート
1 バブルテンプレート法を用いたシリカ中空粒子の調製
1. 1 はじめに
1. 2 バブルをテンプレートとしたシリカ中空粒子の調製方法
1. 3 バブルをテンプレートとしたシリカ中空粒子調製条件の最適化
1. 3. 1 界面活性剤の分子構造の影響
1. 3. 2 エタノール添加の影響
1. 3. 3 pHの影響
1. 3. 4 シリカ前駆体濃度による影響
1. 3. 5 内包ガスによる影響
1. 3. 6 シリカ中空粒子の焼成
1. 4 結論
2 超音波マイクロバブルを用いた中空微粒子調製法
2. 1 はじめに
2. 2 実験装置および手法
2. 2. 1 材料
2. 2. 2 実験装置
2. 2. 3 調製手順
2. 3 実験結果と考察
2. 3. 1 中空超音波ホーンからのマイクロバブル生成
2. 3. 2 中空微粒子調整結果
2. 3. 3 酸性環境下における中空微粒子のサブミクロン化
2. 4 おわりに
3 バブルテンプレート法による中空粒子の製造
3. 1 背景
3. 2 炭酸カルシウム中空粒子の製造
3. 2. 1 製造プロセス
3. 2. 2 炭酸カルシウム中空粒子の製造装置
3. 3 炭酸ガスバブリング時の炭酸カルシウムの析出挙動
3. 3. 1 炭酸カルシウムの核生成と核成長
3. 3. 2 炭酸ガスバブリング反応時における炭酸カルシウムの析出と変態
3. 3. 3 中空粒子形成に必要な炭酸ガスバブリング条件
3. 4 むすび
第5章 噴霧法
1 噴霧乾燥法による中空粒子の作製
1. 1 噴霧乾燥法とは
1. 2 噴霧乾燥法による炭酸カルシウム中空粒子の作製
1. 3 中空粒子の機械的特性
1. 4 まとめ
2 火炎噴霧法による中空粒子の作製
2. 1 諸言
2. 2 技術的な背景
2. 3 実験方法
2. 4 実験結果および考察
2. 4. 1 粒子形態
2. 4. 2 中空構造に及ぼす原料組成の影響と構造制御
2. 5 結言
3 噴霧水滴-油相界面でのゾル-ゲル反応を利用したチタニア中空粒子の作製
3. 1 はじめに
3. 2 噴霧水滴-油相界面でのゾル-ゲル反応を利用したチタニア中空粒子の作製
3. 3 窒素ドープによる可視光応答性チタニア中空粒子の作製
3. 4 静電紡糸法と界面でのゾル?ゲル反応によるチタニア中空ファイバーの作製
3. 5 おわりに
第6章 応用
1 中空粒子の光学材料への展開
1. 1 はじめに
1. 2 高架橋ポリマーで被覆された中空粒子
1. 3 中空粒子含有UV 硬化インク
1. 4 UV インク硬化膜中の中空粒子の状態と光学特性
1. 5 ドット印刷導光板の発光特性
1. 6 バックライトユニットの性能評価
1. 7 中空粒子含有UV 硬化インクのガラス導光板への適用
1. 8 おわりに
2 反射防止フィルム
2. 1 はじめに
2. 2 反射防止フィルムの設計
2. 2. 1 反射防止の原理
2. 2. 2 反射防止フィルムの設計
2. 2. 3 ナノコンポジット設計
2. 2. 4 フィラー設計
2. 3 反射防止フィルムの実用例
2. 3. 1 中空SiO2微粒子を用いた反射防止フィルム
2. 3. 2 高機能化(AS性付与)
2. 3. 3 更なる高性能化
2. 4 おわりに
3 断熱材料
3. 1 はじめに
3. 2 ナノ中空粒子の研究
3. 2. 1 ナノ中空粒子の魅力
3. 2. 2 ナノ中空粒子合成の開発
3. 3 ナノ中空粒子の化学的な分散技術
3. 4 ナノ中空粒子を用いた透明断熱フィルムの開発
3. 5 おわりに
4 アルミニウム防食膜
4. 1 はじめに
4. 2 高機能を引き出すナノテクノロジー
4. 3 アルミニウムの腐食
4. 4 従来のクロメート処理による防食技術
4. 5 防食評価としてのキャス(CASS)試験概要
4. 6 ナノ中空粒子含有防食塗料の展開
4. 7 成功を支えた分散技術
4. 8 おわりに
5 湿式外断熱躯体保護防水仕上げ材 「ドリームコート」について
5. 1 背景
5. 2 塗膜に中空微粒子を導入する効果について
5. 3 「ドリームコート」の透湿性と耐水性について
5. 4 「ドリームコート」の外断熱効果について
5. 5 「ドリームコート」の躯体保護機能について
5. 6 「ドリームコート」の塗装と仕上がりについて
5. 7 まとめ
-

ワイヤレス電力伝送技術の研究開発と実用化の最前線《普及版》
¥4,400
2016年刊「ワイヤレス電力伝送技術の研究開発と実用化の最前線」の普及版。ワイヤレス給電について、携帯電話や医療機器などのデバイスから自動車まで、国内のみならず海外の応用事例も広く紹介した1冊!
(監修:篠原真毅)
<a href="http://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=9161"target=”_blank”>この本の紙版「ワイヤレス電力伝送技術の研究開発と実用化の最前線(普及版)」の販売ページはこちら(別サイトが開きます)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は、2016年当時のものを使用しております。
篠原真毅 京都大学
平山裕 名古屋工業大学
高橋俊輔 早稲田大学
松木英敏 東北大学
藤野義之 東洋大学
庄木裕樹 (株)東芝
Nuno Borges Carvalho Instituto de Telecomunicações;Universidade de Aveiro
Apostolos Georgiadis Heriot-Watt University
Pedro Pinho Instituto de Telecomunicações;Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
Ana Collado Heriot-Watt University
Alírio Boaventura Instituto de Telecomunicações;Universidade de Aveiro
Ricardo Gonçalves Instituto de Telecomunicações;Universidade de Aveiro
Ricardo Correia Instituto de Telecomunicações;Universidade de Aveiro
Daniel Belo Instituto de Telecomunicações;Universidade de Aveiro
Ricard Martinez Alcon Universitat Politecnica de Catalunya
Kyriaki Niotaki Benetel Ltd.
大西輝夫 (株)NTTドコモ
平田晃正 名古屋工業大学
和氣加奈子 (国研)情報通信研究機構
日景隆 北海道大学
横井行雄 京都大学
Seungyoung Ahn KAIST
大平孝 豊橋技術科学大学
石野祥太郎 古野電気(株)
中川義克 インテル(株)
Hatem Zeine OSSIA INC. CEO
Alireza Saghati OSSIA INC.
鶴田義範 (株)ダイヘン
細谷達也 (株)村田製作所
原川健一 (株)ExH(イー・クロス・エイチ)
張兵 (国研)情報通信研究機構
牧野克省 (国研)宇宙航空研究開発機構
-------------------------------------------------------------------------
<<目次>>
第1章 総論
1 ワイヤレス給電の理論―電磁誘導とマイクロ波送電の関係性―
1.1 そもそも,電力とは
1.2 そもそも,ワイヤレス電力伝送とは
1.3 ワイヤレス給電システムの分類
1.4 ワイヤレス給電システムの構成要素
1.4.1 結合器
1.4.2 ワイヤレス給電システムにおける周波数変換・インピーダンス変換・モード変換の実装方法
1.4.3 近傍界型ワイヤレス給電システムにおける構成要素のパラメータ
2 電磁誘導方式ワイヤレス給電技術の歴史―EV―
2.1 はじめに
2.2 移動型ワイヤレス給電
2.3 静止型ワイヤレス給電
2.4 おわりに
3 電磁誘導方式ワイヤレス給電技術の歴史―医療応用―
3.1 はじめに
3.2 非接触電力伝送方式
3.2.1 マイクロ波方式
3.2.2 磁界共鳴方式
3.2.3 電界共鳴方式
3.2.4 電磁誘導方式
3.3 医療分野への応用
3.3.1 充電式心臓ペースメーカ
3.3.2 運動再建電気刺激装置
3.3.3 人工心臓
3.4 生体影響の考え方
3.4.1 100 kHzまでの低周波電磁界
3.4.2 100 kHzを超える高周波電磁界
3.4.3 静磁界に対するガイドライン
4 マイクロ波方式ワイヤレス給電の歴史
4.1 マイクロ波方式ワイヤレス給電の歴史
4.2 実証試験を中心としたマイクロ波受電技術
4.3 まとめ
5 ワイヤレス給電,日本と世界はどう動くのか―標準化の最前線から―
5.1 はじめに
5.2 制度化・標準化における課題
5.3 我が国における制度化
5.4 利用周波数の国際協調
5.4.1 これまでの国際協調議論
5.4.2 2016年ITU-R SG1会合の結果
5.4.3 2016年ITU-R SG1会合以降の対応について
5.5 CISPRにおけるEMC規格の標準化状況
5.6 IEC TC106における電波暴露評価,測定方法の検討
5.7 標準規格化の動向
6 Far-Field Wireless Power Transmission For Low Power Applications
6.1 概要―小電力応用のための遠距離ワイヤレス電力伝送―
6.2 Introduction
6.3 Far Field WPT - Rectenna design: recent progress and challenges
6.4 Novel materials and technologies - Use of cork as an enabler of smart environments
6.4.1 Cork permittivity and loss estimation
6.4.2 Design of an UHF RFID tag antenna
6.4.3 RFID tag measurements
6.4.4 Humidity sensors based on cork
6.4.5 Conclusion
6.5 Applications―Bateryless Wireless Sensor Networks
6.6 Applications―Bateryless Remote Control
6.6.1 The proposed system
6.6.2 Simulation and measurement results
6.6.3 The demonstration prototype
7 ばく露評価と国際標準化動向
7.1 はじめに
7.2 評価指標
7.3 ばく露評価手順
7.4 ばく露評価例
7.4.1 電気自動車用ワイヤレス充電
7.4.2 モバイル用ワイヤレス充電
7.5 国際標準化の動向
8 ワイヤレス給電とEMC―ペースメーカを一例に―
第2章 自動車への展開
1 EV用ワイヤレス給電の市場概要と今後の標準化ロードマップ
1.1 はじめに
1.2 ワイヤレス給電の市場概要とロードマップ
1.2.1 EV・PHVロードマップ
1.2.2 世界のEV・PHEV市場の動向
1.2.3 充電インフラとワイヤレス給電の市場
1.3 ワイヤレス給電と法制度と規則
1.3.1 漏えい電磁界の許容値
1.3.2 利用周波数の選定;ITU WRCでの国際的検討
1.3.3 人体安全の側面
1.4 EV向けワイヤレス給電の国際標準化
1.5 今後の展開
2 EVバスへのワイヤレス充電システムの開発動向
2.1 はじめに
2.2 バス用ワイヤレス充電システムの初期の歩み
2.3 EVバス用ワイヤレス充電システムの開発動向
2.3.1 マウンド方式
2.3.2 1次コイル可動方式
2.3.3 2次コイル昇降方式
2.3.4 大ギャップ方式
2.4 おわりに
3 Korean WPT to EV-OLEV
3.1 概要-韓国における電気自動車へのワイヤレス給電技術-OLEV
3.2 Wireless Power Transfer Technology in Korea
3.2.1 Previous and Researches on Wireless Power Transfer
3.3 Vehicular Wireless Power Transfer System
3.3.1 Concept of On-Line Electric Vehicle
3.3.2 Design of OLEV
3.3.3 Electromagnetic Field Issue
3.3.4 Commercialization
3.4 Future Wireless Power Transfer System in Korea
3.4.1 Railway Systems
3.4.2 Unmanned Aerial Vehicle
4 電化道路電気自動車(EVER)
4.1 ワイヤレス3本の矢
4.2 ワイヤレス電力伝送
4.2.1 磁界結合
4.2.2 電界結合
4.2.3 任意構造への理論拡張
4.3 電気自動車
4.3.1 停車中充電から走行中給電へ
4.3.2 車輪経由電力伝送(V-WPT)
4.3.3 右手左手複合系電化道路
4.3.4 遠端全反射を利用した移動負荷整合方式
4.3.5 バッテリーレス電気自動車
5 管内ワイヤレス電力伝送技術の車載応用
5.1 車載ワイヤレス技術の動向と要求
5.2 管内ワイヤレス電力伝送
5.2.1 マイクロ波送電の実用課題
5.2.2 管内ワイヤレス電力伝送
5.2.3 樹脂導波管技術
5.3 ワイヤレス電力・通信伝送
5.3.1 伝送方式
5.3.2 卓上モデルの評価
5.4 今後の展望と課題
第3章 携帯電話他への応用展開
1 AirFuel Allianceの現状と今後の展開
1.1 はじめに
1.2 AirFuel Allianceの組織構成
1.3 AirFuel Inductive WCの活動
1.4 AirFuel Resonance WCの活動
1.5 AirFuel Uncoupled WCの活動について
1.6 AirFuel Infrastructure WC
1.7 最後に
2 Remote Wireless Power Transmission System ‘Cota’
2.1 概要―遠隔ワイヤレス電力伝送システム「Cota」
2.2 Abstract
2.3 Introduction
2.4 Operation Concepts
2.4.1 Tuning techniques
2.4.2 Near Field Retrodirective Arrays
2.4.3 Employing multi-path propagation in Cota’s favor
2.4.4 Near-field vs. Far-field power transfer
2.5 System
2.5.1 The Charger-Client Concept
2.5.2 Beaconing
2.6 Applications
2.6.1 Charging Multiple Devices
2.6.2 Safety
2.7 Conclusion
3 工場内自動搬送台車(AGV)へのワイヤレス給電
3.1 はじめに
3.2 磁界共鳴方式によるワイヤレス給電の電力伝送原理
3.3 AGVの市場について
3.4 AGVのワイヤレス給電化の利点について
3.5 AGVで使用されている蓄電デバイス
3.6 蓄電デバイスとしての電気二重層キャパシタ(EDLC)利用の利点について
3.7 実用例
3.8 まとめ
4 小型MHz帯直流共鳴ワイヤレス給電システムの設計開発
4.1 はじめに
4.2 直流共鳴ワイヤレス給電システムと高周波パワーエレクトロニクス
4.2.1 直流共鳴ワイヤレス給電システムの構成
4.2.2 パワーエレクトロニクスにおけるワイヤレス給電
4.2.3 高周波パワーエレクトロニクス
4.2.4 ワイヤレス給電と絶縁形スイッチング電源
4.2.5 共鳴ワイヤレス給電における先行技術
4.2.6 直流共鳴方式とMITが示した磁界共鳴方式の比較
4.2.7 インピーダンス変換とインピーダンス整合
4.2.8 小型MHz帯ワイヤレス給電
4.2.9 ワイヤレス給電の回路トポロジー
4.3 6.78 MHz帯磁界結合方式直流共鳴ワイヤレス給電システム規格
4.3.1 システムの概要
4.3.2 システム構成
4.3.3 システムの仕様
4.3.4 電力管理仕様
4.4 直流共鳴ワイヤレス給電システムの設計
4.4.1 直流共鳴ワイヤレス給電システムの構成
4.4.2 直流共鳴ワイヤレス給電システムの電力変換動作
4.4.3 共鳴フィールドの周波数領域解析
4.5 共鳴結合回路の統一的設計法(MRA/HRA/FRA手法)
4.5.1 複共振回路解析(MRA)
4.5.2 入力インピーダンスと電圧利得の解析
4.5.3 GaN FETを用いた10 MHz級50 W動作実験
4.5.4 最適ZVS動作とGaN FETを用いた6.78 MHz実験
4.5.5 共鳴フィールドの実証実験
4.6 まとめ
5 電界結合方式を用いた回転体への電力伝送技術
5.1 まえがき
5.2 電界結合方式
5.2.1 電界結合とは
5.2.2 回路方式
5.3 在来技術との比較
5.4 実施例
5.5 まとめ
6 2次元Surface WPT
6.1 はじめに
6.2 表面電磁界結合WPT技術の概要
6.3 電力伝送をする周波数とその共用検討
6.4 Q値の算出方法
6.4.1 送電シートのQ値の算出方法
6.4.2 受電カプラのQ値
6.5 電力供給制御方式
6.6 表層メッシュパターンの検討
6.7 レトロディレクティブ方式による電力伝送
6.8 おわりに
7 宇宙太陽光発電システムを想定したマイクロ波ビーム方向制御技術の研究開発
7.1 はじめに
7.2 宇宙太陽光発電システム(SSPS)の概要
7.3 過去に世界各国で検討された代表的な宇宙太陽光発電システム(SSPS)
7.4 日本において検討されてきた代表的な宇宙太陽光発電システム(SSPS)
7.4.1 発送電一体・テザー型SSPS
7.4.2 反射鏡型SSPS
7.5 宇宙太陽光発電システムの実現に向けて(マイクロ波無線電力伝送地上実証試験の実施)
7.5.1 マイクロ波による送電ビームの方向制御方式
7.5.2 マイクロ波ビーム方向制御装置の開発
7.5.3 マイクロ波ビーム方向制御精度評価試験(屋内試験)
7.5.4 屋外でのマイクロ波による無線電力伝送
7.5.5 無線電力伝送の実用化に向けた技術実証(デモンストレーション)
7.6 おわりに
-

界面活性剤の最新研究・素材開発と活用技術《普及版》
¥4,070
2016年刊「界面活性剤の最新研究・素材開発と活用技術」の普及版。界面活性剤各種の特性に迫る研究事例および特性を活かした用途開発を徹底解説した1冊!
(監修:荒牧賢治)
<a href="http://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=9162"target=”_blank”>この本の紙版「界面活性剤の最新研究・素材開発と活用技術(普及版)」の販売ページはこちら(別サイトが開きます)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は、2016年当時のものを使用しております。
荒牧賢治 横浜国立大学
鯉谷紗智 横浜国立大学
酒井健一 東京理科大学
懸橋理枝 (地独)大阪市立工業研究所
東海直治 (地独)大阪市立工業研究所
遊佐真一 兵庫県立大学
井村知弘 (国研)産業技術総合研究所
佐伯隆 山口大学
吉村倫一 奈良女子大学
鷺坂将伸 弘前大学
中村武嗣 太陽化学(株)
ビスワス・シュヴェンドゥ 味の素(株)
脇田和晃 日油(株)
村上亮輔 住友精化(株)
斉藤大輔 第一工業製薬(株)
田中佳祐 ニッコールグループ(株)コスモステクニカルセンター
高野啓 DIC(株)
川上亘作 (国研)物質・材料研究機構
小川晃弘 三菱化学フーズ
山口俊介 ニッコールグループ(株)コスモステクニカルセンター
坂井隆也 花王(株)
金子行裕 ライオン(株)
中川和典 第一工業製薬(株)
三橋雅人 AGCセイミケミカル(株)
齋藤嘉孝 日華化学(株)
岡田和寿 竹本油脂(株)
久司美登 日本ペイント・オートモーティブコーティングス(株)
-------------------------------------------------------------------------
<<目次>>
【第1編 界面活性剤の最新研究】
第1章 再生可能原料を用いた合成界面活性剤の機能
1 はじめに
2 ひも状ミセルによる水,油の増粘効果
2.1 ひも状ミセル
2.2 アシルアミノ酸エステルによるひも状ミセルの形成
2.3 ショ糖脂肪酸エステルによるひも状ミセルの形成
2.4 逆ひも状ミセル形成による油の増粘
3 モノおよびポリグリセリン脂肪酸エステルの結晶・液晶微粒子による泡沫安定化
4 ポリグリセリン型界面活性剤水溶液系の相挙動とニオソーム形成
5 おわりに
第2章 ジェミニ型両親媒性物質の実用化も意識した研究展開
1 はじめに
2 アミノ酸系ジェミニ型界面活性剤
3 アルキルアミン・アルキルカルボン酸による複合体(擬似ジェミニ型両親媒性物質)
4 ホスホリルコリン類似基を有する両性ジェミニ型両親媒性物質による乳化
5 おわりに
第3章 長鎖アルキルアミンオキシド誘導体の水溶液挙動-水素結合部位導入の効果
1 はじめに
2 ピリジルアミンオキシド型界面活性剤
3 アミドアミンオキシド型界面活性剤
4 おわりに
第4章 pH応答性を有するジブロック共重合体の会合によるミセル形成
1 はじめに
2 PAMPS-PAaUの合成
3 pHに応答した会合挙動
4 pHに応答したゲスト分子の取り込みと放出
5 まとめ
第5章 ペプチドベース界面活性剤の特性とその応用
1 はじめに
2 化学合成・ペプチド界面活性剤
2.1 構造と特徴
2.2 Surfpep22の合成と界面活性
2.3 Surfpep22による脂質ナノディスク形成
3 バイオ合成(発酵法)・ペプチド界面活性剤
3.1 構造と特徴
3.2 サーファクチン(SF)
3.3 ライケンシン(Lch)
3.4 アルスロファクチン(AF)
4 おわりに
第6章 界面活性剤の棒状ミセルによる抵抗低減効果
1 はじめに
2 DR効果を示す界面活性剤
3 DR効果を示す界面活性剤のレオロジー特性
4 DR効果を示す流れの特徴
5 界面活性剤によるDR効果の実用化
5.1 配管抵抗低減剤の商品化
5.2 DR効果による空調設備の省エネルギー
5.3 DR効果の普及
5.4 実用化の問題点
6 おわりに
第7章 トリメリック型界面活性剤の合成・物性・ミセル形成
1 はじめに
2 トリメリック型界面活性剤
3 カチオンタイプの合成例
4 臨界ミセル濃度
5 表面張力
6 水溶液中でのミセル形成
7 おわりに
第8章 超臨界CO2利用技術に向けたCO2-philic界面活性剤の開発
1 超臨界CO2
2 CO2-philic界面活性剤の設計
2.1 分子形状
2.2 親水性-親CO2性バランス(HCB)
2.3 Winsor R理論
2.4 CO2-philic界面活性剤の親CO2基と親水基
3 CO2-philic界面活性剤の開発の歴史
4 界面活性剤/W/CO2混合系の相挙動と物性研究
5 界面活性剤/W/CO2混合系の応用研究
6 おわりに
【第2編 界面活性剤の高機能化】
第9章 ポリグリセリン脂肪酸エステルの特性と高機能化
1 ポリグリセリン脂肪酸エステルの現状
1.1 非イオン性界面活性剤としてのポリグリセリン脂肪酸エステル
1.2 ポリグリセリン
1.3 ポリグリセリンのエステル化
2 ポリグリセリン脂肪酸エステルの高機能化
2.1 ジグリセリン・トリグリセリンのエステル
2.2 組成を変えたポリグリセリンのエステル
2.3 ポリグリセリンアルキルエーテル
3 おわりに
第10章 アシルアミノ酸エステル系両親媒性油剤
1 はじめに
2 化粧品用油剤とは
3 アシルアミノ酸エステル系油剤とは
3.1 油剤骨格にアミノ酸があることの意義
4 油剤の両親媒性とは
5 アシルアミノ酸エステル系両親媒性油剤
5.1 アシルグルタミン酸誘導体
5.2 アシルサルコシン誘導体
5.3 アシル-N-メチルβアラニン誘導体
6 おわりに
第11章 長鎖PEGを有する非イオン性活性剤
1 はじめに
2 ラウリン酸PEG-80ソルビタン(PSL)の泡質改善効果
3 ポリオキシエチレンアルキルエーテル(PAE)を用いた泡物性評価
3.1 使用したPAEとそれらの物性
3.2 泡弾性のひずみ依存性測定
3.3 泡の粘弾性測定
3.4 IRによる泡膜測定
4 泡質改善メカニズム関する考察
5 おわりに
第12章 化学架橋を工夫したアクリル酸アルキルコポリマー
1 はじめに
2 一般的なアクリル酸アルキルコポリマーの増粘,乳化のメカニズム
2.1 水溶液の増粘機構
2.2 耐塩性
2.3 乳化のメカニズム
3 化学架橋を工夫したアクリル酸アルキルコポリマー『アクペックSER』
3.1 アクペックSERとは
3.2 アクペックSER水溶液の増粘挙動
3.3 アクペックSERの耐塩性
3.4 乳化能力
3.5 顔料の分散
4 アクペックSERと界面活性剤の相乗効果
4.1 高分子界面活性剤と低分子界面活性剤の相互作用
4.2 アクペックSERとアニオン系界面活性剤の相互作用
4.3 アクペックSERと両性界面活性剤の相互作用
4.4 アクペックSERとノニオン系界面活性剤の相互作用
5 おわりに
第13章 低泡性かつ界面活性能に優れた界面活性剤
1 低泡性かつ界面活性能に優れた界面活性剤が要求される背景
2 泡立ちのメカニズム
3 泡立ちと界面活性剤構造の相関
4 低泡性かつ界面活性能に優れたノイゲン(R)LF-Xシリーズ
4.1 ノイゲンLF-Xシリーズ構造の特徴
5 おわりに
第14章 高純度モノアルキルリン酸塩の会合挙動
1 はじめに
2 直鎖型モノセチルリン酸(NIKKOLピュアフォスα)
2.1 αゲルとは
2.2 直鎖型モノセチルリン酸(NIKKOLピュアフォスα)の自己組織化挙動
3 β分岐型モノヘキサデシルリン酸アルギニン(NIKKOLピュアフォスLC)の自己組織化挙動
4 おわりに
第15章 熱分解型フッ素系界面活性剤の開発
1 はじめに
2 熱分解型フッ素系界面活性剤
2.1 レべリング性とリコート性の両立のための設計コンセプト
2.2 当社のフッ素系活性剤“メガファック”シリーズにおけるDS-21の位置づけ
2.3 メガファックDS-21の性状および基本物性
2.4 メガファックDS-21のレベリング性能
2.5 メガファックDS-21の熱分解挙動
2.6 塗膜表面の評価
2.7 まとめ
3 熱分解型フッ素系界面活性剤の応用事例
3.1 ディスプレイ材料用各種レジストへの応用
3.2 低誘電材料として用いるPTFEの分散剤
3.3 機能性表面の創生
4 今後の展望
【第3編 界面活性剤の応用分野】
第16章 医薬品分野における界面活性剤利用技術
1 医薬品用途に利用される界面活性剤
2 経口剤への利用
3 注射剤への利用
4 その他の投与経路への利用
5 リン脂質の利用
6 おわりに
第17章 食品用界面活性剤
1 はじめに
2 乳化剤について
3 乳化剤の種類と性質
3.1 グリセリン脂肪酸エステル
3.2 レシチン
3.3 ショ糖脂肪酸エステル
3.4 その他の乳化剤
4 乳化剤の機能と食品への応用
4.1 界面活性能に基づく機能
4.2 油脂との相互作用
4.3 澱粉との相互作用
4.4 タンパク質との相互作用
5 食品における乳化剤の使い方
6 おわりに
第18章 化粧品用の界面活性剤
1 はじめに
2 化粧品における界面化学
3 化粧品に使用される非イオン界面活性剤
3.1 ポリオキシエチレン脂肪酸
3.2 ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル
3.3 ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油
3.4 ポリオキシエチレンソルビトールテトラ脂肪酸エステル
3.5 グリセリン脂肪酸エステル
3.6 ソルビタン脂肪酸エステル
3.7 ポリグリセリン脂肪酸エステル
3.8 ショ糖脂肪酸エステル
3.9 アルキルポリグルコシド
4 おわりに
第19章 身体洗浄用界面活性剤
1 はじめに~身体用洗浄剤と界面活性剤~
2 身体洗浄用界面活性剤の使い方
2.1 第一界面活性剤
2.2 補助界面活性剤
3 固形石けん
3.1 固形石けんの第一界面活性剤
3.1.1 脂肪酸石けん
3.1.2 脂肪酸イセチオン酸エステルNa塩
3.1.3 アシル化グルタミン酸塩
3.2 固形石けんの補助界面活性剤
3.2.1 長鎖アルキルアルコール、長鎖脂肪酸
3.2.2 脂肪酸アミドプロピルベタイン
4 液体全身洗浄料(ボディーシャンプー)・洗顔料
4.1 液体全身洗浄料・洗顔料の第一界面活性剤
4.1.1 脂肪酸石けん
4.1.2 ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸塩
4.1.3 モノアルキルリン酸塩
4.1.4 アシル化グルタミン酸塩
4.1.5 ポリオキシエチレンアルキルエーテルカルボン酸塩
4.2 液体全身洗浄料・洗顔料の補助界面活性剤
4.2.1 長鎖アルコール・長鎖脂肪酸
4.2.2 脂肪酸アミドプロピルジメチルベタイン
4.2.3 脂肪酸アルカノールアミド
5 シャンプー
5.1 シャンプーの第一界面活性剤
5.1.1 アルキル硫酸塩
5.1.2 ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸塩
5.2 シャンプーに用いられる補助界面活性剤
5.2.1 脂肪酸アミドプロピルジメチルベタイン
5.2.2 脂肪酸アルカノールアミド
5.2.3 ポリオキシエチレンアルキルエーテル
5.2.4 アルキルポリグルコシド
6 ヘアコンディショナー
6.1 ヘアコンディショナーの第一界面活性剤
6.1.1 アルキルジメチルアミン酸塩、アルキルトリメチルアンモニウム塩
6.1.2 脂肪酸アミドプロピルジメチルアミン酸塩
6.2 ヘアコンディショナーの補助界面活性剤
6.2.1 長鎖アルコール
7 おわりに
第20章 快適で環境にやさしい洗剤のための界面活性剤
1 はじめに
2 台所用洗浄剤における効率洗浄の実現
3 衣料用液体洗剤における植物由来の界面活性剤の活用
3.1 α-スルホ脂肪酸メチルエステル塩
3.2 脂肪酸メチルエステルエトキシレート
4 おわりに
第21章 工業用洗浄剤への界面活性剤応用技術
1 はじめに
2 界面活性剤の分類と性能について
3 洗浄のメカニズムと界面活性剤の役割について
3.1 油性汚れの除去機構
3.2 固体微粒子汚れの除去機構
3.3 留意すべきポイント(再付着防止,泡立ち,すすぎ)
4 おわりに
第22章 樹脂添加用フッ素系界面活性剤
1 はじめに
2 ヤングの式
3 樹脂表面のエネルギー
4 パーフルオロアルキル化合物の特徴
4.1 パーフルオロアルキル基
4.2 パーフルオロアルキル構造の合成
4.3 パーフルオロアルキル基の表面エネルギー
5 樹脂への適用
5.1 撥水撥油性の付与
5.2 親水性の付与
6 おわりに
第23章 繊維用界面活性剤と界面化学
1 はじめに
1.1 繊維加工業界における界面活性剤の用途
2 精練剤
3 ポリエステル用分散均染剤
4 オリゴマー除去剤
5 綿用フィックス剤
6 難燃剤
6.1 カーテンの耐久難燃加工
7 撥水剤
8 耐久吸水加工剤
9 おわりに
第24章 コンクリート用界面活性剤
1 はじめに
2 混和剤の減水性
2.1 空気連行による減水効果
2.2 静電反発力によるセメント分散効果
2.3 立体反発力によるセメント分散効果
3 混和剤への機能付与
3.1 増粘させる
3.2 乾燥収縮を低減させる
3.3 CO2排出削減への取組み
4 おわりに
第25章 塗料用界面活性剤
1 はじめに
2 塗料に用いられる界面活性剤の種類
2.1 消泡剤
2.2 リべリング剤
2.3 ハジキ防止剤
2.4 増粘剤・粘性制御剤
2.5 色別れ防止剤
3 顔料分散剤
3.1 顔料分散剤とは
3.2 分散剤の構造とはたらき
3.2.1 ぬれ・吸着・安定化と分散剤の分子構造
3.3 分散剤の適用事例
3.3.1 非水系の分散
3.3.2 水系の分散
3.3.3 水系における適当な疎水基の選択
3.3.4 構造制御による高分子分散剤の高機能化
4 高分子乳化剤
-

おいしさの科学的評価・測定法と応用展開《普及版》
¥3,520
2016年刊「おいしさの科学的評価・測定法と応用展開」の普及版。おいしさの科学的な評価・測定を生かした商品づくりを食品メーカー担当者らが解説した1冊!
(監修:阿部啓子・石丸喜朗)
<a href="http://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=9163"target=”_blank”>この本の紙版「おいしさの科学的評価・測定法と応用展開(普及版)」の販売ページはこちら(別サイトが開きます)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は、2016年当時のものを使用しております。
阿部啓子 東京大学
石丸喜朗 東京大学
三坂巧 東京大学
戸田安香 キッコーマン(株)
鈴木-橋戸南美 京都大学
今井啓雄 京都大学
山本隆 畿央大学;大阪大学
中島健一朗 東京大学
成川真隆 東京大学
吉田竜介 九州大学
二ノ宮裕三 九州大学
永井俊匡 高崎健康福祉大学
朝倉富子 東京大学
緑川景子 東京大学
大池秀明 (国研)農業・食品産業技術総合研究機構
鈴木千尋 日本製粉(株)
伊藤圭祐 静岡県立大学
都甲潔 九州大学
上田玲子 東京大学
伏木亨 龍谷大学
山口裕章 太陽化学(株)
福田惠温 (株)林原
桑垣傳美 キッコーマン食品(株)
山下秀行 (株)樋口松之助商店
若林英行 キリン(株)
山本直之 アサヒグループホールディングス
-------------------------------------------------------------------------
<<目次>>
【第Ⅰ編 おいしさを知る】
第1章 味覚受容の分子基盤
1 はじめに
2 甘味受容体
3 うま味受容体
4 脊椎動物における甘味・うま味受容体の分子進化
5 苦味受容体
6 酸味受容体
7 塩味受容体
8 味覚コーディング
第2章 培養細胞を用いた食味評価系
1 はじめに
2 口腔内に存在する味のセンサー
3 Gタンパク質共役型受容体の機能解析
4 培養細胞を用いた味覚受容体の機能解析
5 ヒト味覚計測細胞の作出
6 ヒト味覚計測細胞の応用利用
7 食味評価に向けた課題
8 最後に
第3章 霊長類の味覚
1 はじめに
2 霊長類の味覚
3 旨味・甘味受容体の遺伝的および機能的多様性
4 霊長類種間および種内における苦味受容体の遺伝的・機能的多様性
5 味覚受容体遺伝子の発現
6 霊長類における味覚研究の展望
第4章 味覚とおいしさの脳内情報処理
1 おいしさとは
2 脳内味覚伝導路
3 味の質の情報処理
4 おいしさの脳機序
4.1 神経回路によるおいしさ
4.2 脳内物質によるおいしさ
5 おいしさと脳活動
6 おいしさの学習・記憶
第5章 摂食行動の脳内情報処理
1 はじめに
2 摂食の目的: 恒常性の維持か嗜好性か?
2.1 恒常性維持のための摂食
2.2 嗜好性の摂食
3 味や栄養は脳内にどのようにして伝わるのか?
3.1 味の感知と栄養の感知
3.2 味・栄養の感知細胞から延髄へ
3.3 延髄からより高次の脳部位へ
3.4 味と栄養の情報の統合
4 恒常性維持のための摂食を制御する脳部位
4.1 視床下部
4.1.1 視床下部弓状核
4.1.2 AgRP神経の機能と役割
4.1.3 視床下部室傍核
4.1.4 視床下部外側野
5 生体恒常性維持のための生体調節機構
5.1 摂食リズム
5.2 食物選択行動
6 嗜好性の摂食を制御する仕組み
6.1 本能行動としての摂食
6.2 神経調節
6.2.1 ドーパミン
6.2.2 セロトニン
7 摂食を抑制する仕組み
8 健康や生理状態が摂食行動に与える影響
9 今後の展望
10 おわりに
第6章 生理状態や食経験に起因する味嗜好性の変化
1 はじめに
2 本能的な味の嗜好性
3 食経験による嗜好性の変化
4 食経験による脳内分子の発現変動
5 母親から子に伝えられる味の記憶
6 栄養状態に起因した味嗜好性変化
7 加齢による味感受性の変化
8 おわりに
第7章 レプチンによる甘味感受性調節機構
1 はじめに
2 レプチン
3 レプチンと味覚感受性
4 レプチンによる甘味抑制機構
5 レプチンによる甘味抑制と肥満
6 ヒト味覚感受性とレプチンの関係
7 腸管内分泌細胞モデルにおけるレプチンの効果
8 おわりに
第8章 タンパク質・脂質・炭水化物のバランス変化による代謝変化
1 タンパク質・脂質・炭水化物のバランス変化
2 バランス目標設定とメカニズム解明それぞれの研究手法
3 動物実験の食餌設計
4 実験デザインと生化学的解析
5 肝臓のトランスクリプトーム解析
6 脂肪組織のトランスクリプトーム解析
7 トランスクリプトームのホメオスタシスに与える影響
8 まとめ
第9章 ゲノミクスを用いた食味関連遺伝子の探索―追肥によるコメの遺伝子発現変化から―
1 はじめに
2 コメの窒素施肥と種子貯蔵物質
2.1 C/Nバランスと貯蔵物質
2.2 追肥と食味
2.3 登熟期種子のゲノミクス解析
2.4 貯蔵タンパク質の変化
2.5 多糖類代謝への影響
3 おわりに
第10章 食品と時間栄養学
1 はじめに
2 体内時計と食欲
3 体内時計の仕組みと時刻因子への同調
4 消化吸収と時計
5 腸内細菌と時計
6 エネルギー代謝と時計
7 高脂肪食による肥満と時計
8 体内時計を動かす食品
9 食べる時刻と体重変化
10 時計遺伝子のタイプと肥満
11 おわりに
第11章 味成分と結合するペプチドの網羅的探索と応用
1 はじめに
2 苦味マスキング剤
3 ペプチドの機能とアレイ解析
4 茶殻加水分解物の苦味マスキング効果の予備試験
5 EGCG結合ペプチドの網羅的探索
6 EGCG結合におけるアミノ酸残基の機能解析
7 苦味受容体発現細胞を用いた苦味マスキング効果の解析
8 タンゲレチン結合ペプチドの網羅的探索と苦味マスキング効果の解析
9 味の分子設計へのペプチドアレイの応用可能性
【第Ⅱ編 おいしさを引き出す】
第12章 味覚センサの開発
1 はじめに
2 味覚センサの原理と測定手順
3 基本味応答
4 苦味の抑制効果の数値化
5 食品の味
6 今後の展望
第13章 官能評価
1 はじめに
2 官能評価概論
2.1 官能評価とは
2.2 官能評価の特徴
2.3 心理物理学的測定
2.3.1 心理物理学的定数
2.3.2 心理物理学的測定法および解析法
2.3.3 心理物理学的法則(Law of Psychophysics)
2.4 官能評価の影響要因
2.5 評価・調査方法とその条件
2.5.1 評価に影響を与える要因のリストアップ
2.5.2 条件の標準化
2.5.3 統計的手法の採用とパネルの育成
3 官能評価各論
3.1 官能評価の形式
3.2 評価者 (panel or assessor)
3.3 評価用語
3.4 評価試料
3.5 官能評価設備と環境
3.6 評価尺度
3.7 目的別の官能評価手法とその解析法
第14章 「こく」とその研究
1 はじめに
2 こくの研究の進展
3 こくの定義
4 栄養素摂取を超えた感覚も
5 「こく味」成分開発の展開
6 こくの新領域:栄養素の連想、あるいは無関係に見える匂いが、こくを増強する事例
【第Ⅲ編 新しいおいしさの開発】
第15章 カスタードクリームの成分分布とおいしさ
1 はじめに
2 同一配合処方による成分分散状態の違いとおいしさ
2.1 混ぜ方の違いがおいしさに及ぼす影響
2.2 IRイメージング装置を用いた成分分布の可視化と官能評価
2.3 せん断速度依存性粘度分析
3 市販品カスタードクリームのおいしさ
3.1 市販品カスタードクリームの成分分布
3.2 市販品カスタードクリームのせん断速度依存性粘度分析
3.3 市販品カスタードクリームの動的粘弾性
4 まとめ
第16章 おいしさに関わるトレハロース
1 はじめに
2 トレハロースのおいしさへの寄与
2.1 デンプン老化抑制
2.2 タンパク質変性抑制効果
2.3 保水性
2.4 冷凍時の組織保護(氷結晶成長抑制)
2.5 矯味・矯臭作用、風味改善効果
2.6 結晶化、ガラス化の応用
3 トレハロースの構造と機能性
第17章 開栓後も鮮度を保持できるしょうゆ容器
1 はじめに
2 これまでのしょうゆ容器
3 鮮度を保持するための容器
3.1 基本的機能・構造
3.2 パウチタイプの鮮度保持容器
3.3 ボトルタイプの鮮度保持容器
3.3.1 基本構造
3.3.2 200mlスクイズボトル(卓上ユース)
3.3.3 キッチンユースボトルの開発 (450ml スクイズボトル)
4 現在の課題と今後の展望
第18章 塩糀
1 はじめに
2 塩糀とは
3 製造方法
3.1 原材料
3.2 糀の製造方法
3.3 仕込み配合
3.4 発酵温度と時間
4 塩糀の成分
4.1 発酵温度、時間、食塩が塩糀中のおいしさに及ぼす影響
4.2 使用する麹菌株
4.3 塩糀中の酵素
5 塩糀の保存
6 醤油仕込み糀
7 最後に
第19章 キリン メッツ コーラ
1 はじめに
2 トクホの市場
3 メッツコーラの開発背景
4 コーラ飲料の特性
5 コーラのおいしさの科学
6 トクホのおいしさ
7 メッツコーラの市場受容性
8 機能性食品のルール
第20章 血圧降下ペプチドをおいしく摂る
1 はじめに
2 乳酸菌発酵による血圧降下ペプチド産生
3 L.helveticusにおけるVPPとIPPの加工
4 酵素法による効率的生産
5 味噌の発酵による降圧ペプチド生産
6 チーズ発酵による降圧ペプチド生産
7 おわりに
-

機能性顔料の開発と応用《普及版》
¥5,500
2016年刊「機能性顔料の開発と応用」の普及版。主要な無機顔料、有機顔料、複合酸化物顔料の開発動向および塗料、インキ、プラスチックなどの着色顔料の応用を網羅解説した1冊!
(編集:シーエムシー出版編集部)
<a href="http://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=9120"target=”_blank”>この本の紙版「機能性顔料の開発と応用(普及版)」の販売ページはこちら(別サイトが開きます)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は、2016年当時のものを使用しております。
清都育郎 DIC㈱
三輪剛之 東洋インキ㈱
尾坂 格 理化学研究所
瀧宮和男 理化学研究所
山本泰生 ハクスイテック㈱
山根健一 大日精化工業㈱
森光太郎 東洋アルミニウム㈱
真田和俊 戸田工業㈱
鈴木龍太 メルク㈱
堂下和宏 日本板硝子㈱
田中雅晃 DIC㈱
岡本久男 大日精化工業㈱
山﨑康寛 オリヱント化学工業㈱
船倉省二 DIC㈱
杉山和弘 DIC㈱
石間洋輔 ㈱ADEKA
宮川有司 シンロイヒ㈱
金原正幸 ㈱コロイダル・インク
大石知司 芝浦工業大学
額田克己 富士ゼロックス㈱
大沢正人 ㈱アルバック
橋本夏樹 ㈱アルバック
鳶島真一 群馬大学
岸 潤一郎 BASFジャパン㈱
野々村美宗 山形大学
新井啓哲 東海カーボン㈱
寺田悠哉 東京インキ㈱
濱﨑智浩 神戸天然物化学㈱
前田 亮 神戸天然物化学㈱
中戸晃之 九州工業大学
青木康充 ㈱ネモト・ルミマテリアル
池田裕志 キクチカラー㈱
仁井本順治 中国塗料㈱
川邉和也 東京インキ㈱
-------------------------------------------------------------------------
<<目次>>
【総論編】
第1章 顔料分散の基礎理論と分散向上手法
1 はじめに
2 顔料分散の各プロセスに関する基礎理論
2.1 濡れ
2.2 微細化
2.3 分散安定化
3 顔料の表面処理
3.1 ロジン処理
3.2 界面活性剤処理
3.3 顔料誘導体処理
3.4 ポリマー処理
4 おわりに
第2章 オフセットインキにおける顔料分散
1 はじめに
2 オフセット印刷について
3 オフセットインキについて
3.1 オフセットインキの組成
3.2 オフセットインキの製造方法
4 オフセットインキの分散設備
4.1 ニーダー
4.2 サンドミル(ビーズミル)
4.3 3本ロール
5 顔料の特徴
5.1 アゾ顔料
5.2 フタロシアニンブルー
5.3 カーボンブラック
6 分散の基礎理論とオフセットインキにおける分散の具体例
6.1 基礎理論
6.2 オフセットインキにおける具体例
7 オフセットインキ生産におけるベース状態と分散性
7.1 練肉ベース
7.2 練肉ベースの粘度と分散性
8 顔料分散性と印刷への影響
8.1 光沢
8.2 着肉不良
8.3 インキ締まり
9 オフセットインキの分散性評価方法
9.1 グラインドメーター
9.2 ろ紙クロマト法
9.3 粒度分布測定
10 まとめ
第3章 塗布プロセス用有機半導体材料
1 はじめに
2 低分子系材料
3 高分子系材料
4 まとめ
【無機顔料編】
第4章 酸化亜鉛ナノパウダ
1 はじめに
2 酸化亜鉛の結晶構造と物性
3 酸化亜鉛の主な品種と用途
4 導電性酸化亜鉛ナノパウダの特徴
5 導電性酸化亜鉛ナノパウダの分散と塗膜
6 塗膜の分光特性
7 蒸着膜の分光特性
8 おわりに
第5章 複合酸化物顔料
1 はじめに
2 種類及び性質
2.1 複合酸化物顔料の特徴
2.2 複合酸化物顔料の種類
3 複合酸化物顔料の製法
3.1 乾式法
3.2 湿式法
4 微粒子顔料
5 遮熱顔料
6 赤外線遮蔽顔料
7 おわりに
第6章 金属粉顔料
1 金属粉顔料の種類と用途
2 アルミニウム顔料
2.1 アルミニウム顔料の製法
2.2 アルミニウム顔料の性質
2.3 アルミニウム顔料の光学的性質とその評価方法
2.4 アルミニウム顔料の表面処理
2.5 その他の用途
3 ブロンズ粉顔料
4 ステンレス鋼フレーク
5 亜鉛末
6 導電性フィラーとしての金属粉顔料
6.1 銀
6.2 銅
6.3 ニッケル
6.4 銀-銅系複合材料
7 3Dプリンター用金属粉
8 金属ナノ粒子
第7章 無機・複合無機顔料
1 概要
2 緒言
3 高反射塗料の実施事例
3.1 当社大竹事業所事務棟屋根の遮熱塗装事例
3.2 高反射塗料の反射特性
3.3 空調電力用の低減率
4 太陽光高反射率の理論と日射反射率
4.1 太陽光放射スペクトル
4.2 JIS K 5602 の制定
4.3 高反射塗料と低反射塗料の比較
4.4 有彩色顔料
5 市販黒色系顔料
6 当社黒顔料の開発
6.1 環境配慮顔料
6.2 実験方法
6.3 結果及び考察
7 高反射顔料の開発の方向性
8 最後に
第8章 パール顔料
1 パール顔料とは
2 パール顔料の構造と意匠性効果
3 パール顔料の種類
4 パール顔料の用途
第9章 薄片状ガラス顔料─内包型と被覆型
1 はじめに
2 内包型薄片状顔料「マイクログラス(R)アイナフレックス(R)」
2.1 溶融法以外の薄片状粒子(フレーク状粒子)作製技術
2.2 新規フレーク作製技術(拡散制御凝集法:FDC 法)
2.3 FDC法で作製した薄片状粒子の応用例
2.4 まとめ
3 被覆型薄片状顔料「マイクログラス(R)メタシャイン(R)」
3.1 マイクログラス(R)メタシャイン(R)とは
3.2 マイクログラス(R)メタシャイン(R)の特徴
3.3 マイクログラス(R)メタシャイン(R)のシリーズ
3.4 まとめ
第10章 アゾ系顔料
1 はじめに
2 合成反応
3 溶性アゾ顔料
4 不溶性アゾ顔料
5 縮合アゾ顔料
6 アゾ系顔料の最近の研究開発動向
7 おわりに
第11章 アゾメチンアゾ系遮熱顔料
1 はじめに
2 AMA顔料について
3 AMAブラックの合成方法
4 AMAブラックの顔料化(結晶変態)
5 AMAブラックの特徴
6 おわりに
第12章 機能性フタロシアニン
1 はじめに
2 触媒機能を利用するフタロシアニン化合物
2.1 人工酸化酵素的消臭機構
2.2 天然高分子キチン / キトサンとの複合化ならびに天然高分子繊維の機能化
2.3 高耐久性固体高分子電解質膜への応用
3 電荷発生材料に利用するフタロシアニン化合物
3.1 チタニルフタロシアニンと結晶変態
3.2 μ-オキソ架橋型金属(Ⅲ)フタロシアニン二量体
4 機能性光学薄膜に利用するフタロシアニン化合物
4.1 μ-オキソ架橋型サブフタロシアニン二量体
4.2 リン誘導体軸置換サブフタロシアニン
5 有機薄膜太陽電池に利用するフタロシアニン化合物
5.1 機能分離型積層型素子の増感機能
5.2 フラーレン / フタロシアニン二量体のバルクヘテロ接合型太陽電池
5.3 PCBM:P3HT バルクヘテロ構造へのフタロシアニン誘導体の添加
6 おわりに
第13章 縮合多環系顔料
1 はじめに
2 新規構造顔料の開発動向
3 固溶体顔料の開発動向
4 蛍光材料への開発動向
5 光導電・半導体材料への開発動向
6 おわりに
第14章 有機系紫外線吸収剤
1 はじめに
2 紫外線吸収剤の光安定化機構について
2.1 紫外線吸収剤に必要な性質
2.2 分子内水素結合をもつ紫外線吸収剤の紫外線無害化機構
3 各種紫外線吸収剤の特徴と構造
3.1 ベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤
3.2 トリアジン系紫外線吸収剤
3.3 ベンゾフェノン系紫外線吸収剤
3.4 その他の紫外線吸収剤
4 おわりに
第15章 有機蛍光顔料
1 有機蛍光顔料の動向
2 化学物質規制状況
2.1 EN-71
2.2 GOTS
2.3 OECO-TEX
2.4 PAHs
2.5 各国インベントリー
3 有機蛍光顔料の特徴
4 有機蛍光顔料の組成
4.1 基体樹脂
4.2 蛍光染料
4.3 有機蛍光顔料の製法
5 有機蛍光顔料の用途展開
6 有機蛍光塗料の用途展開
6.1 屋外・車輌用有機蛍光塗料
6.2 ヘリサイン工程短縮有機蛍光塗料
7 おわりに
【応用・分散技術編】
第16章 超高純度金属ナノインク
1 はじめに
2 金属ナノインクの開発
3 π接合金属ナノ粒子インクの特徴
4 室温PE 技術
5 その他の期待される応用
6 おわりに
第17章 ラテント顔料を用いた有機無機ハイブリッドカラーフィルタ膜の作製─光酸発生剤とマイクロ波照射を用いた簡便なカラーフィルタ膜パターニング法─
1 はじめに
2 有機無機ハイブリッドポリマーと光酸発生剤を用いた微細パターニング形成法
3 有機無機ハイブリッドポリマーのNMR,IRスペクトル
4 光酸発生剤を用いたゾルゲル法によるPMPTMS膜の光パターニング
5 PMPTMS膜の性質
6 ラテント顔料含有PMPTMS膜の形成
7 おわりに
第18章 レーザープリンター用有機光半導体
1 はじめに
2 デジタル化・カラー化と感光体
3 カラー用OPCのCGMに対する要求特性とフタロシアニン顔料
3.1 TiOPc
3.2 GaPc類
4 電荷発生と結晶構造
5 フタロシアニン顔料の電荷発生機構
6 CGMとしての実用化,塗布液設計
7 おわりに
第19章 インクジェット用導電性ナノ粒子インクの特性
1 はじめに
2 導電膜形成に用いる金属ナノ粒子
3 金属ナノ粒子の作製法
4 ナノメタルインクの焼結メカニズム
5 インクジェットプロセス
6 ナノメタルインクの特性
6.1 Auナノメタルインク
6.2 Agナノメタルインク
6.3 低温焼成型Agナノメタルインク
6.4 ITOナノメタルインク
7 スーパーインクジェット(SIJ)印刷
8 おわりに
第20章 リチウム電池用機能性分散体
1 リチウムイオン電池の特徴と用途
2 リチウム電池用LiCoO2正極の金属酸化物による表面修飾
3 リチウムイオン電池用電極作製法とバインダ
4 まとめ
第21章 医薬品業界における固体分散体技術の概要とその応用
1 緒言
2 可溶化技術の概要
3 固体分散体とは
4 固体分散体の調製方法
4.1 噴霧乾燥法(Spray-Drying method:SD法)
4.2 加熱溶融押出法(Hot-Melt Extrusion method:HME法)
5 担体ポリマーの選択
6 固体分散体の利用例
6.1 カレトラ(R)ソフトカプセルとカレトラ(R)配合錠の違い
7 まとめ
第22章 化粧品における顔料分散
1 はじめに
2 化粧品にはどんな顔料が配合されているのか?
3 顔料の表面処理と顔料分散
4 メイク落としにおける顔料分散
5 おわりに
第23章 水性自己分散型カーボンブラック
1 緒言
2 CBについて
3 CBの基本特性
3.1 一次粒子の微細構造
3.2 本粒子径(一次粒子)
3.3 比表面積
3.4 ストラクチャー
3.5 アグリゲート(凝集体)
3.6 化学組成と表面官能基
4 水性自己分散型カーボンブラック
4.1 酸化反応
4.2 有機化反応
4.3 CB品種による影響
4.4 末端官能基の影響
4.5 中和剤の影響
5 結言
第24章 プラスチックにおける顔料分散
1 はじめに
2 プラスチックの種類
3 プラスチックでの使用顔料と分散
4 プラスチック用着色剤の種類と特徴
4.1 ドライカラー
4.2 マスターバッチ
5 顔料分散機の種類と特徴
5.1 3本ロールミル
5.2 ニーダー
5.3 二軸押出機
6 プラスチックにおける顔料分散
6.1 プラスチックにおける顔料の濡れ
6.2 プラスチックにおける顔料の解砕
7 プラスチック形状による顔料分散性比較
8 着色剤の種類による顔料分散性比較
9 おわりに
第25章 カーボンナノチューブ分散体の製造技術およびUV 硬化インキへの応用
1 はじめに
2 CNTの種類と基本特性
3 CNTの選定
4 CNTの分散
5 当社の分散技術への取り組み
6 CNTによる導電性UV硬化インキの開発動向
7 CNT-UV硬化インキの特徴
8 導電性UVインキの厚膜硬化
9 CNT-UVインキの将来性と課題
10 おわりに
第26章 無機ナノシート分散体の液晶形成
1 はじめに─無機ナノシートとそのコロイド分散体─
2 ナノシート液晶の形成機構
3 無機ナノシート液晶の調製
3.1 ナノシート分散体の調製
3.2 ナノシート分散体の液晶化
4 無機ナノシート液晶の構造
5 無機ナノシート液晶の配向制御
6 おわりに
第27章 蓄光性蛍光体
1 はじめに
2 硫化物系蛍光体
2.1 ZnS:Cu, Cl蓄光性蛍光体
2.2 CaS:Eu, Tm
3 アルミン酸塩系蓄光性蛍光体
3.1 SrAl2O4:Eu, Dy蓄光性蛍光体
3.2 Sr4Al14O25:Eu, Dy蓄光性蛍光体
3.3 CaAl2O4:Eu, Nd 蓄光性蛍光体
4 ケイ酸塩系蓄光性蛍光体
4.1 Sr2MgSi2O7:Eu, Dy蓄光性蛍光体
5 酸硫化物系蓄光性蛍光体
5.1 Y2O2S:Eu, Mg, Ti蓄光性蛍光体
6 その他の蓄光性蛍光体
7 おわりに
第28章 重金属フリー防錆顔料
1 はじめに
2 重金属フリー防錆顔料の概要及び種類
2.1 リン酸系防錆顔料
3 主な適用法規
4 おわりに
第29章 船舶防汚塗料用機能性顔料
1 はじめに
2 船舶防汚塗料とは
3 防汚塗料の歴史と防汚顔料の推移
4 無機系防汚顔料
5 有機系防汚顔料
6 防汚顔料の防汚機構
7 その他の機能性顔料(物性改質顔料)
8 防汚塗料用機能性顔料の今後の展開
第30章 グラビアインキにおける顔料分散
1 はじめに
2 グラビア印刷及びグラビアインキ
2.1 包装用グラビアインキ
2.2 グラビア印刷及び後加工
2.3 包装用途でのグラビアインキの構成
2.4 グラビアインキの種類
2.5 グラビアインキの組成
2.6 グラビアインキの顔料
2.7 グラビアインキの樹脂
2.8 グラビアインキの溶剤
2.9 グラビアインキの分散剤
2.10 グラビアインキの添加剤
3 グラビアインキの製造~顔料分散の観点から
3.1 濡れ(プレミックス工程)
3.2 粉砕(分散工程)
3.3 安定化(レットダウン工程)
3.4 品質管理及び充填工程
4 分散及び吸着試験
4.1 微粒子化
4.2 酸塩基の概念
4.3 分散剤の最適添加量
4.4 顔料の吸着とフィルム密着性
4.5 まとめ
5 最後に
-

脳機能改善食品素材の開発と応用《普及版》
¥4,290
2016年刊「脳機能改善食品素材の開発と応用」の普及版。健康食品市場で注目を集めている脳機能改善をサポートする食品素材について「リン脂質・脂肪酸」、「アミノ酸・ペプチド」、「植物エキス」と素材種類別に解説した1冊!
(監修:太田明一)
<a href="http://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=9121"target=”_blank”>この本の紙版「脳機能改善食品素材の開発と応用(普及版)」の販売ページはこちら(別サイトが開きます)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は、2016年当時のものを使用しております。
太田明一 元キリンホールディングス(株)
茂木正樹 愛媛大学
家森幸男 武庫川女子大学
武田英二 徳島健祥会福祉専門学校
佐藤美智子 徳島健祥会福祉専門学校
池住祐哉 徳島健祥会福祉専門学校
幾田一哉 (株)J-オイルミルズ
佐藤俊郎 (株)J-オイルミルズ
加藤豪人 (株)ヤクルト本社
日比野英彦 日本脂質栄養学会
矢澤一良 早稲田大学
水野慎一郎 DSMニュートリションジャパン(株)
田平武 順天堂大学大学院
青山敏明 日清オイリオグループ(株)
加藤智彦 エイチ・ホルスタイン(株)
山田貴史 中部大学
日暮聡志 雪印メグミルク(株)
春田裕子 雪印メグミルク(株)
横越英彦 中部大学;静岡県立大学
衛藤英男 静岡大学
勝又美紀 ILS(株)
高岡晋作 (株)日本生物.科学研究所
前渕元宏 不二製油グループ本社(株)
中村裕道 タマ生化学(株)
大泉康 静岡県立大学
木村純子 静岡県立大学
橋本博之 築野食品工業(株)
澤田一恵 築野食品工業(株)
松木翠 築野食品工業(株)
中村智子 (株)サン・メディカ
栗山雄司 (株)アンチエイジング・プロ;順天堂大学
市川剛士 サンブライト(株)
瀬戸美沙枝 サンブライト(株)
佐藤充克 山梨大学
柳町明敏 (株)エイワイシー
倉重(岩崎)恵子 (株)明治フードマテリア
大澤俊彦 愛知学院大学
渡邉知倫 (株)ファンケル
池本一人 三菱瓦斯化学(株)
阿部皓一 エーザイフード・ケミカル(株)
青木由典 エーザイフード・ケミカル(株)
外薗英樹 三和酒類(株)
大澤一仁 アサヒグループホールディングス(株)
-------------------------------------------------------------------------
<<目次>>
【第1編 総論】
第1章 脳のアンチエイジング
1 脳のアンチエイジングが目指すところ
2 脳神経構成成分
3 脳神経伝達物質成分
4 抗酸化ストレス成分
5 ビタミン成分
6 血流改善成分
7 おわりに
第2章 大豆栄養の健康長寿への貢献
1 日本人の長寿と日本食
2 世界の栄養と健康
3 女性の健康と大豆食
4 大豆摂取と心臓死・癌
5 大豆による介入研究
6 栄養改善のポピュレーションアプローチ
7 環境に優しい大豆食で人類の健康長寿を
第3章 脳機能に対する栄養と食生活
1 子どもの環境と脳機能
2 オキシトシンと脳機能
3 高齢者の認知機能
4 認知機能と食生活
5 認知機能と栄養
5.1 炭水化物
5.2 脂質
5.3 タンパク質
5.4 抗酸化栄養素
6 まとめ
【第2編 素材】
第1章 リン脂質,脂肪酸
1 大豆レシチン
1.1 はじめに
1.2 製法・組成
1.3 生理機能
1.3.1 コリン供給源としての働き
1.3.2 脳に対する機能
1.3.3 認知症に対する大豆レシチンの効果
1.3.4 健常者の記憶に対する大豆レシチンの効果
1.3.5 子供の認知力に対する効果
1.4 安全性
1.5 おわりに
2 大豆ホスファチジルセリンと記憶障害の研究・評価
2.1 はじめに
2.2 大豆PS
2.3 大豆PSの記憶障害改善効果
2.3.1 動物実験
(1) 薬物誘発健忘モデル動物による効果検証
(2) 老齢ラットを用いた記憶障害改善効果の検証
2.3.2 ヒト試験による効果検証
(1) パイロット試験
(2) プラセボ対照二重目隠し試験
2.4 規制関連
2.5 おわりに
3 DHA結合リン脂質とその含有油脂の機能と開発
3.1 概要
3.1.1 原料の選択
3.1.2 魚卵の原料組成
3.1.3 魚卵油の脂質
3.1.4 魚卵油の酸化安定性
3.2 素材の作用機序,効果
3.2.1 作用機序の提案
3.2.2 作用機序の解明の手段
3.3 応用
3.3.1 試験素材
3.3.2 生理機能の証明
(1) 脂質代謝改善効果
(2) レム睡眠増加効果
(3) 接触性皮膚炎モデルラットによる評価
3.4 おわりに
4 DHA/EPA
4.1 序論―魚食の疫学研究―
4.2 「ブレインフード」と「ムードフード」
4.3 エイコサペンタエン酸の血小板凝集抑制作用と医薬品化
4.4 ドコサヘキサエン酸(DHA)の中枢神経系作用
4.5 ω3系脂肪酸による炎症性脂質メディエイター産生の制御
4.6 ω3系脂肪酸と血流改善と血圧コントロール
4.7 新型ω3「クリルオイル」
4.7.1 脳の老化防止
4.7.2 高脂血症の改善
4.7.3 肝機能の改善
4.7.4 生殖機能の向上
4.7.5 心筋梗塞の予防
4.7.6 関節症にも有効
5 藻類由来DHAの特徴と脳機能向上効果
5.1 藻類由来DHAの特徴
5.2 藻類由来DHAの開発と経緯
5.3 藻類の培養と藻類由来DHAの製造
5.4 DHAが足りなくなる日
5.5 藻類由来DHAを使用した臨床試験
5.6 藻類由来DHAの使用の実際
6 ココナッツオイル
6.1 はじめに
6.2 脂肪と脂肪酸の代謝
6.3 ココナッツオイル
6.4 難治性てんかんとケトン食療法
6.5 糖尿病とアルツハイマー病
6.6 アルツハイマー病のココナッツオイル療法
6.7 アルツハイマー病と中鎖脂肪酸
6.8 MCTオイル(AC-1202)のアルツハイマー病患者での治験
6.9 日本人アルツハイマー病患者に対するAC-1202のパイロット試験
6.10 その他の神経疾患
7 中鎖脂肪酸の脳機能への影響
7.1 概要
7.2 素材の作用機序,効果
7.2.1 中鎖脂肪酸の消化吸収と代謝
7.2.2 中鎖脂肪酸の安全性
7.2.3 脳の非常用エネルギー源ケトン体
7.2.4 アルツハイマー病は第3の糖尿病
7.2.5 アルツハイマー病患者への中鎖脂肪酸投与効果
7.3 応用
7.3.1 ケトン体生成源としての中鎖脂肪酸
7.3.2 中鎖脂肪酸の社旗的意義
8 αGPC(グリセロホスホコリン)のメンタルパフォーマンスへの作用
8.1 はじめに
8.2 構造
8.3 GPCの製造
8.4 グリセロホスホコリンの栄養学的役割
8.5 GPCの安全性について
8.6 GPCの体内動態
8.7 GPCの生理機能について
8.8 結論
8.9 日本におけるアルファGPCの市場
9 ミルクセラミド(MC-5)
9.1 はじめに
9.2 ミルクセラミド(MC-5)
9.3 スフィンゴミエリンと脳機能
9.4 MC-5摂取による記憶学習行動試験
9.5 MC-5の記憶学習能に対する作用機序
第2章 アミノ酸・ペプチド
1 機能性アミノ酸・テアニン―緑茶に含まれるテアニンの栄養生理的な効果―
1.1 緑茶特有アミノ酸のテアニンとは
1.2 テアニンと脳との関わり
1.2.1 テアニンのドーパミン放出促進作用
1.2.2 ラットを用いたテアニンによる脳神経作用(記憶学習能)
1.2.3 ヒトを用いたテアニンによる脳神経作用
(1) テアニンはリラクゼーションを誘導する
(2) 女性のイライラ解消:月経前症候群(PMS: Premenstrual syndrome)
(3) テアニンの睡眠改善効果
1.3 環状テアニンについて
1.3.1 緑茶中の環状テアニン量
1.3.2 環状テアニンの合成
1.3.3 環状テアニンの味について
1.4 環状テアニンの機能性について
1.5 おわりに
2 「L-カルニチン」の脳機能改善について
2.1 はじめに
2.2 L-カルニチンとは
2.2.1 L-カルニチンの供給源
2.2.2 L-カルニチンと脳機能のメカニズム
2.3 L-カルニチンの老齢脳機能改善効果
2.3.1 実験方法
2.3.2 結果
(1) 血清および脳内カルニチン濃度
(2) 大脳皮質シナプス活性への効果
2.3.3 結論
2.4 超高齢者へのL-カルニチン摂取試験
2.4.1 実験方法
2.4.2 結果
2.4.3 結論
2.5 おわりに
3 ナットウキナーゼ
3.1 起源および由来
3.2 構造および特性
3.3 ナットウキナーゼ活性測定法
3.4 安全性
3.5 血栓症とナットウキナーゼの生理活性
3.6 おわりに
4 大豆ペプチド
4.1 はじめに
4.2 大豆ペプチド摂取による認知機能改善効果
4.3 大豆ペプチド摂取による脳内神経伝達物質変化
4.4 大豆ペプチド摂取による神経保護効果
4.5 おわりに
第3章 植物エキス
1 イチョウ葉エキスの認知機能について
1.1 はじめに
1.2 GBEの成分組成
1.3 GBEの作用機序
1.4 GBEの臨床試験
1.4.1 認知症患者を対象とした試験
1.4.2 健常者を対象とした試験
1.4.3 大規模臨床試験
1.5 GBEの機能性表示食品
1.6 おわりに
2 柑橘類成分ノビレチンの抗認知症機能性食品開発研究に必要な薬理学的エビデンス
2.1 緒言
2.2 素材の効果および作用機序
2.2.1 ノビレチンの一般薬理作用
2.2.2 記憶障害モデル動物におけるノビレチンによる改善効果の薬理学的検証
(1) マウス
(2) ラット
2.2.3 分子・細胞レベルにおけるノビレチンの作用解析
(1) ラット海馬初代培養神経細胞および海馬CA1領域スライス
(2) ラット副腎褐色細胞腫由来細胞株PC12およびその亜種PC12D
(3) ヒト神経芽細胞腫由来細胞株SK-N-SHなどの細胞
(4) ヒトiPS細胞由来ADモデル神経細胞
2.3 応用開発研究
3 γ-オリザノール
3.1 γ-オリザノールとは
3.2 γ-オリザノールの生理機能
3.3 γ-オリザノールの脳機能改善効果
3.4 γ-オリザノールの食嗜好性の制御作用(脳内報酬系の正常化)
3.5 おわりに
4 アミセノン(ヤマブシタケ抽出素材)
4.1 概要
4.2 作用機序,効果
4.3 応用
4.3.1 認知症と軽度認知機能障害
4.3.2 意欲向上への応用
4.3.3 睡眠の質改善
4.3.4 その他
5 山芋ジオスゲニンの認知症予防に対する効果
5.1 はじめに
5.2 ジオスゲニンとは
5.3 アミロイドβタンパク質の増加抑制ならびに軸索の変性改善による認知症予防
5.4 ホルモン産生促進による認知症予防
5.5 抗炎症による認知症予防
5.6 まとめ
6 VINEATROL 20Mの脳機能改善について
6.1 概要
6.2 素材の作用機序,効果
6.2.1 抗アミロイド作用
6.2.2 抗酸化作用
6.2.3 アポトーシス因子の抑制作用
6.2.4 SIRT-1活性化によるアンチエイジング作用
6.3 まとめ
7 レスベラトロールと脳機能
7.1 概要
7.1.1 RSVの発見と構造
7.1.2 RSVの分析とブドウにおける分布
7.2 素材の作用機序,効果
7.2.1 赤ワインの疫学データ
7.2.2 アルツハイマー病について
7.2.3 RSVの脳神経保護効果
7.3 応用
7.4 おわりに
8 ANM176(R) はアルツハイマー病の改善と予防に役立つ可能性がある
8.1 概要
8.2 ANM176(R)の作用機構
8.3 応用
9 水抽出型(膜濃縮)カシスポリフェノール(AC10)
9.1 はじめに
9.2 カシスとは
9.3 水抽出型 カシスポリフェノール(AC10)とは
9.4 水抽出型 カシスポリフェノール(AC10)の特長と機能性
9.5 水抽出型 カシスポリフェノール(AC10)による脳血流改善機能
9.6 水抽出型 カシスポリフェノール(AC10)による脳末梢血管拡張作用機序
9.7 水抽出型 カシスポリフェノール(AC10)によるアミロイド斑形成抑制作用
9.8 水抽出型 カシスポリフェノール(AC10)の安全性
9.9 おわりに
10 抗酸化ポリフェノールによる脳機能改善効果
10.1 はじめに
10.2 ゴマリグナンによるin vitro系での脳機能改善効果
10.3 ショウジョウバエを用いた個体レベルでの老化予防研究
10.4 高カカオチョコレートを用いた大規模ヒト臨床試験
11 フェルラ酸
11.1 概要
11.2 フェルラ酸の作用機序,作用
11.2.1 抗酸化作用,抗炎症作用
11.2.2 アミロイドβに対する作用
11.2.3 脳機能保護作用
11.2.4 リン酸化タウ低下作用
11.3 応用
第4章 その他
1 PQQ
1.1 概要
1.2 PQQの作用機序,効果
1.2.1 化学的性質と作用
1.2.2 PQQの効果
1.3 応用(ヒト試験)
1.3.1 認識力・認知力改善
1.3.2 コエンザイムQ10との併用効果
1.3.3 気分あるいは睡眠に対する効果
2 トコフェロール,トコトリエノール
2.1 はじめに
2.2 ビタミンEの発見と種類と作用
2.3 脳神経系におけるα-トコフェロール
2.4 脳神経系におけるγ-トコフェロール,トコトリエノール
3 GABA
3.1 はじめに
3.2 GABA摂取による脳機能改善効果
3.3 方法
3.3.1 被験品
3.3.2 被験者
(1) 選択基準
(2) 除外基準
3.3.3 試験スケジュールおよび摂取方法
3.3.4 検査方法
(1) 即時記憶領域
(2) 視空間・構成領域
(3) 言語領域
(4) 集中力領域
(5) 遅延記憶領域
3.3.5 統計処理
3.4 結果
3.4.1 被験者背景
3.4.2 アーバンス神経心理テスト:下位テストの評価点推移
3.4.3 アーバンス神経心理テスト:5認知領域の評価点推移
3.5 考察
3.6 おわりに
4 Lactobacillus helveticus発酵乳
4.1 はじめに
4.2 酸乳の動物に対する有効性
4.2.1 記憶障害予防作用(単回投与)
4.2.2 学習記憶力向上作用(単回投与)
4.2.3 学習記憶力向上作用(長期投与)
4.3 メカニズム
4.4 乳酸菌飲料のヒトに対する有効性
4.4.1 日本語版アーバンス神経心理テストを用いた記憶力・集中力評価
4.4.2 コグヘルスを用いた記憶力・集中力評価
4.5 まとめ
-

DLCの基礎と応用展開《普及版》
¥4,400
2016年刊「DLCの基礎と応用展開」の普及版。DLC技術の構造分析、評価などの基礎理論から各種応用技術までを網羅した1冊!
(監修:大竹尚登)
<a href="http://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=9067"target=”_blank”>この本の紙版「DLCの基礎と応用展(普及版)」の販売ページはこちら(別サイトが開きます)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は、2016年当時のものを使用しております。
大竹尚登 東京工業大学
神田一浩 兵庫県立大学
佐々木信也 東京理科大学
加納眞 KANO Consulting Office
大花継頼 (国研)産業技術総合研究所
平栗健二 東京電機大学
三好理子 (株)東レリサーチセンター
竹田正明 (株)東レリサーチセンター
辻岡正憲 日本アイ・ティ・エフ(株)
平塚傑工 ナノテック(株)
赤理孝一郎 (株)神戸製鋼所
鈴木泰雄 (株)プラズマイオンアシスト
熊谷泰 ナノコート・ティーエス(株)
森広行 (株)豊田中央研究所
佐川琢円 日産自動車(株)
熊谷正夫 (株)不二WPC
松尾誠 (株)iQubiq
岩本喜直 (株)iMott
鹿田真一 関西学院大学
梅原徳次 名古屋大学
鷹林将 (株)アドテックプラズマテクノロジー
白倉昌 オールテック(株)
森貴則 慶應義塾大学
鈴木哲也 慶應義塾大学
中村挙子 (国研)産業技術総合研究所
稗田純子 名古屋大学
青野祐美 防衛大学校
一ノ瀬泉 (国研)物質・材料研究機構
赤坂大樹 東京工業大学
滝川浩史 豊橋技術科学大学
井上雅貴 東京工業大学
髙村瞭太 東京工業大学
葛巻徹 東海大学
-------------------------------------------------------------------------
<<目次>>
第1章 DLCの基礎
1 DLC膜の基礎と応用の概観
1.1 はじめに
1.2 機械とDLC
1.3 切削工具とDLC
1.4 DLCの分類
1.5 DLC成膜の基礎
2 DLC構造分析の基礎
2.1 DLC膜の構造
2.2 DLC膜のsp2/sp3比の分析方法
2.3 DLC膜の水素含有率の分析方法
2.4 ヘテロ元素含有DLC膜の構造解析
2.5 むすび
3 薄膜トライボロジーの基礎
3.1 はじめに
3.2 トライボロジーの基礎メカニズム
3.2.1 摩擦のメカニズム
3.2.2 摩耗のメカニズム
3.2.3 潤滑のメカニズム
3.3 トライボマテリアルとしてのDLCの特徴
3.3.1 高硬度
3.3.2 平滑性と低攻撃性
3.3.3 固体潤滑性
3.3.4 化学的安定性(耐腐性)
3.4 おわりに
4 DLCのトライボロジー応用における留意点
4.1 はじめに
4.2 応用における留意点
4.3 おわりに
5 DLC膜の密着力とその評価
5.1 はじめに
5.2 一般的な評価方法
5.3 摩擦摩耗試験とはく離
5.4 統計的なはく離荷重
5.5 はく離評価における課題
5.6 おわりに
6 DLCの生体親和性
6.1 はじめに
6.2 アモルファス炭素系薄膜(含むDLC膜)と膜特性
6.2.1 アモルファス炭素系薄膜(含むDLC膜)の作製
6.2.2 アモルファス炭素系薄膜(含むDLC膜)の細胞親和性
6.2.3 アモルファス炭素系薄膜(含むDLC膜)の物性評価
6.3 評価結果
6.3.1 細胞親和性評価
6.3.2 膜物性評価
6.3.3 細胞親和性と光学特性
6.4 まとめ
7 固体NMRによる炭素膜の構造分析
7.1 はじめに
7.2 固体高分解能NMR(核磁気共鳴)法によるsp3炭素比率の評価
7.3 DLC膜の評価事例
7.3.1 試料
7.3.2 DLC膜の各種物性評価
7.3.3 DLC膜の構造評価
7.4 まとめ
第2章 機械的応用展開
1 DLCの機械的応用の最前線
1.1 はじめに
1.2 DLCの種類と特徴
1.3 工具・金型への応用
1.3.1 軟質金属切削加工への適用
1.3.2 軟質金属成形用金型への適用
1.3.3 超平滑DLCとその新展開
1.4 DLCの機械部品(摺動部品)への応用
1.4.1 代表的な機械部品への適用事例と最近の取組
1.4.2 高分子部品への適用
1.4.3 新たな機械部品適用への取組
1.5 DLCの自動車部品への応用
1.6 まとめ
2 分析の視点からの機械的応用と特徴
2.1 はじめに
2.2 光学的評価による構造と硬さの関係
2.3 多元素含有とその特性
2.3.1 ボロン含有DLC膜と導電性
2.3.2 フッ素含有DLC膜と撥水性評価
2.4 おわりに
3 DLCの自動車部品への適用の新展開
3.1 はじめに
3.2 自動車部品への適用状況
3.3 DLC膜の摩耗に及ぼす潤滑剤の影響
3.4 DLCの自動車部品適用の新展開
3.4.1 究極のピストンとシリンダの材料仕様
3.4.2 究極のエンジン摩擦低減の可能性
3.5 おわりに
4 UBMS装置によるDLC膜の最前線
4.1 UBMS法の原理と特長
4.2 UBMS装置によるDLC形成プロセス
4.3 UBMS法による高機能DLC膜の形成
4.3.1 中間層による高密着性
4.3.2 硬度制御性
4.3.3 組成制御性
4.4 UBMS装置によるDLC膜の展開
4.4.1 UBMS+AIP
4.4.2 UBMS+プラズマCVD
4.5 おわりに
5 導電性DLCをコートした燃料電池用セパレータの開発
5.1 はじめに
5.2 セパレータに要求される特性
5.2.1 燃料電池の構成
5.2.2 セパレータに要求される特性
5.3 DLCの導電化
5.3.1 DLCとは
5.3.2 DLCの成膜方法
5.3.3 DLCの成膜プロセス
5.3.4 DLCの導電化
5.4 接触抵抗の低減
5.4.1 接触抵抗の原理
5.4.2 接触抵抗
5.5 耐食性
5.5.1 導電性DLC膜の構成
5.5.2 導電性DLC膜の耐食性
5.6 低コスト
5.6.1 高速成膜装置
5.6.2 インライン装置の概念図
5.6.3 成膜速度
5.6.4 低コスト化
5.7 ステンレスセパレータの発電性能
5.7.1 単体セルの発電性能
5.7.2 セルスタックの発電性能
5.8 アルミセパレータの発電性能
5.8.1 セルスタックの発電試験
5.9 まとめ
6 多層化水素含有DLC膜の特性と応用
6.1 はじめに
6.2 成膜装置とプロセス
6.3 密着力評価
6.4 トライボロジー特性
6.5 実用例
6.6 おわりに
7 DLC-Si膜の電動ウォータポンプシャフトへの適用
7.1 はじめに
7.2 鋼材への高密着化技術
7.3 DLC-Si膜のトライボジー特性
7.4 防食設計
7.5 おわりに
8 ta-Cの自動車部品への適用
8.1 はじめに
8.2 ta-Cの自動車部品への適用事例
8.2.1 バルブリフタ
8.2.2 ピストンリング
8.3 ta-C膜における低フリクション化
8.3.1 油性剤による低フリクション化
8.3.2 高真空下での摩擦試験によるta-C膜低フリクション化メカニズム検討
8.3.3 コンピューターシミュレーションによる低フリクション化メカニズム検討
8.4 ta-C膜と省燃費エンジンオイルによる低フリクション化メカニズム
8.5 おわりに
9 WPC処理によるAl合金部材へのDLCコーティング
9.1 はじめに
9.2 WPC処理について
9.2.1 WPC処理とは
9.2.2 WPC処理による複合組織の形成
9.3 DLC被覆のためのアルミニウム合金へのWPC処理
9.3.1 金属基材へのDLCの付着機構
9.3.2 アルミニウム合金表面への密着性向上のための構造
9.3.3 アルミニウム合金へのDLC被覆
9.4 DLC被覆アルミニウムピストンの開発
9.5 おわりに
10 セグメント構造DLC膜のはさみへの応用展開
10.1 理美容用はさみの構造設計
10.2 理美容用S-DLCコーティングはさみの設計
10.3 S-DLCコーティングはさみの特性
10.4 S-DLCコーティングはさみのまとめ
10.5 S-DLCコーティングはさみの今後の展開
11 ナノダイヤモンドの合成と機械的応用
11.1 はじめに
11.2 合成と特性
11.3 機械的応用
11.4 機械的応用の展開
12 a-CNx膜のトライボロジー特性
12.1 はじめに
12.2 a-CN膜の乾燥窒素中における超低摩擦の発現
12.3 a-CNxの乾燥窒素ガス中超低摩擦発現メカニズム
12.4 a-CNxの添加剤を含有しないベース油(PAO油)中での超低摩擦発現
12.5 a-CNx膜の反射分光分析摩擦面その場観察による構造変化層の厚さ及び物性と摩擦係数の関係
12.6 今後の展望
第3章 電気的・光学的・化学的応用展開
1 DLCの電気特性と化学構造との関係
2 DLC膜のガスバリヤ性とその応用の最前線
2.1 はじめに
2.2 PETボトル内面へのDLCコーティングと改良開発の状況
2.3 PETボトルのリユース適性向上への利用
2.4 大気圧プラズマCVD法によるガスバリヤ性向上
2.5 DLC膜と酸化ケイ素系膜の積層膜の大気圧プラズマによるコーティング
2.6 マイクロ波励起大気圧プラズマCVD法によるDLCコーティング
2.7 大気圧プラズマCVD法によるコンクリート保護
2.8 おわりに
3 DLCの表面修飾法
3.1 はじめに
3.2 フッ素官能基化技術
3.3 酸素官能基化技術
3.4 硫黄官能基化技術
3.5 他のカーボン材料への適用
3.6 化学修飾カーボン材料の医用応用
3.7 まとめ
4 BドープDLCの生体親和性
4.1 はじめに
4.2 BドープDLC膜の作製
4.3 BドープDLC膜の表面構造と表面特性
4.4 BドープDLC膜の血液適合性
4.4.1 血液適合性について4)
4.4.2 血液適合性試験
4.4.3 BドープDLC膜の血液適合性
4.5 おわりに
5 アモルファス窒化炭素のガス応答性
5.1 はじめに
5.2 抵抗値の雰囲気依存性
5.3 雰囲気依存性の原因
5.4 まとめ
6 DLCのフィルターへの応用
6.1 はじめに
6.2 研究動向
6.3 DLC製の濾過フィルターの特徴
7 DLC膜の耐エッチング性
第4章 次世代DLC応用のためのキー技術
1 大電力パルススパッタリングによるDLC成膜技術
1.1 はじめに
1.2 高硬度化
1.3 高速成膜
1.4 HiPIMS技術の今後の展開
2 高sp3比DLC膜の成膜
2.1 はじめに
2.2 成膜方法
2.3 真空アーク蒸着
2.4 フィルタードアーク蒸着
2.5 高sp3比DLC膜の作り方
2.6 高sp3比DLC膜の応用
2.7 おわりに
3 準大気圧・大気圧DLC成膜と円管内壁へのDLC成膜
3.1 ナノパルスプラズマCVDと準大気圧下でのDLC成膜
3.2 準大気圧下でのDLC膜の厚膜化
3.3 大気圧下でのDLC成膜
3.4 ナノパルスプラズマCVDによる円管内へのDLC成膜
3.5 まとめ
4 ナノ材料試験システムによるDLC膜の力学特性評価
4.1 緒言
4.2 実験方法
4.2.1 ナノ材料試験システム
4.2.2 試料作製
4.2.3 引張試験
4.2.4 ナノインデンテーション試験
4.3 実験結果および考察
4.3.1 ナノ材料試験システムによるDLC膜の引張試験
4.3.2 ピエゾ駆動型微少引張試験機の開発
4.4 まとめ
第5章 DLCとその応用の未来
-

難水溶性薬物の経口製剤化技術最前線《普及版》
¥4,180
2016年刊「難水溶性薬物の経口製剤化技術最前線」の普及版。難水溶性薬物製剤化のための開発戦略、原薬物性評価、共結晶や非晶質固体分散体、ナノ結晶製剤など製剤技術を詳述した1冊!
(監修:川上亘作)
<a href="http://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=9068"target=”_blank”>この本の紙版「難水溶性薬物の経口製剤化技術最前線(普及版)」の販売ページはこちら(別サイトが開きます)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は、2016年当時のものを使用しております。
川上亘作 (国研)物質・材料研究機構
菅野清彦 東邦大学
片岡誠 摂南大学
野沢健児 沢井製薬㈱
竹内達 沢井製薬㈱
瀬田康生 東京薬科大学
米持悦生 星薬科大学
深水啓朗 明治薬科大学
伊豆津健一 国立医薬品食品衛生研究所
山本克彦 武田薬品工業㈱
山下博之 アステラス製薬㈱
平倉穣 アステラス製薬㈱
上田廣 塩野義製薬㈱
尾上誠良 静岡県立大学
尾崎俊亮 エーザイ㈱
小久保宏恭 信越化学工業㈱
植田圭祐 千葉大学
森部久仁一 千葉大学
小川法子 愛知学院大学
山本浩充 愛知学院大学
永禮三四郎 ㈱奈良機械製作所
井上皓介 ㈱奈良機械製作所
小嶋竜 アステラス製薬㈱
保地毅彦 アステラス製薬㈱
東顕二郎 千葉大学
橋本直文 摂南大学
髙木和行 みづほ工業㈱
石井利博 アシザワ・ファインテック㈱
-------------------------------------------------------------------------
<<目次>>
第1章 難水溶性薬物の経口製剤化戦略
1 難水溶性薬物の開発戦略
1.1 はじめに
1.2 Brick DustとGrease Ball
1.3 原薬形態の変更による溶解性改善
1.4 可溶化溶液製剤
1.5 非晶質固体分散体
1.6 ナノ結晶製剤
1.7 おわりに
2 難水溶性化合物製剤化のためのフレームワーク思考
2.1 フレームワーク思考とは?
2.2 製剤開発のフレームワーク
2.3 経口吸収のフレームワーク1-Biopharmaceutics classification system-
2.4 経口吸収のフレームワーク2-Developability classification system-
2.5 経口吸収のフレームワーク3―律速段階分類―
2.6 経口吸収のフレームワーク4-Fa classification system-
2.7 Fa式およびFaCSに基づく粒子径設定
2.8 FaCSとGUT framework
2.9 終わりに―コンピュータはフレームワークの夢を見るか?―
3 難水溶性薬物の吸収性予測
3.1 はじめに
3.2 難水溶性薬物の経口吸収率の決定要因
3.3 Dissolution/permeation system(D/Pシステム)の概要
3.4 難水溶性薬物の経口吸収率予測
3.5 難水溶性薬物の製剤化による吸収改善効果の予測
3.5.1 脂質製剤を用いた経口吸収改善
3.5.2 微粒子製剤を用いた経口吸収改善
3.5.3 過飽和製剤を用いた経口吸収改善
3.5.4 製剤添加物による溶解性改善と膜透過性変化
3.6 胃内薬物溶解過程を反映したD/Pシステム
3.7 おわりに
4 難水溶性薬物のジェネリック医薬品開発戦略
4.1 ジェネリック医薬品の製剤化戦略
4.1.1 ジェネリック医薬品を取り巻く環境
4.1.2 難溶性薬物の定義と生物学的同等性について
4.1.3 難溶性薬物の製剤開発事例
4.1.4 まとめ
4.2 ジェネリック医薬品開発における消化管内溶出性評価方法
4.2.1 生物学的同等性試験
4.2.2 BCS sub-classification
4.2.3 In Vivo Predictive Dissolution (iPD) methodology
4.2.4 まとめ
第2章 難水溶性原薬の物性改善
1 難水溶性原薬の物性評価
1.1 はじめに
1.2 溶解度と固体相
1.2.1 DMSO(Dimethyl Sulfoxide)析出法
1.2.2 フラスコ振盪法(固体溶解法)
1.2.3 濁度による溶解度の評価
1.2.4 自動化された機器による溶解性評価
1.3 溶出速度
1.3.1 溶出速度評価の目的
1.3.2 開発初期段階で実施する難水溶性化合物の溶出試験
1.3.3 溶出試験方法
1.3.4 回転バスケット法(JP,USP,EP各局方apparatus 1)
1.3.5 パドル法(JP,USP,EP各局方apparatus 2)
1.3.6 フロースルーセル法(USP & EP apparatus 4,JP apparatus 3)
1.3.7 μDISS Profiler(Pion社,Massachusetts,U.S.A.)
1.3.8 inForm(Sirius Analytical Instruments社,East Sussex,U.K.)
1.3.9 溶出試験液
1.4 膜透過性
1.4.1 創薬段階での膜透過性評価
1.4.2 Parallel Artificial Membrane Permeability Assay(PAMPA)
1.4.3 他の膜透過性評価方法
1.5 難水溶性原薬の固体形態の評価
1.5.1 固体形態の分類
1.5.2 原薬の固体形態の評価の流れと評価項目
1.6 まとめ
2 塩による溶解性改善
2.1 はじめに
2.2 塩選択の現状
2.3 スクリーニングの現状
2.4 おわりに
3 塩と共結晶の類似点,相違点
3.1 はじめに
3.2 塩と共結晶の定義ならびに分類
3.2.1 学術論文上における議論
3.2.2 医薬品のレギュレーションにおける議論
3.2.3 塩と共結晶の区別
3.3 溶解性と生体吸収性に関する考察
3.4 おわりに
4 共結晶医薬品の開発と評価
4.1 はじめに
4.2 共結晶(コクリスタル)医薬品について
4.3 共結晶医薬品のレギュレーション
4.3.1 FDAガイダンス
4.3.2 リフレクションペーパー
4.3.3 国際調和と国内における活用への課題
4.4 共結晶を含む医薬品の特性と評価法
4.4.1 共結晶の構造
4.4.2 共結晶形成のスクリーニングと予測
4.4.3 物性の評価法
4.4.4 安定性
4.5 共結晶医薬品の溶出と吸収
4.5.1 In vitroでの溶解・溶出評価
4.5.2 溶出後の物理安定性
4.5.3 消化管内での溶出と吸収
4.6 共結晶の製造と管理
4.6.1 溶液からの晶析
4.6.2 スプレードライおよび凍結乾燥
4.6.3 乾式または溶媒添加粉砕
4.7 製剤の特性評価
4.8 共結晶技術の新薬と既存医薬品での活用
4.9 まとめ
5 共結晶の探索法
5.1 共結晶の有用性,探索の必要性
5.2 共結晶の探索法概説
5.3 共結晶の探索法詳解
5.3.1 Saturation counter slurry法
5.3.2 Cocktail cocrystal grinding法
5.4 医薬品開発における共結晶探索の妥当なタイミング
6 共結晶の熱挙動
6.1 はじめに
6.2 共結晶の相図と共結晶の融点
6.2.1 共結晶の相図と熱挙動
6.2.2 共結晶の融点
6.3 物理的混合物の熱挙動
6.3.1 二成分の物理的混合物の相図と熱挙動
6.3.2 昇温速度の影響
6.3.3 粒子径の影響
6.4 相図に基づく熱的手法による共結晶探索
6.4.1 共結晶スクリーニングの方法
6.4.2 熱的手法によるスクリーニングの優位性と課題点
7 共非晶質:Co-amorphousの研究動向
7.1 はじめに
7.2 共非晶質の定義
7.3 共非晶質形成による溶解性改善例
7.3.1 薬物-薬物共非晶質の報告例
7.3.2 薬物-添加剤共非晶質の報告例
7.4 塩形成を介した共非晶質形成
7.5 共非晶質の調製方法
7.6 共非晶質の物理化学的特性
7.7 共非晶質形成を利用した固体分散体の設計
7.8 おわりに
第3章 非晶質固体分散体
1 非晶質技術を利用した医薬品開発の現状
1.1 はじめに
1.2 医薬品の特性に応じた可溶化技術選択
1.3 固体分散体製剤
1.3.1 定義
1.3.2 固体分散体製剤技術による薬物動態の改善
1.3.3 固体分散体製剤技術を用いた製品
1.3.4 既存薬への固体分散体製剤技術応用
1.4 新しい固体分散体製剤
1.5 おわりに
2 非晶質原薬物性の基礎
2.1 はじめに
2.2 非晶質状態の機器分析
2.3 非晶質固体の非アレーニウス性
2.4 構造緩和
2.5 結晶化
2.6 化学安定性
2.7 溶解度と過飽和溶解
2.8 おわりに
3 非晶質の溶解度
3.1 はじめに
3.2 非晶質の溶解度推定法とその理論的背景
3.3 非晶質の溶解度に基づく過飽和特性評価と製剤処方設計
3.4 おわりに
4 固体分散体のための添加剤の設計
4.1 はじめに
4.2 固体分散体
4.3 水溶性セルロース誘導体
4.4 腸溶性セルロース誘導体
4.5 まとめ
5 固体分散体の過飽和溶解
5.1 はじめに
5.2 固体分散体による薬物過飽和形成
5.3 薬物過飽和維持機構
5.4 可溶化
5.5 過飽和及び可溶化溶解と膜透過性
5.6 おわりに
6 シクロデキストリンを利用した固体分散体設計
6.1 はじめに
6.2 シクロデキストリンの構造と包接特性
6.3 シクロデキストリンによる薬物の非晶質化と固体分散体化
6.4 非晶質医薬品の安定性とシクロデキストリン
6.5 おわりに
7 溶融押出法による固体分散体調製と後工程における粒子の加工技術
7.1 はじめに
7.2 エクストルーダーの特長
7.3 HME法を用いた薬物のアモルファス化
7.4 溶融品の品質検証
7.5 後工程における粒子加工技術の紹介
7.6 おわりに
8 噴霧乾燥法による固体分散体調製
8.1 固体分散体と噴霧乾燥法の概要
8.2 噴霧乾燥品の処方設計とプロセス開発
8.2.1 担体の選択
8.2.2 溶媒の選択
8.2.3 製造条件と粉体特性
8.3 噴霧乾燥品を用いた錠剤設計とプロセス開発
8.4 噴霧乾燥品および噴霧乾燥品を含む錠剤の評価
8.5 おわりに
第4章 ナノ結晶製剤
1 ナノ結晶化技術の基礎と医薬品開発の現状
1.1 はじめに
1.2 ナノ結晶製剤の特徴
1.2.1 薬物ナノ結晶化による経口吸収性の増大
1.2.2 食事の影響の軽減
1.3 ナノ結晶製剤の調製法
1.4 ナノ結晶製剤の物性評価法
1.4.1 ナノ結晶懸濁液中の粒子サイズ・形態・表面状態評価
1.4.2 ナノ結晶懸濁液中の薬物溶解度・溶解速度
1.4.3 ナノ結晶懸濁液の分子状態評価
1.5 ナノ結晶製剤の開発
1.6 市販の経口投与ナノ結晶製剤
1.7 おわりに
2 自転/公転ミキサーによる難水溶性薬物のナノ粒子化製剤
2.1 はじめに
2.2 ナノ粒子化の利点
2.3 自転/公転ナノ粉砕機によるナノ粒子化技術の開発
2.4 自転/公転ナノ粉砕機の機構
2.5 難水溶性薬物のナノ粒子化
2.6 難水溶性低融点化合物のナノ粒子化
2.7 スケールアップ
2.7.1 スケールアップ―粉砕時の至適薬物濃度
2.7.2 スケールアップ―薬物粉砕後の粒度分布に及ぼす公転Gの効果
2.8 難水溶性薬物のナノ粒子製剤の分散性
2.9 溶出試験および経口吸収性に及ぼすGFナノ結晶粒子の分散安定性の効果
2.10 おわりに
3 高圧ホモジナイザーによるナノ粉砕
3.1 はじめに
3.2 高圧ホモジナイザー
3.2.1 バルブ式高圧ホモジナイザーと流路固定式高圧ホモジナイザーの違い
3.3 高圧ホモジナイザーによるナノ粉砕の例
3.4 医薬品業界における高圧ホモジナイザーの利用
3.4.1 脂肪乳剤
3.4.2 脂肪乳剤の処理例
3.4.3 脂肪乳剤の製造プロセス
3.4.4 リポソームの製造方法
3.5 おわりに
4 ビーズミルによる難水溶性薬物のナノ粉砕
4.1 はじめに
4.2 ビーズミルの粉砕原理および運転方法
4.3 ビーズミルの粉砕効率に影響を与える因子
4.3.1 ビーズ径
4.3.2 ビーズ充填率およびアジテータ周速
4.4 ビーズミルでの再現性
4.5 ビーズミルでのスケールアップ
4.6 GMP対応ビーズミル
4.7 おわりに
-

酸化グラフェンの機能と応用《普及版》
¥5,060
2016年刊「酸化グラフェンの機能と応用」の普及版。半導体材料・酸化剤・触媒担体・電極材料・磁性材料として期待される酸化グラフェンの材料化学・応用展開について解説した1冊!
(監修:松本泰道)
<a href="http://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=8939"target=”_blank”>この本の紙版「酸化グラフェンの機能と応用(普及版)」の販売ページはこちら(別サイトが開きます)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は、2016年当時のものを使用しております。
松本泰道 熊本大学
仁科勇太 岡山大学
斉木幸一朗 東京大学
小林慶裕 大阪大学
杉村博之 京都大学
屠宇迪 京都大学
宇都宮徹 京都大学
一井崇 京都大学
小幡誠司 東京大学
谷口貴章 物質・材料研究機構
畠山一翔 熊本大学
竹平裕 熊本大学
村島裕介 熊本大学
速水真也 熊本大学
唐捷 物質・材料研究機構
新谷紀雄 物質・材料研究機構
近藤剛弘 筑波大学
中村潤児 筑波大学
鯉沼陸央 熊本大学
松尾吉晃 兵庫県立大学
井原敏博 熊本大学
北村裕介 熊本大学
新留琢郎 熊本大学
栗原清二 熊本大学
坪川紀夫 新潟大学
藤木一浩 新潟工科大学
山内健 新潟大学
遠藤洋史 富山県立大学
高山哲生 山形大学
伊藤浩志 山形大学
守谷(森棟)せいら 中部大学
西野孝 神戸大学
金善南 熊本大学
緒方智成 熊本大学
-------------------------------------------------------------------------
<<目次>>
第1章 酸化グラフェンの合成
1 はじめに
2 酸化グラフェンの構造
3 酸化グラフェン中の不純物の影響と精製法
4 非金属系酸化剤による合成
4.1 Brodie法
4.2 Brodie法の改良
4.3 Staudenmaier法
5 金属系酸化剤による合成
5.1 Hummers法
5.2 Hummers法の改良
5.3 鉄酸化剤を用いる方法
5.4 Brodie法とHummers法で得られる酸化グラフェンの違い
6 電解法
6.1 イオン液体中での電解による黒鉛の剥離
6.2 水中での電解による黒鉛の酸化剥離
7 マイクロ波照射法
第2章 酸化グラフェンの還元法とグラフェン合成
1 はじめに
2 熱還元法
2.1 はじめに
2.2 真空中や不活性雰囲気中での加熱処理による酸化グラフェンの還元
2.3 炭素を含む反応性ガス雰囲気中での加熱処理による酸化グラフェンの還元
3 光還元法
3.1 GOの光励起反応
3.2 GOのVUV還元
3.3 VUVマイクロ還元加工
3.4 おわりに
4 還元剤による化学的な還元
4.1 はじめに
4.2 種々の化学的還元法の特徴
4.3 GOの修復を伴う化学的還元法
4.4 まとめ
5 金属の触媒性を利用した還元
5.1 はじめに
5.2 金属単結晶を用いた還元方法
5.3 Niを用いたSiO2表面でのその場 (on site) 還元
5.4 GOを用いたgraphene 成長の特徴
5.5 まとめ
6 その他の還元方法
6.1 ArやN2を用いたGOの還元
6.1.1 Arプラズマを用いた還元
6.2 CH4プラズマを用いた酸化グラフェンのグラフェン化
6.3 まとめ
第3章 酸化グラフェンの基本的性質
1 はじめに
2 酸化グラフェンの反応性
3 酸化グラフェンの発光機構
4 酸化グラフェン層間での金属イオン透過性
第4章 酸化グラフェンのプロトン伝導と電気伝導
1 はじめに
2 酸化グラフェンの電子状態
3 酸化グラフェンのプロトン伝導
4 酸化グラフェンの半導体特性と応用
5 その他 ~GOのプロトン/電子混合伝導~
第5章 酸化グラフェンの電気化学デバイスへの応用
1 まえがき
2 グラフェンの特性を活かした高性能スーパーキャパシター
2.1 はじめに
2.2 グラフェンのスーパーキャパシターに関わる特性
2.3 スーパーキャパシター用還元型酸化グラフェンの作製とナノポアの導入
2.4 グラフェンのスーパーキャパシター電極作製
2.5 グラフェンスーパーキャパシターの性能
2.6 グラフェンスーパーキャパシターの応用と実用化
2.7 おわりに
3 燃料電池の酸素極への応用
3.1 燃料電池の白金代替触媒
3.2 窒素ドープグラファイト系触媒
3.3 カーボン中の活性窒素種
3.4 ルイス塩基性とORR活性点
3.5 まとめ
4 酸化グラフェン燃料電池(GOFC)と鉛蓄電池(GOLB)
4.1 GOを用いたポリマー電解質膜燃料電池(PEMFC)
4.2 メタノール直接形燃料電池(DMFC)
4.3 空気亜鉛電池
4.4 GOを用いたバナジウムレドックスフロー電池(VRFB)
4.5 GOを固体電解質として用いたその他の電池特性評価
4.6 おわりに
5 酸化グラフェンのリチウム電池への応用
5.1 はじめに
5.2 GOのリチウム電池正極材料としての応用
5.3 GOの還元物のリチウムイオン電池負極材料としての応用
5.3.1 GOの熱還元物の負極特性
5.3.2 薄層化されたGOの還元物の負極特性
5.4 おわりに
第6章 酸化グラフェンの生体への応用
1 はじめに
2 バイオセンサ
2.1 はじめに
2.2 DNAまたはRNAのセンシング
2.3 タンパク質およびその他の生理活性分子のセンシング
2.4 金属イオンのセンシング
2.5 細胞のセンシング
3 医療材料としての酸化グラフェン
3.1 はじめに
3.2 ドラッグデリバリーシステム
3.3 フォトサーマル治療
3.4 フォトダイナミック治療(光線力学治療)
3.5 バイオイメージング
3.6 組織工学
3.7 安全性
3.8 おわりに
第7章 酸化グラフェンの高分子ハイブリット体
1 はじめに
2 酸化グラフェン/高分子複合体の作製
~酸化グラフェン及びグラフェンへのポリマーのグラフト~
2.1 はじめに
2.2 グラフェンへのGrafting from法によるグラフト化
2.2.1 原子移動重合(ATRP)法によるグラフト化
2.2.2 可逆的不可開裂連鎖移動(RAFT)法によるグラフト化
2.2.3 カリウムカルボン酸塩(COOK)基からのアニオングラフト重合
2.3 グラフェンへの“Grafting onto”法によるグラフト化
2.3.1 GOの官能基と末端反応性ポリマーとの高分子反応
2.3.2 ポリマーラジカル捕捉法によるグラフト化
2.3.3 フェロセン含有ポリマーとの配位子交換反応によるグラフト化
2.3.4 GO表面カルボキシル基開始によるカチオン重合グラフト化
2.3.5 GOへ導入したビニル基を用いるin-situ重合によるグラフト化
2.4 ポリマーグラフトGOの分散性
2.5 おわりに
3 高分子電解質修飾酸化グラフェンを介したゲル型成形加工およびナノ粒子担持技術
3.1 はじめに
3.2 ポリイオンコンプレックス型コンポジットフィルムの作製と成形加工
3.3 酸化チタンナノ粒子の高密度担持
4 射出成形された酸化グラフェン/高分子複合体の物性
4.1 はじめに
4.2 グラフェンの剥離処理法と射出成形品の物性の関係
4.3 マトリクスの親水化によるPMMA共重合体/酸化グラフェン複合材料射出成形品の物性改善
4.4 まとめ
5 酸化グラフェン/高分子複合体の力学的性質
5.1 はじめに
5.2 GOの補強効果
5.3 ポリビニルアルコール系ナノ複合体
5.4 GOの配列による効果
5.5 ポリメタクリル酸メチル系ナノ複合体
5.6 まとめ
6 酸化グラフェン/高分子複合体の伝熱性
6.1 はじめに
6.2 熱伝導メカニズム
6.3 高分子複合体の熱伝導性
6.4 熱伝導測定法
6.5 GO/高分子複合体の熱伝導特性
6.6 GO/高分子複合体の精密構造制御
6.7 まとめ
7 酸化グラフェン/高分子複合体のガスバリア性
7.1 はじめに
7.2 ポリマーのガスバリア性
7.3 ガスバリア性の指標
7.4 フィラーによるガスバリアモデル
7.5 GO/ポリマー複合体のガスバリア性に関する報告例
7.5.1 混合方法の影響
7.5.2 ベースポリマーの影響
7.5.3 GO特性の影響
7.6 まとめ
-

カルコゲナイド系層状物質の最新研究《普及版》
¥4,730
2016年刊「カルコゲナイド系層状物質の最新研究」の普及版。光電変換素子、水カルコゲナイド系層状物質の基礎的事項を網羅し、トランジスタや素発生触媒等、応用展開についても解説した1冊!
(監修:上野啓司、安藤淳、島田敏宏)
<a href="http://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=9040"target=”_blank”>この本の紙版「カルコゲナイド系層状物質の最新研究(普及版)」の販売ページはこちら(別サイトが開きます)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は、2016年当時のものを使用しております。
上野啓司 埼玉大学
安藤淳 産業技術総合研究所
島田敏宏 北海道大学
小間篤 秋田県立大学
柳瀬隆 北海道大学
グエンタンクン 物質・材料研究機構
岡田晋 筑波大学
菅原克明 東北大学
高橋隆 東北大学
神田晶申 筑波大学
松田一成 京都大学
上野和紀 東京大学
山本真人 大阪大学
塚越一仁 物質・材料研究機構
守谷頼 東京大学
北浦良 名古屋大学
小椋厚志 明治大学
石原聖也 明治大学
若林整 東京工業大学
加藤俊顕 東北大学
金子俊郎 東北大学
吾郷浩樹 九州大学
小林佑 首都大学東京
宮田耕充 首都大学東京
阿澄玲子 産業技術総合研究所
野内亮 大阪府立大学
林賢二郎 (株)富士通研究所
實宝秀幸 (株)富士通研究所
大淵真理 (株)富士通研究所
佐藤信太郎 (株)富士通研究所
森貴洋 産業技術総合研究所
中払周 物質・材料研究機構
蒲江 早稲田大学
竹延大志 名古屋大学
毛利真一郎 立命館大学
河本邦仁 (公財)豊田理化学研究所
万春磊 清華大学
田若鳴 (公財)豊田理化学研究所
藤田武志 東北大学
平岡尚文 ものつくり大学
-------------------------------------------------------------------------
<<目次>>
巻頭言
【第1編 カルコゲナイド系層状物質の種類、構造、基礎物性】
第1章 層状物質とは:その種類と構造、基礎物性
1 はじめに
2 層状物質とは
3 層状物質の基礎物性
4 層状物質の種類
4.1 遷移金属ダイカルコゲナイド
4.2 13族カルコゲナイド
4.3 14族カルコゲナイド
4.4 ビスマスカルコゲナイド
4.5 銅酸化物からなる高温超伝導体
4.6 水酸化2価金属
4.7 ハロゲン化金属
4.8 層状ケイ酸塩(フィロケイ酸塩鉱物)
4.9 層状酸化物
4.10 単原子層状物質と類似化合物
第2章 カルコゲナイド系層状物質の構造と物性
1 はじめに
2 カルコゲナイド系層状物質の主な構造
3 カルコゲナイド系層状物質の固体化学―なぜ層状構造で安定なのか?―
4 電子物性と機能
4.1 valleytronics
4.2 トポロジカル物質
4.3 その他の電子応用
5 触媒機能その他
第3章 電界下印加による二硫化モリブデン薄膜の電子構造変調
1 はじめに
2 計算手法
3 電界下の二硫化モリブデン薄膜の電子構造
4 まとめ
第4章 遷移金属ダイカルコゲナイド原子層薄膜の電子状態
1 はじめに
2 角度分解光電子分光法
3 MBE法による遷移金属ダイカルコゲナイド単層膜の作製
4 MoSe2およびWSe2単層膜の高分解能ARPES
5 WSe2単層膜のスピン分解ARPES
6 今後の展望
第5章 超伝導層状カルコゲナイド/グラフェン接合
1 はじめに
2 超伝導体/グラフェン接合におけるアンドレーエフ反射:理論的側面
3 超伝導体/グラフェン接合におけるアンドレーエフ反射:実験的側面
3.1 電子/ホールだまり
3.2 超伝導体からの電荷ドープ
4 超伝導層状カルコゲナイド/グラフェン接合
5 まとめと今後の展望
第6章 単層遷移金属ダイカルコゲナイドの光学的性質
1 はじめに
2 遷移金属ダイカルコゲナイドの電子状態
3 バルクから単層遷移金属ダイカルコゲナイドの電子状態
4 遷移金属ダイカルコゲナイドの光学スペクトル
5 単層MoS2のバレー分極現象
6 単層遷移金属ダイカルコゲナイドの光吸収特性
7 単層遷移金属ダイカルコゲナイドの発光特性
8 化学ドーピングによる単層遷移金属ダイカルコゲナイドの光学制御
9 単層遷移金属ダイカルコゲナイドの発光効率
10 まとめ
第7章 電場誘起超伝導
1 はじめに
2 電場誘起によるキャリアドーピングと超伝導
2.1 電気二重層トランジスタ
2.2 電気二重層トランジスタを用いた層状化合物半導体の電場誘起キャリアドーピング
2.3 キャリアドーピングによる超伝導
3 層状物質の電場誘起超伝導
3.1 ZrNCl の電場誘起超伝導
3.2 MoS2 の電場誘起超伝導
3.3 その他の遷移金属ダイカルコゲナイドの超伝導
第8章 遷移金属ダイカルコゲナイドのラマン分光
1 はじめに
2 結晶構造と振動モード
3 ラマンシフトの層数依存性
4 ラマン活性の層数依存性
5 おわりに
【第2編 合成・構造制御】
第1章 カルコゲナイド系層状物質の単結晶成長とその応用
1 はじめに
2 TMDCの構造
3 TMDCのバルク単結晶成長
3.1 石英アンプルの準備
3.2 原料と輸送剤の準備
3.3 石英アンプルへの原料真空封入
3.4 管状炉での石英アンプル加熱
3.5 加熱後の冷却、試料取り出しと洗浄
4 TMDC単結晶からの原子層FET形成
5 ファンデルワールス・エピタキシー
6 おわりに
第2章 カルコゲナイド系層状物質単結晶の劈開と転写によるヘテロ接合形成1 はじめに
2 歴史
3 劈開
3.1 ①テープの上に層状物質の結晶をのせる
3.1.1 バルク結晶の結晶粒の大きさ
3.1.2 テープを選ぶ
3.1.3 テープの上への結晶ののせ方
3.2 ②テープで結晶を劈開し薄片化する
3.3 ③基板にテープを押し付ける
3.3.1 基板の表面処理
3.3.2 テープのこすりつけ方
3.4 ④テープを剥がして結晶を劈開する
3.5 テープを使用しない劈開法
4 転写法
4.1 乾式転写法(Dry transfer)
4.2 乾式剥離法(Dry release)
4.3 スタンピング法(Stamping)
5 まとめ
第3章 カルコゲナイド系層状物質薄膜のボトムアップ成長
1 はじめに
2 CVD法によるTMDCの成長
3 ツーステップCVD法によるTMDC原子層の成長
4 ワンステップCVD法によるTMDC原子層の成長
5 hBN基板へのTMDCのCVD成長
6 TMDCのMBE成長
第4章 カルコゲナイド系層状物質薄膜のスパッタ成長
1 はじめに
2 スパッタMoS2の膜構造
3 スパッタMoS2の電気特性
4 スパッタMoS2の結晶性と化学状態
5 スパッタMoS2の硫黄欠損補填による膜質向上
6 おわりに
第5章 単層単結晶遷移金属ダイカルコゲナイドの大結晶合成とプラズマ機能化
1 はじめに
2 単層単結晶TMDの大結晶合成
3 不純物添加TMDにおける局在励起子の観測
4 マイルドプラズマ機能化による二層TMDの発光強度増大
5 まとめ
第6章 グラフェン上でのカルコゲナイド系層状物質のCVD成長
1 はじめに
2 グラフェン上でのNbS2のCVD成長
3 グラフェン上でのMoS2のCVD成長
4 グラフェンナノリボン上でのMoS2のCVD成長
5 MoS2/グラフェンのヘテロ構造のデバイス応用
6 MoS2によるグラフェンのグレイン構造の可視化への応用
7 おわりに
第7章 カルコゲナイド系層状物質薄膜を用いた層内/層間ヘテロ接合形成
1 はじめに
2 TMDC原子層の化学気相成長
3 TMDC原子層/グラファイト層間ヘテロ接合の作製と光学的性質
4 Mo/W系TMDCの層内/層間ヘテロ接合の作製
5 Nb/W系TMDCの層内ヘテロ接合の作製
6 おわりに
第8章 液相単層剥離によるカルコゲナイド系層状物質原子層形成
1 はじめに
2 試薬を用いたインターカレーションによる単層剥離法
3 電気化学的なインターカレーションによる剥離法
4 極性有機溶媒や界面活性剤を用いた単層剥離法
5 前駆体を用いたナノシートの液相合成法
6 まとめ
第9章 金属/カルコゲナイド系層状物質接合形成におけるエッジ効果
1 はじめに
2 Schottky障壁高さの実験的抽出
2.1 抽出方法
2.2 抽出過程の例:多層MoS2へのCr/Au電極接合
2.3 チャネル幅依存性によるエッジ効果の確認
3 エッジ効果のモデル化
3.1 バンドの曲がりの定式化
3.2 計算結果の例:多層MoS2への電極接合
4 おわりに
第10章 Al2O3(0001)面上のMoS2成長と理論的考察
1 はじめに
2 多結晶Al2O3基板を用いたMoS2の優先的成長の観察
3 Al2O3(0001)面基板上に成長したMoS2のモルフォロジー
4 おわりに
【第3編 応用】
第1章 カルコゲナイド系層状物質の極薄ボディMOSFET応用
1 MOSFET技術
2 カルコゲナイド系層状物質MOSFET
3 カルコゲナイド系層状物質MOSFETにおける散乱要因
3.1 音響フォノン散乱
3.2 光学フォノン散乱
3.3 フォノン散乱への高誘電率ゲート絶縁膜の影響
3.4 帯電不純物散乱
3.5 ラフネス散乱
4 実験による散乱要因検討
4.1 電界効果移動度の温度依存性評価
4.2 実効移動度評価
5 まとめ
第2章 遷移金属ダイカルコゲナイド半導体α-MoTe2のトランジスタ極性制御
1 はじめに
2 遷移金属ダイカルコゲナイド(TMDC)半導体のトランジスタ応用の利点と課題
3 α相二テルル化モリブデン(α-MoTe2)の新しいトランジスタへの応用
4 α相二テルル化モリブデン(α-MoTe2)ショットキー接合の両極性キャリア注入
5 まとめ
第3章 カルコゲナイド系層状物質を用いた電気二重層トランジスタ
1 はじめに
2 遷移金属ダイカルコゲナイド(TMDC)薄膜
3 電気二重層トランジスタ(EDLT)
4 イオンゲルを用いたTMDC EDLT
4.1 大面積単層TMDC EDLT
4.2 フレキシブル・ストレッチャブルTMDC EDLT
4.3 フレキシブル単層TMDCインバータ
5 EDLTによる新機能素子
5.1 熱電変換機能の制御
5.2 単層TMDCフォトダイオード
5.3 単層TMDC発光ダイオード
6 まとめ
第4章 光電変換材料としての遷移金属カルコゲナイド
1 はじめに―光電変換材料としての遷移金属カルコゲナイド―
2 遷移金属ダイカルコゲナイドを利用したヘテロ構造太陽電池とその光電変換特性
2.1 CVD法による大面積MoS2薄膜合成とその特性評価
2.2 熱剥離テープによる薄膜転写技術
2.3 グラフェン/MoS2/n-Si太陽電池作製手順
2.4 グラフェン/MoS2/n-Si太陽電池の特性測定
2.5 グラフェン/MoS2/n-Si太陽電池の発電機構
3 今後の展望
第5章 カルコゲナイド系層状物質のスピントロニクス応用
1 はじめに
2 層状物質とスピントロニクス
3 層状物質強磁性体
4 まとめ
第6章 カルコゲナイド系層状物質を用いた熱電変換素子
1 はじめに
2 TiS2
3 電気化学インターカレーションによるTiS2/有機複合超格子の構築
4 TiS2/有機複合超格子の組成と構造
5 極性有機分子の静電遮蔽効果によるキャリア移動度のチューニング
6 大誘電率の極性分子H2OのインターカレーションによるZTの向上
7 キャリア濃度の低減による高ZT化
8 フレキシブルn型熱電変換材料の熱電応用
第7章 カルコゲナイド系層状物質の水素発生触媒としての展開
1 はじめに
2 リチウムを利用した化学剥離
3 透過電顕による原子分解能観察
4 水素発生触媒
5 おわりに
第8章 カルコゲナイド系層状物質のトライボロジー応用
1 固体潤滑剤としてのカルコゲナイド系層状物質
2 潤滑剤としての性質
2.1 潤滑メカニズム
2.2 雰囲気の影響
2.3 温度の影響
3 用法
3.1 粉体
3.2 被膜
3.2.1 焼成被膜
3.2.2 スパッタリング膜
3.2.3 ショット処理
3.2.4 その他
3.3 添加剤・充てん剤
3.3.1 潤滑油への添加
3.3.2 樹脂等への充てん
3.4 潤滑油添加剤からの生成
4 応用例
第9章 カルコゲナイド原子膜半導体におけるキャリアの注入と散乱
1 はじめに
2 原子膜伝導における電気伝導の原子層数依存性
2.1 本研究のために作製した試料と計測
2.2 電流注入の層数依存性に関して
2.3 伝導の層数依存性に関して
3 考察と対策
-

再生医療等製品の開発と実用化展望《普及版》
¥4,180
2016年刊「再生医療等製品の開発と実用化展望」の普及版。培養容器、足場材料、培地技術など再生医療等製品製造を支える多くの材料・機器を解説した1冊!
(編集:シーエムシー出版編集部)
<a href="http://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=9039"target=”_blank”>この本の紙版「再生医療等製品の開発と実用化展望(普及版)」の販売ページはこちら(別サイトが開きます)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は、2016年当時のものを使用しております。
毛利善一 再生医療イノベーションフォーラム
添田麻由実 医薬基盤・健康・栄養研究所
佐藤陽治 国立医薬品食品衛生研究所
丸山良亮 医薬品医療機器総合機構
早川堯夫 近畿大学
井家益和 (株)ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング
鮫島正 テルモ㈱
黒柳能光 (有)テクノサージ
菅原桂 (株)ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング
佐藤正人 東海大学
佐藤千香子 (株)セルシード
原井基博 富士ソフト㈱
宮下英之 慶應義塾大学
榛村重人 慶應義塾大学
辻川元一 大阪大学
竹谷健 島根大学
弓場俊輔 産業技術総合研究所
大串始 朗源会大隈病院
酒井佳夫 金沢大学
金子周一 金沢大学
黒田正幸 千葉大学
横手幸太郎 千葉大学
西河芳樹 (株)メガカリオン
赤松健一 (株)メガカリオン
江藤浩之 京都大学
藤田靖之 先端医療振興財団
川本篤彦 先端医療振興財団
岩田隆紀 東京女子医科大学
濵園俊郎 (株)再生医療推進機構
篠原奈美子 (株)再生医療推進機構
腰野蔵人 東京女子医科大学
金井信雄 東京女子医科大学
久保忠彦 広島大学
古田太輔 広島大学
Muhammad Phetrus Johan 広島大学
中島裕子 広島大学
安達伸生 広島大学
越智光夫 広島大学
杉田孝 尾道総合病院
馬場憲三 日本ジェネティクス㈱
今松伸介 ㈱リンフォテック
田川陽一 東京工業大学
塚田亮平 住友ベークライト㈱
松田博行 藤森工業㈱
池内真志 東京大学
橋本朋子 奈良女子大学
山岡哲二 国立循環器病研究センター研究所
野口洋文 琉球大学
朝倉哲郎 東京農工大学
斉藤美佳子 東京農工大学
菊地鉄太郎 東京女子医科大学
清水達也 東京女子医科大学
-------------------------------------------------------------------------
<<目次>>
【総論編】
第1章 再生医療等製品の開発と実際(概論)
1 はじめに
2 再生医療・細胞治療の臨床研究から企業開発への動向
3 再生医療イノベーションフォーラム
第2章 再生医療実用化促進を目指した規制の整備
1 はじめに
2 再生医療関連法
2.1 薬機法
2.2 再生医療等安全確保法
3 再生医療等に関する省令・基準
3.1 GCTP省令(Good gene、Cell & Tissue Practice)
3.2 生物由来原料基準
3.2.1 動物細胞組織原料
3.2.2 反芻動物由来原料
3.2.3 承認された医薬品等の利用
3.2.4 ヒト由来原料等を作製する作業の記録
4 おわりに
第3章 再生医療等製品の承認審査
1 はじめに
2 開発の動向
3 製造販売承認申請
4 承認審査の流れ
5 ヒト細胞加工製品の承認審査における留意事項
5.1 品質
5.2 非臨床安全性
5.3 臨床
6 おわりに
第4章 再生医療の産業化促進と課題
1 はじめに
2 細胞研究から医療ニーズをふまえた再生医療製品候補をいかに探索していくか
3 製品候補の品質・安全性・有効性に関する試験・評価をいかに実施していくか
4 再生医療製品の製造販売承認申請に行政は科学的、医療的、倫理的ひいては国民の保健衛生向上の観点からいかに対処していくか
5 より多くの再生医療製品の産業化に必要な要素
5.1 企業の責務
5.2 費用対効果
5.3 開発対象
5.4 産業化を社会的理解、認知のもとでより適切に進めていくための要件
6 高度な医療技術を少なからず必要とする臨床適用をいかに達成するか、また、経験知の蓄積とその活用をいかにはかっていくか
7 適切な規制環境の整備とその運用をいかにはかるか
8 今後の展望
9 おわりに
【疾病別開発動向編】
第5章 移植片対宿主病治療薬「テムセル(R)HS注」の開発
1 会社沿革と概要
2 細胞医療製品開発
2.1 確認申請
2.2 製造工程
2.3 品質評価
2.4 非臨床試験
2.5 第I/III相試験
2.6 第II/III相臨床試験
3 海外状況と今後の展開
第6章 自家培養表皮
1 はじめに
2 製品開発
2.1 レギュレーション
2.2 製品コンセプト
2.3 製品仕様
2.4 製造法
2.5 製品検査
2.6 ロジスティック
2.7 治験と承認
3 上市後
3.1 保険算定
3.2 使用成績調査
4 適応拡大
4.1 先天性巨大色素性母斑
4.2 表皮水疱症
5 次世代の製品開発
5.1 メラノサイトを含む新型自家培養表皮
5.2 同種培養表皮
6 新法対応
7 海外の動向
8 おわりに
第7章 ヒト(自己)骨格筋由来細胞シート
1 はじめに
2 製品と治験の概要
3 開発経験からの課題
4 これからの再生医療製品の開発
第8章 細胞成長因子を応用した皮膚再生
1 創傷治癒と皮膚再生
2 浅達性および深達性創傷の治癒過程
3 皮膚再生製品の種類と機能
4 最先端医療を可能にする皮膚再生医療製品:同種培養真皮
5 汎用の皮膚再生医療製品:創傷被覆材と皮膚ケア材
6 美容皮膚科領域をターゲットとしたEGF含有皮膚ケア材
7 皮膚再生医療分野の科学的な進歩と実用化における問題点
8 最先端医療から通常の医療へ:製品化の優先順位
第9章 自家培養軟骨
1 日本の再生医療製品をとりまく状況とその変化
2 関節疾患における軟骨再生医療の重要性
3 世界の培養軟骨技術
4 日本国内の培養軟骨技術
5 自家培養軟骨ジャックの開発と普及の課題
6 今後の展望
第10章 軟骨細胞シートによる関節軟骨の再生治療
1 再生医療を取り巻く市場環境
2 細胞シート工学
3 軟骨再生への取り組み
4 軟骨細胞シートの実用化
5 今後の展望
第11章 インプラント型再生軟骨の研究開発から戦略相談を経て企業治験許可までを経験して
1 再生医療への取り組み
2 インプラント型自己細胞再生軟骨について
3 薬事戦略相談対面助言について(相談項目及び対応は一部分のみ紹介)
3.1 品質試験に関する相談
3.1.1 輸送液の抗生物質量の見直しについて
3.2 非臨床試験に関する相談
3.2.1 標準培養期間を超えた期間の設定の妥当性について
3.2.2 性能、安定性および耐久性の評価を行う動物試験について
3.3 治験に関する相談
3.3.1 本試験を非対照試験として実施することについて
3.3.2 本試験の症例数について
4 企業治験
5 薬事戦略相談で再生医療製品開発企業として学んだ事項
6 再生医療製品開発についての考え方(当社として)
第12章 角膜上皮細胞シート
1 概要
2 角膜上皮幹細胞疲弊症と培養上皮移植
3 上皮細胞シートの細胞源
4 上皮細胞シートの培養基質
5 上皮細胞の調整法および継代の有無
6 フィーダーレイヤーおよび血清と上皮細胞シート
7 上皮細胞シートと成長因子およびROCK阻害剤の効果
8 規制の発展と上皮細胞シートの今後
第13章 角膜上皮の再生医療
1 はじめに
2 角膜上皮の再生医療
第14章 重症低ホスファターゼ症に対する骨髄移植併用同種間葉系幹細胞移植
―先天性骨系統疾患への間葉系幹細胞治療の展望―
1 要旨
2 背景
3 低フォスファターゼ症とは
4 低フォスファターゼ症に対する細胞治療
5 他の先天性骨系統疾患に対する同種間葉系幹細胞移植
6 MSCTの有害事象
7 今後の同種間葉系幹細胞を用いた治療
第15章 脂肪組織由来再生(幹)細胞による肝再生治療法の開発
1 はじめに
2 非臨床試験
3 安全性臨床試験
4 実用化にむけた今後の取り組み
5 おわりに
第16章 遺伝子導入脂肪細胞の移植による持続的酵素補充療法-家族性LCAT欠損症を対象とした治療法開発と難治性疾患への応用展開―
1 はじめに
2 遺伝子治療による酵素補充療法
3 遺伝子治療用脂肪細胞
4 LCAT欠損症
5 LCAT欠損症治療に用いる遺伝子導入脂肪細胞の調製
6 遺伝子導入脂肪細胞移植治療の実用化に向けて
7 おわりに
第17章 iPS由来同種血小板輸血製剤の製法
1 はじめに
2 Promegakaryoblast(巨核球前駆細胞)に相当するまで分化した株を不死化しマスターセルバンク(MCB)とする。
3 MCBの細胞を培養し109レベルまで増殖させる。培地交換することにより多核化を促しproplateletを経て1011レベルの血小板を放出させる。
4 生成された血小板の精製、濃縮、製剤化
5 最終製剤の特性解析と規格設定
第18章 下肢血管再生治療
1 はじめ
2 CLIの病態・疫学・治療
3 EPCの特性・体内動態・生理学的重要性
4 EPC移植による下肢血管再生の前臨床試験
5 CLIに対する血管再生療法の第I/IIa臨床試験
6 CD34陽性細胞分離機器に関する医療機器医師主導治験
7 CD34陽性細胞の再生医療等製品としての薬事承認を目指した企業治験計画
8 最後に
第19章 歯根膜細胞シートによる歯周組織再生
1 はじめに
2 我が国における歯周疾患罹患率の現状
3 歯周組織再生の歴史と現状
4 歯周組織治療用細胞シートに関する評価指標
5 臨床研究「自己培養歯根膜細胞シートを用いた歯周組織の再建」
6 同種細胞への移行
7 同種再生医療等製品を製造する際に必要な検討事項
7.1 ドナースクリーニングとマスターセルバンクの構築
7.2 ワーキングセルバンクと最終製品の検査
7.3 最終製品の出荷方法と安定性の確認
7.4 非臨床安全性試験
7.5 臨床プロトコールの設定
8 歯周領域におけるその他の臨床試験・治験の実際
9 今後の展開
第20章 歯髄細胞バンク&DP(歯髄細胞=Dental Pulp)ストック
1 歯髄細胞バンク&ストック事業について
2 再生医療における細胞ソースとしての歯髄細胞のメリット
第21章 食道上皮再生シート製品の開発
1 現在の再生医療
2 食道がん治療の課題、食道再生シート
3 これまで日本欧州での展開
4 Cell-tissue-productsの移植器具、移植用周辺機器
5 今後の展開
【製造技術・支援技術編】
第22章 磁性体封入カプセル・磁性体標識細胞
1 はじめに
2 ドキソルビシン封入磁性体リポソーム
3 磁気ビーズ標識NK細胞
4 おわりに
第23章 再生医療用保存液の開発
1 はじめに
2 緩慢凍結法とは
3 ガラス化凍結法とは
4 現在までの我が国におけるヒトiPS/ES細胞の凍結保存法
5 再生医療用細胞の凍結保存液に求められる条件とは
6 今後に向けて
第24章 再生医療研究支援のための培養容器
1 ライフサイエンスにおける当社のあゆみ
2 高水準の品質管理がなされた培養器材
3 タンパク質吸着抑制表面処理を施した培養器材
3.1 凝集塊培養用培養容器
3.2 スリットウェルプレート
3.3 高効率細胞回収用遠沈管
4 おわりに
第25章 幹細胞培養容器と材料
1 はじめに
2 幹細胞培養で使用される工程資材
3 シングルユース工程資材の材質
4 工程資材のリスクアセスメント
5 工程資材のリスク
5.1 工程資材の細胞培養への影響
5.1.1 溶出物
5.1.2 不溶性微粒子および不溶性異物
5.1.3 エンドトキシンおよび微生物
5.2 工程資材の安定供給
5.3 工程資材の管理
6 動物細胞の培養装置について
6.1 シングルユース培養装置
6.2 シングルユース培養装置の使用上の注意点
6.3 シングルユース培養バッグによる動物細胞培養例
6.4 シングルユース動物細胞培養バッグを使用する利点
6.5 シングルユース培養槽の再生医療への応用
6.6 シングルユース培養槽の課題
7 おわりに
第26章 膜マイクロファブリケーション・デバイス技術
1 はじめに
2 胚様体自動生産デバイス「PASCL」
3 生分解性薄膜を用いた微細流路網
4 おわりに
第27章 組織再生用繊維性スキャホールド
1 はじめに
2 繊維性スキャホールドの作製法
3 構造特性・バルク特性
4 表面特性
4.1 物理化学的特性
4.2 生理活性の付与
5 生体由来材料を用いた繊維性創傷被覆材
6 PLAナノファイバー神経誘導管
7 おわりに
第28章 無血清・アニマルフリー培地
1 はじめに
2 ES/iPS細胞用培地
3 間葉系幹細胞用培地
4 おわりに
第29章 絹を用いた再生医療材料の開発
1 はじめに
2 再生医療材料としての家蚕絹フィブロインの利点
3 再生医療の用途に合わせた家蚕絹フィブロインのプロセッシング
4 絹を用いた人工血管の開発
5 絹を用いた人工角膜の開発
6 絹スポンジを用いた人工耳軟骨の開発
7 おわりに
第30章 単一細胞からの組織の創製を支えるフェムトインジェクション技術
1 はじめに
2 ギャップジャンクションを介した細胞間コミュニケーションの解析の意義
3 フェムトインジェクション技術の現状
3.1 開発の契機
3.2 SMSRの機能の概要
3.3 フェムトインジェクションの実現
3.4 完全自動化を目指す要素技術
4 フェムトインジェクションを基盤技術としたCxのグローバル解析
5 おわりに
第31章 臓器ファクトリーの創製
1 はじめに
2 再生医療等製品の製造施設の抱える課題
2.1 プロセスの再現性
2.2 スケーラビリティー
2.3 フレキシビリティー
3 再生医療向け自動培養装置の抱える課題
4 細胞操作アイソレーター
5 フレキシブル・モジュラー・プラットフォーム
6 組織ファクトリー
7 臓器ファクトリーの創製
8 今後の展開
-

次世代蛍光体材料の開発《普及版》
¥4,400
2016年刊「次世代蛍光体材料の開発」の普及版。高色純度、あるいは環境配慮型の蛍光体材料など、市場が拡大している蛍光体材料の技術とその応用展開を詳説した1冊!
(監修:磯部徹彦)
<a href="http://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=9002"target=”_blank”>この本の紙版「次世代蛍光体材料の開発(普及版)」の販売ページはこちら(別サイトが開きます)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は、2016年当時のものを使用しております。
磯部徹彦 慶應義塾大学
武田隆史 物質・材料研究機構
佐藤泰史 岡山理科大学
冨田恒之 東海大学
小林亮 東北大学
加藤英樹 東北大学
垣花眞人 東北大学
金善旭 新潟大学
長谷川拓哉 新潟大学
戸田健司 新潟大学
佐藤峰夫 新潟大学
大倉央 メルク(株)
石垣雅 鳥取大学
大観光徳 鳥取大学
三上昌義 (株)MCHC R&Dシナジーセンター
正岡顕一郎 日本放送協会
楠木常夫 デクセリアルズ(株)
伊藤靖 デクセリアルズ(株)
宮永昭治 NSマテリアルズ(株)
和泉真 シャープ(株)
吉村健一 シャープ(株)
小笠原一禎 関西学院大学
島村清史 物質・材料研究機構
Encarnacion G Villora 物質・材料研究機構
猪股大介 (株)タムラ製作所
飯塚和幸 (株)タムラ製作所
吉川彰 東北大学
神隆 理化学研究所
上田純平 京都大学大学院
田部勢津久 京都大学大学院
徐超男 産業技術総合研究所
立山博 産業技術総合研究所
松枝直人 愛媛大学大学院
松嶋雄太 山形大学
磯由樹 慶應義塾大学
王浩浩 東京工業大学
和田裕之 東京工業大学
-------------------------------------------------------------------------
<<目次>>
【第1編 次世代蛍光体の探索法】
第1章 単粒子診断法
1 はじめに
2 新蛍光体母体を用いた新蛍光体開発
3 単粒子診断法
4 単粒子診断法を用いた新蛍光体開発の実際
4.1 Ba3N2‐Si3N4‐AlN擬三元系
4.2 Ba3N2‐Si3N4‐AlN‐Li3N擬四元系
5 まとめと展望
第2章 結晶サイト工学を用いた蛍光体の物質探索法―Eu2+賦活オルソシリケート蛍光体を例として―
1 はじめに
2 「結晶サイト工学」の概念と蛍光体物質探索への適用
3 試料の合成手順と評価方法
4 結晶サイト工学を用いた新規酸化物蛍光体の探索と発光特性の評価
4.1 Ca2SiO4系における結晶多形とその制御
4.2 Eu2+賦活Ca2SiO4でのβ→α′L相転移と発光波長の長波長シフト
4.3 高濃度Eu2+賦活α′L‐Ca2SiO4における赤色発光の発現
4.4 Eu2+を高濃度に賦活したα′L‐Ca2SiO4の赤色発光とEu2+が占有する結晶サイトとの関係
4.5 Eu2+を高濃度に賦活したα′L‐Ca2SiO4の赤色発光の起源
4.6 Sr2SiO4:Eu2+における結晶サイトと発光波長の長波長化
5 おわりに
第3章 メルト合成法による白色LED用新規蛍光体の高速探索法
1 はじめに
2 メルト法
3 集光炉(光溶融アークイメージ炉)
4 メルト法による新規蛍光体の高速探索
第4章 マイクロリアクター法による組成・合成条件の最適化法
1 はじめに
2 MR・コンビナトリアル合成装置の特徴
3 MR・コンビナトリアル合成装置を利用した新規多元化合物蛍光体の探索例
4 MR法によるYAG:Ceの合成と粒子サイズの制御
5 MR法によるYVO4:Bi,Euナノ粒子蛍光体の合成
6 まとめ
第5章 理論的探索法
1 はじめに
2 Ce3+/Eu2+ 4f・5d準位の決定要因
3 母体硬さと温度特性に関する再考
4 Eu2+/Ce3+付活モデル計算によるアプローチ
4.1 Ba3Si6O12N2:Eu2+とBa3Si6O9N4:Eu2+の場合
4.2 La3Si6N11:Ce3+とLaSi3N5:Ce3+の場合
5 今後の方向性に関する私見
【第2編 次世代エレクトロニクス用蛍光体】
第1章 UHDTV広色域表色系とディスプレイの設計
1 はじめに
2 UHDTV表色系
2.1 要求条件
2.2 広色域化の方法選定
2.3 設計
2.3.1 現行映像システムの色域包含
2.3.2 等色相条件
2.3.3 デバイス実現可能性
2.4 標準化
3 広色域ディスプレイの開発
3.1 非単波長RGB光源の色度シミュレーション
3.2 実在する色の包含
4 色域包含率計算基準
5 まとめ
第2章 広色域LCDを実現する蛍光体シート
1 はじめに
2 広色域を実現する為の蛍光体シートの活用
3 硫化物蛍光体シートとその特性
4 色域と輝度効率の両立
5 蛍光体シート用硫化物蛍光体について
6 硫化物蛍光体合成方法
7 硫化物蛍光体光学特性
7.1 発光特性
7.2 温度特性
8 信頼性
9 おわりに
第3章 次世代ディスプレイを実現する量子ドット蛍光体
1 はじめに
2 量子ドットとは
3 QDの作製と設計
4 液晶ディスプレイ(LCD)向け白色バックライトへのQD応用
5 量子ドットを用いた直接発光型ディスプレイQLED(量子ドットLED)について
6 課題とまとめ
第4章 フッ化物赤色KSF蛍光体:バックライトLEDへの適用
1 はじめに
2 KSF蛍光体(K2SiF6:Mn4+)
3 KSF蛍光体の液晶バックライトLED応用
4 Sharp βサイアロン蛍光体とKSF蛍光体を組み合わせたバックライトLED
4.1 Sharp βサイアロンの合成
4.2 ディスプレイ特性の試算
4.3 KSF蛍光体とSharp βサイアロン蛍光体を用いたバックライトLEDの試作
5 おわりに
第5章 新規Mn4+賦活酸化物蛍光体の材料設計に向けた多重項エネルギーダイアグラムの第一原理計算に基づく構築
1 はじめに
2 d3イオンのエネルギー準位構造
3 第一原理計算によるダイアグラムの作成
4 DVME法
5 CrO6クラスターのダイアグラム
6 共有結合性と電子相関の効果
7 MnO6クラスターのダイアグラム
8 おわりに
第6章 高輝度白色照明用の単結晶蛍光体
1 はじめに
2 単結晶蛍光体という新しいコンセプト:単結晶蛍光体
3 黄色の単結晶蛍光体
4 緑色の単結晶蛍光体
5 赤色の単結晶蛍光体を目指して
6 粉末状単結晶蛍光体
7 高強度青色照射下での温度安定性
8 まとめ
【第3編 次世代機能性蛍光体】
第1章 放射線検出用無機シンチレータ
1 はじめに
2 シンチレータ(scintillator)
2.1 無機シンチレータの発光原理
2.2 X線、γ線用シンチレータ
2.2.1 NaI、CsI単結晶
2.2.2 CWO、PWO単結晶
2.2.3 BGO単結晶
2.2.4 希土類5d‐4f遷移Ce系、Pr系、Eu系単結晶
2.2.5 高速応答する無機シンチレータ結晶
2.2.6 セラミックス
第2章 近赤外蛍光イメージング用量子ドット
1 はじめに
2 近赤外発光量子ドットの合成法
2.1 CdSeTe/CdS量子ドット
2.2 PbS量子ドット
3 生体蛍光イメージングへの応用1 (生体の第1光学窓)
4 生体蛍光イメージングへの応用2 (生体の第2光学窓)
4.1 リンパ節
4.2 脳血管
4.3 免疫細胞
5 おわりに
第3章 青色蓄光可能なCe3+添加ガーネット長残光蛍光体
1 長残光蛍光体とは
2 長残光蛍光体の課題
2.1 蓄光可能励起波長の長波長化
2.2 残光色のバリエーション
2.3 長残光輝度と残光時間の向上
2.4 化学的耐久性
3 Ce3+添加ガーネット蛍光体
4 電子トラップ中心
5 Y3Al5‐xGaxO12:Ce3+‐Cr3+長残光蛍光体
6 おわりに
第4章 応力発光体の誕生からその応用展開
1 はじめに
2 応力発光のメカニズム
3 紫外光から近赤外光まで発光する応力発光体の多色性
4 応力発光センサの測定原理
5 応力発光センサの種類
6 応力発光センサを用いた応力発光計測システムの構築
7 金属構造体の破壊予知のための応力発光計測システムを用いた疲労亀裂の可視化
8 トンネル内岩盤崩落予知を目的とした応力発光計測システムによる安全管理
9 応力計測システムを用いた供用中の橋梁リアルタイム監視
10 地震に対する応力発光計測システムを用いた構造体の損傷評価
11 今後の展開
第5章 レアアースフリー銀含有ゼオライト蛍光体
1 はじめに
2 ゼオライトの構造および性質
3 銀担持ゼオライトの発光挙動
3.1 銀クラスターの発光
3.2 銀担持ゼオライトの発光
第6章 レアアースフリー3d遷移金属蛍光体
1 3d遷移金属蛍光体と希土類蛍光体
2 代表的な3d遷移金属蛍光体
2.1 d‐d遷移に基づく3d遷移金属蛍光体: 発光中心 Cr3+, Mn2+, Mn4+, Fe3+
2.2 バナジン酸塩化合物蛍光体: 発光中心 VO43‐, V2O74‐, VO3‐
2.3 酸化亜鉛蛍光体
3 青色光(450 nm)励起への応用
4 最後に
【第4編 次世代ナノ蛍光体】
第1章 CdフリーCuInS2量子ドット
1 CIS量子ドットの蛍光メカニズム
2 CIS量子ドットの液相合成
3 CIS量子ドットの高耐光性化
4 まとめ
第2章 ドープ型量子ドット
1 はじめに
2 成長ドーピング法
3 核生成ドーピング法
4 まとめ
第3章 ナノシート蛍光体
1 はじめに
2 ナノシート蛍光体の作製方法
2.1 ボトムアップ法
2.2 トップダウン法
3 ナノシート蛍光体を利用した波長変換膜の作製事例
4 ナノシート蛍光体の展望
第4章 酸窒化物・窒化物ナノ蛍光体 Oxynitride and Nitride Nanophosphor
1 はじめに
2 Ca2Si5N8:Eu2+,Tm3+ナノ粒子
2.1 ナノ粒子生成
2.2 光学特性
3 Ca‐α‐SiAlON:Eu2+ナノ粒子
3.1 ナノ粒子生成
3.2 光学特性
4 AlN:Eu2+ナノ粒子
4.1 ナノ粒子生成
4.2 光学特性
5 応用
6 まとめ
-

ポリフェノール:機能性成分研究開発の最新動向《普及版》
¥4,840
2016年刊「ポリフェノール:機能性成分研究開発の最新動向」の普及版。食品素材としてのポリフェノール研究の最前線について第一線の研究者が詳述した1冊!
(監修:波多野力、下田博司)
<a href="http://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=9004"target=”_blank”>この本の紙版「ポリフェノール:機能性成分研究開発の最新動向(普及版)」の販売ページはこちら(別サイトが開きます)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は、2016年当時のものを使用しております。
波多野力 岡山大学
下田博司 オリザ油化㈱
田中隆 長崎大学
松尾洋介 長崎大学
伊東秀之 岡山県立大学
天倉吉章 松山大学
好村守生 松山大学
谷口抄子 岡山大学
下津祐樹 岡山大学
坂上宏 明海大学
阿部尚仁 岐阜薬科大学
室田佳恵子 近畿大学
津田孝範 中部大学
石丸幹二 佐賀大学
下田昌弘 sainome㈱
難波文男 フジッコ㈱
芦田均 神戸大学
山下陽子 神戸大学
戸田一弥 オリザ油化㈱
倉重(岩崎)恵子 ㈱明治フードマテリア
野口治子 東京農業大学
遠藤伸 ㈱林原
吉村麻紀子 サントリービジネスエキスパート㈱
中村淳一 サントリービジネスエキスパート㈱
森川敏生 近畿大学
二宮清文 近畿大学
天海智博 ニチモウバイオティックス㈱
神谷智康 ㈱東洋新薬
橋本博之 築野食品工業㈱
澤田一恵 築野食品工業㈱
松木翠 築野食品工業㈱
矢内隆章 キリン㈱
生田智樹 ㈱山田養蜂場本社
立藤智基 ㈱山田養蜂場本社
織谷幸太 森永製菓㈱
福光聡 日本製粉㈱
間和彦 日本製粉㈱
福田陽一 タヒボジャパン㈱
松村和明 北陸先端科学技術大学院大学
玄丞烋 京都工芸繊維大学
亀井優徳 森永製菓㈱
山田脩平 九州大学
立花宏文 九州大学
吉川伸仁 日本新薬㈱
水品善之 神戸学院大学;小林製薬㈱
松田久司 京都薬科大学
吉川雅之 京都薬科大学
-------------------------------------------------------------------------
<<目次>>
【第Ⅰ編 ポリフェノール研究の最新動向】
第1章 総論:ポリフェノールの化学構造の多様性とタンニン
1 はじめに:ポリフェノールとタンニン
2 ポリフェノールの性質と分類
3 カテキン類
4 プロアントシアニジンと縮合型タンニン
5 ガロイルグルコース類からエラジタンニンへ
6 エラジタンニンオリゴマーとその多様性
7 C配糖体型エラジタンニンとそのオリゴマー
8 カフェー酸誘導体
9 フロロタンニン
10 おわりに
第2章 タンニンの高分子化:柿のタンニン
1 はじめに
2 渋柿の渋味がなくなる理由
3 その他のポリフェノール高分子化
4 まとめ
第3章 計算化学を利用したポリフェノールの立体構造解析
1 はじめに
2 スペクトル計算の手順
2.1 配座探索
2.2 構造最適化
2.3 スペクトル計算
3 エラジタンニンの立体構造解析
3.1 Vescalagin および castalagin
3.2 Quercusnin A および B
3.3 Neostrictinin および strictinin
4 紅茶ポリフェノールの立体構造解析
4.1 Theacitrins
4.2 Oolongtheanins
5 おわりに
第4章 エラジタンニンの生体内挙動とその代謝産物の機能性
1 はじめに
2 エラジタンニンの生体内挙動と代謝産物の同定
3 エラジタンニンおよび関連ポリフェノールとそれら代謝産物の抗酸化作用
4 エラジタンニンおよびその代謝産物のカラゲニン浮腫試験による抗炎症作用
5 おわりに
第5章 フトモモ科植物のタンニンと樹状細胞に対する作用
1 はじめに
2 フトモモ科植物のタンニン
3 フトモモ科植物における大環状型エラジタンニン2量体 oenothein B の分布
4 ヒト樹状細胞を介した免疫系に及ぼすタンニンの影響
5 おわりに
第6章 阿仙薬のポリフェノール成分と品質評価
1 はじめに
2 阿仙薬に含まれるポリフェノール成分の単離
3 阿仙薬の多角的評価
3.1 阿仙薬のバニリン-塩酸法による総フラバン含量の算出および個別定量
3.2 GPCによる高分子成分の分析
3.3 その他の項目について
4 加熱による(+)-catechinの高分子化と 2量体形成過程の検証
5 単離した化合物の構造について
5.1 阿仙薬から単離した新規プロアントシアニジンの構造
5.2 下部ユニットの8位が結合に関与しているchalcane-flavan 2量体
5.3 下部ユニットの6位が結合に関与しているchalcane-flavan 2量体
6 乾燥葉からの成分の単離
7 おわりに
第7章 薬剤耐性菌に作用するポリフェノールとその作用
1 はじめに
2 MRSAに作用する補骨脂のポリフェノール
3 VREに作用する甘草のポリフェノール
4 抗菌作用を有する高分子ポリフェノール
4.1 マンサク科Hamamelis×intermediaの加水分解性タンニン
4.2 クスノキ科テンダイウヤクの高分子プロシアニジン
4.3 高分子量タンニン類の抗菌作用
5 おわりに
第8章 ポリフェノール類の抗腫瘍作用 ― in vitro 評価法を用いた網羅的検証
1 はじめに
2 生体を反映した in vitro 腫瘍選択性の評価法の開発
3 天然及び有機合成化合物の腫瘍選択性
3.1 抗がん剤
3.2 ポリフェノール関連化合物
3.3 その他の有機化合物
3.4 新規抗腫瘍性物質の探索
4 ポリフェノールは, 抗がん剤のケラチノサイト毒性を緩和できるのか?
5 今後の展望
第9章 スチルベンオリゴマーの化学と最近の研究
1 はじめに
2 スチルベノイドとは
3 植物界におけるスチルベノイドの分布
4 スチルベンオリゴマーの生物活性
第10章 フラボノイドの生体利用性研究の最近の進歩
1 はじめに
2 フラボノイドの消化管での動態
3 フラボノイド代謝物のプロファイリング
4 フラボノイドの生体利用性の向上
5 フラボノイドの標的臓器
6 おわりに
第11章 アントシアニン, ベリー類の健康機能
1 はじめに
2 アントシアニンの化学
3 アントシアニン, ベリー類の肥満・糖尿病予防・抑制作用
3.1 肥満
3.2 糖尿病
4 アントシアニン, ベリー類の健康機能と代謝物の関与
5 ヒト介入試験
6 課題と今後の展望
第12章 植物組織培養によるポリフェノール類の生産
1 はじめに
2 Hemiphragma heterophyllum(ゴマノハグサ科)の成分
2.1 茎葉培養系
2.2 毛状根培養系
3 コミカンソウ (Phyllanthus urinaria)(トウダイグサ科)の成分
3.1 茎葉培養系および毛状根培養系の確立とPAP2遺伝子導入
3.2 茎葉培養体および毛状根の成分分析
【第Ⅱ編 食品素材としてのポリフェノールの研究開発】
第1章 タンニン・プロシアニジン
1 ブドウ種子『ノンエンベロープウイルスに対する抗ウイルス作用』
2 月見草種子:ペンタガロイルグルコース
2.1 はじめに
2.2 動物における抗糖尿病作用と作用メカニズム
2.3 ヒトでの有効性
2.4 おわりに
3 黒大豆種皮ポリフェノールの血管に対する作用
3.1 はじめに
3.2 黒大豆ポリフェノール素材『クロノケアSP』の開発
3.3 クロノケアSPの血管内皮機能改善作用
3.3.1 培養細胞試験によるNO産生促進効果の検証
3.3.2 ヒト投与試験(NO産生能促進効果)
3.3.3 培養細胞試験によるTie2活性化作用の検証
3.3.4 ヒト投与試験(むくみ改善効果)
3.3.5 まとめ
3.4 おわりに
4 カカオポリフェノールの抗肥満効果
4.1 はじめに
4.2 プロシアニジン
4.3 肥満がもたらす生活習慣病とチョコレートの効果
4.4 抗肥満効果に関わる鍵分子AMPK
4.5 プロシアニジンによるAMPKのリン酸化
4.6 カカオポリフェノールの抗肥満効果
4.7 まとめ
第2章 アントシアニン
1 MaquiBrightR(マキベリー抽出物)のドライアイ改善作用
1.1 はじめに
1.2 マキベリーの機能性成分
1.3 ドライアイとは
1.4 ドライアイ改善作用(動物モデル試験)
1.5 ドライアイ改善作用(ヒト臨床試験)
1.6 おわりに
2 水抽出型 カシスポリフェノール(AC10)
2.1 はじめに
2.2 水抽出型 カシスポリフェノール(AC10)とは
2.3 水抽出型 カシスポリフェノール(AC10)の特長
2.4 水抽出型 カシスポリフェノール(AC10)による末梢血流サポート機能
2.4.1 安静時の末梢血流サポート機能
2.4.2 タイピング負荷時の末梢血流サポート機能(疲労様症状;肩こり緩和)
2.4.3 冷水負荷時の末梢血流サポート機能(末梢体温維持, 冷え緩和)
2.4.4 顔面の末梢血流サポート機能(疲労様症状;目のクマ緩和)
2.4.5 脳の末梢血流サポート機能
2.4.6 末梢血流サポート機能(末梢血管拡張機能)の作用機序
2.5 水抽出型 カシスポリフェノール(AC10)によるアイケア機能
2.5.1 ピント調節サポート機能, 眼や腰の疲れ緩和
2.5.2 暗所での光感度調節サポート機能
2.5.3 アイケア機能の作用機序
2.6 水抽出型 カシスポリフェノール(AC10)の安全性
2.7 おわりに
3 アスコルビン酸によるアントシアニン色素退色に対する各種化合物の影響
第3章 フラボノイドなど
1 糖転移ヘスペリジン(モノグルコシルヘスペリジン)
1.1 はじめに
1.2 特性
1.3 糖転移ヘスペリジンのビタミンCリサイクル作用
1.4 糖転移ヘスペリジンの血流改善作用
1.5 糖転移ヘスペリジンの皮膚色および肌質改善効果(肌のくすみ改善, 敏感肌緩和)
1.6 おわりに
2 ケルセチン配糖体
2.1 はじめに
2.2 ケルセチンの生理作用
2.2.1 ケルセチンの脂肪分解作用
2.2.2 ケルセチン配糖体のマウス抗肥満作用
2.2.3 ケルセチン配糖体のヒト体脂肪低減作用
2.3 まとめ
3 エバーラスティングフラワーの血糖上昇抑制作用
3.1 はじめに
3.2 エバーラスティングフラワー抽出エキスの抗糖尿病作用
3.2.1 ショ糖負荷マウスモデルを用いた血糖上昇抑制作用
3.2.2 α-グルコシダーゼ阻害活性
3.2.3 DPP-Ⅳ阻害活性
3.2.4 活性寄与成分の探索
3.2.5 TNF-α感受性低減活性
3.3 おわりに
4 ローズヒップ:ティリロサイド
4.1 はじめに
4.2 ローズヒップについて
4.3 ティリロサイドの機能性
4.3.1 糖質加水分解酵素阻害活性および消化管からの糖吸収抑制活性
4.3.2 肝および筋肉における脂肪酸酸化亢進作用
4.4 ローズヒップ抽出物のヒト内臓脂肪量に与える影響
4.5 おわりに
5 機能性表示食品に向けアグリコン型イソフラボンAglyMaxRの特徴と有用性
5.1 はじめに
5.2 大豆イソフラボンについて
5.2.1 大豆イソフラボンの分類と特徴
5.2.2 AglyMaxの特徴
5.3 AglyMaxの機能性とそのエビデンス
5.3.1 更年期症状の緩和
5.3.2 不妊症に向け受精卵の着床サポート
5.3.3 エクオールへの代謝
5.3.4 その他の機能性について
5.4 AglyMaxの安全性
5.5 おわりに
6 体脂肪と肝機能をWサポートする「葛の花エキス」
6.1 はじめに
6.2 「葛の花エキス」とは
6.3 動物試験結果について
6.3.1 遺伝性の肥満2 型糖尿病モデルマウスでの知見
6.3.2 高脂肪食負荷マウスでの知見
6.3.3 高脂肪食とアルコールの同時負荷時の知見
6.3.4 まとめ
6.4 ヒト試験結果について
6.4.1 体脂肪に及ぼす影響
6.4.2 肝機能に及ぼす影響
6.5 安全性について
6.6 おわりに
第4章 フェニルプロパノイドなど
1 フェルラ酸
1.1 フェルラ酸とは
1.2 注目されるフェルラ酸の機能
1.2.1 MSに対する機能
1.2.2 精神疾患に対する機能
1.2.3 その他の機能
1.3 今後の展望
2 ブドウに含まれるレスベラトロール
2.1 はじめに
2.2 赤ワインエキス, レスベラトロールは心臓の機能維持に関与する
2.3 レスベラトロールは動脈硬化の進行を抑制する
2.4 レスベラトロールは糖尿病性の腎障害を抑制する
3 メリンジョ由来レスベラトロール
3.1 はじめに
3.2 メリンジョの成分および規格
3.3 メリンジョの安全性
3.4 メリンジョ飲用時の薬物動態
3.5 メリンジョの機能性
3.5.1 抗菌活性
3.5.2 抗酸化活性
3.5.3 生活習慣病関連
3.5.4 がん関連
3.5.5 免疫関連
3.5.6 美容関連
3.5.7 歯周病関連
3.5.8 抗老化作用
3.5.9 メリンジョ由来レスベラトロールの作用機序
3.6 おわりに
4 パセノールTM(パッションフルーツ種子エキス)の開発
4.1 はじめに
4.2 ピセアタンノールの化学構造と性質
4.3 ピセアタンノールの経口吸収性と生理作用
4.4 ピセアタンノールの血糖値上昇抑制作用
4.5 おわりに
5 オリーブ果実エキス ―マスリン酸―
5.1 はじめに
5.2 オリーブ果実に含まれる様々な成分
5.3 炎症抑制成分「マスリン酸」の同定
5.4 作用メカニズムの解明
5.5 生体での炎症への有効性
5.5.1 浮腫(急性炎症)モデルでの検証
5.5.2 関節炎(慢性炎症)モデルでの検証
5.5.3 軽度ヒザ関節痛を有する中高齢者での検証
5.6 運動との併用による身体機能への影響
5.7 オリーブ果実エキス(マスリン酸)の特長
5.8 食品への応用
5.9 おわりに
6 タヒボのフェニルエタノイド カフェオイル配糖体
6.1 はじめに
6.2 タヒボの有効性
6.3 タヒボのポリフェノール
6.3.1 骨粗鬆症に対する効果
6.3.2 性機能増強に関する効果
6.4 タヒボの抗炎症活性成分
6.5 おわりに
第5章 カテキン
1 緑茶カテキンの再生医療への応用
1.1 はじめに
1.2 臓器・組織保存液
1.3 角膜の保存
1.4 膵島の保存
1.5 保存のメカニズム
1.6 移植免疫反応の阻害作用
1.7 EGCG を用いたガン細胞の増殖阻害並びに抑制作用を有する抗ガン剤
1.8 おわりに
2 「べにふうき」緑茶の食品への利用
2.1 はじめに
2.2 茶葉の加工方法
2.2.1 菓子, 食品に添加する原料として, 茶葉全体または茶葉抽出エキスを使用するか?
2.2.2 茶の苦味・渋味抑制効果の高い食品素材の探索
2.3 おわりに
3 緑茶カテキンのmicroRNA発現調節作用
3.1 緑茶カテキンセンシング
3.2 microRNAとは
3.3 緑茶カテキンEGCGのmiRNA発現調節作用
3.4 緑茶カテキンEGCGのmiRNAを介したがん遺伝子発現抑制作用
3.5 緑茶カテキンEGCGのmiRNA発現調節作用メカニズム
3.6 おわりに
第6章 キサントン
1 α-マンゴスチン
1.1 はじめに
1.2 キサントン化合物の構造
1.3 α-マンゴスチン
1.3.1 抗炎症作用
1.3.2 抗糖化作用
1.3.3 抗腫瘍作用
1.3.4 α-マンゴスチンの吸収と代謝
1.4 おわりに
2 マンゴスチンから得られたキサントン類のDNA合成酵素阻害活性と抗がん作用
2.1 マンゴスチンとは
2.2 マンゴスチンから単離したキサントン類
2.3 キサントン類8物質の哺乳類Pol阻害活性
2.4 キサントン類8物質のヒトがん細胞増殖抑制活性
2.5 β-Mangostinのヒト子宮がん細胞に対する影響
2.6 マンゴスチン果皮由来キサントン類の構造と抗がん活性の相関
2.7 まとめ
第7章 クロロゲン酸類
1 コーヒー生豆:クロロゲン酸
1.1 はじめに
1.2 動物における抗肥満作用と作用メカニズム
1.3 ヒトでの有効性
1.4 おわりに
2 マテ:クロロゲン酸類
2.1 はじめに
2.2 マテ葉部エキスおよび単離
2.3 抗糖尿病および抗肥満作用
2.4 アルドース還元酵素阻害作用
-

腸内細菌・口腔細菌と全身疾患(普及版)
¥5,170
2015年刊「腸内細菌・口腔細菌と全身疾患」の普及版。全身各所で起こる疾患の発症・増悪に関与する腸内細菌や口腔細菌をターゲットとした創薬、予防・治療、機能性食品開発および、乳酸菌関連製品や口腔ケア製品の市場動向を収載した一冊!
(監修:落合邦康)
<a href="http://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=8656"target=”_blank”>この本の紙版「腸内細菌・口腔細菌と全身疾患(普及版)」の販売ページはこちら(別サイトが開きます)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は、2015年当時のものを使用しております。
落合邦康 日本大学
平山和宏 東京大学
泉福英信 国立感染症研究所
大坂利文 東京女子医科大学
山本真悠子 (株)ヤクルト本社
松本敏 (株)ヤクルト本社
津田真人 日本大学
細野朗 日本大学
角田圭雄 京都府立医科大学
伊藤義人 京都府立医科大学
園山慶 北海道大学
入江潤一郎 慶應義塾大学
山下智也 神戸大学
平田健一 神戸大学
井上亮 京都府立大学大学院
阪上由子 滋賀医科大学
塚原隆充 京都府立大学大学院;(株)栄養・病理学研究所
松本光晴 協同乳業(株)
内藤真理子 長崎大学
田代有美子 日本歯科大学
高橋幸裕 日本歯科大学
古西清司 日本歯科大学
山下喜久 九州大学
竹下徹 九州大学
Marni E. Cueno 日本大学
神尾宜昌 日本大学
宮崎裕司 明海大学
菊池建太郎 明海大学
草間薫 明海大学
今井健一 日本大学
高柴正悟 岡山大学
西村英紀 九州大学
落合智子 日本大学
松下健二 国立長寿医療研究センター
結束貴臣 横浜市立大学;神奈川歯科大学
本多靖 横浜市立大学
小川祐二 横浜市立大学
今城健人 横浜市立大学
米田正人 横浜市立大学
和田孝一郎 島根大学
中島淳 横浜市立大学
相澤(小峯)志保子 日本大学
廣畑直子 日本大学
早川智 日本大学
高橋直紀 新潟大学
山崎和久 新潟大学
宮本潤基 広島大学
鈴木卓弥 広島大学
重久晃 (株)ヤクルト本社
田村宗明 日本大学
南木康作 慶應義塾大学
水野慎大 慶應義塾大学
金井隆典 慶應義塾大学
-------------------------------------------------------------------------
<<目次>>
【第I編 細菌叢動態】
第1章 腸内細菌叢とその変動因子
1 腸内細菌叢
2 腸内細菌叢の宿主に対する影響
2.1 感染防御
2.2 代謝産物
2.3 免疫
2.4 その他の影響
3 消化管の部位による細菌叢構成の違い
4 腸内細菌叢の安定性
5 腸内細菌叢が変動する要因
5.1 年齢
5.2 宿主の生理機能
5.3 ストレス
5.4 免疫
5.5 肥満
5.6 食餌
5.7 抗菌性物質
5.8 プロバイオティクス
第2章 口腔細菌叢とその変動因子
1 はじめに
2 口腔細菌叢の形成機構
2.1 口腔常在細菌叢のはじまり
2.2 歯牙と口腔細菌叢の関係
2.3 歯表面バイオフィルムの形成機構
2.4 バイオフィルム形成に影響を与える因子
2.4.1 唾液
2.4.2 口腔清掃習慣
2.4.3 食生活
2.4.4 微生物に対する免疫力
2.4.5 歯表面の形状
2.4.6 歯列の状態
2.4.7 補綴、修復物の存在
2.5 舌上のバイオフィルムおよび微生物叢
3 外因子による口腔細菌叢への影響
3.1 抗生物質投与による影響
3.2 義歯による影響
4 おわりに
第3章 クォーラムセンシング機構
1 はじめに
1.1 クォーラムセンシング
1.2 グラム陰性細菌のAI-1を介したクォーラムセンシング機構
1.3 グラム陽性細菌のAIPsを介したクォーラムセンシング機構
1.4 AI-2を介した異種細菌間のクォーラムセンシング機構
1.5 AI-3を介したクォーラムセンシング機構
2 腸内常在細菌由来のAI-2がコレラ菌の定着を阻害する
3 クォーラムクエンチング
3.1 細胞外AI-2の分解による異種細菌間相互作用の妨害
3.2 乳酸菌による黄色ブドウ球菌のQS阻害
4 腸管内AI-2レベルが腸内細菌叢の構成に影響を与える
5 口腔細菌叢の形成におけるクォーラムセンシングの関与
5.1 口腔バイオフィルム形成におけるAI-2を介したクォーラムセンシングの関与
5.2 異種細菌間クォーラムクエンチングによるS. mutansのバイオフィルム形成阻害
6 おわりに
【第II編 腸内細菌と疾患】
第1章 腸内細菌と炎症性腸疾患・大腸がん
1 はじめに
2 炎症性腸疾患と腸内細菌叢
3 大腸がんと腸内細菌叢
4 大腸がんとIL-6シグナル
5 プロバイオティクスによる炎症性腸疾患・大腸がん予防
6 おわりに
第2章 アレルギー疾患
1 はじめに
2 アレルギーにおける腸内細菌叢の変化
3 腸内細菌によるアレルギー反応の調節
3.1 腸内細菌によるTh1/Th2バランスとIgE産生応答の調節
3.2 腸内細菌による制御性T細胞の誘導
3.3 腸内細菌が産生する短鎖脂肪酸による制御性T細胞の誘導
3.4 経口免疫寛容の誘導と腸内細菌
4 プロバイオティクス・プレバイオティクスによるアレルギー反応の調節
5 おわりに
第3章 非アルコール性脂肪性肝炎/肝癌
1 非アルコール性脂肪肝炎(NASH)とは?
2 NASHと腸内細菌
3 肝癌と腸内細菌
4 腸内細菌に対する治療とNASH・肝癌
第4章 メタボリックシンドローム
1 はじめに
2 無菌マウスは肥満になりにくい
3 肥満に特有の腸内細菌叢
4 腸内細菌叢と肥満の因果関係
5 腸内細菌叢が肥満・メタボに寄与するメカニズム
6 腸内細菌叢と肥満・メタボの関係性を左右する環境因子
7 おわりに
第5章 腸内細菌と糖尿病
1 はじめに
2 腸内細菌の2型糖尿病における特徴
3 腸内細菌の2型糖尿病の病態への影響
3.1 腸内細菌による短鎖脂肪酸産生と血糖制御
3.2 腸内細菌による胆汁酸代謝と血糖制御
3.3 腸内細菌による慢性炎症と血糖制御
4 腸内細菌を標的とした2型糖尿病治療
5 おわりに
第6章 動脈硬化と腸内細菌
1 はじめに
2 動脈硬化に関わる免疫機序と免疫臓器としての腸管
3 腸管からの動脈硬化予防
4 腸内フローラと腸管免疫調節
5 動脈硬化に腸内細菌が関与するというエビデンス
6 腸内細菌への治療的介入と動脈硬化への影響
7 腸内細菌の異常と疾患との関連を考える
8 まとめ
第7章 自閉症スペクトラム障害
第8章 腸内細菌と認知機能
1 はじめに
2 脳内因子と腸内細菌
2.1 中枢神経系因子
2.2 解糖系(グルコース代謝)
2.3 ミクログリア
3 腸内菌叢と関連する生命現象と認知機能の関係
3.1 食生活
3.2 肥満
3.3 肝性脳症
4 加齢時の学習・記憶力の向上(動物実験)
4.1 ポリアミン
4.2 マウス実験
5 プロバイオティクスを用いたヒト認知機能へのアプローチ
6 おわりに
【第III編 口腔細菌と疾患】
第1章 歯周病原菌Porphyromonas gingivalisの病原因子とその環境適応、遺伝的多様性について
1 はじめに
2 P. gingivalisの病原因子
3 P. gingivalisのゲノム解析
4 動く遺伝子による遺伝情報の水平伝達
5 網羅的ゲノム比較からの新規分泌系、type IX分泌機構の発見
6 今後の研究の展望
第2章 感染性心内膜炎
1 はじめに
2 歯性菌血症
3 感染性心内膜炎とは
4 IEの発症メカニズムと原因菌
4.1 IEの発症メカニズム
4.2 原因菌
5 IEの診断
6 IEの治療と予防法
6.1 治療
6.2 予防
7 歯科におけるIEのリスクと予防法
8 ハイリスク患者への予防法の教育
第3章 高齢者の肺炎と口腔細菌
1 はじめに
2 高齢者の肺炎について考えるうえでの基礎事項
2.1 高齢者において注意すべき肺炎
2.1.1 誤嚥性肺炎
2.1.2 人工呼吸器関連肺炎
2.2 口腔に存在する常在細菌叢
3 高齢者の肺炎と口腔細菌
4 口腔ケアと肺炎の予防
5 おわりに
第4章 歯周病とButyrate paradox―歯周病における酸化ストレスと全身疾患―
1 はじめに
2 歯周病と歯周病原細菌
3 Butyrate paradox
4 酪酸によって誘導される酸化ストレスと疾患
4.1 全身への影響
4.2 細胞への影響
5 おわりに
第5章 インフルエンザ
1 はじめに
2 インフルエンザウイルス
2.1 インフルエンザウイルスの分類
2.2 インフルエンザウイルスの生活環
2.3 インフルエンザによるパンデミック
2.4 インフルエンザと細菌感染
3 インフルエンザと口腔細菌
3.1 ノイラミニダーゼ産生口腔細菌
3.2 トリプシン様酵素産生口腔細菌
3.3 口腔細菌がインフルエンザ薬に及ぼす影響
3.4 口腔ケアがインフルエンザ発症に及ぼす影響
4 おわりに
第6章 口腔微生物と“がん”
1 はじめに
2 う蝕とがん
3 歯周病とがん
4 ウイルスとがん
5 おわりに
第7章 歯周病原細菌とウイルス感染症―細菌-ウイルスの微生物間相互作用による潜伏ウイルスの再活性化機構―
1 はじめに
2 HIVとEBVのライフサイクルと潜伏感染の問題点
3 HDACによるウイルス潜伏感染維持機構
4 歯周病原菌の代謝産物・酪酸によるウイルス潜伏感染の破綻
5 歯周病によるHIV感染症進行の可能性
6 腸管と女性生殖器に常在する酪酸産生菌による潜伏HIV再活性化
7 Sp1を介する酪酸誘導性HIV活性化メカニズム
8 おわりに
第8章 歯周病とメタボリックシンドローム(なぜ歯周病が全身に影響を及ぼすか)
第9章 糖尿病
1 臨床介入試験が示唆するもの
2 脂肪組織が歯周炎症を増幅するうえで重要な役割を果たす
3 歯周病との関わりからとらえる高度肥満と日本人型肥満の類似点と相違点
第10章 歯周病で誘導される動脈硬化と酸化ストレス
1 はじめに
2 感染による酸化ストレスおよび脂質酸化の増加
3 歯周病および動脈硬化におけるインフラマソームの活性化
4 酸化ストレスおよび酸化LDLによるインフラマソームの活性化
5 インフラマソームとTh17細胞活性化による炎症の持続
6 抗酸化因子を用いての歯周病および動脈硬化の制御
7 おわりに
第11章 認知症
1 はじめに
2 認知症、特にアルツハイマー病
3 炎症とアルツハイマー病
4 歯周病、歯周病関連細菌とアルツハイマー病
5 おわりに
第12章 非アルコール性脂肪肝炎と口腔内細菌
1 はじめに
2 歯周病とNASH
2.1 歯周病菌について
2.2 Porphyromonas gingivalisとNASH
3 歯周病菌によるNASH進展メカニズム
3.1 P.g.菌自体による肝組織への影響
3.2 歯周菌が放出するエンドトキシンによる肝組織への影響
3.3 肝臓におけるET感受性亢進
3.4 歯周病菌の腸管侵入による影響
4 NASHにおける歯周治療
5 おわりに
第13章 口腔細菌と妊娠合併症
1 はじめに
2 口腔細菌と胎盤の細菌叢
3 歯周病と早産
4 歯周病と妊娠高血圧症候群
5 歯周病の胎盤傷害メカニズム
6 おわりに
第14章 腸内細菌叢への影響
1 はじめに
2 歯周病とは
3 歯周病が全身疾患に及ぼす病因メカニズムとその問題点
3.1 菌血症説とその問題点
3.2 炎症メディエーター説とその問題点
4 腸内細菌叢のdysbiosisと疾患の関連
5 歯周病と全身疾患との関連の新たなメカニズム
6 P. gingivalis口腔投与による代謝への影響と腸内細菌叢の変化
7 まとめ
【第IV編 細菌叢改善法】
第1章 プロバイオティクス
1 プロバイオティクスとは
2 プロバイオティクスの機能性
3 プロバイオティクスの整腸作用・細菌叢改善
3.1 特定保健用食品としてのプロバイオティクス
3.2 細菌叢改善‐下痢や便秘の改善
3.3 細菌叢改善‐有害菌・病原菌の排除
3.4 細菌叢改善‐腸内細菌叢と肥満
4 プロバイオティクスの今後の展望
4.1 食品としてのプロバイオティクス
4.2 医薬品としてのプロバイオティクス
第2章 プレバイオティクス
1 はじめに
2 プレバイオティクスとは
3 プレバイオティクスの種類
3.1 フラクトオリゴ糖
3.2 ガラクトオリゴ糖
3.3 イソマルトオリゴ糖
3.4 キシロオリゴ糖
3.5 ヒトミルクオリゴ糖
4 乳酸菌やビフィズス菌によるプレバイオティクス代謝機構
4.1 ビフィズス菌によるガラクトオリゴ糖の代謝機構
4.2 乳酸菌によるガラクトオリゴ糖の代謝機構
4.3 ビフィズス菌によるフラクトオリゴ糖代謝機構
4.4 乳酸菌によるフラクトオリゴ糖代謝機構
4.5 キシロオリゴ糖の代謝機構
4.6 ヒトミルクオリゴ糖の代謝機構
5 プレバイオティクスの生理効果
5.1 ガラクトオリゴ糖、フラクトオリゴ糖の生理効果
5.2 ヒトミルクオリゴ糖の生理効果
6 おわりに
第3章 口腔ケア用天然抗菌・殺菌成分
1 口腔ケア
1.1 口腔ケアの背景
1.2 口腔ケアの実際
2 天然抗菌・殺菌成分
2.1 抗菌・殺菌成分
2.2 口腔内の抗菌・殺菌物質
2.3 天然抗菌・殺菌成分
3 口腔ケア剤
3.1 口腔ケア剤の付加価値
3.2 カテキン
3.3 カテキンの抗菌効果
3.3.1 In vitro
3.3.2 In vivo
4 おわりに
第4章 糞便微生物移
1 はじめに
2 糞便微生物移植の方法
3 糞便微生物移植の再評価
4 炎症性腸疾患を対象とした糞便微生物移植
5 過敏性腸症候群に対する糞便微生物移植
6 腸管外疾患を対象とした糞便微生物移植
7 おわりに
【第V編 市場動向】
第1章 乳酸菌関連製品の市場動向
1 市場の動向
1.1 市場規模の推移
1.2 市場のトレンド
2 個別市場の動向
2.1 発酵乳
2.2 乳製品乳酸菌飲料/乳酸菌飲料/乳酸菌入り清涼飲料
2.3 食品/健康食品(サプリメント)
3 企業動向
第2章 口腔ケア製品の市場動向
1 市場の動向
1.1 市場の推移
1.2 市場成長の背景
2 個別市場の動向
2.1 口腔ケア用品
2.2 口腔ケア用具・機器
2.3 口腔ケア食品
3 メーカー動向
3.1 ライオン
3.2 サンスター
3.3 花王
3.4 小林製薬
-

バイオマス分解酵素研究の最前線―セルラーゼ・ヘミセルラーゼを中心として―(普及版)
¥3,410
2012年刊「バイオマス分解酵素研究の最前線」の普及版!バイオマス分解酵素を網羅的・体系的にまとめた貴重な一冊!バイオマス利用の低コスト化・省エネルギー化のカギとなる酵素改変・利用技術が満載!
(監修:近藤昭彦・天野良彦・田丸浩)
<a href="https://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=5465"target=”_blank”>この本の紙版「バイオマス分解酵素研究の最前線(普及版)」の販売ページはこちら(別サイトが開きます)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は、2012年当時のものを使用しております。br> 神田鷹久 信州大学
天野良彦 信州大学
蓮沼誠久 神戸大学
近藤昭彦 神戸大学
森川康 長岡技術科学大学
小笠原渉 長岡技術科学大学
志田洋介 長岡技術科学大学
川口剛司 大阪府立大学
荒井基夫 大阪府立大学
藤井達也 (独)産業技術総合研究所
澤山茂樹 京都大学
野功一 信州大学
小杉昭彦 (独)国際農林水産業研究センター
森隆 (独)国際農林水産業研究センター
三宅英雄 三重大学
田丸浩 三重大学
石川一彦 (独)産業技術総合研究所
金子哲 (独)農業・食品産業技術総合研究機構
林清 (独)農業・食品産業技術総合研究機構
小西照子 琉球大学
竹田匠 岩手生物工学研究センター
渡辺裕文 (独)農業生物資源研究所
高橋潤一 帯広畜産大学
谷村彩 京都大学
劉文 京都大学
山田京平 京都大学
豊原治彦 京都大学
井上潤一 (独)理化学研究所;シナプテック(株)
大熊盛也 (独)理化学研究所
渡辺隆司 京都大学
小林良則 (一財)バイオインダストリー協会
苅田修一 三重大学
高田理江 京都大学
五十嵐圭日子 東京大学
伏信進矢 東京大学
湯井敏文 宮崎大学
椎葉大偉 宮崎大学
堀川祥生 京都大学
杉山淳司 京都大学
田島健次 北海道大学
阪本龍司 大阪府立大学
粟冠和郎 三重大学
幸田勝典 (株)豊田中央研究所
今村千絵 (株)豊田中央研究所
池内暁紀 (株)豊田中央研究所
伊藤洋一郎 (株)豊田中央研究所
中西昭仁 京都大学
Bae Jungu 京都大学
黒田浩一 京都大学
植田充美 京都大学
梅津光央 東北大学
金渡明 東北大学
中澤光 東北大学
村島弘一郎 Meiji Seika ファルマ(株)
荒勝俊 花王(中国)研究開発中心有限公司
矢野伸一 (独)産業技術総合研究所
川出雄二郎 三重大学
杉浦純 王子製紙(株)
趙雅蘋 王子製紙(株)
水野正浩 信州大学
山田亮祐 神戸大学
林徳子 (独)森林総合研究所
朴龍洙 静岡大学
尾崎克也 花王(株)
社領正樹 ノボザイムズジャパン(株)
森茂治 天野エンザイム(株)
-------------------------------------------------------------------------
<<目次>>
序章
1 セルラーゼ研究,古くから現在へ
1.1 はじめに
1.2 セルラーゼ研究の推移
1.3 セルラーゼ研究の流れの中で興味ある話題
1.3.1 Swelling factor (SF) などにみる酵素水解
1.3.2 酵素による水解曲線が寝てくる現象
1.3.3 セルロースミクロフィブリルと酵素作用
1.3.4 セルロースの酵素分解に対する研究の方向
1.4 おわりに
2 バイオマス分解酵素研究の新たな展開
2.1 はじめに―加速するバイオリファイナリー研究―
2.2 バイオリファイナリーに資するバイオマス分解酵素研究
2.3 プロセス統合化のためのバイオマス分解微生物の利用
2.4 おわりに
【第1編 多様なセルラーゼ・ヘミセルラーゼ】
第1章 糸状菌・担子菌の酵素
1 Trichoderma reesei
1.1 はじめに
1.2 T. reeseiセルラーゼの種類と機能
1.3 T. reeseiセルラーゼ遺伝子とその発現調節
1.4 バイオマス分解用高機能T. reeseiセルラーゼの創成
2 糸状菌Trichoderma reeseiにおけるセルラーゼ・へミセルラーゼ遺伝子発現機構
2.1 セルロース分解性糸状菌Trichoderma reesei
2.2 T. reeseiにおけるセルラーゼ・ヘミセルラーゼの生産機構
2.3 T. reeseiにおけるセルラーゼ・ヘミセルラーゼ遺伝子の転写調節因子
2.4 T. reeseiにおけるセルラーゼ・キシラナーゼ遺伝子の誘導発現モデル
3 Aspergillus aculeatus のセルラーゼ系
3.1 Aspergillus aculeatus のセルラーゼとその利用
3.2 Aspergillus aculeatusのセルラーゼ遺伝子
4 Acremonium cellulolyticus
4.1 はじめに
4.2 A. cellulolyticus糖化酵素による植物バイオマスの糖化特性
4.3 A. cellulolyticusのゲノム解析および遺伝子操作技術
4.4 おわりに
5 担子菌(Irpex lacteus)のセルラーゼ
5.1 バイオマス分解酵素生産菌としての魅力
5.2 CBHIタイプのセルラーゼ
5.3 CBHIIタイプのセルラーゼ
5.4 エンド型セルラーゼ
5.5 β-グルコシダーゼとセロビオース脱水素酵素
第2章 菌類の酵素
1 好熱嫌気性細菌Clostridium thermocellumが生産するセルロソーム-その特徴と高活性セルロソーム開発
1.1 はじめに
1.2 Clostridium thermocellumのセルロソームの特徴
1.3 高活性Clostridium thermocellum S14株の分離と特性
1.4 セルラーゼ酵素複合体を生産する好熱嫌気性好アルカリ性細菌の分離
1.5 おわりに
2 Clostridium属細菌(中温菌)
2.1 はじめに
2.2 セルロソーム
2.3 セルロソームとノンセルロソームの相乗効果
2.4 セルロソーム生産性中温菌Clostridium属のゲノム解析
2.5 おわりに
3 耐熱性菌―超耐熱性セルラーゼー
3.1 はじめに
3.2 超耐熱性セルラーゼ酵素の発見
3.3 超耐熱性エンド型セルラーゼの産業応用
3.4 超耐熱性セルラーゼの構造機能解析
3.5 今度の展開
4 放線菌
4.1 放線菌のセルロース分解酵素系
4.2 放線菌のヘミセルラーゼ
第3章 植物由来の細胞壁分解酵素
1 はじめに
2 植物細胞壁の構造
3 植物成長に関与する細胞壁分解酵素
4 セルロース生合成に関与する細胞壁分解酵素
5 防御応答に関与している細胞壁分解酵素
6 果実の熟成および軟化に関与する細胞壁分解酵素
7 セルロース系バイオマスの利用において
第4章 昆虫の酵素(ゴキブリ,シロアリ,カミキリムシなど)
1 はじめに
2 GH9エンドグルカナーゼ
2.1 昆虫由来GH9 EGのリコンビナント生産
3 昆虫由来GH5 EG
4 昆虫由来GH45 EG
5 GH48に属する昆虫由来酵素
6 GH28に属する昆虫由来酵素
7 β-グルコシダーゼ
7.1 昆虫由来GH1 BGL
7.2 昆虫由来GH3 酵素
7.3 昆虫由来 BGLのリコンビナント発現生産と特性
8 昆虫の消化性共生微生物のセルラーゼ
9 今後の昆虫セルラーゼ研究
第5章 動物の酵素
1 ルーメンからの酵素
1.1 ルーメンセルロース・ヘミセルロース分解菌
1.2 アンモニアストリッピングとR.flavefaciensによるセルロース・ヘミセルロースの分解モデル
2 水生生物のセルラーゼとヘミセルラーゼ
2.1 緒論
2.2 外源性と内源性のセルラーゼ
2.2.1水生生物とセルラーゼ保有微生物との共生
2.2.2 内源性セルラーゼを持つ水生生物
2.2.3 セルラーゼの起源
2.3 外源性と内源性のへミセルラーゼ
2.4 まとめ
第6章 環境遺伝子の網羅的解析と植物バイオマス分解酵素
1 はじめに
2 メタゲノム解析の方法
3 メタゲノム解析によって網羅的に取得された配列群
4 メタトランスクリプトーム解析-シロアリ共生微生物の解析例の紹介-
5 課題と展望
【第2編 関連酵素】
第7章 リグニン分解酵素
1 白色腐朽菌によるリグニン分解
2 リグニン分解酵素
2.1 リグニンペルオキシダーゼ
2.2 バーサタイルペルオキシダーゼ(VP)
2.3 マンガンペルオキシダーゼ
2.4 ラッカーゼ
3 リグニン分解に関与する担子菌の多様な酵素
第8章 セルロース膨潤タンパク質
1 植物細胞壁のゆるみを誘導するエクスパンシン
2 エクスパンシンの多様性
3 遺伝子情報を用いたエクスパンシンの探索
4 エクスパンシンによる細胞壁糖鎖の分解促進作用
5 糖化へのエクスパンシン利用
【第3編 セルラーゼの構造・機能】
第9章 セルラーゼ活性測定の標準化
1 はじめに
2 還元糖定量法の標準化
3 タンパク質の定量法
4 酵素活性・糖化能測定法
4.1 FPU活性測定法
4.2 CMCase活性測定法
4.3 β-Glucosidase活性測定法
4.3.1 pNPG法
4.3.2 Cellobiose法
4.4 Avicelase活性測定法
4.5 Xylanase活性測定法
4.6 β-Xylosidase活性測定法
4.7 バイオマス酵素糖化能測定法
5 おわりに
第10章 セルラーゼの立体構造と作用機作
1 セルラーゼの立体構造
1.1 GHファミリー5(GH5)
1.2 GHファミリー6(GH6)
1.3 GHファミリー7(GH7)
1.4 GHファミリー8(GH8)
1.5 GHファミリー9(GH9)
1.6 GHファミリー12(GH12)
1.7 GHファミリー44(GH44)
1.8 GHファミリー45(GH45)
1.9 GHファミリー48(GH48)
1.10 GHファミリー61(GH61)
1.11 GHファミリー124(GH124)
2 セルラーゼとリグノセルロースの分子間相互作用
2.1 はじめに
2.2 リグニンによるセルラーゼの阻害
2.3 リグニンへの吸着性を支配する酵素の構造
2.4 セルラーゼのリグノセルロースへの非生産的な吸着を軽減する添加剤
2.5 CBMの基質認識と前処理バイオマス表層糖鎖解析への応用
2.6 おわりに
3 セルラーゼのプロセッシブ性と構造の相関
3.1 はじめに
3.2 セロビオヒドロラーゼはなぜセルロースをセロビオースで切り出すのか?
3.3 セルラーゼの構造がプロセッシビティに与える影響
3.4 エンド型-エキソ型とプロセッシビティの違い
3.5 セルロース基質がエンド型-エキソ型,プロセッシビティに与える影響
3.6 おわりに
4 セルラーゼの反応機構
4.1 標準的な反応機構
4.2 GHファミリーと反応機構の対応
4.3 例外的な反応機構
4.4 基質の歪み
第11章 セロビオヒドロラーゼ糖結合性モジュールのドッキング解析椎葉大偉
1 はじめに
2 セルロース結晶面に対するCBMの結合様式
3 セルロース結晶表面認識に関わるアミノ酸残基
4 おわりに
第12章 セルラーゼによる分解程度を指標とした基質構造の
ハイスループット分析
1 はじめに
2 近赤外分光法と多変量解析
3 前処理残渣による検量モデルの構築
4 前処理濾液による検量モデルの構築
5 展望
第13章 セルロース合成における分解酵素の役割
1 はじめに
2 バクテリアにおけるセルロース合成酵素遺伝子と合成酵素複合体(TC)
3 バクテリア由来エンドグルカナーゼの立体構造
4 セルロース合成における分解酵素の機能
5 おわりに
【第4編 ヘミセルラーゼの構造・機能】
第14章 ヘミセルラーゼの立体構造
1 キシラナーゼの立体構造
2 α-L-アラビノフラノシダーゼの立体構造
3 α-グルクロニダーゼの立体構造
第15章 ヘミセルラーゼの作用機作
1 はじめに
2 キシランの構造
2.1 グルクロノキシラン(O-アセチル-4-O-メチルグルクロノキシラン)
2.2 アラビノグルクロノキシラン(アラビノ-4-O-メチルグルクロノキシラン)
2.3 アラビノキシラン
3 キシラン分解酵素
3.1 エンド-β-1,4-キシラナーゼ(EC 3.2.1.8)
3.2 β-キシロシダーゼ(EC 3.2.1.37)
3.3 α-L-アラビノフラノシダーゼ(EC 3.2.1.55)
3.4 フェルラ酸エステラーゼ(EC 3.1.1.73)
3.5 α-D-グルクロニダーゼ(EC 3.2.1.139)
3.6 アセチルキシランエステラーゼ(EC 3.1.1.72)
4 キシログルカン(XG)の構造
5 XG分解酵素
5.1 XG特異的エンド-β-1,4-グルカナーゼ(キシログルカナーゼ;EC 3.2.1.151)
5.2 オリゴXG還元末端特異的セロビオヒドロラーゼ(EC 3.2.1.150)
5.3 オリゴXG特異的イソプリメベロース生成酵素(EC 3.2.1.120)
5.4 その他
6 マンナンの構造
6.1 直鎖マンナン
6.2 グルコマンナン
6.3 ガラクトマンナン
6.4 ガラクトグルコマンナン
7 マンナン分解酵素
7.1 エンド-β-1,4-マンナナーゼ(EC 3.2.1.78)
7.2 β-マンノシダーゼ(EC 3.2.1.25)
7.3 β-グルコシダーゼ(EC 3.2.1.21)
7.4 α-ガラクトシダーゼ(EC 3.2.1.22)
7.5 アセチル(ガラクト)グルコマンナンエステラーゼ(EC 3.1.1.6)
8 おわりに
【第5編 セルラーゼの高機能化】
第16章 人工セルロソームの構築と酵母での発現
1 はじめに ―人工セルロソーム構築のための分子生物学的基盤
2 人工セルロソームの構築
3 人工セルロソームの酵母への導入
3.1 Aga1-Aga2システムによる酵母表層上での骨格タンパク質の発現
3.2 酵母表層での骨格タンパク質と酵素の複合体形成
4 おわりに
第17章 無細胞合成系を用いたセルラーゼの高機能化
1 はじめに
2 無細胞系の最適化によるセルラーゼの活性型での生産
3 無細胞合成系によるセルラーゼの高機能化
3.1 改良型SIMPLEX法による分解活性の向上
3.2 アラニンスキャニングを利用した活性中心の最適化
3.3 有利変異の相加
4 おわりに
第18章 細胞表層工学を利用した最適なセルラーゼカクテルの構築
1 はじめに
2 バイオエタノールの現状
2.1 セルラーゼによるセルロースの分解
2.2 セルラーゼ提示酵母によるセルロースからの発酵
2.3 セルラーゼカクテルの選抜
3 おわりに
第19章 モジュール再編成によるセルラーゼの高機能化
1 はじめに
2 固相基質分解酵素の構造的特徴
3 モジュール単位での直接融合による組換え蛋白質設計
4 コヘシン―ドッケリン相互作用を利用したセルラーゼ連結
5 ビオチン―アビジン相互作用を利用したセルラーゼ連結
6 ナノ材を骨格としたセルラーゼ連結
7 おわりに
【第6編 セルラーゼ・ヘミセルラーゼの大量生産】
第20章 セルラーゼ高生産糸状菌Trichoderma reesei日本型系統菌株の開発
1 Trichoderma reesei日本型系統樹進化への転写調節因子の関与
1.1 日本型系統樹の比較ゲノム解析
1.1.1 カタボライトリプレッション部分的解除株
1.1.2 β-グルコシダーゼを正に調節する新規転写調節因子BglR
1.2 日本型系統樹の進化とは?
2 日本型系統菌株のさらなる進化
2.1 最適比率での酵素生産技術開発
2.2 日本独自の最適比率での酵素生産技術開発(マイナープロモーターの利用)
第21章 Acremonium cellulolyticus由来糖質分解酵素の工業化検討
1 はじめに
2 菌株育種による生産性向上検討
3 培地・培養条件の最適化による生産性向上について
第22章 Bacillus
1 はじめに
2 枯草菌ゲノムの改変技術
3 枯草菌宿主の改良
3.1 枯草菌遺伝子の機能性評価
3.2 宿主ゲノムの縮小化による酵素高生産化
4 枯草菌の酵素高生産化技術
4.1 アミノ酸代謝系の制御によるセルラーゼ高生産化
4.2 分泌装置の改良によるセルラーゼ高生産化
4.3 細胞膜・壁の人工改変によるセルラーゼ高生産化
5 ゲノム縮小株への技術統合による高機能化
【第7編 バイオマス利用分野への展開】
第23章 バイオマス酵素糖化反応の解析
1 はじめに
2 標準前処理標品の調製
3 市販セルラーゼの特性
4 前処理物の糖化パターン
5 成分酵素の糖化における役割
6 酵素コスト低減と頭打ち現象
7 おわりに
第24章 機械的前処理バイオマスの酵素分解
1 はじめに
2 微粉砕による前処理
3 前処理バイオマスの酵素糖化
4 おわりに
第25章 セルロソームの回収・再利用法の開発
1 はじめに
2 セルロソームについて
3 セルロソーム回収・再利用
3.1 回収することの優位性
3.2 セルロソームの回収
3.3 セルロソームの回収・再利用
4 まとめ・今後の展望
第26章 セルラーゼ回収・再利用によるエタノール発酵の高効率化
1 はじめに
2 バイオマスの糖化プロセス
3 まとめ
第27章 再生セルロースの酵素分解
1 はじめに
2 再生セルロースとは
3 セルラーゼによるセルロースIIの酵素分解特性
4 イオン液体処理により得られる再生セルロースの酵素分解
第28章 セルラーゼ細胞表層提示酵母を用いたバイオマス変換
1 はじめに
2 統合型バイオプロセスによるエタノール生産
3 統合型バイオエタノール生産を実現する細胞表層提示技術
4 セルラーゼ細胞表層提示酵母を用いたセルロースからの統合型バイオエタノール生産
5 セルラーゼ細胞表層提示割合最適化法の開発
6 おわりに
第29章 リグニン分解酵素表層提示酵母を用いたバイオマス変換
1 はじめに
2 細胞表層提示酵母を用いた前処理の利点と可能性
3 ラッカーゼI提示酵母を用いたバイオマスの前処理
3.1 ラッカーゼI提示酵母の構築
3.2 ラッカーゼI提示酵母による稲わらの前処理&セルラーゼ提示酵母による糖化・発酵
4 おわりに
第30章 セルラーゼによるセルロースのナノファイバー化
1 はじめに
2 従来のセルロースナノファイバー製造法
3 酵素加水分解によるセルロースの微細化
3.1 Trichoderma CBHI(Cel7A)の作用で見られる微細化
3.2 Trichoderma CBHI(Cel7A)のCBMの作用で見られる微細化
3.3 エンドグルカナーゼと物理的破壊の同時併用処理による微細化
第31章 ペーパースラッジを原料としたセルラーゼの生産とペーパースラッジのバイオエタノールへの変換
1 はじめに
2 PSとは
3 未処理PSを用いたセルラーゼの生産
4 PS由来のセルラーゼを用いたPSの糖化
5 PS由来のセルラーゼを用いたPSの同時糖化・発酵によるエタノールの生産
5.1 PSのSHFによるエタノール生産
5.2 PSの同時糖化・発酵によるエタノールの生産
5.3 PSの同時糖化・発酵によるエタノールの生産向上
6 おわりに
【第8編 修飾酵素としての応用展開】
第32章 洗剤への応用
1 はじめに
2 洗剤用アルカリセルラーゼの開発
3 高機能セルラーゼ開発と構造機能解析
4 洗剤用セルラーゼの状況と今後の展望
第33章 繊維業界でのセルラーゼの利用
1 はじめに
2 デニムの洗い加工へのセルラーゼの応用(バイオウォッシュ加工)
3 天然セルロース系繊維加工へのセルラーゼの応用
3.1 セルラーゼの精錬工程への応用(バイオ精錬)
3.2 セルラーゼの仕上げ加工への応用(バイオフィニッシュ加工)
第34章 紙パルプへの応用
1 はじめに
2 濾水性向上による,リサイクルパルプの乾燥費用削減
3 クラフトパルプの叩解エネルギー削減
4 脱インク
5 クラフトパルプの漂白促進
6 漂白ユーカリクラフトパルプの黄変防止
第35章 食品への応用
1 はじめに
2 醸造
2.1 ビール
2.2 ワイン
3 果汁・野菜加工
4 製パン
5 最近動向
5.1 高齢者・介護用食品製造
5.2 香気前駆体(配糖体)の分解による茶,ワインの香気増強とイソフラボンの効率的アグリコン化
5.3 農産物からの食品生産の効率化と食品廃棄物の減量化
-

フッ素樹脂の最新動向(普及版)
¥2,255
2013年刊「フッ素樹脂の最新動向」の普及版。
耐熱性、耐候性、耐薬品性、難燃性、摺動性、絶縁性、非粘着性など優れた特性を有するフッ素樹脂!合成などの開発動向、多方面で進む用途展開、そしてリサイクル技術や生分解性まで、フッ素樹脂の最新動向を完全網羅!コーティングやライニングで、撥水・撥油、耐食、帯電防止などの表面処理を!
(監修:澤田英夫)
<a href="https://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=5746"target=”_blank”>この本の紙版「フッ素樹脂の最新動向(普及版)」の販売ページはこちら(別サイトが開きます)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
執筆者の所属表記は、2013年当時のものを使用しております。
澤田英夫 弘前大学大学院
成田正 埼玉工業大学
吉田正人 島根大学
飯塚真理 島根大学
齋藤禎也 弘前大学大学院
井戸向さつき 弘前大学大学院
矢嶋尊 大陽日酸(株)
増田祥 旭硝子(株)
大島明博 大阪大学
稲木信介 東京工業大学
淵上寿雄 東京工業大学
白川大祐 旭硝子(株)
石関健二 旭硝子(株)
森田正道 ダイキン工業(株)
井田政宏 ニチアス(株)
中島陽司 旭硝子(株)
堀久男 神奈川大学
藤森厚裕 埼玉大学
清水道晃 日立電線(株)
佐久間充康 (株)クレハ・バッテリー・マテリアルズ・ジャパン
三宅直人 旭化成イーマテリアルズ(株)
白鳥世明 慶應義塾大学
中西智昭 日本フッソ工業(株)
佐藤勝之 ユニマテック(株)
森澤義富 旭硝子(株)
大久保篤 中興化成工業(株)
道本忠憲 日東電工(株)
-------------------------------------------------------------------------
<<目次>>
【開発動向】
第1章 重付加反応による新しいタイプのフッ素ポリマーの合成
1 はじめに
2 ラジカル重付加反応による新しいタイプのフッ素ポリマーの合成
3 アニオン重付加反応による新しいタイプのフッ素ポリマーの合成
4 おわりに
第2章 新規含フッ素テロマーの合成:フルオロアルキル基含有スチレンダイマー類の合成と性質
1 はじめに
2 フルオロアルキル基含有スチレンダイマー類の合成と性質
第3章 含フッ素オリゴマー/無機ナノコンポジット類の開発とその機能発現
1 はじめに
2 フルオロアルキル基含有オリゴマー/シリカナノコンポジット類の調製と機能発現
3 フルオロアルキル基含有オリゴマー/炭酸カルシウムナノコンポジット類の調製と耐熱性
4 おわりに
第4章 高配向カーボンナノチューブを用いた導電性フッ素樹脂の作製技術
1 はじめに
2 樹脂添加材としての高配向CNTの特徴
3 導電性樹脂作製に適した加工法とは
4 導電性フッ素樹脂の作製プロセス(概略)
4.1 第1工程;CNT分散液作製工程
4.2 第2工程;溶媒のエタノール転換工程
4.3 第3工程;フッ素樹脂の添加・混合工程
4.4 第4工程;超臨界炭酸処理工程
4.5 第5工程;乾燥・粉末回収工程
5 CNT分散液作製(第1工程詳細)
6 溶媒のエタノール転換工程(第2,3工程詳細)
7 超臨界炭酸処理(第4,5工程詳細)
8 混合スラリーの乾燥・回収(第6工程詳細)
9 導電性フッ素樹脂の性能評価
10 導電性ICトレイの作製
11 まとめ
第5章 流れ性,塗膜物性を向上した粉体塗料用フッ素樹脂
1 はじめに
2 粉体塗料用樹脂に求められる特性
3 粉体塗料樹脂のレオロジー
4 熱硬化粉体塗料用フッ素樹脂の構造設計
5 初期開発熱硬化粉体塗料用フッ素樹脂と新規開発品について
第6章 量子ビームを用いた各種フッ素樹脂の微細加工
1 はじめに
2 放射光(SR光)によるマイクロスケール微細加工
3 イオンビームによるナノスケール微細加工
4 TRafプロセスによる微細加工
5 まとめと今後の展望
第7章 電解法による共役系高分子のフッ素化
1 はじめに
2 共役系高分子の電解フッ素化
2.1 選択的電解フッ素化
2.2 高分子電解反応
2.3 共役系高分子の電解フッ素化
3 CRS法によるポリアニリンのフッ素化
4 共役系高分子膜の傾斜的表面修飾
4.1 バイポーラ電気化学
4.2 バイポーラ電極上での傾斜的エレクトロクリック反応
5 おわりに
第8章 パーフルオロポリエーテルの合成と応用
1 パーフルオロポリエーテルとは
2 フッ素オイルの種類と特徴
3 パーフルオロポリエーテルの製造法
3.1 光酸化重合
3.2 開環重合
4 パーフルオロポリエーテルの問題点
5 パーフルオロポリエーテルの用途例
6 ハードディスクドライブにおける官能基含有PFPEの使用例
7 おわりに
第9章 フルオロアクリレートホモポリマーの動的撥液性
1 はじめに
2 撥液性の評価方法
3 転落角
4 転落速度(静置法)
5 転落速度(着弾法)
6 おわりに
第10章 架橋フッ素樹脂コーティング技術とその応用
1 はじめに
2 架橋フッ素系樹脂
3 架橋フッ素系樹脂コーティング
4 架橋フッ素樹脂コーティング技術の応用
5 おわりに
第11章 PFAライニング配管の寿命診断
1 はじめに
2 ライニングとは
3 PFAとは
4 PFAライニング配管の特徴・用途
5 PFAライニング配管の劣化・損傷形態
5.1 クラック・クレーズ
5.2 ブリスター
5.3 絶縁破壊・ピンホール
5.4 変形・座屈
5.5 その他
5.5.1 外装管腐食
5.5.2 ライニングフレアー面のキズ・亀裂・変形
5.5.3 異物堆積
5.5.4 磨耗減肉(エロージョン)
6 PFAライニングの調査手順
6.1 外観観察
6.2 気密試験・ピンホール検査
6.3 解体・観察
6.4 物性評価
6.5 総合評価
7 寿命診断への取組み
7.1 目的
7.2 寿命診断手順
7.3 寿命診断基準
8 透過
8.1 透過について
8.2 透過対策
9 まとめ
第12章 フッ素系ポリマーの分離分析技術
1 はじめに
2 フッ素系ポリマーの溶解
3 フッ素系溶媒のポリマー溶解性
4 フッ素系ポリマーの液体クロマトグラフィー
5 フッ素系ポリマーの質量分析
6 おわりに
第13章 機能性有機フッ素化合物の分解反応の開発
1 はじめに
2 鉄粉+熱水を用いたPFAS類の還元分解
3 ヘテロポリ酸を用いたPFCA類の光触媒分解
4 ペルオキソ二硫酸イオンを用いたPFCA類の光酸化分解
5 ペルオキソ二硫酸イオンを用いたPFCA類の温水分解
6 PFOA代替物質:H-PFCA類の分解
7 PFOS代替物質:PFAES類の分解
8 フッ素系イオン交換膜の分解・無機化反応
9 おわりに
【応用展開】
第14章 “結晶性”フッ素系共重合体による耐熱性透明材料の創製
1 はじめに
2 試料と測定方法
3 フッ素系共重合体光伝送材料の構造―機能相関
4 固定熱処理と自由収縮処理の影響
5 おわりに
第15章 ハイブリッド電気自動車に使用されるフッ素系材料
1 はじめに
2 HEVへの応用
2.1 オイルポンプ内配線材
2.2 モーター内部配線材
2.3 電源用ハーネス
3 おわりに
第16章 フッ化ビニリデン系樹脂の応用:リチウムイオン二次電池電極用バインダー
1 はじめに
2 リチウムイオン二次電池と電極用バインダーについて
2.1 リチウムイオン二次電池(LIB)
2.2 電極の構造
2.3 バインダーの役割
2.4 電池用バインダーの種類
3 「クレハKFポリマー」とバインダーグレードの概要
4 PVDFの性質〜バインダーとしての特徴〜
4.1 PVDFの構造
4.2 化学的性質
4.3 電気化学特性と分子軌道計算
5 PVDFバインダーのグレード種類と性能
5.1 標準バインダー
5.2 高接着バインダー?:超高分子量タイプ
5.3 高接着バインダー?:変性タイプ
5.4 柔軟性バインダー
5.4.1 VDF系コポリマー:W#7500
5.4.2 フッ素系ゴム(試作品)
5.4.3 コア・シェル型ポリマー(試作品)
6 バインダーの結着メカニズム
6.1 結着状態の観察
6.2 バインダー分布状態の観察
7 今後
第17章 フッ素系電解質材料の高性能化と高耐久化
1 固体高分子形燃料電池について
2 フッ素系電解質膜について
3 フッ素系電解質膜の課題
4 旭化成イーマテリアルズにおける取り組み
第18章 フッ素修飾ナノ粒子による超撥水・高撥油コーティング
1 はじめに
2 超撥水・撥油表面
3 コーティング溶液の作製方法
4 液体表面張力の調整
5 濡れ性の評価
5.1 水・エタノール混合溶液に対する接触角・転落角測定結果
5.2 油に対する濡れ性の評価
6 まとめ
第19章 フッ素樹脂焼き付けコーティングおよびライニング
1 はじめに
2 非粘着・離型用途のコーティング
2.1 用途
2.2 皮膜構成
2.3 コーティング方法
2.4 プライマー
3 耐食ライニング
3.1 耐食性とは
3.2 浸透現象
3.3 皮膜構成
3.4 用途
4 ロトライニング
5 高純度ライニング
6 帯電防止コーティング・ライニング
6.1 帯電防止の考え方
6.2 非粘着・離型性コーティングでの帯電性の確認
6.3 耐食ライニングでの帯電性の確認
6.4 静電気災害の予防
7 剥離帯電防止コーティング
7.1 剥離帯電防止の考え方
7.2 対策
7.3 効果
8 さいごに
第20章 生分解性フッ素テロマー化合物を用いた表面処理剤
1 フッ素テロマー
1.1 はじめに
1.2 フッ素テロマー合成
1.3 フッ素テロマーの環境への影響
2 生分解性フッ素テロマー化合物
2.1 設計と合成
2.2 従来テロマーとの物性比較
2.3 生分解性評価
3 表面処理剤への応用
3.1 繊維処理向け撥水撥油剤
3.2 防汚処理剤
3.3 固体表面処理向け撥水撥油剤
4 おわりに
第21章 環境発電のためのフッ素系ポリマーを用いた高性能エレクトレット膜
1 環境発電と材料
2 エレクトレットとその材料
3 エレクトレットを用いた振動発電
4 エレクトレット材料としてのCYTOPTM
5 まとめ
第22章 フッ素樹脂含浸ファブリック
1 はじめに
2 フッ素樹脂原料
2.1 PTFEディスパージョン
2.2 その他のディスパージョン
3 繊維織布材料
3.1 ガラス繊維織布
3.2 その他の織布
4 PTFE含浸ファブリックの加工工程
4.1 含浸
4.2 乾燥・焼結
4.3 織布のハンドリング
4.4 含浸工程
5 フッ素樹脂含浸ファブリックの用途
第23章 フッ素樹脂粘着テープ
1 概要
1.1 支持体フィルム
1.1.1 PTFE切削フィルム
1.1.2 PTFE圧延フィルム
1.1.3 PTFEコーティングフィルム
1.2 表面接着処理
1.3 粘着剤
2 フッ素樹脂粘着テープの用途
2.1 耐熱用途例―耐熱性,非粘着性利用
2.2 難接着性被着体への接着例―薄膜・滑り性・難燃性利用
2.3 その他シリコーン粘着剤以外の使用例―柔軟性・寸法安定性,シリコーンフリー利用
3 最近の動向
-

高分子の結晶化制御―研究開発の最前線とその応用―(普及版)
¥3,740
2012年刊「高分子の結晶化制御」の普及版。
未解明な部分の多い高分子の「結晶化」について、最新情報を紹介!高次構造の解析、プロセス段階の計測、成形加工における結晶化制御技術を詳述!汎用プラスチック製品の可能性が込められた必読の書籍!
(監修:鞠谷雄士)
<a href="https://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=5569"target=”_blank”>この本の紙版「高分子の結晶化制御(普及版)」の販売ページはこちら(別サイトが開きます)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は、2012年当時のものを使用しております。br> 奥居徳昌 東京工業大学
梅本晋 東京工業大学
山本隆 山口大学
櫻井伸一 京都工芸繊維大学
吉岡太陽 豊田工業大学
辻正樹 京都大学
金谷利治 京都大学
松葉豪 山形大学
野末佳伸 住友化学(株)
田實佳郎 関西大学
高和宏行 ユニオプト(株)
築地光雄 ユニオプト(株)
大越豊 信州大学
土岐重之 State University New York at Stony Brook,Department of Chemistry.New York 11794 USA
上原宏樹 群馬大学
撹上将規 埼玉大学
山延健 群馬大学
塩谷正俊 東京工業大学
久保山敬一 東京工業大学
扇澤敏明 東京工業大学
西田幸次 京都大学
辻秀人 豊橋技術科学大学
吉田博久 首都大学東京
浅井茂雄 東京工業大学
斎藤拓 東京農工大学
鞠谷雄士 東京工業大学
宝田亘 東京工業大学
木村将弘 東レ(株)
金井俊孝 出光興産(株)
船木章 出光興産(株)
村瀬浩貴 東洋紡績(株)
伊藤浩志 山形大学
-------------------------------------------------------------------------
<<目次>>
【第1編】高分子結晶構造の基礎
第1章高分子の特徴と結晶化の基礎
1はじめに
2高分子単結晶
3結晶化速度
第2章分子シミュレーションによる結晶構造と高次構造の解明
1はじめに
2シミュレーション概観
3結晶構造の予測
4高分子結晶化のシミュレーション
4.1均一核形成
4.2折り畳み結晶の成長
4.3ガラスからの結晶化
4.4流動結晶化と繊維構造の発現
5大変形による結晶組織の変化
6おわりに
第3章共重合体の結晶構造
1緒言
2結晶性共重合体の構造形成の特徴
3非晶-非晶ジブロック共重合体のミクロ相分離の基礎
4構造解析法(結晶化の動力学解析も含む)
5各論
5.1結晶-非晶ブロック共重合体
5.2結晶-結晶ブロック共重合体
5.3結晶-液晶ブロック共重合体
6総括/将来展望
第4章透過型電子顕微鏡法による結晶性高分子固体の高次構造解析
1はじめに
2制限視野電子回折(Selected-area Electron Diffraction: SAED)
2.1光学特性の異なる三種類のPBT二次元球晶を与える構造的要因の解明
2.2電界紡糸ナノファイバー単繊維の配向解析
3暗視野観察(Dark-field Imaging)
3.1一軸配向PBT薄膜に形成されるシシカバブ構造の暗視野観察とその結晶学的構造
4おわりに
第5章中性子散乱によるポリエチレンのシシケバブ構造形成機構解析
1はじめに
2シシケバブ生成における高分子量成分の効果
3高分子量成分がシシを作ることの直接証明とシシの形態観察
4延伸過程におけるシシケバブ形成
5低分子量の役割
6おわりに
第6章中性子散乱を用いたアイソタクチックポリプロピレンのシシケバブ構造解析
1背景
1.1シシケバブ構造
1.2シシケバブ構造の発見とその物性
1.3コイル―ストレッチ転移
1.4流動誘起結晶化のその場観察と臨界絡み合い濃度
1.5シシケバブ構造形成過程のその場観察
2中性子散乱によるシシケバブ構造解析
2.1実験の目的
2.2中性子散乱
2.3試料調製
3実験結果と考察
3.1中性子散乱実験の結果
3.2シシケバブ構造形成機構の一般性について
4シシケバブ構造形成機構解明に向けた今後の展望
【第2編】結晶構造変化のその場計測による解析
第7章球晶構造形成過程のその場計測
1はじめに
2球晶内部構造の形成過程でのその場計測
2.1AFMによるラメラ構造の成長過程のその場計測
2.2放射光を用いたX線回折/散乱による球晶成長と2次結晶化のその場計測
2.3偏光顕微鏡下での球晶成長と内部構造変化のその場計測
3等温結晶化での球晶形成過程のその場計測
3.1全結晶化挙動と核発生挙動の影響
3.2負圧による球晶間でのキャビテーション発生
第8章複屈折のその場計測法
1はじめに
2複屈折
3複屈折の数学的表現
4複屈折の計測のその場観察
4.1セナルモン法
4.2回転検光子法
4.3高度な複屈折計測
5その場観察の複屈折における測定系
6まとめ
第9章繊維の一軸伸長過程での配向結晶化
1はじめに
2測定システム
3PET繊維の配向結晶化挙動
3.1連続延伸過程の特徴
3.2配向結晶化時の温度・直径プロフィール
3.3X線回折による配向結晶化過程の解析
4PTT, PBT, およびPEN繊維の配向結晶化挙動
5Nylon 6繊維の配向結晶化挙動
6PP, PVDF, およびPVA繊維の配向結晶化挙動
7まとめ
第10章ゴム一軸伸長下の結晶化挙動解析
1はじめに
2応力―歪関係と伸張結晶化の同時測定法
3天然ゴムと合成ポリイソプレン
3.1伸張結晶化と応力―歪関係
3.2結晶分率
3.3延伸結晶の開始歪
3.4結晶の大きさ
3.5結晶格子の大きさ
3.6応力緩和と結晶化
3.7定歪での結晶の融解と生成
4未加硫天然ゴムと未加硫合成ポリイソプレンゴム
5他の汎用加硫ゴム
6充填系加硫物
7まとめ
第11章超高分子量ポリエチレンの溶融超延伸過程におけるインプロセス計測とフィルム高性能化
1はじめに
2インプロセス計測システムの開発とそのインハウス化
3溶融延伸過程におけるインプロセス計測
4溶融延伸挙動に与える分子量特性の効果
5固体NMRによる絡み合い状態の定量化
6今後の展望
第12章一軸伸長過程における長周期構造及びボイドの変化
1はじめに
2繊維の長周期構造
2.1繊維の小角X線散乱パターン
2.2繊維の長周期構造モデル
3繊維・フィルムにおけるボイドの生成・成長挙動
3.1延性・脆性とボイドの生成・成長
3.2繊維の伸長過程におけるボイドの生成・成長挙動
3.3フィルムの伸長過程におけるボイドの生成・成長挙動
3.4ボイドの生成・成長挙動に及ぼすフィラー添加効果及び試験片形状の影響
4おわりに
【第3編】各種ポリマーの結晶化挙動の最新情報
第13章PTTの結晶構造と光学異方性
1はじめに
2結晶化温度とPTT結晶のモルホロジー
3PTT球晶の複屈折
3.1複屈折(リタデーション)の結晶化温度依存性
3.2単位格子の配向方向
3.3固有複屈折の計算
4まとめ
第14章アイソタクチックポリプロピレンのメゾ相形成とメゾ相からの結晶化
1はじめに
2結晶性高分子におけるメゾ相
3iPPのメゾ相のローカル構造
4iPPのメゾ相の形成機構
5iPPコポリマーのメゾ相
6放射光によるiPPのメゾ相形成過程のその場測定
7iPPのメゾ相の安定化エネルギー
8iPPのメゾ相からの速い昇温による結晶化
第15章PLAステレオコンプレックス結晶化
1はじめに
2ポリ乳酸のHMSC結晶化
3置換型ポリ乳酸のHMSC結晶化
4ポリ乳酸/置換型ポリ乳酸のHTSC結晶化
5核剤としての応用
6おわりに
【第4編】特殊条件下の結晶化
第16章超高速DSCによる融解・結晶化挙動解析
1示差走査熱量測定(DSC)
2高分子結晶の融解
3核生成と結晶成長
4高速冷却過程の結晶化
5高速冷却で得られた結晶の融解
6まとめ180
第17章高圧CO2によるPLLAの結晶高次構造と物性の制御
1はじめに
2高圧CO2処理について
3高圧CO2処理したPLLAの構造
3.1結晶化挙動及び結晶構造
3.2結晶高次構造
4高圧CO2処理したPLLAの物性
4.1フィルムの透明性
4.2力学的性質
4.3結晶高次構造と物性との関係
5おわりに
第18章超臨界CO2による結晶高次構造制御
1はじめに
2結晶高次構造
3結晶構造
4結晶化挙動
5結晶化中のCO2の排除と多孔化
6コンポジットにおける結晶核剤効果と高次構造
7部分融解と結晶化
8おわりに
【第5編】成形加工における結晶化制御
第19章成形加工における結晶化の基礎
1はじめに
2準静的な結晶化の考え方
3準静的とする仮定が成り立たない系
4流れ場の影響
4.1エントロピー低下が結晶化を加速する効果
4.2流動履歴が結晶化を加速する効果
4.3どちらの効果が支配的か?
4.4流動場の結晶化に対する核剤の効果
5結晶化の進展が成形加工における高次構造形成挙動に及ぼす影響
6結晶化と複屈折の関係
7延伸過程の結晶化
8今後の流動場の結晶化の研究
8.1溶融紡糸過程の低デボラ数化によるポリエステル繊維の高強度化
8.2ブレンド繊維の低温押出しにおける高融点成分の結晶化
8.3弾性材料の高速紡糸における配向結晶化挙動
9おわりに
第20章PETフィルム成形における結晶化挙動
1はじめに
2PETフィルムの製造プロセス
3フィルム延伸過程における結晶化挙動の解析
4一軸延伸過程におけるPETフィルムの結晶化挙動
5幅拘束一軸延伸におけるPETフィルムの結晶化挙動
6同時二軸延伸過程におけるPETフィルムの配向形成と結晶化挙動
7逐次二軸延伸過程における結晶化挙動
8二軸延伸PETフィルムにおける結晶配向
9おわりに
第21章PETフィルム形成過程における予備加熱効果
1はじめに
2PETの非晶構造制御技術
2.1PET非晶構造
2.2PET結晶構造
2.3拘束非晶構造制御
2.4易成形二軸配向PETフィルム
2.5表面機能化
3応用例
4おわりに
第22章PPシート・フィルム成形における透明性制御
1はじめに
2溶融樹脂膜の外部ヘーズに及ぼす押出スクリュー形状および内部ヘーズに及ぼすダイス内剪断応力の影響
2.1基本形状による予備評価
2.2スクリュー形状の最適化
2.3透明性に与えるダイ内剪断応力の影響
3高透明性PPシート製造に寄与する因子の解析9
3.1透明性に与える立体規則性の影響0
3.2透明性に与える分子量分布の影響
3.3透明性に与える透明改質剤としてのL-LDPE添加の影響
4おわりに
第23章ポリエチレン高強度繊維紡糸過程の構造形成
1はじめに
2紡糸直後の線維の内部構造
3シシケバブ構造の構造形成
4紡糸課程での構造形成の観察
第24章マイクロ射出成形加工における結晶化
1はじめに
2射出成形における結晶化挙動
3マイクロ射出成形による構造形成
3.1超薄肉成形品の構造形成
3.2微小成形品の構造形成
3.3マイクロ微細表面構造を有する成形品の構造形成
4おわりに
-

大容量Liイオン電池の製造・コスト解析と安全性―製造・コスト・安全性・国際規格・市場展望―(普及版)
¥2,255
2013年刊「大容量Liイオン電池の製造・コスト解析と安全性」の普及版。
製造工程とコストを設備投資と原材料費などで分析し、安全性とその測定規格は、産業用とEV用に区分、道路交通サイドの規制も詳説している。
(監修:佐藤登)
<a href="https://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=7926"target=”_blank”>この本の紙版「大容量Liイオン電池の製造・コスト解析と安全性(普及版)」の販売ページはこちら(別サイトが開きます)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
執筆者の所属表記は、2013年当時のものを使用しております。
佐藤登 名古屋大学;エスペック(株)
菅原秀一 泉化研(株)
風間智英 (株)野村総合研究所
藤田誠人 (株)野村総合研究所
-------------------------------------------------------------------------
<<目次>>
第1章 大型リチウムイオン電池の現状と展望
1 はじめに
2 EV法規発効から車載用二次電池開発の歴史を振り返る
3 EVからHEVへのシフトと電池開発
4 自動車各社の開発状況
5 車載用電池の信頼性確保と安全性の確立
第2章 原材料,部材の概要と生産総量(MWh)との関係
1 総括表と動向(1995年~2020年)
1.1 総括表の設定と背景
1.2 原材料別の特徴(1)
1.3 原材料別の特徴(2)
1.4 その他の原材料
1.5 集電箔
1.6 外装材と端子類
2 正負極材と導電剤
2.1 正負極材の投入量
2.2 正極と負極のバランス
2.3 導電剤
3 電解液と電解質
4 セパレータ
5 バインダー
6 集電箔と外装材
6.1 集電箔
6.2 ラミネート外装材
7 原材料,部材の“10年モデル”
7.1 1,000~10,000 MWh/年と材料の所用量
7.2 モデルとしてのHV車
7.3 累積販売台数
8 文献・資料一覧
第3章 大容量Liイオンセルの製造プロセス――前工程,中間工程および後工程――
1 製造業務の流れと区分
1.1 前半と後半,大きく異なる工場環境
1.2 原料から製品まで
1.3 業界としての問題解決
1.4 セルメーカーの二面性
1.5 セル内蔵する化学物質
1.6 化学物質規制とトレーサビリティー
1.7 消防法危険物としての電解液
1.8 セルの集積と電解液の数量
1.9 海外の規制との関連
1.10 REACHの“成形品”
1.11 製造以外の業務
2 製造品目の設定
2.1 製造へのセルの諸元
2.2 Ah容量と関連事項
2.3 Ah容量設定(1)電極板の欠陥
2.4 Ah容量設定(2)不良品対応
2.5 量産段階での問題解決
2.6 Ah容量の測定方法
2.7 市場製品におけるAh表示
2.8 Ah容量の製品事例(1)
2.9 Ah容量の製品事例(2)
2.10 Ah容量の製品事例(3)
2.11 自動車用のAh容量の設定
2.12 定置型の蓄電池の容量
3 製造プロセス全体の流れと生産速度
3.1 全工程の流れ
3.2 製造設備と付帯設備
3.3 原料,部材と製造装置の関係
3.4 工程の操業パターン
3.5 セルのロット管理
3.6 一貫生産と区分・分業スタイル
3.7 区分生産の活用(1)電極板購入
3.8 区分生産の活用(2)乾セル輸出
4 前工程(粉体加工とスラリー調製)
4.1 混合,混練の諸問題
4.2 導電性賦与
4.3 関連(1)導電助剤とバインダーの“機能阻害”
4.4 関連(2)導電剤の不可逆容量
4.5 関連(3)粒子のモルフォロジー
4.6 メカノケミカル(1)分散と混合
4.7 メカノケミカル(2)装置
4.8 粉体のスラリー化
4.9 スラリー媒体の影響
4.10 スラリーの脱泡
4.11 まとめ,混練から粉砕まで
5 中間工程(塗工,乾燥,電極板評価)
5.1 塗工パターンと目付量,充填率
5.1.1 塗工パターン
5.1.2 集電箔と表面
5.1.3 電極板の目付量
5.1.4 電極の断面と厚み
5.1.5 電極板の密度と空隙率
5.2 塗工機と塗工,乾燥過程と塗工速度
5.2.1 塗工機の機構
5.2.2 逐次片面塗工
5.2.3 塗工ヘッド
5.2.4 臨界顔料体積濃度
5.2.5 塗工直後の流れとレベリング
5.2.6 塗工スラリーの媒体
5.2.7 乾燥ステップ
5.2.8 塗工速度と目付量
5.2.9 電極板のアニール
5.3 電極の断面,表面と粒子の結着,接着
5.3.1 模式とイメージ
5.3.2 電極板の表面
5.4 電極板の評価
5.4.1 測定と評価項目
5.4.2 電解液への浸漬試験
5.4.3 セルとしての評価
5.4.4 試作評価のステップ
5.4.5 電極板の試作
6 後工程(プレス,スリット,組立,封止,初充電と検査)
6.1 後工程全体の流れ
6.2 スリットとプレス
6.2.1 スリットとカット
6.2.2 粉落ちとバリ
6.2.3 プレス機のイメージ
6.2.4 プレスの効果(1)
6.2.5 プレスの効果(2)
6.3 セル組立(積層/捲回,電極付,封止)
6.3.1 セルの構造と電極付け
6.3.2 電極板と端子の関係
6.3.3 電極板とセパレータの位置関係
6.3.4 外装材と封止
6.3.5 セルの組立装置(1)
6.3.6 セルの組立装置(2)
6.3.7 端子の接続と溶着
6.3.8 ラミネート外装材の封止
6.3.9 組立セルの最終乾燥
6.3.10 電解液の充填
6.3.11 電解液の取り扱いと安全
6.4 初充電と検査
6.4.1 CC定電流とCV定電圧充電
6.4.2 電流密度と充放電レート
6.4.3 初充電工程における設定とデータ
6.4.4 自己放電量とACR,DCR
6.4.5 生産計画と原材料調達
6.5 類似の蓄電デバイス
6.5.1 リチウムイオンキャパシタ(LIC)とポリマーリチウムイオン
6.5.2 ポリマーリチウムイオン電池
7 製造プロセスの機器とメーカー(転用と新規開発)
7.1 小型と大型の工程機器
7.2 工程機器の海外移転と影響
7.3 この分野への新規参入
7.4 機器ごとの特徴
7.5 付帯設備
7.6 転用と新規開発
第4章 大容量Liイオン電池の原材料コスト
1 タイプ別のセル設計と原材料の投入量および工程ロス
1.1 セルのタイプと原材料
1.2 原材料コスト要因
1.3 標準1Ahセルの体積と重量
1.4 1~100Ahセルの重量
1.5 原材料のコスト例
1.6 工程ロスと影響
1.7 不良ロスの原因
1.8 正常なロスの範囲
1.9 工程ロスの合計
1.10 工程ロスと産業廃棄物
1.11 正負極材の品質保証項目
2 原材料の構成(1) 正極材,負極材および導電剤
2.1 試算の過程
2.2 コストパフォーマンス
2.3 導電剤
3 原材料の構成(2) 電解液,セパレータ,集電箔,バインダー,外装材
3.1 電解液
3.2 セパレータ
3.3 銅とアルミ集電箔
3.4 ラミネート外装材
3.5 金属函体の外装
4 原材料の試算単価レベルの設定
4.1 単価の設定とコスト試算
4.2 高価格レベルの正極材
4.3 負極材のコスト試算
5 正・負極材のコストレベル
5.1 まとめ,正極+負極のコスト
5.2 EV電池に換算した材料コスト
第5章 大容量Liイオン電池の製造コスト, 設備投資と諸費用
1 コストの意味とコスト試算のベース
1.1 二次電池とコスト(容器と中身)
1.1.1 容器と中身
1.1.2 小型,中型のセル
1.1.3 自動車における燃費
1.1.4 系統電力における発電コスト
1.1.5 蓄電コスト
1.2 仮想工場の生産品目の設定とスケール
1.2.1 30Ahセルを100万個/年
1.2.2 市販車のkWh容量との対比
1.2.3 リチウムエナジージャパン㈱LEJの実例
1.2.4 セルの外装形式
2 本体設備
2.1 全体の問題点
2.2 本体製造設備
2.3 設備投資の総額
2.4 設備投資の参考事例
3 付帯設備
3.1 付帯設備の運転コスト
3.2 試験機器と測定
3.3 充放電装置の回生
4 セルの製造原価とコスト構成(原材料,設備償却,労務,用役ほか)
4.1 製造原価の試算
4.2 原材料コストの比率
5 販売価格と利益率
5.1 販売価格の想定
5.2 粗利で見た採算性
5.3 10年後の予測
6 コストダウンの可能性とシミュレーション
6.1 原材料費の影響
6.2 別の試算とシミュレーション
第6章 大容量Liイオン電池の規格と標準化
1 規格の定める内容と諸規格のマップ
1.1 規格の内容
1.2 規格などの拘束力
1.3 規格の対象と内容(1)
1.4 規格の対象と内容(2)
1.5 規格のマップ
1.6 自動車関連
1.7 自動車独自の問題
1.8 化学物質など広範囲の問題
1.9 輸送問題
1.10 試験コスト
2 充放電特性などの測定規格と実施条件
2.1 試験の性格,正常と破壊
2.2 規格などの存在
2.3 付加機器類のコスト
2.4 性能要求事項
2.5 単電池への要求事項(1)
2.6 単電池への要求事項(2)
2.7 単電池への要求事項(3)
2.8 充放電サイクル耐久性
2.9 性能要求事項の解説
3 規格の役割と効果
3.1 規格の役目と効果
3.2 単電池(セル)の規格
3.3 単電池の規格要求事項
3.4 組電池における規格要求事項
4 EU電池指令および海外の動向と国内の対応
4.1 EU指令などとの関連
4.2 日本国内の対応
4.3 電池への表示(マーキング)
5 規格における電圧,電流,充放電,充電率,サイクル特性(技術資料)
第7章 大容量Liイオン電池の安全性試験に関する規格
1 諸規格の一覧 ―電気的試験,機械的試験ほか―
1.1 安全性試験規格の一覧
1.2 アジアの安全性試験規格
1.3 安全性に関する経緯
1.4 ガイドラインとJISの制定
1.5 電気用品安全法
1.6 最新のJIS規格
1.7 試験条件などで一律に決め難い点
1.8 安全性規格の活用
1.9 電気的な安全性試験
1.10 外部短絡,内部短絡
1.11 過充電試験
1.12 セル,モジュール,ユニット
1.13 機械的・熱的な試験
1.14 セルの形状などの影響
2 製品の安全認証システムへの移行
2.1 90年代のISO化からの流れ
2.2 安全性の表示
2.3 TUVによる事例
3 JIS,電気用品安全法および諸規程
3.1 JIS C 8715-2 安全性試験の内容と特徴(1)
3.1.1 JIS制定の経緯
3.1.2 産業用リチウムイオン電池への適用
3.2 JIS C 8715-2 安全性試験の内容と特徴(2)
3.2.1 要求事項とは
3.2.2 試験の実施数
3.2.3 試験結果の扱い
3.3 JIS C 8715-2 安全性試験の内容と特徴(3)
3.3.1 試験前の電池の状態
3.3.2 JIS C 8715-1,2における充電
3.3.3 機能安全性試験における充電停止
3.3.4 試験の求める内容
3.3.5 電池の特性のバラツキ
3.4 関連する技術情報
3.5 電気用品安全性法
4 UL,UNの安全性試験規格と運用
4.1 ULの安全性試験規格
4.2 ULのEVへの拡大
4.3 UN国連危険物輸送基準勧告
4.4 UNの安全試験
4.5 UNクラス9の運用
5 その他の安全性試験規格とハザードレベル
5.1 高速道路などでのEV規制
5.2 中国のEV用安全性規格と釘刺試験
5.3 釘刺試験の実例
5.4 ハザードとリスク
5.5 セルのハザードレベル
6 安全性に関する原材料とセル設計の対応(資料)
第8章 定置用Liイオン蓄電池市場の動向と展望
1 定置用Li イオン蓄電池市場が注目される背景
2 定置用Li イオン蓄電池の市場展望
3 定置用Li イオン蓄電池市場の種類と特徴
3.1 「A;既存市場」
3.2 「B;新規市場」
4 定置用市場の変化
4.1 系統安定化のため発電所/送電網へ設置(B-1)
4.2 送電網への投資延期を目的として配電所へ設置(B-2)
4.3 非常時バックアップや電気代削減のための住宅・建物など電力需要家へ設置(B-3)
5 定置用Li イオン蓄電池市場の動向と予測
-

微粒子分散・凝集ハンドブック(普及版)
¥2,695
2014年刊「微粒子分散・凝集ハンドブック」の普及版。
微粒子の分散・凝集技術について、基礎から工業、環境、先端ナノテクノロジーまで、各分野の詳細研究内容を徹底解説している。
(監修:川口春馬)
<a href="https://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=8093"target=”_blank”>この本の紙版「微粒子分散・凝集ハンドブック(普及版)」の販売ページはこちら(別サイトが開きます)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
執筆者の所属表記は、2014年発行当時のものを使用しております。
芝田隼次 関西大学
大坪泰文 千葉大学
大島広行 東京理科大学
森隆昌 法政大学
種谷真一 種谷技術士事務所
石井利博 アシザワ・ファインテック(株)
光石一太 倉敷ファッションセンター(株)
木俣光正 山形大学
山田保治 神奈川大学
前畑英雄 富士ゼロックス(株)
松村保雄 富士ゼロックス(株)
野口弘道 インクジェットコンサルタント
竹村泰彦 (公社)高分子学会;ゴム技術フォーラム ; 元JSR(株) ; 元(社)日本ゴム協会
坂井悦郎 東京工業大学
岩井和史 (株)レニアス
渡辺実 栗田工業(株)
三浦和彦 東京理科大学
小林大祐 東京理科大学
寺坂宏一 慶應義塾大学
野々村美宗 山形大学
那須昭夫 (株)資生堂
白木賢太郎 筑波大学
岩下和輝 筑波大学
角田裕三 (有)スミタ化学技術研究所
遠藤洋史 東京理科大学
河合武司 東京理科大学
倉島義博 日本ゼオン(株)
矢野浩之 京都大学
河崎雅行 日本製紙(株)
佐藤明弘 星光PMC(株)
伏見速雄 王子ホールディングス(株)
-------------------------------------------------------------------------
<<目次>>
第1章 微粒子分散・凝集の工学
1 水系・非水系における分散・凝集制御
1.1 ゼータ電位と粒子間相互作用
1.1.1 粒子の荷電の原因
1.1.2 ゼータ電位とは
1.1.3 粒子間の距離と引力・反発力エネルギー
1.1.4 ゼータ電位による凝集・分散の制御
1.2 非水系での凝集・分散
1.2.1 無極性非水溶媒中の凝集・分散
1.2.2 極性のある非水溶媒中での凝集・分散
2 凝集分散系のレオロジー
2.1 はじめに
2.2 凝集分散系の基本的なレオロジー挙動
2.2.1 擬塑性流動と降伏応力
2.2.2 凝集分散系の動的粘弾性
2.3 凝集分散系におけるチクソトロピー挙動
2.3.1 粘度の時間依存性と履歴挙動
2.3.2 チクソトロピー挙動の測定
2.4 特異な粒子間相互作用の導入と分散系のレオロジーコントロール
2.4.1 高分子と界面活性剤の併用によるレオロジーコントロール
2.4.2 会合性高分子によるレオロジーコントロール
2.5 おわりに
3 凝集速度の制御
3.1 はじめに
3.2 自由拡散による凝集速度
3.3 粒子間の相互作用
3.4 相互作用場における凝集速度と安定度比
3.5 2次極小を考慮した凝集
3.6 おわりに
第2章 分散・凝集技術
1 分散・凝集の計測と評価 1.1 沈降による評価
1.2 沈降静水圧による評価
1.3 浸透圧による評価
1.4 顕微鏡による直接観察
1.5 分散・凝集評価において注意すべき点
1.5.1 粒子径分布との対応
1.5.2 粘度との対応
2 混合・分散装置
2.1 分散系の流動分散の理論的背景
2.1.1 変形と流動
2.1.2 軌道理論による凝集粒子の分散
2.2 普通撹拌機による分散
2.2.1 回転翼の長さ
2.2.2 粒子の浮遊限界撹拌速度式
2.3 粒子-液系における物質移動
2.4 高速撹拌機による分散
2.5 コロイドミルによる分散
2.6 メディア(媒体)式分散機
2.6.1 メディア式分散機の形態
2.6.2 運転方法
2.7 超音波分散機
3 ビーズミルでの分散技術
3.1 はじめに
3.2 ビーズミルの分散原理
3.3 ビーズミルの運転方法
3.4 ビーズミルの分散効率に影響を与える因子
3.4.1 ビーズ径
3.4.2 ビーズ充填率およびアジテータ周速
3.5 過分散とマイルド分散
3.5.1 過分散
3.5.2 マイルド分散
3.6 ナノ粒子分散大量生産用ビーズミル
3.7 おわりに
4 フィラー分散技術
4.1 はじめに
4.2 フィラーの表面処理技術
4.2.1 シラン剤
4.2.2 チタネート剤
4.2.3 その他のカップリング剤
4.3 フィラー形状が複合材料の特性に及ぼす影響
4.4 フィラーの表面処理手法
4.4.1 湿式加熱法
4.4.2 湿式濾過法
4.4.3 乾式撹拌法
4.4.4 インテグレルブレンド法
4.4.5 スプレードライ法
4.5 フィラーと樹脂の混練分散技術
4.5.1 樹脂とフィラーとの混練性
4.5.2 ナノフィラーを取扱う際の留意点
5 スラリーの調製・分散技術
5.1 はじめに
5.2 付着力
5.3 界面活性剤および水溶性高分子のスラリー分散効果
5.3.1 マグネタイト粒子への吸着
5.3.2 沈降試験
5.3.3 分散スラリーの調製
5.4 おわりに
6 シランカップリング剤の活用
6.1 はじめに
6.2 シランカップリング剤の構造と機能
6.2.1 なぜ有機-無機材料界面の制御が必要か
6.2.2 シランカップリング剤の構造
6.2.3 シランカップリング剤の反応
6.2.4 シランカップリング剤の作用機構
6.2.5 シランカップリング剤の処理効果
6.3 シランカップリング剤の使用・選択法
6.3.1 シランカップリング剤の使用法
6.3.2 シランカップリング剤の使用量
6.3.3 シランカップリング剤の選択基準
6.4 効果的なシランカップリング剤処理法
6.4.1 無機材料表面に薄層(単分子層)を形成させる
6.4.2 溶解度パラメーター(SP値)をそろえる
6.5 おわりに
第3章 工業における分散・凝集
1 トナーの製造における分散制御技術
1.1 はじめに
1.2 電子写真法とトナー製法の変遷
1.3 代表的なケミカルトナープロセスとその特徴
1.3.1 懸濁重合法
1.3.2 乳化重合凝集法
1.3.3 溶解懸濁法
1.3.4 エステル伸長重合法
1.4 ケミカルトナーの画質特性
1.5 おわりに
2 インクジェット(IJ)インクの分散と凝集の制御
2.1 インク機能の3要素
2.2 顔料分散
2.3 インクの調製
2.4 分散状態の測定
2.5 容器内及び装置上の安定性
3 ゴム・エラストマーにおけるフィラー分散制御
3.1 はじめに
3.2 工業的に行われている一般的なゴムへのフィラー分散技術
3.3 無機フィラーのゴム中へのナノ分散系
3.3.1 CB,シリカのナノ分散系
3.3.2 クレーのナノ分散系
3.3.3 カーボンナノチューブ(CNT)のナノ分散系
3.4 有機フィラーのゴム中へのナノ分散系
3.4.1 ゴム中でのin situ有機フィラー合成
3.4.2 セルロースナノファイバー(CNF)のナノ分散系
3.5 おわりに
4 セメントの分散制御とコンクリートの流動性制御
4.1 はじめに
4.2 化学混和剤
4.3 セメント系分散剤
4.4 分散剤によるセメントの分散機構
4.5 ポリカルボン酸系分散剤について
4.6 セメント系材料の粉体設計
4.7 おわりに
5 ハードコート材へのフィラー分散
5.1 はじめに
5.2 赤外線遮蔽ハードコートの設計コンセプト
5.3 赤外線遮蔽機能付与プライマーコートの検討
5.3.1 赤外線遮蔽機能付与プライマーコートの調製
5.3.2 赤外線遮蔽効果の最適化
5.3.3 塗料の保管における注意点
5.4 赤外線遮蔽ハードコートの性能
5.5 まとめ
第4章 環境と生活における分散・凝集
1 排水処理における凝集剤の利用法
1.1 はじめに
1.2 凝集処理の概要
1.3 無機凝結剤の種類と特徴
1.4 有機凝結剤の種類と特徴
1.5 排水処理用高分子凝集剤の種類と特徴
1.6 汚泥処理の概要と脱水用高分子凝集剤
1.7 排水処理の効果的なシステム
2 大気エアロゾル(PM2.5)の生成プロセス
2.1 大気エアロゾル
2.2 エアロゾル粒子の大きさ(粒径)
2.3 粒径分布
2.4 生成プロセス(1) 分散による生成
2.4.1 地表面から発生するエアロゾル粒子(土壌粒子)
2.4.2 海面から発生するエアロゾル粒子(海塩粒子)
2.5 生成プロセス(2) 気体の粒子化による生成
2.5.1 単成分単相粒子生成
2.5.2 多成分単相粒子生成
3 マイクロバブル群の超音波場における凝集と再分散
3.1 マイクロバブル
3.2 拡大視野下でのマイクロバブルの動的挙動の観察
3.2.1 実験装置
3.2.2 超音波照射がマイクロバブルの動的挙動におよぼす影響
3.3 超音波場でのマイクロバブルの凝集・合一
3.4 超音波によるマイクロバブルの急速脱泡
3.4.1 実験装置
3.4.2 超音波が脱泡速度におよぼす影響
3.5 おわりに
4 粉体化粧料における微粒子の分散・成型
4.1 はじめに
4.2 粉体化粧料に配合される微粒子とその役割
4.3 化粧料における微粒子の分散・成型技術
4.3.1 表面処理
4.3.2 界面活性剤の配合
4.3.3 粉体成型
4.4 おわりに
5 紫外線散乱剤の分散技術
5.1 はじめに
5.2 分散安定化の考え方
5.3 紫外線散乱剤分散系の評価方法
5.3.1 紫外線防御性に及ぼす分散状態の影響
5.3.2 レオロジー解析の妥当性および必要性
5.3.3 紫外線散乱剤サスペンションのレオロジー解析
5.3.4 紫外線防御性とレオロジー特性との相関性
5.4 おわりに
6 タンパク質の凝集:モデルと測定法
6.1 はじめに
6.2 タンパク質凝集のモデル
6.3 昇温にともなうタンパク質凝集
6.4 一定温度でのタンパク質の加熱凝集
6.5 タンパク質凝集の測定法
6.6 最後に
第5章 先端ナノテクノロジーにおける分散・凝集
1 カーボンナノチューブの液相および固相分散技術
1.1 はじめに
1.2 カーボンナノチューブの分散における留意点
1.2.1 CNTの観点から
1.2.2 マトリックス(分散媒)の観点から
1.2.3 濡れ剤と分散剤の観点から
1.2.4 分散機の観点から
1.2.5 分散終点の判定
1.3 カーボンナノチューブの分散事例
1.3.1 水中での液相分散
1.3.2 超臨界二酸化炭素を用いたポリカーボネート樹脂中でのCNT分散
1.3.3 亜臨界水を用いた熱可塑性樹脂中でのCNT分散(湿式亜臨界解砕法)
1.3.4 弾性混練法によるCNT/ゴムセルレーション複合材料
1.4 おわりに
2 グラフェンの樹脂分散技術
2.1 はじめに
2.2 グラフェンの特性
2.2.1 グラフェンの分子構造
2.2.2 グラフェンとCNTの比較
2.3 グラフェンおよび酸化グラフェンの製造
2.3.1 グラフェンおよび酸化グラフェンの合成方法
2.3.2 グラフェン類縁体の分類
2.4 グラフェンおよび酸化グラフェンの分散制御
2.4.1 両グラフェンの化学修飾
2.4.2 両グラフェンとポリマーの複合•分散化
2.4.3 ポリイオンコンプレックス形成を利用した酸化グラフェンの自在成形
2.5 おわりに
3 リチウムイオン二次電池のバインダー分散技術
3.1 はじめに
3.2 負極用バインダー
3.2.1 負極用バインダーの種類と特徴
3.2.2 スラリー作製上の留意点
3.2.3 乾燥工程上の留意点
3.3 正極用バインダー
3.3.1 正極用水系バインダー
3.3.2 水系バインダーの分散性
3.3.3 水系正極用バインダーを用いた電池の性能
3.4 まとめ
4 セルロースナノファイバーの製造と分散技術
4.1 はじめに
4.2 セルロースナノファイバーの構造と物性
4.3 セルロースナノファイバーおよびウィスカーの製造
4.4 セルロースナノファイバーおよびウィスカーによるラテックス補強
4.5 構造用セルロースナノファイバー強化材料
4.6 透明ナノコンポジット
4.7 セルロースナノファイバーの染色
4.8 おわりに
5 TEMPO酸化セルロースナノファイバーの分散性について
5.1 はじめに
5.2 CSNFの製造方法とナノ分散化のメカニズム
5.2.1 樹木の階層構造とセルロースミクロフィブリルのナノ分散
5.2.2 CSNFの製造方法
5.3 CSNFの水中における分散性
5.3.1 分散状態の評価法
5.3.2 カルボキシル基量の影響
5.3.3 樹種による影響
5.3.4 分散液中の塩濃度による影響
5.4 CSNFの特長と分散剤としての利用
5.4.1 CSNFの特長と主な用途
5.4.2 CSNFの粘弾性特性
5.4.3 CSNFの分散剤としての利用
5.5 おわりに
6 変性・改質によるセルロースナノファイバーの分散・凝集状態の制御と熱可塑性樹脂との複合化
6.1 はじめに
6.2 CNFの変性・改質について
6.3 静電相互作用を利用したCNFの変性・改質
6.4 変性CNF強化樹脂
6.5 おわりに
7 セルロースナノファイバーの製造と透明シート化技術
7.1 はじめに
7.2 CNF製造技術
7.2.1 酸化処理
7.2.2 エステル化
7.3 CNFの透明シート化技術とその物性
7.3.1 CNFの透明シート化技術
7.3.2 CNF透明シートの物性
7.4 CNF樹脂コンポジットの開発
7.5 おわりに
-

発酵・醸造食品の最新技術と機能性II(普及版)
¥3,080
2011年刊「発酵・醸造食品の最新技術と機能性 II」の普及版!麹菌や酵母など微生物のゲノム情報を利用して展開された研究と、環境・エネルギー問題の解決に貢献する日本の伝統的な発酵醸造技術を紹介!!
(監修:北本勝ひこ
<a href="https://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=5430"target=”_blank”>この本の紙版「発酵・醸造食品の最新技術と機能性II(普及版)」の販売ページはこちら(別サイトが開きます)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は、2011年当時のものを使用しております。
北本勝ひこ 東京大学大学院
北垣浩志 佐賀大学
磯谷敦子 (独)酒類総合研究所
鈴木康司 アサヒグループホールディングス(株)
吉田 聡 キリンホールディングス(株)
井沢真吾 京都工芸繊維大学大学院
高木博史 奈良先端科学技術大学院大学
小笠原博信 秋田県総合食品研究センター
岩下和裕 (独)酒類総合研究所
樋口裕次郎 University of Exeter School of Biosciences Associate
丸山潤一 東京大学大学院
竹内道雄 東京農工大学大学院
堀内裕之 東京大学大学院
板谷光泰 慶應義塾大学
外山博英 琉球大学
松下一信 山口大学
下飯 仁 (独)酒類総合研究所
渡辺大輔 (独)酒類総合研究所
塚原正俊 (株)バイオジェット
鼠尾まい子 (株)バイオジェット
小山泰二 (公財)野田産業科学研究所
小川真弘 (公財)野田産業科学研究所
小池英明 (独)産業技術総合研究所
町田雅之 (独)産業技術総合研究所
大島栄治 三省製薬(株)
比嘉良喬 三省製薬(株)
豊島快幸 ヤマサ醤油(株)
茂木喜信 ヤマサ醤油(株)
鳴海一成 (独)日本原子力研究開発機構
大浦 新 月桂冠(株)
渡辺敏郎 ヤヱガキ醗酵技研(株)
広常正人 大関(株)
竹中史人 辰馬本家酒造(株)
大澤一仁 カルピス(株)
大木浩司 カルピス(株)
木村啓太郎 (独)農業・食品産業技術総合研究機構
尹 載宇 韓国啓明大学校
有岡 学 東京大学大学院
秦 洋二 月桂冠(株)
小池謙造 花王(株)
幸田明生 大関(株)
坊垣隆之 大関(株)
佐々木真弓 旭硝子(株)
東田英毅 旭硝子(株)
-------------------------------------------------------------------------
<<目次>>
第1編:発酵・醸造の基礎研究
第1章 ミトコンドリア輸送をターゲットとした低ピルビン酸清酒酵母の育種とその実用化
1 はじめに
2 ピルビン酸分子の物理化学的性質
3 酵母におけるピルビン酸の代謝
4 酒類醸造におけるピルビン酸・α-アセト乳酸の制御
5 ミトコンドリア輸送をターゲットとするという新たなピルビン酸低減育種手法
6 育種したピルビン酸低減清酒酵母の実地醸造実証試験
7 育種酵母を使った工場スケールの仕込ではエタノール生産能の低下なくピルビン酸及びα-アセト乳酸が顕著に低減している
8 育種したピルビン酸低減清酒酵母の醸造産業への技術移転
第2章 清酒の熟成に関与する香気成分
1 はじめに
2 清酒の貯蔵による香気成分の変化
3 老香と熟成香
4 DMTSの生成機構
5 おわりに
第3章 ビール産業における微生物管理技術の最近の進展
1 ビール混濁性乳酸菌(Lactobacillus属およびPediococcus属)
1.1 ビール混濁性乳酸菌の研究に関わる歴史
1.2 乳酸菌によるビールの変敗現象
1.3 乳酸菌のホップ耐性
1.3.1 細胞膜レベルでの耐性機構
1.3.2 細胞壁レベルにおける耐性機構
1.3.3 その他のホップ耐性機構
1.4 ホップ耐性遺伝子を指標としたビール混濁性判定法
1.5 検査培地で生育しないビール混濁性乳酸菌の検出法の開発
2 Pectinatus属およびMegasphaera属
2.1 Pectinatus属およびMegasphaera属に関わる研究の歴史
2.2 Pectinatus属およびMegasphaera属によるビールの混濁
2.3 Pectinatus属およびMegasphaera属の検査法
2.4 その他のPectinatus属およびMegasphaera属の特徴
3 おわりに
第4章 下面発酵酵母のメタボローム解析
1 はじめに
2 下面発酵酵母の硫黄系物質代謝の解析と亜硫酸高生産株の育種
3 下面発酵酵母の機能未知遺伝子の解析
4 各種酵母のメタボローム解析
5 おわりに
第5章 エタノールストレス応答および醸造過程における酵母mRNA動態とオルガネラ形態変化の解析
1 酵母とエタノールストレス
2 mRNA fluxに及ぼすエタノールストレスの影響
2.1 エタノールストレス応答時の選択的mRNA核外輸送
2.2 HSP mRNAのhyperdadenylationによる核内滞留
2.3 エタノールストレスによる翻訳抑制とP-body・ストレス顆粒
2.4 醸造過程におけるP-bodyの形成
2.5 エタノールストレスによる酵母ストレス顆粒の形成
2.6 エタノールストレス条件下や醸造過程後期での遺伝子発現制御
3 オルガネラに及ぼすエタノールストレスの影響
3.1 ミトコンドリア
3.2 液胞
4 まとめ
第6章 酵母の発酵環境ストレス耐性機構の解析と実用酵母の育種への応用
1 はじめに
2 プロリン
3 プロリン・アルギニン代謝(一酸化窒素生成)
4 ユビキチンシステム
5 おわりに
第7章 麹菌におけるトランスポゾン(Crawler)活性の発見と実用株育種への応用
1 はじめに
2 糸状菌および麹菌のトランスポゾン研究
3 麹菌のDNAトランスポゾンCrawlerの構造的特徴
4 Crawlerの活性化とトランスポゾン・トラッピング
5 様々なCrawler転移株の挿入位置
6 Crawlerの切り出し効率の計測による転移活性化条件の再検討
7 Crawlerの足跡配列(Footprint)
8 Crawlerの各種麹菌株における分布
9 Crawlerの実用株育種への応用
10 おわりに
第8章 糸状菌に特異な機能未知遺伝子を探る
1 はじめに
2 糸状菌のゲノム解析と機能未知遺伝子
3 糸状菌類に保存された機能未知遺伝子
4 糸状菌類に高度に保存され高発現する遺伝子の破壊
5 遺伝子破壊株の表現型
第9章 麹菌のタンパク質分泌経路とエンドサイトーシス
1 はじめに
2 麹菌のタンパク質分泌経路の解析
2.1 分泌タンパク質の可視化
2.2 タンパク質分泌機構の可視化
2.2.1 ERの可視化
2.2.2 SNAREの可視化
2.3 隔壁へのタンパク質分泌経路の解析
3 麹菌のエンドサイトーシスの解析
3.1 糸状菌におけるエンドサイトーシスのこれまでの研究
3.2 麹菌におけるエンドサイトーシスの可視化
3.3 麹菌の菌糸先端におけるエンドサイトーシスによるリサイクリング
4 まとめ
第10章 麹菌の隔壁孔を介した細胞間連絡―多細胞生物としての生育を支える分子メカニズム―
1 はじめに
2 麹菌では低浸透圧ショックにより菌糸先端が溶菌する
3 Woronin bodyは隔壁孔をふさぎ溶菌の伝播を防ぐ
4 Woronin bodyはペルオキシソームから分化する
5 ストレスに応答して隔壁孔に凝集するタンパク質
6 おわりに
第11章 ゲノム情報に基づく麹菌プロテアーゼ遺伝子とその産物の解析
1 はじめに
2 エキソ型プロテアーゼ
2.1 アミノペプチダーゼ
2.2 ジペプチジル―,トリペプチジルペプチダーゼ
2.3 カルボキシペプチダーゼ(CPase)
2.3.1 セリンタイプCPase
2.3.2 メタロCPase
2.4 ジペプチダーゼ
3 エンド型プロテアーゼ
3.1 セリンプロテアーゼ
3.2 システインプロテアーゼ
3.3 アスパルティックプロテアーゼ
3.4 金属プロテアーゼ
4 おわりに
第12章 麹菌とその近縁糸状菌のキチン合成酵素とキチナーゼ
1 はじめに
2 キチン合成酵素
2.1 クラスIとクラスIIに属するキチン合成酵素
2.2 クラスIIIに属するキチン合成酵素
2.3 クラスVとクラスVIに属するキチン合成酵素
2.4 クラスIV,VIIに属するキチン合成酵素
3 キチナーゼ
3.1 クラスIIIキチナーゼ
3.2 クラスVキチナーゼ
4 おわりに
第13章 納豆菌と枯草菌:ゲノムから眺める安全な菌の活用
1 はじめに
2 枯草菌ゲノムと納豆菌ゲノム解読
3 ゲノムから見えた納豆菌KEIO株
3.1 予想以上に多かったIS
3.2 納豆菌plasmids
4 枯草菌と納豆菌の有効活用
4.1 枯草菌168株ゲノムコンパクト化
4.2 枯草菌168株ゲノム活用
4.3 納豆菌のゲノム活用
5 おわりに
第14章 耐熱性酢酸菌を使った酸化発酵による有用物質生産系の開発
1 はじめに
2 酢酸菌と酸化発酵
3 耐熱性酢酸菌と耐熱化の機構について
4 耐熱性酢酸菌を使った酢酸発酵
5 耐熱性酢酸菌を使った有用物質生産
6 おわりに
第2編:醸造微生物の最新技術
第15章 清酒酵母と実験室酵母の交配による清酒醸造特性のQTL解析
1 はじめに
2 清酒酵母と他の酵母はどこが違うのか
3 清酒酵母の特性を決定する遺伝子の解析
4 質的形質と量的形質
5 QTL解析実験のデザイン
6 K7の一倍体の取得と醸造特性の解析
7 清酒酵母と実験室酵母の交雑によって得られた一倍体の醸造特性の解析
8 醸造特性のQTL解析
9 発酵力に関与するQTLの原因遺伝子の推定
10 細胞増殖速度のQTL解析
11 おわりに
第16章 ガス発生量計測システムを用いた清酒発酵プロファイルの定量的解析
1 はじめに
2 清酒醸造における発酵モニタリング
3 ガス発生量計測システムを用いた清酒発酵モニタリング
4 清酒発酵プロファイルの定量的解析
4.1 清酒もろみにおける発酵速度
4.2 発酵速度のピークに関する定量的解析
4.3 清酒発酵プロファイルのモデル化に向けて
5 おわりに
第17章 清酒酵母のストレス応答欠損と高エタノール発酵性
1 はじめに
2 実はストレスに弱い清酒酵母
3 清酒酵母におけるストレス応答欠損の分子メカニズム
3.1 清酒酵母のストレス応答欠損
3.2 清酒酵母に特異的なMSN4遺伝子の機能欠失変異
3.3 清酒酵母に特異的なHsf1pの恒常的高リン酸化
4 ストレス応答とエタノール発酵との新たな関係性
5 おわりに
第18章 次世代シーケンサSOLiDを用いた実用泡盛黒麹菌株の比較ゲノム解析
1 泡盛と黒麹菌株
2 実用泡盛黒麹菌株における比較ゲノム解析の意義
3 次世代シーケンサSOLiDによる黒麹菌の解析
4 黒麹菌遺伝子と泡盛風味の関係
5 今後の展望
第19章 麹菌における染色体工学と転写因子の網羅的解析
1 はじめに
2 遺伝子破壊株の作製
3 遺伝子破壊ライブラリーの作製
4 遺伝子破壊株の解析
5 染色体工学を用いた転写因子遺伝子の解析
6 まとめ
第20章 コウジ酸の生合成遺伝子,麹菌培養条件に応答した遺伝子発現機構
1 コウジ酸の産業利用
2 条件特異的な生合成
3 DNAマイクロアレイによる発現解析
4 得られた遺伝子クラスターの特徴
5 KA生産に関連した転写制御
6 まとめ
第21章 イオンビーム,ガンマ線照射が誘発する麹菌ゲノム変異の解析と麹菌育種への展開
1 はじめに
2 イオンビームおよびガンマ線照射について
3 麹菌へのイオンビームおよびガンマ線照射について
4 生存率の比較
5 変異率の比較
6 変異スペクトルの解析
6.1 点変異
6.2 染色体間組換え
6.3 大規模遺伝子欠損
7 おわりに
第3編:醸造食品の機能性
第22章 酒粕由来機能性ペプチド
1 はじめに
2 前回からの続報
3 「機能性データベース~清酒編」の更新
3.1 サンプル素材
3.2 アッセイ系
3.3 効果・効能
3.4 同定成分
4 乳酸発酵液化粕
4.1 抗健忘症作用
4.2 血圧降下作用
4.3 酒粕ペプチドとの組み合わせ効果
5 酒粕ペプチドの肝細胞保護効果
5.1 in vitro細胞試験
5.2 マウス肝機能保護試験
5.3 酒粕ペプチドの成分同定
6 今後の展望
第23章 酒粕レジスタントプロテイン
1 はじめに
2 レジスタントプロテイン
3 酒粕発酵物
4 酒粕発酵物の機能性
4.1 高コレステロール食における脂質代謝改善効果
4.2 コレステロール胆石形成抑制効果
4.3 油吸着効果
4.4 肥満抑制効果
4.5 腸内環境改善効果
5 おわりに
第24章 甘酒の栄養素と機能性
1 はじめに
2 甘酒の栄養素
3 甘酒の機能性
4 甘酒のヒトの健康への効果
5 おわりに
第25章 日本酒由来成分αGGの機能性
1 はじめに
2 清酒中のαGG
3 αGGの化学的特性
4 αGGの経口摂取による機能性
5 αGGの外用剤としての機能性
6 おわりに
第26章 酸乳の脳機能改善作用
1 はじめに
2 酸乳の脳機能改善作用
2.1 評価法
2.2 評価物質
2.3 酸乳の単回投与による記憶障害予防作用
2.4 酸乳の単回投与による学習記憶力向上作用
2.5 酸乳の長期投与による学習記憶力向上作用
3 おわりに
第27章 納豆の機能性
1 はじめに
2 1次機能(エネルギー・栄養補給機能)
3 2次機能(嗜好性,色,形,食感などにより食欲を左右する機能)
4 3次機能(生体の正常な機能を維持するための生体調節機能)
5 おわりに
第4編:醸造微生物による物質生産
第28章 有用タンパク質生産のための麹菌の育種
1 はじめに
2 pyrG選択マーカー遺伝子リサイクリング技術の確立
3 プロテアーゼ遺伝子多重破壊株による異種タンパク質の生産
4 液胞タンパク質ソーティングレセプター遺伝子破壊株による異種タンパク質の生産
5 おわりに
第29章 麹菌によるシロアリセルラーゼの生産
1 はじめに
2 セルロース系バイオマスの糖化
3 シロアリセルラーゼのバイオマス消化システム
4 麹菌を用いた異種タンパク質生産システム
5 麹菌を用いたシロアリおよび共生原生生物由来エンドグルカナーゼの生産
5.1 シロアリ由来GHF9エンドグルカナーゼ
5.2 共生原生生物由来GHF7エンドグルカナーゼ
5.3 共生原生生物由来GHF45エンドグルカナーゼ
5.4 シロアリ由来β-グルコシダーゼ
6 おわりに
第30章 麹菌チロシナーゼを用いた新規染毛料原料のバイオ生産
1 はじめに
2 固体培養で発現する麹菌チロシナーゼの発見
3 麹菌チロシナーゼを染毛料へ利用
4 メラニン前駆体のバイオ合成に向けたプロセス開発
5 メラニン前駆体・DHIの工業生産
6 メラニン前駆体による染毛技術の開発
7 おわりに
第31章 麹菌タンパク質高発現システムを用いた有用タンパク質の生産
1 はじめに
2 麹菌タンパク質高発現システムの構築
2.1 高発現プロモーターの開発
2.2 5'UTRの改変による翻訳の効率化
3 異種タンパク質の発現
3.1 野生型遺伝子の発現
3.2 遺伝子のデザイン
3.3 合成遺伝子を用いた発現
4 BDF生産用リパーゼの発現
4.1 開発の背景
4.2 各種リパーゼの高生産
4.3 放射線照射による変異導入
4.4 メタノリシス反応
5 おわりに
第32章 分裂酵母ミニマムゲノムファクトリーを用いた物質生産系の改良
1 はじめに
2 分裂酵母染色体縮小化株の構築
3 分裂酵母染色体縮小化株の増殖性能
4 分裂酵母染色体縮小化株における異種タンパク質生産性の向上
5 異種タンパク質生産性向上機構の解析
6 おわりに -

レアメタルフリー二次電池の最新技術動向(普及版)
¥3,410
2013年刊「レアメタルフリー二次電池の最新技術動向」の普及版!豊富な資源を使い、低コストで、大容量化、長寿命化、高安全性を目指した次世代二次電池の開発動向を詳述!!
(監修:境 哲男)
<a href="https://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=5711"target=”_blank”>この本の紙版「レアメタルフリー二次電池の最新技術動向(普及版)」の販売ページはこちら(別サイトが開きます)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は、2013年当時のものを使用しております。
境 哲男 (独)産業技術総合研究所
岡田重人 九州大学
智原久仁子 九州大学
中根堅次 住友化学(株)
久世 智 住友化学(株)
藪内直明 東京理科大学
片岡理樹 (独)産業技術総合研究所
向井孝志 (独)産業技術総合研究所
稲澤信二 住友電気工業(株)
沼田昂真 住友電気工業(株)
井谷瑛子 住友電気工業(株)
福永篤史 住友電気工業(株)
酒井将一郎 住友電気工業(株)
新田耕司 住友電気工業(株)
野平俊之 京都大学大学院
萩原理加 京都大学大学院
小山 昇 エンネット(株)
幸 琢寛 (独)産業技術総合研究所
小島敏勝 (独)産業技術総合研究所
上町裕史 (株)ポリチオン
辰巳砂昌弘 大阪府立大学
長尾元寛 大阪府立大学
林 晃敏 大阪府立大学
森下正典 (独)産業技術総合研究所
江田祐介 (独)産業技術総合研究所
坂本太地 (独)産業技術総合研究所
小島 晶 神戸大学大学院
岩佐繁之 日本電気(株)
佐藤正春 (株)村田製作所
目代英久 (株)本田技術研究所
鋤柄 宜 (株)本田技術研究所
本間 格 東北大学
八尾 勝 (独)産業技術総合研究所
山縣雅紀 関西大学
石川正司 関西大学
永金知浩 日本電気硝子(株)
森田昌行 山口大学
吉本信子 山口大学
高﨑智昭 川崎重工業(株)
西村和也 川崎重工業(株)
-------------------------------------------------------------------------
<<目次>>
第1章 ナトリウムイオン電池用材料の研究開発
1 材料開発1
1.1 ポストリチウムイオン二次電池の背景
1.2 ナトリウムイオン電池用正極候補
1.2.1 層状岩塩酸化物NaFeO2
1.2.2 層状硫化物TiS2
1.2.3 パイライト型硫化物FeS2
1.2.4 フッ素化ポリアニオン系Na3V2(PO4)2F3
1.2.5 有機系ロジゾン酸二ナトリウムNa2C6O6
1.3 ナトリウムイオン電池用負極候補
1.3.1 ナトリウム金属
1.3.2 金属系負極
1.3.3 炭素
1.4 ナトリウムイオン二次電池
1.5 まとめ
2 材料開発2
2.1 はじめに
2.2 材料設計における基本指針
2.3 層状酸化物
2.4 オキソ酸塩系材料
2.5 まとめ
3 材料開発と電池化
3.1 諸言
3.2 正極材料
3.3 負極材料
3.4 Na0.95Li0.15(Ni0.15Mn0.55Co0.1)O2/Sn-Sb硫化物系ナトリウムイオン電池の充放電特性と安全性評価
3.5 まとめ
4 FSA系溶融塩電解質電池
4.1 はじめに
4.2 MSBの現状
4.2.1 アルカリ金属ビス(フルオロスルフォニル)アミド塩の電池電解液への適用
4.2.2 充放電特性
4.2.3 フローティング充電特性
4.2.4 組電池の試作
4.3 電池の安全性に関する検討
4.4 まとめ
第2章 イオウ系材料の研究開発
1 イオウ系正極の開発状況 小山昇
1.1 はじめに
1.2 結合およびレドックス活性
1.3 単体硫黄のレドックス特性
1.4 硫黄化合物のレドックス電位による分類
1.4.1 第一グループの有機物
1.4.2 第二グループの有機物
1.4.3 第三グループの有機物
1.5 おわりに
2 有機硫黄系正極の研究開発
2.1 はじめに
2.2 硫黄系正極について
2.3 硫黄系正極の課題
2.4 硫黄変性ポリアクリロニトリル正極材料の合成と電極・電池を用いた評価の概要
2.5 硫黄変性ポリアクリロニトリル材料の合成
2.6 硫黄変性ポリアクリロニトリルの材料特性
2.7 電極およびセルの作製と充放電試験条件
2.7.1 塗工電極
2.7.2 カーボンペーパーを集電体に用いた電極
2.7.3 電池構成
2.8 電極性能
2.8.1 SPAN電極のサイクル寿命
2.8.2 SPAN電極の入出力特性
2.8.3 SPAN電極の体積変化
2.9 SPAN/SiO系フルセルの電池性能
2.9.1 フルセル用Liプリドープ設計
2.9.2 サイクル特性
2.9.3 出力特性
2.9.4 温度特性
2.9.5 大型電池
2.10 SPAN正極を用いたその他の電池
2.10.1 全固体電池
2.10.2 メタルフリー電池
2.10.3 バイポーラ型電池
2.10.4 ナトリウムイオン二次電池
2.10.5 その他の有機硫黄系正極
2.11 SPAN/SiO系電池の安全性試験
2.11.1 釘刺し試験
2.11.2 過充電試験と発生ガスの分析
2.12 まとめと展望
3 硫黄導電性高分子「ポリチオン」
3.1 はじめに
3.2 硫黄系材料および有機系正極材の開発動向
3.2.1 硫黄
3.2.2 有機ジスルフィド化合物
3.2.3 含硫黄ポリマー
3.2.4 正極材料の高容量化:有機系正極材
3.3 ポリチオンの有機硫黄ポリマー
3.3.1 コンセプト
3.3.2 有機硫黄ポリマーの展開
3.4 合成ならびに製造法の検討
3.4.1 合成指針
3.4.2 製造に向けた取組み
3.5 電池特性
3.6 化学構造と電子構造の評価
3.6.1 化学構造:結晶構造評価
3.6.2 電子構造XAFS評価
3.7 実用化製造検討
3.8 まとめと今後
4 硫化物無機固体電解質を用いた全固体硫黄系電池の開発 辰巳砂昌弘,長尾元寛,林晃敏
4.1 はじめに
4.2 硫化物ガラス系固体電解質を用いたバルク型全固体リチウム電池
4.3 硫黄系正極―銅複合体の全固体リチウム電池への応用
4.3.1 硫黄系正極材料を用いた全固体二次電池
4.3.2 単体硫黄―銅系複合体の作製と全固体Li/S電池
4.3.3 硫化リチウム―銅系複合体の作製と全固体Li/S電池
4.4 硫黄系正極―ナノカーボン複合体の作製と全固体リチウム電池への応用
4.4.1 単体硫黄―ナノカーボン複合体の作製と全固体Li/S電池
4.4.2 硫化リチウム―ナノカーボン複合体の作製と全固体Li/S電池
4.5 おわりに
第3章 シリコン系材料の研究開発
1 シリコン系負極材料
1.1 はじめに
1.2 Si負極を用いたセルの作製と評価
1.3 Si粉末の製造法について
1.4 各種Si負極の特性
1.5 Si負極の体積変化
1.6 LiFePO4正極/Si負極セル
1.6.1 入出力特性
1.6.2 高温・低温特性
1.7 高エネルギー密度形Li過剰正極/Si負極セル
1.7.1 初期特性とサイクル特性
1.7.2 釘刺し試験
1.8 おわりに
2 ケイ酸塩系正極材料の合成と電極特性
2.1 はじめに
2.2 リチウムシリケート系材料の開発経緯
2.2.1 リチウムシリケートの材料研究
2.2.2 リチウムシリケートの電極材料としての検討
2.2.3 リチウムシリケート正極の熱的安定性
2.2.4 リチウムシリケートの合成方法とカーボン付与方法
2.2.5 リチウムシリケート正極材料の構造の研究
2.2.6 リチウムシリケート正極材料の計算化学研究
2.2.7 リチウムシリケート正極材料の世界的研究動向
2.3 シリケート系正極材料の特性
2.3.1 溶融炭酸塩を用いたリチウムシリケート系正極の合成
2.3.2 シリケート系正極材料の特性評価
2.3.3 Li2FeSiO4を用いた実電池の作製と評価
2.4 シリケート系正極材料の今後
2.5 まとめ
第4章 有機系材料の研究開発
1 有機ラジカル正極
1.1 まえがき
1.2 ラジカルポリマー正極
1.3 PTMA有機ラジカル電池の特性
1.4 エネルギー密度の向上(n型ラジカル材料)
1.5 むすび
2 多電子系有機二次電池
2.1 はじめに
2.2 高エネルギー密度有機二次電池の開発戦略
2.3 有機二次電池と多電子反応
2.4 ルベアン酸を活物質とする多電子系有機二次電池
2.5 ルベアン酸誘導体
2.6 多電子系有機二次電池の可能性
3 有機全固体電池 本間格
3.1 はじめに
3.2 有機活物質の多電子反応容量
3.3 有機活物質の高エネルギー密度特性
3.4 準固体電解質
3.5 有機分子の電極特性
3.6 全固体電池デバイス
3.7 全固体電池のサイクル特性
3.8 まとめ
4 キノン系有機正極
4.1 レアメタルフリー正極としての有機正極
4.1.1 はじめに
4.1.2 有機正極の先行研究
4.2 結晶性低分子有機正極
4.2.1 ジメトキシベンゾキノン
4.2.2 環拡張型キノン
4.2.3 インディゴ
4.3 ナトリウム電池やマグネシウム電池への適用
4.4 課題と今後の展開
5 天然高分子を用いた蓄電デバイス用材料の研究開発
5.1 はじめに
5.2 天然高分子を用いたゲル電解質の開発
5.2.1 電気化学キャパシタ用ゲル電解質
5.2.2 リチウムイオン二次電池用ゲル電解質への展開
5.3 天然高分子を用いた複合電極の開発
5.3.1 電気化学キャパシタ用活性炭複合電極の開発とその高出力特性
5.3.2 リチウムイオン電池用複合電極に対する天然高分子バインダーの可能性
5.4 おわりに
第5章 ガラス結晶化法によるリン酸鉄正極材料の開発
1 はじめに
2 LFP結晶化ガラスの製造プロセス
3 LFP結晶化ガラスの構造
4 LFP結晶化ガラスの電池特性
5 まとめ
第6章 マグネシウム二次電池材料の研究開発
~現状と課題
1 はじめに
2 負極材料のための電解質設計
2.1 マグネシウムイオン電池用負極材料の電解質設計
2.2 マグネシウム金属負極の電解質設計
2.3 電解質の固体化
3 正極材料のための電解質設計
4 おわりに
第7章 ニッケル水素化物電池のレアメタルフリー化
1 諸言
2 産業用大型Ni-MH電池
3 合金負極のコバルトフリー化
4 ニッケル正極のコバルトフリー化
5 電極のファイバー化によるコバルトフリー化
6 おわりに -

ナノワイヤ最新技術の基礎と応用展開(普及版)
¥3,190
2013年刊「ナノワイヤ最新技術の基礎と応用展開」の普及版。「ナノワイヤ」の基礎(成長、物性・理論)から、太陽電池をはじめ発光ダイオード、レーザー、センサー、光検出器など、デバイスへの応用を網羅!!
(監修:福井孝志)
<a href="https://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=5712"target=”_blank”>この本の紙版「ナノワイヤ最新技術の基礎と応用展開(普及版)」の販売ページはこちら(別サイトが開きます)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は、2013年当時のものを使用しております。
福井孝志 北海道大学
比留間健之 (株)日立製作所
竹田精治 大阪大学産業科学研究所
清水智弘 関西大学
小田俊理 東京工業大学
舘野功太 NTT物性科学基礎研究所
池尻圭太郎 北海道大学
山口雅史 名古屋大学
原真二郎 北海道大学
岡田龍雄 九州大学
中村大輔 九州大学
本久順一 北海道大学
深田直樹 (独)物質・材料研究機構
河口研一 (株)富士通研究所
荒川泰彦 東京大学
有田宗貴 東京大学
舘林 潤 東京大学
八井 崇 東京大学大学院
秋山 亨 三重大学
広瀬賢二 日本電気(株)
小林伸彦 筑波大学
岸野克巳 上智大学
和保孝夫 上智大学
冨岡克広 北海道大学量;(独)科学技術振興機構
柳田 剛 大阪大学
吉村正利 北海道大学
-------------------------------------------------------------------------
<<目次>>
序章 ナノワイヤ研究の最新動向
【第I編 成長】
第1章 ナノワイヤ成長の概論
1 はじめに ―ナノワイヤのルーツ:ホイスカー ―
2 ホイスカーからナノワイヤへ
3 ナノワイヤの成長機構
3.1 中軸ラセン転位による成長
3.2 気相-液相-固相(Vapor-Liquid-Solid)成長
3.3 ナノワイヤの選択成長
3.4 ナノワイヤ成長における原料原子の表面拡散効果
3.5 異種材料接合におけるナノワイヤ成長
4 まとめ
第2章 VLSシリコンナノワイヤー成長
1 はじめに
2 VLS法によるシリコン・ナノワイヤー成長を決める因子
3 VLS法によるシリコン・ナノワイヤー成長の実際
4 触媒となる金シリコンナノ液滴
5 シリコン・ナノワイヤーの核形成
6 シリコン・ナノワイヤー成長過程の解析
7 おわりに
第3章 テンプレート成長法について
1 はじめに
2 テンプレートについて
3 テンプレート中での成長方法について
4 自己組織形成テンプレートを用いたナノワイヤの成長
第4章 VLS Geナノワイヤ成長
1 はじめに
2 VLS成長
3 種々の触媒金属
4 垂直成長
5 Ge-NW成長の精密制御
6 Ge-NWの低温成長
7 デバイス応用
8 おわりに
第5章 VLS法によるIII-V族ナノワイヤ成長
1 はじめに
2 長波長帯発光ナノワイヤ
3 GaAs(311)B基板上横成長GaAsナノワイヤ
4 自己触媒VLS法によるInPナノワイヤ
5 InAsナノワイヤの超伝導量子デバイスへの応用展開
6 まとめ
第6章 選択成長法によるIII-V族化合物半導体ナノワイヤ
1 はじめに
2 MOVPE選択成長法によるナノワイヤ形成プロセス
3 選択成長によるナノワイヤの形状および結晶構造解析
3.1 選択成長におけるファセッティング成長(GaAs選択成長基板面方位依存性)
3.2 選択成長によるナノワイヤの成長特性
3.3 ナノワイヤの形状制御技術 成長の縦・横方向制御
3.4 ナノワイヤの結晶構造解析
4 ナノワイヤにおける結晶構造の変化
5 ナノワイヤの成長機構モデル
6 Si基板上のナノワイヤ選択成長
7 おわりに
第7章 III-Vナノワイヤon Si
1 はじめに
2 Si基板上無触媒(自己触媒)VLS法による化合物半導体ナノワイヤ
3 Ga供給量依存性
4 As供給量依存性
5 成長中断の効果
6 GaAs/AlxGa1-xAsのコア・シェルヘテロ構造
7 まとめ
第8章 強磁性体/半導体複合ナノワイヤ
1 はじめに
2 作製プロセス
3 強磁性体ナノクラスタの選択形成
4 強磁性体/半導体複合ナノワイヤの選択形成
5 電気特性
6 おわりに
第9章 ZnOナノワイヤ成長
1 はじめに
2 ZnOナノ結晶の成長
2.1 CVD
2.2 熱炭素CVD
2.3 パルスレーザー堆積法
2.4 水熱法
2.5 電着法
3 制御法
3.1 成長方向制御
3.2 結晶サイズの制御
3.3 密度制御
3.4 成長位置
4 導電性制御
5 まとめ
【第II編 物性・理論】
第1章 光物性
1 はじめに
2 ナノワイヤ光導波路と共振器効果
3 光学異方性
4 結晶構造転移と光学特性
5 ナノワイヤアレイにおける光吸収
6 ヘテロ構造半導体ナノワイヤの発光特性
7 光励起による誘導放出およびレーザ発振
8 ナノワイヤ発光素子
9 おわりに
第2章 ドーピング
1 はじめに
2 ドーピング方法
2.1 成長時ドーピング
2.2 イオン注入を利用したドーピング
3 ドーピング評価
3.1 結合・電子状態
3.2 不純物分布
3.3 不純物の挙動
4 まとめ
第3章 径方向量子井戸・量子ドットナノワイヤ構造と光学特性
1 はじめに
2 ナノワイヤに形成可能な量子ヘテロ構造
3 径方向量子井戸ナノワイヤの物性
4 径方向量子ドットナノワイヤの物性
5 まとめ
第4章 ナノワイヤ量子ドットの光学特性
1 はじめに
2 位置制御された単一GaN/AlGaNナノワイヤ量子ドットの結晶成長と光学特性
3 InGaAs/GaAsナノワイヤ量子ドットの結晶成長と光学特性
4 InGaAs/GaAsナノワイヤ積層量子ドットの結晶成長と光学特性
5 おわりに
第5章 ZnOナノロッド量子井戸構造を用いたナノフォトニックデバイスの進展
1 まえがき
2 ZnOナノロッド量子井戸構造
3 近接場エネルギー移動の制御
4 近接場光の協調現象の観測
5 むすび
第6章 形成機構計算
1 はじめに
2 ナノワイヤの結晶構造
3 ナノワイヤにおける閃亜鉛鉱-ウルツ鉱構造相対的安定性
4 二次元核形成にもとづくナノワイヤ形成機構
5 エピタキシャル成長条件を考慮したナノワイヤ形成機構
6 ナノワイヤ形状の成長条件依存性
7 まとめ
第7章 熱伝導、熱電性能
1 ナノワイヤの熱伝導実験
2 ナノワイヤの熱伝導計算
3 低温での普遍的な熱伝導の振舞い
4 熱電エネルギー変換と熱電性能指数
4.1 熱電性能の物性・理論
4.2 ナノワイヤの熱電性能増大の可能性
4.3 シリコンナノワイヤの熱電性能実験
4.4 シリコンナノワイヤの熱電性能計算
5 まとめ
【第III編 デバイス】
第1章 GaN ナノコラム発光デバイス
1 はじめに
2 GaN 系発光デバイスの直面する課題
3 ナノコラムとナノ結晶効果
4 規則配列ナノコラムとナノコラムLED
5 発光色制御と集積型LED
6 まとめ
第2章 回路応用
1 はじめに
2 デジタル回路
3 アナログ回路
4 ナノワイヤの配置制御技術
5 むすび
第3章 ナノワイヤのトランジスタ応用
1 はじめに
2 ナノワイヤトランジスタの技術動向
3 Si基板上のIII-Vナノワイヤ選択成長
4 ナノワイヤ縦型トランジスタの作製
5 InGaAs/InP/InAlAs/InGaAsコアマルチシェルナノワイヤチャネル
6 まとめ
第4章 ナノワイヤを活用した不揮発性メモリ―ナノワイヤメモリスタ―
1 はじめに
2 自己組織化酸化物ナノワイヤを用いたプレーナー型メモリスタ素子
3 ナノワイヤメモリスタを用いた極微素子特性の解明
4 ナノワイヤメモリスタ素子を用いた動作起源の解明
5 おわりに
第5章 III-V族化合物半導体ナノワイヤ太陽電池
1 はじめに
2 ナノワイヤの特長
2.1 光トラッピング
2.2 電子正孔対分離の改善
2.3 格子不整合の緩和
2.4 省資源化
3 III-V族化合物半導体ナノワイヤ太陽電池の動向
4 今後の展開
4.1 高効率化
4.2 低コスト化
5 まとめ -

定置型Liイオン蓄電池の開発(普及版)
¥2,640
2013年刊「定置型Liイオン畜電池の開発」の普及版!定置型Liイオン蓄電池の用途、コスト解析、劣化診断、システム適用と 材料の長寿命化、正極材、負極材、電解液、セパレータ、バインダー、集電箔、外装材等を紹介!!
(監修:堀江英明,田中謙司)
<a href="https://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=5722"target=”_blank”>この本の紙版「定置型Liイオン畜電池の開発(普及版)」の販売ページはこちら(別サイトが開きます)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は、2013年当時のものを使用しております。
堀江英明 東京大学
田中謙司 東京大学
今村大地 (一財)日本自動車研究所
藤原信浩 (株)先端技術情報総合研究所
藤田誠人 (株)野村総合研究所
菅原秀一 泉化研(株)
鳩野敦生 前・富士重工業(株)
橋崎克雄 三菱重工業(株)
小暮正紀 三菱重工業(株)
橋本 勉 三菱重工業(株)
辻川知伸 (株)NTTファシリティーズ
荒川正泰 (株)NTTファシリティーズ総合研究所
小沢和典 エナックス(株)
田路和幸 東北大学
南野充則 伊藤忠テクノソリューションズ(株)
荻須謙二 戸田工業(株)
斉藤光正 住友大阪セメント(株)
武内正隆 昭和電工(株)
鳶島真一 群馬大学
山田一博 東レバッテリーセパレータフィルム(株)
荒井健次 日本ゼオン(株)
高橋直樹 日本ゼオン(株)
-------------------------------------------------------------------------
<<目次>>
【第1編 総論 定置型リチウムイオン蓄電池の可能性と展望】
第1章 リチウムイオン電池とスマートグリッド用定置型市場創造への可能性
1 はじめに
2 電力システムの課題
3 内燃機関と双方向エネルギーネットワークシステムの要件
4 高性能環境車両の取り組みと考え方
5 エネルギーのタイムシフトとネットワーク化
6 都市・地域のエネルギーシステムの『ハイブリッド化』
7 巨大市場としての定置用リチウムイオン電池の可能性
8 二次電池の歴史と課題
9 リチウムイオン電池の動作原理
10 民生用電池の価格
11 定置用電池の価値とコスト
12 リチウムイオン電池の寿命
第2章 グリッドスケール蓄電池の定置用途への取組みと今後の可能性
1 概要
2 電力グリッドにおける蓄電システムの可能性
2.1 他のエネルギー貯蔵方式との比較
3 定置用二次電池を用いた都市のエネルギー効率化への運用サービス設計
第3章 車載用リチウムイオン電池の定置用途への利用
1 はじめに
2 車載リチウムイオン電池の二次利用に関する取り組み状況
3 車載リチウムイオン電池の定置用蓄電池システムへの利用
4 V2H関連技術の開発動向
5 まとめと今後の展望
第4章 定置型に向けたリチウムイオン電池の方向性
1 はじめに
2 リチウム二次電池の特徴
3 技術的な留意点
3.1 信頼性
3.2 安全性
3.3 電池発熱対策
3.4 使用温度範囲
3.5 高容量
3.6 満充電状態での劣化抑制の課題
4 電池材料および製造について
4.1 正極
4.2 負極
4.2.1 合金系の例
4.3 アルミ箔,銅箔
4.4 セパレータ
4.4.1 耐熱セパレータ
4.5 製造設備
4.6 製造
4.6.1 乾燥,水分管理,コンタミ管理
4.7 長寿命化に重要な,極低露点グローブボックス
4.8 エネルギー貯蔵効率
4.9 定置用LIBに関する火災防止条例抜粋
4.9.1 リチウムイオン蓄電池設備の設置と貯蔵に共通する安全対策
4.9.2 リチウムイオン蓄電池設備の設置に係る安全対策
4.9.3 リチウムイオン電池等の貯蔵に係る安全対策
5 大型電力貯蔵用の例
5.1 SAFT社の定置用蓄電システム
6 リチウムイオン蓄電池導入に補助金
6.1 事業名称
6.2 事業概要
6.3 補助対象者
6.4 補助対象機器
6.5 補助率と補助上限額
6.6 事業期間
6.7 補助金申請の流れ
7 将来展望
第5章 定置型Liイオン蓄電池市場の動向と展望
1 定置用Liイオン蓄電池市場が注目される背景
2 定置用Liイオン蓄電池の市場展望
3 定置用Liイオン蓄電池市場の種類と特徴
3.1 「A ; 既存市場」
3.2 「B;新規市場」
4 定置用市場の変化
4.1 B-1;系統安定化のため発電所/送電網へ設置
4.2 B-2;送電網への投資延期を目的として配電所へ設置
4.3 B-3;非常時バックアップや電気代削減のための住宅・建物など電力需要家へ設置
5 定置用Liイオン蓄電池市場の動向と予測
第6章 大容量Liイオン電池のコスト解析
1 定置型蓄電池のシステムと経済問題
1.1 自然エネルギー蓄電デバイス
1.2 市販の蓄電システムと価格
1.3 定置型蓄電システムの市場価格と市場規模
1.4 小型・移動型における利便性
1.5 大型Liイオン蓄電池の価値
1.6 定置型における新たな価値
1.7 大規模自然エネルギー蓄電の特殊性
1.8 発電と蓄電のコストとその負担
2 セル製造の原材料コスト
2.1 原材料コスト
2.2 正負極材のコスト
2.3 自動車用電池での事例
2.4 原材料のコストダウン
2.5 セルの生産量MWhと正負極材投入量
3 セル製造コスト(設備,労務,用役ほか)
3.1 生産設備と大型,小型の区別
3.2 製造設備の試算
3.3 工場原価への不良率、設備投資額の影響
4 セルの工場原価と販売価格
4.1 原材料コスト
4.2 販売価格と利益率
4.3 別の基礎データによる試算
5 セル,モジュールとユニット
5.1 周辺回路
5.2 系統連系における事例
5.3 周辺システムのコストと効率
6 蓄電システムの運用と蓄電コスト
6.1 蓄電システムの運用とコスト
6.2 充電方法CCとCV
6.3 セル・モジュールの運用とサイクル寿命
6.4 SOC上限カットによるサイクル寿命向上
6.5 蓄電コスト試算(1)
6.6 蓄電コスト試算(2)
6.7 蓄電コスト試算(3)
6.8 蓄電コスト試算(4)
7 まとめ
第7章 Liイオン電池管理システムへ向けた電池劣化診断技術の提案
1 はじめに
2 動機と目的
3 ベンチマーク
3.1 SOHの推定方法
3.1.1 内部抵抗の増加を計測する方法
3.1.2 劣化指標を用いる方法
3.1.3 満充電容量の低下を計測する方法
3.2 SOCの推定方法
3.2.1 電流積算法
3.2.2 電池モデル式
4 アプローチ
4.1 アプローチの特徴
4.2 電池impedanceの周波数特性
4.3 電池の電気的な構造
4.4 Warburg impedanceの物理的意味
4.5 Faraday impedanceの物理的意味
5 結果および結果の検討
5.1 電池管理システム向けの測定方式の提案
5.2 複素演算化による分解能の向上
6 結言
【第2編 Liイオン電池の開発と定置型蓄電システムへの適用】
第1章 電力貯蔵・産業用機器向け高性能大型リチウムイオン二次電池の開発
1 はじめに
2 リチウムイオン二次電池の特長
2.1 リチウムイオン二次電池について
2.2 当社リチウムイオン二次電池の特長
2.2.1 電池材料
2.2.2 電極構造
2.2.3 電池形状と外装
3 リチウムイオン二次電池の仕様と性能
3.1 当社リチウムイオン二次電池の仕様
3.2 当社リチウムイオン二次電池の性能
3.2.1 放電レート特性(25℃)
3.2.2 充電レート特性(25℃)
3.2.3 低温放電レート特性(温度特性)
4 電池の安全性評価試験
5 適用製品例
6 まとめ
第2章 定置用大容量リチウムイオン電池の開発と通信用バックアップシステム
1 はじめに
2 難燃化剤添加による安全性の向上
2.1 難燃化剤添加の効果検証
2.2 200Ah級大形セルにおける安全性評価
3 フロート寿命特性の改善
3.1 部分置換したスピネル系マンガン酸リチウムによる寿命性能の向上
3.2 電解液の最適化による寿命性能の向上
4 システムの開発
4.1 バッテリーマネジメント技術
4.2 バックアップ電源システム
5 まとめ
第3章 ラミネート型定置型リチウムイオン蓄電池の開発
1 はじめに
2 リチウムイオン電池の寿命
3 ラミネート型の信頼性
4 25Ah級大型電池
5 コスト削減
6 おわりに
【第3編 拡がる定置型Liイオン蓄電池システム】
第1章 直流‐交流ハイブリッド定置型蓄電池システム
1 はじめに
2 家庭向け小規模DC-ACハイブリッド電力システムと定置型蓄電池
3 ビルシステム向け中規模DC-ACハイブリッド電力システムと定置型蓄電池
3.1 発電量が不安定な再生可能エネルギーを電源として,地産地消による安定的な運用を行うシステムの完成
3.2 ITを活用した負荷電力の完全制御と見える化技術の確立
3.3 ITを活用した大型蓄電システムの制御・管理システム確立
3.4 ITによる蓄電システム及び移動体エネルギーを融合した新エネルギーシステムの確立
3.5 IT融合による低炭素型社会システムの構築および省エネルギー型社会活動の誘発
4 まとめ
第2章 スマートグリッドと情報システム
1 概要
2 伊藤忠テクノソリューションズ 新エネルギー・インフラ事業部の実績
2.1 PVシミュレーション技術
2.2 風力発電シミュレーション技術
3 スマートグリッドに必要な情報システムのプラットフォーム
4 E-PLSM
4.1 E-PLSM概要
4.2 E-PLSM構成
4.3 データ収集・データベース構造
4.3.1 データ収集方法
4.3.2 データベース構造
5 実証事例
5.1 実証実験における目的
5.2 実証実験全体像
5.3 実証実験での利用画面
6 おわりに
第3章 大規模定置利用リチウムイオン電池の可能性―巨大産業創成に向けて―
1 はじめに――電力システムにおけるエネルギー蓄積の必要性
2 蓄電所の機能と創造される価値
3 蓄電所のデザイン検討
3.1 全自家用車による総走行エネルギー量の見積もり(EV走行時)
4 蓄電所の規模と配置
4.1 配電用変電所近傍に設置する蓄電所用二次電池の規模
4.1.1 昼夜のロードレベリングへの対応(電力量の10%を緩和)
4.1.2 1MW×8時間の緩和
5 リチウムイオン電池の競争力――コスト競争力からの有意性
6 リチウムイオン電池の競争力――エネルギー効率の有意性
7 おわりに
【第4編 Liイオン蓄電池の材料開発:長寿命化の技術】
第1章 定置電源用Liイオン電池の正極材料
1 はじめに
2 定置用大型電池に求められる特性
3 正極材料
3.1 定置型Li-ion電池の正極材料に求められる要件
3.2 Spinel Mn系正極材料
3.2.1 LiMn2O4(Spinel)4.2V級
3.2.2 Li(Ni0.5Mn1.5)O4 (Spinel)5V級
3.3 三成分系正極材料 (Layered)
3.3.1 三成分系正極材料4.2V級
3.3.2 三成分系正極材料4.6V級
3.4 製造プロセスに関して
4 おわりに
第2章 オリビン型正極材料と長寿命化技術
1 はじめに
2 LiFePO4の特徴
3 LiFePO4の長寿命化技術
3.1 サイクル劣化のメカニズム
3.2 表面処理,添加剤による高温溶出防止
3.3 正極材の長寿命化対策
3.3.1 カーボンコート
3.3.2 粒径制御と高結晶性化
3.3.3 鉄系不純物の影響
3.4 その他の長寿命化技術
3.4.1 水分の管理
3.4.2 電圧制御
3.4.3 大気による劣化の防止
4 おわりに
第3章 大型LIB用炭素系負極材料の開発
1 はじめに―昭和電工の炭素・黒鉛系Liイオン二次電池(LIB)関連材料―
2 炭素系LIB負極材料の開発状況
2.1 LIB負極材料の種類と代表特性
2.2 LIB要求項目
2.3 各種炭素系LIB負極材料の特性
3 人造黒鉛負極材のサイクル寿命,保存特性,入出力特性の改善
3.1 人造黒鉛SCMG(R)-ARの特徴
3.2 人造黒鉛SCMG(R)の急速充電性(入力特性)改良
4 VGCF(R)の蓄電両用LIB負極用導電助剤としての添加効果
4.1 VGCF(R)添加によるサイクル寿命の改善
4.2 VGCF(R)添加による出力特性の向上
第4章 定置型蓄電池と電解液
1 はじめに
2 定置型電池の種類と今後の展開
3 電気自動車電池の電力貯蔵装置への再利用
4 リチウムイオン電池用電解液の安定性
5 負極表面処理による電解液の安定性向上
6 正極表面処理による電解液安定性の向上
7 安全性向上のための電解液改良
8 まとめ
第5章 セパレータ
1 はじめに
2 微多孔膜タイプセパレータの基本機能
3 微多孔膜タイプセパレータのフィルム物性
3.1 細孔構造および孔径分布
3.2 厚みおよび透過性(空孔率,孔径,曲路率,Gurley値)
3.3 機械的強度
3.4 シャットダウン特性,メルトインテグリティー特性,メルトダウン温度
3.5 熱収縮率
3.6 その他
4 微多孔膜タイプセパレータの製法
5 当社品“セティーラ”の特徴
5.1 細孔構造および孔径分布
5.2 機械的強度
5.3 シャットダウン特性,メルトインテグリティー特性,メルトダウン温度
6 共押出技術を用いた微多孔膜タイプ多層セパレータ
7 コーティング技術を用いた微多孔膜タイプ多層セパレータ
7.1 コーティング技術
7.2 耐熱ポリマーコーティング
8 おわりに
第6章 バインダー
1 はじめに
2 負極用バインダー
2.1 負極用バインダーの種類と特徴
2.2 スラリー作製上の留意点
2.3 乾燥工程上の留意点
2.4 負極用バインダーの電池性能への影響事例
3 正極用バインダー
3.1 正極用バインダーの種類と特徴
3.2 開発品バインダーの耐酸化性
3.3 正極用水系バインダーの分散性
3.4 水系正極用バインダーを用いた電池性能
4 まとめ
第7章 集電箔および外装材料
1 はじめに
2 大型リチウムイオン電池(セル)の内部構造
2.1 円筒型,平板型と扁平捲
2.2 大電流放電と放熱性
3 集電箔の材料とスペック
3.1 集電箔の選択
4 外装材の構成と加工,組立(封止)
4.1 各種のリチウムイオン電池(セル)の外装材
4.2 ラミネート包材と加工
4.3 金属缶(函)体の外装
5 安全性と放熱設計
5.1 定置用リチウムイオン電池(セル)の安全性
5.2 セルの熱暴走
5.3 法規制と試験方法 -

熱電変換技術の基礎と応用ークリーンなエネルギー社会を目指してー(普及版)
¥2,750
2011年刊「熱電変換技術の基礎と応用」の普及版!新たな発電技術の決定打!工場排熱から太陽熱、バイク・自動車の排気熱など身近な熱が電気に換える
(編纂:日本熱電学会,編集:舟橋良次・木村 薫・黒崎 健・竹内恒博)
<a href="https://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=5428"target=”_blank”>この本の紙版「熱電変換技術の基礎と応用《普及版》クリーンなエネルギー社会を目指して」の販売ページはこちら(別サイトが開きます)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は、2011年当時のものを使用しております。
◆編纂
日本熱電学会
◆編集委員長
舟橋良次 産業技術総合研究所
◆編集委員(五十音順)
木村 薫 東京大学
黒崎 健 大阪大学
竹内恒博 名古屋大学
◆執筆者
舟橋良次 産業技術総合研究所
梶川武信 梶川TK事務所
寺崎一郎 名古屋大学
内田健一 東北大学
齊藤英治 東北大学
田中耕太郎 芝浦工業大学
小椎八重航 理化学研究所
竹内恒博 名古屋大学
宮崎 譲 東北大学
三上祐史 産業技術総合研究所
牟田浩明 大阪大学
黒崎 健 大阪大学
山中伸介 大阪大学
高畠敏郎 広島大学
森 孝雄 物質・材料研究機構
黒木和彦 電気通信大学
吉田 隆 名古屋大学
河本邦仁 名古屋大学
池田輝之 科学技術振興機構
小菅厚子 大阪府立大学
岡本範彦 京都大学
乾 晴行 京都大学
高際良樹 東京大学
木村 薫 東京大学
中村孝則 (株)村田製作所
宮崎康次 九州工業大学
尾崎公洋 産業技術総合研究所
高木健太 産業技術総合研究所
菅野 勉 パナソニック(株)
小林 航 筑波大学
武田雅敏 長岡技術科学大学
新藤尊彦 (株)東芝
佐々木恵一 (株)東芝
大石高志 (株)東芝
高田裕実 (株)東芝
増井 芽 (株)アクトリー
堀田善治 東京工業大学
藤田和博 (株)TESニューエナジー
松岡保静 (株)NTTドコモ
内山直樹 (株)アツミテック
西野洋一 名古屋工業大学
北城 栄 NECエンジニアリング(株)
下山淳一 東京大学
-------------------------------------------------------------------------
<<目次>>
はじめに
第1章 熱電変換の現在・過去・未来
1 熱電変換技術における発展の波
2 熱電材料の革新と未来
3 熱電変換のビジョンとシステム展開の可能性
4 むすび
第2章 熱電変換の基礎科学
1 熱電変換現象
1.1 熱電効果
1.2 性能指数
1.3 物質開発の時代へ
1.4 半導体物理を超えて
1.5 おわりに
2 スピンゼーベック効果と絶縁体を用いた熱電発電
2.1 はじめに
2.2 絶縁体ベース熱電変換素子の試料構造と熱起電力生成メカニズム
2.3 絶縁体におけるスピンゼーベック効果の観測
2.3.1 単結晶Y3Fe5O12/Pt複合構造における縦型スピンゼーベック効果
2.3.2 単結晶LaY3Fe5O12/Pt複合構造における横型スピンゼーベック効果
2.3.3 焼結体絶縁体磁石を用いた熱電変換
2.4 まとめと今後の展望
3 アルカリ金属熱電変換の基礎
3.1 作動原理と実際の形状
3.2 発電特性とAMTECの特徴
3.3 最近の性能向上に関する研究
3.3.1 小型細管構造による電極面積増加の方法
3.3.2 電極微細構造によるカソード側電極の改良
3.3.3 作動流体をNa以外とする方法
3.4 応用技術
4 電子構造からみた熱電材料:クーロン相互作用の役割
4.1 はじめに
4.2 熱電効果の熱力学
4.3 クーロン相互作用と電流のエントロピー
4.4 新しい熱電材料の探索にむけて
5 フォノン分散の特徴から理解される格子熱伝導度低減機構
5.1 はじめに
5.2 格子熱伝導度の温度依存性
5.3 格子熱伝導度を低減させる指針
5.4 実験による指針の確認
5.5 シミュレーションによる指針の確認
5.6 おわりに
第3章 材料
1 シリサイド
1.1 はじめに
1.2 HMSの化学組成と結晶構造
1.3 HMSの電子構造
1.4 14電子則
1.5 HMSの熱電特性
1.6 おわりに―実用化に向けて―
2 ホイスラー合金
2.1 はじめに
2.2 ホイスラー型Fe2VAl合金
2.3 熱電応用に向けた材料開発
2.4 まとめ
3 ハーフホイスラー合金
3.1 はじめに
3.2 試料合成
3.3 電気的特性
3.4 熱・機械的特性
3.5 性能指数・まとめ
4 クラスレート化合物
4.1 金属間クラスレートの結晶構造
4.2 ラットリングによる格子熱伝導率の抑制
4.3 Ba8Ga16Ge30とBa8Ga16Sn30の電荷キャリア制御
4.4 Ba8Ga16Sn30と置換系の中温領域での優れた熱電変換性能
4.5 まとめ
5 ホウ素系高温熱電変換材料
5.1 はじめに
5.2 ホウ素系化合物についての導入
5.3 多ホウ化物における低熱伝導率の起源について
5.4 古典的なホウ素系化合物における熱電的性質
5.4.1 ボロンカーバイド(いわゆる"B4C")
5.4.2 ベータボロン(β-B)
5.4.3 ヘキサボライド
5.4.4 RB66
5.5 新規なホウ素系化合物
5.5.1 希土類ホウ炭化物RB17CN、RB22C2N、RB28.5C4
5.5.2 希土類ホウケイ化物RB44Si2
5.6 展望
6 熱電酸化物の物性と電子構造
6.1 はじめに
6.2 コバルト酸化物および関連するp型物質
6.3 n型熱電酸化物
6.4 おわりに
7 ナノ薄膜構造熱電変換材料
8 3D超格子SrTiO3バルク材料
8.1 SrTiO3(STOと略称)のナノ構造化
8.2 STO超格子による巨大熱起電力発生
8.3 ナノ粒子化による熱伝導率の低減
8.4 3D超格子STOセラミックス
9 PbTe基ナノコンポジット材料
9.1 はじめに
9.2 バルクナノコンポジット材料の誕生
9.3 ナノ構造制御
9.3.1 LAST 系
9.3.2 ナノ構造の制御のために
9.4 おわりに
10 酸化物系自然ナノ構造熱電材料
10.1 はじめに
10.2 ナノチェッカーボード構造酸化物
10.3 ナノ相分離酸化物とマイクロ複合酸化物
10.4 試料の同定と分析
10.5 試料の熱伝導率
10.6 おわりに
11 PBET界面制御による熱電材料の高性能化
11.1 はじめに
11.2 チムニーラダー構造
11.3 Mn置換したRu基シリサイドの組織と界面構造
11.4 PBET的特性を示す異相界面の密度と熱電特性
12 13族―遷移金属の擬ギャップ・狭ギャップ系材料
12.1 はじめに
12.2 高い熱電特性を得るための材料探索指針
12.2.1 電子構造と結合性
12.2.2 結晶構造と結合性
12.3 擬ギャップ系材料
12.3.1 材料設計指針
12.3.2 アルミ系正0面体準結晶の熱電特性
12.4 狭ギャップ系材料
13 構造空孔分布制御による熱電材料の高性能化
13.1 はじめに
13.2 Ga2Se3における構造空孔の分布状態と熱伝導率の関係
13.3 Cu-Ga-Te三元系化合物の熱電特性
13.4 まとめと結論
第4章 モジュール・デバイス
1 ビア充填型モジュールの開発
1.1 はじめに
1.2 ビア充填型モジュールの特徴
1.3 ビア充填型モジュールの作製
1.3.1 熱電材料
1.3.2 モジュールの作製プロセス
1.4 ビア充填型モジュールの発電特性
1.4.1 モジュールの発電特性の予測
1.4.2 モジュールの外観と発電特性
1.4.3 ビア型モジュールのバリエーション
1.5 おわりに
2 広い温度域で使用可能なカスケードモジュール
2.1 エネルギー,環境問題
2.2 熱電発電材料
2.3 酸化物熱電モジュール
2.4 カスケード熱電モジュール
2.5 実証試験
2.6 高効率化へ
2.7 まとめ
3 熱電マイクロジェネレーター
3.1 はじめに
3.2 熱電マイクロジェネレーターの作製プロセス
3.3 低コスト作製プロセス
3.4 ナノ構造薄膜を利用したマイクロジェネレーター
3.5 まとめ
4 微粒子を用いた小型発電モジュール
4.1 はじめに
4.2 微小球状粒子の接合
4.3 Fe2VAl系合金への適用
4.4 まとめ
5 非対角熱電効果を用いた熱電トランスデューサ
5.1 はじめに
5.2 非対角熱電効果
5.3 傾斜積層体における非対角熱電効果
5.4 層状酸化物CaxCoO2傾斜エピタキシャル薄膜における非対角熱電効果
5.5 まとめと将来展望
6 熱ダイオード
6.1 熱ダイオードとは
6.2 熱ダイオードの原理
6.3 これからの熱ダイオード
6.4 おわりに
7 フレキシブル熱電変換素子
7.1 はじめに
7.2 薄膜を利用した熱電変換素子
7.3 フレキシブル熱電変換素子
7.3.1 基本構造
7.3.2 シミュレーションによる特性予測
7.3.3 素子の試作と発電特性
7.4 おわりに
第5章 システム
1 未利用の排熱を有効に使う熱電発電システム
1.1 まえがき
1.2 熱電発電システムの基本構成と設計フローの概略
1.3 熱電発電システムの発電部の基本構成と熱電変換モジュール
1.4 熱電発電システムの特徴と変換効率
1.5 熱電発電システムの適用例
1.6 熱電発電システムの長期信頼性
1.7 あとがき
2 産業廃棄物焼却炉における熱電発電実証
2.1 はじめに
2.2 産業廃棄物焼却施設における発電の課題と熱電発電の位置付け
2.2.1 温水を利用した発電技術
2.2.2 温風を利用した発電技術
2.2.3 蒸気を利用した発電技術
2.2.4 その他の熱媒体を利用した発電技術
2.2.5 直接排ガスを利用した発電技術
2.3 産業廃棄物焼却炉における熱電発電を妨げる要因
3 太陽熱利用熱電発電システム
3.1 はじめに
3.2 熱電モジュールによる太陽エネルギーの直接熱電変換
3.3 熱電モジュールの太陽熱活用海水淡水化プロセスへの適用
3.4 おわりに
4 排熱利用の熱供給システム
4.1 はじめに
4.2 カスケードユニット
4.3 ACPユニットの評価
4.4 CPユニットの評価
4.5 発電鍋
4.6 まとめ
5 熱電供給型太陽エネルギー利用システム
5.1 はじめに
5.2 太陽光の集光技術
5.3 熱電供給型太陽光発電システム
5.3.1 太陽電池の特徴
5.3.2 発電モジュールの構造
5.3.3 水循環システム
5.3.4 サンプルモジュール
5.4 原理検証
5.4.1 モジュールの発電電力
5.4.2 内部温水の温度上昇
5.5 考察
5.6 あとがき
6 バイク・自動車への熱電発電の応用
6.1 はじめに
6.2 ホイスラー型Fe2VAl合金のバイク・自動車への応用に向けた研究開発
6.2.2 ホイスラー型Fe2VAl合金
6.2.3 Fe2VAl熱電モジュールの開発
6.3 バイク・自動車における熱電発電の現状と将来
6.3.1 バイク・自動車における廃熱
6.3.2 Fe2VAl熱電モジュールの実車搭載による発電試験
6.3.3 バイク・自動車への熱電発電の応用に向けて
7 電子システムの冷却技術と熱電冷却の応用
7.1 まえがき
7.2 冷却技術の動向
7.3 冷却技術の種類
7.3.1 冷却技術の分類
7.3.2 空冷
7.3.3 液冷
7.3.4 相変化冷却
7.3.5 冷凍冷却
7.3.6 熱電冷却
7.4 熱電デバイスの冷却への応用
7.4.1 ペルチェ素子冷却の概要
7.4.2 ペルチェ素子の特性
7.4.3 光通信用レーザダイオード冷却への応用
7.4.4 ペルチェ素子冷却の今後の展望
7.5 あとがき
8 超伝導技術と熱電変換技術
8.1 超伝導物質
8.2 超伝導機器の冷却方法
8.3 超伝導応用への熱電材料導入の可能性と期待
8.4 まとめ
第6章 熱電変換技術によるクリーンエネルギー社会へのインパクト
―熱電ロードマップ―
1 「太陽エネルギー社会」の実現に向けて
2 熱電ロードマップ
2.1 熱電科学基礎研究
2.2 材料開発
2.3 デバイス・モジュール(熱電発電)
-

高分子の架橋と分解III(普及版)
¥2,915
2012年刊「高分子の架橋と分解III」の普及版!高分子の架橋と分解について基礎および最新動向をまとめた1冊!架橋と分解の理論および反応例だけでなく架橋分子の架橋構造解析を紹介!
(監修:角岡正弘・白井正充)
<a href="https://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=5467"target=”_blank”>この本の紙版「高分子の架橋と分解III《普及版》」の販売ページはこちら(別サイトが開きます)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は、2012年当時のものを使用しております。
角岡正弘 大阪府立大学名誉教授
白井正充 大阪府立大学
中山雍晴 元 関西ペイント(株)
三好理子 (株)東レリサーチセンター
阿久津幹夫 前 カシュー(株)
村山智 日本ポリウレタン工業(株)
村田保幸 三菱化学(株)
高田泰廣 DIC(株)
瀬川正志 サンビック(株)
岩崎和男 岩崎技術士事務所
小山靖人 東京工業大学
高田十志和 東京工業大学
クリスティアン・ルスリム アドバンスト・ソフトマテリアルズ(株)
田畑智 アドバンスト・ソフトマテリアルズ(株)
西田治男 九州工業大学
橋本保 福井大学
増谷一成 京都工芸繊維大学
木村良晴 京都工芸繊維大学
宇山浩 大阪大学
薮内尚哉 日本ビー・ケミカル(株)
大塚英幸 九州大学
吉江尚子 東京大学
松川公洋 (地独)大阪市立工業研究所
大山俊幸 横浜国立大学
戸塚智貴 和光純薬工業(株)
佐々木健夫 東京理科大学
松本章一 大阪市立大学
佐藤絵理子 大阪市立大学
岡崎栄一 東亞合成(株)
桐野学 (株)スリーボンド
冨田育義 東京工業大学
中川佳樹 (株)カネカ
三宅弘人 (株)ダイセル
湯川隆生 (株)ダイセル
-------------------------------------------------------------------------
<<目次>>
第1章 高分子の架橋と分解
1 高分子の架橋と分解を取り巻く状況
1.1 はじめに
1.2 架橋と分解の基礎概念
1.2.1 架橋の概念
1.2.2 分解の概念
1.2.3 架橋構造の解析
1.3 架橋と分解の活用
1.3.1 架橋を活用する高分子機能材料
1.3.2 分解を活用する高分子機能材料
1.3.3 架橋と分解を併用する高分子機能材料
1.4 おわりに
2 架橋高分子の基礎―架橋剤の種類,反応および応用例
2.1 ハードな架橋
2.1.1 酸化重合による架橋
2.1.2 炭素-炭素2重結合の重合による架橋
2.1.3 アミノ樹脂による架橋
2.1.4 イソシアネート基による架橋
2.1.5 ブロックイソシアネートによる架橋
2.1.6 エポキシ基による架橋
2.1.7 シラノール基による架橋
2.1.8 ヒドラジドによる架橋
2.1.9 カルボジイミドによる架橋
2.1.10 その他の架橋
2.2 ソフトな架橋
2.2.1 必要に応じて逆反応する架橋
2.2.2 結合と解離を繰り返す架橋
2.2.3 固定されない架橋
第2章 高分子の架橋と分析・評価
1 固体NMR による架橋高分子の構造・劣化評価―LED 封止樹脂,シリコーン樹脂を中心に
1.1 はじめに
1.2 エポキシ系LED封止樹脂の構造解析
1.3 シリコーン系封止樹脂の構造解析
1.4 熱劣化による架橋シリコーンゴムの化学構造変化
1.5 おわりに
2 超微小硬度計を使ったUV硬化型ハードコート材の開発方法
2.1 はじめに
2.2 高い耐擦傷と耐熱性を兼ね備える必要性の背景
2.3 予備試験,開発方法のコンセプトと材料探査
2.3.1 UV照射時の素材表面の温度の測定
2.3.2 様々な硬度計の調査と開発方法のコンセプト
2.3.3 上記コンセプトに基づく超微小硬度試験機による材料の探査
2.4 探査された材料の試験結果
2.5 まとめ
第3章 架橋型ポリマーの特徴と活用法
1 ポリウレタンの高次構造による物性制御
1.1 ポリウレタンの架橋構造
1.2 ポリウレタンの一次構造
1.3 一次構造,高次構造,物性の関係
1.4 まとめ
2 エポキシ樹脂の合成・樹脂設計と活用法
2.1 エポキシ樹脂の概要と特徴
2.1.1 エポキシ樹脂の一般的特性
2.1.2 エポキシ樹脂の種類と分類
2.2 エポキシ樹脂の合成
2.2.1 グリシジル化(一段法)
2.2.2 二段法
2.2.3 その他のエポキシ化方法
2.2.4 エポキシ樹脂の変性
2.2.5 その他のプロセス
2.3 エポキシ樹脂の構造と物性
2.4 エポキシ樹脂の活用法
2.4.1 エポキシ樹脂の選択
2.4.2 硬化剤の選択
2.4.3 その他の添加剤
2.5 まとめ
3 高耐候性UV硬化型樹脂の設計とその用途展開
3.1 はじめに
3.2 UV硬化型無機-有機ハイブリッド樹脂の設計
3.2.1 樹脂合成方法
3.2.2 塗料設計
3.2.3 硬化塗膜サンプルの作製方法
3.2.4 硬化塗膜の一般物性
3.3 硬化塗膜の耐候性評価
3.3.1 促進耐候試験結果
3.3.2 屋外曝露試験結果
3.3.3 耐候性発現のメカニズム
3.4 プラスチック保護コートとしての用途展開
3.4.1 太陽電池用フロントシート
3.4.2 高耐候ハードコートフィルム
3.4.3 ナノインプリント反射防止フィルム
3.5 おわりに
4 太陽電池用封止剤EVAの開発・高性能化
4.1 太陽電池モジュールの構造
4.2 EVA樹脂に関して
4.2.1 EVA樹脂の生産量
4.2.2 EVA樹脂の分類
4.3 結晶系シリコンセルの封止向けEVA封止材について
4.3.1 EVA封止材の組成と架橋・接着の原理
4.3.2 結晶系シリコン太陽電池モジュールの製造方法
4.3.3 太陽電池用ラミネーターの条件設定に関して
4.4 EVA封止材の耐久性に関して
4.5 まとめ
5 架橋を伴う発泡成形
5.1 はじめに
5.2 発泡成形における架橋の意義
5.2.1 架橋の目的(狙い)
5.2.2 発泡成形法の分類
5.2.3 発泡成形における架橋方法の分類
5.3 重合反応架橋法の応用例
5.3.1 重合反応架橋法による架橋反応
5.3.2 化学量論の概念(考え方)
5.3.3 ポリウレタンフォームの場合の架橋反応
5.3.4 フェノールフォームの場合の架橋反応
5.3.5 重合反応架橋法の発泡体の製造工程
5.3.6 重合反応架橋法の発泡体の性質及び用途例
5.4 化学架橋法の応用例
5.4.1 化学架橋法による架橋反応
5.4.2 化学架橋法による架橋発泡体の製造工程
5.4.3 化学架橋法による架橋の発泡体の性質および用途例
5.5 電子線架橋法の応用例
5.5.1 電子線架橋法による架橋反応
5.5.2 電子線架橋法による架橋発泡体の製造工程
5.5.3 電子線架橋法による架橋発泡体の性質および用途例
5.6 その他の発泡成形法
5.6.1 無架橋法によるポリオレフィン系フォーム
5.6.2 固相発泡成形法によるフォーム
5.7 おわりに
第4章 新しい架橋反応とその応用
1 ニトリルオキシドを用いる高効率架橋
1.1 はじめに
1.2 ニトリルオキシドの化学
1.3 単官能性安定ニトリルオキシドを用いた高分子の修飾反応
1.4 2官能性安定ニトリルオキシドの合成と架橋反応
1.5 無溶媒条件下での架橋反応
1.6 アンビデント反応剤を用いる架橋
1.7 おわりに
2 可動な架橋点を持つポリロタキサンの塗料への応用
2.1 はじめに
2.2 PRの合成と分子設計
2.2.1 量産に適した合成
2.2.2 PRの分子設計
2.3 SRMとその物性
2.3.1 スライドリングゲル(SRG)
2.3.2 SRMエラストマー
2.3.3 SRMの用途
2.4 SRMの塗料への応用
2.4.1 塗料用材料検討に関する構造最適化
2.4.2 SRMクリア塗膜の特徴
2.5 おわりに
第5章 ポリマーのリサイクル技術
1 リサイクルを意図したポリマーの開発
1.1 はじめに
1.2 リサイクルを可能とする要因―ヘテロ原子を主鎖に有するポリマーを中心にして
1.2.1 熱力学的要因
1.2.2 構造的要因
1.3 分解制御可能な結合の導入によるリサイクル性ポリマーの合成
1.3.1 ポリオレフィン類似リサイクル性ポリマーの合成
1.3.2 各種制御可能な化学結合を持った新規リサイクル性ポリマーの合成
1.4 バイオマス由来ポリマーのリサイクル性制御
1.4.1 ポリ乳酸の物性および解重合性の制御
1.4.2 ポリ-3-ヒドロキシ酪酸からの選択的ビニルモノマー変換と酵素法による再重合
1.5 ポリマーアロイからの選択的リサイクル分離
1.6 おわりに
2 ケミカルリサイクル用ポリマーとしてのアセタール結合を導入したポリウレタン材料とエポキシ樹脂
2.1 はじめに
2.2 アセタール結合を有するポリウレタン材料
2.3 アセタール結合を有するエポキシ樹脂
2.4 おわりに
第6章 植物由来材料の利用
1 バイオベースポリマーの分子・材料設計
1.1 はじめに
1.2 バイオベースポリマー
1.3 新しいバイオベースポリマー
1.4 機能性バイオベースポリマーの開発
1.5 バイオリファイナリー
1.6 生分解性とバイオマス度
1.7 ポリ乳酸
1.8 ステレオコンプレックス型ポリ乳酸
1.9 おわりに
2 植物由来高性能バイオベースポリマー材料の開発
2.1 はじめに
2.2 柔軟性に優れた油脂架橋ポリマー
2.3 油脂架橋ポリマー/バイオファイバー複合材料
2.4 酸無水物を硬化剤に用いる油脂架橋ポリマー
2.5 エポキシ化油脂を用いる屋根用塗料の実用化
2.6 おわりに
3 星型ポリ乳酸ポリオールの2液硬化型およびUV硬化型塗料への応用
3.1 はじめに
3.2 実験
3.2.1 星型PLAポリオールの合成
3.2.2 多官能星型PLAオリゴマーの合成
3.2.3 塗膜作製方法
3.2.4 塗膜評価方法
3.3 結果と考察
3.4 まとめ
第7章 可逆的な架橋・分解可能なポリマー
1 ラジカルプロセスに基づく架橋高分子の合成と反応
1.1 はじめに
1.2 熱刺激を利用するラジカルプロセスに基づく架橋高分子の合成と反応
1.3 光刺激を利用するラジカルプロセスに基づく架橋高分子の合成と反応
1.4 おわりに
2 動的架橋を利用したネットワークポリマーの機能化―硬軟物性変換性と修復性
2.1 はじめに
2.2 動的結合を有する結晶性ネットワークポリマーの硬軟物性変換
2.2.1 架橋反応と結晶化の動的過程がネットワークポリマーの構造と物性に与える影響
2.2.2 プレポリマー分子量が硬軟物性変換に与える影響
2.2.3 架橋と結晶化制御による更なる機械特性チューニング
2.3 動的結合を有するネットワークポリマーの修復性
2.3.1 柔軟な非晶性ネットワークポリマーの修復性
2.3.2 結晶性と修復性
2.3.3 修復性DAポリマーの耐熱性の改善
2.4 おわりに
第8章 ポリマーの分解を活用する機能性材料
1 光分解性ポリシランブロック共重合体を用いたハイブリッド材料の開発
1.1 はじめに
1.2 ポリシランブロック共重合体の合成
1.3 ポリシラン-シリカハイブリッド薄膜の作製
1.4 ポリシラン-シリカハイブリッドの屈折率変調薄膜
1.5 ポリシラン-シリカハイブリッド薄膜の光誘起異方性
1.6 ポリシラン-ジルコニアハイブリッドのサーモクロミズム抑制と熱光学特性
1.7 ポリシラン共重合体の化学吸着と金ナノ粒子の作製
1.8 おわりに
2 高分子の分解・反応を利用した微細パターン形成法―反応現像画像形成
2.1 はじめに
2.2 ポジ型反応現像画像形成
2.2.1 アミン含有現像液を用いたパターン形成
2.2.2 アルカリ水溶液現像によるパターン形成
2.3 ネガ型反応現像画像形成
2.3.1 OH-を求核剤として用いた感光性ポリイミド
2.3.2 アルカリ水溶液現像によるパターン形成
2.4 おわりに
3 高分子アゾ重合開始剤を用いたブロックポリマーへの応用
3.1 はじめに
3.2 高分子アゾ開始剤の原理
3.3 高分子アゾ開始剤の合成
3.4 高分子アゾ開始剤を用いたブロック共重合体の特性
3.4.1 ブロック共重合体の合成
3.4.2 ブロック共重合体の特性
3.5 おわりに
4 光塩基発生剤を利用した光解重合性ポリオレフィンスルホン
4.1 はじめに
4.2 光塩基発生剤を組み込んだポリオレフィンスルホンの光解重合
4.3 塩基増殖反応を利用した高感度化
4.4 塩基遊離型の光塩基発生剤を用いた場合
4.5 露光部が揮発する高分子
4.6 光照射で剥離する接着剤への応用
4.7 おわりに
5 アクリル系ブロックポリマーを用いる易解体性接着材料の開発
5.1 はじめに
5.2 ポリアクリル酸t-ブチルの側鎖反応挙動
5.3 ポリアクリル酸ブロック共重合体の接着特性
5.4 二重刺激応答性のポリアクリル酸エステル粘着剤の設計
5.5 高性能二重刺激応答型易解体性粘着材料の設計
第9章 UV硬化と微細加工
1 UV硬化における話題と課題
1.1 はじめに
1.2 UV-LEDの現状と課題
1.3 UV-LED用開始剤の開発―UVラジカル開始剤およびUVカチオン開始剤用増感剤
1.4 酸素の硬化阻害と汚れにくい表面加工技術
1.5 ハイパーブランチオリゴマーおよび分解性モノマーを利用する硬化収縮抑制対策
1.6 高耐侯性UV硬化型塗料―無機・有機ハイブリッドの利用
1.7 高分子量光開始剤―食品包装材用インクの開始剤
1.8 実用化が期待される光塩基発生剤
1.9 おわりに
2 マレイミドアクリレートを利用したUV硬化材料
2.1 はじめに
2.2 マレイミド化合物の光化学
2.2.1 マレイミドとビニルエーテルの交互共重合
2.2.2 マレイミドとアクリル系モノマー・オリゴマーの混合系の反応
2.2.3 マレイミド単独の反応
2.2.4 マレイミド環の置換基による反応性の差異
2.3 マレイミドアクリレートの特性
2.3.1 ラマン分光法を利用したマレイミド基の反応性解析
2.3.2 コーティング剤への応用
2.4 マレイミドアクリレートポリマーの特性
3 アミンイミドを基本骨格とした熱,光塩基発生剤の開発と架橋剤としての利用
3.1 はじめに
3.2 アミンイミドの合成
3.2.1 熱活性を向上させたアミンイミドの合成
3.2.2 光活性を向上させたアミンイミドの合成
3.2.3 BFIの芳香環パラ位への置換基の導入と熱,光活性
3.3 BFIの光ラジカル開始剤としての特性
3.4 BFIを架橋剤として利用した接着剤の開発
3.4.1 エポキシ樹脂の単独硬化システム
3.4.2 エポキシ樹脂とポリチオールからなる硬化システム
3.4.3 エポキシ樹脂とアクリレート樹脂からなる光-熱デュアル硬化システム
3.5 おわりに
4 UV硬化型テレケリックポリアクリレート
4.1 はじめに
4.2 テレケリックポリアクリレートの概略
4.3 テレケリックポリアクリレートの合成
4.4 テレケリックポリアクリレートのUV硬化
4.5 UV硬化型テレケリックポリアクリレートの特徴
4.6 おわりに
5 UVインプリント材料の開発
5.1 はじめに
5.2 UVインプリントについて
5.3 UV硬化性樹脂の特徴
5.3.1 ラジカル硬化系
5.3.2 イオン硬化系
5.4 UV硬化樹脂のインプリントへの適用性
5.4.1 インプリント用途への取り組み
5.4.2 インプリント用UV硬化性樹脂
5.5 おわりに
6 リワーク型アクリル系モノマーの開発とUVインプリント材料への応用
6.1 はじめに
6.2 リワーク型多官能アクリル系モノマーの分子設計
6.3 UV硬化と分解・可溶化
6.4 UVインプリント材料への応用
6.5 おわりに -

微生物を活用した新世代の有用物質生産技術(普及版)
¥2,970
2012年刊「微生物を活用した新世代の有用物質生産技術」の普及版!日本が誇る新発想の微生物・酵素による物質生産の基盤技術を集結!医薬品,食品,化粧品,環境・エネルギー,各産業分野における代表的な応用技術を紹介!
(監修:穴澤秀治)
<a href="https://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=5658"target=”_blank”>この本の紙版「微生物を活用した新世代の有用物質生産技術《普及版》」の販売ページはこちら(別サイトが開きます)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は、2012年当時のものを使用しております。
穴澤秀治 (一財)バイオインダストリー協会
尾崎克也 花王(株)
東田英毅 旭硝子(株)
熊谷博道 旭硝子(株)
板谷光泰 慶應義塾大学
原島 俊 大阪大学
Yeon-HeeKim Dong-Eui大学
西沢正文 慶應義塾大学
池田治生 北里大学
小山泰二 (公財)野田産業科学研究所
森浩 禎 奈良先端科学技術大学院大学
竹内力矢 奈良先端科学技術大学院大学
町田雅之 産業技術総合研究所
竹川 薫 九州大学
松沢智彦 九州大学
池田正人 信州大学
八十原良彦 (株)カネカ
松山彰収 (株)ダイセル
福西広晃 日本電気(株)
島田次郎 日本大学
関口順一 信州大学
眞鍋憲二 花王(株)
児玉武子 花王(株)
田中瑞己 東北大学
五味勝也 東北大学
秦洋 二 月桂冠(株)
安枝 寿 味の素(株)
手塚武揚 東京大学
大西康夫 東京大学
木野邦器 早稲田大学
小川 順 京都大学
櫻谷英治 京都大学
岸野重信 京都大学
安藤晃規 京都大学
清水 昌 京都学園大学
黒岩 崇 東京都市大学
伊澤直樹 (株)ヤクルト本社
的場康幸 広島大学
杉山政則 広島大学
乾 将行 (公財)地球環境産業技術研究機構
湯川英明 (公財)地球環境産業技術研究機構
若山 樹 国際石油開発帝石(株)
中島田豊 広島大学
西尾尚道 広島大学
-------------------------------------------------------------------------
<<目次>>
【第I編 基盤技術】
第1章 ミニマムゲノムファクトリー
1 大腸菌
1.1 なぜ大腸菌か
1.2 削除すべき遺伝子の選択
1.4 ゲノム削減株の造成
1.5 ゲノム削減株の評価
1.6 今後の展開
2 枯草菌
2.1 はじめに
2.2 産業用酵素と枯草菌による酵素分泌生産
2.3 枯草菌ゲノムの効率的欠失技術
2.4 枯草菌遺伝子の機能解析と大規模欠失の構築
2.5 ゲノム縮小株MGB874株の機能評価・解析
2.6 ゲノム縮小株の改良による次世代宿主の創製
3 分裂酵母
3.1 はじめに
3.2 分裂酵母
3.3 分裂酵母ミニマムゲノムファクトリー
3.4 まとめ
第2章 大規模ゲノム改変技術
1 長鎖のDNA設計と微生物宿主での合成生物学
1.1 微生物による有用物質の生産
1.2 多数の遺伝子の一括操作の必要性
1.3 遺伝子集積の実情
1.4 長鎖DNA分子の脆弱性
1.5 枯草菌の能力:その1(OGAB法)
1.6 枯草菌の能力:その2(ドミノ法)
1.7 OGAB法の課題
1.8 ドミノ法の課題
1.9 集積遺伝子設計での塩基配列GC含量と繰り返し配列
1.10 合成コスト
1.11 迅速化と長期保存の課題
1.12 まとめ
2 出芽酵母におけるゲノムの大規模改変技術の開発と応用
2.1 はじめに
2.2 ゲノムのワードプロセッシングのための基盤技術の開発
2.3 染色体分断技術(PCR-mediated Chromosome Splitting Technology:PCS)の開発
2.4 オーバーラップPCR法による染色体分断法の高効率化
2.5 染色体分断技術の応用
2.5.1 ワンステップ染色体任意領域削除技術(PCR-mediated Chromosome Deletion Technology:PCD)
2.5.2 ゲノムの再編成技術(Genome Reorganization Technology:GReO)
2.6 おわりに
3 放線菌のゲノムデザイン
3.1 はじめに
3.2 物質生産菌としての「放線菌」
3.3 放線菌ゲノム
3.4 物質生産のためのStreptomycesゲノムの改変
3.5 ゲノムデザイン宿主における物質生産
3.6 おわりに
第3章 オミクス情報の活用とライブラリーの創成
1 麹菌のゲノム情報の菌株育種への展開
1.1 はじめに
1.2 麹菌の比較ゲノム
1.3 転写因子の機能解析と育種への応用
1.4 麹菌のミニマムゲノムを目指して
1.5 おわりに
2 大腸菌網羅的変異株ライブラリーの創成と活用
2.1 はじめに
2.2 大腸菌とは
2.3 網羅研究の重要性
2.4 リソース構築
2.5 リソースの質の管理
2.6 リソースの活用
2.7 リソース利用における注意点
2.8 設計可能な育種に向けて
2.9 おわりに
3 オミックス情報の統合的解析と活用
3.1 オミックス解析の技術的背景
3.2 比較ゲノム解析による遺伝子機能の推定
3.3 トランスクリプトーム情報の統合
3.4 オミックス情報の統合解析と産業利用
3.5 おわりに
4 オミックス情報を用いた分裂酵母の改変
4.1 はじめに
4.2 DNAマイクロアレイを用いた分裂酵母のトランスクリプトーム解析
4.3 分裂酵母のアルコールデヒドロゲナーゼ(ADH)遺伝子adh1破壊株のトランスクリプトーム解析
4.4 異種タンパク質生産に依存して発現が変動する分裂酵母遺伝子の解析
4.5 熱ショックに応答する分裂酵母遺伝子の検索
4.6 マイクロアレイを用いた分裂酵母凝集素遺伝子の同定と物質生産への応用
5 ゲノム情報のコリネ菌育種への展開
5.1 はじめに
5.2 最少の有効変異のみからなる菌株の育種技術「ゲノム育種」
5.2.1 狙いと方法論
5.2.2 リジン生産菌のゲノム育種
5.2.3 アルギニン生産菌のゲノム育種
5.3 異種細菌のin silico代謝マップをモデルにして代謝経路を再設計する育種
5.3.1 背景
5.3.2 in silico代謝マップに着眼した育種の構想
5.3.3 S. mutans型レドックス代謝系をもつコリネ菌の育種
5.4 おわりに
第4章 生産向上のための新技術の展開
1 複合酵素系を活用した精密有機合成
1.1 はじめに
1.2 立体反転反応による光学活性アルコール類の合成プロセス
1.2.1 キラルアルコール化合物の立体反転反応の実際
1.2.2 NADPH依存性グルコース脱水素酵素
1.2.3 立体反転反応による(R)-3-クロロ-1,2-プロパンジオールの合成
1.2.4 立体反転反応による(S)-3-クロロ-1,2-プロパンジオールの合成プロセス
1.3 アミノ基転移酵素を利用した光学活性アミン類の合成プロセス
1.3.1 新規トランスアミナーゼの探索
1.3.2 還元酵素系利用によるトランスアミナーゼ反応の改善
1.4 おわりに
2 有機溶媒耐性菌の利用
2.1 はじめに
2.2 非水系反応場における微生物の機能解析と評価
2.3 非水系反応場で細胞構造を維持できる微生物のスクリーニング
2.4 DC2201と大腸菌の有機溶媒耐性の比較
2.5 DC2201の遺伝子発現システムの構築
2.6 DC2201を用いた(R)-マンデル酸(RMA)生産
2.7 DC2201を用いた(S)-4-クロロ-3-ヒドロキシアセト酪酸エチル(ECHB)生産
2.8 おわりに
3 高精度な酵素反応シミュレーション:シトクロムP450の事例
3.1 はじめに
3.2 P450Vdh(Vitamin D3 Hydroxylase)の概要
3.3 MDシミュレーションによる構造揺らぎ解析(T70R変異)
3.4 SMDシミュレーションによる基質の取込・放出経路の解析(T70R変異)
3.5 自由エネルギー計算による副反応抑制機構の解析(I88VとL171V変異)
3.5.1 反応活性の変化の厳密計算
3.5.2 変異のホットスポット予測
3.6 密度汎関数法による水酸化反応機構の解析
3.7 今後の展望
4 細胞表層工学を用いた分泌タンパク生産性の向上
4.1 溶菌抑制技術
4.1.1 溶菌酵素阻害因子IseAによる溶菌抑制
4.1.2 細胞壁構造変化による溶菌抑制
4.2 細胞壁アニオン性ポリマー組成改変によるタンパク質生産向上
4.3 細胞膜脂質組成改変によるタンパク質生産向上
4.4 まとめ
5 麹菌を宿主とした異種タンパク質の分泌生産
5.1 はじめに
5.2 高発現用プロモーター
5.3 コドン最適化による転写産物の安定化
5.4 5’非翻訳領域配列による翻訳効率の向上
5.5 キャリアタンパク質の融合
5.6 細胞内タンパク質輸送過程における改良
5.7 プロテアーゼ遺伝子の破壊
5.8 細胞壁へのタンパク質吸着
5.9 おわりに
6 麹菌の酵素生産の特徴と組換えタンパク質生産への応用
6.1 麹菌の酵素生産の特徴
6.2 アミラーゼ遺伝子の発現制御
6.3 固体培養で特異的に発現する遺伝子の発見
6.4 固体培養での遺伝子発現
6.5 固体培養での遺伝子発現の複雑性
6.6 麹菌を用いた異種タンパク生産
6.7 麹菌の高発現プロモーターの探索
7 L-グルタミン酸の新規高効率型発酵生産技術
7.1 はじめに
7.2 通常のL-グルタミン酸発酵とその代謝経路
7.3 高効率なL-グルタミン酸生産のための新規代謝経路の設計
7.4 ホスホケトラーゼ(PKTase)をコードするxfp遺伝子の単離と発現
7.5 C. glutamicumにおけるxfp遺伝子の機能的発現
7.6 L-グルタミン酸生産におけるPKTaseの効果
7.7 PKT経路を導入したC. glutamicumでのL-グルタミン酸生産性の向上
7.8 おわりに
【第II編 医薬品】
第5章 放線菌の二次代謝産物生産を誘導する微生物ホルモン
1 はじめに
2 放線菌の微生物ホルモン
3 二次代謝・形態分化をグローバルに制御するA-ファクター制御カスケード
4 γ-ブチロラクトンによる抗生物質生産の制御
5 おわりに
第6章 微生物酵素を用いたペプチド製造法の開発
1 はじめに
2 ペプチドの製造法
2.1 ジペプチドの製造法
2.2 L-アミノ酸リガーゼの発見とジペプチド合成
3 ペプチド性生理活性物質生産微生物からのLalの探索
3.1 植物病原ペプチド合成細菌からの探索
3.2 ペプチド性抗生物質生産菌からの探索
4 オリゴペプチド合成酵素の発見
5 ゲノム情報を活用したオリゴペプチド合成酵素の探索
6 既知酵素を活用した新規合成法の開発
6.1 非リボソームペプチド合成酵素の構成ドメインを活用した合成法
6.2 タンパク質修飾酵素RimKを用いたポリアミノ酸合成
7 おわりに
【第III編 食品】
第7章 高度不飽和脂肪酸・共役脂肪酸含有油脂の微生物生産
1 はじめに
2 M. alpinaを用いるPUFAの生産
2.1 n-6系PUFA含有油脂
2.2 n-3系PUFA含有油脂
2.3 n-9系PUFA含有油脂
2.4 その他の希少PUFA含有油脂
3 腸内細菌におけるPUFA代謝
3.1 乳酸菌のPUFA飽和化代謝
3.2 PUFA飽和化代謝系酵素を活用する共役脂肪酸生産
4 おわりに
第8章 酵素を利用した生理活性オリゴ糖の生産
1 はじめに
2 オリゴ糖生産用酵素バイオリアクター
2.1 酵素バイオリアクターの分類
2.1.1 充填層型バイオリアクター
2.1.2 撹拌槽型バイオリアクター
2.1.3 膜型バイオリアクター
2.2 酵素バイオリアクターによるオリゴ糖生産
2.2.1 多糖の加水分解反応によるオリゴ糖生産
2.3 縮合・転移反応によるオリゴ糖生産
3 酵素バイオリアクターによる海洋バイオマスからの生理活性オリゴ糖生産
3.1 キトサンオリゴ糖とは
3.2 キトサンオリゴ糖の生産方法
3.3 多点結合法によるキトナサーゼの固定化と安定化
3.4 酵素バイオリアクターによるキトサンオリゴ糖の生産
4 おわりに
【第IV編 化粧品】
第9章 乳酸菌発酵を利用した化粧品素材の開発
1 はじめに
2 皮膚の保湿成分と乳酸菌
3 乳酸菌培養液
4 乳酸桿菌/アロエベラ発酵液
5 新規微生物によるヒアルロン酸生産
6 効果測定
7 安全性と申請・承認
8 おわりに
第10章 チロシナーゼの三次元構造と酒粕由来のチロシナーゼ阻害剤
1 はじめに
2 チロシナーゼの三次元構造
3 触媒部位の構造
4 酒粕由来のチロシナーゼ阻害剤
5 おわりに
【第V編 環境・エネルギー】
第11章 新規産業バイオリファイナリーの実現へ向けて
1 はじめに
2 増殖非依存型バイオプロセス
3 非可食バイオマス利用技術の開発
3.1 バイオ変換工程に必要な技術特性
3.2 C6,C5糖類の同時利用
3.3 醗酵阻害物質耐性
3.4 高生産株の創製
4 おわりに
第12章 光合成微生物による光水素製造技術
1 緒言
2 光合成微生物による光水素製造技術とは
2.1 光合成微生物の分類
2.2 光合成微生物による光水素生産の原理
2.3 光合成微生物による光水素生産の酵素
3 光合成細菌による光水素製造のコスト(当時)
3.1 フォトバイオリアクター
3.2 前提諸条件の試算
3.3 試算結果
4 まとめ
第13章 嫌気微生物による有用物質生産と環境浄化・エネルギー回収への応用
1 はじめに
2 有用物質生産の微生物資源としてのメタン発酵エコシステム
3 化成品原料(光学活性化合物)の嫌気的発酵生産
4 クリーンエネルギー(水素,エタノール)の嫌気的発酵生産
5 生理活性物質(ビタミンB12関連物質)の嫌気的発酵生産
6 二酸化炭素固定による嫌気的エタノール生産
7 嫌気性微生物群の環境浄化・エネルギー回収への応用(メタン発酵)
7.1 メタン発酵フェーズ毎の最適化による高速メタン発酵(多槽型メタン発酵)
7.2 低含水率でのメタン発酵(乾式メタン発酵)
8 おわりに -

機能性食品素材のためのヒト評価(普及版)
¥2,970
2013年刊「機能性食品素材のためのヒト評価」の普及版!機能性食品素材のヒト試験・評価に関する研究手法を徹底解説!ストレス、骨・関節、眼、脳、口腔、免疫、胃腸、アレルギー、更年期、アルコール代謝、泌尿器、生活習慣病に関する実際の評価事例を一挙掲載!
(監修:山本哲郎)
<a href="https://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=5723"target=”_blank”>この本の紙版「機能性食品素材のためのヒト評価《普及版》」の販売ページはこちら(別サイトが開きます)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は、2013年当時のものを使用しております。
伏島あゆみ 近畿大学九州短期大学
津田 彰 久留米大学
秋月さおり 協和発酵バイオ(株)
桐浴隆嘉 キリン(株)
外薗英樹 三和酒類(株)
長岡 功 順天堂大学
坪井 誠 一丸ファルコス(株)
井本良子 (株)エバーライフ
神﨑範之 サントリーウエルネス(株)
丸尾敏夫 帝京大学
山下栄次 アスタリール(株)
橋本正史 ケミン・ジャパン(株)
畠 修一 タマ生化学(株)
古賀良彦 杏林大学
中野昌彦 三菱ガス化学(株)
加藤豪人 (株)ヤクルト本社
酒井正士 (株)ヤクルト本社
梁 洪淵 鶴見大学
斎藤一郎 鶴見大学
清水康光 サンスター(株)
雫石 聰 サンスター(株)
寺本民生 帝京大学
河合博成 アークレイグループ
水道裕久 サンスター(株)
抜井一貴 日清ファルマ(株)
青山敏明 日清オイリオグループ(株)
宮﨑幸司 (株)ヤクルト本社
松本 剛 ポーラ化成工業(株)
長谷川秀樹 国立感染症研究所
栗原重一 味の素(株)
山中大輔 東京薬科大学
元井益郎 東栄新薬(株)
高橋信一 杏林大学
河内智子 キッコーマン(株)
三田村理恵子 藤女子大学
早川弘子 (株)ヤクルト本社
長岡正人 (株)ヤクルト本社
松井 登 山本漢方製薬(株)
榎本雅夫 NPO日本健康増進支援機構
今井伸二郎 静岡県立大学;日清製粉グループ高次機能性食品探索研究室
山本敏樹 日本大学
森山光彦 日本大学
吉村貴史 三菱ガス化学(株)
大石 元 東京大学
矢野 哲 東京大学
武谷雄二 (独)労働者健康福祉機構
仲宗根靖 (株)健康家族
増田宏子 東京大学
堀江重郎 順天堂大学
山田静雄 静岡県立大学
伊藤由彦 静岡県立大学
鈴木朝日 キューサイ(株)
黒川美保子 キューサイ(株)
影山慎二 かげやま医院
渡辺 貢 (株)渡辺オイスター研究所
Jeffry Michael Strong ホーファーリサーチ社
-------------------------------------------------------------------------
<<目次>>
第1章 ストレス,疲労,睡眠
序論:ストレス,疲労,睡眠の概念的理解
〈1〉 はじめに
〈2〉 ストレスモデル
〈2.1〉 心理的ストレスモデル
〈2.2〉 生理的ストレスモデル
〈3〉 ストレスモデルからみた「疲労」と「睡眠」
〈3.1〉 ストレスと疲労
〈3.2〉 ストレスと睡眠
〈3.3〉 疲労と睡眠問題
〈4〉 ストレスの心理学的研究法
〈4.1〉 実験法
〈4.2〉 質問紙法
〈5〉 食品成分摂取によるストレスへの対処
1 オルニチン
1.1 L-オルニチンとストレス・疲労
1.1.1 現代社会とストレス・疲労
1.1.2 L-オルニチンによる疲労回復およびストレス改善作用
1.2 試験
1.2.1 L-オルニチンの経口投与がヒトメンタルストレスに及ぼす影響
1.2.2 L-オルニチンの経口投与が疲労気味のヒトの肌質に及ぼす影響
1.3 考察
1.4 おわりに
2 GABA
2.1 はじめに
2.2 大麦乳酸発酵液ギャバの抗ストレス作用
2.2.1 方法
2.2.2 結果
2.3 大麦乳酸発酵液ギャバの睡眠の質改善作用
2.3.1 方法
2.3.2 結果
2.4 おわりに
第2章 骨,関節の健康
序論
〈1〉 はじめに
〈2〉 変形性関節症における軟骨の病態変化と評価法
〈2.1〉 関節軟骨の構造と機能
〈2.2〉 OAにおける病態変化
〈2.3〉 変形性関節症の評価法
〈3〉 関節疾患に関連するバイオマーカー
〈4〉 関節マーカーを用いた評価
〈4.1〉 変形性膝関節症について
〈4.2〉 スポーツ選手について
〈5〉 まとめ
1 プロテオグリカン
1.1 はじめに
1.2 プロテオグリカンとは
1.3 プロテオグリカンの役割
1.4 食経験と歴史
1.5 素材としての鮭鼻軟骨
1.6 素材の検討
1.7 試験計画
1.8 ヒト経口摂取試験
1.9 おわりに
2 ヒアルロン酸
2.1 序論
2.1.1 関節におけるヒアルロン酸の組織生理学的役割
2.1.2 関節軟骨障害を来す病気と関節損傷
2.1.3 HAの経口摂取が関節軟骨障害の予防・改善に役立つ可能性
2.2 病変関節に対するHA食品の有効性評価法
2.2.1 膝OA症状緩和効果の評価法
2.2.2 関節軟骨代謝改善効果の評価法
2.3 軟骨障害のある膝関節に対する「皇潤」の効果を検討した介入試験の実施例
2.3.1 膝OA発症者における症状改善効果ならびに軟骨代謝改善効果に関する試験
2.3.2 大学サッカー選手における関節痛緩和効果に関する試験
2.3.3 大学サッカー選手における骨と軟骨の代謝に対する改善効果に関する試験
2.4 考察とまとめ
3 グルコサミン
3.1 はじめに
3.2 グルコサミンの変形性関節症に対する改善効果
3.3 グルコサミンの変形性関節症改善効果の作用機序
3.4 グルコサミンの安全性
3.5 まとめ
第3章 眼
序論 視機能とその評価
〈1〉 視覚系
〈1.1〉 視力
〈1.2〉 視野
〈1.3〉 色覚
〈1.4〉 光覚
〈2〉 屈折系
〈2.1〉 屈折
〈2.2〉 調節
〈3〉 眼筋系
〈3.1〉 眼球運動
〈3.2〉 輻湊・開散
〈3.3〉 眼位
〈3.4〉 両眼視
〈3.5〉 眼精疲労
〈3.6〉 眼筋系の評価
1 アスタキサンチン
1.1 はじめに
1.2 VDT(情報提示機器:Visual Display Terminal)作業者での評価
1.2.1 予備試験
1.2.2 摂取量設定試験
1.2.3 効果確認試験
1.3 眼負荷被験者での評価
1.3.1 HFC測定試験
1.3.2 視覚負荷試験
1.4 中高齢者での評価
1.5 作用メカニズム解明へのアプローチ
1.6 おわりに
2 眼機能に関するルテインのヒト評価
2.1 はじめに
2.2 ルテインの発見
2.3 ルテインの眼の健康に関する機能性と作用機序
2.4 ルテインの観察研究
2.5 ルテインのヒト介入試験―加齢黄斑変性を中心として
2.6 ルテインと黄斑色素光学密度(MPOD)
2.7 注目されるNIHが行ったルテインの大規模臨床試験AREDS2研究
2.8 ルテインの推奨摂取量
3 ヒルベリーエキスに含まれるアントシアニンと眼の機能への影響
3.1 仮性近視,眼性疲労に対する影響
3.2 視機能改善とケモカイン
3.3 糖尿病性および高血圧性網膜症への効果
3.4 真正な視機能に対するビルベリーエキスの影響
3.5 夜間視力の改善
第4章 脳機能
序論―脳機能画像による食品の効果の評価―
〈1〉 はじめに
〈2〉脳機能画像
〈2.1〉 脳波
〈2.2〉 PET
〈2.3〉 NIRS
〈3〉 脳機能画像による食品の評価の限界と陥穽
1 PQQ(ピロロキノリンキノン)
1.1 PQQとは
1.2 PQQの機能
1.3 ヒト試験
1.3.1 単語の記憶テスト,Stroop試験
1.3.2 アーバンス(RBANS)試験
1.3.3 タッチエムでの評価
1.3.4 ストレス,疲労及び睡眠に対する効果
1.4 おわりに
2 ホスファチジルセリン
2.1 はじめに
2.2 軽度な記憶障害を持つ高齢者に対する大豆PSの効果検証試験(パイロット試験)
2.3 軽度な記憶障害を持つ高齢者に対する大豆PSの効果検証試験(プラセボ対照二重目隠し試験)
2.4 まとめ
第5章 口腔
序論
〈1〉 はじめに
〈2〉 口腔の機能
〈2.1〉 摂食・嚥下機能
〈2.2〉 味覚
〈2.3〉 コミュニケーション
〈3〉 口腔の機能における唾液の重要性
〈3.1〉 ドライマウス
〈3.2〉 ドライマウスの原因と診断
〈3.3〉 ドライマウスの対処
〈4〉 まとめ
1 カルシウムとイソフラボン
1.1 はじめに
1.2 歯周病の概要について
1.3 歯周病の臨床評価について
1.4 食品素材と歯周組織の健康維持について
1.5 カルシウムと大豆イソフラボンアグリコンを用いた商品開発の方向性について
1.6 臨床試験について
1.7 歯周組織の破壊に対する評価結果
1.8 生化学的マーカーを用いた評価結果
1.9 おわりに
2 歯周病と食品素材に関する総説
2.1 はじめに
2.2 歯周保健のための機能性食品
2.3 歯周保健のための機能性食品の評価法
2.4 歯周保健のための機能性食品素材
2.4.1 VC,ビタミンE(VE)とその関連食品
2.4.2 カルシウム,ビタミンD(VD)とその関連食品
2.4.3 脂肪酸
2.4.4 プロバイオティクス
2.4.5 抗菌性食品
2.5 おわりに
第6章 生活習慣病
序論
〈1〉 動脈硬化性疾患とは
〈2〉 脂質異常症
〈3〉 高血圧
〈4〉 糖尿病
〈5〉 肥満(メタボリックシンドローム)
〈6〉 動脈硬化予防のための生活習慣の改善(健康食品に対する期待)
〈6.1〉 体重のコントロール
〈6.2〉 食事療法
〈7〉 おわりに
1 ハッサク果実由来オーラプテンと糖・脂質代謝関連ヒト試験
1.1 はじめに
1.2 糖・脂質代謝関連のヒト試験で注意すべき事項
1.2.1 実施時期
1.2.2 被験者の検査前日の食事内容
1.2.3 被験者の選定および被験者とCRC(ヒト試験コーディネータ)のコミュニケーション
1.2.4 臨床検査値の精度
1.3 ハッサク果実由来のオーラプテンがメタボリックシンドローム予備群のヒトに及ぼす影響
1.3.1 緒言
1.3.2 方法
1.3.3 結果
1.3.4 考察
1.4 おわりに
2 ニーム
2.1 はじめに
2.2 素材
2.2.1 内蔵脂肪細胞の脂肪蓄積抑制作用
2.2.2 ヒトモニター試験:酸化ストレス
2.2.3 ヒト長期摂取試験
2.2.4 ヒトモニター試験:アディポネクチン
2.3 おわりに
3 アブラナ科野菜
3.1 はじめに
3.2 開発の経緯
3.3 関与成分の設定
3.4 ヒトにおける摂取量の検討:3用量比較試験
3.5 プラセボ対照二重盲検試験
3.6 試験飲料の安全性について
3.7 製品特長
3.8 おわりに
4 小麦アルブミンを利用した機能性粉体食品素材
4.1 はじめに
4.2 小麦アルブミンとは
4.3 小麦アルブミンの機能特性
4.3.1 構造
4.3.2 作用機序
4.3.3 小麦アルブミンによるデンプンの消化・吸収遅延効果
4.3.4 小麦アルブミンの食後血糖値低下に伴う脂質代謝改善
4.3.5 小麦アルブミンの安全性
4.4 商品化への道のり
4.5 まとめ
5 中鎖脂肪酸
5.1 はじめに
5.2 長鎖脂肪酸の消化吸収と代謝
5.3 中鎖脂肪酸の消化吸収と代謝
5.4 中鎖脂肪酸の安全性
5.5 中鎖脂肪酸の短期摂取効果
5.5.1 熱産生効果
5.5.2 食後の血中TAG上昇抑制効果
5.6 中鎖脂肪酸の長期摂取効果
5.6.1 MCTの体脂肪蓄積抑制効果
5.6.2 中・長鎖脂肪酸TAG(MLCT)の体脂肪蓄積抑制効果
5.7 中鎖脂肪酸の低栄養改善効果
5.8 おわりに
6 グァバ葉ポリフェノール―血糖コントロール作用と安全性―
6.1 はじめに
6.2 α-グルコシダーゼ阻害活性と関与成分
6.3 動物モデルでの有効性
6.4 ヒトでの有効性
6.4.1 単回摂取試験
6.4.2 継続摂取試験
6.5 安全性
6.6 おわりに
7 アロニア果実の機能性
7.1 はじめに
7.2 アロニア果実中の機能成分および薬理作用
7.3 自律神経活動度ならび代謝活性の評価
7.4 抗肥満活性の評価
7.5 脂肪細胞における遺伝子発現の評価
7.6 まとめ
第7章 免疫
序論 : 感染防御免疫(インフルエンザ)
〈1〉 はじめに
〈2〉 粘膜での免疫応答
〈3〉 ウイルス感染の信号
〈4〉 インフルエンザ感染の自然免疫応答と獲得免疫
〈5〉 腸内細菌叢が気道粘膜免疫に与える影響
〈6〉 粘膜免疫の防御機構
〈7〉 ワクチン及び感染で誘導される免疫
〈8〉 経鼻インフルエンザワクチンの開発
〈9〉 経鼻インフルエンザワクチンのヒトでの有効性
〈10〉 まとめ
1 シスチン・テアニン
1.1 はじめに
1.2 高齢者でのインフルエンザワクチン接種後の応答改善効果
1.3 風邪予防効果
1.4 強度運動負荷時の免疫機能低下の抑制効果
1.5 外科手術後の早期回復効果
1.6 おわりに
2 アガリクス
2.1 はじめに
2.2 免疫強化素材として
2.3 栽培・加工方法の追求
2.4 食品としての安全性
2.5 ヒトへの有効性評価
2.5.1 生活習慣病への作用(肥満,糖尿病関連)
2.5.2 免疫系への作用(NK細胞)
2.5.3 免疫系への作用(抗βグルカン抗体)
2.6 おわりに
第8章 胃腸の健康
序論
〈1〉 代替療法の目指すもの
〈1.1〉 茶カテキン
〈1.2〉 ラクトフェリン
〈1.3〉 ブロッコリスプラウト
〈1.4〉 プロバイオティックス
〈2〉 おわりに
1 乳酸発酵野菜入り野菜・果実混合飲料の整腸作用
1.1 はじめに
1.2 腸内環境改善作用(動物試験)
1.3 乳酸発酵野菜入り野菜・果実混合飲料の整腸作用(ヒト試験)
1.4 おわりに
2 フコイダン:抗ピロリ菌作用,胃症状改善作用
2.1 はじめに
2.2 オキナワモズクフコイダンの平均構造
2.3 抗ピロリ菌作用
2.3 抗ピロリ菌作用
2.3.1 Helicobacter pylori(H. pylori)接着抑制作用
2.3.2 ピロリ菌活性抑制作用
2.3.3 ピロリ菌感染予防作用
2.4 胃症状改善作用
2.4.1 動物モデルによる胃潰瘍予防効果および治癒促進効果の検証
2.4.2 抗潰瘍効果に関する作用機作
2.4.3 ヒトにおける抗潰瘍作用および胃機能改善効果
2.5 オキナワモズクフコイダンの腸管吸収性
2.6 オキナワモズクフコイダンの安全性
2.7 おわりに
3 大麦若葉粉末
3.1 青汁と大麦若葉
3.2 大麦若葉と「大麦若葉粉末」の安全性の検証
3.2.1 食経験
3.2.2 有害成分の含有
3.2.3 前臨床試験による評価
3.2.4 ヒトでの評価
3.3 大麦若葉粉末由来の食物繊維
3.4 大麦若葉粉末由来の食物繊維の作用機序
3.5 ヒト試験による大麦若葉粉末の便通改善作用の検証
3.5.1 試験方法
3.5.2 試験1(1日摂取量の検討試験)
3.5.3 試験2(便通改善の有効性の検証試験)
3.6 まとめ
第9章 アレルギー
序論
〈1〉 はじめに
〈2〉 アレルギー有病率の増加とその要因
〈3〉 プロバイオティクス
〈3.1〉 アトピー性皮膚炎に対する効果
〈3.2〉 アレルギー性鼻炎(花粉症)に対する効果
〈3.3〉 プロバイオティクスによる抗アレルギー効果の作用機序
〈3.4〉 プロバイオティクスによる発症予防の試み
〈4〉 フラボノイド
〈5〉 おわりに
1 青大豆によるスギ花粉症抑制効果
1.1 スギ花粉症概要
1.2 スギ花粉症の予防治療及び対処療法の現状
1.3 花粉症に用いられる健康食品
1.4 青大豆研究の背景
1.5 青大豆のスギ花粉症臨床試験
1.5.1 方法
1.5.2 結果
1.5.3 考察
第10章 アルコール代謝
序論
〈1〉 はじめに
〈2〉 アルコール代謝
〈3〉 アルコールと肝障害
〈4〉 症例
1 CoQ10
1.1 はじめに
1.2 肝臓におけるアルコールの代謝
1.3 コエンザイムQ10(CoQ10)とは
1.4 CoQ10と電子伝達系
1.5 抗酸化剤としてのCoQ10
1.6 肝臓とCoQ10
1.7 CoQ10のアルコール代謝への効果
1.8 臨床試験に適したCoQ10の剤形の検討
1.9 アルコール代謝の臨床試験
1.10 臨床試験結果
1.11 おわりに
第11章 更年期
序論 中高年女性の好発疾患と健康管理
〈1〉 概要
〈1.1〉 更年期に関する用語
〈1.2〉 更年期の重要性
〈1.3〉 疫学的見地からみた更年期
〈2〉 好発疾患と管理
〈2.1〉 更年期障害
1 中高年期とくに更年期周辺女性における「伝統にんにく卵黄」の有用性
1.1 にんにくの歴史
1.2 にんにくの成分とその機能
1.3 経緯
1.4 「伝統にんにく卵黄」の試験製品と方法
1.5 末梢血行促進作用
1.6 更年期周辺女性の気分プロフィールに対する影響
1.7 おわりに
第12章 泌尿器,前立腺
序論
〈1〉 泌尿器科における機能性食品の有効性
〈2〉 前立腺がん
〈3〉 前立腺肥大症
〈4〉 LOH症候群(男性更年期障害)とテストステロン
1 ノコギリヤシ
1.1 はじめに
1.2 排尿障害モデル動物に対する改善作用
1.3 前立腺および膀胱の薬理学的受容体に対する作用
1.4 薬理活性成分
1.5 前立腺肥大患者における臨床作用
1.6 副作用および薬物との相互作用
1.7 おわりに
第13章 抗酸化
1 マガキ(Crassostrea gigas)軟体部エキスの抗酸化作用と新規抗酸化物質に関する研究
1.1 はじめに
1.2 第一実験「2型糖尿病患者におけるカキ肉エキス含有食品の亜鉛補充効果および抗酸化効果」
1.2.1 はじめに
1.2.2 方法
1.2.3 結果および考察
1.3 第二実験「自然発症糖尿病モデルマウスKKAy/Taにおけるカキ肉エキス含有食品の抗酸化機能に対する影響」
1.3.1 はじめに
1.3.2 方法
1.3.3 結果および考察
1.4 第三実験「マガキ(Crassostrea gigas)より発見された新規抗酸化物質の精製,同定,化学合成と抗酸化能に関する研究」
1.4.1 はじめに
1.4.2 抗酸化活性物質の精製
1.4.3 抗酸化物質の同定
1.4.4 抗酸化物質の化学合成
1.4.5 抗酸化能測定
1.4.6 考察
2 天然の抗酸化エキスピクノジェノール(R)の効果
2.1 はじめに
2.2 ピクノジェノール(R)の抗酸化作用の発見と実績
2.3 ピクノジェノール(R)と他の抗酸化剤との相乗効果
2.4 抗酸化作用による生活習慣病に対するピクノジェノール(R)の効果
2.5 抗酸化作用による認知機能に対するピクノジェノール(R)の効果
2.6 ピクノジェノール(R)の抗酸化作用によるアンチエイジング効果
2.7 おわりに -

全固体電池開発の最前線(普及版)
¥5,280
2011年刊「全固体電池開発の最前線」の普及版!全固体電池の開発の基礎から応用までを解説し、また「トヨタ自動車」をはじめとする企業6社の研究開発動向を網羅!!
(監修:辰巳砂昌弘)
<!--
<a href="https://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=5412"target=”_blank”>この本の紙版「全固体電池開発の最前線(普及版)」の販売ページはこちら(別サイトが開きます)</a> -->
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は、2011年当時のものを使用しております。
菅野了次 東京工業大学
佐藤峰夫 新潟大学
辰巳砂昌弘 大阪府立大学
林 晃敏 大阪府立大学
前川英己 東北大学
山本 仁 大阪大学
松本 一 (独)産業技術総合研究所
明渡 純 (独)産業技術総合研究所
小和田善之 兵庫教育大学
高田和典 (独)物質・材料研究機構
町田信也 甲南大学
岡田重人 九州大学
小林栄次 九州大学
金村聖志 首都大学東京
竹内友成 (独)産業技術総合研究所
蔭山博之 (独)産業技術総合研究所
中西康次 立命館大学
田渕光春 (独)産業技術総合研究所
栄部比夏里 (独)産業技術総合研究所
太田俊明 立命館大学
妹尾 博 (独)産業技術総合研究所
境 哲男 (独)産業技術総合研究所
辰巳国昭 (独)産業技術総合研究所
小林弘典 (独)産業技術総合研究所
今西誠之 三重大学
須賀健雄 早稲田大学
西出宏之 早稲田大学
桑田直明 東北大学
入山恭寿 静岡大学
嵯峨根史洋 静岡大学
内本喜晴 京都大学
折笠有基 京都大学
奥村豊旗 (独)産業技術総合研究所
山本和生 (財)ファインセラミックスセンター
濱 重規 トヨタ自動車(株)
川本浩二 トヨタ自動車(株)
清野美勝 出光興産(株)
上村 卓 住友電気工業(株)
小林直哉 (株)サムスン横浜研究所
印田 靖 (株)オハラ
坂本明彦 日本電気硝子(株)
-------------------------------------------------------------------------
<<目次>>
【固体電解質の開発動向編】
第1章 無機固体電解質の開発動向と展望
1 はじめに
2 固体電解質探索の歴史と現状,様々な物質
3 イオン導電体の物質例―Li10GeP2S12
4 イオン導電体を用いたデバイス―アプリケーションから見たイオン導電体
5 全固体電池の実現に向けて
6 新しいイオン導電体発見への期待
第2章 酸化物系リチウムイオン伝導体
1 はじめに
2 Aサイト欠損ペロブスカイト型リチウムイオン伝導体
3 NASICON型リチウムイオン伝導体
4 β-Fe2(SO4)型リチウムイオン伝導体
5 ガーネット型リチウムイオン伝導体
6 薄膜型リチウムイオン伝導体
7 まとめ
第3章 無機ガラス系固体電解質
1 はじめに
2 ガラス電解質の作製方法
3 ガラス電解質の導電率
4 ガラスセラミック電解質の導電率
5 おわりに
第4章 錯体水素化物リチウムイオン伝導体群と全固体電池への応用
1 はじめに
2 既知の水素含有リチウムイオン伝導体
2.1 水素化α-Li3N
2.2 リチウムイミド(Li2NH)
3 リチウムボロハイドライド(LiBH4)
3.1 リチウムボロハイドライドのリチウムイオン伝導特性
3.2 リチウムボロハイドライドのリチウムイオン伝導相の室温安定化
4 その他の水素化物への展開
5 固体電池への応用展開
6 おわりに
第5章 低障壁高分子固体電解質の研究開発
1 緒言
2 低障壁高分子固体電解質の分子設計
3 低障壁高分子固体電解質の合成
4 低障壁高分子固体電解質のイオン伝導度評価
5 モデル錯体の構造解析によるリチウムイオン配位様式の推定
6 結言
第6章 プラスチッククリスタル電解質
1 はじめに
2 プラスチッククリスタルとは
3 プラスチッククリスタルの固体電解質への応用
3.1 分子系
3.2 オニウム塩
3.3 その他の塩
4 おわりに
第7章 エアロゾルデポジション(AD)法による常温セラミックスコーティングと全固体薄膜型リチウムイオン電池への応用
1 はじめに
2 エアロゾルデポジション法による常温衝撃固化現象
3 成膜条件の特徴
3.1 原料粉末の影響
4 常温衝撃固化と成膜メカニズムに関する検討
4.1 粒子衝突速度の測定
4.2 緻密膜形成の基本メカニズム
5 高硬度,高絶縁AD膜と実用化への試み
6 全固体・薄膜型リチウムイオン電池への応用
7 大面積コーティングへの挑戦
8 今後の技術展望
第8章 硫化物ガラス系固体電解質のイオン伝導性と計算科学
1 はじめに
2 Li2S-SiS2-MxSy系ガラス中のLi+イオンの化学結合
3 Li+イオン伝導性に対する添加物効果
4 超イオン伝導性Li7P3S11結晶
4.1 結晶構造とLiサイト
5 硫化物系固体電解質中のLi+イオンの伝導メカニズム
【全固体リチウム電池の開発と展望編】
第9章 硫化物固体電解質を用いたバルク型電池の開発と展望
1 はじめに
2 硫化物固体電解質のバルク型電池用電解質としての特質
3 硫化物固体電解質の開発とバルク型電池
4 硫化物固体電解質電池の展望
5 おわりに
第10章 バルク型全固体二次電池の高容量化
1 はじめに
2 硫化物固体電解質を用いたバルク型全固体電池の作製
3 高容量電極活物質の適用による電池の高容量化
3.1 硫黄正極活物質
3.2 リン負極活物質
4 電極-電解質固体界面制御による電池の高容量化
4.1 電極活物質の微粒子化
4.2 ガラス性液体の利用
4.3 電極活物質上への固体電解質薄膜コーティング
5 おわりに
第11章 全固体型リチウム電池用Li-Si合金の開発と応用
1 はじめに
2 メカニカルミリング(MM)法によるLi-Si合金の作製
3 メカニカルミリング(MM)法により合成されたLi-Si合金の全固体電池用負極材料特性
4 メカニカルミリング(MM)法により合成したLi-Si-Ge合金の特性
5 まとめ
第12章 オールナシコン型全固体電池
1 はじめに
2 リン酸ナシコン型全固体対称電池
2.1 全固体Li電池:Li3V2(PO4)3/Li1.5Al0.5Ge1.5(PO4)3/Li3V2(PO4)3
2.2 全固体Na電池:Na3V2(PO4)3/Na3Zr2(SiO4)2PO4/Na3V2(PO4)3
3 おわりに
第13章 3次元電池
1 はじめに
2 3次元電池の構造
3 3次元電池用固体電解質
4 3次元規則配列多孔構造とホールアレイ構造の複合化
5 まとめ
第14章 通電焼結を用いた全固体電池の構築
1 はじめに
2 通電焼結法を用いた金属酸化物正極活物質―炭素複合体の作製
3 通電焼結法を用いた硫黄系正極活物質―炭素複合体の作製
4 通電焼結法を用いた正極/電解質/負極積層体の作製
第15章 全固体リチウムポリマー電池
1 はじめに
2 ポリマー電解質
3 ポリマー電解質用負極材料
4 ポリマー電解質用正極材料
5 まとめ
第16章 フレキシブルラジカルポリマー電池
1 はじめに
2 ラジカルポリマー電池の作動原理と特長
3 ラジカルポリマー電池の位置づけと将来展望
4 新しい有機系電極活物質(多電子系、導電性高分子など)での展開
第17章 全固体薄膜電池と界面構築
1 はじめに
2 全固体薄膜電池
2.1 薄膜電池の特徴
2.2 薄膜電池の構造
3 薄膜電池の作製方法
3.1 材料
3.2 薄膜作製方法
4 PLD法による薄膜電池の作製法
4.1 正極材料の薄膜化
4.2 固体電解質の薄膜化
4.3 負極の薄膜化
5 PLD法による薄膜電池の作製と界面特性
6 まとめ
第18章 リチウム二次電池の全固体化に向けた界面制御
1 はじめに
2 固体電解質/電極活物質界面で起こる電荷移動反応の熱力学的考察
2.1 活性化エネルギー(Ea)
2.2 前指数因子
2.2.1 Li+移動系
2.2.2 電子移動系(Li析出溶解反応)
3 まとめ
第19章 放射光を用いた全固体リチウム二次電池電極/電解質の界面評価
1 緒言
2 実験手法
3 電極/電解質界面の修飾
4 界面修飾による電気化学特性の変化
5 深さ分解X線吸収分光法(DR-XAFS)
6 おわりに
第20章 電子線ホログラフィーによる全固体電池反応のその場観察
1 はじめに
2 電子線ホログラフィーの原理
3 TEM観察用全固体リチウム電池の作製
4 電子線ホログラフィーによる電位分布のその場観察
5 まとめ
【企業における蓄電池の全固体化に向けた研究開発動向と展望編】
第21章 自動車用次世代型全固体電池の研究開発と展望
1 はじめに
2 全固体電池のメリットと課題
3 活物質の表面コーティングで界面制御
4 固体電解質の化学的安定性
5 界面抵抗と固体電解質の化学的安定性の関係
6 自動車用次世代型全固体電池の展望
第22章 硫化物系無機固体電解質を用いた全固体電池の開発
1 はじめに
2 硫化物系無機固体電解質の特徴
3 硫化物系無機固体電解質を用いた全固体リチウム電池
4 硫化物系無機固体電解質を用いた全固体リチウム電池の安全性
5 大型(ラミネート型)電池の作製
6 おわりに
第23章 硫化物固体電解質薄膜を用いた全固体リチウム電池の開発
1 緒言
2 薄膜全固体リチウム電池のデザイン,及び技術課題
3 硫化物固体電解質の薄膜化プロセス
3.1 成膜条件
3.2 Liイオン伝導特性
3.3 Li金属に対する固体電解質膜の化学安定性
4 Li金属の薄膜化プロセス
5 薄膜全固体リチウム電池試作,及び充放電評価
5.1 薄膜全固体リチウム電池試作
5.2 充放電試験結果
6 結言
第24章 バルク型全固体電池の特性向上
1 はじめに
2 固体電解質を用いた電池の課題
3 全固体電池の特性
3.1 出力&寿命特性
3.1.1 LiCoO2正極を用いた全固体電池の特性
3.1.2 正極/固体電解質界面での副生物抑制技術開発
3.2 安全性
3.3 エネルギー密度
3.4 温度特性
4 まとめ
第25章 全固体電池用酸化物ガラスセラミックス電解質の開発
1 はじめに
2 酸化物系固体電解質
3 酸化物系ガラスセラミックス電解質
4 固体電解質の新しい応用
5 新しいガラスセラミックス電解質
6 ガラスセラミックス電解質の全固体電池への応用
第26章 ガラス系電極材料の全固体電池への応用
1 はじめに
2 リン酸鉄リチウム系結晶化ガラス
3 LFP結晶化ガラスの製造プロセス
4 LFP結晶化ガラスの構造と電池特性
5 スズリン酸系ガラス
6 SnPガラスの電池特性
7 まとめ
-

リチウムイオン電池の部材開発と用途別応用(普及版)
¥4,620
2011年刊「リチウムイオン電池の部材開発と用途別応用」の普及版!部材開発、次世代自動車、電車、エコハウスなど、用途別の開発動向と各メーカーの動向、国内外の市場動向についても網羅!!
(監修:金村聖志)
<a href="http://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=5389"target=”_blank”>この本の紙版「リチウムイオン電池の部材開発と用途別応用(普及版)」の販売ページはこちら(別サイトが開きます)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は、2011年当時のものを使用しております。
金村聖志 首都大学東京大学院
田渕光春 (独)産業技術総合研究所
秋本順二 (独)産業技術総合研究所
今泉純一 (株)田中化学研究所
本間 剛 長岡技術科学大学
小松高行 長岡技術科学大学
佐々木龍朗 住友ベークライト(株)
森山斉昭 石原産業(株)
関 志朗 (財)電力中央研究所
鳶島真一 群馬大学
辰巳砂昌弘 大阪府立大学
林 晃敏 大阪府立大学
荒井健次 日本ゼオン(株)
堀江英明 日産自動車(株)
小笠正道 公益財団法人 鉄道総合技術研究所
田口義晃 公益財団法人 鉄道総合技術研究所
田路和幸 東北大学
高田和典 (独)物質・材料研究機構
石原達己 九州大学
佐藤正春 (株)村田製作所
阿久戸敬治 島根大学
-------------------------------------------------------------------------
<<目次>>
第Ⅰ編 部材開発の最前線
第1章 正極材料
1 三元系
1.1 緒 言
1.2 三元系正極材料の電気化学反応特性
1.3 合成方法
1.4 安定性
1.5 その他の三元系材料
1.6 まとめ
2 酸化物固溶体系
2.1 はじめに
2.2 酸化物固溶体系正極材料の魅力と高容量発現機構
2.3 酸化物固溶体系正極材料の充放電特性制御のために考慮すべき因子
2.4 新規Li2MnO3系正極開発について
2.5 おわりに
3 ガラス結晶化法によるリン酸塩系正極材料の創製
3.1 はじめに
3.2 大型LiB向け正極材の開発動向
3.3 リン酸系正極活物質の特徴
3.4 LiFePO4前駆体ガラスの作製と熱物性
3.5 マンガン置換によるLiMnxFe1-xPO4ガラス形成能と電池特性
3.6 他の候補材料のガラス結晶化
3.7 まとめと今後の展望
第2章 負極材料
1 ハードカーボン系
1.1 はじめに
1.2 ハードカーボンとグラファイト
1.2.1 炭素化の相違
1.2.2 炭素構造の相違
1.3 フェノール樹脂系ハードカーボン材料の研究例
1.3.1 フェノール樹脂類を用いたハードカーボン材
1.3.2 フェノール樹脂系ハードカーボン材の充放電特性
1.4 まとめ
2 チタン系材料
2.1 はじめに
2.2 Li-Ti-O系材料
2.2.1 スピネル型チタン酸リチウムの化学組成、結晶構造、充放電特性
2.2.2 結晶格子の安定による高サイクル特性
2.2.3 粒子サイズ,比表面積の最適化による高負荷特性
2.3 他のチタン系材料
2.3.1 TiO2系材料
2.3.2 H-Ti-O系材料
2.3.3 M-Li-Ti-O系(M=Na,Sr,Ba)材料
2.4 終わりに
第3章 電解液
1 イオン液体電解質系
1.1 はじめに
1.2 イオン液体
1.3 イオン液体を用いたリチウム二次電池の研究・開発
1.4 イオン液体を用いたリチウムイオン二次電池の実現に向けて
1.5 おわりに
2 機能性電解液
2.1 はじめに
2.2 リチウム電池用電解液に要求される基本特性
2.3 電解液の導電率(イオン伝導度)
2.4 電解液の安定性
2.5 リチウムイオン電池用電解液の分類と特徴
2.6 負極表面処理添加剤
2.7 正極表面修飾添加剤
2.8 難燃性電解液
2.9 過充電防止剤
2.10 今後の展開
3 無機ガラス系固体電解質
3.1 はじめに
3.2 ガラス電解質の作製方法
3.3 ガラス電解質の導電率
3.4 ガラスセラミック電解質の導電率
3.5 おわりに
第4章 バインダー
1 はじめに
2 負極用バインダー
2.1 負極用バインダーの種類と特徴
2.2 スラリー作製上の留意点
2.3 乾燥工程上の留意点
2.4 負極用バインダーの電池性能への影響事例
3 正極用バインダー
3.1 正極用バインダーの種類と特徴
3.2 正極用水系バインダー
3.3 水系バインダーの分散性
3.4 水系正極用バインダーを用いた電池の性能
4 まとめ
第Ⅱ編 リチウムイオン電池の用途別応用
第1章 環境車輛用高性能電池の研究開発
1 高性能環境車両用電池システム
2 電池に求められる特性
第2章 高性能二次電池の評価
1 電池の基本的特性と考え方
2 電池の基本的な評価
第3章 電源ハイブリッド型電車における蓄電池システム開発―架線レス・バッテリーLRV―
1 はじめに
2 バッテリー搭載型電車の意義
3 蓄電媒体の選定
3.1 蓄電媒体の選定にあたって
3.2 蓄電媒体に要求されるエネルギー量
3.3 寿命を考慮した搭載エネルギー量の決定
4 急速充電の方式
5 車載バッテリーの温度上昇抑制方策―セル配置による放熱量の推定と温度上昇予測
6 保護系統の開発(安全確保)と車体へのバッテリー分散配置
6.1 主バッテリー
6.2 バッテリー保護系統
6.3 バッテリーモジュール配置
7 バッテリーモニタ装置の開発
7.1 バッテリー充電残量推定および劣化容量推定
7.2 運転台と客室内のディスプレイ表示(エネルギー表示画面とGPSマルチ画面)
8 架線レス・バッテリー走行
8.1 架線レス・バッテリーLRV
8.2 急速充電とバッテリー走行
9 実用化とさらなる展開に向けた期待
9.1 より安全なバッテリーへ
9.2 内部抵抗の低減
9.3 感電防止策
10 おわりに
第4章 エコハウスプロジェクトにおける太陽光発電による直流電力貯蔵リチウムイオン電池
1 3.11以前のエコハウスと電力利用に関する考え方
2 3.11以降のエコハウスと電力利用の考え方
3 これからのスマートコミュニティを構築するためのエコハウスは
4 太陽電池の出力変動をなくすための蓄電システム
5 コンデンサー的な蓄電池利用と系統からの電気のバックアップ
6 一般住宅への適用
7 まとめ
第Ⅲ編 ポストリチウムイオン電池の開発動向
第1章 全固体リチウムイオン電池の開発
1 はじめに
2 リチウムイオン電池の課題
3 無機固体電解質を用いた全固体化への期待
4 全固体リチウム電池の歴史
5 固体電解質の開発動向
6 ナノイオニクス
7 おわりに
第2章 金属―空気電池,亜鉛―空気電池,リチウム―空気電池の開発の現状
1 はじめに
2 金属―空気電池の特長と亜鉛―空気電池
3 Li-空気,Li-空気-水2次電池の特徴,開発の現状と課題
4 Li-空気電池2次電池の空気極触媒開発の動向
5 電極反応の解析と空気極触媒
6 空気極触媒としてのメソポーラスMnO2の作成と応用
7 おわりに
第3章 有機二次電池の可能性
1 はじめに
2 有機化合物を活物質とする二次電池の動作原理と特徴
3 多電子系有機二次電池
3.1 ニトロニルニトロキシドラジカル
3.2 キノイド化合物
3.3 トリキノキサリニレン
3.4 ルベアン酸
4 多電子系有機二次電池の可能性
第4章 光空気二次電池の開発
1 はじめに
2 光空気二次電池の概要
2.1 基本構成と充放電反応イメージ
2.2 光充電(自己再生)の原理
3 光充放電機能を実現する光空気二次電池
3.1 負極に水素吸蔵合金を用いた電池系
3.1.1 電池構成
3.1.2 光充放電機能実現への課題
3.1.3 金属水素化物の解離(自己放電)抑制
3.1.4 光充電を実現するエネルギーレベルの形成
3.1.5 SrTiO3-LaNi3.76Al1.24Hn|KOH|O2系電池の光充放電挙動
3.2 金属活物質―半導体複合電極を用いた電池系
3.3 放電生成物の光反応を利用した電池系
4 光空気二次電池の特徴と可能性
5 おわりに
第Ⅳ編 リチウムイオン二次電池の市場
第1章 リチウムイオン電池の生産概況
1 概要
2 市場動向
3 メーカー動向
3.1 三洋電機(パナソニックグループ)
3.2 ソニー
3.3 ジーエス・ユアサ コーポレーション
3.4 NEC
3.5 日立製作所
3.6 東芝
3.7 その他国内メーカー
3.7.1 エナックス
3.7.2 エリーパワー
3.8 海外メーカー
3.8.1 サムスンSDI
3.8.2 LG化学
3.8.3 BYD(比亜迪)
3.8.4 BAK(比克)
3.8.5 コンチネンタル社
4 用途動向
第2章 構成材料の市場動向
1 主要4部材の市場
2 正極材料
2.1 概要
2.2 市場動向
2.3 メーカー動向
2.3.1 コバルト系メインのメーカー
2.3.2 マンガン系メインのメーカー
2.3.3 ニッケル系メインのメーカー
2.3.4 3元系メインのメーカー
2.3.5 リン酸鉄系メインのメーカー
2.3.6 その他のメーカー
2.3.7 主な海外メーカー
3 負極材料
3.1 概要
3.1.1 炭素系材料
3.1.2 新材料
3.2 市場動向
3.3 メーカー動向
3.3.1 炭素系材料メーカー
3.3.2 新材料系メーカー
3.3.3 海外メーカー
4 電解液・電解質
4.1 概要
4.2 電解液溶質材料
4.3 市場動向
4.4 メーカー動向
4.4.1 六フッ化リン酸リチウム(LiPF6)を溶質に用いるメーカー
4.4.2 六フッ化リン酸リチウム(LiPF6)メーカー
4.4.3 その他の電解液メーカー
5 セパレータ
5.1 概要
5.2 市場動向
5.3 メーカー動向
5.3.1 既存メーカーの動向
5.3.2 新規参入(予定を含む)メーカー
第3章 用途別市場動向
1 大型パワー用途
2 大型エネルギー用途
第4章 ポストリチウムイオン電池動向
1 既存リチウムイオン電池の改良
2 容量が2倍の革新電池
3 容量が3倍以上の革新電池
-

海藻バイオ燃料(普及版)
¥4,510
2011年刊「海藻バイオ燃料」の普及版!海藻を利用したバイオ燃料開発の基礎から応用とプロジェクト情報、収率、採算性など抱える問題点とその解決に向けた取組みまでを紹介!!
(監修:能登谷正浩)
<a href="http://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=5356"target=”_blank”>この本の紙版「海藻バイオ燃料(普及版)」の販売ページはこちら(別サイトが開きます)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は、2011年当時のものを使用しております。
能登谷正浩 東京海洋大学
野津 喬 農林水産省 大臣官房環境バイオマス政策課
香取義重 (株)三菱総合研究所
Jeong-Jun Yoon Green Materials Technology Center
Yong Jin Kim Green Process & Material R&D Group
Choul-Gyun Lee Department of Biotechnology
浦野直人 東京海洋大学
高木俊之 東京海洋大学
伊佐亜希子 (独)産業技術総合研究所
三島康史 (独)産業技術総合研究所
澤辺智雄 北海道大学
佐藤 実 東北大学
佐古 猛 静岡大学
岡島いづみ 静岡大学
七條保治 新日鐵化学(株)
岡崎奈津子 新日鐵化学(株)
松井 徹 東京ガス(株)
中島田豊 広島大学
西尾尚道 広島大学
石橋康弘 熊本県立大学
中道隆広 長崎総合科学大学
谷生重晴 バイオ水素(株)
若山 樹 国際石油開発帝石(株)
-------------------------------------------------------------------------
<<目次>>
第1章 海藻バイオ燃料の考え方
1 地球温暖化とエネルギー問題
1.1 地球温暖化の原因
1.2 二酸化炭素の排出とバイオ燃料
1.3 自然環境の保全とバイオ燃料生産
2 なぜ海藻なのか?~海藻によるバイオ燃料生産の有効性~
2.1 陸と海の利用環境
2.2 海藻の生育と環境保全の機能
3 バイオ燃料資源としての海藻
3.1 海藻の生産
3.2 大型海藻,コンブやホンダワラの利用
4 海藻バイオ燃料研究とそのアイデアと研究費
第2章 政策・プロジェクト
1 バイオマス活用推進基本計画の概要
1.1 はじめに
1.2 基本計画策定の背景と経緯
1.3 バイオマス・ニッポン総合戦略の総括
1.4 バイオマスの活用の推進に関する施策についての基本的な方針
1.4.1 バイオマスの種類ごとの特性に応じた最大限の利用
1.4.2 食料・木材の安定供給の確保
1.4.3 環境の保全への配慮
1.5 バイオマスの活用推進に関して国が達成すべき目標
1.5.1 将来的に実現すべき社会の姿
1.5.2 2020年における目標
1.6 バイオマスの活用の推進に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策
1.6.1 バイオマスの活用に必要な基盤の整備
1.6.2 バイオマス又はバイオマス製品等を供給する事業の創出等
1.6.3 バイオマス製品等の利用の促進
1.6.4 その他
1.7 バイオマスの活用に関する技術の研究開発に関する事項
1.7.1 技術の研究開発の重要性とその推進に当たっての基本的事項
1.7.2 廃棄物系バイオマスの有効利用に関する技術開発の基本的な方向性
1.7.3 未利用バイオマスの有効利用に関する技術開発の基本的な方向性
1.7.4 バイオマスの高度利用に向けて中期的に解決すべき技術的課題
1.7.5 低炭素社会の実現に向けて長期的に取り組むべき技術開発の方向性
1.8 まとめ
2 アポロ&ポセイドン構想2025の現状と課題
2.1 はじめに
2.2 アポロ&ポセイドン構想2025
2.2.1 アポロ&ポセイドン構想2025とは
2.2.2 研究開発のあゆみ
2.2.3 アポロ&ポセイドン構想2025の関連プロジェクト
2.3 革新的バイオエネルギー変換技術の研究開発
2.3.1 アポロ&ポセイドン構想2025の実現方策
2.3.2 大型海藻のバイオ燃料化の課題
2.3.3 革新的バイオエネルギー変換技術の開発
2.3.4 大型海藻の増養殖と収穫
2.4 今後の課題
2.4.1 既存の行政施策の課題
2.4.2 原料価格問題
2.4.3 社会状況変化への対応
2.5 おわりに
3 韓国の海藻バイオマス開発プロジェクト
3.1 はじめに
3.2 バイオエネルギーと食糧問題
3.3 韓国における海藻類バイオエネルギー開発の正当性
3.4 韓国の海洋バイオエネルギー政策及び技術開発プロジェクト
3.5 結論
第3章 バイオエタノール生産技術
1 酵母発酵によるアオサ・ホテイアオイからのエタノール生産
1.1 はじめに
1.2 海洋バイオマス(アオサ・ホテイアオイを中心として)
1.2.1 アオサ(Ulva属)
1.2.2 ホテイアオイ(Eichhornia crassipes)
1.3 アオサ・ホテイアオイ体内の多糖類とその糖化工程
1.4 糖化液のエタノール発酵
1.5 酵母によるエタノール生産効率の改善について
1.6 おわりに
2 大型緑藻類からのエタノール生産技術
2.1 はじめに
2.2 緑藻が生産する多糖類
2.3 緑藻の単糖の組成と含有量
2.4 緑藻の全グルコース量と貯蔵性デンプン量
2.5 水熱前処理,酵素糖化およびエタノール発酵の検討
2.5.1 水熱前処理による酵素糖化性
2.6 シオグサ・ジュズモの酵素糖化
2.7 酵素糖化液を用いたエタノール発酵
2.8 酵素糖化およびエタノール発酵に与える塩分の影響
2.9 高基質濃度での酵素糖化およびエタノール発酵
2.10 おわりに
3 マリンビブリオを活用した海藻からのエタノール生産
3.1 はじめに
3.2 我が国におけるエネルギー需給とエネルギー生産に果たす水産分野の取り組み
3.2.1 エネルギー需給の動向
3.2.2 水産分野での取り組み
3.3 マリンビブリオを利用した海洋バイオ燃料の生産
3.3.1 エタノール発酵能の高い海洋微生物の探索
3.3.2 エタノール生産の最適化
3.4 マリンビブリオによるエタノール-水素同時生産
3.5 マリンビブリオのバイオマス燃料産生に関与する遺伝子
3.6 おわりに
4 連続発酵による海藻からの高効率エタノール生産技術
4.1 どうして海藻を利用してのエタノール生産か
4.2 エタノール原料としての海藻バイオマス
4.3 海藻からのエタノール生産工程
4.3.1 液化
4.3.2 糖化
4.3.3 エタノール発酵
4.4 発電所冷却水取水口に集まる海藻から効率的エタノール生産
4.5 今後の課題
第4章 亜臨界水による海藻の燃料化技術
1 はじめに
2 亜臨界水とは
3 海藻の油化
3.1 バッチ実験装置
3.2 亜臨界水による海藻の分解・油化
4 おわりに
第5章 バイオマスガス生産技術
1 海藻ごみからのメタン生産技術
1.1 海藻バイオマス(海藻ごみ)事例
1.2 海藻からのメタン生産
1.3 海藻メタン発酵実証事例
1.3.1 海藻原料
1.3.2 実証試験装置
1.3.3 海藻のメタン発酵試験
1.3.4 残渣利用
1.4 まとめ
2 海藻のメタン発酵技術
2.1 海藻のカスケード利用システムの中でのメタン発酵の役割
2.2 海藻のメタン発酵過程
2.3 海藻のメタン発酵収率
2.4 海藻のメタン発酵条件
2.5 海藻のメタン発酵装置
2.6 藻類のメタン発酵の問題点
2.7 最後に
3 海藻からのメタン製造技術
3.1はじめに
3.2 高温可溶化メタン発酵
3.3 ワカメを使用したメタン発酵
3.4 おわりに
第6章 バイオ水素生産技術
1 海藻バイオマス発酵水素生産技術
1.1 発酵水素発生の経路と代謝産物
1.2 バクテリアの水素発生速度と水素収率
1.3 海藻バイオマスからの水素生産性
1.4 水素発酵と塩分の影響
1.5 海藻バイオマスによるエネルギー自給の可能性
1.6 各種発酵エネルギー変換法とのエネルギー変換効率比較
1.7 結言
2 光合成微生物(藻類・光合成細菌)による光水素生産
2.1 緒言
2.2 光合成微生物による光水素生産技術の適用分野
2.2.1 CO2有効利用技術としての適用
2.2.2 廃水処理・廃熱回収への適用
2.2.3 副生産物生産への適用
2.2.4 再生可能エネルギーに関する法対応としての適用
2.3 光合成微生物による光水素生産のメカニズム
2.3.1 光合成微生物による光水素生産の原理
2.3.2 光合成微生物による光水素生産の酵素
2.4 光合成微生物による光水素生産のプロセス及びシステム
2.4.1 気体燃料
2.4.2 固体燃料
2.4.3 液体燃料
2.4.4 フォトバイオリアクター
2.4.5 密閉型フォトバイオリアクター
2.4.6 開放型フォトバイオリアクター
2.5 IEA-HIA Annex 21 Extendedの活動
2.5.1 Abiological Systems
2.5.2 Dark BioHydrogen Systems
2.5.3 Photo BioHydrogen Systems
2.5.4 Bio-Inspired Fuel Cells
2.5.5 Over All Analysis
2.6 結言 -

ビタミンの科学と最新応用技術(普及版)
¥4,840
2011年刊「ビタミンの科学と最新応用技術」の普及版!新しいビタミンの機能、誘導体の開発動向、疾病とビタミンの関連など、注目されるテーマを第一線で活躍する研究者27名が執筆!!
(監修:糸川嘉則)
<!--<a href="http://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=5354"target=”_blank”>この本の紙版「ビタミンの科学と最新応用技術(普及版)」の販売ページはこちら(別サイトが開きます)</a> -->
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は、2011年当時のものを使用しております。
早川享志 岐阜大学
糸川嘉則 仁愛大学
渡邊敏明 兵庫県立大学
澤村弘美 兵庫県立大学
渡辺恭良 (独)理化学研究所
犬塚 學 仁愛大学
榎原周平 兵庫県立大学
翠川 裕 鈴鹿医療科学大学
柴田克己 滋賀県立大学
森脇久隆 岐阜大学
中西憲幸 HMN赤坂クリニック
石神昭人 東京都健康長寿医療センター研究所
久保寺登 活性型ビタミンD誘導体研究所
阿部皓一 エーザイ(株)エーザイジャパン
中川公恵 神戸薬科大学
青山勝彦 オルト(株)
木村忠明 (株)ヘルスビジネスマガジン社
渭原 博 東邦大学
橋詰直孝 和洋女子大学
鳴瀨 碧 仁愛大学
平池秀和 帝京短期大学
西野輔翼 立命館大学
瀧谷公隆 大阪医科大学
玉井 浩 大阪医科大学
池田涼子 仁愛大学
浦野四郎 芝浦工業大学
高津博勝 Industrial University of Selangor
-------------------------------------------------------------------------
<<目次>>
第1章 ビタミンの基礎知識
1 ビタミン発見の歴史
1.1 はじめに
1.2 東洋における脚気の蔓延とビタミンB1の発見
1.3 西洋におけるペラグラの蔓延とナイアシンの発見
1.4 ビタミンCの発見とビタミンのA,B,C
1.5 その他のB群ビタミンの発見
1.6 脂溶性ビタミンの発見
1.7 脚気とビタミンの発見
2 ビタミンの定義と必要量・摂取量
2.1 ビタミンの定義
2.2 ビタミンの必要量
2.3 ビタミンの摂取量
3 ビタミン様作用物質
3.1 ユビキノン
3.2 リポ酸
3.3 コリン
3.4 イノシトール
3.5 カルニチン
3.6 オロト酸
3.7 p-アミノ安息香酸
3.8 ビタミンP
3.9 ビタミンU
3.10 ピロロキノリンキノン
3.11 パンガミン酸
3.12 ビオプテリン
第2章 新しいビタミンの機能
1 ビタミンと疲労
1.1 疲労とは? 疲労の研究進展と解明されてきたメカニズム概説
1.2 疲労の計測とバイオマーカー
1.3 疲労動物モデルを用いた研究
1.4 抗疲労食品素材の開発
1.5 ビタミンと疲労
1.6 まとめ
2 遺伝子に働く脂溶性ビタミン:先天性代謝異常症の遺伝子診断への応用
2.1 はじめに
2.2 ビタミンDの働きとしくみ
2.3 活性型ビタミンD3の先天性代謝異常症の遺伝子診断への応用
2.3.1 フルクトース 1,6-ビスフォスファターゼ(FBPase)欠損症(OMIN #229700)
2.3.2 活性型ビタミンD3によるフルクトース 1,6-ビスフォスファターゼ(FBPase)遺伝子の発現誘導
2.3.3 FBPase欠損症の遺伝子診断法の確立と臨床応用
2.3.4 脂溶性ビタミンによるヒトFBPase 遺伝子の転写誘導メカニズムの解明
2.4 おわりに
3 葉酸の機能
3.1 はじめに
3.2 葉酸の吸収,輸送,排泄
3.3 葉酸の生化学的機能
3.4 葉酸の生理機能と欠乏症
3.5 葉酸の分析法
4 ビタミンC(アスコルビン酸)による食中毒原因菌検出への応用
4.1 はじめに
4.2 アスコルビン酸の抗菌活性
4.3 アスコルビン酸のサルモネラ硫化水素産生に及ぼす影響
4.3.1 通常のサルモネラ分離
4.3.2 MY現象および,ミドリングの発見
4.3.3 MY現象におけるサルモネラの特異性
4.3.4 ラオスにおけるアスコルビン酸を用いたサルモネラの検出調査
4.3.5 ラオス市場における食品衛生の現状
4.4 まとめ
第3章 食品とビタミン
1 食品中のビタミンの形態とヒトにおける消化・吸収・貯蔵ならびに食品中のビタミン測定方法
1.1 脂溶性ビタミン
1.1.1 ビタミンA
1.1.2 ビタミンD
1.1.3 ビタミンE
1.1.4 ビタミンK
1.2 水溶性ビタミン(B群ビタミン)
1.2.1 ビタミンB1
1.2.2 ビタミンB2
1.2.3 ビタミンB6
1.2.4 ビタミンB12
1.2.5 ナイアシン
1.2.6 パントテン酸
1.2.7 葉酸
1.2.8 ビオチン
1.3 水溶性ビタミン(ビタミンC)
2 食品の貯蔵・加工・調理過程におけるビタミンの損失
2.1 脂溶性ビタミン
2.1.1 ビタミンA
2.1.2 ビタミンD
2.1.3 ビタミンE
2.1.4 ビタミンK
2.2 水溶性ビタミン(B群ビタミン)
2.2.1 ビタミンB1
2.2.2 ビタミンB2
2.2.3 ビタミンB6
2.2.4 ビタミンB12
2.2.5 ナイアシン
2.2.6 パントテン酸
2.2.7 葉酸
2.2.8 ビオチン
2.3 水溶性ビタミン(ビタミンC)
3 ビタミンの良好な供給源
3.1 脂溶性ビタミン
3.1.1 ビタミンA
3.1.2 ビタミンD
3.1.3 ビタミンE
3.1.4 ビタミンK
3.2 水溶性ビタミン(B群ビタミン)
3.2.1 ビタミンB1
3.2.2 ビタミンB2
3.2.3 ビタミンB6
3.2.4 ビタミンB12
3.2.5 ナイアシン
3.2.6 パントテン酸
3.2.7 葉酸
3.2.8 ビオチン
3.3 水溶性ビタミン(ビタミンC)
4 食事中のビタミンの生体利用率
4.1 脂溶性ビタミン
4.1.1 ビタミンA
4.1.2 ビタミンD
4.1.3 ビタミンE
4.1.4 ビタミンK
4.2 水溶性ビタミン(B群ビタミン)
4.3 水溶性ビタミン(ビタミンC)
第4章 薬剤・サプリメントとビタミン
1 ビタミンA誘導体の開発
1.1 はじめに
1.2 ビタミンA誘導体開発の歴史
1.3 実地臨床におけるビタミンA誘導体の効果
1.4 ポリエン骨格を持つレチノイド
1.5 芳香族レチノイド
1.6 レキシノイド
1.7 アンタゴニスト
1.8 おわりに
2 ビタミンB12誘導体の開発
2.1 はじめに
2.2 生体内に存在する4種類のビタミンB12
2.3 4種類のビタミンB12の開発と臨床応用
2.4 メチルB12の開発とメチル水銀問題
2.5 メチルB12は末梢性神経障害治療剤
2.6 メチルB12の臨床応用
2.6.1 乏精子症の精子数を改善
2.6.2 睡眠覚醒リズム障害のリズムを同調
2.6.3 認知症の知的機能を改善
2.7 最近のトピックス
2.7.1 ALSに対するメチルB12の研究
2.7.2 動脈硬化のリスクファクター―ホモシステイン―
2.8 おわりに
3 ビタミンC誘導体の開発
3.1 ビタミンCの化学構造
3.2 ビタミンCの立体異性体,エリソルビン酸
3.3 水溶液中でのビタミンCの解離
3.4 ビタミンCの還元力
3.5 ビタミンCの再生
3.6 ビタミンC誘導体
3.7 ビタミンC誘導体の皮膚への浸透性
3.8 ビタミンC誘導体のコラーゲン遺伝子発現促進効果
3.9 食品添加物としてのビタミンCおよびビタミンC誘導体
3.10 今後のビタミンC誘導体の開発
4 ビタミンD誘導体の開発
4.1 はじめに
4.2 第一の節目におけるビタミンDの生理的意義の発見
4.3 第二の節目における活性型ビタミンDの発見と臨床応用
4.4 第三の節目における活性型ビタミンD誘導体の創薬研究
4.5 おわりに
5 ビタミンE誘導体の開発
5.1 ビタミンEの概要
5.2 ビタミンE誘導体の種類
5.3 ビタミンE誘導体の生物活性・国際単位
5.4 ビタミンE誘導体の物性
5.5 ビタミンE誘導体の吸収
5.6 注目される誘導体
5.6.1 コハク酸エステル
5.6.2 リン酸エステル
5.6.3 ジメチルグリシン誘導体
5.6.4 モノグルコシド
5.6.5 その他の誘導体
5.7 おわりに
6 ビタミンK2誘導体の開発
6.1 はじめに
6.2 ビタミンKの化学構造
6.3 ビタミンKの体内分布
6.4 ビタミンKサイクル
6.5 ビタミンKの生理作用
6.5.1 血液凝固に対する作用
6.5.2 血管石灰化に対する作用
6.5.3 骨に対する作用
6.6 メナキノン-4の生合成
6.7 メナキノン-4生合成の生物学的意義
6.8 ビタミンK製剤・ビタミンKサプリメント・保健機能食品
6.9 おわりに
7 マーケティングとビタミン
7.1 ビタミンサプリメントの黎明
7.1.1 マーケティングとビタミンという表題
7.1.2 ビタミンサプリメントとは何か
7.1.3 ビタミンサプリメント―わが国では
7.1.4 ビタミンサプリメントの黎明―渡辺正雄らの功績を中心に
7.1.5 サプリメントが何故必要とされるのか
7.1.6 ノーベル賞受賞者,ポーリング博士のVC大量投与
7.1.7 ウィリアムズ教授の「完全栄養」
7.1.8 ウィリアムズ博士の「保健量」
7.1.9 渡辺正雄とビタミンB群サプリメントの開発
7.2 サプリメントマーケットの展開と未来
7.2.1 再び伸びに転じた健康食品市場
7.2.2 通販の伸びが市場の伸び支える
7.2.3 ベーシックなビタミンサプリ
7.2.4 ビタミンサプリが市場形成された理由
7.2.5 日米の産業形成にも大きな影響
7.2.6 "栄養補助食品"の登場
7.2.7 ビタミンEに製粉企業など大手が参入
7.2.8 西武のバイタミンショップ
7.2.9 健康食品の規格基準づくり
7.2.10 アメリカで制度化の動き
7.2.11 日本で機能性食品からトクホへ
7.2.12 抗酸化・抗炎症機能の時代へ
7.2.13 栄養補助食品企業に新たな時代が
7.2.14 テレビ発の健康食品ブームとドラッグストア
7.2.15 ネットワークビジネスが拡大
7.2.16 通販の価格破壊と健康食品の大衆化
7.2.17 栄養補助食品にも効果表示が
7.2.18 医療への健康食品の利用へ
7.2.19 注目されるビタミンの効果
7.2.20 2030年には6000億円市場にも
第5章 ビタミンの検査・栄養状態の判定
1 はじめに
2 ビタミンB1
2.1 血液の検査
2.2 血清の検査
2.3 尿の検査
2.4 関連する検査
3 ビタミンB2
3.1 血液の検査
3.2 血清の検査
3.3 尿の検査
3.4 関連する検査
4 ビタミンB6
4.1 血液の検査
4.2 血清の検査
4.3 尿の検査
4.4 関連する検査
5 ビタミンB12
5.1 血液の検査
5.2 血清の検査
5.3 尿の検査
5.4 関連する検査
6 葉酸
6.1 血液の検査
6.2 血清の検査
6.3 尿の検査
6.4 関連する検査
7 ナイアシン
7.1 血液の検査
7.2 血清の検査
7.3 尿の検査
7.4 関連する検査
8 パントテン酸
8.1 血液の検査
8.2 血清の検査
8.3 尿の検査
9 ビオチン
9.1 血液の検査
9.2 血清の検査
9.3 尿の検査
9.4 関連する検査
10 ビタミンC
10.1 血液の検査
10.2 血清の検査
10.3 尿の検査
11 ビタミンA
11.1 血液の検査
11.2 血清の検査
11.3 尿の検査
11.4 関連する検査
12 ビタミンD
12.1 血液の検査
12.2 血清の検査
12.3 尿の検査
12.4 関連する検査
13 ビタミンE
13.1 血液の検査
13.2 血清の検査
13.3 尿の検査
13.4 関連する検査
14 ビタミンK
14.1 血液の検査
14.2 血清の検査
14.3 尿の検査
14.4 関連する検査
第6章 疾患とビタミン
1 ビタミン欠乏症
1.1 ビタミン欠乏症とは
1.2 ビタミン欠乏症
1.2.1 水溶性ビタミン欠乏症
1.2.2 脂溶性ビタミン欠乏症
2 ビタミン過剰症
2.1 はじめに
2.2 脂溶性ビタミン
2.2.1 ビタミンA
2.2.2 ビタミンD
2.2.3 ビタミンE
2.2.4 ビタミンK
2.3 水溶性ビタミン
2.3.1 ビタミンB1
2.3.2 ビタミンB2
2.3.3 ナイアシン
2.3.4 パントテン酸
2.3.5 ビタミンB6
2.3.6 葉酸
2.3.7 ビタミンB12
2.3.8 ビオチン
2.3.9 ビタミンC
3 癌とビタミン
3.1 はじめに
3.2 ビタミンA,レチノイド,カロテノイド
3.3 ビタミンD
3.4 ビタミンE
3.5 ビタミンK
3.6 ビタミンC
3.7 ビタミンB2
3.8 ビタミンB6
3.9 ビタミンB12
3.10 葉酸
3.11 ナイアシン
3.12 ビタミン様物質
3.13 おわりに
4 循環器疾患とビタミン
4.1 ビタミンAと循環器疾患
4.1.1 ビタミンAの機能・代謝
4.1.2 ビタミンAと先天性心疾患
4.2 ビタミンB群および葉酸と循環器疾患
4.2.1 ビタミンB群,葉酸とホモシステイン
4.2.2 ホモシステインと循環器疾患
4.3 ビタミンEと循環器疾患
4.3.1 ビタミンEの機能・代謝
4.3.2 ビタミンEと循環器疾患の発症予防
4.4 ビタミンKと循環器疾患
4.4.1 ビタミンKの機能・代謝
4.4.2 ビタミンKと循環器疾患
5 ビタミンAと糖尿病―インスリン抵抗性と脂肪細胞分化抑制―
5.1 背景
5.2 RBPのインスリン抵抗性促進作用
5.3 ビタミンAによるエネルギー代謝調節
6 老化とビタミン
6.1 はじめに
6.2 老化の要因を説明する学説
6.3 老化をもたらす生体の酸化損傷とビタミンEによる防御
6.4 老化と酸化ストレスによる認識機能障害とビタミンEによる防御
6.5 老化にともなう認識機能低下をビタミンで改善させる研究状況
6.5.1 食物摂取による認識機能改善
6.5.2 脂溶性ビタミンによる認識機能改善
6.5.3 水溶性ビタミンによる認識機能改善
6.6 おわりに -

ナノカーボンの応用と実用化―フラーレン,ナノチューブ,グラフェンを中心に―(普及版)
¥6,600
2011年刊「ナノカーボンの応用と実用化」の普及版!急速に研究開発が進むナノカーボン材料の応用と実用化、ナノカーボン材料の安全性、標準化について国内の一流研究者が執筆!!
(監修:篠原久典)
<a href="https://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=5318"target=”_blank”>この本の紙版「ナノカーボンの応用と実用化―フラーレン,ナノチューブ,グラフェンを中心に―(普及版)」の販売ページを見る(別サイトへ移動)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は、2011年当時のものを使用しております。
篠原久典 名古屋大学
有川峯幸 フロンティアカーボン(株)
瀧本裕治 東洋炭素(株)
井上 崇 東洋炭素(株)
岡田洋史 東北大学
笠間泰彦 イデア・インターナショナル(株)
三宅邦仁 住友化学(株)
増野匡彦 慶應義塾大学
乾 重樹 大阪大学
山名修一 ビタミンC60バイオリサーチ(株)
北口順治 三菱商事(株)
橋本 剛 (株)名城ナノカーボン
佐藤謙一 東レ(株)
角田裕三 (有)スミタ化学技術研究所
宮田耕充 名古屋大学
浅利琢磨 パナソニック(株)
林 卓哉 信州大学
岩井大介 (株)富士通研究所
秋庭英治 クラレリビング(株)
長谷川雅考 (独)産業技術総合研究所
永瀬雅夫 徳島大学
塚越一仁 (独)物質・材料研究機構
宮崎久生 (独)物質・材料研究機構
小高隼介 (独)物質・材料研究機構
村上睦明 (株)カネカ
後藤拓也 三菱ガス化学(株)
小林俊之 ソニー(株)
日浦英文 日本電気(株)(NEC)
Michael V.Lee (独)物質・材料研究機構
大淵真理 (株)富士通研究所
白石誠司 大阪大学
阿多誠文 (独)産業技術総合研究所
永井裕祟 名古屋大学
豊國伸哉 名古屋大学
市原 学 名古屋大学
栁下皓男 JFEテクノリサーチ(株)
大塚研一 JFEテクノリサーチ(株)
-------------------------------------------------------------------------
<<目次>>
第1章 ナノカーボン研究の展開と実用化に向けて
1 ナノカーボン研究のはじまりと展開
2 ナノカーボンは応用されなくては
3 グラフェンは,どうか?
4 ナノカーボンを安全に実用化するために
第2章 フラーレン
1 工業生産と応用展開
1.1 フラーレンの製品種類
1.2 フラーレンの工業生産
1.2.1 フラーレン工業生産の概要
1.2.2 製造プロセス設計の観点から活用されるフラーレン特性
1.2.3 最近の製造技術トピックス
1.3 フラーレンの応用展開
1.3.1 フラーレン応用展開概要
1.3.2 有機薄膜太陽電池への応用
1.3.3 半導体プロセス材料への応用
1.3.4 CFRP等の複合材料や樹脂への添加剤応用
1.3.5 炭素ソースとしての応用
2 ナノカーボン原料・材料
2.1 はじめに
2.2 フラーレン、カーボンナノチューブの基礎
2.2.1 フラーレン
2.2.2 カーボンナノチューブ
2.3 アーク放電法によるナノカーボン製造用の原料
2.3.1 金属内包フラーレン合成用のロッド
2.3.2 単層カーボンナノチューブ合成用のロッド
2.4 ナノカーボンの分離・精製
2.4.1 金属内包フラーレンの分離・精製
2.4.2 単層カーボンナノチューブの純化
2.5 ナノカーボンの新しい合成方法とその原料
2.6 おわりに
3 C60内包フラーレン:生成と分離
3.1 はじめに
3.1.1 金属内包C60フラーレン研究の発端
3.1.2 金属内包C60フラーレンの抽出精製
3.1.3 アルカリ金属内包C60フラーレン
3.1.4 後期遷移金属内包C60
3.2 非金属原子内包C60フラーレン
3.2.1 水素内包C60フラーレン
3.2.2 希ガス内包C60フラーレン
3.2.3 窒素内包C60フラーレン
3.3 おわりに
4 有機薄膜太陽電池
4.1 有機薄膜太陽電池の開発動向
4.1.1 歴史
4.1.2 有機薄膜太陽電池とは
4.1.3 有機薄膜太陽電池の現状と課題
4.1.4 p型共役系高分子およびn型フラーレンの開発例
4.2 当社の有機薄膜太陽電池開発状況
4.2.1 OPV開発の背景
4.2.2 開発状況
4.3 今後の展開
5 金属内包フラーレンの造影剤応用
5.1 はじめに
5.2 MRI造影剤とGd金属内包フラーレン
5.3 Gd内包フラーレンの合成と分離
5.4 Gd@C82(OH)40の合成とMRI造影能
5.5 ケージ構造の強化を狙った新規フラレノールの合成
5.6 発展を続ける金属内包フラーレンの造影剤への応用研究
5.7 おわりに
6 フラーレンの抗炎症効果
6.1 はじめに
6.2 フラーレン及びその誘導体の化学的性質と生理活性
6.2.1 光依存活性酸素生成に基づく生理活性
6.2.2 金属内包フラーレンの応用
6.2.3 酸化還元を受けやすく、またラジカルとの反応性が高いことに基づく生理活性
6.2.4 高い疎水性に基づく生理活性
6.2.5 抗菌活性
6.3 展望
7 フラーレンの臨床試験
7.1 はじめに
7.2 臨床試験:フラーレンの尋常性ざ瘡(ニキビ)に対する効果
7.2.1 臨床試験
7.3 フラーレンの毛成長に対する効果
7.4 展望
8 化粧品
8.1 今やスキンケア化粧品成分の定番
8.2 女性が化粧品に求めている機能は何と言っても美白
8.3 美白用の高機能化粧品には抗酸化成分が欠かせない
8.4 フリーラジカル・活性酸素がメラニン産生細胞を活性化する
8.5 抗酸化成分フラーレンの製品化への障壁
8.6 フラーレン配合成分Radical Sponge(R)の登場
8.7 フラーレンの化粧品成分としての有効性
8.7.1 フリーラジカル・活性酸素消去効果
8.7.2 フラーレンの優れた抗酸化性能
8.7.3 メラニン顆粒産生抑制効果
8.7.4 臨床試験による美白効果の証明
8.8 シワにも効く。ガイドライン準拠の臨床試験で確認
8.9 安全性に関する整備された情報
8.10 まとめ
9 フラーレンのビジネス展開
9.1 三菱商事のフラーレンビジネスの歴史
9.2 三菱商事の戦略
9.2.1 ビジネスモデル
9.2.2 ビジネス戦略と戦術
9.3 ビジネス
9.3.1 産業用展開
9.3.2 ライフサイエンス用展開
9.4 まとめ
第3章 カーボンナノチューブ
1 カーボンナノチューブの合成・販売
1.1 CNTの種類
1.2 CNTの合成法
1.3 CNTの販売
1.3.1 SWNT
1.3.2 MWNT
1.3.3 CNT分散液
1.3.4 金属型・半導体型SWNT
1.3.5 CNTコートディッシュ
1.3.6 まとめ
2 CNT透明導電フィルム
2.1 はじめに
2.2 ITOフィルムについて
2.3 CNT利用透明導電フィルム開発のモチベーション
2.4 CNTを用いた透明導電フィルム開発に必要な技術
2.5 高品質なCNTおよびその製造技術について
2.6 CNT分散化技術
2.7 ドーピング方法
2.8 CNT分散液塗工方法
2.9 今後の展開と期待
3 CNT透明導電塗料
3.1 はじめに
3.2 CNT透明導電塗料の調製と評価
3.2.1 CNTの選択
3.2.2 CNT分散液の調製
3.2.3 バインダー/モノマーの配合(塗料化)
3.2.4 製膜
3.2.5 塗膜特性の評価
3.2.6 他の塗布型透明導電塗料との比較
3.3 おわりに
4 電子デバイス(薄膜トランジスタ)
4.1 はじめに
4.2 ナノチューブ試料の特徴
4.3 ナノチューブの分散・分離法
4.4 ナノチューブの製膜法
4.5 トランジスタ特性
4.6 おわりに
5 キャパシタ
5.1 キャパシタとは
5.2 カーボンナノチューブ(CNT)を電極に使用したキャパシタ
5.2.1 CNT粉末を塗工もしくは成形して電極にした構造
5.2.2 垂直配向CNTを転写して電極にした構造
5.2.3 垂直配向CNTを根元接続して電極にした構造
5.3 今後の課題
6 リチウムイオン二次電池
6.1 はじめに
6.2 カーボンナノチューブのリチウムイオン二次電池への利用
6.3 カーボンナノチューブのその他の蓄電池への応用
6.4 おわりに
7 放熱・配線応用
7.1 はじめに
7.2 カーボンナノチューブの配向合成技術
7.3 放熱応用
7.3.1 背景としての移動体通信基地局向け高出力増幅器の現状
7.3.2 CNT放熱バンプを用いた基地局向けフリップリップ高出力増幅器のコンセプト
7.3.3 CNTバンプ形成プロセスおよび増幅器アセンブリプロセス
7.3.4 CNT放熱バンプを用いたフリップチップ高出力増幅器の特性
7.4 おわりに
8 カーボンナノチューブのコーティングによる導電繊維「CNTEC」
8.1 はじめに
8.2 CNT分散液
8.3 CNTコーティング導電繊維
8.4 導電繊維「CNTEC」応用製品
8.4.1 ファブリックヒーター
8.4.2 複写機ブラシ
8.4.3 その他
8.5 安全性
8.6 おわりに
第4章 グラフェン
1 大面積低温合成
2 SiC上のグラフェン成長
2.1 SiC上グラフェンの特徴
2.2 SiC上グラフェンの成長機構
2.3 SiC上グラフェンの評価技術
2.3.1 層数同定技術
2.3.2 膜質評価技術
2.3.3 局所電子物性評価
2.4 今後の課題
3 電子デバイス"SiC上グラフェンでの電界効果素子の試作と評価"
3.1 グラフェン基板
3.2 表面構造依存伝導の検出用グラフェン電界効果素子
3.2.1 SiC基板上のグラフェンの詳細
3.2.2 作製プロセス
3.2.3 電気伝導の測定
3.2.4 等価回路モデルによる伝導異方性の解析
3.2.5 伝導の考察
3.3 まとめ
4 グラファイト系炭素の合成と物性
4.1 はじめに
4.2 グラフェンとグラファイト
4.3 高分子から作製する高品質グラファイト
4.4 高品質グラファイトシート(Graphinity)とその応用
4.5 グラファイトブロック(GB)とその応用
4.6 おわりに
5 酸化グラフェン
5.1 はじめに
5.2 酸化グラフェンの合成
5.3 酸化グラフェンの構造と特徴
5.4 酸化グラフェンの還元
5.5 酸化グラフェンの応用
5.5.1 透明導電性塗布膜
5.5.2 高強度複合体
5.6 おわりに
6 透明導電性フィルム
6.1 はじめに
6.2 グラフェン透明導電膜の成膜方法
6.2.1 化学気相成長法による成膜
6.2.2 分散液からの成膜
6.3 グラフェンの光学特性
6.4 グラフェンの電気伝導特性
6.5 グラフェン透明導電膜の特長
6.6 おわりに
7 絶縁体上へのグラフェンの直接形成
7.1 はじめに
7.2 新規グラフェン成長技術:液相グラフェン成長法の原理
7.3 液相グラフェン成長法の実験方法
7.4 絶縁体上グラフェンの観察と評価
7.4.1 SiC基板上の液相グラフェン成長
7.4.2 液相法によるグラフェンの成長条件
7.4.3 様々な炭素源からグラフェン成長
7.4.4 様々な絶縁体基板上でのグラフェン成長
7.5 液相グラフェン成長法の特長とその応用可能性
7.6 まとめ
8 LSI配線技術
8.1 はじめに
8.2 Cu配線置き換えの可能性
8.3 多層グラフェン合成技術
8.3.1 SiC基板の熱分解による合成
8.3.2 触媒金属を用いた熱CVD法による合成
8.3.3 触媒金属を用いないプラズマCVD法による合成
8.4 おわりに
9 スピンデバイス
第5章 ナノカーボン材料の安全性
1 ナノカーボンの社会受容:総論
1.1 はじめに
1.2 日本のナノテクノロジーの背景
1.3 ナノテクノロジーと科学的不確実性
1.4 ナノテクノロジー研究開発の現状
1.5 ナノEHSに関する取り組み
1.6 今後の課題と展開
1.7 PENが担う社会との双方向コミュニケーション
1.8 おわりに
2 ナノカーボンの細胞毒性・発癌性
2.1 ナノカーボンの種類とその安全性について
2.2 アスベスト問題とその発癌メカニズム
2.3 カーボンナノチューブの毒性評価の難しさについて
2.4 カーボンナノチューブの細胞毒性について:マクロファージを中心に
2.5 カーボンナノチューブの細胞毒性について:上皮細胞/中皮細胞を中心に
2.6 おわりに
3 生体影響評価
3.1 はじめに
3.2 フラーレンの安全性評価
3.3 カーボンナノチューブの安全性評価
3.3.1 繊維形状に基づく生体影響の可能性
3.3.2 繊維形状と体内動態との関係
3.3.3 生体影響を決めるより広範な要因
3.3.4 Golden Standardとしての吸入曝露実験によるハザード評価
3.3.5 代替法としての気管内投与法,咽頭吸引法,鼻腔投与法
3.3.6 カーボンナノチューブの多様性と安全性評価
3.4 おわりに
4 工業標準化と国際的な動向
4.1 はじめに
4.2 ナノテクノロジー国際標準化協議を英国が提唱
4.3 TC229の体制と業務範囲
4.4 日本におけるナノテクノロジー国際標準化の取組み
4.5 TC229におけるナノカーボン関連審議の状況
4.5.1 JWG1[用語・命名法]
4.5.2 JWG2〔計量・計測〕
4.5.3 WG3[健康安全環境]
4.5.4 WG4[材料規格]
4.6 おわりに
5 安全管理
5.1 はじめに
5.2 ナノカーボンの有害性
5.3 ナノカーボンの暴露可能性
5.4 ナノカーボンの安全管理
5.5 おわりに -

自動車用プラスチック新材料の開発と展望 (普及版)
¥4,950
2011年刊「自動車用プラスチック新材料の開発と展望」の普及版!自動車の軽量化において、高品質を誇る日本の自動車部品・材料のプラスチック化の話題とパーツごとの独自の進化を解説!!
(編集:シーエムシー出版 編集部)
<a href="https://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=5235"target=”_blank”>この本の紙版「自動車用プラスチック新材料の開発と展望 (普及版)」の販売ページを見る(別サイトへ移動)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は、2011年当時のものを使用しております。
倉内紀雄 倉内技術経営ラボ
箱谷昌宏 ジャパンコンポジット(株)
岡本正巳 豊田工業大学
北野彰彦 東レ(株)
藤田祐二 三菱化学(株)
新井雅之 日本ポリプロ(株)
菅原 誠 SABICイノベーティブプラスチックスジャパン合同会社
伊東禎治 ダイセル・エボニック(株)
帆高寿昌 帝人化成(株)
柳井康一 日本ゼオン(株)
常岡和記 三菱自動車工業(株)
寺澤 勇 三菱自動車工業(株)
白石信夫 (株)白石バイオマス
松坂康弘 三井化学(株)
太田 実 フドー(株)
小山剛司 フドー(株)
井上 隆 山形大学
堺 大 クオドラント・プラスチック・コンポジット・ジャパン(株)
金澤 聡 日本ポリエチレン(株)
林七歩才 (株)クラレ
藤田容史 ポリプラスチックス(株)
吉村信宏 東洋紡績(株) 総合研究所
澤田克己 ダイセル・エボニック(株)
出口浩則 出光興産(株) 機能材料部
岡田明彦 出光興産(株) 機能材料部
広野正樹 三菱エンジニアリングプラスチックス(株)
芹澤 肇 ポリプラスチックス(株)
加藤清雄 旭化成ケミカルズ(株)
松田孝昭 旭化成ケミカルズ(株)
-------------------------------------------------------------------------
<<目次>>
第1章 自動車樹脂部品の動向と将来展望
1 自動車樹脂化の流れ
2 次世代自動車の動向
3 次世代自動車と高分子材料
4 新素材・新技術の例
4.1 次世代自動車を支える軽元素
4.2 重要なナノテクノロジーの例
5 まとめ
第2章 ボディー
1 外装・外板
1.1 低密度クラスA-SMC
1.1.1 はじめに
1.1.2 低密度クラスA-SMCの開発動向
1.1.3 低密度クラスA-SMCによる軽量化効果
1.1.4 低密度クラスA-SMCの適用例
1.1.5 おわりに
1.2 ナノコンポジット材料
1.2.1 はじめに
1.2.2 ナノコンポジットの種類とナノフィラー
1.2.3 用途分野
1.2.4 新規な3次元ナノ多孔体
1.2.5 展望
1.3 炭素繊維複合材料の自動車ボディへの適用
1.3.1 はじめに
1.3.2 海外の適用状況
1.3.3 国内の適用状況
1.3.4 まとめと今後の展望
1.4 バンパー材としてのPPの技術開発
1.4.1 はじめに
1.4.2 PPの特徴
1.4.3 PPバンパーの歴史
1.4.4 PPバンパー材開発のための要素技術
1.4.5 おわりに
1.5 フェンダー用樹脂材料の開発―Noryl GTX樹脂―
1.5.1 はじめに
1.5.2 フェンダーの樹脂化とメリット
1.5.3 フェンダー用樹脂材料と要求性能
1.5.4 Noryl GTX 樹脂と特徴
1.5.5 フェンダー樹脂化の課題と対応
1.5.6 樹脂フェンダーの今後
1.5.7 おわりに
1.6 ポリメタクリルイミド(PMI)硬質発泡材 ロハセルの自動車への展開
1.6.1 はじめに
1.6.2 ロハセルとは
1.6.3 ロハセルの特長
1.6.4 サンドイッチ構造におけるロハセル
1.6.5 ロハセルの加工方法
1.6.6 ロハセルの性能vsコスト
1.6.7 ロハセルの自動車向け用途例
1.6.8 おわりに
2 窓
2.1 ポリカーボネート樹脂製の自動車窓
2.1.1 樹脂グレージングを支える新素材技術
2.1.2 樹脂グレージングを支える新加工技術
2.1.3 実用化技術例(J-X3αテクノロジーによる窓とボディの一体化成形技術)
2.1.4 今後の展望
3 内装
3.1 インストルメントパネル表皮用パウダースラッシュ材料
3.1.1 はじめに
3.1.2 インストルメントパネルの基本構造
3.1.3 インストルメントパネル表皮の成形方法
3.1.4 パウダースラッシュ材料
3.1.5 おわりに
3.2 液状化木材フェノール樹脂成形品
3.2.1 液状化木材フェノール樹脂の概要
3.2.2 成形材料の製造工程
3.2.3 自動車用カップ型灰皿の要求性能
3.2.4 成形材料の性能
3.2.5 今後の課題
3.2.6 まとめ
3.3 植物由来ポリウレタン
3.3.1 はじめに
3.3.2 植物素材の選定
3.3.3 植物由来ポリウレタン
3.3.4 まとめ
3.4 バイオマスフェノールコンパウンド
3.4.1 はじめに
3.4.2 バイオマスフェノール樹脂
3.4.3 バイオマスフェノールコンパウンド
3.4.4 今後の展開
4 構造部品
4.1 耐衝撃性・耐熱老化性PLAアロイ
4.1.1 はじめに
4.1.2 PLAのゴム補強
4.1.3 結晶性プラスチックとのアロイ化による靭性向上
4.1.4 耐衝撃性・耐熱老化性PLAアロイ
4.1.5 靭性発現機構
5 アンダーボデーシールド
5.1 GMTコンポジット材料の展開
5.1.1 はじめに
5.1.2 GMTの特徴と用途事例
5.1.3 GMTex?の特徴と用途事例
5.1.4 SymaLITE?とその用途事例
5.1.5 アンダーボデーシールド材としてのGMT
5.1.6 一般乗用系車種のアンダーボデーシールドに求められるニーズ
5.1.7 これからの自動車設計において
第3章 燃料システム
1 燃料タンク
1.1 HDPE樹脂
1.1.1 ポリエチレン燃料タンク
1.1.2 ポリエチレン燃料タンクのメリット
1.1.3 ポリエチレン燃料タンクの多層化
1.1.4 多層ポリエチレン燃料タンクの層構成と使用材料
1.1.5 多層ポリエチレン燃料タンク用材料
1.1.6 溶着部品用材料
1.1.7 アドブルー(尿素水)タンク用材料
1.1.8 今後の展望
1.2 EVOH系燃料タンクとバイオ燃料への対応
1.2.1 はじめに
1.2.2 EVOH樹脂
1.2.3 EVOH系燃料タンク
1.2.4 おわりに
2 燃料系部品
2.1 POM樹脂(フューエルポンプモジュール)
2.1.1 はじめに
2.1.2 燃料系部品の校正
2.1.3 燃料系部品における樹脂材料
2.1.4 フューエルポンプモジュール
2.1.5 バイオ燃料への対応
2.1.6 おわりに
第4章 機構部品
1 エンジン系部品
1.1 ポリアミド樹脂
1.1.1 はじめに
1.1.2 自動車部品に採用されている樹脂とポリアミド樹脂の位置づけ
1.1.3 具体的な開発例
1.1.4 おわりに
2 駆動系部品
2.1 PEEK樹脂
2.1.1 はじめに
2.1.2 PEEKの歴史,需給動向
2.1.3 ベスタキープの商品群と主な特長
2.1.4 各産業分野におけるベスタキープ(自動車分野以外)
2.1.5 自動車分野
2.1.6 各種加工法におけるベスタキープ
2.1.7 べスタキープの技術開発動向について
2.1.8 おわりに
2.2 炭素繊維複合材料のプロペラシャフトへの適用
2.2.1 国内の適用状況
2.2.2 CFRP製プロペラシャフトの特長
第5章 電装部品・ランプ
1 電装部品
1.1 SPS樹脂のHV車への応用
1.1.1 はじめに
1.1.2 SPSとは
1.1.3 SPSの特徴
1.1.4 HV車分野への応用展開
1.1.5 おわりに
1.2 ジアリルフタレート樹脂成形材料
1.2.1 ジアリルフタレート樹脂とは
1.2.2 プレポリマーの製造と特徴
1.2.3 ジアリルフタレート樹脂成形材料(ダポール)の特徴と用途
2 ランプ
2.1 ヘッドランプレンズ(PC樹脂)
2.1.1 ポリカーボネート樹脂(PC)製ヘッドランプの特徴とPC化のメリット
2.1.2 ヘッドランプに要求される性能
2.1.3 ハードコート技術と塗膜性能
2.1.4 ヘッドランプグレード「ユーピロンMLシリーズ」
2.1.5 ヘッドランプ周辺技術
2.1.6 今後の材料系の課題
2.2 COC樹脂
2.2.1 はじめに
2.2.2 COCの特長
2.2.3 期待される用途
2.2.4 まとめ
第6章 タイヤ―省燃費タイヤトレッド用変性S-SBRの開発動向―
1 まえがき
2 環境との調和と省燃費性
3 タイヤの転がり抵抗の低減
4 転がり抵抗とブレーキ性能の制御と評価技術
5 S-SBRのポリマーデザイン
6 今後の材料開発の動向
第7章 自動車用プラスチックの開発状況―主要樹脂別使用実態と開発の方向・話題―
1 PE樹脂
2 PP樹脂
3 ABS樹脂
4 PMMA樹脂
5 PC樹脂
6 PBT樹脂
7 ポリアミド樹脂
8 ポリアセタール(POM)樹脂
9 PPS樹脂
10 LCP樹脂
11 PEEK樹脂
12 PPE樹脂
13 バイオマスプラスチック
14 ポリアミド(バイオポリアミド)
15 次世代自動車(HEV,EV)向けプラスチック
16 ポリアミド(バイオポリアミド)
17 次世代自動車(HEV,EV)向けプラスチック -

食のバイオ計測の最前線 (普及版)
¥6,050
2011年刊「食のバイオ計測の最前線―機能解析と安全・安心の計測を目指して―」の普及版!難しかった食品の機能や安全性を、バイオ計測を使い、数値化して客観的に評価する解析・計測技術と手法、機器などを解説!!
(監修: 植田充美)
<a href="http://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=5290"target=”_blank”>この本の紙版「食のバイオ計測の最前線 (普及版)」の販売ページを見る(別サイトへ移動)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は、2011年当時のものを使用しております。
植田充美 京都大学
若山純一 (独)農業・食品産業技術総合研究機構
杉山滋 (独)農業・食品産業技術総合研究機構
民谷栄一 大阪大学
北川文彦 京都大学
川井隆之 京都大学
大塚浩二 京都大学
小西聡 立命館大学
小林大造 立命館大学
殿村渉 立命館大学
清水一憲 京都大学
重村泰毅 大阪夕陽丘学園短期大学
伊藤嘉浩 (独)理化学研究所
秋山真一 名古屋大学
田丸浩 三重大学
芝崎誠司 兵庫医療大学
野村聡 (株)堀場製作所
稲森和紀 東洋紡績(株)
境雅寿 (株)森永生科学研究所
高木陽子 京都電子工業(株)
遠藤真 日本エイドー(株)
山本佳宏 京都市産業技術研究所
谷敏夫 (株)バイオエックス
坂本智弥 京都大学
山口侑子 京都大学
高橋信之 京都大学
河田照雄 京都大学
津川裕司 大阪大学
小林志寿 大阪大学
馬場健史 大阪大学
福崎英一郎 大阪大学
木村美恵子 タケダライフサイエンスリサーチセンター
齊藤雄飛 京都府立大学
増村威宏 京都府立大学
山西倫太郎 徳島大学
柴田敏行 三重大学
廣岡青央 京都市産業技術研究所
羽鳥由信 日本新薬(株)
村越倫明 ライオン(株)
小野知二 ライオン(株)
森下聡 ライオン(株)
上林博明 ライオン(株)
鈴木則行 ライオン(株)
杉山圭吉 ライオン(株)
西野輔翼 立命館大学
高松清治 不二製油(株)
米谷俊 江崎グリコ(株)
丸勇史 サンヨーファイン(株)
山口信也 サンヨーファイン(株)
馬場嘉信 名古屋大学
木船信行 (財)日本食品分析センター
岡野敬一 (独)農林水産消費安全技術センター
矢野博 (独)農業・食品産業技術総合研究機構
万年英之 神戸大学
笹崎晋史 神戸大学
末信一朗 福井大学
黒田浩一 京都大学
家戸敬太郎 近畿大学
中村伸 (株)島津製作所
大野克利 日清食品ホールディングス(株)
山田敏広 日清食品ホールディングス(株)
天野典英 サントリービジネスエキスパート(株)
橋爪克仁 タカラバイオ(株)
中筋愛 タカラバイオ(株)
谷岡隆 神鋼テクノ(株)
隈下祐一 サラヤ(株)
永井博 (株)堀場製作所
-------------------------------------------------------------------------
序章 バイオ計測を用いた食の機能解析と安全・安心の向上
1 「バイオ計測」によるデジタル定量分析
2 革新的材料との融合による「バイオ計測」の飛躍
3 「バイオ計測」を推進する拠点事業の展開モデル
【計測開発編】
第1章 大学・研究機関の研究動向
1 SPMナノセンサーと食品応用
1.1 はじめに
1.2 従来のアレルゲン検出技術
1.3 AFMによるアレルゲン検出の原理
1.4 AFMによるアレルゲン検出の実際
1.4.1 基板への抗原の固定
1.4.2 探針上への抗体の固定
1.4.3 AFMによる抗体抗原反応の計測
1.4.4 測定溶液条件の検討とアレルゲンの検出
1.5 今後の展開
2 食品の安全性や機能を評価するPOC型バイオセンサーデバイスの開発
2.1 はじめに
2.2 印刷電極を用いたポータブル遺伝子センサー
2.3 新たな印刷電極型免疫センサーの開発
2.4 イムノクロマト検出キットと携帯電話通信技術との連携
2.5 おわりに
3 マイクロチップ電気泳動における糖鎖分析の高感度化
3.1 はじめに
3.2 PVA修飾チャネルにおけるLVSEPのイメージング
3.3 オリゴ糖のLVSEP-MCE分析
4 バイオセンサーデバイスにおけるサンプル前処理技術
4.1 はじめに
4.2 μTASを応用したパーティクル分離技術
4.2.1 膜フィルタ内蔵マイクロ流路チップを応用した分離技術
4.2.2 遠心マイクロ流路チップを応用した分離技術
4.3 μTASを応用した微量サンプル分注技術
4.4 マイクロデバイスを用いた単一細胞の位置制御技術
4.4.1 陰圧を用いた細胞群の位置制御
4.4.2 磁力を用いた細胞群の位置制御
4.5 おわりに
5 機能性ペプチド探索のための新しいアプローチ―ヒト血液中からの食事由来ペプチドの検出と同定―
5.1 はじめに
5.2 ペプチド経口摂取による健康状態改善効果
5.3 ペプチド摂取後の血液からの血球画分とタンパク質の除去
5.4 血漿中食事由来コラーゲンペプチド(ペプチド型Hyp)濃度の測定
5.5 HPLCによる血漿中食事由来ペプチドの同定
5.6 プレカラム誘導化によるペプチド同定1(PITC誘導化)
5.7 プレカラム誘導化によるペプチド同定2(AQC誘導化)
5.8 おわりに
6 食品関連マイクロアレイ技術
6.1 はじめに
6.2 食品の遺伝子分析
6.2.1 食品分析
6.2.2 育種への応用
6.3 食品の安全性・機能性評価
6.3.1 安全性評価
6.3.2 機能性食品の研究
6.4 食品アレルギー研究,診断
6.4.1 DNAマイクロアレイ
6.4.2 抗原マイクロアレイ
6.4.3 ペプチド・マイクロアレイ
6.5 おわりに
7 バイオ計測への魚類バイオテクノロジーの応用
7.1 はじめに
7.2 魚類によるバイオマテリアル生産技術の開発
7.2.1 バイオマテリアル生産における魚類のアドバンテージ
7.2.2 組換え体タンパク質生産
7.2.3 抗体生産
7.3 透明金魚を使った水質モニタリング
7.4 おわりに―新産業の創出を目指して―
8 特異的抗体の微生物生産と回収法の開発
8.1 はじめに
8.2 抗体の調製方法
8.3 分子ディスプレイ法
8.4 酵母分子ディスプレイ
8.5 Zドメインの分子ディスプレイと抗体の回収系
8.6 抗体以外の親和性タンパク質の調製
第2章 メーカー(企業)の開発動向
1 食の機能と安全評価に寄与するpH計測
1.1 はじめに
1.2 pH測定法の原理と電極のバリエーション
1.2.1 ガラス電極とISFETの原理
1.2.2 pH測定用電極のバリエーション
1.3 半固形・固形食品の測定例
1.4 pH測定電極のより効果的な活用法
1.4.1 連続モニタリングによる反応解析
1.4.2 電極の最適なメンテナンス
1.5 おわりに
2 SPRイメージングによるアレイ解析
2.1 はじめに
2.2 SPRイメージング解析によるペプチドアレイ上におけるリン酸化検出
2.2.1 プロテインキナーゼの網羅的解析の重要性
2.2.2 SPRイメージングによるOn-chipリン酸化の検出系
2.3 ペプチドの金表面への固定化に関する表面化学
2.4 SPRイメージングによる創薬スクリーニングへの展開の可能性
2.4.1 細胞溶解液中のPK活性のSPR測定
2.4.2 SPRイメージング解析によるPK阻害剤の評価
2.5 おわりに
3 ELISA法の原理と測定法―免疫反応の形式(サンドイッチ法,競合法)と測定反応(吸光法,蛍光法)ならびに測定時の注意点―
3.1 はじめに
3.2 ELISA法の分類
3.2.1 サンドイッチ法
3.2.2 競合法
3.2.3 吸光法
3.2.4 蛍光法
3.3 測定時の注意点
3.3.1 マイクロピペットの誤操作
3.3.2 反応時間の厳守
3.3.3 試薬温度
3.3.4 反応温度
3.3.5 プレートの乾燥
3.3.6 洗浄不良
3.3.7 プレート底面の汚れ
3.4 おわりに
4 低分子抗原用抗体およびイムノセンサの実用化
4.1 はじめに
4.2 低分子抗原用抗体の開発
4.3 イムノセンサの開発
4.4 イムノセンサの実用化
4.5 おわりに
5 電気泳動用高度分析試薬の開発
5.1 はじめに
5.2 抽出試薬キットの開発
5.3 機器と試薬の最適化
5.4 二次元電気泳動システムの検証と今後の展望
6 高感度信号累積型ISFETバイオセンサーの開発
6.1 はじめに
6.2 高感度半導体センサー開発の経過
6.3 ISFETセンサーの原理
6.4 高感度信号累積型ISFETプロトンセンサー(AMISセンサー)
6.5 AMISセンサーの特徴
6.6 おわりに
【機能解析編】
第3章 大学・研究機関の研究動向
1 食品成分の機能評価法:肥満・メタボリックシンドロームへのアプローチ
1.1 背景・概要
1.2 食品成分のスクリーニングとその機能解析
1.2.1 ルシフェラーゼアッセイ
1.2.2 抗炎症食品成分の機能解析
1.3 新たなスクリーニング系の構築
1.3.1 蛍光タンパク質レポーターを用いたスクリーニング系の構築
1.3.2 蛍光タンパク質レポーターの課題
1.4 まとめ
2 メタボリックフィンガープリンティングによる食品/生薬の品質評価
2.1 はじめに
2.2 食品/生薬研究におけるメタボロミクスの位置づけ
2.3 GC/MSメタボロミクス
2.4 データマイニングシステムの開発
2.5 データマイニングシステムの緑茶研究での検証
2.6 食品/生薬におけるメタボロミクス研究のこれから
3 栄養アセスメントのための計測技術の現状と発展
3.1 栄養アセスメント計測の現状
3.2 日本人の食事摂取基準と日本食品標準成分表
3.3 健康って何?
3.4 健康増進志向の中での個人の栄養アセスメントの現状と課題
3.5 栄養はバランスが最も重要
3.6 健康栄養インフォメーション
3.7 日常生活の見直し
3.8 栄養状態表示のための生化学検査
3.8.1 成分別測定の必要性
3.9 他の栄養素のアンバランスを招く
3.10 正確に栄養状態を反映する検査方法の開発と適正な栄養アセスメント
3.11 まとめ
4 新規半導体デバイス(積分型ISFET)の食・計測技術への展開
4.1 食品産業における計測技術の重要性
4.2 現在の分析技術の課題と解決のための技術開発
4.3 食品分析領域へのバイオセンサーの応用
4.4 測定用酵素反応機構の開発:食品管理項目の測定例
4.4.1 エタノールの測定
4.4.2 プロテアーゼ活性の測定
4.5 まとめ
5 米粒および米加工品におけるタンパク質の可視化技術の開発と利用
5.1 はじめに
5.2 米粒中のタンパク質分布の解析
5.3 米加工品中のタンパク質の分析例
5.4 おわりに
6 カロテノイドの抗アレルギー作用
6.1 免疫機能に対するカロテノイドの影響に関する研究報告の歴史
6.2 適応免疫系のTh1/Th2 バランスとアレルギー
6.3 抗体産生に対するβ-カロテンの影響
6.3.1 β-カロテン摂取とIgE抗体産生ならびにTh1/Th2バランス
6.3.2 β-カロテンと抗原提示細胞の抗酸化性
6.3.3 抗原呈示細胞内の酸化還元状態とTh1/Th2バランス
6.4 肥満細胞に対するカロテノイドの影響に関する研究報告
6.5 炎症の抑制とカロテノイド
7 海藻の抗酸化物質とその機能解析
7.1 はじめに
7.2 フロロタンニン類(海藻ポリフェノール類)
7.3 ブロモフェノール類
7.4 カロテノイド
7.5 おわりに
8 バイオ計測技術を応用した清酒酵母の分類と開発
8.1 タンパク質の二次元電気泳動法を用いた清酒酵母の発現解析
8.2 発現解析を応用した酵母の分類
8.3 泡なし酵母の解析と開発
8.4 吟醸酒製造用酵母の解析と開発
第4章 メーカー(企業)の開発動向
1 低分子ヒアルロン酸の開発
1.1 はじめに―ヒアルロン酸とは
1.2 ヒアルロン酸の機能
1.3 食品中のヒアルロン酸の分析
1.4 ヒアルロン酸の経口吸収性
1.5 ヒアルロン酸の体内動態
1.6 ヒアルロン酸の経口摂取による効果(ヒトでの効果の検証)
1.7 おわりに
2 ラクトフェリンの脂質代謝抑制作用について
2.1 背景
2.2 実験方法
2.2.1 肥満成人男女を対象としたランダム化二重盲検プラセボ対照試験
2.2.2 消化酵素によるラクトフェリンの分解試験
2.2.3 ラット腸間膜由来前駆脂肪細胞試験
2.3 結果
2.3.1 ヒト試験によるラクトフェリン腸溶錠の内臓脂肪低減効果
2.3.2 消化酵素によるラクトフェリンの分解挙動
2.3.3 ラクトフェリン,およびそのペプシン分解物,トリプシン分解物による脂肪蓄積抑制効果
2.4 考察
3 遺伝子発現から見た大豆たん白の生理機能
3.1 はじめに
3.2 遺伝子発現に着目した大豆たん白質の機能研究
3.3 網羅的遺伝子発現解析手法による大豆たん白質機能の解析
3.4 オリゴヌクレオチドDNAマイクロアレイを用いた研究例
3.5 おわりに
4 GABA高含有チョコレートのストレス緩和効果について
4.1 ストレス緩和の必要性
4.2 ストレスの測定について
4.3 γ-アミノ酪酸(GABA)について
4.4 GABA高含有チョコレートのストレス緩和効果
4.4.1 チョコレートとストレス緩和
4.4.2 GABA高含有チョコレートとストレス緩和
4.5 まとめ
5 シアル酸の機能性
5.1 はじめに
5.2 シアル酸の製造法
5.3 シアル酸の安全性
5.4 シアル酸の機能
5.4.1 抗ウイルス作用
5.4.2 学習能向上効果
5.4.3 育毛効果
5.5 おわりに
【安全・安心の計測編】
第5章 大学・研究機関の研究動向
1 食の安全・安心を計測するナノバイオ技術
1.1 はじめに
1.2 ナノバイオデバイスによる遺伝子解析
1.3 ナノバイオデバイスによるタンパク質解析
1.4 おわりに
2 食の安全・安心における分析者の役割
2.1 食の安全と安心
2.2 食品の安全性を揺るがした事件と分析の関わり
2.2.1 食品添加物
2.2.2 環境汚染(公害)問題と食品の安全性
2.2.3 輸入食品の問題
2.2.4 微生物(食中毒)の問題
2.3 現在の状況(国際的動向を中心に)
2.3.1 化学物質の評価
2.3.2 国際的な食品の安全性評価
2.3.3 Codex委員会における国際的な運用
2.3.4 現在議論されている化学物質
2.3.5 生活習慣病と食品栄養成分
2.4 分析機関の今後の対応
2.5 分析のコスト
2.6 フード・ファディズムについて
2.7 食の安心と食品分析の使命
3 DNA分析の手法などを用いた食品表示の真正性確認
3.1 食品表示と(独)農林水産消費安全技術センターの表示監視業務
3.2 分析対象の表示
3.3 FAMICが表示監視に利用する分析技術の概要
3.4 PCR法を用いたDNA分析
3.4.1 遺伝子組換え食品の表示確認分析
3.4.2 名称および原材料の表示確認分析
3.4.3 産地表示などの確認分析
3.5 元素組成を用いた分析
3.6 安定同位体比分析
3.6.1 炭素安定同位体比を利用した原材料の推定分析
3.6.2 その他の安定同位体比分析による原料推定
3.7 その他の表示監視のための技術と社会的検証
4 食品・農産物におけるDNA鑑定の実用化の現状と展望
4.1 はじめに
4.2 DNA鑑定とは
4.3 食品・農産物におけるDNA鑑定の現状
4.4 食品・農産物におけるDNA鑑定の実用化のあり方
4.5 おわりに
5 DNA鑑定を利用した牛肉偽装表示の防止
5.1 はじめに
5.2 家畜牛の系統・品種
5.3 偽装表示の背景
5.4 国産牛の鑑別技術の開発
5.5 輸入牛肉に対する鑑別技術の開発
5.6 まとめ
6 残留農薬を見逃さない検出・除去バイオ細胞センサー技術の開発
6.1 はじめに
6.2 OPHを用いた有機リン系農薬のバイオセンシング
6.3 酵母細胞表層工学を用いた有機リン検出用生体触媒
6.3.1 OPHとEGFPの細胞表層上への共発現系の構築
6.3.2 水ガラスに固定したOPH-EGFP共発現酵母での有機リン化合物に対する蛍光応答
6.4 おわりに
7 安全・安心な植物促進増産の新手法の開発とその機構解析
7.1 はじめに
7.2 糖アルコールとその性質
7.3 エリスリトールによる生育促進作用
7.4 トランスクリプトームによる生育促進機構の解析
7.5 おわりに
8 完全養殖クロマグロのブランド化とトレーサビリティ手法
8.1 完全養殖クロマグロ
8.2 ブランド化戦略
8.3 トレーサビリティ手法
第6章 メーカー(企業)の開発動向
1 DNA鑑定・食品検査システムの開発;核酸抽出,PCRから検出,判定まで
1.1 はじめに
1.2 定性PCR法の課題と新たな提案
1.3 定性PCR法にもとづくDNA鑑定システム
1.3.1 定性PCR法の流れとシステム構成
1.3.2 肉種鑑別への適用事例
1.3.3 マグロ属魚類の品種判別への適用事例
1.3.4 アレルギー物質を含む食品検査への適用事例
1.4 今後の課題と将来の展望
2 ヒト細胞を用いた新規遺伝毒性試験法 NESMAGET
2.1 はじめに
2.2 試験原理
2.3 試験方法
2.4 NESMAGETの特徴1:DNA損傷形式の異なる遺伝毒性物質の反応性
2.5 NESMAGETの特徴2:既存の遺伝毒性試験との比較
2.6 NESMAGETの特徴3:各細胞による反応性の差
2.7 おわりに
3 バイオ計測手法を活用した微生物の迅速検出・同定の試み
3.1 緒言
3.2 好気性有胞子細菌の菌種迅速同定用DNAマイクロアレイ
3.3 蛍光マイクロコロニー法による微生物迅速検出
3.4 結語
4 リアルタイムPCR法を活用した工程管理の迅速簡便化
4.1 はじめに
4.2 リアルタイムPCR法の原理
4.3 応用例の紹介
4.3.1 牛挽肉増菌培養液からのベロ毒素遺伝子(VT1/VT2遺伝子)の検出
4.3.2 ドライソーセージ原材料肉の判別
4.4 おわりに
5 直接電解オゾン水の食材洗浄への応用
5.1 はじめに
5.2 オゾン水と塩素系薬剤との洗浄比較
5.3 直接電解式オゾン水の生成
5.4 オゾン水による食材洗浄
5.4.1 オゾン水による食材の洗浄方法およびオゾン水供給方法
5.4.2 オゾン水による食材洗浄の最適化
5.4.3 オゾン水洗浄条件の検討
5.5 おわりに
6 ノロウイルス対策としての殺菌剤の有効利用
6.1 はじめに
6.2 ノロウイルスの特徴とその対策
6.3 各種殺菌剤・洗浄剤のノロウイルスに対する有効性
6.4 ノロウイルス対策としての消毒と手洗い
6.4.1 手洗い
6.4.2 モノ・環境
6.4.3 汚物処理
6.5 まとめ
7 おいしい野菜づくりを支えるコンパクト硝酸イオンメータの開発
7.1 はじめに
7.2 農業用コンパクト硝酸イオンメータの開発
7.3 硝酸イオンの測定方法
7.4 コンパクト硝酸イオンメータによる測定方法
7.4.1 作物体測定方法
7.4.2 土壌測定方法
7.5 イオンクロマトグラフとの相関
7.5.1 作物体測定
7.5.2 土壌測定
7.6 おわりに -

電気自動車のためのワイヤレス給電とインフラ構築(普及版)
¥6,930
2011年刊「電気自動車のためのワイヤレス給電とインフラ構築」の普及版!電気自動車普及のためのワイヤレス給電、電磁誘導・磁気共鳴・マイクロ波、急速充電器の開発とネットワークシステムの実例を解説!!
(監修:堀洋一・横井行雄)
<a href="https://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=5220"target=”_blank”>この本の紙版「電気自動車のためのワイヤレス給電とインフラ構築(普及版)」の販売ページを見る(別サイトへ移動)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は2011年当時のものです。
横井行雄 長野日本無線(株)
松木英敏 東北大学
小紫公也 東京大学
居村岳広 東京大学
髙橋俊輔 昭和飛行機工業(株)
阿部茂 埼玉大学
安間健一 三菱重工業(株)
篠原真毅 京都大学
竹野和彦 (株)NTTドコモ
安倍秀明 パナソニック電工(株)
佐藤文博 東北大学
黒田直祐 (株)フィリップス エレクトロニクス ジャパン
多氣昌生 首都大学東京
丸田理 東京電力(株)
岩坪整 日本ユニシス(株)
鈴木匠 JX日鉱日石エネルギー(株)
鶴留寿英 (株)アルバック
近藤信幸 (株)アルバック
青木新二郎 パーク24(株)
藤川博康 三菱重工パーキング(株)
福田博文 KDDI(株)
山光正 オリックス自動車(株)
古川信也 三菱自動車工業(株)
朝倉吉隆 トヨタ自動車(株)
水口雅晴 大丸有地区・周辺地区環境交通推進協議会
斉藤仁司 神奈川県
宇佐美由紀 豊田市
荻本和彦 東京大学
田中謙司 東京大学
須田義大 東京大学
-------------------------------------------------------------------------
総論―電気自動車普及に向けた動き―
【第 I 編 ワイヤレス給電】
序論―ワイヤレス給電―
<基礎>
第1章 ワイヤレス給電の基礎
1 はじめに
2 ギャップを有する電磁誘導給電
3 磁気共鳴給電
3.1 基礎原理とインピーダンス整合
3.2 高Q値コイル
3.3 障害物と漏れ電磁界
4 電磁ビーム伝送給電
4.1 ガウシアンビーム
4.2 マイクロ波ビーム給電
4.3 レーザービーム給電
<電気自動車への応用>
第2章 電気自動車とワイヤレス給電および電磁共鳴技術
1 電気自動車へのワイヤレス給電の需要
2 電気自動車へのワイヤレス給電の発展
3 電気自動車へのワイヤレス給電の技術的課題
4 電磁共鳴技術
4.1 磁界共鳴技術の基本特性
4.2 磁界共鳴技術の等価回路
4.3 中継コイルと等価回路
第3章 電磁共鳴方式によるワイヤレス給電
1 はじめに
2 ワイヤレス給電方式の位置づけ
3 磁界共鳴ワイヤレス給電技術
4 原理デモシステムについて
5 フレキシブル性と同調制御
6 安全・安心のために
第4章 電磁誘導方式による電気自動車向けワイヤレス給電
1 はじめに
2 電磁誘導方式の原理
3 電磁誘導方式の開発
4 電動バスによる実証走行試験
5 おわりに
第5章 電気自動車向けワイヤレス給電
1 はじめに
2 電気自動車向けワイヤレス給電の特徴
3 一次直列二次並列コンデンサ方式
3.1 等価回路とコンデンサ値の決定法
3.2 理想変圧器特性とトランス効率
4 角形コア両側巻トランスと円形コア片側巻トランス
5 1.5kW角形コア両側巻トランスの特性
5.1 トランス仕様
5.2 標準ギャップ長70mmでの給電実験
5.3 標準ギャップ長140mmでの特性
6 二次電池充電実験
7 おわりに
第6章 マイクロ波ワイヤレス給電
1 開発背景,目的について
2 無線充電システム原理
3 本システムの設備概要
4 本システムの特長・利点
5 現在の開発状況
5.1 基本技術の研究
5.1.1 送受電効率の改善
5.1.2 送電器価格の低減
5.1.3 車両への影響遮断
5.1.4 安全性確保
5.1.5 電気自動車への充電実験
5.2 実用化技術の研究
6 課題と今後の展望
6.1 送受電効率
6.2 耐運用環境性能
第7章 電気自動車用マイクロ波ワイヤレス給電
1 はじめに
2 マイクロ波無線送電の効率
3 マイクロ波を用いた電気自動車無線充電―静止時充電―
4 マイクロ波を用いた電気自動車無線充電―移動中充電―
5 おわりに
<拡がるワイヤレス応用>
第8章 医療・民生家電機器とワイヤレス給電
1 医療・民生家電機器へのワイヤレス給電の需要
2 医療・民生家電機器へのワイヤレス給電の発展
3 医療・民生家電機器へのワイヤレス給電の技術的課題
第9章 モバイル機器におけるワイヤレス給電の適用手法
1 概要
2 ワイヤレス伝送の適用事例
3 適用の課題
3.1 位置と効率の関係
3.2 充電場所と効率の関係
3.3 充電時の放射雑音
3.4 電池への影響について
4 まとめ
第10章 携帯用電子機器のワイヤレス給電技術
1 はじめに
2 電磁誘導給電の訴求ポイントと実用化商品
3 分離着脱式トランスと非接触給電システムの等価回路
4 実用化のための問題点と課題
5 基本技術
5.1 分離着脱式トランスの結合係数増大技術
5.2 負荷整合技術
5.3 ソフトスイッチング回路
6 実用技術
6.1 コールドスタンバイと本体検知
6.2 金属異物の加熱対策
6.3 電力伝送と信号送受信機能を持つ非接触充電システム
7 出力安定化技術
8 超薄型平面コイルと薄型充電器による面給電システム
9 おわりに
第11章 医療機器用充電システム
1 はじめに
2 人工臓器へのワイヤレス給電
3 治療デバイスへのワイヤレス給電
4 計測機器へのワイヤレス給電(ワイヤレス通信)
第12章 携帯デバイス向けワイヤレス充電国際規格の標準化
1 はじめに
2 標準化はなぜ必要か?
2.1 携帯デバイス用充電器の共通化
2.2 汎用ワイヤレス充電器普及への課題
2.3 標準化による充電インフラの構築
2.4 結果から手段を導く
2.5 規格策定のバイブル
3 ワイヤレスパワーコンソーシアム(WPC)について
3.1 WPCの組織
3.2 WPC規格のロゴ “qi”(チー)
3.3 これまでに発行された規格書
3.4 ライセンスについて
4 Volume-1規格の概要
4.1 なぜ近接電磁誘導方式を選んだか?
4.2 コイルの位置合わせ(カップリング)
4.3 設計自由度と互換性
5 WPC規格充電システムの概要
5.1 基本システム構成
5.2 送受電部の回路構成と電力の受渡し
5.3 トランスミッターの種類
5.4 レシーバーの共振回路
6 電力の制御と通信
6.1 電力制御のパラメーターとアルゴリズム
6.2 負荷変調による通信
6.3 制御データのエンコーディング
6.4 4つの制御ステップ
7 「規格書Part-2」パフォーマンスに関する要求
7.1 供給保障電力
7.2 温度上昇
7.3 ユーザーインターフェース
8 「規格書Part-3」規格適合認定試験について
8.1 認定試験項目の概要
8.2 規格適合認定試験のプロセスとライセンス製品の販売
8.3 テストツール
9 おわりに
<電波利用の現状と課題>
第13章 電磁界の人体ばく露と人体防護
1 はじめに
2 電磁界の生体影響
3 人体防護ガイドラインの動向
4 規制の動向
4.1 米国
4.2 欧州
4.3 日本
5 ICNIRPガイドライン
5.1 時間変化する電界,磁界,電磁界(300GHzまで)へのばく露制限のガドライン
5.2 時間変化する電界および磁界(1 Hz-100 kHz)へのばく露制限のガイドライン
6 測定評価方法
7 ワイヤレス給電における生体電磁環境
8 おわりに
【第II編 電気自動車普及のためのインフラ構築】
<充電インフラ構築および取り組み・サービス>
第1章 充電インフラ整備の現状と標準化動向
1 はじめに
2 充電インフラの開発動向
2.1 チャデモ方式の概要
2.2 安全性確保のしくみ
3 充電方式の標準化動向
3.1 米国の状況
3.2 欧州の状況
3.3 中国の状況
4 充電インフラのあり方
5 充電電力需要の影響
6 チャデモ協議会の概要
7 充電インフラの将来像
第2章 充電インフラシステムサービス「smart oasis」
1 はじめに
2 充電インフラシステムサービスとは
2.1 充電器の現状
2.2 給電スタンド
2.2.1 充電器の種類
2.2.2 通信モジュール
2.3 通信ネットワーク
2.4 サービス管理システム
2.4.1 「給電スタンド」の利用条件設定
2.4.2 「給電スタンド」と地図情報の連携
2.4.3 満空情報の提供
2.4.4 障害検知・障害通知
2.4.5 携帯による予約管理
2.4.6 課金・決済処理
2.4.7 コールセンターサービス
2.5 その他の連携
2.5.1 カーナビ連携
2.5.2 エコポイントとの連携
3 今後の展開
第3章 サービスステーションにおける電気自動車の充電インフラ
1 背景
2 課題
2.1 SSにおけるEVの急速充電サービスの提供
2.2 SSにおけるEVの急速充電中の付加サービスの提供
2.3 SSを拠点としたEVによる有人型カーシェアリングサービスの提供
3 モニターユーザー調査
3.1 モニターユーザー調査のための急速充電器の設置
3.2 モニターユーザーの設定
3.3 モニターユーザーによる利用
3.4 モニターユーザーからの情報の収集
4 実証事業の成果
4.1 充電インフラのビジネスモデルについて
4.1.1 SSにおけるEVの急速充電サービスの提供
4.1.2 SSにおけるEVの急速充電中の付加サービスの提供
4.1.3 SSを拠点としたEVによる有人型カーシェアリングサービスの提供
4.2 充電設備について
第4章 急速充電器の開発・普及状況
1 急速充電器
1.1 電気自動車と充電器
1.2 急速充電器と車載電池
1.3 DCチャージャ-(直流給電)
1.4 車輌と充電器間の充電プロトコル
2 急速充電器に求められる開発要件
2.1 急速充電器の目的
2.2 充電プロトコル
2.3 安全への考慮
3 アルバックの急速充電器
4 普及状況と普及の為に
5 配電網への影響
第5章 パーク&チャージ ―パーク24による充電設備の展開―
1 パーク&チャージの開始:第二次EVブーム
1.1 第二次ブームの問題点
1.2 パブリック充電機器開発実験
2 第三次EVブーム
2.1 第三次ブームの特徴:インフラ面から見た第二次ブームとの違い
3 充電インフラの整備:パーク24グループの取り組み
3.1 東京電力との実証実験
3.2 自治体駐車場の管理・充電機能設置
3.3 EVカーシェアリング等の実験
3.4 パーク&チャージの展開と充電機能の検証
4 充電インフラ整備における課題
4.1 充電設備の使い勝手の改善
4.2 クルマとの協調
4.3 認証・課金の在り方
5 未来へ向けて
5.1 楽しさ―加速性能
5.2 いままでにない動き
5.3 パーソナルモビリティから自動走行へ
第6章 立体駐車場における充電インフラ(plug-in リフトパーク)
1 はじめに
2 充電機能
2.1 パレットへの電力供給方法
2.2 充電方式
2.3 充電分電盤
3 充電操作フロー
3.1 パレットの呼び出し
3.2 充電ケーブルの接続
3.3 充電方法の選択
3.4 充電開始
4 充電インフラにおける立体駐車場特有の問題
4.1 充電電源の確保
4.2 構造上の問題
5 今後の開発テーマ
5.1 充電機能対応機種の拡大
5.2 使用電力を従来比で30%削減
5.3 安全で人に優しい操作性
6 おわりに
第7章 スマート充電システム
1 背景
2 事業内容
2.1 ピーク時の負荷を平準化
2.2 ニーズに合わせた充電パターン
2.2.1 特徴
2.2.2 メリット
2.3 夜間電力を活用
3 構成
4 実際の充電例
5 利用シーン
6 事務所の駐車場におけるビジネスモデル検討
第8章 カーシェアリング
1 はじめに
2 カーシェアリングとは
3 利用方法
4 カーシェアリングのCO2抑制効果
4.1 無駄な自動車利用の抑止
4.2 モーダルシフト
4.3 低公害車の利用
5 カーシェアリングとEV
6 利用者の評価
6.1 EV
6.2 急速充電器
7 EVの運用事例
7.1 EVによるカーシェアリング
7.2 公用車の共同利用
8 電気自動車の事業的課題
9 おわりに
<自動車メーカーとインフラ>
第9章 三菱自動車の充電インフラに対する電気自動車普及への取り組み
1 はじめに
2 i-MiEVと充電インフラ
3 航続距離と充電インフラ
第10章 トヨタ自動車のプラグインハイブリッド普及に向けた取り組み
1 ハイブリッド車開発への取り組み
1.1 自動車を取り組む環境
1.2 トヨタハイブリッドシステム
2 プラグインハイブリッド車
2.1 プラグインハイブリッド
2.2 プラグインハイブリッド車の排出ガス・燃費試験方法
2.3 プリウスプラグインハイブリッドの概要
3 普及への取り組み状況
<地域・自治体での取り組み>
第11章 大丸有地区における環境交通導入の取り組みについて
1 はじめに
2 この街の交通の出発点とその後
3 物流から環境交通実験へ
4 実験のポイント
5 EVカーシェアリング実験
6 EVコミュニティタクシー
7 社会実験の成果としてコミュニティタクシーが運行スタート
8 EV運転による急速充電器活用(東京・大手町~横浜・みなとみらい)
9 今後の充電インフラ整備について
10 おわりに
第12章 電気自動車(EV)普及に向けた神奈川県の取り組み
1 はじめに
2 EV導入に対する補助
3 有料駐車場及び高速料金の割引
4 最近の主な取組
4.1 太陽光発電による充電システム稼働
4.2 EVシェアリングモデル事業
5 「EV充電ネットワーク」の構築
5.1 充電インフラ整備の取り組み
5.2 「EV充電ネットワーク」の構築
5.3 「EV充電ネットワーク」の具体的な取り組み
6 充電インフラ情報検索WEBサイト開設
7 「EVサポートクラブ」の設立
8 神奈川県における新たな取組み
8.1 「地球と人に優しい」かながわEVタクシープロジェクト
8.2 箱根EVタウンプロジェクト
9 その他の取組み
10 おわりに
第13章 ハイブリッド・シティとよたの取り組み
1 はじめに
2 クルマのまちの課題
3 交通まちづくりにおける「共働」
4 クルマのまちならではの「先進的な交通まちづくり」
4.1 PHV導入と充電施設の整備
4.2 PHV選定理由
4.3 充電施設の配置
4.4 充電施設設計コンセプト
4.5 充電施設概要
4.6 充電システムの特徴
5 普及啓発活動
6 地方都市型低炭素社会システムの取組みを世界へ
7 今後の取組みと課題
8 おわりに
【第III編 電気自動車が実現する低炭素な未来社会】
第1章 スマートグリッドの展開
1 エネルギー技術戦略
1.1 超長期エネルギー技術ビジョン
1.2 エネルギー技術戦略マップ
2 再生可能エネルギー発電導入と電力需給の長期的課題
2.1 電力システムの展望
2.2 再生可能エネルギーの発電特性とならし効果
2.3 電力需給への影響
2.4 柔軟な需給調整に向けた系統および需要での取組み
3 集中/分散のエネルギーマネジメントの協調
3.1 需要の能動化と分散エネルギー貯蔵
3.2 分散エネルギーマネジメントとスマートグリッド
3.3 モデル解析例
4 電力システムのスマート化の展開
4.1 系統発電技術
4.2 電力システムの運用技術
4.3 スマートグリッドへの展開
第2章 スマートグリッドと電気自動車
1 スマートグリッドと電気自動車
2 電気自動車の充電の電力システムに関する課題
3 電気自動車の充電調整(G2V)
3.1 戸建て住宅での電気自動車充電
3.2 集合住宅,商業施設などでのEV充電
3.3 多数台のEV充電
4 電気自動車の充放電制御(V2G)とスマートグリッドへの適用の将来
第3章 電気自動車に始まる二次電池の普及と環境対応型社会システムの構築 ―沖縄におけるグリーン・ニューディールプロジェクト―
1 はじめに
2 沖縄グリーン・ニューディールプロジェクト
3 レンタカーへのEV導入モデル
4 充電シミュレーションに基づく配置法
5 車載用二次電池の定置再利用モデル
6 おわりに
第4章 パーソナルモビリティ・ビークル
1 はじめに
2 パーソナルモビリティ・ビークルの分類と定義
3 パーソナルモビリティ・ビークルの安定性と安定化制御
3.1 自転車の安定性と安定化制御
3.2 平行二輪車モードの安定化制御
4 パーソナルモビリティ・ビークルの操縦性
5 交通環境への受容性および歩行環境への親和性
6 パーソナルモビリティ・ビークル活用によるCO2排出削減効果の試算
-

ポリウレタンの化学と最新応用技術 (普及版)
¥5,940
2011年刊「ポリウレタンの化学と最新応用技術」の普及版!原材料・副資材、分子設計、加工技術等、多岐にわたるポリウレタン応用製品の開発と安全性、リサイクル問題に関する情報を網羅!!
(監修: 松永勝治)
<!--<a href="http://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=5219"target=”_blank”>この本の紙書籍の販売ページはコチラ(別サイトが開きます)</a>-->
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は2011年当時のものです。
山本茂生 住化バイエルウレタン(株)
鈴木千登志 旭硝子(株)
松永勝治 東洋大学
木曾浩之 東ソー(株)
奈佐利久 モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社
徳安範昭 大八化学工業(株)
早福博史 モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社
大谷一嘉 当栄ケミカル(株)
徳山朋紀 三光化学工業(株)
平岡教子 長崎大学
松本信介 三井化学(株)
村山智 日本ポリウレタン工業(株)
石原眞人 日本ミラクトラン(株)
岩崎和男 岩崎技術士事務所
和田浩志 旭硝子(株)
竹川淳 第一工業製薬(株)
武井良道 サンユレック(株)
宮澤文雄 富士紡ホールディングス(株)
高木正孝 フジボウ愛媛(株)
今井景太 (株)イノアックコーポレーション
三村成利 (株)東洋クオリティワン
大川栄二 アキレス(株)
郷博之 (株)エービーシー建材研究所
大嵜武 三井化学(株)
東本徹 荒川化学工業(株)
林俊一 (株)SMPテクノロジーズ
山田英介 愛知工業大学
浅井清次 浅井技術士事務所 MC Labo.
和田康一 住化バイエルウレタン(株)
山崎聡 三井化学(株)
小椎尾謙 長崎大学
-------------------------------------------------------------------------
第1章 ポリウレタンの原材料と副資材
1 イソシアネート
1.1 はじめに
1.2 イソシアネート
1.2.1 イソシアネートの合成法
1.2.2 イソシアネート基の反応の化学
1.2.3 産業上利用されるイソシアネート
(1) イソシアネートモノマー
(2) 変性イソシアネート
1.2.4 最近の開発動向
2 ポリオール
2.1 ポリオールとは
2.2 ポリエーテルポリオール
2.2.1 PPG
2.2.2 ポリマーポリオール
2.2.3 ポリオキシテトラメチレングリコール
2.3 ポリエステルポリオール
2.3.1 重縮合系ポリエステルポリオール
2.3.2 ポリカプロラクトンポリオール
2.4 ポリカーボネートジオール
2.5 ポリブタジエンポリオール
2.6 各種ポリオールを用いたポリウレタン樹脂の性能比較
2.7 バイオマスポリオール
2.7.1 植物油系ポリオール
3 副資材
3.1 鎖延長剤・架橋剤・硬化剤
3.2 触媒
3.2.1 はじめに
3.2.2 ポリウレタン触媒の役割と機能
3.2.3 アミンエミッション低減触媒
3.2.4 難燃性改良触媒
3.2.5 おわりに
3.3 整泡剤
3.3.1 はじめに
3.3.2 整泡剤の役割
(1) 軟質ポリウレタンフォーム
(2) 硬質ポリウレタンフォーム
(3) 高弾性(HR)ポリウレタンフォーム
(4) ポリエステルウレタンフォーム
3.4 難燃剤の最新技術
3.4.1 はじめに
3.4.2 ポリウレタンフォームの概要
(1) 硬質ウレタンフォームの需要
(2) 軟質ウレタンフォームの需要
(3) 課題
3.4.3 難燃化原理と難燃基準に対する材料の選択
3.4.4 おわりに
3.5 酸化防止剤・着色防止剤
3.5.1 ポリウレタンと酸化防止剤
3.5.2 酸化防止剤の種類と特徴
(1) フェノール系酸化防止剤
(2) リン酸系酸化防止剤
(3) イオウ系酸化防止剤
(4) 相乗効果
3.5.3 着色防止剤
3.6 イオン伝導機構による制電性ポリウレタンの技術開発
3.6.1 技術的背景
3.6.2 制電性樹脂の分子設計
(1) 制電剤の作用機構
(2) リチウムイオンによる高分子固体電解質
3.6.3 イオン伝導機構による制電性ポリウレタン
(1)イオン伝導性ポリオール
(2)イオン伝導性グライム類
(3)イオン伝導性脂肪酸エステル
(4)イオン伝導性高分子型帯電防止剤
3.6.4 制電性ポリウレタンの今後の展開
第2章 ポリウレタンの分子設計
1 ポリウレタンエラストマーの分子設計
1.1 はじめに
1.2 分類
1.3 合成法と反応性
1.4 鎖構造
1.5 分岐ないし架橋構造
1.6 相構造
1.7 物性
1.8 おわりに
2 フォームの分子設計
2.1 はじめに
2.2 硬質フォーム
2.2.1 原材料
2.2.2 用途・成形方法と分子設計
2.3 軟質フォーム
2.3.1 原材料
2.3.2 用途・成形方法と分子設計
2.4 おわりに
第3章 ポリウレタンの分析と構造解析
1 はじめに
2 ポリウレタンの分析
2.1 各種分析方法
2.2 ポリウレタンの各種分析法
2.2.1 イソシアネート基の分析
2.2.2 イソシアネート関連生成物の定性
2.2.3 ポリウレタン樹脂の組成分析
2.2.4 添加剤,触媒,不純物,副生成物などの分析
2.3 コンピューターの利用
3 ポリウレタンの構造解析
3.1 一次構造と高次構造
3.2 構造解析法
3.3 フォームのセル構造の観察
4 ポリウレタンの構造と物性の関係
5 まとめ
第4章 ポリウレタン加工技術
1 熱可塑性エラストマー
1.1 はじめに
1.2 TPUの種類と特徴
1.3 TPUの性質
1.3.1 吸湿性と予備乾燥
1.3.2 粘度特性
1.4 成形方法
1.4.1 射出成形
1.4.2 押出成形
1.4.3 カレンダー成形
1.4.4 パウダースラッシュ成形
1.4.5 溶液法
1.5 おわりに
2 熱硬化性ポリウレタンエラストマー
2.1 概要
2.1.1 ポリウレタンエラストマーの歴史
2.1.2 ポリウレタンエラストマーの分類
2.1.3 ポリウレタンエラストマーの需要動向
2.2 注型エラストマー(非発泡タイプ)
2.2.1 原料及び生成化学反応
2.2.2 成形工程及び設備
2.2.3 物性
2.2.4 特徴及び用途
2.3 注型エラストマー(発泡タイプ)
2.3.1 マイクロセルラーエラストマーの原料及び生成化学反応
2.3.2 成形工程及び設備
2.3.3 物性
2.3.4 特徴及び用途
2.4 その他のエラストマー
2.4.1 混練型(ミラブル型)エラストマー
2.4.2 スプレーエラストマー
2.5 新技術,新製品の開発動向
2.5.1 原料関係
2.5.2 成形性の向上
2.5.3 新用途開発
2.5.4 その他の動向
3 ポリウレタンフォームの概要と成形加工技術
3.1 はじめに
3.2 ポリウレタンフォームの市場
3.3 気泡構造
3.4 ポリウレタンフォームの製造プロセス
3.4.1 軟質ポリウレタンフォーム
3.4.2 硬質ポリウレタンフォーム
3.5 おわりに
4 水系ウレタン樹脂
4.1 はじめに
4.2 水系ウレタン樹脂の種類と用途
4.3 非反応型水系ウレタン樹脂の特長
4.3.1 内部架橋構造体の形成
4.3.2 フィルムの形成機構
4.3.3 フィルム物性の発現機構
4.4 反応型水系ウレタン樹脂の特長
4.4.1 架橋剤としての利用
4.4.2 ブロック剤の種類
4.5 水系ウレタン樹脂の高機能化
4.5.1 常温架橋技術(二液型)
4.5.2 常温架橋技術(一液型)
4.5.3 UV・EB架橋技術
4.6 今後の水系ウレタン樹脂
第5章 ポリウレタンの応用
1 車載用電子,燃料電池関係モジュールパッキングのための高信頼性を持つウレタン樹脂
1.1 はじめに
1.2 ポリウレタン樹脂の従来の技術開発概要および新規開発動向
1.3 ポリウレタン樹脂の原材料の種類
1.4 電装部品,燃料電池関連に使用されるポリウレタン樹脂の性質
1.4.1 イソシアヌレート化による問題点
1.4.2 要求特性
1.4.3 防湿絶縁ポリウレタン樹脂の開発製品群について
1.4.4 耐候性
1.4.5 耐湿性
1.4.6 耐熱性
1.4.7 放熱性
1.4.8 難燃性
1.5 今後の展望
2 精密研磨用材料-研磨パッド
2.1 研磨パッドの役割とポリウレタン
2.2 研磨パッドの硬さとポリウレタン
2.3 研磨パッドの種類
2.4 研磨パッドの最近の動き
2.5 おわりに
3 自動車・鉄道車両材料
3.1 はじめに
3.2 ポリウレタンの自動車用途概況
3.3 自動車への展開
3.3.1 シートクッション・シートバック
3.3.2 インストルメントパネル
3.3.3 天井材
3.3.4 フロアカーペット
3.3.5 エンジン周り吸遮音材
3.4 鉄道車両への展開
3.4.1 シート
3.4.2 軌道パッド
4 家具・寝具用材料
4.1 はじめに
4.2 家具・寝具の市場動向
4.3 マットレスの歴史
4.3.1世界のマットレスの歴史
4.3.2日本のマットレスの歴史
4.4 家具・寝具用ポリウレタンフォームについて
4.4.1 各フォームの特徴
4.4.2 低反発フォームについて
4.5 家具・寝具用クッション用フォームの基準について
4.5.1 優良ウレタンマーク制度
4.5.2 家庭用品品質表示法
4.5.3 JIS規格
4.6 最近の技術開発について
4.6.1 低反発フォームのグレードアップ
4.6.2 その他の新材料
4.6.3 療養・介護マットレス
4.7 まとめ
5 土木建築材料
5.1 断熱材
5.1.1 硬質ウレタンフォームの断熱材として優れた特長
5.1.2 硬質ウレタンフォーム断熱製品の成形形態による大きな分類
5.1.3 硬質ウレタンフォームのJIS規格
5.1.4 公的仕様書の状況
5.1.5 省エネルギー基準による断熱厚さ(鉄筋コンクリート造等の住宅)
5.1.6 施工概要
5.2 塗り床材
5.2.1 はじめに
5.2.2 ウレタン樹脂を使用した塗り床材の種類
5.2.3 弾性型ウレタン樹脂系塗り床材
5.2.4 硬質型ウレタン樹脂系塗り床材
5.2.5 水性硬質ウレタン系塗り床材
5.2.6 その他の特殊機能床材
(1) 駐車場用防水床仕上げ材
(2) ゴムチップ弾性舗装材
(3) 石材モルタル舗装材
5.2.7 最近の技術動向
6 塗料・接着剤・バインダー
6.1 食品包装用接着剤
6.1.1 はじめに
6.1.2 ウレタン接着剤の主な原料
6.1.3 ウレタン接着剤の基本構造
(1)一液湿気型
(2)二液硬化型
6.1.4 ウレタン接着剤の加工方法
6.1.5 ウレタン接着剤の機能
6.1.6 ウレタン接着剤の衛生性
6.1.7 おわりに
6.2 印刷インキ用バインダー
6.2.1 ポリウレタン樹脂バインダーの分類
6.2.2 印刷インキの用途と需要量
6.2.3 食品包装材料の製造工程
6.2.4 包装グラビアインキに求められる物性
6.2.5 インキ用バインダーとしてのポリウレタン樹脂の設計
6.2.6 インキバインダー用ポリウレタン樹脂の原料
6.2.7 包装グラビアインキ用ポリウレタン樹脂の環境対応
6.2.8 おわりに
7 その他の応用例
7.1 ポリウレタン系形状記憶ポリマーの特性と応用
7.1.1 はじめに
7.1.2 本ポリマーの種類と形態
7.1.3 材料の特性
(1) 弾性率
(2) 形状回復性と形状固定性
(3) 水蒸気透過性
(4) 体積膨張特性
(5) エネルギー散逸特性
(6) 光学的屈折率特性
(7) その他の性質
7.1.4 応用
(1) 産業分野
(2) 医療分野
(3) 生活関連
(4) 衣料
(5) 易解体ねじ
(6) その他
7.1.5 おわりに
7.2 炭素ナノ材料/ポリウレタン系コンポジット
7.2.1 はじめに
7.2.2 カーボンナノチューブ系コンポジット
7.2.3 グラファイト系コンポジット
7.2.4 フラーレン系コンポジット
7.3 ウレタンジェル
7.3.1 汎用ウレタンジェル
7.3.2 疎水ジェル
7.3.3 親水ジェル
7.3.4 おわりに
第6章 環境対応型ポリウレタンの開発動向
1 法規制と将来動向
1.1 TDI
1.2 MDI
1.3 その他イソシアネート
1.4 TDA 及び MDA
1.5 ポリオール
1.6 ポリウレタン原料に関する工業会
2 ポリウレタンのリサイクルについて
2.1 はじめに
2.2 ポリウレタンリサイクルの現状
2.3 ポリウレタンのリサイクル技術
2.3.1 マテリアルリサイクル
2.3.2 ケミカルリサイクル
2.3.3 サーマルリサイクル
2.4 断熱材のリサイクルについて
2.4.1 RPF(Refuse Paper and Plastic Fuel)化によるリサイクル
2.4.2 断熱材中フロンの問題
2.5 まとめ
3 バイオポリウレタンについて
3.1 はじめに
3.2 ポリウレタンの市場と化学
3.2.1 ポリイソシアネート
3.2.2 ポリオール
3.3 バイオポリウレタンフォームの開発
3.3.1 開発コンセプト
3.3.2 植物由来原料の選定とバイオポリウレタンフォームの位置づけ
3.3.3 第一世代バイオポリオールの開発
3.3.4 第二世代バイオポリオールの開発
3.4 バイオポリウレタンの動向
3.4.1 最近の開発事例
3.4.2 バイオポリウレタン原材料
3.5 今後の技術課題
3.6 おわりに
4 ポリウレタンの安全性
4.1 寝具・家具からのTDI蒸気による暴露
4.2 硬質ポリウレタンスプレーフォーム施工時の安全性
4.3 食品包装材
4.4 フロン規制
4.5 火災問題
4.6 廃棄物処理とリサイクル
4.7 ポリウレタン製品に含まれる未反応モノマー
4.8 ポリウレタンの安全性に関する工業会
第7章 ポリウレタンの研究動向
1 はじめに
2 ポリウレタンのミクロ相分離状態
2.1 原子間力顕微鏡(AFM)を用いた構造観察
2.2 誘電緩和法を用いた相分離状態と分子運動性
2.3 伸張過程におけるミクロ相分離構造変化
3 機能付与を意識した研究例
3.1 原料の化学構造に基づいた力学物性制御
3.2 フィラー添加による力学物性制御
3.3 接着材料
3.4 生体材料
3.5 新しいポリウレタンの合成法
4 おわりに -

電子部品用エポキシ樹脂の最新技術 II(普及版)
¥6,710
2011年刊「電子部品用エポキシ樹脂の最新技術Ⅱ」の普及版!エポキシ樹脂と副資材、配合物の機能、応用分野の用途と要求物性などを網羅し、また新たな機能特性と注目分野への技術動向を詳述!!
(監修:越智光一・岸肇・福井太郎)
<!--<a href="https://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=5199"target=”_blank”>この本の紙版「電子部品用エポキシ樹脂の最新技術 II(普及版)」の販売ページを見る(別サイトへ移動)</a> -->
-------------------------------------------------------------------------
※執筆者の所属表記は、2011年当時のものを使用しております。
【監修】
越智光一 関西大学
岸肇 兵庫県立大学
福井太郎 パナソニック電工(株)
【著者】
越智光一 関西大学
中西政隆 日本化薬(株)
村田保幸 三菱化学(株) 機能化学本部
中村美香 大阪ガスケミカル(株)
奥村浩一 ダイセル化学工業(株)
吉田一浩 チッソ石油化学(株)
小椋一郎 DIC(株)
稲冨茂樹 旭有機材工業(株)
鈴木実 日立化成工業(株)
近岡里行 (株)ADEKA
有光晃二 東京理科大学
内田博 昭和電工(株)
永田員也 旭化成ケミカルズ(株)
岸肇 兵庫県立大学
中村吉伸 大阪工業大学 (吉の上は「土」)
佐藤千明 東京工業大学
高橋昭雄 横浜国立大学
久保内昌敏 東京工業大学
松田聡 兵庫県立大学
西川宏 大阪大学
上利泰幸 (地独)大阪市立工業研究所
原田美由紀 関西大学
今井隆浩 (株)東芝
古森清孝 パナソニック電工(株)
藤原弘明 パナソニック電工(株)
中村吉宏 日立化成工業(株)
米本神夫 パナソニック電工(株)
元部英次 パナソニック電工(株)
真子玄迅 味の素ファインテクノ(株)
宮川健志 電気化学工業(株)
大野浩正 ヘンケルエイブルスティックジャパン(株)
岩倉哲郎 日立化成工業(株)
小日向茂 住友金属鉱山(株)
矢野博之 新日鐵化学(株)
小高潔 ナミックス(株)
中村裕一 ハンツマン・ジャパン(株)
山口真史 積水化学工業(株)
浦崎直之 日立化成工業(株)
小谷勇人 日立化成工業(株)
三宅弘人 ダイセル化学工業(株)
後藤慶次 電気化学工業(株)
-------------------------------------------------------------------------
【第1編 電子部品用エポキシ樹脂と副資材】
第1章 エポキシ樹脂
1. ノボラック型エポキシ樹脂
1.1 ナフタレン含有ノボラック型エポキシ樹脂
1.2 ビスフェノールAノボラック型エポキシ樹脂
1.3 トリスフェノールメタン型エポキシ樹脂
1.4 テトラキスフェノールエタン型エポキシ樹種
1.5 ジシクロペンタジエン型エポキシ樹脂
1.6 フェノールアラルキル型エポキシ樹脂
2. ビフェニル型エポキシ樹脂
2.1 ビフェニル型エポキシ樹脂の構造と特徴
2.2 ビフェニル型エポキシ樹脂の種類
2.3 ビフェニル型エポキシ樹脂の封止材用としての特性
2.3.1 溶融粘度
2.3.2 成形性
2.3.3 吸湿性
2.3.4 低応力性
2.3.5 接着性
2.3.6 耐熱性
2.4 ビフェニル型エポキシ樹脂の展開
2.4.1 新しい半導体技術への対応
2.4.2 新規なビフェニル型エポキシ樹脂の開発
2.4.3 高分子量エポキシ樹脂への導入
2.5 まとめ
3. フルオレン型エポキシ樹脂
3.1 はじめに
3.2 フルオレン型エポキシ樹脂
3.3 合成方法
3.4 基本物性
3.5 硬化物物性
3.6 耐黄変性試験
3.7 分散性
3.8 おわりに
4. 脂環式エポキシ樹脂
4.1 はじめに
4.2 脂環式エポキシ樹脂の合成法
4.3 脂環式エポキシ樹脂の種類と性状
4.3.1 低分子脂環式エポキシ樹脂
4.3.2 オリゴマー型脂環式エポキシ樹脂
4.3.3 新規な脂環式エポキシ樹脂
4.4 脂環式エポキシ樹脂の反応性と硬化物物性
4.4.1 脂環式エポキシ基の反応性
4.4.2 酸無水物硬化
4.4.3 UVカチオン硬化
4.4.4 熱カチオン硬化
4.4.5 アミン硬化
4.5 脂環式エポキシ樹脂の代表的な用途
4.5.1 LED封止材
4.5.2 インク・コーティング関係
4.5.3 電気・電子材料
4.5.4 添加剤・その他
4.6 おわりに
5. 無機骨格を有するエポキシ樹脂
5.1 はじめに
5.2 エポキシ変性シルセスキオキサン
5.2.1 ダブルデッカー型シルセスキオキサン
5.2.2 エポキシ変性ダブルデッカー型シルセスキオキサン
5.3 エポキシ変性シルセスキオキサンの特性
5.3.1 グリシジル変性ダブルデッカー型シルセスキオキサン
5.3.2 脂環エポキシ変性シルセスキオキサン
5.4 おわりに
6. 高機能エポキシ樹脂の分子設計と合成技術,および基礎物性
6.1 はじめに
6.2 高機能エポキシ樹脂の開発
6.2.1 速硬化性エポキシ樹脂
6.2.2 高耐熱性エポキシ樹脂
6.2.3 低熱膨脹性エポキシ樹脂
6.2.4 低吸湿性エポキシ樹脂
6.2.5 低誘電特性エポキシ樹脂
6.2.6 高難燃性エポキシ樹脂
6.2.7 柔軟強靭性エポキシ樹脂
6.3 おわりに
第2章 硬化剤
1. フェノール系エポキシ樹脂硬化剤
1.1 はじめに
1.2 フェノール樹脂の基礎
1.3 エポキシ樹脂とフェノール樹脂の反応
1.4 半導体封止材料エポキシ樹脂硬化剤
1.4.1 半導体封止材料の進歩
1.4.2 封止材用フェノール樹脂系エポキシ樹脂硬化剤の動向
1.5 まとめ
2. 酸無水物類
2.1 はじめに
2.2 酸無水物系硬化剤の種類
2.3 酸無水物系硬化剤の使用にあたって
2.3.1 配合に関して
2.3.2 吸湿,揮散に関して
2.3.3 安全性に関して
2.4 酸無水物系硬化剤の開発動向
2.5 おわりに
3. カチオン系開始剤
3.1 はじめに
3.2 光カチオン開始剤
3.2.1 メリット
3.2.2 デメリット
3.3 熱カチオン開始剤
3.4 おわりに
4. 光塩基発生剤および塩基増殖剤
4.1 はじめに
4.2 新規光塩基発生剤の開発
4.2.1 光環化型塩基発生剤
4.2.2 光脱炭酸型塩基発生剤
4.3 塩基増殖反応による高感度化
4.3.1 塩基増殖剤
4.3.2 分解挙動
4.3.3 アニオンUV硬化への応用
4.4 おわりに
第3章 添加剤
1. 強靱性,耐湿性付与剤
1.1 はじめに
1.2 CEAとα-オレフィンの共重合反応
1.3 共重合体の物性
1.4 共重合体の硬化物の物性値と強靭性・耐湿性付与効果
1.5 フッ素原子導入共重合体
1.6 おわりに
2. フィラー
2.1 フィラーの種類
2.2 フィラーの表面
2.2.1 金属酸化物,水酸化物フィラー
2.2.2 共有結合性フィラーおよび金属フィラー
2.3 フィラーの表面処理
2.3.1 シランカップリング剤
2.3.2 チタネートカップリング剤
2.3.3 脂肪酸,界面活性剤などのイオン結合性有機化合物
2.4 有機-無機ハイブリッド
【第2編 エポキシ樹脂配合物の機能化】
第4章 力学的機能
1. 強靱性
1.1 はじめに
1.2 ゴム添加によるエポキシ樹脂強靭化
1.3 ポリマー微粒子添加によるエポキシ樹脂強靭化
1.4 ポリマーアロイによるエポキシ樹脂の強靭化
1.5 おわりに
2. 低内部応力性
2.1 はじめに
2.2 内部応力とは
2.3 内部応力の低減
2.3.1 ゴム変性
2.3.2 無機粒子の充てん
2.4 強靭性の向上
2.4.1 ゴム変性
2.4.2 無機粒子の充てん
2.5 おわりに
3. 接着性
3.1 はじめに
3.2 接着性とは何か
3.2.1 接着性の定義
3.2.2 応力基準およびひずみ基準
3.2.3 破壊力学的基準
3.3 接着性を考慮した接合部の設計
3.3.1 ICチップと封入樹脂と界面強度
3.3.2 コヘッシブゾーンモデルを用いた接合部の強度予測
3.4 おわりに
第5章 耐久性・耐候性
1. エポキシ樹脂の耐熱性
1.1 はじめに
1.2 物理的耐熱性
1.3 化学的耐熱性
1.4 高耐熱化
2. 耐湿性
2.1 はじめに
2.2 吸水特性
2.2.1 Fickの理想拡散に基づく吸水特性
2.2.2 化学構造と吸水性
2.2.3 無機フィラーの効果
2.3 吸液後の乾燥と物性
2.4 浸入した水の分布と計測
2.5 電子部品の耐湿信頼性
2.5.1 PCT
2.5.2 樹脂の耐熱衝撃性に及ぼす水の影響
2.6 おわりに
3. エポキシ樹脂の疲労き裂伝ぱ特性
3.1 はじめに
3.2 耐疲労性の評価法
3.3 エポキシ樹脂の疲労き裂伝ぱ特性
3.4 おわりに
第6章 伝導的機能
1. 導電性
1.1 はじめに
1.2 導電メカニズム
1.3 導電フィラーの最新動向
1.3.1 導電フィラーの複合添加
1.3.2 導電フィラーに対する表面処理
1.4 おわりに
2. 熱伝導性―フィラー系高熱伝導性エポキシ樹脂
2.1 高熱伝導性高分子材料への期待
2.2 高分子材料の複合化による熱伝導率に及ぼす影響
2.2.1 粒子分散複合材料の有効熱伝導率に与える影響と予測式
2.2.2 熱伝導率に与える影響
2.3 応用分野と将来性
3. 熱伝導性―液晶性エポキシ樹脂系
3.1 はじめに
3.2 構造制御に用いられるメソゲン基と液晶性エポキシ樹脂の特徴
3.3 局所配列および巨視的構造を有する硬化物の創製と熱伝導性
3.4 局所配列構造の形成過程を利用した高熱伝導性コンポジットの創製
3.5 おわりに
第7章 光学的・電気的機能
1. エポキシ樹脂硬化物の屈折率制御
1.1 はじめに
1.2 屈折率に影響を及ぼす基本的な因子
1.3 分極率の異なる原子の導入による屈折率制御
1.4 充填密度の変化による屈折率制御
1.5 おわりに
2. 耐高電圧特性(耐絶縁破壊性)
2.1 はじめに
2.2 エポキシ樹脂の電気絶縁性と測定方法
2.3 絶縁破壊特性が受ける影響
2.4 絶縁破壊特性の向上
2.4.1 球状フィラー充填による絶縁破壊特性の向上
2.4.2 ナノフィラー分散による絶縁破壊特性の向上
2.5 おわりに
【第3編 電子部品用エポキシ樹脂の用途と要求物性】
第8章 基板材料
1. 高速通信用プリント配線板材料
1.1 はじめに
1.2 高速通信用PWB材料の要求特性
1.2.1 銅張積層板の材料構成
1.2.2 高速通信材料への要求物性
1.2.3 絶縁樹脂
1.2.4 ガラスクロス
1.2.5 銅箔
1.3 低誘電エポキシ樹脂銅張積層板
1.4 おわりに
2. 環境対応型プリント基板材料
2.1 はじめに
2.2 プリント基板に関係する法規制の動きと対応技術
2.3 鉛フリー対応技術について
2.4 ハロゲンフリー対応技術について
2.4.1 基板用エポキシ樹脂の難燃化技術の進歩
2.4.2 ハロゲンフリープリント基板材料の特性
2.5 おわりに
3. エポキシ樹脂を用いた最新PKG基板材料
3.1 はじめに
3.2 半導体パッケージの動向と半導体パッケージ基板材料に求められる特性
3.3 エポキシ樹脂の設計
3.3.1 高絶縁信頼性材料への対応
3.3.2 反り低減材料への対応
3.3.3 環境調和型材料への対応
3.4 実用事例
3.5 おわりに
4. ビルドアップ基板用層間絶縁材料
4.1 はじめに
4.2 半導体パッケージ基板用層間絶縁材に求められる特性
4.3 半導体パッケージ基板用層間絶縁フィルム
4.3.1 ABFを用いた多層基板の製造プロセス
4.3.2 ABFの構成
4.3.3 ABFの特徴
4.3.4 ABFの品種とそれぞれの特性
4.4 次世代の層間絶縁材料
4.4.1 次世代の層間絶縁材に要求される性能
4.4.2 次世代向けABF
4.5 ガラスクロスとの複合化材料
4.6 おわりに
5. 高放熱性金属ベース基板
5.1 放熱性基板
5.2 金属ベース基板の構造
5.3 絶縁層の高放熱材料設計
5.4 金属ベース基板の信頼性
5.5 まとめ
第9章 実装材料
1. ダイボンディングペースト
1.1 はじめに
1.2 ダイボンドペーストの分類
1.2.1 リードフレーム用ダイボンドペースト
1.2.2 有機基板用ダイボンドペースト
1.3 マーケットトレンドロードマップ
1.3.1 ダイボンドペーストのマーケットドライバー
1.3.2 ダイボンドペーストの要求特性
1.4 ダイボンドペーストロードマップ
2. ダイボンディングフィルム
2.1 はじめに
2.2 高密度実装の動向とダイボンディングフィルムの必要特性
2.3 エポキシ樹脂/アクリルポリマー系の特徴
2.4 エポキシ樹脂/アクリルポリマー系の補強
2.5 フィルムのダイボンディング用途への適用
2.6 おわりに
3. 導電性接着剤(ペースト)
3.1 はじめに
3.2 Agエポキシの組成概要
3.3 導電性に影響をおよぼす金属粉末の界面活性剤(解こう剤:Lubricant/有機物)
3.4 Agエポキシ硬化物の導電性
3.4.1 直流電気伝導測定
3.4.2 AFM観察
3.5 Agエポキシの電気伝導機構の検討
3.6 新しい導電性接着剤の試み
4 フリップチップ実装用NCP(Non Conductive Paste)
4.1 はじめに
4.2 NCPの要求特性
4.3 設計
4.3.1 硬化挙動
4.3.2 信頼性
4.3.3 材料設計
4.4 おわりに
5. アンダーフィル材―フリップチップ用,COF用,CSP補強用
5.1 はじめに
5.2 アンダーフィルの材料構成
5.2.1 樹脂組成
5.2.2 フィラーについて
5.2.3 その他の添加剤
5.3 アンダーフィルの要求特性と課題
5.3.1 流動特性
5.3.2 接続方式の変化とLow-Kの脆弱化
5.4 熱応力シミュレーション技術のアンダーフィル開発への応用
5.5 COF用アンダーフィル
5.6 2次実装用アンダーフィル
5.7 おわりに
第10章 注目用途へのエポキシ樹脂の展開
1. エネルギー用途―風力発電用FRP材料
1.1 はじめに
1.2 風力発電ブレードの大型化
1.3 風力発電ブレードの成形方法
1.3.1 レジンインフュージョン
1.3.2 構造接着プロセス
1.4 ブレードの製造プロセス
1.5 ブレード製造に用いられるエポキシ樹脂システムおよび構造接着剤
1.5.1 ブレード製造に用いられるインフュージョン用エポキシ樹脂
1.5.2 ブレード製造に用いられる構造用接着剤
1.6 おわりに
2. 液晶ディスプレー用シール剤
2.1 はじめに
2.2 UVシール剤の構成
2.2.1 構成
2.2.2 各成分の役割
2.2.3 各材料の特徴
2.3 UVシール剤の必要機能
2.3.1 UV硬化性
2.3.2 熱硬化性
2.3.3 低汚染性
2.3.4 ポットライフ/ディスペンス性
2.3.5 長期信頼性
2.3.6 接着力
3. 高輝度白色LED用途―白色リフレクタ材料
3.1 はじめに
3.2 表面実装型LED動向と白色反射モールド樹脂の必要特性
3.3 成形方法と白色反射モールド樹脂の設計
3.4 LED用白色反射モールド樹脂の事例
3.4.1 開発材の物性
3.4.2 開発材を用いたLEDパッケージの試作工程と結果
3.4.3 LEDパッケージの信頼性
3.4.4 開発材の寿命
3.4.5 まとめ
3.5 おわりに
4. ナノファブリケーション用途―光ナノインプリント材料へのエポキシ樹脂の応用
4.1 はじめに
4.2 ナノインプリント技術
4.2.1 ナノインプリントの種類
4.2.2 光ナノインプリント材料への適用性
4.3 カチオン硬化システムの特徴
4.3.1 カチオン硬化性化合物
4.3.2 硬化収縮について
4.3.3 硬化収縮のメカニズム
4.3.4 基材密着性とモールド離型性
4.4 まとめ
5. 光学部品用UV硬化型エポキシ接着剤
5.1 はじめに
5.2 光学部品用UV接着剤について
5.3 UV硬化型エポキシ接着剤の特徴
5.4 UV硬化型エポキシ接着剤の硬化機構
5.5 UV-LEDについて
5.5.1 分光分布
5.5.2 寿命
5.5.3 高安全性・低ランニングコスト
5.6 UV硬化型エポキシ接着剤の硬化特性
5.7 UV硬化型エポキシ接着剤「ハードロック UVX-Bシリーズ」
5.8 おわりに -

未来を動かすソフトアクチュエータ―高分子・生体材料を中心とした研究開発―(普及版)
¥7,480
2010年刊「未来を動かすソフトアクチュエータ―高分子・生体材料を中心とした研究開発―」の普及版!ロボット、医療、福祉など様々な分野で実用化が進んでいる高分子アクチュエータに加え、期待されるバイオアクチュエータの材料や応用、制御、市場動向を解説!!
(監修:長田義仁・田口隆久)
<a href="https://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=7633"target=”_blank”>この本の紙版「未来を動かすソフトアクチュエータ―高分子・生体材料を中心とした研究開発―(普及版)」の販売ページを見る(別サイトへ移動)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は2010年当時のものです。
長田義仁 (独)理化学研究所
田口隆久 (独)産業技術総合研究所
三俣哲 山形大学
山内健 新潟大学
須丸公雄 (独)産業技術総合研究所
高木俊之 (独)産業技術総合研究所
杉浦慎治 (独)産業技術総合研究所
金森敏幸 (独)産業技術総合研究所
菊地邦友 和歌山大学
安積欣志 (独)産業技術総合研究所
土谷茂樹 和歌山大学
金藤敬一 九州工業大学
奥崎秀典 山梨大学
杉野卓司 (独)産業技術総合研究所
清原健司 (独)産業技術総合研究所
石橋雅義 (株)日立製作所
平井利博 信州大学
千葉正毅 SRIインターナショナル
田實佳郎 関西大学
渡辺敏行 東京農工大学
吉原直希 東京農工大学
草野大地 東京農工大学
甲斐昌一 九州大学大学院
立間徹 東京大学
山上達也 (株)コベルコ科研
都井裕 東京大学
高木賢太郎 名古屋大学
釜道紀浩 東京電機大学
佐野滋則 豊橋技術科学大学
大武美保子 東京大学
関谷毅 東京大学
加藤祐作 東京大学
福田憲二郎 東京大学
染谷隆夫 東京大学
向井利春 (独)理化学研究所
郭書祥 香川大学
伊原正 鈴鹿医療科学大学
渕脇正樹 九州工業大学
昆陽雅司 東北大学
和氣美紀夫 (株)HYPER DRIVE
森島圭祐 東京農工大学
藤里俊哉 大阪工業大学
角五彰 北海道大学
JianPing Gong 北海道大学
佐野健一 (独)理化学研究所
川村隆三 (独)理化学研究所
-------------------------------------------------------------------------
【第1編 ソフトアクチュエータの開発状況と市場動向】
第1章 人工筋肉技術の開発状況と市場動向
1 概要
2 研究開発の状況
2.1 高分子材料を利用するアクチュエータ
2.2 形状記憶材料を利用するアクチュエータ
2.3 空気圧を利用するアクチュエータ
2.4 静電力を利用するアクチュエータ
3 市場・企業動向
【第2編 高分子アクチュエータの材料】
第2章 磁場駆動による磁性ゲルアクチュエータ
1 はじめに
2 伸縮運動
3 回転運動
4 可変弾性ゲル
5 おわりに
第3章 熱, 電磁波駆動によるゲルアクチュエータ
1 はじめに
2 発熱体としてのナノ・マイクロ材料
3 ナノ・マイクロ材料の複合化
4 おわりに
第4章 光駆動ゲルアクチュエータ
1 はじめに
2 光応答収縮ゲルの構造と物性
3 ロッド状ゲルアクチュエータの光屈曲制御
4 シート状ゲルアクチュエータへの微小パターン照射による表面形状制御
5 マイクロ流路の光制御への応用
6 おわりに
第5章 イオン導電性高分子アクチュエータ
1 はじめに
2 イオン導電性高分子アクチュエータの作製・加工, 評価法
2.1 作製・加工法
2.2 評価法
3 水系イオン導電性高分子アクチュエータの特性,モデル
4 イオン液体系イオン導電性高分子アクチュエータの特性,モデル
5 まとめ
第6章 導電性高分子ソフトアクチュエータ
1 はじめに
2 導電性高分子の電解伸縮
3 電解伸縮の増大化
4 電解伸縮による伸縮率-応力曲線
5 ポリアニリンの過荷重下での電解伸縮の学習効果
6 電解伸縮のトレーニング効果と形状記憶
7 おわりに
第7章 空気中で電場駆動する導電性高分子アクチュエータ
1 緒言
2 実験
3 結果と考察
3.1 フィルムの比表面積
3.2 水蒸気吸着特性
3.3 電気収縮挙動
3.4 収縮応力と体積仕事容量
3.5 直動アクチュエータとポリマッスル
第8章 カーボンナノチューブ・イオン液体複合電極の伸縮現象を利用した高分子アクチュエータ
1 はじめに
2 アクチュエータの作成法と駆動メカニズム
3 アクチュエータの評価と性能改善
3.1 イオン液体の選択
3.2 電極膜への添加物の導入
3.3 ナノカーボン材料の影響
4 今後の展望
第9章 炭素ナノ微粒子(CNP)コンポジットアクチュエータ
1 はじめに
2 溶液中動作CNPコンポジットアクチュエータ
3 大気中動作CNPコンポジットアクチュエータ
第10章 誘電性ポリマーアクチュエータ―膨潤ゲルから結晶性ポリマーフィルムまで―
1 はじめに
2 電場で駆動する誘電性ポリマー柔軟材料の分類
3 誘電性ポリマーゲルの変形
3.1 誘電ポリマーゲルの電場駆動
4 低誘電率ポリマー柔軟材料の電場駆動
4.1 可塑化PVCの電場による可逆的なクリープ変形
4.2 ポリウレタン(PU)の電場による屈曲変形特性
4.3 ポリエチレンテレフタレート(PET)の振動運動など
5 まとめ
第11章 誘電エラストマートランスデューサー
1 はじめに
2 開発背景
3 EPAMアクチュエーターの原理
4 EPAMアクチュエーターの素材, 性能および開発動向
5 EPAMアクチュエーターの応用展開
6 EPAM発電の原理
7 革新的直流発電システムへの展開
8 EPAMアクチュエーターの将来
第12章 圧電ポリマーアクチュエータ
1 はじめに
2 圧電ポリマーの圧電性基礎
2.1 結晶の圧電性
2.2 圧電ポリマーフィルム
2.3 配向制御の実際
3 アクチュエータとしての圧電ポリマーの基本性能
4 実用化に近づけるアクチュエータ材料の開発例
4.1 Macro Fiber Composite
4.2 キラル圧電ポリマー繊維素子
4.3 セルフセンシングアクチュエータ
4.4 多孔性エレクトレット
4.5 配向制御
4.6 蒸着重合
4.7 分子制御
5 おわりに
第13章 光駆動高分子ゲルアクチュエータ
1 はじめに
2 光応答性部位の設計
3 高分子ゲルとは
4 分子レベルの変形を如何にマクロな変形へとシンクロさせるか
5 光応答性高分子ゲルの光応答挙動
5.1 光応答性ポリアミド酸ゲルの合成
5.2 ポリアミド酸ゲルの光照射による吸光度変化
5.3 6FDA/DAA棒状ポリアミド酸ゲルの屈曲挙動
5.4 ゲルの調整時濃度依存性の測定
5.5 光応答速度の向上
6 おわりに
第14章 電界駆動型液晶エラストマーアクチュエータの物性と応用
1 はじめに
2 電界応答する液晶エラストマーの構造
2.1 基本構造
2.2 ポリドメインとモノドメイン
2.3 液晶エラストマーの熱物性
3 液晶エラストマーの電気力学効果
3.1 ネマチック液晶エラストマーの電界応答
3.2 膨潤した液晶エラストマーの電気光学効果
3.3 液晶エラストマーの磁気効果
4 膨潤液晶エラストマーの物性的特徴のまとめ
5 電界駆動型液晶エラストマーの応用
6 おわりに
第15章 高分子ゲルを用いた電気化学および光電気化学アクチュエータ
1 はじめに
2 高分子ゲルを用いた電気化学アクチュエータ
3 光触媒反応に基づくアクチュエータ
4 部分的な形状変化
5 プラズモン光電気化学反応の利用
6 Ag+を利用する光電気化学アクチュエータ
7 おわりに
【第3編 高分子アクチュエータのモデリング・制御】
第16章 高分子アクチュエータの分子論的メカニズム
1 序
2 現象論
3 分子論
4 まとめ
第17章 連続体的手法によるアクチュエータモデリング
1 はじめに
2 電気的な応力拡散結合モデル
2.1 基礎方程式
2.2 電気的な応力拡散結合モデル
3 高分子電解質ゲルのオンザガー係数
3.1 イオンサイズの効果
3.2 流動電位の実測値との比較
4 ゲルの曲げと緩和のメカニズム
4.1 基礎方程式
4.2 初期の曲げ
4.3 緩和時間
5 実験との比較
6 結論
第18章 高分子アクチュエータの材料モデリング
1 イオン導電性高分子アクチュエータ
2 イオン導電性高分子アクチュエータの電気化学応答の計算モデリング
2.1 前方運動
2.2 後方運動
3 イオン導電性高分子アクチュエータの三次元変形応答解析
4 導電性高分子アクチュエータ
5 導電性高分子アクチュエータの電気化学・多孔質弾性応答の計算モデリング
5.1 多孔質弾性体の剛性方程式
5.2 圧力に対するポアソン方程式
5.3 体積ひずみ速度の発展方程式
5.4 イオン輸送方程式
5.5 計算手順
6 固体電解質ポリピロールアクチュエータの電気化学・多孔質弾性応答解析
第19章 イオン導電性高分子アクチュエータの制御モデル
1 はじめに
2 高分子アクチュエータのモデリング
2.1 モデリングの手法
2.2 IPMCアクチュエータのモデリング
3 力制御のための伝達関数モデル
3.1 IPMCアクチュエータの力計測
3.2 電気系モデルおよび電気機械変換系モデル
3.3 力計測系全体のモデル
4 物理原理(電場応力拡散結合)に基づく状態方程式モデル
4.1 状態方程式とは
4.2 電場応力拡散結合モデルとその状態空間表現について
4.3 電気系
4.4 電気機械変換系
4.5 機械系
4.6 全体の系の状態方程式
4.7 シミュレーション
5 まとめ
第20章 イオン導電性高分子アクチュエータの制御手法
1 はじめに
2 変形量の制御
2.1 ハードウェア構成例
2.2 PID制御
2.3 ブラックボックスモデルを用いた2自由度制御系
3 IPMCセンサ統合系を用いたフィードバック制御
4 力制御のためのロバストなPIDフィードバック
4.1 IPMCアクチュエータの不確かさの表現と制御系設計手法
4.2 実験
5 まとめ
第21章 高分子ゲルアクチュエータの電場による制御
1 はじめに
2 イオン性高分子ゲルの変形モデル
2.1 高分子ゲルの基本モデル
2.2 吸着解離方程式に基づくイオン性高分子ゲルの変形モデル
3 一様電場によるイオン性ゲルの形状制御
3.1 一様電場におけるイオン性高分子ゲルの波形状パタン形成
3.2 極性反転によるイオン性高分子ゲルの形状制御
4 空間分布電場によるイオン性高分子ゲルの変形運動制御
4.1 一列に配置した電極により生成される電場によるイオン性高分子ゲルの屈曲反転運動制御
4.2 二次元配列状に配置した電極により生成される電場によるヒトデ型ゲルロボットの起き直り運動制御
5 まとめ
【第4編 高分子アクチュエータの応用】
第22章 有機アクチュエータと有機トランジスタを用いた点字ディスプレイの開発
1 はじめに
2 研究背景
2.1 有機トランジスタとエレクトロニクス
2.2 点字ディスプレイ
3 デバイス構造および作製プロセス
3.1 デバイス構造と動作原理
3.2 有機トランジスタの作製プロセス
3.3 イオン導電性高分子アクチュエータ
3.4 アクチュエータシートとトランジスタシートの集積化
4 電気特性
4.1 トランジスタ
4.2 イオン導電性高分子アクチュエータ
4.3 有機トランジスタと高分子アクチュエータを集積化しての素子特性
5 点字ディスプレイのデモンストレーション
6 課題
7 低電圧駆動の点字ディスプレイの開発状況
7.1 デバイス構成
7.2 3V駆動可能なドライバー用有機トランジスタおよび有機SRAMの作製プロセス
7.3 ドライバー有機トランジスタの電気特性と集積化
7.4 有機SRAMの特性
7.5 考察
8 今後の展望
第23章 高分子アクチュエータのソフトロボットへの応用
1 これからのロボットに求められる柔らかさ
2 表面電極分割によるIPMCの多自由度化
3 ソフトなヘビ型水中ロボット
4 双安定アクチュエータ構造
5 IPMCアクチュエータとセンサの同時使用
第24章 高分子アクチュエータのマイクロロボットへの応用
1 研究の背景
1.1 背景
1.2 開発目標
2 首振り型水中マイクロロボット
2.1 首振り型水中マイクロロボットの動作原理
2.2 首振り型水中マイクロロボットの特性評価
3 2PDLを用いた多自由度水中歩行ロボット
3.1 2PDLを用いた多自由度水中歩行ロボットの動作原理
3.2 2PDLを用いた多自由度水中歩行ロボットの特性評価
4 八足水中マイクロロボット
4.1 八足水中マイクロロボットの動作原理
4.2 八足水中マイクロロボットの特性評価
5 多機能水中ロボット
5.1 多機能水中ロボットの動作原理
5.2 多機能水中ロボットの特性評価
6 赤外線制御による水中マイクロロボット
6.1 赤外線制御による水中マイクロロボットの動作原理
6.2 赤外線制御による水中マイクロロボットの特性評価
7 まとめと今後の展望
第25章 高分子アクチュエータ/センサの医療応用
1 はじめに
2 アクチュエータ
2.1 カテーテル関連駆動機構としての高分子電解質膜
2.2 ポンプ駆動機構としての高分子電解質膜
2.3 運動機能補助・器具操作補助機能としての高分子電解質膜
2.4 その他の導電性高分子のアクチュエータ応用
3 センサ
3.1 動作用センサ
3.2 pHセンサ
3.3 SMITスマート生地
3.4 ガスセンサ
4 導電性媒体としての高分子電解質膜の医療応用
4.1 植込型生体用電極コーティング
5 生体適合性
第26章 高分子アクチュエータのマイクロポンプへの応用
1 緒言
2 実験装置および方法
3 結果および考察
3.1 開閉運動する導電性高分子ソフトアクチュエータ
3.2 導電性高分子ソフトアクチュエータを駆動源とするマイクロポンプ
4 マイクロポンプの基礎性能
5 まとめ
第27章 高分子アクチュエータの触覚ディスプレイへの応用
1 はじめに
2 イオン導電性高分子アクチュエータ
3 IPMCアクチュエータの触覚ディスプレイへの適用
4 布のような手触りを呈示する触感ディスプレイ
5 局所滑り覚呈示による把持力調整反射の誘発
6 おわりに
第28章 誘電エラストマートランスデューサーの様々な応用
1 はじめに
2 開発背景
3 アクチュエーター,センサーとしての誘電エラストマー
3.1 ロボット, 介護, リハビリ用アクチュエーター, センサー
3.2 音響機器等への応用
3.3 その他のアプリケーション
4 EPAM発電デバイスへの応用
4.1 EPAM波力発電
4.2 EPAM水車発電
4.3 持ち運び可能な小型発電機の開発
4.4 ウエアラブル発電
4.5 人工筋肉発電の将来
5 今後の展開
【第5編 次世代のソフトアクチュエータ―バイオアクチュータ―】
第29章 3次元細胞ビルドアップ型バイオアクチュエータの創製
1 はじめに
2 細胞外基質を用いた心筋細胞の3次元培養方法の確立
3 心筋細胞ゲルのマイクロ化
4 マイクロ心筋細胞ゲルの性能評価
4.1 変位,周波数測定
4.2 収縮力測定
4.3 寿命評価
4.4 ゲル組織切片の構造観察
4.5 まとめ
5 マイクロ心筋細胞ゲルの制御方法の検討
5.1 電気パルス刺激に対する応答性の評価
5.2 化学刺激に対する応答性の評価
6 バイオアクチュエータへの応用
6.1 マイクロピラーアクチュエータ
6.2 チューブ型マイクロポンプ
7 結言と今後の展望
第30章 組織工学技術を用いたバイオアクチュエータの開発
1 はじめに
2 筋細胞を用いたバイオアクチュエータ
3 我々の骨格筋細胞を用いたバイオアクチュエータ
4 組織学および分子生物学的評価
5 収縮力
6 バイオアクチュエータによる物体の駆動
7 おわりに
第31章 ATP駆動型ソフトバイオマシンの創製
1 はじめに
2 分子モーターの受動的自己組織化
3 分子モーターの能動的自己組織化
4 自己組織化の時空間制御
5 分子モーター集合体における自発的秩序構造形成
6 おわりに
第32章 バイオアクチュエータとしての細胞骨格トレッドミルマシン
1 はじめに
2 トレッドミルとは?
3 トレッドミルマシン研究の現状
4 細胞骨格タンパク質で創る超高分子階層性ゲルとトレッドミルアクチュエータの可能性
5 おわりに -

ゾル-ゲル法技術の最新動向(普及版)
¥4,840
2010年に発行された『ゾルーゲル法技術の最新動向』の普及版!多方面で応用されるゾル-ゲル技術を国内第1線の研究・開発者が基礎から応用までをまとめた書籍。リチウムイオン二次電池、色素増感型太陽電池への応用も解説!
(監修:作花済夫)
<a href="https://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=5148"target=”_blank”>この本の紙版「ゾル-ゲル法技術の最新動向(普及版)」の販売ページを見る(別サイトへ移動)</a>
-------------------------------------------------------------------------
<<著者一覧>>
※執筆者の所属表記は2010年当時のものです。
作花済夫 京都大学名誉教授
郡司天博 東京理科大学
安盛敦雄 東京理科大学
野上正行 名古屋工業大学
牧島亮男 北陸先端科学技術大学院大学
髙橋雅英 大阪府立大学
余語利信 名古屋大学
下嶋 敦 東京大学
若林隆太郎 早稲田大学
浦田千尋 早稲田大学
黒田一幸 早稲田大学
平島 碩 慶應義塾大学名誉教授
片桐清文 名古屋大学;関西大学
中西和樹 京都大学
酒井正年 扶桑化学工業(株)
高橋亮治 愛媛大学
柴田修一 東京工業大学
阿部啓介 旭硝子(株)
公文創一 セントラル硝子(株)
神谷和孝 日本板硝子(株)
松田厚範 豊橋技術科学大学
下岡弘和 九州工業大学
桑原 誠 東京大学名誉教授
永井順一 NSSエンジニアリング(株)
大崎 壽 (独)産業技術総合研究所
吉田知也 (独)産業技術総合研究所
長尾昌善 (独)産業技術総合研究所
皆合哲男 日本板硝子(株)
加藤一実 (独)産業技術総合研究所
伊藤省吾 兵庫県立大学
森口 勇 長崎大学
山田博俊 長崎大学
田淵智美 (独)造幣局
忠永清治 大阪府立大学
清水武洋 伊藤光学工業(株)
城﨑由紀 岡山大学
都留寛治 九州大学
早川 聡 岡山大学
尾坂明義 岡山大学
宇山 浩 大阪大学
-------------------------------------------------------------------------
【ゾル-ゲル過程編】
第1章 ゾル-ゲル法の現状
1. はじめに
2. ゾル-ゲル法で作られる材料の微細構造
3. ゾル-ゲル法の研究動向
4. ゾル-ゲル法によって合成される材料の現状
4.1 透明導電膜
4.2 発光材料(ルミネッセンス材料)
4.2.1 蛍光材料
4.2.2 レーザー
4.2.3 りん光材料(長時間光る材料)
4.2.4 シンチレーション材料
4.3 光触媒
4.3.1 TiO2光触媒の応用
4.3.2 作用表面積の増大
4.3.3 ドーピングの効果
4.3.4 可視光応答光触媒
4.3.5 プラスチック上の光触媒膜
4.4 エアロゲル
4.4.1 サブクリティカル乾燥でつくられるシリカエアロゲル
4.4.2 シリカ以外の物質のエアロゲル
4.4.3 有機-無機ハイブリッドエアロゲル
5. おわりに
第2章 新しいゾル-ゲル法の原料
1. はじめに
2. 一次元ゾル-ゲル法の原料
3. 二次元ゾル-ゲル法の原料
4. 三次元ゾル-ゲル法の原料
5. おわりに
第3章 ゲル化と無機バルク体の形成
1. はじめに
2. ゾル-ゲル法によるシリカゲルの作製プロセス
2.1 反応に影響する因子
2.2 ゲルの細孔構造に影響する因子
2.3 添加物のゲルの構造に及ぼす影響
3. 多成分系バルクガラスの作製
3.1 高融点酸化物を含むケイ酸塩ガラスの作製
3.2 アルカリ金属・アルカリ土類金属酸化物などを含む多成分ケイ酸塩ガラスの作製
4. ゾル-ゲル法を用いた機能性バルクガラスの作製
4.1 CdS微粒子分散光学ガラスの作製
4.2 屈折率分布ガラスの作製
4.3 磁性体微粒子分散ガラスの作製
5. おわりに
第4章 無機イオン・ナノ粒子分散材料の形成
1. はじめに
2. 希土類イオン分散ガラス
3. ナノ粒子分散ガラス
4. ナノ粒子-希土類イオン共ドープガラス
第5章 有機・無機ナノコンポジットの形成
1. はじめに
2. 有機・無機コンポジット、有機・無機ハイブリッドの例
2.1 光関連材料
2.2 バイオ関連材料
2.3 光、バイオ関連以外の材料
3. 化学結合を考慮した有機・無機ナノハイブリッドの実例
3.1 有機色素・ケイ酸塩ナノハイブリッド材料
3.2 ビタミンB12を酸化チタンと複合化した材料
第6章 無溶媒縮合法による有機-無機ハイブリッドの合成と応用
1. 有機修飾無機系ポリマー材料
2. 酸塩基反応を利用した有機-無機ハイブリッド材料の合成と応用
2.1 リン酸と塩化ケイ素の反応性
2.2 有機修飾ケイリン酸系材料による再書き込み可能なフォログラフィックメモリー材料
3. おわりに
第7章 透明機能性ナノ結晶粒子/ポリマーハイブリッド材料
1. はじめに
2. 透明ハイブリッド材料
3. ペロブスカイトナノ結晶粒子/ポリマーハイブリッド
4. 磁性ナノ粒子/ポリマーハイブリッド
5. おわりに
第8章 自己組織化によるシリカ系有機・無機ハイブリッドの合成
1. はじめに
2. R'-Si(OR)3型分子からのハイブリッド合成
3. (RO)3Si-R'-Si(OR)3型分子からのハイブリッド合成
4. 形態制御―薄膜化―
5. 形態制御―ベシクル形成―
6. シロキサン部の設計によるメソ構造制御
7. おわりに
第9章 メソ多孔体の作製
1. はじめに
2. 組成制御
2.1 修飾剤を用いた表面組成設計
2.2 異種金属の導入
3. メソ構造制御
3.1 メソ構造制御
3.2 メソ構造解析
4. 形態制御
4.1 メソ多孔体微粒子
4.2 メソ多孔体薄膜の合成およびメソ孔の配向制御
5. おわりに
第10章 バルクゲルの焼結
1. はじめに
2. 焼結の理論
2.1 粘性流動焼結
2.2 拡散焼結
3. ゲル焼結の実際
4. ホットプレス焼結
5. おわりに
第11章 静電相互作用による分子組織体を利用したナノハイブリッドの作製と応用
1. はじめに
2. 静電相互作用を利用したハイブリッド超薄膜作製法としての交互積層法
3. 交互積層膜を利用したナノハイブリッドコーティング薄膜
4. コロイド粒子への交互積層によるコア-シェル粒子の作製とプロトン伝導体への応用
5. コロイドをテンプレートとした中空カプセルの作製と外部刺激応答性材料への応用
6. おわりに
第12章 膜の形成―スピンコーティング膜表面の放射状凹凸―
1. はじめに
2. 触針式表面粗さ計によるストライエーションの定量的評価
3. 回転基板上に供給するゾルの量、ゾルの粘度、基板回転速度の効果
4. 静止基板上に作製されるゲル膜におけるストライエーションの形成
5. 静止基板上に作製されるゲル膜におけるその場観察
6. ストライエーションの形成機構
7. ストライエーションの形成を抑制するために:溶媒の揮発性の効果
8. おわりに
【ゾル-ゲル法の応用編】
<多孔質モノリス>
第13章 多孔質シリカによるモノリス型液体クロマトグラフィーカラム
1. はじめに
2. 液体クロマトグラフィーの発展と課題
3. シリカ系モノリス型カラム
4. モノリス型カラムの利点と課題
5. バイオ分析、医療関連デバイスへの展開
6. おわりに
<粒子および粉末>
第14章 高純度コロイダルシリカの製法、特性とその応用例
1. はじめに
2. 高純度コロイダルシリカの製造方法
3. 高純度コロイダルシリカの特性
4. 高純度コロイダルシリカの応用例
第15章 固体触媒
1. 固体触媒とその調製
2. 固体触媒のゾル-ゲル法による調製の概略
3. シリカ担持金属触媒における高分散化
4. 階層細孔構造を有する固体触媒
5. おわりに
第16章 ガラス微小球レーザー
1. 球状光共振器の原理
2. 微小球レーザーの研究の歴史
3. テラス微小球の作製とレーザー発振
4. 光ファイバーカプラの作製と励起実験
5. おわりに
<膜およびコーティング>
第17章 光反射防止膜
1. はじめに
2. 膜設計
2.1 透明性
2.2 低反射特性
2.3 光入射角と膜厚設計
3. 膜構成
3.1 単層低反射膜
3.2 多層低反射膜
3.3 多層膜間の界面強度
4. 膜特性
4.1 実用特性
4.2 低反射性
5. おわりに
第18章 自動車用赤外線カットガラス
1. はじめに
2. 赤外線カットガラスの構成
3. 赤外線カット膜
4. おわりに
第19章 自動車窓ガラス用撥水性膜
1. はじめに
2. 持続的な自動車用撥水ガラス
3. 撥水剤および膜構成
4. 高耐久撥水コート
5. PFOA問題
6. おわりに
第20章 ゾル-ゲルマイクロ・ナノパターニング
1. はじめに
2. エンボス法・インプリント法
3. フォトリソグラフィー法
4. ソフトリソグラフィー法
5. 固体表面のエネルギー差を利用する方法
6. チタニアの光触媒作用を利用する方法
7. 電気泳動堆積と撥水-親水パターンを利用する方法
8. 電気流体力学的不安定性を利用したパターニング
9. 光誘起自己組織化を利用したパターニング
10. おわりに
第21章 高誘電率ナノ結晶膜
1. はじめに
2. 高濃度アルコキシド溶液を用いるゾル-ゲル法(高濃度ゾル-ゲル法)
3. BaTiO3ナノ結晶自立膜の作製とその誘電特性
4. おわりに
第22章 エレクトロクロミック膜
1. はじめに
2. ゾル-ゲル法によるエレクトロクロミック膜の作製
2.1 金属アルコキシドを用いるゾル-ゲル法の一般論
2.2 タングステンアルコキシドを用いるゾル-ゲル法によるWO3膜
2.3 タングステンアルコキシドの合成法
2.3.1 W(OR)6の合成
2.3.2 WO(OR)4の合成
2.4 アルコキシド以外を出発原料とするゾル-ゲル法によるWO3膜
2.5 WO3以外のゾル-ゲル法によるEC薄膜
3. おわりに
第23章 スピンオングラス(SOG)
1. はじめに
2. SOGの用途と組成
3. 拡散源としてのSOG
4. 平坦化SOG
5. 低誘電率SOG
6. プラズマ処理によるSOG膜形成
第24章 光触媒膜の窓ガラスへの適用
1. はじめに
2. 光触媒の特徴
2.1 ガラスの汚れ
2.2 光触媒クリーニングガラス(セルフクリーニングガラス)の特性
2.3 その他の特性(空気浄化、抗菌・抗ウィルス性など)
3. 光触媒クリーニングガラスの製造技術
3.1 溶液
3.1.1 光触媒
3.1.2 シリコーンレジン
3.1.3 フィラー
3.1.4 その他固形分
3.1.5 溶媒
3.1.6 溶液に関する留意点
3.2 コーティング
3.2.1 コーティング方法の検討
3.2.2 スプレー法での留意点
3.3 焼成
3.3.1 焼成
3.3.2 冷却時の割れ
4. おわりに
第25章 強誘電体薄膜
1. はじめに
2. 最近の研究例
2.1 高誘電率誘電体薄膜:チタン酸バリウム(BaTiO3)
2.2 非鉛系圧電体薄膜:ビスマス系層状強誘電体(CaBi4Ti4O15)
2.3 マルチフェロイック薄膜:ビスマスフェライト(BiFeO3)
3. おわりに
第26章 ゾル-ゲル法での分散・凝集のコントロールによる色素増感型太陽電池用ナノ結晶多孔質TiO2膜の作製
1. はじめに
2. 光散乱粒子による変換効率の向上
3. TiO2ゾルの乾燥粉末によるナノ粒子凝集とその色素増感太陽電池光電特性変化に関する研究
3.1 TiO2粉末からのTiO2ペーストの準備
3.2 TiO2ゾルからのTiO2ペーストの準備
3.3 調製したペーストの状態
3.4 スクリーン印刷したTiO2透明層の表面
3.5 ペーストから作製した色素増感太陽電池の光電特性
4. 二次粒子から作製するメソ・マクロポーラスTiO2薄膜による色素増感型湿式太陽電池
5. 単分散P-25ペースト重ね塗りによるメソ・マクロポーラス膜の構造制御
6. おわりに
第27章 燃料電池へのゾル-ゲル法の応用
1. はじめに
2. 電解質を作製するためのゾル-ゲル法のポイント
3. プロトン伝導体への応用
4. プロトン伝導性薄膜ガラスの作製
5. イオン液体をプロトン伝導パスにした電解質
6. おわりに
第28章 キャパシタおよびLiイオン二次電池電極材料の開発
1. はじめに
2. カーボンナノ多孔構造制御と電気二重層キャパシタ特性
3. Liイオン二次電池電極材料のナノ構造制御と高速充放電特性
3.1 TiO2/カーボンナノチューブ(CNT)ナノ複合多孔体の合成と充放電特性
3.2 V2O5/多孔カーボンナノ複合体の合成と充放電特性
4. おわりに
<その他の応用>
第29章 銀製品の防錆コーティング
1. はじめに
2. 銀製品の保護膜に要求される特性
3. 有機高分子・無機ハイブリッド塗料
4. ハイブリッド膜の特性
4.1 アルコキシシランの種類と耐溶剤性
4.2 アルコキシシランの種類と耐摩擦性
4.3 アルコキシシランの種類と密着性
4.4 コーティング膜としての硬さ、耐候性
5. おわりに
第30章 ガスバリアコーティング膜
1. はじめに
2. 高分子フィルムへの有機-無機ハイブリッド膜の直接コーティング
2.1 基板の前処理の影響
2.2 耐摩耗性とガスバリア性を兼ね備えた有機-無機ハイブリッドコーティング
2.3 マイクロ波処理による低温緻密化
2.4 生分解性プラスチックへの応用
2.5 その他の例
3. 気相法による無機膜形成と有機-無機ハイブリッドを組み合わせたガスバリアコーティング
3.1 気相法によりSiO2がコーティングされた高分子フィルムへの有機-無機ハイブリッド膜のコーティング
3.2 中間層として有機-無機ハイブリッド膜を用いる場合
4. おわりに
第31章 眼鏡レンズ用ハードコート材料
1. はじめに
2. ゾル-ゲル法によるハードコート材料
3. 眼鏡レンズ用ハードコート材料の構成
4. ハードコート液の調合の注意点
5. ハードコートの塗布方法
6. 塗布条件、塗布環境
7. 高屈折率ハードコート材料
8. 耐衝撃性付与コート材料
第32章 有機-無機ハイブリッド材料の合成と細胞・組織適合性評価
1. はじめに
1.1 ハイブリッドとコンポジット
1.2 有機-無機ハイブリッドの歴史
1.3 医用応用を目指す生体適合ハイブリッドの設計指針
2. オーモシル型ハイブリッド
3. ゼラチン-シロキサン型ハイブリッド
4. キトサン-シロキサン型ハイブリッド
5. おわりに
第33章 固定化酵素担体への応用
1. はじめに
2. 酵素法によるバイオディーゼルの製造
3. シリカモノリスを担体とする固定化リパーゼの開発
4. おわりに